あなたにおすすめの小説

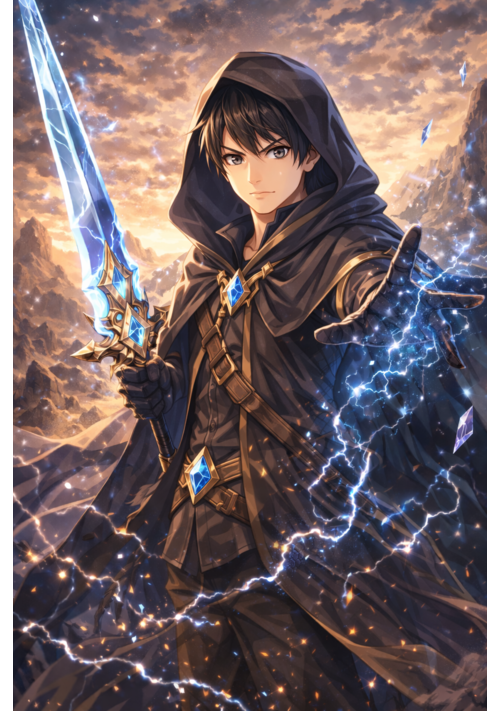
R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~
イット
ファンタジー
オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。
そのまま半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。
だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。
凛人はその命令を、拒否する。
不死であっても無敵ではない。
戦いでは英雄王に殴り倒される始末。しかし一つ選択を誤れば国が滅びる危うい存在。
それでも彼は、星を守るために戦う道を選んだ。
女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。
これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

処刑された勇者は二度目の人生で復讐を選ぶ
シロタカズキ
ファンタジー
──勇者は、すべてを裏切られ、処刑された。
だが、彼の魂は復讐の炎と共に蘇る──。
かつて魔王を討ち、人類を救った勇者 レオン・アルヴァレス。
だが、彼を待っていたのは称賛ではなく、 王族・貴族・元仲間たちによる裏切りと処刑だった。
「力が強すぎる」という理由で異端者として断罪され、広場で公開処刑されるレオン。
国民は歓喜し、王は満足げに笑い、かつての仲間たちは目を背ける。
そして、勇者は 死んだ。
──はずだった。
十年後。
王国は繁栄の影で腐敗し、裏切り者たちは安穏とした日々を送っていた。
しかし、そんな彼らの前に死んだはずの勇者が現れる。
「よくもまあ、のうのうと生きていられたものだな」
これは、英雄ではなくなった男の復讐譚。
彼を裏切った王族、貴族、そしてかつての仲間たちを絶望の淵に叩き落とすための第二の人生が、いま始まる──。

最強賢者の最強メイド~主人もメイドもこの世界に敵がいないようです~
津ヶ谷
ファンタジー
綾瀬樹、都内の私立高校に通う高校二年生だった。
ある日、樹は交通事故で命を落としてしまう。
目覚めた樹の前に現れたのは神を名乗る人物だった。
その神により、チートな力を与えられた樹は異世界へと転生することになる。
その世界での樹の功績は認められ、ほんの数ヶ月で最強賢者として名前が広がりつつあった。
そこで、褒美として、王都に拠点となる屋敷をもらい、執事とメイドを派遣してもらうことになるのだが、このメイドも実は元世界最強だったのだ。
これは、世界最強賢者の樹と世界最強メイドのアリアの異世界英雄譚。

巻き込まれ異世界召喚、なぜか俺だけ竜皇女の推しになった
ノラクラ
ファンタジー
俺、霧島悠斗は筋金入りの陰キャ高校生。
学校が終わったら即帰宅して、ゲームライフを満喫するのが至福の時間――のはずだった。
だがある日の帰り道、玄関前で学園トップスターたちの修羅場に遭遇してしまう。
暴君・赤城獅童、王子様系イケメン・天条院義孝、清楚系美少女・柊奏、その親友・羽里友莉。
よりによって学園の顔ぶれが勢ぞろいして大口論!?
……陰キャ代表の俺に混ざる理由なんて一ミリもない。見なかったことにしてゲームしに帰りたい!
そう願った矢先――空気が変わり、街に巨大な魔法陣が出現。
赤城たちは光に呑まれ、異世界へと召喚されてしまった。
「お~、異世界召喚ね。ラノベあるあるだな」
そう、他人事のように見送った俺だったが……。
直後、俺の足元にも魔法陣が浮かび上がる。
「ちょ、待て待て待て! 俺は陰キャだぞ!? 勇者じゃないんだぞ!?」
――かくして、ゲームライフを愛する陰キャ高校生の異世界行きが始まる。

九尾と契約した日。霊力ゼロの陰陽師見習いが大成するまで。
三科異邦
ファンタジー
「霊力も使えない。術式も出せない。
……西園寺玄弥、お前は本当に陰陽師か?」
その言葉は、もう何度聞いたか分からない。
霊術学院の訓練場で、俺はただ立ち尽くしていた。
周囲では炎が舞い、水がうねり、風が刃のように走る。
同年代の陰陽師たちが、当たり前のように霊を操っている。
――俺だけが、何もできない。
反論したい気持ちはある。
でも、できない事実は変わらない。
そんな俺が、
世界最強クラスの妖怪と契約することになるなんて――
この時は、まだ知る由もなかった。
これは――
妖怪の王を倒すべく、九尾の葛葉や他の仲間達と力を合わせて成長していく陰陽師見習いの物語。

悪徳貴族の、イメージ改善、慈善事業
ウィリアム・ブロック
ファンタジー
現代日本から死亡したラスティは貴族に転生する。しかしその世界では貴族はあんまり良く思われていなかった。なのでノブリス・オブリージュを徹底させて、貴族のイメージ改善を目指すのだった。

SSSレア・スライムに転生した魚屋さん ~戦うつもりはないけど、どんどん強くなる~
草笛あたる(乱暴)
ファンタジー
転生したらスライムの突然変異だった。
レアらしくて、成長が異常に早いよ。
せっかくだから、自分の特技を活かして、日本の魚屋技術を異世界に広めたいな。
出刃包丁がない世界だったので、スライムの体内で作ったら、名刀に仕上がっちゃった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















