15 / 47
何もわからないままバイトは始まる
第15話
しおりを挟む
尿意は自覚すると、途端に耐えがたくなった。
今すぐ公衆トイレを探さなくては。透は車内から周囲を確認したが、ここから見えるのは数件の家と草原だ。公園や公共施設らしき建物は、来た道にも見当たらない。
透の頭に絶望の2文字が浮かんだ。
この場で漏らすか。いや、19でそれはない。絶対に避けたい。たとえ低くても、見つかる可能性に賭けて探そう。
透はそう決意し、車から飛び出した。
「あんた、うちに用かい」
「ひぃっ」
真横から声がして、透は飛び退いた。一瞬、尿意が引っ込む。
顎紐のついた、つばの広い麦藁帽を被った老婆だ。浅黒く皺だらけの肌に似つかわしくないほど、目が欄々として生気が漲っている。
「ここらのもんじゃないだろう。東京から来たのかい」
「ええ、まあ。はい」
「はっきりせん子だね。どこから来たんだい」
「と、東京です」
たじたじになって答えると、老婆から畳みかけるように質問が飛んできた。
「何しにきたんだい」
「まあ、観光みたいなもので」
「ここは何もないがね。牛でも見に来たのかい」
「はいそうです!」
透は面倒くさくなり、観光旅行に来た元気な少年の体で乗り切ることにした。自分が出せる中で最も無邪気な声を出す。
「小学生の校外学習ぶりに見たので、ものすごくワクワクしました」
「そらよかったねえ」
老婆は銀歯を輝かせて笑った。
「わしは生まれてから、ずーっとここで暮らしていたもんだから、すっかり見慣れちまった」
「ずっと……!?」
すごい。町から出たいと思ったことはないんだろうか。
老婆はなんでもないような顔でさらに言った。
「かれこれ100年だ」
「100年!?」
透は素っ頓狂な声を上げた。
「生きてみると、100年は長くないさ。あんたもあっという間に爺さんだ」
老婆は催眠術を掛けるような口調で言って、透の目の奥を覗き込んだ。透は迫りくる生気に気圧されながらも、100年が短かったらどんなにいいだろうと思った。
「わしが生まれたのはね」
長い話の始まりを思わせる語り出しは、意外にもそこで途切れた。何か気に障る反応をしただろうかと動揺する透に、老婆が呆れた様子で言った。
「あんた、さっきから落ち着かないね。便所使うかい?」
なぜ気づかれたのだと目を見開く透に、老婆は言った。
「100年も生きているとね、だいたいのことはわかるのさ」
老婆の家で手洗いを借り、透は冷静さを取り戻した。途端に、ランとの約束を破ったことへの罪悪感が顔を出した。早く車に戻らなければ。
「お邪魔しました。ありがとうございました」
「あんた、ちょいと食べていきなよ」
「え」
声の方へ向かうと、老婆が居間のテーブルに半円型に切ったスイカを並べていた。
「しっかり食べんと、暑さに負けちまうよ」
「ありがとうございます。でも俺、戻らないといけなくて」
「種はこの袋に出してな」
「あ、はい」
透はあれよあれよという間にテーブルの前に座らされた。透の皿にだけ、種をとりやすいようにとフォークまで用意してある。透は食べてすぐ戻ればいいかと思い直し、勧められたスイカに齧りついた。
「うまいだろう」
「はい」
咀嚼すると、瑞々しい果汁が口の中に広がった。飲み下すたび、喉を通る冷たさが心地良い。
「スイカなんて久しぶりに食べました」
「都会のもんは食べないのかね」
「いや、そんなことはないと思います。たまたま俺が食べる機会がなかっただけで……」
透の言葉を遮るように、居間と奥の部屋を仕切る襖が開いた。
寝間着姿の男が顔を出す。中年で痩身の、神経質そうな男だ。
「あれ、お客さん?」
「牛を見に来た、東京からのお客だ」
「……へえ。東京から」
男はぎこちなく会釈をした。透も軽く頭を下げる。
「こんな格好ですみません。ゆっくりしていってください」
「たけしの教え子かい?」
「ちがうってばあちゃん。俺は東京では教えてないから」
男は老婆にスイカを勧められると「あとで食べるよ」と言い、再び奥に消えた。
「好物なのにねえ」
老婆は男のぶんの皿をキッチンに運び、戻ってくると言った。
「孫だよ。癌を患って、お医者さまに長くないと言われてね。わしより先に逝ってしまうかもしれん」
透は咀嚼を止め、意味もなく皿に溜まったスイカの汁を見つめた。
「先生の仕事もやめてな。ここは緑が多いから、身体にいいんでないかと、娘夫婦に頼まれたのさ」
「そうなんですか」
気の利いた言葉が何も出てこない自分が不甲斐ない。
老婆は自分の皿を脇へ押しやり、大切なものを託すような視線で透を見た。
「あんた、身体を大事にしなさいな。粗末にしたら、あんたが思うよりもたーくさんの人が悲しむんだよ」
透は老婆の言葉の意味を考えながら、黙ってスイカを食べた。赤い部分をくまなく食べると、ようやく老婆の合格が出た。
ごちそうさまと手を合わせ、玄関で靴を履いていると、老婆がガサガサと音を立てて何かを持ってくる。
「うちで採れたトマトときゅうりだ。持っていきな」
「いいんですか?」
「いいさ。夏野菜は身体にいいんだから」
ビニール袋を覗くと、不揃いなトマトときゅうりの他に、個包装の煎餅が数枚入っていた。
「このお煎餅もいただいていいんですか?」
「そりゃたけしが入れたんだ。もらっておきな」
老婆は目尻の皺を深くし、ひとり言のように呟いた。
「これもご縁だねえ……」
門扉を出ると、ちょうど道の先にランが見えた。透は咄嗟に姿勢を低くし、俊敏な動きで車内に滑り込んだ。ほどなくして助手席に影が落ち、見上げるとランが窓の傍に立っていた。
「丸見えだ」
「そうですよね……」
今すぐ公衆トイレを探さなくては。透は車内から周囲を確認したが、ここから見えるのは数件の家と草原だ。公園や公共施設らしき建物は、来た道にも見当たらない。
透の頭に絶望の2文字が浮かんだ。
この場で漏らすか。いや、19でそれはない。絶対に避けたい。たとえ低くても、見つかる可能性に賭けて探そう。
透はそう決意し、車から飛び出した。
「あんた、うちに用かい」
「ひぃっ」
真横から声がして、透は飛び退いた。一瞬、尿意が引っ込む。
顎紐のついた、つばの広い麦藁帽を被った老婆だ。浅黒く皺だらけの肌に似つかわしくないほど、目が欄々として生気が漲っている。
「ここらのもんじゃないだろう。東京から来たのかい」
「ええ、まあ。はい」
「はっきりせん子だね。どこから来たんだい」
「と、東京です」
たじたじになって答えると、老婆から畳みかけるように質問が飛んできた。
「何しにきたんだい」
「まあ、観光みたいなもので」
「ここは何もないがね。牛でも見に来たのかい」
「はいそうです!」
透は面倒くさくなり、観光旅行に来た元気な少年の体で乗り切ることにした。自分が出せる中で最も無邪気な声を出す。
「小学生の校外学習ぶりに見たので、ものすごくワクワクしました」
「そらよかったねえ」
老婆は銀歯を輝かせて笑った。
「わしは生まれてから、ずーっとここで暮らしていたもんだから、すっかり見慣れちまった」
「ずっと……!?」
すごい。町から出たいと思ったことはないんだろうか。
老婆はなんでもないような顔でさらに言った。
「かれこれ100年だ」
「100年!?」
透は素っ頓狂な声を上げた。
「生きてみると、100年は長くないさ。あんたもあっという間に爺さんだ」
老婆は催眠術を掛けるような口調で言って、透の目の奥を覗き込んだ。透は迫りくる生気に気圧されながらも、100年が短かったらどんなにいいだろうと思った。
「わしが生まれたのはね」
長い話の始まりを思わせる語り出しは、意外にもそこで途切れた。何か気に障る反応をしただろうかと動揺する透に、老婆が呆れた様子で言った。
「あんた、さっきから落ち着かないね。便所使うかい?」
なぜ気づかれたのだと目を見開く透に、老婆は言った。
「100年も生きているとね、だいたいのことはわかるのさ」
老婆の家で手洗いを借り、透は冷静さを取り戻した。途端に、ランとの約束を破ったことへの罪悪感が顔を出した。早く車に戻らなければ。
「お邪魔しました。ありがとうございました」
「あんた、ちょいと食べていきなよ」
「え」
声の方へ向かうと、老婆が居間のテーブルに半円型に切ったスイカを並べていた。
「しっかり食べんと、暑さに負けちまうよ」
「ありがとうございます。でも俺、戻らないといけなくて」
「種はこの袋に出してな」
「あ、はい」
透はあれよあれよという間にテーブルの前に座らされた。透の皿にだけ、種をとりやすいようにとフォークまで用意してある。透は食べてすぐ戻ればいいかと思い直し、勧められたスイカに齧りついた。
「うまいだろう」
「はい」
咀嚼すると、瑞々しい果汁が口の中に広がった。飲み下すたび、喉を通る冷たさが心地良い。
「スイカなんて久しぶりに食べました」
「都会のもんは食べないのかね」
「いや、そんなことはないと思います。たまたま俺が食べる機会がなかっただけで……」
透の言葉を遮るように、居間と奥の部屋を仕切る襖が開いた。
寝間着姿の男が顔を出す。中年で痩身の、神経質そうな男だ。
「あれ、お客さん?」
「牛を見に来た、東京からのお客だ」
「……へえ。東京から」
男はぎこちなく会釈をした。透も軽く頭を下げる。
「こんな格好ですみません。ゆっくりしていってください」
「たけしの教え子かい?」
「ちがうってばあちゃん。俺は東京では教えてないから」
男は老婆にスイカを勧められると「あとで食べるよ」と言い、再び奥に消えた。
「好物なのにねえ」
老婆は男のぶんの皿をキッチンに運び、戻ってくると言った。
「孫だよ。癌を患って、お医者さまに長くないと言われてね。わしより先に逝ってしまうかもしれん」
透は咀嚼を止め、意味もなく皿に溜まったスイカの汁を見つめた。
「先生の仕事もやめてな。ここは緑が多いから、身体にいいんでないかと、娘夫婦に頼まれたのさ」
「そうなんですか」
気の利いた言葉が何も出てこない自分が不甲斐ない。
老婆は自分の皿を脇へ押しやり、大切なものを託すような視線で透を見た。
「あんた、身体を大事にしなさいな。粗末にしたら、あんたが思うよりもたーくさんの人が悲しむんだよ」
透は老婆の言葉の意味を考えながら、黙ってスイカを食べた。赤い部分をくまなく食べると、ようやく老婆の合格が出た。
ごちそうさまと手を合わせ、玄関で靴を履いていると、老婆がガサガサと音を立てて何かを持ってくる。
「うちで採れたトマトときゅうりだ。持っていきな」
「いいんですか?」
「いいさ。夏野菜は身体にいいんだから」
ビニール袋を覗くと、不揃いなトマトときゅうりの他に、個包装の煎餅が数枚入っていた。
「このお煎餅もいただいていいんですか?」
「そりゃたけしが入れたんだ。もらっておきな」
老婆は目尻の皺を深くし、ひとり言のように呟いた。
「これもご縁だねえ……」
門扉を出ると、ちょうど道の先にランが見えた。透は咄嗟に姿勢を低くし、俊敏な動きで車内に滑り込んだ。ほどなくして助手席に影が落ち、見上げるとランが窓の傍に立っていた。
「丸見えだ」
「そうですよね……」
0
あなたにおすすめの小説


邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ふたなり治験棟 企画12月31公開
ほたる
BL
ふたなりとして生を受けた柊は、16歳の年に国の義務により、ふたなり治験棟に入所する事になる。
男として育ってきた為、子供を孕み産むふたなりに成り下がりたくないと抗うが…?!

冴えないおじさんが雌になっちゃうお話。
丸井まー(旧:まー)
BL
馴染みの居酒屋で冴えないおじさんが雌オチしちゃうお話。
イケメン青年×オッサン。
リクエストをくださった棗様に捧げます!
【リクエスト】冴えないおじさんリーマンの雌オチ。
楽しいリクエストをありがとうございました!
※ムーンライトノベルズさんでも公開しております。


上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

オメガ修道院〜破戒の繁殖城〜
トマトふぁ之助
BL
某国の最北端に位置する陸の孤島、エゼキエラ修道院。
そこは迫害を受けやすいオメガ性を持つ修道士を保護するための施設であった。修道士たちは互いに助け合いながら厳しい冬越えを行っていたが、ある夜の訪問者によってその平穏な生活は終焉を迎える。
聖なる家で嬲られる哀れな修道士たち。アルファ性の兵士のみで構成された王家の私設部隊が逃げ場のない極寒の城を蹂躙し尽くしていく。その裏に棲まうものの正体とは。
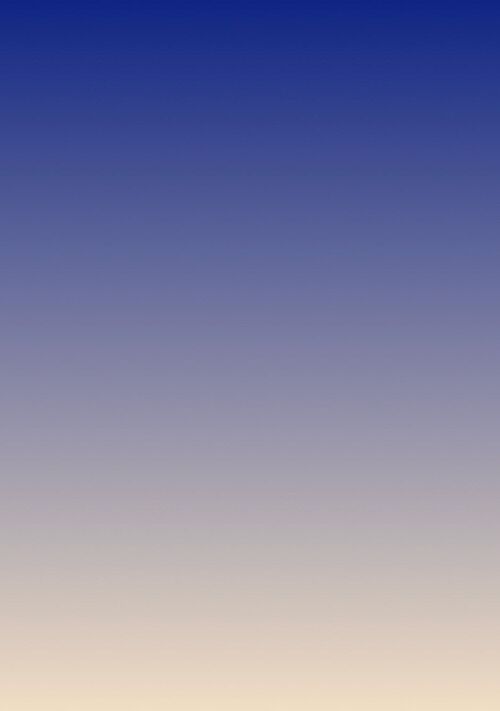
あの部屋でまだ待ってる
名雪
BL
アパートの一室。
どんなに遅くなっても、帰りを待つ習慣だけが残っている。
始まりは、ほんの気まぐれ。
終わる理由もないまま、十年が過ぎた。
与え続けることも、受け取るだけでいることも、いつしか当たり前になっていく。
――あの部屋で、まだ待ってる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















