39 / 47
番外編
今日はいい日☆
しおりを挟む雪が目に涙をいっぱい溜めて見つめる先には、透がいて、楽しそうに誰かと話していた。あんなに笑っている透を初めて見たが、何が雪を泣かせたのか、亮太にはさっぱりわからなかった。
走っていってしまった雪を、あっけにとられて見送ったまま、亮太はしばらく動けなかった。
「邪魔だよ」
「……っ、すみません」
人にぶつかり文句を言われて、ようやく我に返った。流動体のように動き続ける人波では、止まっているだけで迷惑をかける。とにかくここから移動しなくては。
あてどなく歩きながら、帰るべきだろうかと思った。今まで祭りや花火大会のような場で1人取り残されることなどなかったから、どうしていいか迷ってしまう。
「まだ花火上がってないもんな」
帰るにはもったいない。5分ぐらい見てみるか。打ち上がるまでは、残り10分を切っているようだし。
「雪ちゃん、ちゃんと駅に着けたかな」
何もない夜空を見上げていたら、雪のことばかりが頭に浮かんだ。
明るくて笑顔が可愛い女の子だなと、初めに見たときから思っていた。雪の笑顔にはいやな嘘がない。
相手に取り入ろうとか、騙そうとか、そういう目的で笑顔を使う人間と、亮太は少なからず出会ってきた。そういう相手と渡り合うには、自分も笑顔で武装しなければならない。
いつしか上手な笑顔を覚え、それを苦労せず使いこなせるようになった。
でも友達といるときぐらいは、素の自分でいたいと思った。
その点透は、亮太がくだらない話をしても「何を言っているんだこいつ」という顔をしながら、律儀に最後まで聞いてくれる。
特段オチがなくても、高尚な話じゃなくても、失望して離れていったりしない。
小馬鹿にされていると感じるときはあるが、透に呆れられるのを亮太は案外気に入っている。
風が吹いたら飛んで行ってしまいそうな危うさがあり、心配になって声を掛けたのがきっかけだが、友達になれてよかったなと亮太はつくづく思っている。
雪も透も、大好きだ。大好きな2人だから、結ばれてくれたら嬉しい。……きっと嬉しい。
「お兄さん」
通り過ぎようとした屋台の中から声がした。
「……俺ですか?」
「はいそうです。ラムネ買いませんか? 冷えていて美味しいですよ」
眼鏡を掛けた若い男が、にこやかにそう言ってきた。商売相手に向けるには温かすぎるぐらいの笑顔で、この人は苦労していそうだなと思った。
「1本ください」
ちょうど喉が渇いていたので、亮太は迷わずそう答えた。
「はい、まいどあり」
「いくらですか?」
「あー……タダでいいですよ」
「え、どうしてです?」
「うーん。あ、ほら、もう屋台も閉じる時間ですからね」
間と表情から、即席で作った理由なのが丸わかりだった。正直な人なんだなと亮太は微笑ましく思った。本当の理由はわからない。でも、相手が善意で言ってくれているのは伝わってきた。
普段は面倒を避けるために断るところだが、今日くらいはいいかもしれない。
「わかりました。じゃあ、お言葉に甘えます。ついでに何か食べるものを買っていいですか? ここ、パン屋ですよね」
そう言うと、男は嬉しそうに顔をほころばせた。
「ええ。パン屋です。メニューにあるものは一通り揃っていますので、お好きなものをお選びください」
「うわ、いっぱいあるんですね。じゃあ、おすすめのメロンパンで」
「アイスクリームを挟んだものとそうでないものがありますが、どちらになさいますか?」
「パンにアイス挟むんですか? すごいな。じゃあ挟んだほうでお願いします」
「かしこまりました。少々お待ちください」
できあがりを待っていると、後ろの方でピュ~ッと音がした。振り向くと、パッと夜空に大輪が咲いていた。
「はじまりましたね。はいどうぞ」
「ありがとうございます」
男はメロンパンをラムネを渡し終えると、するりと屋台から出てきた。重力を感じさせない身のこなしが、亮太のうちで飼っている猫みたいだった。
「裏に椅子ありますけど、使います?」
「いいんですか?」
「ええ。ずっと立ってるのも疲れるでしょう」
「ちょっと持っててください」と亮太に1本のラムネを預けて、男は2脚のパイプ椅子を持って戻ってきた。
「はあ……」
男は椅子に腰掛けるなり、体の底から漏れたよう深いため息をついた。
「お疲れ様です。ずっとおひとりで回していたんですか?」
「そうなんです。色々事情がありまして」
男は難しい顔をしつつ眉間に手をやった。
「いやでも、僕のことはいいのですよ。どうぞ飲んでください」
「ありがとうございます」
瓶のラムネは、たしかによく冷えていた。パチパチと口のなかで爆ぜる炭酸が、頭上で弾ける花火とリンクしているようで、何だかおかしかった。
次々に打ち上がる花火を30発ほど見ただろうかという頃になって、亮太の興味は隣に座るくたびれた様子の男に移った。
「おいくつなんですか?」
ぼんやりと花火を見ていた瞳が、亮太の方を向いた。花火をしっかり見ようとしていたのだろうか、先ほどよりもパッチリと開いている。まるで楽しいおもちゃを見つけたときの猫みたいだった。
「僕ですか?」
「そうです。歳近そうだなって思ったので」
そう話すと、男は眉を下げて微笑んだ。徳の高そうな笑顔だ。
「19歳、大学1年です」
「え! 同い歳です!」
「そうですか」
声を上擦らせる亮太に対して、男は目を伏せて静かに微笑むだけだった。
「俺は✕✕大なんですけど、もしかして同じ大学だったりします?」
「それはどうでしょうね」
「濁された……!」
頭を抱えて落ち込む亮太に、男は何か言いたげな表情をした。
「俺の顔、何かついてます?」
「いえ。その……アイスクリームが溶けてこぼれています」
下を見れば、いつの間にか地面に丸く白い跡がいくつもできていた。そこに無数のアリが群がっている。
「えっ! あああ! ごめんなさいすぐ食べます!」
作り手にしてみればさぞ不愉快な光景だっただろう。申し訳なくなり、亮太は話すのをやめて食べることに集中することにした。
「そんな勢いで食べたら喉に詰まりますよ」
「いや、めちゃくちゃ美味しいのでつい」
サクッとした外側と、ふわふわの生地。バターの香ばしい香りと冷たいバニラの味が相性抜群だ。
「そうですか。それはよかったです。アイスクリーム入りは今回限定ですが、そのメロンパンはいつでも売っているので、またぜひ食べにいらしてください」
「店舗があるんですね! いいことを聞きました。絶対また食べに行きます」
「一応、店舗というより移動販売車なのですが、このあたりの地域を巡回しております」
「へえー!」
そういえば、移動販売車と似たようなニュアンスの言葉を、どこかで聞いた覚えがあった。それほど前のことではないはずだ。
「どうかされました?」
「いや、なんでもないです。それよりメロンパン、あとひと口になっちゃいました。あっという間すぎて悲しいです」
お世辞ではなく、今まで食べたメロンパンの中で最も美味しかったので、食べ切ってしまうのが惜しかった。
雨に濡れた犬のようにしょぼくれる亮太に、男は逡巡した様子を見せた。
「……よろしければもう1つお食べになりますか?」
「いいんですか?! 食べます!」
男は細い目を丸くして、それからくすっと笑った。口の端がきゅっと持ち上がっている。今までよりも素に近い笑顔で、亮太は嬉しくなった。
「構いませんよ。たくさん食べてもらえるのは嬉しいですから。取ってきますね」
「お願いします!」
とどのつまり、亮太は最後の花火が打ち上がって消えていくのをしっかり見届け、家に帰った。
「ただいまー」
玄関を開けると、三毛猫のちくわが出迎えてくれた。目を細めて足元にすり寄ってくるのがとても可愛らしい。
「似てるよな」
ふわふわの顎の下を撫でながら、最後まで共に花火を見た男のことを思い出す。
「にゃー」
「だよな。ちくわもそう思うよな」
「にゃーん」
「ん? なんだ、遊ぶか?」
「にゃー」
「よし、じゃあ俺の部屋行こうぜ」
亮太の言葉を理解したかのように、ちくわはさっと足から離れて階段を駆け上がっていく。
そのあとを追いながら、今日はいい日だったなと亮太は思うのだった。
0
あなたにおすすめの小説


邪神の祭壇へ無垢な筋肉を生贄として捧ぐ
零
BL
鍛えられた肉体、高潔な魂――
それは選ばれし“供物”の条件。
山奥の男子校「平坂学園」で、新任教師・高尾雄一は静かに歪み始める。
見えない視線、執着する生徒、触れられる肉体。
誇り高き男は、何に屈し、何に縋るのか。
心と肉体が削がれていく“儀式”が、いま始まる。

ふたなり治験棟 企画12月31公開
ほたる
BL
ふたなりとして生を受けた柊は、16歳の年に国の義務により、ふたなり治験棟に入所する事になる。
男として育ってきた為、子供を孕み産むふたなりに成り下がりたくないと抗うが…?!

冴えないおじさんが雌になっちゃうお話。
丸井まー(旧:まー)
BL
馴染みの居酒屋で冴えないおじさんが雌オチしちゃうお話。
イケメン青年×オッサン。
リクエストをくださった棗様に捧げます!
【リクエスト】冴えないおじさんリーマンの雌オチ。
楽しいリクエストをありがとうございました!
※ムーンライトノベルズさんでも公開しております。


上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。

オメガ修道院〜破戒の繁殖城〜
トマトふぁ之助
BL
某国の最北端に位置する陸の孤島、エゼキエラ修道院。
そこは迫害を受けやすいオメガ性を持つ修道士を保護するための施設であった。修道士たちは互いに助け合いながら厳しい冬越えを行っていたが、ある夜の訪問者によってその平穏な生活は終焉を迎える。
聖なる家で嬲られる哀れな修道士たち。アルファ性の兵士のみで構成された王家の私設部隊が逃げ場のない極寒の城を蹂躙し尽くしていく。その裏に棲まうものの正体とは。
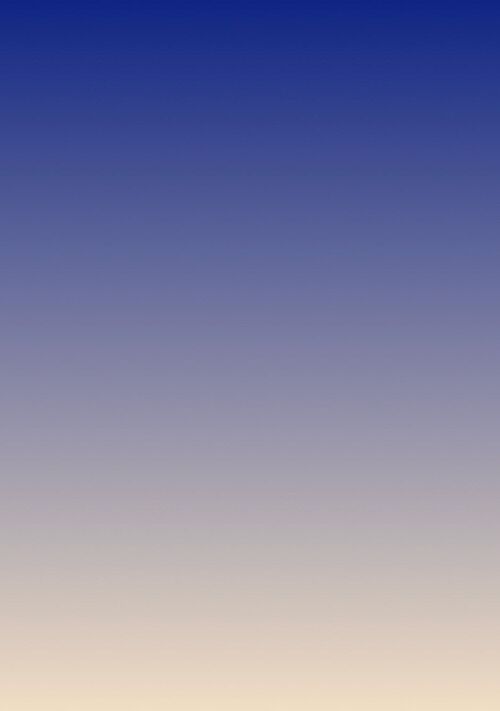
あの部屋でまだ待ってる
名雪
BL
アパートの一室。
どんなに遅くなっても、帰りを待つ習慣だけが残っている。
始まりは、ほんの気まぐれ。
終わる理由もないまま、十年が過ぎた。
与え続けることも、受け取るだけでいることも、いつしか当たり前になっていく。
――あの部屋で、まだ待ってる。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















