1 / 17
第一話 他人
しおりを挟む
桜がどこも満開だった。
私は東京の普通高校に入学して、2週間が経った。しかし、私はとても高校生活が嫌だった。
私の人生そのものが嫌だったからだ。
そんな私が高校生活を楽しむということができるはずがないということはわかっていのだ。
私は自分が嫌いだ。
学校の廊下で、私はひっそりと歩いていた。
なぜなら、他人にはわからないだろう私の裏の顔、闇があることを隠したまま、誰かと接する必要があって、恐怖に怯えているからだ。
人には人の、自分には自分の持っているいいところと悪いところは違うはずだ。人と話すことが大好きである人もいれば、一人で誰とも話さずに日々を過ごすのが好きな人もいる。私は何もしないまま時が過ぎるのを待っている方が好きだ。「一人」と言うレッテルを貼られて
「学校生活どうなの?」「寂しくない?」と、先生や両親によく言われるけど、自分自身が「生きている」という瞬間をこの体で感じているのなら、それはそれでいいのだろうと私は思っているんだ。
高校一年生の私は、窓側の席で授業中、休み時間関係なくずっと窓の外を眺めているのが好きだ。窓の外には、休み時間だからかグラウンドで遊んでいる人や学校の外を走っている数台の車、そして私が住んでいる住宅街までもが見えていた。別に外の風景が好きだからと言うわけではない。ただ私の心が休まると言う意味で眺めているだけだ。これ以外に何が好きかと言ったら、学校の屋上に行くことぐらいしか頭に思い浮かばない。よく昼食の時間に屋上に行っている。そこにいると、空気も美味しいし、私が私らしくいられる。簡単に言えば、気持ちいいの一言だ。そこには誰もおらず、気持ちがさらに楽になる。まるで蒼茫(そうぼう)とした青空を見ながら、野原に寝転がって楽しんでいる人間のようだ。普段、あまり笑わない私にとってここは唯一の至福な場所だ。教室は窓の外を眺めるのはいいけれど、室内はクラスメイトたちの声でうるさく、とても落ち着かないのである。
この日の授業最後のチャイムが鳴った。放課後になってもいつものように窓の外を眺めていた。「黄昏」がよっぽど好きなのだろう。
私は、今まで風景を好きになったことがなかったが、窓の外を眺めているうちに風景に対してだんだん興味が湧いてきたのだ。そのため、私は美術部に入ることにしたのだ。
本当は入りたくなかったけど、お母さんが
「何かあなたが打ち込めることができる部活に入ったほうがいいわ。」
と、私に説得してくれたので、何らかの部活動に入ることを決心した。
しかし、部活に入った時に私の予測が当たってしまったのだ。先輩や同級生に何も話しかけることができなかった。やっと自分に好きなことが見つかってこの部活に入ろうと決めたのに、どうしても他人に気を遣ってしまう。
人と話すことをどうでもよく思っている私だったが、心の底ではとても焦っていたのだ。
毎日何も変哲のないバインダーに少しずつ色を足していくのを見て、
「いつか、この絵が完成する時が来たら、私は何をしているのだろうか。」
と、私は思っていた。
少し先の未来なんて誰にもわからない。もしかしたら、この世からいなくなっているのかもしれない。私はそう考えながら、限られた時間の中で、完成に導こうと日々頑張っている。
夕焼けがもう少しで沈みかかろうとする時に部活が終わり自転車を漕いで家に帰った。
家が学校に近いことから、登下校に対しての心配が微塵もないという。
「ただいま。」
家に帰るといつものようにお母さん
が出迎えてくれた。
「あら、おかえり、今日もお疲れ様。」と、私に返してくれたが、
「いいえ、そんなことはないわ。」と適当に返してしまった。
寝室に赴き、私はベッドに寝転がり、頭の中で色々と考える。
「絵を描くのが好きだから、画家になりたい」
という願望は一切私にはないが、人生は限られているから、一つ一つの行動に対して後悔したくないだけだ。
「今日も何事もなく一日を過ごすことができてよかった。」
と、毎日自分に言い聞かせている。そしてご飯を食べて、お風呂に入って勉強をして、たくさん寝ると言う生活を送っている。
翌日、窓の外を見つめていた私は、ずっとあることを考えていた。
「私にとって他人とは何なの?」
実は、昨日の晩御飯の時、お母さんからこんなことを言われたのだ。
「なんか何もかも楽しくなさそうに見えるわ。」
と、それに対して私は
「え?何で?」
と、疑問と驚きが混ざっていた。
「結構前から、あなたが笑っているところを見なくなったの。お母さんすごく心配してるんだから。」
と私に優しそうに言ってくれた。
「ううん。気にしないで。別に誰かにいじめられてるっていうわけじゃないからさ。」
と、私は返答した。
「本当に?」と、お母さんは心配してくれた。
「何かあったら遠慮なく言って。お母さん助けてあげるから。あなたはお母さんの味方なんだから。」
と、誰かを救ってくれるような言葉を私にかけてくれた。
「ああ、うん、わかったよ。」
と、私はなぜか黙り込んでしまったことが昨日あったのだ。
「他人か・・・。」
と、考えているうちに、私は他人からどう思われているのかを気にするようになった。
数時間が経ち、国語の授業を受けていた。田口先生からいつも通りに教科書を私に読んでほしいと言う依頼があったので、ゆっくりと声に出して音読を行った。
「すると、ある男の子が私に突っ込んできて・・・。」しばらくその文章を読んでいるうちに、私は手を止めてしまった。頭の中で恐ろしい激痛が走っていく・・・。
「バタン!!!」
と、壁にぶつかったような大きな物音を立て、急に教室の床めがけて私は倒れてしまった。
しばらくして、目が覚めた。
額には冷えピタシートと氷水が入っている袋のようなものが、頭に吊るされてあった。ピンク色のカーテンに囲まれている。私が起き上がったのと同時にカーテンを開けて、保健室の橋本先生から話しかけようとしてくれたのだ。起き上がった時、体全体に痛みが走った。
「あらら、まだ治ってないから起き上がらないで。」
と、橋本先生は対応してくれた。
「ああ、すみません。」
と、謝っていた。
橋本先生曰く、国語の授業中に突然倒れた私を背中に担いで田口先生が、保健室まで届けてくれたそうだ。
「突然倒れたので私もびっくりしたんですよ。」
と、田口先生が言っていたのだ。
倒れてからの記憶が全くなかったため、橋本先生から全て聞いたのだ。すると、
「しかし、突然倒れたりするってことは何か問題があるんじゃないかと思うの。何かあったの?」
と、私に言った。
「別に貧血とかではないんですけど、最近よく倒れるんです。」
と言った。
「でも、それではないと言うことは他に何かあるのかしら。今すぐ言え、と言うわけじゃないから、今度倒れそうになった時、心配事で苦しそうな時があったら、いつでも来なさい。」
と私を気にかけて話してくれた。
「はい。わかりました。」
私は安心した。担任の悠木先生に報告しておくとも言われたので心が楽になった。
「橋本先生ありがとうございました。失礼します。」
と私は保健室を後にした。
「何でこんなに倒れるの?」
「何で色々なことで苦しむのだろう?」
などと、たくさん一人で考え込んできた私だったが、このことがきっかけで他人がいることの大切さを見にしみて感じた。
「他人ってこんなにいいものだったんだ。」
「何で気づかなかったんだろう。こんなにも先生方が私を気にかけてくれるなんて、私も少しは楽になるかな。」
と嬉しかった。
すると、私に複数の上級生がぶつかってきた。
「おい、あぶねーよ、ちゃんと前見ろよ。」
「すみません、ごめんなさい。」
私はすぐに謝った。「ごめんなさい」が一番私がすぐに出る言葉だと思う。良いこともあるが、必要のないところで言ってしまったり、または悪いことをしていないのにも関わらず、ずっと謝り続けているなど勿論私にも悪いところはたくさんある。正直自分でも言わなくてもいいところで謝ってしまうところが嫌になっている。
そんなことを考えながら、教室に自分の場所なんてないのにもかかわらず、一歩一歩教室に向かって歩いて行った。
「でもいいの、少しずつ自分の嫌なところを流していけば大丈夫だよ。」
と言い聞かせた。
教室に到着して、クラスメイトたちのうるさい声で賑わっている中で、私の机に目の焦点を合わせると机が荒らされていた。教科書、ノートそしてプリント類がぐちゃぐちゃになって置いてあった。
「私、もしかしてクラスメイト全員にいじめられているの?嫌われているの?」
私はクラスメイトたちに関心なんて一ミリもなかったが、この状況から嫌われているということを初めて知ったのだ。
「私、何もしてないのにいじめにあうわけがない。」
プリント類がぐちゃぐちゃになっている状態を私はたくさんの感情が襲いかかってきたのか、頭の中で何を考えているのかがわからなくなった。心の底では焦りと悲しみが込み上げてきているのに。
ただ一つだけ覚えていたことは、混乱しすぎて一歩も動けなかったことだ。
私は恐る恐る椅子に座り、整理整頓をし直していたところ、あるものを見つけた。
「え?これは・・・。」
果たして、それの正体は何だろうか?
第二話に続く
私は東京の普通高校に入学して、2週間が経った。しかし、私はとても高校生活が嫌だった。
私の人生そのものが嫌だったからだ。
そんな私が高校生活を楽しむということができるはずがないということはわかっていのだ。
私は自分が嫌いだ。
学校の廊下で、私はひっそりと歩いていた。
なぜなら、他人にはわからないだろう私の裏の顔、闇があることを隠したまま、誰かと接する必要があって、恐怖に怯えているからだ。
人には人の、自分には自分の持っているいいところと悪いところは違うはずだ。人と話すことが大好きである人もいれば、一人で誰とも話さずに日々を過ごすのが好きな人もいる。私は何もしないまま時が過ぎるのを待っている方が好きだ。「一人」と言うレッテルを貼られて
「学校生活どうなの?」「寂しくない?」と、先生や両親によく言われるけど、自分自身が「生きている」という瞬間をこの体で感じているのなら、それはそれでいいのだろうと私は思っているんだ。
高校一年生の私は、窓側の席で授業中、休み時間関係なくずっと窓の外を眺めているのが好きだ。窓の外には、休み時間だからかグラウンドで遊んでいる人や学校の外を走っている数台の車、そして私が住んでいる住宅街までもが見えていた。別に外の風景が好きだからと言うわけではない。ただ私の心が休まると言う意味で眺めているだけだ。これ以外に何が好きかと言ったら、学校の屋上に行くことぐらいしか頭に思い浮かばない。よく昼食の時間に屋上に行っている。そこにいると、空気も美味しいし、私が私らしくいられる。簡単に言えば、気持ちいいの一言だ。そこには誰もおらず、気持ちがさらに楽になる。まるで蒼茫(そうぼう)とした青空を見ながら、野原に寝転がって楽しんでいる人間のようだ。普段、あまり笑わない私にとってここは唯一の至福な場所だ。教室は窓の外を眺めるのはいいけれど、室内はクラスメイトたちの声でうるさく、とても落ち着かないのである。
この日の授業最後のチャイムが鳴った。放課後になってもいつものように窓の外を眺めていた。「黄昏」がよっぽど好きなのだろう。
私は、今まで風景を好きになったことがなかったが、窓の外を眺めているうちに風景に対してだんだん興味が湧いてきたのだ。そのため、私は美術部に入ることにしたのだ。
本当は入りたくなかったけど、お母さんが
「何かあなたが打ち込めることができる部活に入ったほうがいいわ。」
と、私に説得してくれたので、何らかの部活動に入ることを決心した。
しかし、部活に入った時に私の予測が当たってしまったのだ。先輩や同級生に何も話しかけることができなかった。やっと自分に好きなことが見つかってこの部活に入ろうと決めたのに、どうしても他人に気を遣ってしまう。
人と話すことをどうでもよく思っている私だったが、心の底ではとても焦っていたのだ。
毎日何も変哲のないバインダーに少しずつ色を足していくのを見て、
「いつか、この絵が完成する時が来たら、私は何をしているのだろうか。」
と、私は思っていた。
少し先の未来なんて誰にもわからない。もしかしたら、この世からいなくなっているのかもしれない。私はそう考えながら、限られた時間の中で、完成に導こうと日々頑張っている。
夕焼けがもう少しで沈みかかろうとする時に部活が終わり自転車を漕いで家に帰った。
家が学校に近いことから、登下校に対しての心配が微塵もないという。
「ただいま。」
家に帰るといつものようにお母さん
が出迎えてくれた。
「あら、おかえり、今日もお疲れ様。」と、私に返してくれたが、
「いいえ、そんなことはないわ。」と適当に返してしまった。
寝室に赴き、私はベッドに寝転がり、頭の中で色々と考える。
「絵を描くのが好きだから、画家になりたい」
という願望は一切私にはないが、人生は限られているから、一つ一つの行動に対して後悔したくないだけだ。
「今日も何事もなく一日を過ごすことができてよかった。」
と、毎日自分に言い聞かせている。そしてご飯を食べて、お風呂に入って勉強をして、たくさん寝ると言う生活を送っている。
翌日、窓の外を見つめていた私は、ずっとあることを考えていた。
「私にとって他人とは何なの?」
実は、昨日の晩御飯の時、お母さんからこんなことを言われたのだ。
「なんか何もかも楽しくなさそうに見えるわ。」
と、それに対して私は
「え?何で?」
と、疑問と驚きが混ざっていた。
「結構前から、あなたが笑っているところを見なくなったの。お母さんすごく心配してるんだから。」
と私に優しそうに言ってくれた。
「ううん。気にしないで。別に誰かにいじめられてるっていうわけじゃないからさ。」
と、私は返答した。
「本当に?」と、お母さんは心配してくれた。
「何かあったら遠慮なく言って。お母さん助けてあげるから。あなたはお母さんの味方なんだから。」
と、誰かを救ってくれるような言葉を私にかけてくれた。
「ああ、うん、わかったよ。」
と、私はなぜか黙り込んでしまったことが昨日あったのだ。
「他人か・・・。」
と、考えているうちに、私は他人からどう思われているのかを気にするようになった。
数時間が経ち、国語の授業を受けていた。田口先生からいつも通りに教科書を私に読んでほしいと言う依頼があったので、ゆっくりと声に出して音読を行った。
「すると、ある男の子が私に突っ込んできて・・・。」しばらくその文章を読んでいるうちに、私は手を止めてしまった。頭の中で恐ろしい激痛が走っていく・・・。
「バタン!!!」
と、壁にぶつかったような大きな物音を立て、急に教室の床めがけて私は倒れてしまった。
しばらくして、目が覚めた。
額には冷えピタシートと氷水が入っている袋のようなものが、頭に吊るされてあった。ピンク色のカーテンに囲まれている。私が起き上がったのと同時にカーテンを開けて、保健室の橋本先生から話しかけようとしてくれたのだ。起き上がった時、体全体に痛みが走った。
「あらら、まだ治ってないから起き上がらないで。」
と、橋本先生は対応してくれた。
「ああ、すみません。」
と、謝っていた。
橋本先生曰く、国語の授業中に突然倒れた私を背中に担いで田口先生が、保健室まで届けてくれたそうだ。
「突然倒れたので私もびっくりしたんですよ。」
と、田口先生が言っていたのだ。
倒れてからの記憶が全くなかったため、橋本先生から全て聞いたのだ。すると、
「しかし、突然倒れたりするってことは何か問題があるんじゃないかと思うの。何かあったの?」
と、私に言った。
「別に貧血とかではないんですけど、最近よく倒れるんです。」
と言った。
「でも、それではないと言うことは他に何かあるのかしら。今すぐ言え、と言うわけじゃないから、今度倒れそうになった時、心配事で苦しそうな時があったら、いつでも来なさい。」
と私を気にかけて話してくれた。
「はい。わかりました。」
私は安心した。担任の悠木先生に報告しておくとも言われたので心が楽になった。
「橋本先生ありがとうございました。失礼します。」
と私は保健室を後にした。
「何でこんなに倒れるの?」
「何で色々なことで苦しむのだろう?」
などと、たくさん一人で考え込んできた私だったが、このことがきっかけで他人がいることの大切さを見にしみて感じた。
「他人ってこんなにいいものだったんだ。」
「何で気づかなかったんだろう。こんなにも先生方が私を気にかけてくれるなんて、私も少しは楽になるかな。」
と嬉しかった。
すると、私に複数の上級生がぶつかってきた。
「おい、あぶねーよ、ちゃんと前見ろよ。」
「すみません、ごめんなさい。」
私はすぐに謝った。「ごめんなさい」が一番私がすぐに出る言葉だと思う。良いこともあるが、必要のないところで言ってしまったり、または悪いことをしていないのにも関わらず、ずっと謝り続けているなど勿論私にも悪いところはたくさんある。正直自分でも言わなくてもいいところで謝ってしまうところが嫌になっている。
そんなことを考えながら、教室に自分の場所なんてないのにもかかわらず、一歩一歩教室に向かって歩いて行った。
「でもいいの、少しずつ自分の嫌なところを流していけば大丈夫だよ。」
と言い聞かせた。
教室に到着して、クラスメイトたちのうるさい声で賑わっている中で、私の机に目の焦点を合わせると机が荒らされていた。教科書、ノートそしてプリント類がぐちゃぐちゃになって置いてあった。
「私、もしかしてクラスメイト全員にいじめられているの?嫌われているの?」
私はクラスメイトたちに関心なんて一ミリもなかったが、この状況から嫌われているということを初めて知ったのだ。
「私、何もしてないのにいじめにあうわけがない。」
プリント類がぐちゃぐちゃになっている状態を私はたくさんの感情が襲いかかってきたのか、頭の中で何を考えているのかがわからなくなった。心の底では焦りと悲しみが込み上げてきているのに。
ただ一つだけ覚えていたことは、混乱しすぎて一歩も動けなかったことだ。
私は恐る恐る椅子に座り、整理整頓をし直していたところ、あるものを見つけた。
「え?これは・・・。」
果たして、それの正体は何だろうか?
第二話に続く
0
あなたにおすすめの小説

Hand in Hand - 二人で進むフィギュアスケート青春小説
宮 都
青春
幼なじみへの気持ちの変化を自覚できずにいた中2の夏。ライバルとの出会いが、少年を未知のスポーツへと向わせた。
美少女と手に手をとって進むその競技の名は、アイスダンス!!
【2022/6/11完結】
その日僕たちの教室は、朝から転校生が来るという噂に落ち着きをなくしていた。帰国子女らしいという情報も入り、誰もがますます転校生への期待を募らせていた。
そんな中でただ一人、果歩(かほ)だけは違っていた。
「制覇、今日は五時からだから。来てね」
隣の席に座る彼女は大きな瞳を輝かせて、にっこりこちらを覗きこんだ。
担任が一人の生徒とともに教室に入ってきた。みんなの目が一斉にそちらに向かった。それでも果歩だけはずっと僕の方を見ていた。
◇
こんな二人の居場所に現れたアメリカ帰りの転校生。少年はアイスダンスをするという彼に強い焦りを感じ、彼と同じ道に飛び込んでいく……
――小説家になろう、カクヨム(別タイトル)にも掲載――

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。
ピコサイクス
青春
大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。
真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。
引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。
偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。
ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。
優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。
大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。
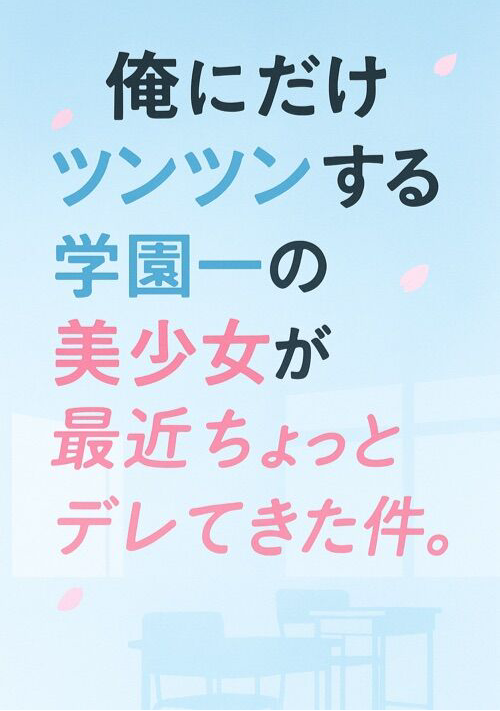
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

現実とサキュバスのあいだで ――夢で告白した相手が、同居を始めた話
そう
青春
ある日家に突然現れた謎のサキュバスのホルさん!
好感度はMAXなようで流されるがまま主人公はホルさんと日常を過ごします。
ほのぼのラブコメというか日常系小説
オチなどはなく、ただひたすらにまったりします
挿絵や文章にもAIを使用しております。
苦手な方はご注意ください。

妹の仇 兄の復讐
MisakiNonagase
青春
神奈川県の海に近い住宅街。夏の終わりが、夕焼けに溶けていく季節だった。
僕、孝之は高校三年生、十七歳。妹の茜は十五歳、高校一年生。父と母との四人暮らし。ごく普通の家庭で、僕と茜は、ブラコンやシスコンと騒がれるほどではないが、それなりに仲の良い兄妹だった。茜は少し内気で、真面目な顔をしているが、家族の前ではよく笑う。特に、幼馴染で僕の交際相手でもある佑香が来ると、姉のように慕って明るくなる。
その平穏が、ほんの些細な噂によって、静かに、しかし深く切り裂かれようとは、その時はまだ知らなかった。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

キャバ嬢(ハイスペック)との同棲が、僕の高校生活を色々と変えていく。
たかなしポン太
青春
僕のアパートの前で、巨乳美人のお姉さんが倒れていた。
助けたそのお姉さんは一流大卒だが内定取り消しとなり、就職浪人中のキャバ嬢だった。
でもまさかそのお姉さんと、同棲することになるとは…。
「今日のパンツってどんなんだっけ? ああ、これか。」
「ちょっと、確認しなくていいですから!」
「これ、可愛いでしょ? 色違いでピンクもあるんだけどね。綿なんだけど生地がサラサラで、この上の部分のリボンが」
「もういいです! いいですから、パンツの説明は!」
天然高学歴キャバ嬢と、心優しいDT高校生。
異色の2人が繰り広げる、水色パンツから始まる日常系ラブコメディー!
※小説家になろうとカクヨムにも同時掲載中です。
※本作品はフィクションであり、実在の人物や団体、製品とは一切関係ありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















