この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

陰キャの俺が学園のアイドルがびしょびしょに濡れているのを見てしまった件
暁ノ鳥
キャラ文芸
陰キャの俺は見てしまった。雨の日、校舎裏で制服を濡らし恍惚とする学園アイドルの姿を。「見ちゃったのね」――その日から俺は彼女の“秘密の共犯者”に!? 特殊な性癖を持つ彼女の無茶な「実験」に振り回され、身も心も支配される日々の始まり。二人の禁断の関係の行方は?。二人の禁断の関係が今、始まる!

俺を振ったはずの腐れ縁幼馴染が、俺に告白してきました。
true177
恋愛
一年前、伊藤 健介(いとう けんすけ)は幼馴染の多田 悠奈(ただ ゆうな)に振られた。それも、心無い手紙を下駄箱に入れられて。
それ以来悠奈を避けるようになっていた健介だが、二年生に進級した春になって悠奈がいきなり告白を仕掛けてきた。
これはハニートラップか、一年前の出来事を忘れてしまっているのか……。ともかく、健介は断った。
日常が一変したのは、それからである。やたらと悠奈が絡んでくるようになったのだ。
彼女の狙いは、いったい何なのだろうか……。
※小説家になろう、ハーメルンにも同一作品を投稿しています。
※内部進行完結済みです。毎日連載です。

隣に住んでいる後輩の『彼女』面がガチすぎて、オレの知ってるラブコメとはかなり違う気がする
夕姫
青春
【『白石夏帆』こいつには何を言っても無駄なようだ……】
主人公の神原秋人は、高校二年生。特別なことなど何もない、静かな一人暮らしを愛する少年だった。東京の私立高校に通い、誰とも深く関わらずただ平凡に過ごす日々。
そんな彼の日常は、ある春の日、突如現れた隣人によって塗り替えられる。後輩の白石夏帆。そしてとんでもないことを言い出したのだ。
「え?私たち、付き合ってますよね?」
なぜ?どうして?全く身に覚えのない主張に秋人は混乱し激しく否定する。だが、夏帆はまるで聞いていないかのように、秋人に猛烈に迫ってくる。何を言っても、どんな態度をとっても、その鋼のような意思は揺るがない。
「付き合っている」という謎の確信を持つ夏帆と、彼女に振り回されながらも憎めない(?)と思ってしまう秋人。これは、一人の後輩による一方的な「好き」が、平凡な先輩の日常を侵略する、予測不能な押しかけラブコメディ。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
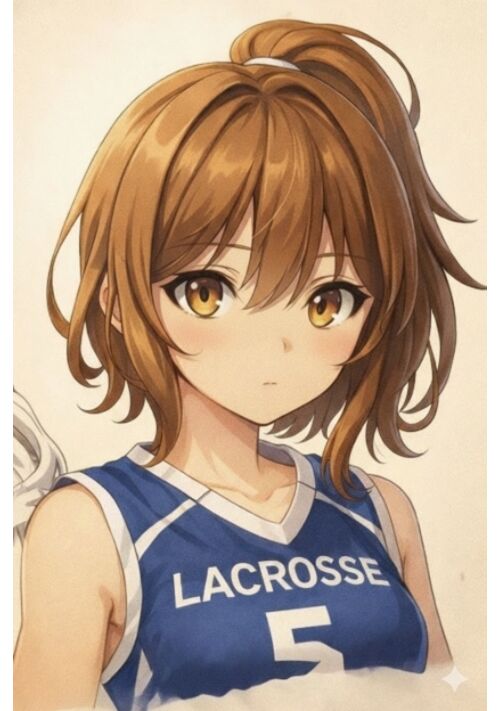
私の守護霊さん『ラクロス編』
Masa&G
キャラ文芸
本作は、本編『私の守護霊さん』の番外編です。
本編では描ききれなかった「ラクロス編」を、単独でも読める形でお届けします。番外編だけでも内容はわかりますが、本編を先に読んでいただくと、より物語に入り込みやすくなると思います。
「絶対にレギュラーを取って、東京代表に行きたい――」
そんな想いを胸に、宮司彩音は日々ラクロスの練習に明け暮れている。
同じポジションには、絶対的エースアタッカー・梶原真夏。埋まらない実力差に折れそうになる彩音のそばには、今日も無言の相棒・守護霊さんがいた。
守護霊さんの全力バックアップのもと、彩音の“レギュラー奪取&東京代表への挑戦”が始まる──。

隣の家の幼馴染と転校生が可愛すぎるんだが
akua034
恋愛
隣に住む幼馴染・水瀬美羽。
毎朝、元気いっぱいに晴を起こしに来るのは、もう当たり前の光景だった。
そんな彼女と同じ高校に進学した――はずだったのに。
数ヶ月後、晴のクラスに転校してきたのは、まさかの“全国で人気の高校生アイドル”黒瀬紗耶。
平凡な高校生活を過ごしたいだけの晴の願いとは裏腹に、
幼馴染とアイドル、二人の存在が彼の日常をどんどんかき回していく。
笑って、悩んで、ちょっとドキドキ。
気づけば心を奪われる――
幼馴染 vs 転校生、青春ラブコメの火蓋がいま切られる!

昔義妹だった女の子が通い妻になって矯正してくる件
マサタカ
青春
俺には昔、義妹がいた。仲が良くて、目に入れても痛くないくらいのかわいい女の子だった。
あれから数年経って大学生になった俺は友人・先輩と楽しく過ごし、それなりに充実した日々を送ってる。
そんなある日、偶然元義妹と再会してしまう。
「久しぶりですね、兄さん」
義妹は見た目や性格、何より俺への態度。全てが変わってしまっていた。そして、俺の生活が爛れてるって言って押しかけて来るようになってしまい・・・・・・。
ただでさえ再会したことと変わってしまったこと、そして過去にあったことで接し方に困っているのに成長した元義妹にドギマギさせられてるのに。
「矯正します」
「それがなにか関係あります? 今のあなたと」
冷たい視線は俺の過去を思い出させて、罪悪感を募らせていく。それでも、義妹とまた会えて嬉しくて。
今の俺たちの関係って義兄弟? それとも元家族? 赤の他人?
ノベルアッププラスでも公開。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















