10 / 11
【序章】始まらずに終わった話、或いは終わりが始まる話
10. その恋は始まらずに終わった
しおりを挟む
三月十三日、金曜日。
俗に言う〝十三日の金曜日〟だが、ホッケーマスクの怪人に出くわすようなこともなく、その日の午前は順調に過ぎていった。
強いて普段と違うことがあったとすれば、伊恵理が自力で起床したことくらいだろうか。いや、単に今朝が昨日の朝ほど寒くなかったためかもしれないが。このまま手の掛からない子へと育ってくれれば、おかんとしては喜ばしい限りだ。
――事態が動いたのは、昼休みに敢介が鑑識課を訪れた時だ。
「出たよ、合致する指紋」
いつものことながら目許に隈を作っている足穂が、指紋採取に使ったサンプルの入っているビニール袋を掲げた。
それは――空になったコーヒーフレッシュの容器だった。
「同じ指紋は下駄箱からも取れてた。偽装の疑いがあるわけでもなし、ここまで揃えば、ほぼ間違いないんじゃない?」
足穂の言葉を聞きながら、敢介はその差出人の最有力候補の顔を、頭の中に思い浮かべる。
敢介の下駄箱にラブレターが投函されたのは、昨日の朝のこと。確かに彼女なら、その時間帯に敢介の下駄箱に先回りしていることもできただろう。
意外と言えば意外な相手だったが、しかし昨日一日を振り返ってみると、腑に落ちるものがあるのも確かだった。論理でなく直感として、だが。
「ありがとな、藤浪。お陰で誰の仕業か解った」
「礼には及ばないよ。私はただ、君のくれた弁当のお返しをしただけ」
だからこの後何が起ころうと自分は一切関知しないと、つまりはそういう意図の宣言だった。相変わらず足穂は足穂だ。
「……まぁ、わざわざ放課後だなんていう、人目に付く時間帯に下駄箱を調べるだなんて羞恥プレイを演じさせられたことについては、別料金をもらいたいところだけど」
「そこは借り一つということで。……本当のところ、釣り餌がなくても、向こうから生け簀に飛び込んできていたんだけどさ」
代わりに、無関係かつもっと面倒臭いのに食いつかれてしまったのは、少し誤算だった。今後はもう少し慎重に作戦を立てることにしようと思う。
足穂に別れを告げて、鑑識課の部屋から出たところで、「お、いいところに」という呟きが耳に届いた。
釣られて振り返ると、ふわふわと柔らかそうな髪をした女の子が、獲物を前に舌舐めずりするような顔で立っていた。
篠倉累――敢介の風紀委員会時代の同僚だ。
「よう、腹黒ウサギ。ちょっと面貸しな」
「それ、言ってみたかっただけだろ。どうせ今から同じ授業を受けるんだ。移動しながらでいいか?」
相手の返事を待たずに、敢介は教室を目指して歩き出す。
累はすぐにその横に並ぶと、はぁ、とこれ見よがしに溜息をついた。
「……憂木クン、前にも言ったかもしれないが、キミにはもっと遊び心ってものがあっていいと思うんだ」
「俺にだって遊び心くらいあるさ。ただお前とは相性が良くないだけだろう。確か前にも言ったはずだよな」
それで用件は何だよ、と敢介は本題を促したが、累はつんと唇を尖らせた。
「教えてやろうかと思ったけどやめた」
「お前が俺に用があることつったら、大方伊恵理のことだろうな。……ああ、昨日の放課後からどうにも様子が変なのは、実はお前の所為か」
ちっ、と累は舌打ちした。図星だったようだ。
「なら、後で本人に直接確認してやりな。オイラから話す気はもう失せた」
「そこまで期待してないよ。ま、お前のことだからあいつのためを思っての発言だろうがな」
累は軽く頬を赤らめると、照れ隠しか敢介の足を蹴ってきた。痛い。
◆
放課後。敢介は通話アプリのメッセージ機能を使って、ラブレターの差出人を呼び出した。
用件、もとい呼び出す口実自体は、別に今日が初めてという内容ではないので、きっと何も疑わずに敢介と合流してくれることだろう。
ただ、想いを寄せている相手にふと呼び出されるという、そんな状況を演出してしまっていることには、多少罪悪感を覚えないでもなかった。
待ち合わせ場所は、校門の前。
果たしてそこに訪れたのは、
「やあ、敢介くん。待ったかい?」
「いえ、大丈夫です。……すみません、用事もないのに学校まで呼びつけちゃって」
「ははっ、用事がないから私の手を借りようと思ったんだろう?」
そう言って屈託なく笑ったのは、生徒寮第27号棟〈日出荘〉の寮生――指原毬藻だった。
先に〝用件〟の方を済ませてしまおうと、敢介は毬藻と連れ立って歩き出した。
これから向かう先は、最寄り駅付近にある商店街だ。生徒寮御用達の、食材や日用品の調達場所だ。
「今日は〈校編室〉はサボりかい?」
「ちゃんと上司に許可はもらいましたよ。今日は年に一度の《十三日の金曜日セール》の日だから買い出しに行くって。……まぁ『今年は十一月にもう一回あるわよ』と返されちゃいましたけどね」
「特売セールを理由に仕事を休ませてもらえるのか……。君の上司って、確かあの〝美人過ぎる総務次長〟だろう? 意外に柔軟な人なんだね」
厳密には、敢介の直属の上司は資料課長なのだが、その〝美人過ぎる総務次長〟がこれを兼任しているため、いちおう指し示す人物そのものは間違っていない。
「取り澄ましているのは見た目だけで、中身は結構融通を利かせてくれる物分かりのいい人ですよ」
「そっかー……もっと話してみれば良かった。もう一年、この学校にいたかったなぁ」
「今夜は特売の牛肉ですき焼きをやりますから、それで勘弁して下さい。〝同じ鍋を囲んだ仲〟として」
「ははっ、確かに〝同じ鍋を囲んだ仲〟には恵まれたね、私は!」
敢介が毬藻と交わす言葉は、普段と何ら違うものではなかった。
特別意識しているわけではない。自然にこういう風に話せるようになるだけの時間を、確かに二人で過ごしてきた。
「こうして毬藻先輩と買い出しに行くのも、今日が最後になりますかね」
「かもねぇ。後輩の男子に食材の目利きを教わるだなんて、なかなかできない経験だったよ」
いつからだったのだろうか。毬藻が敢介に好意を寄せるようになったのは――。
商店街で買い物を終えると、後はもう寮への帰路に就くしかなくなる。
このタイミングに切り出そうと敢介は決めていた。
「――毬藻先輩」
「ん?」
毬藻が首を巡らせる動きに合わせて、耳許で赤いピアスが揺れる。
たぶん違うだろうが、ルビーに似ているようにも見える。その宝石言葉は――〝愛〟、そして〝勇気〟とも。
心臓の鼓動が早まるのを感じながら、努めて冷静さを装って、敢介は口を開く。
「すみません。来週、俺は先輩と一緒に昼飯を食べることはできません」
もしも。
もしも毬藻が、あのラブレターの差出人でなかったならば、この言葉は額面通りの意味しか持たない。毬藻が「何の話?」と笑って、それで済むことだ。
しかし――その言葉に含まれた真意を、毬藻は理解できてしまったようだった。
一瞬、はっ、と目を見開いて、そして、すぐに悟りきったような穏やかな微笑みを浮かべた。
「そっか。……始まらずに終わってしまうんだね、私の恋は」
「別に先輩のことが嫌いなわけじゃないです。ただ、俺は――」
「ああ、皆まで言うな。解ってる。今の君にとって、一番大事なのは――伊恵理ちゃん、なんだろう?」
「…………」
返す言葉は思いつかなかった。付け足す言葉も見つけられなかった。
確かに伊恵理のことは大切に思っている。けれども――〝どう〟大切なのかは、敢介自身、正直よく解らない。だから、静かに頷き返すことくらいしか、できなかった。
「いいんだよ、それで。困ったことに、私が惹かれたのは、そうやって誰かの力になり続けている君の姿だったんだから」
すみません、という言葉はすんでのところで呑み込んだ。きっと毬藻は謝罪の言葉など求めていない。では、何と言えば、今の自分の正直な気持ちを伝えられるだろうか。
「ありがとうございます、毬藻先輩。最後にこんな想い出をくれて」
今度は毬藻が押し黙った。無言のまま頭上を仰ぐ。敢介はそんな毬藻の顔を見ないように、ただずっと前を向いていた。
見据えた先では、夕陽が山の向こうへと沈んでいくところだった。空の色が橙から群青へと変わっていく。――昼と夜が肩を並べることを許された、ほんの一瞬の、奇蹟の時間。
やがて、はぁ、と腹の底に溜まっていたものを全て放り出すかのように、毬藻は長い息を吐いた。
「よし、この話はもうおしまい。寮に戻ったら、私と君は今まで通り、仲の良い先輩と後輩だ。決着が付いてスッキリしたよ」
「了解です。……ところで、最後に一つだけ、訊いてもいいですか?」
「おや、何かな?」
そう言って首を傾げる毬藻の顔は、もう既に〝先輩〟の顔になっていた。強い人なのだな、と今更ながらに尊敬の念を覚える。
だから敢介も、奔放な寮生に手を焼かされるおかんの顔をしながら、
「今時どうして、手紙なんて回りくどい真似を?」
んー、と毬藻は少しだけ考える間を置いて、
「電話やメールは好きじゃないんだ。手紙くらいの速さが、ちょうどいい」
俗に言う〝十三日の金曜日〟だが、ホッケーマスクの怪人に出くわすようなこともなく、その日の午前は順調に過ぎていった。
強いて普段と違うことがあったとすれば、伊恵理が自力で起床したことくらいだろうか。いや、単に今朝が昨日の朝ほど寒くなかったためかもしれないが。このまま手の掛からない子へと育ってくれれば、おかんとしては喜ばしい限りだ。
――事態が動いたのは、昼休みに敢介が鑑識課を訪れた時だ。
「出たよ、合致する指紋」
いつものことながら目許に隈を作っている足穂が、指紋採取に使ったサンプルの入っているビニール袋を掲げた。
それは――空になったコーヒーフレッシュの容器だった。
「同じ指紋は下駄箱からも取れてた。偽装の疑いがあるわけでもなし、ここまで揃えば、ほぼ間違いないんじゃない?」
足穂の言葉を聞きながら、敢介はその差出人の最有力候補の顔を、頭の中に思い浮かべる。
敢介の下駄箱にラブレターが投函されたのは、昨日の朝のこと。確かに彼女なら、その時間帯に敢介の下駄箱に先回りしていることもできただろう。
意外と言えば意外な相手だったが、しかし昨日一日を振り返ってみると、腑に落ちるものがあるのも確かだった。論理でなく直感として、だが。
「ありがとな、藤浪。お陰で誰の仕業か解った」
「礼には及ばないよ。私はただ、君のくれた弁当のお返しをしただけ」
だからこの後何が起ころうと自分は一切関知しないと、つまりはそういう意図の宣言だった。相変わらず足穂は足穂だ。
「……まぁ、わざわざ放課後だなんていう、人目に付く時間帯に下駄箱を調べるだなんて羞恥プレイを演じさせられたことについては、別料金をもらいたいところだけど」
「そこは借り一つということで。……本当のところ、釣り餌がなくても、向こうから生け簀に飛び込んできていたんだけどさ」
代わりに、無関係かつもっと面倒臭いのに食いつかれてしまったのは、少し誤算だった。今後はもう少し慎重に作戦を立てることにしようと思う。
足穂に別れを告げて、鑑識課の部屋から出たところで、「お、いいところに」という呟きが耳に届いた。
釣られて振り返ると、ふわふわと柔らかそうな髪をした女の子が、獲物を前に舌舐めずりするような顔で立っていた。
篠倉累――敢介の風紀委員会時代の同僚だ。
「よう、腹黒ウサギ。ちょっと面貸しな」
「それ、言ってみたかっただけだろ。どうせ今から同じ授業を受けるんだ。移動しながらでいいか?」
相手の返事を待たずに、敢介は教室を目指して歩き出す。
累はすぐにその横に並ぶと、はぁ、とこれ見よがしに溜息をついた。
「……憂木クン、前にも言ったかもしれないが、キミにはもっと遊び心ってものがあっていいと思うんだ」
「俺にだって遊び心くらいあるさ。ただお前とは相性が良くないだけだろう。確か前にも言ったはずだよな」
それで用件は何だよ、と敢介は本題を促したが、累はつんと唇を尖らせた。
「教えてやろうかと思ったけどやめた」
「お前が俺に用があることつったら、大方伊恵理のことだろうな。……ああ、昨日の放課後からどうにも様子が変なのは、実はお前の所為か」
ちっ、と累は舌打ちした。図星だったようだ。
「なら、後で本人に直接確認してやりな。オイラから話す気はもう失せた」
「そこまで期待してないよ。ま、お前のことだからあいつのためを思っての発言だろうがな」
累は軽く頬を赤らめると、照れ隠しか敢介の足を蹴ってきた。痛い。
◆
放課後。敢介は通話アプリのメッセージ機能を使って、ラブレターの差出人を呼び出した。
用件、もとい呼び出す口実自体は、別に今日が初めてという内容ではないので、きっと何も疑わずに敢介と合流してくれることだろう。
ただ、想いを寄せている相手にふと呼び出されるという、そんな状況を演出してしまっていることには、多少罪悪感を覚えないでもなかった。
待ち合わせ場所は、校門の前。
果たしてそこに訪れたのは、
「やあ、敢介くん。待ったかい?」
「いえ、大丈夫です。……すみません、用事もないのに学校まで呼びつけちゃって」
「ははっ、用事がないから私の手を借りようと思ったんだろう?」
そう言って屈託なく笑ったのは、生徒寮第27号棟〈日出荘〉の寮生――指原毬藻だった。
先に〝用件〟の方を済ませてしまおうと、敢介は毬藻と連れ立って歩き出した。
これから向かう先は、最寄り駅付近にある商店街だ。生徒寮御用達の、食材や日用品の調達場所だ。
「今日は〈校編室〉はサボりかい?」
「ちゃんと上司に許可はもらいましたよ。今日は年に一度の《十三日の金曜日セール》の日だから買い出しに行くって。……まぁ『今年は十一月にもう一回あるわよ』と返されちゃいましたけどね」
「特売セールを理由に仕事を休ませてもらえるのか……。君の上司って、確かあの〝美人過ぎる総務次長〟だろう? 意外に柔軟な人なんだね」
厳密には、敢介の直属の上司は資料課長なのだが、その〝美人過ぎる総務次長〟がこれを兼任しているため、いちおう指し示す人物そのものは間違っていない。
「取り澄ましているのは見た目だけで、中身は結構融通を利かせてくれる物分かりのいい人ですよ」
「そっかー……もっと話してみれば良かった。もう一年、この学校にいたかったなぁ」
「今夜は特売の牛肉ですき焼きをやりますから、それで勘弁して下さい。〝同じ鍋を囲んだ仲〟として」
「ははっ、確かに〝同じ鍋を囲んだ仲〟には恵まれたね、私は!」
敢介が毬藻と交わす言葉は、普段と何ら違うものではなかった。
特別意識しているわけではない。自然にこういう風に話せるようになるだけの時間を、確かに二人で過ごしてきた。
「こうして毬藻先輩と買い出しに行くのも、今日が最後になりますかね」
「かもねぇ。後輩の男子に食材の目利きを教わるだなんて、なかなかできない経験だったよ」
いつからだったのだろうか。毬藻が敢介に好意を寄せるようになったのは――。
商店街で買い物を終えると、後はもう寮への帰路に就くしかなくなる。
このタイミングに切り出そうと敢介は決めていた。
「――毬藻先輩」
「ん?」
毬藻が首を巡らせる動きに合わせて、耳許で赤いピアスが揺れる。
たぶん違うだろうが、ルビーに似ているようにも見える。その宝石言葉は――〝愛〟、そして〝勇気〟とも。
心臓の鼓動が早まるのを感じながら、努めて冷静さを装って、敢介は口を開く。
「すみません。来週、俺は先輩と一緒に昼飯を食べることはできません」
もしも。
もしも毬藻が、あのラブレターの差出人でなかったならば、この言葉は額面通りの意味しか持たない。毬藻が「何の話?」と笑って、それで済むことだ。
しかし――その言葉に含まれた真意を、毬藻は理解できてしまったようだった。
一瞬、はっ、と目を見開いて、そして、すぐに悟りきったような穏やかな微笑みを浮かべた。
「そっか。……始まらずに終わってしまうんだね、私の恋は」
「別に先輩のことが嫌いなわけじゃないです。ただ、俺は――」
「ああ、皆まで言うな。解ってる。今の君にとって、一番大事なのは――伊恵理ちゃん、なんだろう?」
「…………」
返す言葉は思いつかなかった。付け足す言葉も見つけられなかった。
確かに伊恵理のことは大切に思っている。けれども――〝どう〟大切なのかは、敢介自身、正直よく解らない。だから、静かに頷き返すことくらいしか、できなかった。
「いいんだよ、それで。困ったことに、私が惹かれたのは、そうやって誰かの力になり続けている君の姿だったんだから」
すみません、という言葉はすんでのところで呑み込んだ。きっと毬藻は謝罪の言葉など求めていない。では、何と言えば、今の自分の正直な気持ちを伝えられるだろうか。
「ありがとうございます、毬藻先輩。最後にこんな想い出をくれて」
今度は毬藻が押し黙った。無言のまま頭上を仰ぐ。敢介はそんな毬藻の顔を見ないように、ただずっと前を向いていた。
見据えた先では、夕陽が山の向こうへと沈んでいくところだった。空の色が橙から群青へと変わっていく。――昼と夜が肩を並べることを許された、ほんの一瞬の、奇蹟の時間。
やがて、はぁ、と腹の底に溜まっていたものを全て放り出すかのように、毬藻は長い息を吐いた。
「よし、この話はもうおしまい。寮に戻ったら、私と君は今まで通り、仲の良い先輩と後輩だ。決着が付いてスッキリしたよ」
「了解です。……ところで、最後に一つだけ、訊いてもいいですか?」
「おや、何かな?」
そう言って首を傾げる毬藻の顔は、もう既に〝先輩〟の顔になっていた。強い人なのだな、と今更ながらに尊敬の念を覚える。
だから敢介も、奔放な寮生に手を焼かされるおかんの顔をしながら、
「今時どうして、手紙なんて回りくどい真似を?」
んー、と毬藻は少しだけ考える間を置いて、
「電話やメールは好きじゃないんだ。手紙くらいの速さが、ちょうどいい」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

陰キャの俺が学園のアイドルがびしょびしょに濡れているのを見てしまった件
暁ノ鳥
キャラ文芸
陰キャの俺は見てしまった。雨の日、校舎裏で制服を濡らし恍惚とする学園アイドルの姿を。「見ちゃったのね」――その日から俺は彼女の“秘密の共犯者”に!? 特殊な性癖を持つ彼女の無茶な「実験」に振り回され、身も心も支配される日々の始まり。二人の禁断の関係の行方は?。二人の禁断の関係が今、始まる!

俺を振ったはずの腐れ縁幼馴染が、俺に告白してきました。
true177
恋愛
一年前、伊藤 健介(いとう けんすけ)は幼馴染の多田 悠奈(ただ ゆうな)に振られた。それも、心無い手紙を下駄箱に入れられて。
それ以来悠奈を避けるようになっていた健介だが、二年生に進級した春になって悠奈がいきなり告白を仕掛けてきた。
これはハニートラップか、一年前の出来事を忘れてしまっているのか……。ともかく、健介は断った。
日常が一変したのは、それからである。やたらと悠奈が絡んでくるようになったのだ。
彼女の狙いは、いったい何なのだろうか……。
※小説家になろう、ハーメルンにも同一作品を投稿しています。
※内部進行完結済みです。毎日連載です。

隣に住んでいる後輩の『彼女』面がガチすぎて、オレの知ってるラブコメとはかなり違う気がする
夕姫
青春
【『白石夏帆』こいつには何を言っても無駄なようだ……】
主人公の神原秋人は、高校二年生。特別なことなど何もない、静かな一人暮らしを愛する少年だった。東京の私立高校に通い、誰とも深く関わらずただ平凡に過ごす日々。
そんな彼の日常は、ある春の日、突如現れた隣人によって塗り替えられる。後輩の白石夏帆。そしてとんでもないことを言い出したのだ。
「え?私たち、付き合ってますよね?」
なぜ?どうして?全く身に覚えのない主張に秋人は混乱し激しく否定する。だが、夏帆はまるで聞いていないかのように、秋人に猛烈に迫ってくる。何を言っても、どんな態度をとっても、その鋼のような意思は揺るがない。
「付き合っている」という謎の確信を持つ夏帆と、彼女に振り回されながらも憎めない(?)と思ってしまう秋人。これは、一人の後輩による一方的な「好き」が、平凡な先輩の日常を侵略する、予測不能な押しかけラブコメディ。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
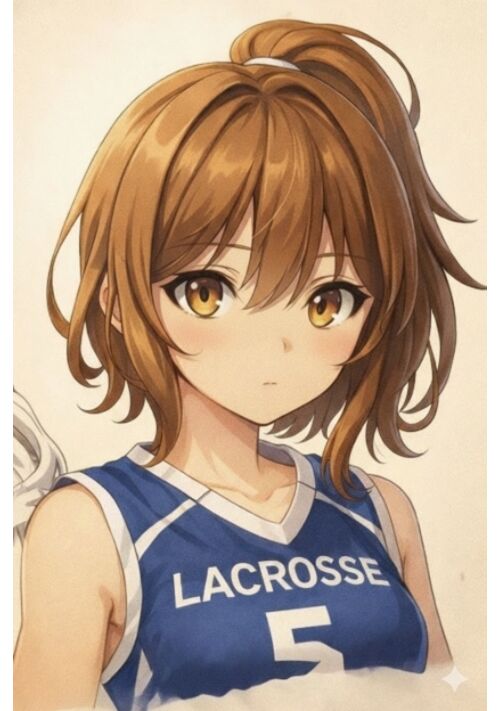
私の守護霊さん『ラクロス編』
Masa&G
キャラ文芸
本作は、本編『私の守護霊さん』の番外編です。
本編では描ききれなかった「ラクロス編」を、単独でも読める形でお届けします。番外編だけでも内容はわかりますが、本編を先に読んでいただくと、より物語に入り込みやすくなると思います。
「絶対にレギュラーを取って、東京代表に行きたい――」
そんな想いを胸に、宮司彩音は日々ラクロスの練習に明け暮れている。
同じポジションには、絶対的エースアタッカー・梶原真夏。埋まらない実力差に折れそうになる彩音のそばには、今日も無言の相棒・守護霊さんがいた。
守護霊さんの全力バックアップのもと、彩音の“レギュラー奪取&東京代表への挑戦”が始まる──。

隣の家の幼馴染と転校生が可愛すぎるんだが
akua034
恋愛
隣に住む幼馴染・水瀬美羽。
毎朝、元気いっぱいに晴を起こしに来るのは、もう当たり前の光景だった。
そんな彼女と同じ高校に進学した――はずだったのに。
数ヶ月後、晴のクラスに転校してきたのは、まさかの“全国で人気の高校生アイドル”黒瀬紗耶。
平凡な高校生活を過ごしたいだけの晴の願いとは裏腹に、
幼馴染とアイドル、二人の存在が彼の日常をどんどんかき回していく。
笑って、悩んで、ちょっとドキドキ。
気づけば心を奪われる――
幼馴染 vs 転校生、青春ラブコメの火蓋がいま切られる!

昔義妹だった女の子が通い妻になって矯正してくる件
マサタカ
青春
俺には昔、義妹がいた。仲が良くて、目に入れても痛くないくらいのかわいい女の子だった。
あれから数年経って大学生になった俺は友人・先輩と楽しく過ごし、それなりに充実した日々を送ってる。
そんなある日、偶然元義妹と再会してしまう。
「久しぶりですね、兄さん」
義妹は見た目や性格、何より俺への態度。全てが変わってしまっていた。そして、俺の生活が爛れてるって言って押しかけて来るようになってしまい・・・・・・。
ただでさえ再会したことと変わってしまったこと、そして過去にあったことで接し方に困っているのに成長した元義妹にドギマギさせられてるのに。
「矯正します」
「それがなにか関係あります? 今のあなたと」
冷たい視線は俺の過去を思い出させて、罪悪感を募らせていく。それでも、義妹とまた会えて嬉しくて。
今の俺たちの関係って義兄弟? それとも元家族? 赤の他人?
ノベルアッププラスでも公開。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















