26 / 63
1巻 学内格差編
第9話 ①
しおりを挟む
「単刀直入に聞く」
満さんは鋭い眼光で俺の目を射貫くように睨んできた。
「君、電気系統の物質を操れるだろう? 恐らく栄養ドリンク辺りがトリガーだな」
――え?
なぜこの人は貴津学園の生徒でもないのに、能力のことを知っているんだ!?
というか、どうして俺の秘密をものの一瞬で見抜けたんだろう?
「なんで分かったのって顔をしているな」
俺はこくこくと首を縦に振った。
「さっき君の右手から一瞬雷光が迸ったのを見てしまってね。それで確信したよ」
この人は天才だ。なにしろ天王坂高校を卒業している。
しかし単なる天才でもなさそうだ。
満さんは絶対にこの不可解な能力についての詳細な事情を知っている。
「君を能力者に変えたドリンクにも心当たりはある。今の段階ではまだ詳しい内容は話せないけどね――そうか、奴らは本格的に計画を実行しはじめたか……」
「あの、奴らとは? 計画って」
顎に手を当てて神妙な面持ちで思案する満さんに疑問をぶつける。
「詳細は追々話すつもりではいるけど、迫害された人々を救済しようとしているとある組織があってね」
「そんな怪しげな組織があるんですか」
今や日本もすっかり物騒な国になったものだよ。
「その組織に関与している誰かが、何らかの理由から貴津学園に件のドリンクを送りつけたんだ」
「どうしてそんなことを……」
「単純に実験台にしたかったんじゃないかな」
高校生を実験台にするとか、とんでもない組織だな。
「学園はドリンクを飲ませる前に検査したと言ってましたよ? ドリンクに訝しい成分はないってお墨付きもありましたし」
専門機関が調べた結果、異常は見つからなかった。
更に学園長も承認していたんだ。がさつだけど天才の学園長が異常を見落とすはずがない。
――――だけど、もし、気づいていながら理由があって意図的にスルーしていたとしたら?
そんな疑念がふと脳裏をよぎるも、満さんは俺の思案を待たずして話を続ける。
「なら、現代の科学では察知できないように作られていると考えるべきだね」
そんなことが実現できる組織があるのか……?
眉唾な話でとても信じられないけど、俺自身が実際に超能力という不可解な現象に遭遇してしまっている以上否定はできない。
「なぜこうなったのかを今考えても時間の無駄だ」
つまり現段階で超能力の詳細を追ったところで何も解決できないと満さんは暗に告げている。
「話の方向性を変えよう。ドリンクを飲んだ人は全員超能力を使えるようになった?」
「いえ、使えた人と使えなかった人がいました」
俺や豊原は使えて太一や誠司は使えなかった。
「ほう。両者の違いは分かるかい?」
「能力者は暗い人や捻くれた人が多かったと思います。よく言えば個性的と言いますか……」
自分で言っててあれだけど俺も該当者なので複雑な心境だ。
「なるほどな――ときに高坂君はRPGは好きかい?」
RPG? プレイは結構してはいるけど。
「え、えぇ、好きですよ。先週発売した作品は特にやり込んでます」
「おお、気が合うね。俺もその作品にハマってるよ」
い、いきなり話が明後日の方向に脱線していませんかね?
「すまない、話が逸れてしまったね。で、だ。RPGではよく魔法の概念があるよね。君だったらゲームで何のために魔法を使う?」
単に敵にダメージを与えるだけならば通常攻撃で事足りる。魔法を使うシチュエーションがあるとすれば――
「魔法は敵との相性によっては通常攻撃よりも敵により大きなダメージを与えられますからね。簡潔に言えば敵をやっつけるため、ですかね」
「普通はそうだね。では補助魔法や回復魔法の存在意義は?」
「補助魔法は効率よく相手を倒すために使いますし、回復魔法がないと味方が死んでしまいますね」
戦闘において、特に回復魔法は重宝する。RPGにおいてHPの温存は死活問題だ。
「ゲームオーバーにならないためにはどうする?」
「パーティのHPを残しつつ敵を倒す、それしかないと思いますよ」
「そうだね。つまり補助魔法だろうが回復魔法だろうが、結果的に魔法というものは『敵を倒すための手段』に集約される」
ゲームの中ではそうかもしれない。けど現実世界で回復魔法が存在するなら、その使用目的はゲームとは違うはずだ。誰かを傷つけるためではなく誰かを助けるため。怪我や病気を治療するため。それらの用途に使われるべきだ。
「少なくとも君が得た能力はね、人を傷つけるために存在しているんだ」
超能力は使い方によって人の命を奪うこともできてしまうって太一にも言われたっけ。
「ここからは俺の推測だけど、ドリンクに入っていた物質がドリンク摂取者の体内――恐らくは脳に侵入して記憶を辿るんだ。そこで陰性か陽性かの判断を行い、陽性の場合は物質が脳に常駐する」
物質とか記憶とか、小難しい話になってきたな。
「陰性と陽性の判断材料は何になるんですか?」
「記憶の内容だ」
特定の記憶が能力発動の引き金になるってことか?
「さっきも言ったけど、ゲームでの魔法の存在理由は誰かを倒す――端的に言えば破壊が目的だ。標的を倒すぞ、悪者には制裁を、あいつが憎い――そういった他害の感情が能力のエネルギーに成し得るとしたら?」
他者への憎悪は感情なので姿形はない。それが超能力として具現化する? それって普通に危険じゃないか?
「感情は鉄や石油などとは違って目に見えて存在する有限物質ではない。記憶として持ち続ける限り永遠に存在するものだ」
嫌な感情は記憶を失わない限り、本人次第でいつでも記憶から蘇ってしまう。記憶の出来事を克服して気にならなくなったら話は別だろうけど。
「そんなものがエネルギー源になれば能力が使い放題だよね? ゲームでよくあるMPの概念を無視できる。非常に恐ろしい仕組みだよ」
「枯渇しない魔力みたいなものですか。チートじみてますね」
チートという単語を聞いた満さんは頷いた。
「記憶というものは、記憶喪失にでもならない限り決してなくなりはしないからね。たとえ本人が忘れていても、海馬にはいつまでも残っている。つまり、記憶を能力発動の燃料にすれば、能力が永久に使えるようになる」
感情が恒久的な魔力を提供し、記憶が超能力を実体化させるって仕組みか。
「石油とかの有限な資源とは違って、記憶は残っている限り空にならないですもんね」
「ちなみにどんな記憶があれば能力が使えるようになると思う?」
満さんが次なる問いを投げかけてきた。
先ほどの話から考えるに負の記憶だよね。
「嫉妬や憎しみとか、トラウマの記憶が能力を発動させるエネルギー源になるんじゃないでしょうか」
「正解だ」
満さんは微笑すら浮かべずに俺を見つめてくる。
「こんなことを聞くのは酷なんだけど、君には過去にそういった類の出来事があるかい? あ、無理に話す必要はないからね」
過去――――心当たりがありすぎる。
俺は幼少時代からの幼馴染に劣等感など様々な感情を抱いた。嫉妬心や羨望感は今をも持ち続けているし、幼馴染同士で比較され続けてきた過去は、俺の記憶に黒歴史として強く刻み込まれている。
「俺は、幼馴染に対して嫉妬や羨望の感情を抱き続けてます」
「なるほど。君の場合は記憶に残っている嫉妬心などがドリンクの成分と反応して能力が使えるようになったんだね」
羨ましい。なんで同じ幼馴染でもこうも違うんだ。そんな負の感情が記憶として残り、その記憶を媒体に俺の両手から雷が作り出せるってメカニズムか。
ん? ここで腑に落ちない点が。
「クラスメイトの中には単に浮いたり瞬間移動する能力の人もいましたよ? それは攻撃目的とは違うんじゃないですか?」
満さんは口元に手を当てて目を閉じた。
「なんとも言えないけど、浮いて他者を踏みつけることができるかもしれない。瞬間移動で他者の背後へと回って攻撃をしかけることができるかもしれない。パッと見攻撃目的ではない能力でもこじつけてみると、結局は攻撃手段になり得るかもしれないよね」
「発想の転換ですね」
それにしてもみんな人生谷ありなんだなぁ。
能力者はみんな、俺のように屈折した思いを抱いて生きているのだろうか。
思い出したくもない過去に蝕まれているのだろうか。
そういえば豊原も能力者だけど……まぁ、あいつはなんとなく想像はつく。
「すまないが、君たちから超能力を消失させる方法は分からない」
「そう、ですよね」
いくら満さんでも、奇妙な能力の全てを把握しているはずもなく。
本人は推測と謙遜してたけどおおよそ正解っぽい気がするし、そこまで予想できるだけでも十分だしすごいと思う。
「だが、先ほど話したトンデモ組織はまもなく淘汰される手筈だから、そこは心配いらないよ」
満さんはそこまで話すと、鋭く光っていた目を細めて優しい笑みを零す。
「つまらない話をして申し訳なかったね」
「いえ、色々と知れてよかったです」
何も分からずに得体の知れない超能力を持ったままでは気味が悪かったしね。
「さて、ここからは純粋に親交を深めようじゃないか」
この人、いくらなんでも切り替えが早すぎない? さっきまでの重い話で締まった空気は一瞬で掻き消え、いきなりだらけモードに入ったぞ。
「なにせ、真夏が男の子を自宅に連れ込んだのは初めてだからね。正直ビックリだ」
「そ、そうなんですか!?」
ものすっごく意外だ。喜ぶべきか?
「星川さんは学園ですごい人気ですよ。特に男子からは入学早々騒がれてましたし」
1科とは交流がない俺の耳にすら入ってきたので、相当な熱気なのが分かる。
「ははは、真夏は男に対してあまりいい感情は抱いてないんだよね」
「えっ、そうなんですか?」
少なくとも俺に対する接し方は普通だし、周囲の男子とも良好な関係に見えるけどなぁ。
「もっとも、その原因を作り出したのは俺と親父なんだけどね」
満さんは肩をすくめる。何かあったのかな?
「お兄さんは天王坂高校を出ているんですよね?」
「真夏め、俺の経歴を話したのか。まぁいいけどさ」
満さんは天王坂高校の話題に対して面白くなさそうな反応を示す。
「天王坂を卒業して、世間一般では日本一と称されている大学に現役で入ったまではよかったんだけど」
すごいな。周囲から讃えられるべきレベルの神童じゃないか。
「知らず知らずのうちに中退してニートになっていた」
いや、そんなキリッとした顔であっさり言われましてもどう反応すればいいのか分かりません。大学入学からの展開が早すぎませんかね。
満さんは鋭い眼光で俺の目を射貫くように睨んできた。
「君、電気系統の物質を操れるだろう? 恐らく栄養ドリンク辺りがトリガーだな」
――え?
なぜこの人は貴津学園の生徒でもないのに、能力のことを知っているんだ!?
というか、どうして俺の秘密をものの一瞬で見抜けたんだろう?
「なんで分かったのって顔をしているな」
俺はこくこくと首を縦に振った。
「さっき君の右手から一瞬雷光が迸ったのを見てしまってね。それで確信したよ」
この人は天才だ。なにしろ天王坂高校を卒業している。
しかし単なる天才でもなさそうだ。
満さんは絶対にこの不可解な能力についての詳細な事情を知っている。
「君を能力者に変えたドリンクにも心当たりはある。今の段階ではまだ詳しい内容は話せないけどね――そうか、奴らは本格的に計画を実行しはじめたか……」
「あの、奴らとは? 計画って」
顎に手を当てて神妙な面持ちで思案する満さんに疑問をぶつける。
「詳細は追々話すつもりではいるけど、迫害された人々を救済しようとしているとある組織があってね」
「そんな怪しげな組織があるんですか」
今や日本もすっかり物騒な国になったものだよ。
「その組織に関与している誰かが、何らかの理由から貴津学園に件のドリンクを送りつけたんだ」
「どうしてそんなことを……」
「単純に実験台にしたかったんじゃないかな」
高校生を実験台にするとか、とんでもない組織だな。
「学園はドリンクを飲ませる前に検査したと言ってましたよ? ドリンクに訝しい成分はないってお墨付きもありましたし」
専門機関が調べた結果、異常は見つからなかった。
更に学園長も承認していたんだ。がさつだけど天才の学園長が異常を見落とすはずがない。
――――だけど、もし、気づいていながら理由があって意図的にスルーしていたとしたら?
そんな疑念がふと脳裏をよぎるも、満さんは俺の思案を待たずして話を続ける。
「なら、現代の科学では察知できないように作られていると考えるべきだね」
そんなことが実現できる組織があるのか……?
眉唾な話でとても信じられないけど、俺自身が実際に超能力という不可解な現象に遭遇してしまっている以上否定はできない。
「なぜこうなったのかを今考えても時間の無駄だ」
つまり現段階で超能力の詳細を追ったところで何も解決できないと満さんは暗に告げている。
「話の方向性を変えよう。ドリンクを飲んだ人は全員超能力を使えるようになった?」
「いえ、使えた人と使えなかった人がいました」
俺や豊原は使えて太一や誠司は使えなかった。
「ほう。両者の違いは分かるかい?」
「能力者は暗い人や捻くれた人が多かったと思います。よく言えば個性的と言いますか……」
自分で言っててあれだけど俺も該当者なので複雑な心境だ。
「なるほどな――ときに高坂君はRPGは好きかい?」
RPG? プレイは結構してはいるけど。
「え、えぇ、好きですよ。先週発売した作品は特にやり込んでます」
「おお、気が合うね。俺もその作品にハマってるよ」
い、いきなり話が明後日の方向に脱線していませんかね?
「すまない、話が逸れてしまったね。で、だ。RPGではよく魔法の概念があるよね。君だったらゲームで何のために魔法を使う?」
単に敵にダメージを与えるだけならば通常攻撃で事足りる。魔法を使うシチュエーションがあるとすれば――
「魔法は敵との相性によっては通常攻撃よりも敵により大きなダメージを与えられますからね。簡潔に言えば敵をやっつけるため、ですかね」
「普通はそうだね。では補助魔法や回復魔法の存在意義は?」
「補助魔法は効率よく相手を倒すために使いますし、回復魔法がないと味方が死んでしまいますね」
戦闘において、特に回復魔法は重宝する。RPGにおいてHPの温存は死活問題だ。
「ゲームオーバーにならないためにはどうする?」
「パーティのHPを残しつつ敵を倒す、それしかないと思いますよ」
「そうだね。つまり補助魔法だろうが回復魔法だろうが、結果的に魔法というものは『敵を倒すための手段』に集約される」
ゲームの中ではそうかもしれない。けど現実世界で回復魔法が存在するなら、その使用目的はゲームとは違うはずだ。誰かを傷つけるためではなく誰かを助けるため。怪我や病気を治療するため。それらの用途に使われるべきだ。
「少なくとも君が得た能力はね、人を傷つけるために存在しているんだ」
超能力は使い方によって人の命を奪うこともできてしまうって太一にも言われたっけ。
「ここからは俺の推測だけど、ドリンクに入っていた物質がドリンク摂取者の体内――恐らくは脳に侵入して記憶を辿るんだ。そこで陰性か陽性かの判断を行い、陽性の場合は物質が脳に常駐する」
物質とか記憶とか、小難しい話になってきたな。
「陰性と陽性の判断材料は何になるんですか?」
「記憶の内容だ」
特定の記憶が能力発動の引き金になるってことか?
「さっきも言ったけど、ゲームでの魔法の存在理由は誰かを倒す――端的に言えば破壊が目的だ。標的を倒すぞ、悪者には制裁を、あいつが憎い――そういった他害の感情が能力のエネルギーに成し得るとしたら?」
他者への憎悪は感情なので姿形はない。それが超能力として具現化する? それって普通に危険じゃないか?
「感情は鉄や石油などとは違って目に見えて存在する有限物質ではない。記憶として持ち続ける限り永遠に存在するものだ」
嫌な感情は記憶を失わない限り、本人次第でいつでも記憶から蘇ってしまう。記憶の出来事を克服して気にならなくなったら話は別だろうけど。
「そんなものがエネルギー源になれば能力が使い放題だよね? ゲームでよくあるMPの概念を無視できる。非常に恐ろしい仕組みだよ」
「枯渇しない魔力みたいなものですか。チートじみてますね」
チートという単語を聞いた満さんは頷いた。
「記憶というものは、記憶喪失にでもならない限り決してなくなりはしないからね。たとえ本人が忘れていても、海馬にはいつまでも残っている。つまり、記憶を能力発動の燃料にすれば、能力が永久に使えるようになる」
感情が恒久的な魔力を提供し、記憶が超能力を実体化させるって仕組みか。
「石油とかの有限な資源とは違って、記憶は残っている限り空にならないですもんね」
「ちなみにどんな記憶があれば能力が使えるようになると思う?」
満さんが次なる問いを投げかけてきた。
先ほどの話から考えるに負の記憶だよね。
「嫉妬や憎しみとか、トラウマの記憶が能力を発動させるエネルギー源になるんじゃないでしょうか」
「正解だ」
満さんは微笑すら浮かべずに俺を見つめてくる。
「こんなことを聞くのは酷なんだけど、君には過去にそういった類の出来事があるかい? あ、無理に話す必要はないからね」
過去――――心当たりがありすぎる。
俺は幼少時代からの幼馴染に劣等感など様々な感情を抱いた。嫉妬心や羨望感は今をも持ち続けているし、幼馴染同士で比較され続けてきた過去は、俺の記憶に黒歴史として強く刻み込まれている。
「俺は、幼馴染に対して嫉妬や羨望の感情を抱き続けてます」
「なるほど。君の場合は記憶に残っている嫉妬心などがドリンクの成分と反応して能力が使えるようになったんだね」
羨ましい。なんで同じ幼馴染でもこうも違うんだ。そんな負の感情が記憶として残り、その記憶を媒体に俺の両手から雷が作り出せるってメカニズムか。
ん? ここで腑に落ちない点が。
「クラスメイトの中には単に浮いたり瞬間移動する能力の人もいましたよ? それは攻撃目的とは違うんじゃないですか?」
満さんは口元に手を当てて目を閉じた。
「なんとも言えないけど、浮いて他者を踏みつけることができるかもしれない。瞬間移動で他者の背後へと回って攻撃をしかけることができるかもしれない。パッと見攻撃目的ではない能力でもこじつけてみると、結局は攻撃手段になり得るかもしれないよね」
「発想の転換ですね」
それにしてもみんな人生谷ありなんだなぁ。
能力者はみんな、俺のように屈折した思いを抱いて生きているのだろうか。
思い出したくもない過去に蝕まれているのだろうか。
そういえば豊原も能力者だけど……まぁ、あいつはなんとなく想像はつく。
「すまないが、君たちから超能力を消失させる方法は分からない」
「そう、ですよね」
いくら満さんでも、奇妙な能力の全てを把握しているはずもなく。
本人は推測と謙遜してたけどおおよそ正解っぽい気がするし、そこまで予想できるだけでも十分だしすごいと思う。
「だが、先ほど話したトンデモ組織はまもなく淘汰される手筈だから、そこは心配いらないよ」
満さんはそこまで話すと、鋭く光っていた目を細めて優しい笑みを零す。
「つまらない話をして申し訳なかったね」
「いえ、色々と知れてよかったです」
何も分からずに得体の知れない超能力を持ったままでは気味が悪かったしね。
「さて、ここからは純粋に親交を深めようじゃないか」
この人、いくらなんでも切り替えが早すぎない? さっきまでの重い話で締まった空気は一瞬で掻き消え、いきなりだらけモードに入ったぞ。
「なにせ、真夏が男の子を自宅に連れ込んだのは初めてだからね。正直ビックリだ」
「そ、そうなんですか!?」
ものすっごく意外だ。喜ぶべきか?
「星川さんは学園ですごい人気ですよ。特に男子からは入学早々騒がれてましたし」
1科とは交流がない俺の耳にすら入ってきたので、相当な熱気なのが分かる。
「ははは、真夏は男に対してあまりいい感情は抱いてないんだよね」
「えっ、そうなんですか?」
少なくとも俺に対する接し方は普通だし、周囲の男子とも良好な関係に見えるけどなぁ。
「もっとも、その原因を作り出したのは俺と親父なんだけどね」
満さんは肩をすくめる。何かあったのかな?
「お兄さんは天王坂高校を出ているんですよね?」
「真夏め、俺の経歴を話したのか。まぁいいけどさ」
満さんは天王坂高校の話題に対して面白くなさそうな反応を示す。
「天王坂を卒業して、世間一般では日本一と称されている大学に現役で入ったまではよかったんだけど」
すごいな。周囲から讃えられるべきレベルの神童じゃないか。
「知らず知らずのうちに中退してニートになっていた」
いや、そんなキリッとした顔であっさり言われましてもどう反応すればいいのか分かりません。大学入学からの展開が早すぎませんかね。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

隣に住んでいる後輩の『彼女』面がガチすぎて、オレの知ってるラブコメとはかなり違う気がする
夕姫
青春
【『白石夏帆』こいつには何を言っても無駄なようだ……】
主人公の神原秋人は、高校二年生。特別なことなど何もない、静かな一人暮らしを愛する少年だった。東京の私立高校に通い、誰とも深く関わらずただ平凡に過ごす日々。
そんな彼の日常は、ある春の日、突如現れた隣人によって塗り替えられる。後輩の白石夏帆。そしてとんでもないことを言い出したのだ。
「え?私たち、付き合ってますよね?」
なぜ?どうして?全く身に覚えのない主張に秋人は混乱し激しく否定する。だが、夏帆はまるで聞いていないかのように、秋人に猛烈に迫ってくる。何を言っても、どんな態度をとっても、その鋼のような意思は揺るがない。
「付き合っている」という謎の確信を持つ夏帆と、彼女に振り回されながらも憎めない(?)と思ってしまう秋人。これは、一人の後輩による一方的な「好き」が、平凡な先輩の日常を侵略する、予測不能な押しかけラブコメディ。

クラスのマドンナがなぜか俺のメイドになっていた件について
沢田美
恋愛
名家の御曹司として何不自由ない生活を送りながらも、内気で陰気な性格のせいで孤独に生きてきた裕貴真一郎(ゆうき しんいちろう)。
かつてのいじめが原因で、彼は1年間も学校から遠ざかっていた。
しかし、久しぶりに登校したその日――彼は運命の出会いを果たす。
現れたのは、まるで絵から飛び出してきたかのような美少女。
その瞳にはどこかミステリアスな輝きが宿り、真一郎の心をかき乱していく。
「今日から私、あなたのメイドになります!」
なんと彼女は、突然メイドとして彼の家で働くことに!?
謎めいた美少女と陰キャ御曹司の、予測不能な主従ラブコメが幕を開ける!
カクヨム、小説家になろうの方でも連載しています!

ヤンデレ美少女転校生と共に体育倉庫に閉じ込められ、大問題になりましたが『結婚しています!』で乗り切った嘘のような本当の話
桜井正宗
青春
――結婚しています!
それは二人だけの秘密。
高校二年の遙と遥は結婚した。
近年法律が変わり、高校生(十六歳)からでも結婚できるようになっていた。だから、問題はなかった。
キッカケは、体育倉庫に閉じ込められた事件から始まった。校長先生に問い詰められ、とっさに誤魔化した。二人は退学の危機を乗り越える為に本当に結婚することにした。
ワケありヤンデレ美少女転校生の『小桜 遥』と”新婚生活”を開始する――。
*結婚要素あり
*ヤンデレ要素あり
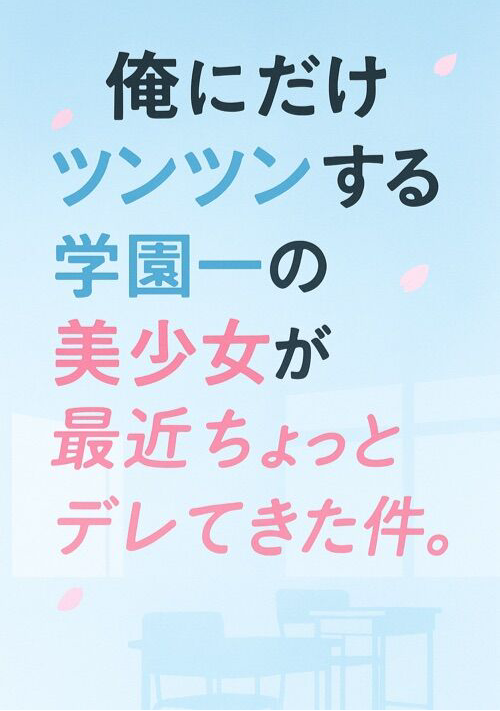
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















