2 / 12
ナナシ荘へようこそ
しおりを挟む
篁四郎がナナシ荘に引っ越して来たのは8月の初めだった。
元いたアパートも住人は全員引っ越していって、秋には取り壊し工事が始まるらしい。定食屋も無事に閉店して、最終日には外に行列ができる忙しさだった。
おかげで7月はテストとバイトに明け暮れ、潤子との予定が合わず、引っ越し当日にナナシ荘を訪れる羽目になったのだ。
渡された住所を頼りに篁四郎が訪れたナナシ荘は二階建てのごく普通の家に見えた。
門にはナナシ荘と書かれた石の札が埋め込まれていた。
「あ、篁四郎くん、来たね」
「今日からお世話になります」
チャイムを鳴らしたら、すぐに潤子が出てきてくれた。他にも潤子以外の住人がいるらしく、開けられた玄関には男物の靴が並んでいた。
「他の人たちも待ってるよ」
「何人いるんですか?」
「私の他に2人いるよ。2人ともいい人だから」
「そうですか」
篁四郎が潤子から言われたバイト内容は、このナナシ荘での料理係だった。
特に料理の専門学校に行っているわけでも、得意なわけでもないのだと篁四郎が言っても、潤子は覚えていけばいいと言って料理の腕は木にしていないようだった。
「潤子さん、本当に僕でいいんですか?」
「篁四郎くんがいいの」
「料理できないですよ?」
「でも出会ってから少しは勉強したでしょ」
「家で自炊する回数が増えたくらいですけど」
「十分よ」
ネットで検索すれば料理のレシピなどいくらでも出てくる。篁四郎は定食屋で貰った余りものの食材を使って、炒め物や煮物を作っては失敗したり成功したりとしていた。
人に出すには躊躇うレベルではあるが、潤子がそれでいいというなら、もっと他のことで求められる仕事があるのかもしれない。
電球を変えたり、高いところのものをとったり、掃除をしたり、そういうこともやるのかもしれない。篁四郎自身特別背が高いというわけではないが、人並みの男性の身長はあるし、潤子よりはずっと背が高い。
それなら料理が下手でも歓迎される意味は分かる。
「入って入って」
「おじゃまします」
「下に台所とリビングとお風呂とおトイレと部屋が二つあるの。その一つを使ってね。二階は5部屋あって、私たちの部屋がそれぞれあるから」
「掃除とかは……」
「自分の部屋と台所以外はしなくていいわ」
「え?」
「だって篁四郎くんは料理係だもの」
笑う潤子の顔に嘘はない。
潤子が篁四郎の料理レベルでいいというのだから他にもなにかあると思っていたが、純粋に料理を求められているのであれば、もう少しレシピ本など買っていればよかったし、定食屋の店長に料理のコツなど聞いておけばよかった。
そう思ってももう遅い。
この家に入った瞬間から、篁四郎は料理係で、それ以外の何者でもなくなったのだ。
「リビングに他の2人もいるから」
「……はい」
「ここがお風呂と洗面所。ここがトイレ」
案内しながら奥へ行く潤子の後をついて行く。
「ここがリビングで、こっちが篁四郎くんの部屋」
リビングのドアのすぐ左にあるドアを開けながら、潤子が言う。
そこはごく普通の六畳の和室だった。
元々住んでいたアパートも六畳間の和室だったから、これなら荷物も全部余裕で入るだろう。
「篁四郎くん、家電はどうしたの?」
「リサイクルセンターに売りました。なかなか良い金になりましたよ」
「じゃあ、卒業するまではここにいてくれるんだ」
「そのつもりです」
「よかった」
定食屋のバイトも大学4年間するつもりだった。アパートも大学に近くて引っ越す理由もなかったし、ぼんやりと就職したら会社に通勤しやすいところに引っ越すだろうと思っていた。
その予定が崩れた今、このナナシ荘が卒業するまでの篁四郎の住む場所でバイトする場所になったのだ。
「では、他の2人に紹介するね」
篁四郎の部屋のドアを閉めて、潤子がリビングのドアを開ける。
そこはごく普通の家庭のリビングだった。
左側には台所とダイニングテーブルが置いてあり、右側にはテレビとローテーブル、そしてソファーが置いてあった。
そのソファーに四十代くらいの不機嫌そうな男性と、床に二十代くらいの手足の長い綺麗な青年が座っていた。
「ソファーに座っているのがシンさん、こっちがタツキくん。2人とも、こちらは新しい料理係の佐々木田篁四郎くん。よろしくね」
「佐々木田篁四郎です。よろしくお願いします」
篁四郎がそう挨拶すると、タツキがぴょんと立ち上がって人懐こい笑顔で肩を組んできた。
「わぁーやっと料理係来てくれたんだ。オレ、タツキ! 好きな食べ物は唐揚げ。作れる?」
「……作ったことない」
「……」
「……頑張ります」
「そうそうその意気。美味いやつ頼むわ」
にこにこと笑うタツキは、人当たりが良さそうで少しだけほっとした。篁四郎より少し年上に見えるが、潤子と似ているわけではなく関係はよく分からなかった。
「俺は鯖の味噌煮が好物だからな」
そうボソっと言ったのはシンだった。にこりともせず、ただそれだけ言ったら視線をテレビに移してしまった。
テレビでは天気予報が明日の天気は晴れだと言っていた。
「明日晴れなんだ。洗濯も各自だからね」
「あ、はい」
「なにはともあれ、ナナシ荘に来てくれてありがとう」
潤子がそう言うと、タツキも笑う。
「そうそう。料理係助かるんだよ。シローが来てくれて」
「シロー?」
「名前長くて覚えらんなかったから、シローでいいっしょ」
「はぁ」
ちらりとシンを見ると、なにも言われなかったが歓迎されてないわけではないらしい。
その証拠にもう一度「鯖の味噌煮忘れんなよ」と念を押されて、タツキと潤子がシンに気づかれないように笑っていた。
「あの」
「なぁに?」
「気になってたんですけど、ナナシ荘のナナシってなんなんですか?」
「え?」
「あぁ?」
「あ!」
篁四郎の質問に、タツキ、シン、潤子の順に三者三様の反応をする。どうやら知らないことに驚いているタツキとシンと、説明することを忘れていた潤子という状況らしい。
「潤子さん、説明してないの?」
「一番説明しねぇといけねぇとこだろうが」
「忘れてた」
タツキやシンに言われても特に気にした様子ではなく、潤子が声を出して笑う。
「篁四郎くんがバイトOKしてくれて嬉しくてすっかり忘れてたよ」
「ナナシってなにか意味があるんですか?」
「私も、シンさんもタツキくんもナナシなの」
「ナナシ?」
初めて聞いた言葉に、篁四郎が首を傾げる。
そういえば潤子の名字は知らない。タツキもシンも名字を名乗らなかったから、それが名字なのかもしれない。
なにか特殊な親戚同士なのだろうかと思っていると、潤子が話を続けた。
「妖怪でもない、人間でもない、分類に名前がない者をナナシと呼ぶのよ」
「妖怪?」
「そう。見たことない?」
まるで珍しい動物や伝統工芸を知っているか聞くかのように潤子が言う。
篁四郎自身親に連れられてあちこちに旅行したことがあるし、大学生になるだけの知識は持っている。だが、妖怪がこの世に存在するというのは信じたことはなかった。それはあくまでも小説やアニメの中での話で、実在するなんて思ったことはなかったからだ。
「見たこと、ないです」
だから、潤子の問いにもそう答えるしかなかった。
「潤子さんも、タツキさんも、シンさんも、その、ナナシなんですか?」
「そうだよ」
「それって、人間じゃ、ないってこと?」
「そう。人間じゃない」
潤子もタツキもシンも、ごく普通の人間に見える。目が三つあるわけじゃないし、耳が尖っているわけでも、牙が生えているわけでもない。角も生えていないのに、人間じゃないと言われてもどう反応していいのか分からない。
「人間じゃないって、どういうことですか?」
そう聞けば、潤子はなにも隠すことはないという風に笑った。
「私は四年に一度しか年を取らない。タツキくんは人より身体能力が優れてる」
「二階くらいならぽーんって飛ぶよ、オレ」
「そうそう。すっごいよ。それでシンさんは死なない」
「死なない?」
「刺されても、撃たれても死なねぇよ。痛ぇけどな」
潤子の説明に、タツキとシンがそれぞれ補足するように語る。
それが本当なのか、それを信じていいのか分からないまま立っていると、潤子がダイニングテーブルに誘った。
「シンさんを刺すわけにはいかないから、これ見せてあげる」
篁四郎をダイニングテーブルの椅子に座らせて、潤子が数枚の写真を取り出す。
それは白黒だったり、カラー写真でも古いものだったりした。その一枚には万博の入り口に今より幼い潤子が笑って写っていた。
「合成じゃないよ」
「でも大阪万博って」
「私、閏年生まれなんだ」
「あの四年に一度の?」
「そう。誕生日がこないと年をとれないじゃない? だから私は四年に一度しか年をとれないの。その写真は大阪万博だから13くらいかな」
「じゃあ、潤子さんって今」
「同級生は95歳」
「うちのひいばあちゃんと同じくらいじゃないですか」
「でも23だよ。誕生日は23回しか来てないもの。正解には23歳と3年目」
「来年は閏年ですね」
「そう、だから久しぶりに年を取るの。みんなで盛大にパーティーしてね」
「……はい」
潤子があまりになんでもないように話すから、そういうものだと思うようになった。きっとシンは刺されてても死ぬことはなく、タツキも屋根まで一っ飛びしてしまうのだろう。
それは見てなくても、潤子の言葉を信じただけだ。
「四年に一回しか年を取らない人間はいないし、そんな妖怪もいない。だからナナシって呼ばれてるの。そういう人が集まったのがこのナナシ荘。妖怪たちもね、集まって暮らしてるのよ」
「そうなんですか」
「集められて、の間違いだろうが」
潤子の言葉に、シンがそう言う。人によって解釈は様々のようだ。
「考え方はそれぞれだからね。篁四郎くんも機会があったら妖怪の人たちに会うといいわ」
「妖怪の人たちってどんな……」
「見かけは人間と同じなんだけど、ろくろ首は首が伸びるし、河童は水掻きがあって泳ぐのが得意だし、特別なことができるのよ」
「僕からしたら、潤子さんたちも十分特別ですよ」
「そうかもしれないわね」
篁四郎がそう言うと、ふっと潤子やタツキ、シンの持つ空気が柔らかくなった。
人間ではない。でも妖怪でもない、そんな中途半端な存在として「ナナシ」は扱われてきたのかもしれない。
ごく普通の人間である篁四郎にとっては、3人は不思議な存在だし、特別なものを持つ人々だ。なにもないわけじゃない。
「シロー、今日の夕飯なに?」
タツキが篁四郎の肩に腕を回してそう聞く。
「えっと、考えてなかった……冷蔵庫とか材料見て考えます」
「唐揚げでもいいから」
「揚げ物はもうちょっと練習してから」
「ちぇー」
「そういうのはボチボチ上手くなるもんだ。俺は鯵の開きも好物だ」
「あ、シンさんずっちぃの! 俺トンカツ!」
前のアパートでは隣人の顔すら知らなかった。
ここでは毎日挨拶する相手がいて、一緒に食卓を囲む相手がいる。
「ナナシ」と呼ばれる人たちでも、特別なものを持っていても、話しているとごく普通の人と変わらない。
初めて会ったタツキともシンとも、どうやら上手くやれそうだ。そのことに篁四郎は少しだけほっとした。
それから引っ越しのトラックが来て六畳の和室に荷物を運ぶのをみんなが手伝ってくれた。
布団にテーブル、それに本棚と衣装ボックス。六畳の和室はアパートの時と同じ雰囲気になった。
そうやって引っ越しの片づけをしていたらあっという間に夕食の時間になってしまい、苦肉の策として篁四郎は台所の棚にあった鯖の味噌煮の缶詰を出した。炊いたご飯に鯖の味噌煮、それにレトルトの味噌汁。
一見すると完璧な布陣に思えた。
「おおー人が用意してくれた夕飯!」
喜ぶタツキと缶詰に不満そうにしつつもすぐに手をつけてくれたシン。
「次は副菜もつけてくれよ」
「はい」
「日頃はみんな食べたいものをバラバラに食べてるの。一緒に食べるの久しぶりで嬉しい」
そう言って潤子が炊き立てのご飯を口に運んだ。
篁四郎がアパートで使っていた茶碗が、みんなの茶碗の一緒に並ぶ。
それが仲間になった気持ちにさせてくれて、少しだけくすぐったかった。
元いたアパートも住人は全員引っ越していって、秋には取り壊し工事が始まるらしい。定食屋も無事に閉店して、最終日には外に行列ができる忙しさだった。
おかげで7月はテストとバイトに明け暮れ、潤子との予定が合わず、引っ越し当日にナナシ荘を訪れる羽目になったのだ。
渡された住所を頼りに篁四郎が訪れたナナシ荘は二階建てのごく普通の家に見えた。
門にはナナシ荘と書かれた石の札が埋め込まれていた。
「あ、篁四郎くん、来たね」
「今日からお世話になります」
チャイムを鳴らしたら、すぐに潤子が出てきてくれた。他にも潤子以外の住人がいるらしく、開けられた玄関には男物の靴が並んでいた。
「他の人たちも待ってるよ」
「何人いるんですか?」
「私の他に2人いるよ。2人ともいい人だから」
「そうですか」
篁四郎が潤子から言われたバイト内容は、このナナシ荘での料理係だった。
特に料理の専門学校に行っているわけでも、得意なわけでもないのだと篁四郎が言っても、潤子は覚えていけばいいと言って料理の腕は木にしていないようだった。
「潤子さん、本当に僕でいいんですか?」
「篁四郎くんがいいの」
「料理できないですよ?」
「でも出会ってから少しは勉強したでしょ」
「家で自炊する回数が増えたくらいですけど」
「十分よ」
ネットで検索すれば料理のレシピなどいくらでも出てくる。篁四郎は定食屋で貰った余りものの食材を使って、炒め物や煮物を作っては失敗したり成功したりとしていた。
人に出すには躊躇うレベルではあるが、潤子がそれでいいというなら、もっと他のことで求められる仕事があるのかもしれない。
電球を変えたり、高いところのものをとったり、掃除をしたり、そういうこともやるのかもしれない。篁四郎自身特別背が高いというわけではないが、人並みの男性の身長はあるし、潤子よりはずっと背が高い。
それなら料理が下手でも歓迎される意味は分かる。
「入って入って」
「おじゃまします」
「下に台所とリビングとお風呂とおトイレと部屋が二つあるの。その一つを使ってね。二階は5部屋あって、私たちの部屋がそれぞれあるから」
「掃除とかは……」
「自分の部屋と台所以外はしなくていいわ」
「え?」
「だって篁四郎くんは料理係だもの」
笑う潤子の顔に嘘はない。
潤子が篁四郎の料理レベルでいいというのだから他にもなにかあると思っていたが、純粋に料理を求められているのであれば、もう少しレシピ本など買っていればよかったし、定食屋の店長に料理のコツなど聞いておけばよかった。
そう思ってももう遅い。
この家に入った瞬間から、篁四郎は料理係で、それ以外の何者でもなくなったのだ。
「リビングに他の2人もいるから」
「……はい」
「ここがお風呂と洗面所。ここがトイレ」
案内しながら奥へ行く潤子の後をついて行く。
「ここがリビングで、こっちが篁四郎くんの部屋」
リビングのドアのすぐ左にあるドアを開けながら、潤子が言う。
そこはごく普通の六畳の和室だった。
元々住んでいたアパートも六畳間の和室だったから、これなら荷物も全部余裕で入るだろう。
「篁四郎くん、家電はどうしたの?」
「リサイクルセンターに売りました。なかなか良い金になりましたよ」
「じゃあ、卒業するまではここにいてくれるんだ」
「そのつもりです」
「よかった」
定食屋のバイトも大学4年間するつもりだった。アパートも大学に近くて引っ越す理由もなかったし、ぼんやりと就職したら会社に通勤しやすいところに引っ越すだろうと思っていた。
その予定が崩れた今、このナナシ荘が卒業するまでの篁四郎の住む場所でバイトする場所になったのだ。
「では、他の2人に紹介するね」
篁四郎の部屋のドアを閉めて、潤子がリビングのドアを開ける。
そこはごく普通の家庭のリビングだった。
左側には台所とダイニングテーブルが置いてあり、右側にはテレビとローテーブル、そしてソファーが置いてあった。
そのソファーに四十代くらいの不機嫌そうな男性と、床に二十代くらいの手足の長い綺麗な青年が座っていた。
「ソファーに座っているのがシンさん、こっちがタツキくん。2人とも、こちらは新しい料理係の佐々木田篁四郎くん。よろしくね」
「佐々木田篁四郎です。よろしくお願いします」
篁四郎がそう挨拶すると、タツキがぴょんと立ち上がって人懐こい笑顔で肩を組んできた。
「わぁーやっと料理係来てくれたんだ。オレ、タツキ! 好きな食べ物は唐揚げ。作れる?」
「……作ったことない」
「……」
「……頑張ります」
「そうそうその意気。美味いやつ頼むわ」
にこにこと笑うタツキは、人当たりが良さそうで少しだけほっとした。篁四郎より少し年上に見えるが、潤子と似ているわけではなく関係はよく分からなかった。
「俺は鯖の味噌煮が好物だからな」
そうボソっと言ったのはシンだった。にこりともせず、ただそれだけ言ったら視線をテレビに移してしまった。
テレビでは天気予報が明日の天気は晴れだと言っていた。
「明日晴れなんだ。洗濯も各自だからね」
「あ、はい」
「なにはともあれ、ナナシ荘に来てくれてありがとう」
潤子がそう言うと、タツキも笑う。
「そうそう。料理係助かるんだよ。シローが来てくれて」
「シロー?」
「名前長くて覚えらんなかったから、シローでいいっしょ」
「はぁ」
ちらりとシンを見ると、なにも言われなかったが歓迎されてないわけではないらしい。
その証拠にもう一度「鯖の味噌煮忘れんなよ」と念を押されて、タツキと潤子がシンに気づかれないように笑っていた。
「あの」
「なぁに?」
「気になってたんですけど、ナナシ荘のナナシってなんなんですか?」
「え?」
「あぁ?」
「あ!」
篁四郎の質問に、タツキ、シン、潤子の順に三者三様の反応をする。どうやら知らないことに驚いているタツキとシンと、説明することを忘れていた潤子という状況らしい。
「潤子さん、説明してないの?」
「一番説明しねぇといけねぇとこだろうが」
「忘れてた」
タツキやシンに言われても特に気にした様子ではなく、潤子が声を出して笑う。
「篁四郎くんがバイトOKしてくれて嬉しくてすっかり忘れてたよ」
「ナナシってなにか意味があるんですか?」
「私も、シンさんもタツキくんもナナシなの」
「ナナシ?」
初めて聞いた言葉に、篁四郎が首を傾げる。
そういえば潤子の名字は知らない。タツキもシンも名字を名乗らなかったから、それが名字なのかもしれない。
なにか特殊な親戚同士なのだろうかと思っていると、潤子が話を続けた。
「妖怪でもない、人間でもない、分類に名前がない者をナナシと呼ぶのよ」
「妖怪?」
「そう。見たことない?」
まるで珍しい動物や伝統工芸を知っているか聞くかのように潤子が言う。
篁四郎自身親に連れられてあちこちに旅行したことがあるし、大学生になるだけの知識は持っている。だが、妖怪がこの世に存在するというのは信じたことはなかった。それはあくまでも小説やアニメの中での話で、実在するなんて思ったことはなかったからだ。
「見たこと、ないです」
だから、潤子の問いにもそう答えるしかなかった。
「潤子さんも、タツキさんも、シンさんも、その、ナナシなんですか?」
「そうだよ」
「それって、人間じゃ、ないってこと?」
「そう。人間じゃない」
潤子もタツキもシンも、ごく普通の人間に見える。目が三つあるわけじゃないし、耳が尖っているわけでも、牙が生えているわけでもない。角も生えていないのに、人間じゃないと言われてもどう反応していいのか分からない。
「人間じゃないって、どういうことですか?」
そう聞けば、潤子はなにも隠すことはないという風に笑った。
「私は四年に一度しか年を取らない。タツキくんは人より身体能力が優れてる」
「二階くらいならぽーんって飛ぶよ、オレ」
「そうそう。すっごいよ。それでシンさんは死なない」
「死なない?」
「刺されても、撃たれても死なねぇよ。痛ぇけどな」
潤子の説明に、タツキとシンがそれぞれ補足するように語る。
それが本当なのか、それを信じていいのか分からないまま立っていると、潤子がダイニングテーブルに誘った。
「シンさんを刺すわけにはいかないから、これ見せてあげる」
篁四郎をダイニングテーブルの椅子に座らせて、潤子が数枚の写真を取り出す。
それは白黒だったり、カラー写真でも古いものだったりした。その一枚には万博の入り口に今より幼い潤子が笑って写っていた。
「合成じゃないよ」
「でも大阪万博って」
「私、閏年生まれなんだ」
「あの四年に一度の?」
「そう。誕生日がこないと年をとれないじゃない? だから私は四年に一度しか年をとれないの。その写真は大阪万博だから13くらいかな」
「じゃあ、潤子さんって今」
「同級生は95歳」
「うちのひいばあちゃんと同じくらいじゃないですか」
「でも23だよ。誕生日は23回しか来てないもの。正解には23歳と3年目」
「来年は閏年ですね」
「そう、だから久しぶりに年を取るの。みんなで盛大にパーティーしてね」
「……はい」
潤子があまりになんでもないように話すから、そういうものだと思うようになった。きっとシンは刺されてても死ぬことはなく、タツキも屋根まで一っ飛びしてしまうのだろう。
それは見てなくても、潤子の言葉を信じただけだ。
「四年に一回しか年を取らない人間はいないし、そんな妖怪もいない。だからナナシって呼ばれてるの。そういう人が集まったのがこのナナシ荘。妖怪たちもね、集まって暮らしてるのよ」
「そうなんですか」
「集められて、の間違いだろうが」
潤子の言葉に、シンがそう言う。人によって解釈は様々のようだ。
「考え方はそれぞれだからね。篁四郎くんも機会があったら妖怪の人たちに会うといいわ」
「妖怪の人たちってどんな……」
「見かけは人間と同じなんだけど、ろくろ首は首が伸びるし、河童は水掻きがあって泳ぐのが得意だし、特別なことができるのよ」
「僕からしたら、潤子さんたちも十分特別ですよ」
「そうかもしれないわね」
篁四郎がそう言うと、ふっと潤子やタツキ、シンの持つ空気が柔らかくなった。
人間ではない。でも妖怪でもない、そんな中途半端な存在として「ナナシ」は扱われてきたのかもしれない。
ごく普通の人間である篁四郎にとっては、3人は不思議な存在だし、特別なものを持つ人々だ。なにもないわけじゃない。
「シロー、今日の夕飯なに?」
タツキが篁四郎の肩に腕を回してそう聞く。
「えっと、考えてなかった……冷蔵庫とか材料見て考えます」
「唐揚げでもいいから」
「揚げ物はもうちょっと練習してから」
「ちぇー」
「そういうのはボチボチ上手くなるもんだ。俺は鯵の開きも好物だ」
「あ、シンさんずっちぃの! 俺トンカツ!」
前のアパートでは隣人の顔すら知らなかった。
ここでは毎日挨拶する相手がいて、一緒に食卓を囲む相手がいる。
「ナナシ」と呼ばれる人たちでも、特別なものを持っていても、話しているとごく普通の人と変わらない。
初めて会ったタツキともシンとも、どうやら上手くやれそうだ。そのことに篁四郎は少しだけほっとした。
それから引っ越しのトラックが来て六畳の和室に荷物を運ぶのをみんなが手伝ってくれた。
布団にテーブル、それに本棚と衣装ボックス。六畳の和室はアパートの時と同じ雰囲気になった。
そうやって引っ越しの片づけをしていたらあっという間に夕食の時間になってしまい、苦肉の策として篁四郎は台所の棚にあった鯖の味噌煮の缶詰を出した。炊いたご飯に鯖の味噌煮、それにレトルトの味噌汁。
一見すると完璧な布陣に思えた。
「おおー人が用意してくれた夕飯!」
喜ぶタツキと缶詰に不満そうにしつつもすぐに手をつけてくれたシン。
「次は副菜もつけてくれよ」
「はい」
「日頃はみんな食べたいものをバラバラに食べてるの。一緒に食べるの久しぶりで嬉しい」
そう言って潤子が炊き立てのご飯を口に運んだ。
篁四郎がアパートで使っていた茶碗が、みんなの茶碗の一緒に並ぶ。
それが仲間になった気持ちにさせてくれて、少しだけくすぐったかった。
0
あなたにおすすめの小説

睿国怪奇伝〜オカルトマニアの皇妃様は怪異がお好き〜
猫とろ
キャラ文芸
大国。睿(えい)国。 先帝が急逝したため、二十五歳の若さで皇帝の玉座に座ることになった俊朗(ジュンラン)。
その妻も政略結婚で選ばれた幽麗(ユウリー)十八歳。 そんな二人は皇帝はリアリスト。皇妃はオカルトマニアだった。
まるで正反対の二人だが、お互いに政略結婚と割り切っている。
そんなとき、街にキョンシーが出たと言う噂が広がる。
「陛下キョンシーを捕まえたいです」
「幽麗。キョンシーの存在は俺は認めはしない」
幽麗の言葉を真っ向否定する俊朗帝。
だが、キョンシーだけではなく、街全体に何か怪しい怪異の噂が──。 俊朗帝と幽麗妃。二人は怪異を払う為に協力するが果たして……。
皇帝夫婦×中華ミステリーです!

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
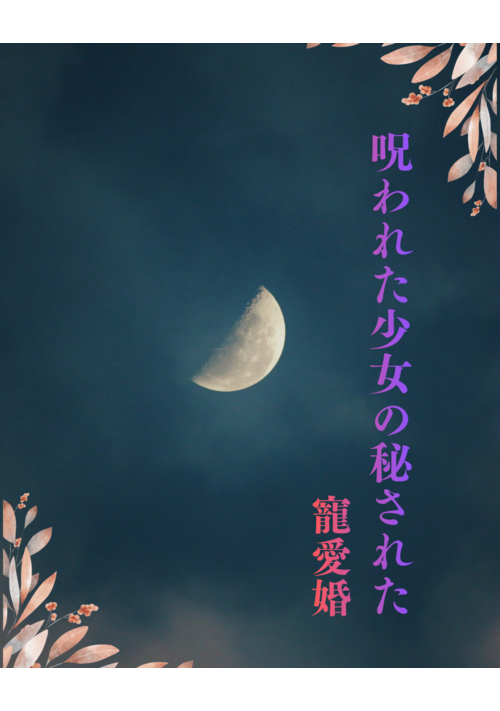
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。


烏の王と宵の花嫁
水川サキ
キャラ文芸
吸血鬼の末裔として生まれた華族の娘、月夜は家族から虐げられ孤独に生きていた。
唯一の慰めは、年に一度届く〈からす〉からの手紙。
その送り主は太陽の化身と称される上級華族、縁樹だった。
ある日、姉の縁談相手を誤って傷つけた月夜は、父に遊郭へ売られそうになり屋敷を脱出するが、陽の下で倒れてしまう。
死を覚悟した瞬間〈からす〉の正体である縁樹が現れ、互いの思惑から契約結婚を結ぶことになる。
※初出2024年7月

【完結】20年後の真実
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。
マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。
それから20年。
マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。
そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。
おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。
全4話書き上げ済み。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















