9 / 27
本編
9 痛くて苦しいのはどうして?
しおりを挟む
モモハ様に指名されてから七日が過ぎた。
僕はまた誰にも指名されなくなってしまい、こうしてぼんやりと窓の外を眺める日々を送っている。主人に僕にできることがないか聞いてみたけど「男娼が男娼以外の仕事をしてどうする」と睨まれてしまった。
「でも、その男娼の仕事がないんだもんなぁ」
モモハ様に聞いた変な噂がまだ流れているんだろうか。それならものすごく困るし、立派な営業妨害だ。
「……もし噂のせいじゃなくて、ただ指名されなくなったけだとしたら……」
一瞬そんなことを考えてしまった。
指名されなくなった男娼はやめるしかない。身請け先があるならまだしも、行き先がないままやめれば住む場所も働く場所も失うことになる。僕みたいなひょろっとしただけの男に男娼以外の仕事が見つかるとは思えない。つまり、男娼をやめるということは人生の終わりということだ。
「やめやめ! 嫌なことなんて考えても、どうしようもない!」
ただでさえアララギ中佐を思い出さないようにするだけでも大変なのに、こんなことばかり考えていたら気が滅入ってしまう。
「こんなときは甘い物を食べるに限る!」
趣味といえばお金を貯めることくらいの僕にとって、街に出て甘い物を食べることが唯一の気晴らしだった。僕はいつもより少し多めの硬貨を持って外に出た。
娼館街の通りは相変わらずキラキラした人たちで溢れている。お客さんたちもだけど、娼婦や男娼も大抵は着飾っていた。なぜなら自分を綺麗に見せるのが仕事だからだ。
だけど僕は下働きのような格好で歩く。身なりにお金をかけたくないからなんだけど、主人からは「せめてもう少しどうにかしろ」と言われるくらい地味だった。
「そんなこと言っても、僕なんかが着飾ったところでどうしようもないし」
綺麗で可愛い男娼なら着飾る意味もあるだろう。でも、平凡な僕が着飾ったところで意味がない。それに変に目立つのも嫌だし、知り合いに気づかれないほうが気が楽だと思っている。
「さぁて、今日は何を食べようかな。いつもよりちょっと奮発してフルーツタルトもいいなぁ。うーん、でも生クリームも捨て難いし、チョコレートも食べたい気分だし、迷っちゃうなぁ」
娼館街の門から出て通りを進むと馴染みの洋菓子店がある。そこへ向かいながら、僕の頭の中は綺麗で甘いケーキのことでいっぱいになっていた。
それなのに、ふと視界に入った人影にすうっと視線が引き寄せられた。いつもなら数日前のお客さんを見かけても気づかないのに、びっくりするくらいその人に視線が吸い寄せられる。
「……アララギ中佐だ」
大きな噴水の向こう側に軍服姿のアララギ中佐がいた。ガッシリした大きな体に真っ黒な軍服がすごく似合っている。帯刀しているということは仕事中なのかもしれない。初めて見る軍服姿の中佐に、僕は「かっこいい……」と一瞬にして見惚れてしまった。そうして、中佐の隣にもう一人いることに気がついた。
「誰だろう」
淡いピンク色のドレスを着た小柄な女性だ。中佐の腕に手を絡めているくらいだから親しい人なんだろう。綺麗に整えられた頭を必死に上げながら中佐と何か話をしている。
「貴族のご令嬢かな」
身なりからそう思った。僕からは背中しか見えない中佐がどんな顔をしているのかはわからないけど、女性はニコニコしている。
「……っ」
急に胸が苦しくなった。ズキズキして息も少しだけ苦しくなる。
僕は足を引きずるように噴水から離れた。楽しみにしていた甘い物のことなんてすっかり消えてしまい、いまはただ自分の部屋に早く帰りたくて仕方ない。
(なんでこんなに苦しいんだろう)
中佐が貴族らしき女性と一緒にいるのを見ただけなのに、僕の体は一体どうしてしまったんだろう。変だなと思ったけど、胸も息もどんどん苦しくなってそれどころじゃなくなる。
倒れてしまうんじゃないかと怖くなった僕は、とにかく娼館に帰ろうと足を動かした。そうして娼館街の門をくぐったところで誰かにぶつかってしまった。よろよろとした足取りだったせいか、ほんの少しぶつかっただけなのに尻もちをついてしまう。
「っと、ごめん! って、ツバキじゃないか」
「あ、ヤナギさん」
「どうかしたのか?」
「あの、ごめんなさい」
「いや、それは僕も前をよく見ていなかったからお互い様だ。そうじゃなくて、……ツバキ、何かあった?」
「……いえ、別に、なにも」
一瞬、中佐と女性の姿が蘇った。でも、それを見ただけで何かあったわけじゃない。だから僕は何でもないと答えた。
「うーん、そうは見えないんだけど。……そうだ、時間ある?」
「はい」
「じゃ、僕の部屋においで」
「えぇー、ヤナギさんの部屋に行ったって知られたら、また何か言われちゃいそうだなぁ」
そう言ったらヤナギさんがふわりと笑った。
絶対に嫌味を言われるだろうからいつもは行かないけど、差し出された手を断る気にはなれない。それに何となく一人になるのが嫌で、僕は誘われるままヤナギさんの部屋についていった。
ヤナギさんの部屋は娼館の一階の奥にある。そこは暗黙の了解で主人以外は近づかない場所だ。僕は手ほどきを受けていたということもあって、これまでも何度か部屋に入ったことがある。久し振りに入ったヤナギさんの部屋は相変わらず物が少なくて、でも落ち着いた雰囲気で少しだけいい匂いがした。
「お茶いれるから、ちょっと待ってて」
奥に消えたヤナギさんを待ちながら、ぼんやりと庭を眺める。部屋からは整えられた中庭がよく見える。真ん中あたりには大きくなった藤の蔓が木陰を作っていて、そういえば昔、あの下でよく泣いたなぁなんてことを思い出した。
「藤の木、大きくなりましたね」
「そうだなぁ。これでも毎年あちこち切ってはいるんだけどね」
「そうなんですか?」
「藤の蔓って、気をつけないとどんどん伸びちゃうからね。きちんと手入れしないと、屋根まで伸びたら大変なことになる」
「そっかぁ、大変なんですね。いっそのこと根元から切ってしまおうとは思わないんですか?」
「さすがにそれはかわいそうでしょ。それに、ジュッテンが許さないだろうし」
「へ? 主人が?」
「一緒にあの下で遊んだ思い出の花だからね。そうそう、泣いてたツバキとの思い出もあるし」
「うわぁぁ、ヤナギさん、それもう忘れてくださいよぅ」
娼館に来たばかりの頃、鈍臭かった僕は仕事で失敗してばかりしていた。それでも頑張ろうと努力したものの、どんなに頑張っても失敗ばかりしてしまう。
そんな自分が心底嫌になった。失敗ばかりしていたら別のところに売られてしまうかもしれない。それが怖くて、僕は厠や風呂場でこっそり泣いたりしていた。
「ツバキが努力家なのは、ジュッテンも僕もちゃんとわかってる。いまは失敗しても、そのうちできるようになるからね」
泣いている僕にそう声をかけてくれたのがヤナギさんだった。「泣きたくなったら、ここで泣いていいよ」と言ってくれたのを真に受けた僕は、泣きそうになるたびに藤の木の下に隠れて少しだけメソメソした。そんな僕の頭をヤナギさんが撫でてくれて……なんてことがあったあの頃が懐かしい。
「あの頃のツバキは純粋な子どもって感じで可愛かったなぁ。あ、いまも十分可愛いよ?」
「僕が可愛くないことは、僕が一番知ってますよー」
「あははは、そりゃあ見た目はグングン大きくなったからね。でも中身はあの頃のままで可愛い。まぁ、ちょっと育ち方に難があるのは心配な部分だけど」
「育ち方って、僕はもう子どもじゃないですってば」
「うんうん、体は立派な大人になったな」
うぅむ、どうもヤナギさんは僕を子ども扱いしすぎるような気がする。そりゃ五歳のときから面倒をみてくれているヤナギさんからすれば、いつまでも子どもみたいに見えるのかもしれない。それでも僕だってもうすぐ二十五歳になる。体だって主人くらいの大きさになった。それに見た目が決して可愛いものじゃないこともよくわかっている。
(そもそも僕を可愛いとか言うの、ヤナギさんくらいだし)
ということは、やっぱり子ども扱いされているのかもしれない。何だか情けなくて、つい口を尖らせてしまった。そのままヤナギさんが入れてくれたミルクティーにフゥフゥと息を吹きかける。
「で、ツバキ、何かあったでしょ」
「いいえ? 何もないですよ?」
本当にそんなことを言われる心当たりがないから、僕は首を傾げながらそう答えた。
「じゃあ、アララギ中佐と何かあった?」
「へ!?」
急に中佐の名前が出てビックリした。同時に噴水のところで見かけた姿を思い出して、またキュウッと胸が苦しくなる。
「……何もないですよ。中佐がずっと来てないのは、ヤナギさんも知ってるじゃないですか」
「うん、そうだな。じゃあ、街で会った?」
「会ってはないです。……チラッと、見かけはしましたけど」
「ふむふむ。じゃあ、そのときの中佐がいつもと違ったとか?」
ヤナギさんの優しい声に促されるように、気がついたら僕は噴水のところで女性と一緒にいるアララギ中佐を見たことを話していた。
「そっか、女性と一緒だったのか」
「中佐は上級士官だし、恋人がいてもおかしくないですよ」
「恋人」って単語を口にした途端に、今度は胸がキリキリと痛くなった。同じくらい苦しくて、ちょっと息がしづらい。
「うーん、どうだろうなぁ。アララギ中佐は中佐だけど、ちょっと違うからな」
「ちょっと違う?」
「うん、そう。もちろんツバキが言うように中佐っていうのは上級士官なんだけどね。でも、アララギ中佐は貴族出身じゃないから」
「へ?」
「アララギ中佐は軍曹から叩き上げで中佐になった人だと言われているんだけど……。結構有名な話なんだけど、その様子じゃツバキは知らなかったのか」
そんな話、まったく知らなかった。というか、僕はアララギ中佐のことは中佐だっていうこと以外、何も知らない。
昔から僕はお客さんへの興味が薄い。というより、行為以外のことはあまり話さないようにしてきた。好きな食べ物や飲み物を聞いたりはするけど、家族のことや仕事のことを聞くことはない。お客さんから話してくる場合も聞き役に徹するだけで、深く聞いたり知ろうとしたこともなかった。
(だって、詳しく知ってしまったら後が寂しくなるだけだ)
深く知ってしまったぶん、必要とされなくなったときの悲しみは大きくなる。そんな思いをするくらいなら最初から何も知らないほうがいい。
だから、アララギ中佐のことも何も知らないままだ。中佐も自分のことを話すほうじゃないから、お酒は辛いほうが好きということと、意外と甘いものも食べる、なんてことくらいしか知らない。
「貴族出身じゃない場合の上級士官の最高位っていうのがあってね。准将って言うんだけど、アララギ中佐はそれより上の大佐のさらに上、少将にって話が持ち上がっているらしいよ」
「少将って、それって三番目に偉い人ですよね?」
「そうだね。少将ともなれば特権階級中の特権階級だ。異例なことだけど大将直々の命令らしいし、そうなったらその辺りの貴族でも叶わないくらいのお金持ちになるねぇ」
ヤナギさんの言葉に、僕は頭がクラクラした。ここは娼館街随一の高級娼館だけど、そんな偉い人がお客さんとして来ることはまずない。仮に娼婦や男娼を必要としたとしても自分のお屋敷に呼ぶのが普通で、呼ばれる側もほんのひと握りの選ばれた人だけだ。
まさか、自分のお客さんがそんな偉い人になるなんて思ってもみなかった。それはとても嬉しいことのはずなのに、胸がズキズキしてますます息苦しくなってくる。
「いやぁ、アララギ中佐がそんな大出世するとは思わなかったな」
「……僕も、すごく驚いてます。そんな人が僕のお客さんだったなんて、びっくりしすぎて現実じゃないみたいです」
「なに言ってるの。中佐はツバキの上客中の上客じゃないか」
「そうですけど……。あ、でも、きっともう指名はされないと思います。っていうか、少将になったら高級娼館に来ることもなくなるだろうし」
「さて、それはどうかな。僕はツバキを指名しに来ると思うけど」
「ヤナギさんったら、なに言ってるんですか。さすがに少将に昇進したら来ませんって。それに恋人がいるのに、わざわざ男娼に会いに来るとかおかしいじゃないですか」
「あはは」と笑いながらも、どんどん胸が痛くなってきた。ギュウッと苦しくなって、ヤナギさんと話しているのもつらくなってくる。
これ以上ここにいるのもしんどいなぁと思っていると、下働きの子がヤナギさんを呼びに来た。なんでも主人が呼んでいるとかで、「ごめんな」と言ってヤナギさんが部屋を出て行く。
僕は内心ホッとしながら、自分の部屋に戻ることにした。部屋に入って、ベッドにぽすんと座ってからぼんやりと窓の外を眺めた。
「そっかぁ。アララギ中佐は、アララギ少将になるのかぁ」
少将は王宮に呼ばれるくらいの地位だから、僕とはまったく別の世界の人になるということだ。
「そんな偉い人になるなら、奥様がいないと困るんじゃないかな」
偉い人たちは、王宮に呼ばれるとき奥様同伴だと聞いたことがある。ということは、今日見かけたあの小柄な女性が未来の奥様だったのかもしれない。チラッと見ただけでも、パッチリした目が可愛らしい若いご令嬢のように見えた。
「中佐の歳はわからないけど、お似合いだったなぁ」
僕なんかが隣にいるより、よほどお似合いだ。
「……って、なんで僕が中佐の隣に……あはは、変なの」
笑いながら、胸が痛くて苦しくてどうしようもなくなってくる。どうしてこんなに苦しいのかわからないけど、この感じは僕にとってあまりよくないような気がした。
「それにしても軍服姿、かっこよかったなぁ」
あれが最初で最後に見る中佐の軍服姿になった。そう思いながら何度もかっこいい姿を頭に浮かべる。思い出すだけでつらくて苦しくなるのに、忘れないようにと思って何度も何度も思い返した。
僕はまた誰にも指名されなくなってしまい、こうしてぼんやりと窓の外を眺める日々を送っている。主人に僕にできることがないか聞いてみたけど「男娼が男娼以外の仕事をしてどうする」と睨まれてしまった。
「でも、その男娼の仕事がないんだもんなぁ」
モモハ様に聞いた変な噂がまだ流れているんだろうか。それならものすごく困るし、立派な営業妨害だ。
「……もし噂のせいじゃなくて、ただ指名されなくなったけだとしたら……」
一瞬そんなことを考えてしまった。
指名されなくなった男娼はやめるしかない。身請け先があるならまだしも、行き先がないままやめれば住む場所も働く場所も失うことになる。僕みたいなひょろっとしただけの男に男娼以外の仕事が見つかるとは思えない。つまり、男娼をやめるということは人生の終わりということだ。
「やめやめ! 嫌なことなんて考えても、どうしようもない!」
ただでさえアララギ中佐を思い出さないようにするだけでも大変なのに、こんなことばかり考えていたら気が滅入ってしまう。
「こんなときは甘い物を食べるに限る!」
趣味といえばお金を貯めることくらいの僕にとって、街に出て甘い物を食べることが唯一の気晴らしだった。僕はいつもより少し多めの硬貨を持って外に出た。
娼館街の通りは相変わらずキラキラした人たちで溢れている。お客さんたちもだけど、娼婦や男娼も大抵は着飾っていた。なぜなら自分を綺麗に見せるのが仕事だからだ。
だけど僕は下働きのような格好で歩く。身なりにお金をかけたくないからなんだけど、主人からは「せめてもう少しどうにかしろ」と言われるくらい地味だった。
「そんなこと言っても、僕なんかが着飾ったところでどうしようもないし」
綺麗で可愛い男娼なら着飾る意味もあるだろう。でも、平凡な僕が着飾ったところで意味がない。それに変に目立つのも嫌だし、知り合いに気づかれないほうが気が楽だと思っている。
「さぁて、今日は何を食べようかな。いつもよりちょっと奮発してフルーツタルトもいいなぁ。うーん、でも生クリームも捨て難いし、チョコレートも食べたい気分だし、迷っちゃうなぁ」
娼館街の門から出て通りを進むと馴染みの洋菓子店がある。そこへ向かいながら、僕の頭の中は綺麗で甘いケーキのことでいっぱいになっていた。
それなのに、ふと視界に入った人影にすうっと視線が引き寄せられた。いつもなら数日前のお客さんを見かけても気づかないのに、びっくりするくらいその人に視線が吸い寄せられる。
「……アララギ中佐だ」
大きな噴水の向こう側に軍服姿のアララギ中佐がいた。ガッシリした大きな体に真っ黒な軍服がすごく似合っている。帯刀しているということは仕事中なのかもしれない。初めて見る軍服姿の中佐に、僕は「かっこいい……」と一瞬にして見惚れてしまった。そうして、中佐の隣にもう一人いることに気がついた。
「誰だろう」
淡いピンク色のドレスを着た小柄な女性だ。中佐の腕に手を絡めているくらいだから親しい人なんだろう。綺麗に整えられた頭を必死に上げながら中佐と何か話をしている。
「貴族のご令嬢かな」
身なりからそう思った。僕からは背中しか見えない中佐がどんな顔をしているのかはわからないけど、女性はニコニコしている。
「……っ」
急に胸が苦しくなった。ズキズキして息も少しだけ苦しくなる。
僕は足を引きずるように噴水から離れた。楽しみにしていた甘い物のことなんてすっかり消えてしまい、いまはただ自分の部屋に早く帰りたくて仕方ない。
(なんでこんなに苦しいんだろう)
中佐が貴族らしき女性と一緒にいるのを見ただけなのに、僕の体は一体どうしてしまったんだろう。変だなと思ったけど、胸も息もどんどん苦しくなってそれどころじゃなくなる。
倒れてしまうんじゃないかと怖くなった僕は、とにかく娼館に帰ろうと足を動かした。そうして娼館街の門をくぐったところで誰かにぶつかってしまった。よろよろとした足取りだったせいか、ほんの少しぶつかっただけなのに尻もちをついてしまう。
「っと、ごめん! って、ツバキじゃないか」
「あ、ヤナギさん」
「どうかしたのか?」
「あの、ごめんなさい」
「いや、それは僕も前をよく見ていなかったからお互い様だ。そうじゃなくて、……ツバキ、何かあった?」
「……いえ、別に、なにも」
一瞬、中佐と女性の姿が蘇った。でも、それを見ただけで何かあったわけじゃない。だから僕は何でもないと答えた。
「うーん、そうは見えないんだけど。……そうだ、時間ある?」
「はい」
「じゃ、僕の部屋においで」
「えぇー、ヤナギさんの部屋に行ったって知られたら、また何か言われちゃいそうだなぁ」
そう言ったらヤナギさんがふわりと笑った。
絶対に嫌味を言われるだろうからいつもは行かないけど、差し出された手を断る気にはなれない。それに何となく一人になるのが嫌で、僕は誘われるままヤナギさんの部屋についていった。
ヤナギさんの部屋は娼館の一階の奥にある。そこは暗黙の了解で主人以外は近づかない場所だ。僕は手ほどきを受けていたということもあって、これまでも何度か部屋に入ったことがある。久し振りに入ったヤナギさんの部屋は相変わらず物が少なくて、でも落ち着いた雰囲気で少しだけいい匂いがした。
「お茶いれるから、ちょっと待ってて」
奥に消えたヤナギさんを待ちながら、ぼんやりと庭を眺める。部屋からは整えられた中庭がよく見える。真ん中あたりには大きくなった藤の蔓が木陰を作っていて、そういえば昔、あの下でよく泣いたなぁなんてことを思い出した。
「藤の木、大きくなりましたね」
「そうだなぁ。これでも毎年あちこち切ってはいるんだけどね」
「そうなんですか?」
「藤の蔓って、気をつけないとどんどん伸びちゃうからね。きちんと手入れしないと、屋根まで伸びたら大変なことになる」
「そっかぁ、大変なんですね。いっそのこと根元から切ってしまおうとは思わないんですか?」
「さすがにそれはかわいそうでしょ。それに、ジュッテンが許さないだろうし」
「へ? 主人が?」
「一緒にあの下で遊んだ思い出の花だからね。そうそう、泣いてたツバキとの思い出もあるし」
「うわぁぁ、ヤナギさん、それもう忘れてくださいよぅ」
娼館に来たばかりの頃、鈍臭かった僕は仕事で失敗してばかりしていた。それでも頑張ろうと努力したものの、どんなに頑張っても失敗ばかりしてしまう。
そんな自分が心底嫌になった。失敗ばかりしていたら別のところに売られてしまうかもしれない。それが怖くて、僕は厠や風呂場でこっそり泣いたりしていた。
「ツバキが努力家なのは、ジュッテンも僕もちゃんとわかってる。いまは失敗しても、そのうちできるようになるからね」
泣いている僕にそう声をかけてくれたのがヤナギさんだった。「泣きたくなったら、ここで泣いていいよ」と言ってくれたのを真に受けた僕は、泣きそうになるたびに藤の木の下に隠れて少しだけメソメソした。そんな僕の頭をヤナギさんが撫でてくれて……なんてことがあったあの頃が懐かしい。
「あの頃のツバキは純粋な子どもって感じで可愛かったなぁ。あ、いまも十分可愛いよ?」
「僕が可愛くないことは、僕が一番知ってますよー」
「あははは、そりゃあ見た目はグングン大きくなったからね。でも中身はあの頃のままで可愛い。まぁ、ちょっと育ち方に難があるのは心配な部分だけど」
「育ち方って、僕はもう子どもじゃないですってば」
「うんうん、体は立派な大人になったな」
うぅむ、どうもヤナギさんは僕を子ども扱いしすぎるような気がする。そりゃ五歳のときから面倒をみてくれているヤナギさんからすれば、いつまでも子どもみたいに見えるのかもしれない。それでも僕だってもうすぐ二十五歳になる。体だって主人くらいの大きさになった。それに見た目が決して可愛いものじゃないこともよくわかっている。
(そもそも僕を可愛いとか言うの、ヤナギさんくらいだし)
ということは、やっぱり子ども扱いされているのかもしれない。何だか情けなくて、つい口を尖らせてしまった。そのままヤナギさんが入れてくれたミルクティーにフゥフゥと息を吹きかける。
「で、ツバキ、何かあったでしょ」
「いいえ? 何もないですよ?」
本当にそんなことを言われる心当たりがないから、僕は首を傾げながらそう答えた。
「じゃあ、アララギ中佐と何かあった?」
「へ!?」
急に中佐の名前が出てビックリした。同時に噴水のところで見かけた姿を思い出して、またキュウッと胸が苦しくなる。
「……何もないですよ。中佐がずっと来てないのは、ヤナギさんも知ってるじゃないですか」
「うん、そうだな。じゃあ、街で会った?」
「会ってはないです。……チラッと、見かけはしましたけど」
「ふむふむ。じゃあ、そのときの中佐がいつもと違ったとか?」
ヤナギさんの優しい声に促されるように、気がついたら僕は噴水のところで女性と一緒にいるアララギ中佐を見たことを話していた。
「そっか、女性と一緒だったのか」
「中佐は上級士官だし、恋人がいてもおかしくないですよ」
「恋人」って単語を口にした途端に、今度は胸がキリキリと痛くなった。同じくらい苦しくて、ちょっと息がしづらい。
「うーん、どうだろうなぁ。アララギ中佐は中佐だけど、ちょっと違うからな」
「ちょっと違う?」
「うん、そう。もちろんツバキが言うように中佐っていうのは上級士官なんだけどね。でも、アララギ中佐は貴族出身じゃないから」
「へ?」
「アララギ中佐は軍曹から叩き上げで中佐になった人だと言われているんだけど……。結構有名な話なんだけど、その様子じゃツバキは知らなかったのか」
そんな話、まったく知らなかった。というか、僕はアララギ中佐のことは中佐だっていうこと以外、何も知らない。
昔から僕はお客さんへの興味が薄い。というより、行為以外のことはあまり話さないようにしてきた。好きな食べ物や飲み物を聞いたりはするけど、家族のことや仕事のことを聞くことはない。お客さんから話してくる場合も聞き役に徹するだけで、深く聞いたり知ろうとしたこともなかった。
(だって、詳しく知ってしまったら後が寂しくなるだけだ)
深く知ってしまったぶん、必要とされなくなったときの悲しみは大きくなる。そんな思いをするくらいなら最初から何も知らないほうがいい。
だから、アララギ中佐のことも何も知らないままだ。中佐も自分のことを話すほうじゃないから、お酒は辛いほうが好きということと、意外と甘いものも食べる、なんてことくらいしか知らない。
「貴族出身じゃない場合の上級士官の最高位っていうのがあってね。准将って言うんだけど、アララギ中佐はそれより上の大佐のさらに上、少将にって話が持ち上がっているらしいよ」
「少将って、それって三番目に偉い人ですよね?」
「そうだね。少将ともなれば特権階級中の特権階級だ。異例なことだけど大将直々の命令らしいし、そうなったらその辺りの貴族でも叶わないくらいのお金持ちになるねぇ」
ヤナギさんの言葉に、僕は頭がクラクラした。ここは娼館街随一の高級娼館だけど、そんな偉い人がお客さんとして来ることはまずない。仮に娼婦や男娼を必要としたとしても自分のお屋敷に呼ぶのが普通で、呼ばれる側もほんのひと握りの選ばれた人だけだ。
まさか、自分のお客さんがそんな偉い人になるなんて思ってもみなかった。それはとても嬉しいことのはずなのに、胸がズキズキしてますます息苦しくなってくる。
「いやぁ、アララギ中佐がそんな大出世するとは思わなかったな」
「……僕も、すごく驚いてます。そんな人が僕のお客さんだったなんて、びっくりしすぎて現実じゃないみたいです」
「なに言ってるの。中佐はツバキの上客中の上客じゃないか」
「そうですけど……。あ、でも、きっともう指名はされないと思います。っていうか、少将になったら高級娼館に来ることもなくなるだろうし」
「さて、それはどうかな。僕はツバキを指名しに来ると思うけど」
「ヤナギさんったら、なに言ってるんですか。さすがに少将に昇進したら来ませんって。それに恋人がいるのに、わざわざ男娼に会いに来るとかおかしいじゃないですか」
「あはは」と笑いながらも、どんどん胸が痛くなってきた。ギュウッと苦しくなって、ヤナギさんと話しているのもつらくなってくる。
これ以上ここにいるのもしんどいなぁと思っていると、下働きの子がヤナギさんを呼びに来た。なんでも主人が呼んでいるとかで、「ごめんな」と言ってヤナギさんが部屋を出て行く。
僕は内心ホッとしながら、自分の部屋に戻ることにした。部屋に入って、ベッドにぽすんと座ってからぼんやりと窓の外を眺めた。
「そっかぁ。アララギ中佐は、アララギ少将になるのかぁ」
少将は王宮に呼ばれるくらいの地位だから、僕とはまったく別の世界の人になるということだ。
「そんな偉い人になるなら、奥様がいないと困るんじゃないかな」
偉い人たちは、王宮に呼ばれるとき奥様同伴だと聞いたことがある。ということは、今日見かけたあの小柄な女性が未来の奥様だったのかもしれない。チラッと見ただけでも、パッチリした目が可愛らしい若いご令嬢のように見えた。
「中佐の歳はわからないけど、お似合いだったなぁ」
僕なんかが隣にいるより、よほどお似合いだ。
「……って、なんで僕が中佐の隣に……あはは、変なの」
笑いながら、胸が痛くて苦しくてどうしようもなくなってくる。どうしてこんなに苦しいのかわからないけど、この感じは僕にとってあまりよくないような気がした。
「それにしても軍服姿、かっこよかったなぁ」
あれが最初で最後に見る中佐の軍服姿になった。そう思いながら何度もかっこいい姿を頭に浮かべる。思い出すだけでつらくて苦しくなるのに、忘れないようにと思って何度も何度も思い返した。
22
あなたにおすすめの小説

バイト先に元カレがいるんだが、どうすりゃいい?
cheeery
BL
サークルに一人暮らしと、完璧なキャンパスライフが始まった俺……広瀬 陽(ひろせ あき)
ひとつ問題があるとすれば金欠であるということだけ。
「そうだ、バイトをしよう!」
一人暮らしをしている近くのカフェでバイトをすることが決まり、初めてのバイトの日。
教育係として現れたのは……なんと高二の冬に俺を振った元カレ、三上 隼人(みかみ はやと)だった!
なんで元カレがここにいるんだよ!
俺の気持ちを弄んでフッた最低な元カレだったのに……。
「あんまり隙見せない方がいいよ。遠慮なくつけこむから」
「ねぇ、今どっちにドキドキしてる?」
なんか、俺……ずっと心臓が落ち着かねぇ!
もう一度期待したら、また傷つく?
あの時、俺たちが別れた本当の理由は──?
「そろそろ我慢の限界かも」

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

希少なΩだと隠して生きてきた薬師は、視察に来た冷徹なα騎士団長に一瞬で見抜かれ「お前は俺の番だ」と帝都に連れ去られてしまう
水凪しおん
BL
「君は、今日から俺のものだ」
辺境の村で薬師として静かに暮らす青年カイリ。彼には誰にも言えない秘密があった。それは希少なΩ(オメガ)でありながら、その性を偽りβ(ベータ)として生きていること。
ある日、村を訪れたのは『帝国の氷盾』と畏れられる冷徹な騎士団総長、リアム。彼は最上級のα(アルファ)であり、カイリが必死に隠してきたΩの資質をいとも簡単に見抜いてしまう。
「お前のその特異な力を、帝国のために使え」
強引に帝都へ連れ去られ、リアムの屋敷で“偽りの主従関係”を結ぶことになったカイリ。冷たい命令とは裏腹に、リアムが時折見せる不器用な優しさと孤独を秘めた瞳に、カイリの心は次第に揺らいでいく。
しかし、カイリの持つ特別なフェロモンは帝国の覇権を揺るがす甘美な毒。やがて二人は、宮廷を渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく――。
運命の番(つがい)に抗う不遇のΩと、愛を知らない最強α騎士。
偽りの関係から始まる、甘く切ない身分差ファンタジー・ラブ!
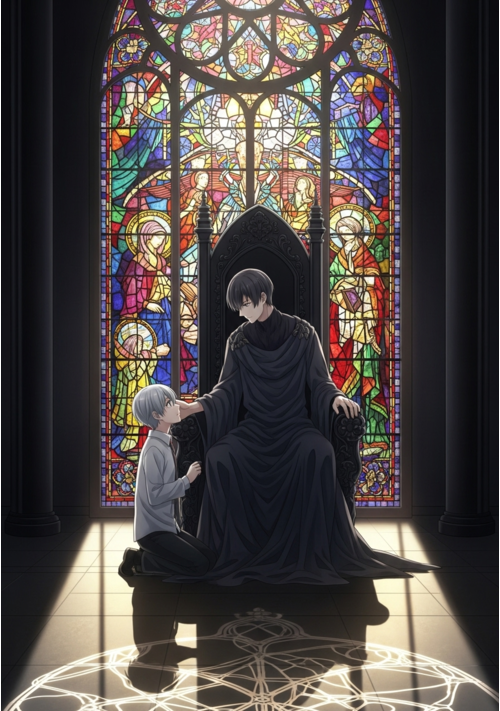
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

隣国のΩに婚約破棄をされたので、お望み通り侵略して差し上げよう。
下井理佐
BL
救いなし。序盤で受けが死にます。
文章がおかしな所があったので修正しました。
大国の第一王子・αのジスランは、小国の王子・Ωのルシエルと幼い頃から許嫁の関係だった。
ただの政略結婚の相手であるとルシエルに興味を持たないジスランであったが、婚約発表の社交界前夜、ルシエルから婚約破棄するから受け入れてほしいと言われる。
理由を聞くジスランであったが、ルシエルはただ、
「必ず僕の国を滅ぼして」
それだけ言い、去っていった。
社交界当日、ルシエルは約束通り婚約破棄を皆の前で宣言する。

巷で噂の国宝級イケメンの辺境伯は冷徹なので、まっっったくモテませんが、この度婚約者ができました。
明太子
BL
オーディスは国宝級イケメンであるにも関わらず、冷徹な性格のせいで婚約破棄されてばかり。
新たな婚約者を探していたところ、パーティーで給仕をしていた貧乏貴族の次男セシルと出会い、一目惚れしてしまう。
しかし、恋愛偏差値がほぼ0のオーディスのアプローチは空回りするわ、前婚約者のフランチェスカの邪魔が入るわとセシルとの距離は縮まったり遠ざかったり…?
冷徹だったはずなのに溺愛まっしぐらのオーディスと元気だけどおっちょこちょいなセシルのドタバタラブコメです。

ブラコンすぎて面倒な男を演じていた平凡兄、やめたら押し倒されました
あと
BL
「お兄ちゃん!人肌脱ぎます!」
完璧公爵跡取り息子許嫁攻め×ブラコン兄鈍感受け
可愛い弟と攻めの幸せのために、平凡なのに面倒な男を演じることにした受け。毎日の告白、束縛発言などを繰り広げ、上手くいきそうになったため、やめたら、なんと…?
攻め:ヴィクター・ローレンツ
受け:リアム・グレイソン
弟:リチャード・グレイソン
pixivにも投稿しています。
ひよったら消します。
誤字脱字はサイレント修正します。
また、内容もサイレント修正する時もあります。
定期的にタグも整理します。
批判・中傷コメントはお控えください。
見つけ次第削除いたします。

異世界にやってきたら氷の宰相様が毎日お手製の弁当を持たせてくれる
七瀬京
BL
異世界に召喚された大学生ルイは、この世界を救う「巫覡」として、力を失った宝珠を癒やす役目を与えられる。
だが、異界の食べ物を受けつけない身体に苦しみ、倒れてしまう。
そんな彼を救ったのは、“氷の宰相”と呼ばれる美貌の男・ルースア。
唯一ルイが食べられるのは、彼の手で作られた料理だけ――。
優しさに触れるたび、ルイの胸に芽生える感情は“感謝”か、それとも“恋”か。
穏やかな日々の中で、ふたりの距離は静かに溶け合っていく。
――心と身体を癒やす、年の差主従ファンタジーBL。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















