8 / 27
本編
8 なんだか変なんです
しおりを挟む
アララギ中佐が来なくなって二十日が経った。こんなに長く中佐の顔を見なかったのは最初の頃以来だからか変な感じがする。
そのせいか、最近中佐の顔を頻繁に思い出すようになった。とくに最後に見た顔が忘れられない。困っているように見えたけど、あれはやっぱり怒っていたんじゃないだろうか。
「僕が何か言ったんだろうなぁ」
昔に比べたら変なことは言わなくなったと思う。それでも「もしかして」と不安になる。
「今度指名してくれたときに謝ろう」
でも、もし指名してくれなかったら? それどころか二度と来なかったら……そう思ったら胸がギュッと苦しくなった。こうやって痛みを感じる日が増えてきた。しかもアララギ中佐のことを考えるときに限って痛くなる。
「それもこれも毎日暇にしているせいだ」
中佐が来なくなってからも僕を指名してくれるお客さんは一人もいない。男娼としてあるまじき状況だけど、主人からは「おまえにはたっぷり金を落としてもらっているから問題ない」と言われて首を傾げた。
「指名されないのに問題ないなんて、そんなわけないのに」
かといって余計なことを言えば説教されるに決まっている。だから毎日こうしてぼんやり過ごす時間ばかりが増えていた。
「……やっぱり駄目だ!」
ただぼんやりしているだけなんて、僕の性に合わない。
五歳でここに来たときは下働きとして、十歳からは下働きに加えて先輩たちの雑用係もこなしてきた。お客さんを取るようになってからは男娼の仕事しかしていないけど、部屋の掃除や片付けなんかは下働きに任せないで自分でやっている。
それなのに、中佐が来なくなっただけで何もやる気にならないなんて駄目だ。なにより時間があると中佐のことばかり考えてしまう自分が怖い。
「よし、仕事を探しに行こう」
男娼の僕は下働きをする必要はないけど、何かやれることがないか主人に聞いてみよう。そう思って部屋を出た。
「やぁ、ツバキじゃないか」
主人の部屋に行く前に、娼館の玄関で懐かしい人に声をかけられた。
「あ、…………モモハ様」
「あれ? もしかして僕の名前、忘れちゃってた?」
「そんなことあるわけないじゃないですかぁ」
「あはは」と笑いながら、本当はそうだったことに冷や汗をかいた。
モモハ様は僕が男娼になった頃に指名してくれていたお客さんだ。間隔は空いていたけど、珍しく三度指名してくれたから名前を思い出すことができた。
そういえば、モモハ様は結構な家柄の貴族だと聞いた気がする。当時ほとんど指名されなかった僕にとっては貴重なお客さんで、服や腕輪をもらったりもした。本人は「三男坊だから自由気ままなんだ」と言っていたけど、こうして昼間から高級娼館にいるということは、いまも自由気ままに暮らしているに違いない。
「そうだ。ツバキってお客取るのやめたの?」
「いいえ、そんなことないですよ?」
「え? そうなの?」
「?」
不思議そうなモモハ様の顔に、僕のほうが首を傾げた。こうして僕がここにいられるのは現役の男娼だからだ。もしお客さんを取らなくなるとしたら、男娼を廃業してここを出て行くときだ。
「僕はまだこうして働いてますし、お客様の指名は大歓迎ですよ?」
「ふふ、ツバキは昔から気持ちいいことが大好きだったもんね~。じゃあ、あの噂は間違いだったってことか」
「噂ですか?」
「うん。ここ二、三カ月くらいだけど、ツバキの指名ができないって話だったから、てっきり引退するのかと思ってた」
「えぇー。引退する予定なんてありませんし、お客様を断ったりもしませんけど」
「だよね~」
まさかそんな噂が流れていたとは思わなかった。だから誰も僕を指名してくれなくて、こうして暇になったというわけか。
理由はわかったけど、どうしてそんなことになったのかがわからない。意地悪で噂を流した人がいたとしても、主人が知ったら激怒するはずだ。それなのに主人が怒っているような様子はなかった。僕がウンウン考えていると、モモハ様に「じゃあさ」と声をかけられた。
「僕が指名したら、相手してくれる?」
「え? あ、はい、もちろんです」
指名してもらえるのはありがたい。そう思って頷いたら、にこりと笑ったモモハ様が受付を兼ねた応接間に入っていった。
その日の陽暮れ前に、僕は難しい顔をした主人に呼ばれた。そこでモモハ様に指名されたことを聞いた。
「なるほど、今回の指名の件はわかった」
指名された経緯を話すと、なぜか主人が厳しい顔になった。
「もしかして僕、何かしましたか……?」
「いいや、男娼が直接客から約束を取るのは間違いじゃない。そういう意味では、おまえは何もやらかしてない」
「やらかしていない」という言葉にビクッとしつつも、それならどうしてそんな怖い顔をしているんだろうと思った。主人の綺麗な形の眉はググッと中央に寄っている。目つきだっていつもより鋭い。口元はもちろん笑っていないし、超絶美人が怒った姿は震えるくらい怖かった。
「まぁ、ここは娼館だからな。男娼が客を取らなくなったらお終いではある」
「あの」
「上客との約束は大事だが絶対ではない。それは彼方さんも理解していることだ」
「あのぅ」
「なにより本人が取りつけた指名だ。俺がどうこう言うことでもないだろうし」
「あの~」
主人には僕の声がまったく聞こえていないのか、そっと声をかけても視線すら向けてもらえなかった。かといって大声で呼ぶのも怖いしと困っていると、ヤナギさんが部屋に入ってきた。
ヤナギさんは主人の片腕で、高級娼館で働く人たちを取り仕切っている。僕の手ほどきをしてくれた人ということもあって、これまでにも何かと相談に乗ってもらっている頼れる人だ。
「あれ? ツバキ、どうしたの?」
「ヤナギさぁん」
僕の情けない声に主人を見たヤナギさんは、「あらら」と言って苦笑した。
「ジュッテン、呼び出した相手を放置して考え事に耽るなって、いつも言ってるだろう?」
「ん? あぁ、ヤナギか」
「ヤナギか、じゃないよ? ツバキが困ってる」
「あぁ、そうだった。すまなかったな」
「別にいいですけど」
「あはは。困った顔のツバキも可愛いなぁ」
「ヤナギさん! 可愛いって、僕もうすぐ二十五になるんですけど」
ちょっとむくれながらそう言うと、「そうかそうか、もう二十五か」なんて言いながらヤナギさんが僕の頭を撫でた。僕より少ししか背が高くないヤナギさんに頭を撫でられるのは微妙な感じがするけど、ここに来た頃のことを思い出すからか少しだけ嬉しくなる。
「何歳になっても、ツバキは僕にとっては可愛い弟みたいなものだからね」
そう言って目を細めて笑うヤナギさんのほうこそ、いつまでも若いと思う。
(っていうか、実際何歳なんだろう)
僕が五歳でここに来たときにはもう仕切りの仕事をしていたから、それほど若くないはずだ。それなのにヤナギさんはいつまで経っても見た目が変わらなくてかっこいい。姐さんたちにも男娼たちにもすごく人気があって、ヤナギさんに手ほどきされた僕はいつも羨ましがられていた。
「で、ジュッテンは何をそんなに難しい顔してたんだ?」
「あぁいや、ツバキに指名が入ったんだ」
「……なるほど。まぁ男娼のままだから、仕方ないことではあるね」
ヤナギさんまで難しい顔になった。もしかして僕がお客さんに指名されるのはまずいことだったんだろうか。でも僕は男娼だ。お客さんに指名されないことのほうがまずい。それなのに、どうして二人とも困った顔をしているんだろう。
「それとなく噂を流しておいたけど、やっぱり限界だったな。彼方さんに連絡する?」
「いや、その辺も納得のうえでの約束だからな。今回のことで何か言われたりはしないだろう」
「なるほど。じゃあ、何がそんなに気になるの?」
「いや、この段階でというのがな」
「うーん、たしかになぁ」
今度は二人そろって僕を見ている。
「ツバキは、まだ男娼としてお客様に指名されたい?」
ヤナギさんの言葉に僕は大きく頷いた。
「僕は男娼ですから、やめるまではお客様が指名してくれないと困ります」
「なるほど、それはもっともだ。じゃあ、モモハ様の指名を受けてもいいんだね?」
「はい、僕は大丈夫ですけど……。もしかして、何か問題があるんですか?」
「まぁ大丈夫だとは思うけど」
「ツバキが自分で決めたことだ。彼方さんの件は、また別だろう」
「そうだね。まぁ、これも仕方ないか」
またよくわからない話に戻ってしまった。結局、最後まで主人とヤナギさんが何に困っているのかはわからなかった。
そうして僕は次の日の夜、久しぶりにお客さんを迎えることになった。
「うぅ~、緊張するなぁ」
中佐以外のお客さんは久しぶりだからか妙に緊張する。そのせいか、無意味に何度もお酒やお茶の確認をしてしまった。
「そういや中佐、お酒にもお茶にも関心がないみたいだったなぁ」
しまった、また中佐のことを思い出してしまった。途端にギュッと胸が痛くなる。こんなことじゃ駄目だとわかっているのに、一度思い出すと次々にいろんなことが頭に浮かんだ。
最初は怖かった中佐の強面も、思い出すときは可愛い表情しか出て来ない。ほんの少し碧眼が笑うのも可愛いけど、へにょりと口が歪むときが一番可愛かった。
それに大きな体も可愛いと思う。ゴツゴツした手は僕の頭を覆うくらい大きくて、全身を撫でられるとすごく気持ちがいい。もちろんあの手に腰を掴まれて、立派すぎる逸物がググッと挿入り込むのはとんでもない気持ちよさで……。
「って、何やってんだよ僕は」
これからお客さんが来るのに、別のお客さんのことを思い出すなんて初めてだ。
慌てて頭を振って気持ちを切り替えたけど、モモハ様との行為の最中もアララギ中佐のことばかり思い出すことになってしまった。
「はぁ……相変わらずツバキのココ、締まりがすごくて気持ちいいなぁ」
「んっ、ぁ、ぁん!」
「ふふっ、ここ、好きだったよね……っと!」
「ひんっ!」
モモハ様の先端が、グリグリと前立腺を押し潰しながら奥に挿入ってきた。たしかに気持ちよかったけど、なぜかちょっとだけ物足りなく感じてしまう。
(中佐のだったら、もっと力強く擦ってくれて……もっとナカをめいっぱい広げてるって感じ、なのに……)
「はぁ、も、イキそ……。前、いじってあげる」
「ひゃうっ!?」
「はは、すごいビッショリだね。は、はぁ、は、は……っ」
「ひぅっ、あ、あっ、あっ、ぁあっ!」
ガンガン腰をぶつけながら、モモハ様の手が僕の性器を握ったことに驚いた。
(中佐のときは、前、触んなくても、出ちゃうから……ぁあんっ!)
グチュグチュ音を立てて性器を擦り上げられるのは気持ちいいのに、どうしてか変な感じがした。こうして前を擦らないとイケなかったのが嘘のように、擦られるほうがうまくイケなくなっている。
「あ、あ、あぁ! 出ちゃ、出ちゃ、うぅ……!」
久しぶりに勢いよく射精した気がした。いつもはトロトロ押し出されるように出るからか、まるで粗相をしてしまった気がして落ち着かない。
それでも射精に合わせるように後ろがギュッと締まって、それを突き破るようにモモハ様の逸物が動いた。そうして最後にドクン! と弾けた。ドクドクと吐き出される精液が僕の奥を濡らしている。それなのに、やっぱり物足りない気がした。
(中佐のは、奥の壁にぶつかって、そこをたくさん突いてくれて、それが死ぬほど気持ちがいいから、かなぁ)
残念ながらモモハ様の逸物は、中佐の逸物ほど奥には届かない。それに僕の意識も最後まではっきりしている。中佐とだったら、一度目の絶頂ですでに軽く飛んでいるはずだ。
「はぁっ、気持ちよかった。あぁ、ツバキの泣き顔、やっぱりいいなぁ」
「モモハさま」
「体はこんなに立派になったのに、泣き顔はまるで子どもみたいだ。それがすごくやらしくて癖になるんだよね。そういう客は意外といるんだけど、ここの主人は客選びが厳しいからなぁ」
よくわからないけど、モモハ様も僕の泣き顔が好きだったんだと初めて知った。「やっぱり男娼としてどうなんだろう」と思いはしたものの、それで指名してくれたんだから文句はない。
怠いながらも動く体をずらして、モモハ様の腕に身を寄せる。モモハ様とは同じくらいの体格だから、くっつくと寄り添うような感じになった。
(すっぽり抱きしめてくれる中佐って、やっぱり大きいんだなぁ)
それに中佐は一回だけで終わったりはしない。
結局僕は、最後までアララギ中佐のことを思い出してばかりだった。モモハ様との行為も十分気持ちよかったはずなのに、どこか物足りなくて体の奥が燻り続ける。
(中佐、いつ来てくれるかなぁ)
モモハ様の体温を感じながら、また中佐を思い出した。強面の顔を思い浮かべるだけで胸がキュウッと苦しくなって、それに気づかない振りをしながら目を閉じた。
そのせいか、最近中佐の顔を頻繁に思い出すようになった。とくに最後に見た顔が忘れられない。困っているように見えたけど、あれはやっぱり怒っていたんじゃないだろうか。
「僕が何か言ったんだろうなぁ」
昔に比べたら変なことは言わなくなったと思う。それでも「もしかして」と不安になる。
「今度指名してくれたときに謝ろう」
でも、もし指名してくれなかったら? それどころか二度と来なかったら……そう思ったら胸がギュッと苦しくなった。こうやって痛みを感じる日が増えてきた。しかもアララギ中佐のことを考えるときに限って痛くなる。
「それもこれも毎日暇にしているせいだ」
中佐が来なくなってからも僕を指名してくれるお客さんは一人もいない。男娼としてあるまじき状況だけど、主人からは「おまえにはたっぷり金を落としてもらっているから問題ない」と言われて首を傾げた。
「指名されないのに問題ないなんて、そんなわけないのに」
かといって余計なことを言えば説教されるに決まっている。だから毎日こうしてぼんやり過ごす時間ばかりが増えていた。
「……やっぱり駄目だ!」
ただぼんやりしているだけなんて、僕の性に合わない。
五歳でここに来たときは下働きとして、十歳からは下働きに加えて先輩たちの雑用係もこなしてきた。お客さんを取るようになってからは男娼の仕事しかしていないけど、部屋の掃除や片付けなんかは下働きに任せないで自分でやっている。
それなのに、中佐が来なくなっただけで何もやる気にならないなんて駄目だ。なにより時間があると中佐のことばかり考えてしまう自分が怖い。
「よし、仕事を探しに行こう」
男娼の僕は下働きをする必要はないけど、何かやれることがないか主人に聞いてみよう。そう思って部屋を出た。
「やぁ、ツバキじゃないか」
主人の部屋に行く前に、娼館の玄関で懐かしい人に声をかけられた。
「あ、…………モモハ様」
「あれ? もしかして僕の名前、忘れちゃってた?」
「そんなことあるわけないじゃないですかぁ」
「あはは」と笑いながら、本当はそうだったことに冷や汗をかいた。
モモハ様は僕が男娼になった頃に指名してくれていたお客さんだ。間隔は空いていたけど、珍しく三度指名してくれたから名前を思い出すことができた。
そういえば、モモハ様は結構な家柄の貴族だと聞いた気がする。当時ほとんど指名されなかった僕にとっては貴重なお客さんで、服や腕輪をもらったりもした。本人は「三男坊だから自由気ままなんだ」と言っていたけど、こうして昼間から高級娼館にいるということは、いまも自由気ままに暮らしているに違いない。
「そうだ。ツバキってお客取るのやめたの?」
「いいえ、そんなことないですよ?」
「え? そうなの?」
「?」
不思議そうなモモハ様の顔に、僕のほうが首を傾げた。こうして僕がここにいられるのは現役の男娼だからだ。もしお客さんを取らなくなるとしたら、男娼を廃業してここを出て行くときだ。
「僕はまだこうして働いてますし、お客様の指名は大歓迎ですよ?」
「ふふ、ツバキは昔から気持ちいいことが大好きだったもんね~。じゃあ、あの噂は間違いだったってことか」
「噂ですか?」
「うん。ここ二、三カ月くらいだけど、ツバキの指名ができないって話だったから、てっきり引退するのかと思ってた」
「えぇー。引退する予定なんてありませんし、お客様を断ったりもしませんけど」
「だよね~」
まさかそんな噂が流れていたとは思わなかった。だから誰も僕を指名してくれなくて、こうして暇になったというわけか。
理由はわかったけど、どうしてそんなことになったのかがわからない。意地悪で噂を流した人がいたとしても、主人が知ったら激怒するはずだ。それなのに主人が怒っているような様子はなかった。僕がウンウン考えていると、モモハ様に「じゃあさ」と声をかけられた。
「僕が指名したら、相手してくれる?」
「え? あ、はい、もちろんです」
指名してもらえるのはありがたい。そう思って頷いたら、にこりと笑ったモモハ様が受付を兼ねた応接間に入っていった。
その日の陽暮れ前に、僕は難しい顔をした主人に呼ばれた。そこでモモハ様に指名されたことを聞いた。
「なるほど、今回の指名の件はわかった」
指名された経緯を話すと、なぜか主人が厳しい顔になった。
「もしかして僕、何かしましたか……?」
「いいや、男娼が直接客から約束を取るのは間違いじゃない。そういう意味では、おまえは何もやらかしてない」
「やらかしていない」という言葉にビクッとしつつも、それならどうしてそんな怖い顔をしているんだろうと思った。主人の綺麗な形の眉はググッと中央に寄っている。目つきだっていつもより鋭い。口元はもちろん笑っていないし、超絶美人が怒った姿は震えるくらい怖かった。
「まぁ、ここは娼館だからな。男娼が客を取らなくなったらお終いではある」
「あの」
「上客との約束は大事だが絶対ではない。それは彼方さんも理解していることだ」
「あのぅ」
「なにより本人が取りつけた指名だ。俺がどうこう言うことでもないだろうし」
「あの~」
主人には僕の声がまったく聞こえていないのか、そっと声をかけても視線すら向けてもらえなかった。かといって大声で呼ぶのも怖いしと困っていると、ヤナギさんが部屋に入ってきた。
ヤナギさんは主人の片腕で、高級娼館で働く人たちを取り仕切っている。僕の手ほどきをしてくれた人ということもあって、これまでにも何かと相談に乗ってもらっている頼れる人だ。
「あれ? ツバキ、どうしたの?」
「ヤナギさぁん」
僕の情けない声に主人を見たヤナギさんは、「あらら」と言って苦笑した。
「ジュッテン、呼び出した相手を放置して考え事に耽るなって、いつも言ってるだろう?」
「ん? あぁ、ヤナギか」
「ヤナギか、じゃないよ? ツバキが困ってる」
「あぁ、そうだった。すまなかったな」
「別にいいですけど」
「あはは。困った顔のツバキも可愛いなぁ」
「ヤナギさん! 可愛いって、僕もうすぐ二十五になるんですけど」
ちょっとむくれながらそう言うと、「そうかそうか、もう二十五か」なんて言いながらヤナギさんが僕の頭を撫でた。僕より少ししか背が高くないヤナギさんに頭を撫でられるのは微妙な感じがするけど、ここに来た頃のことを思い出すからか少しだけ嬉しくなる。
「何歳になっても、ツバキは僕にとっては可愛い弟みたいなものだからね」
そう言って目を細めて笑うヤナギさんのほうこそ、いつまでも若いと思う。
(っていうか、実際何歳なんだろう)
僕が五歳でここに来たときにはもう仕切りの仕事をしていたから、それほど若くないはずだ。それなのにヤナギさんはいつまで経っても見た目が変わらなくてかっこいい。姐さんたちにも男娼たちにもすごく人気があって、ヤナギさんに手ほどきされた僕はいつも羨ましがられていた。
「で、ジュッテンは何をそんなに難しい顔してたんだ?」
「あぁいや、ツバキに指名が入ったんだ」
「……なるほど。まぁ男娼のままだから、仕方ないことではあるね」
ヤナギさんまで難しい顔になった。もしかして僕がお客さんに指名されるのはまずいことだったんだろうか。でも僕は男娼だ。お客さんに指名されないことのほうがまずい。それなのに、どうして二人とも困った顔をしているんだろう。
「それとなく噂を流しておいたけど、やっぱり限界だったな。彼方さんに連絡する?」
「いや、その辺も納得のうえでの約束だからな。今回のことで何か言われたりはしないだろう」
「なるほど。じゃあ、何がそんなに気になるの?」
「いや、この段階でというのがな」
「うーん、たしかになぁ」
今度は二人そろって僕を見ている。
「ツバキは、まだ男娼としてお客様に指名されたい?」
ヤナギさんの言葉に僕は大きく頷いた。
「僕は男娼ですから、やめるまではお客様が指名してくれないと困ります」
「なるほど、それはもっともだ。じゃあ、モモハ様の指名を受けてもいいんだね?」
「はい、僕は大丈夫ですけど……。もしかして、何か問題があるんですか?」
「まぁ大丈夫だとは思うけど」
「ツバキが自分で決めたことだ。彼方さんの件は、また別だろう」
「そうだね。まぁ、これも仕方ないか」
またよくわからない話に戻ってしまった。結局、最後まで主人とヤナギさんが何に困っているのかはわからなかった。
そうして僕は次の日の夜、久しぶりにお客さんを迎えることになった。
「うぅ~、緊張するなぁ」
中佐以外のお客さんは久しぶりだからか妙に緊張する。そのせいか、無意味に何度もお酒やお茶の確認をしてしまった。
「そういや中佐、お酒にもお茶にも関心がないみたいだったなぁ」
しまった、また中佐のことを思い出してしまった。途端にギュッと胸が痛くなる。こんなことじゃ駄目だとわかっているのに、一度思い出すと次々にいろんなことが頭に浮かんだ。
最初は怖かった中佐の強面も、思い出すときは可愛い表情しか出て来ない。ほんの少し碧眼が笑うのも可愛いけど、へにょりと口が歪むときが一番可愛かった。
それに大きな体も可愛いと思う。ゴツゴツした手は僕の頭を覆うくらい大きくて、全身を撫でられるとすごく気持ちがいい。もちろんあの手に腰を掴まれて、立派すぎる逸物がググッと挿入り込むのはとんでもない気持ちよさで……。
「って、何やってんだよ僕は」
これからお客さんが来るのに、別のお客さんのことを思い出すなんて初めてだ。
慌てて頭を振って気持ちを切り替えたけど、モモハ様との行為の最中もアララギ中佐のことばかり思い出すことになってしまった。
「はぁ……相変わらずツバキのココ、締まりがすごくて気持ちいいなぁ」
「んっ、ぁ、ぁん!」
「ふふっ、ここ、好きだったよね……っと!」
「ひんっ!」
モモハ様の先端が、グリグリと前立腺を押し潰しながら奥に挿入ってきた。たしかに気持ちよかったけど、なぜかちょっとだけ物足りなく感じてしまう。
(中佐のだったら、もっと力強く擦ってくれて……もっとナカをめいっぱい広げてるって感じ、なのに……)
「はぁ、も、イキそ……。前、いじってあげる」
「ひゃうっ!?」
「はは、すごいビッショリだね。は、はぁ、は、は……っ」
「ひぅっ、あ、あっ、あっ、ぁあっ!」
ガンガン腰をぶつけながら、モモハ様の手が僕の性器を握ったことに驚いた。
(中佐のときは、前、触んなくても、出ちゃうから……ぁあんっ!)
グチュグチュ音を立てて性器を擦り上げられるのは気持ちいいのに、どうしてか変な感じがした。こうして前を擦らないとイケなかったのが嘘のように、擦られるほうがうまくイケなくなっている。
「あ、あ、あぁ! 出ちゃ、出ちゃ、うぅ……!」
久しぶりに勢いよく射精した気がした。いつもはトロトロ押し出されるように出るからか、まるで粗相をしてしまった気がして落ち着かない。
それでも射精に合わせるように後ろがギュッと締まって、それを突き破るようにモモハ様の逸物が動いた。そうして最後にドクン! と弾けた。ドクドクと吐き出される精液が僕の奥を濡らしている。それなのに、やっぱり物足りない気がした。
(中佐のは、奥の壁にぶつかって、そこをたくさん突いてくれて、それが死ぬほど気持ちがいいから、かなぁ)
残念ながらモモハ様の逸物は、中佐の逸物ほど奥には届かない。それに僕の意識も最後まではっきりしている。中佐とだったら、一度目の絶頂ですでに軽く飛んでいるはずだ。
「はぁっ、気持ちよかった。あぁ、ツバキの泣き顔、やっぱりいいなぁ」
「モモハさま」
「体はこんなに立派になったのに、泣き顔はまるで子どもみたいだ。それがすごくやらしくて癖になるんだよね。そういう客は意外といるんだけど、ここの主人は客選びが厳しいからなぁ」
よくわからないけど、モモハ様も僕の泣き顔が好きだったんだと初めて知った。「やっぱり男娼としてどうなんだろう」と思いはしたものの、それで指名してくれたんだから文句はない。
怠いながらも動く体をずらして、モモハ様の腕に身を寄せる。モモハ様とは同じくらいの体格だから、くっつくと寄り添うような感じになった。
(すっぽり抱きしめてくれる中佐って、やっぱり大きいんだなぁ)
それに中佐は一回だけで終わったりはしない。
結局僕は、最後までアララギ中佐のことを思い出してばかりだった。モモハ様との行為も十分気持ちよかったはずなのに、どこか物足りなくて体の奥が燻り続ける。
(中佐、いつ来てくれるかなぁ)
モモハ様の体温を感じながら、また中佐を思い出した。強面の顔を思い浮かべるだけで胸がキュウッと苦しくなって、それに気づかない振りをしながら目を閉じた。
15
あなたにおすすめの小説

バイト先に元カレがいるんだが、どうすりゃいい?
cheeery
BL
サークルに一人暮らしと、完璧なキャンパスライフが始まった俺……広瀬 陽(ひろせ あき)
ひとつ問題があるとすれば金欠であるということだけ。
「そうだ、バイトをしよう!」
一人暮らしをしている近くのカフェでバイトをすることが決まり、初めてのバイトの日。
教育係として現れたのは……なんと高二の冬に俺を振った元カレ、三上 隼人(みかみ はやと)だった!
なんで元カレがここにいるんだよ!
俺の気持ちを弄んでフッた最低な元カレだったのに……。
「あんまり隙見せない方がいいよ。遠慮なくつけこむから」
「ねぇ、今どっちにドキドキしてる?」
なんか、俺……ずっと心臓が落ち着かねぇ!
もう一度期待したら、また傷つく?
あの時、俺たちが別れた本当の理由は──?
「そろそろ我慢の限界かも」

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。
毒島醜女
BL
目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。
そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。
彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。
「これでやっと安心して退場できる」
これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。
目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。
「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」
その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。
「あなた……Ωになっていますよ」
「へ?」
そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――
オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

希少なΩだと隠して生きてきた薬師は、視察に来た冷徹なα騎士団長に一瞬で見抜かれ「お前は俺の番だ」と帝都に連れ去られてしまう
水凪しおん
BL
「君は、今日から俺のものだ」
辺境の村で薬師として静かに暮らす青年カイリ。彼には誰にも言えない秘密があった。それは希少なΩ(オメガ)でありながら、その性を偽りβ(ベータ)として生きていること。
ある日、村を訪れたのは『帝国の氷盾』と畏れられる冷徹な騎士団総長、リアム。彼は最上級のα(アルファ)であり、カイリが必死に隠してきたΩの資質をいとも簡単に見抜いてしまう。
「お前のその特異な力を、帝国のために使え」
強引に帝都へ連れ去られ、リアムの屋敷で“偽りの主従関係”を結ぶことになったカイリ。冷たい命令とは裏腹に、リアムが時折見せる不器用な優しさと孤独を秘めた瞳に、カイリの心は次第に揺らいでいく。
しかし、カイリの持つ特別なフェロモンは帝国の覇権を揺るがす甘美な毒。やがて二人は、宮廷を渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく――。
運命の番(つがい)に抗う不遇のΩと、愛を知らない最強α騎士。
偽りの関係から始まる、甘く切ない身分差ファンタジー・ラブ!
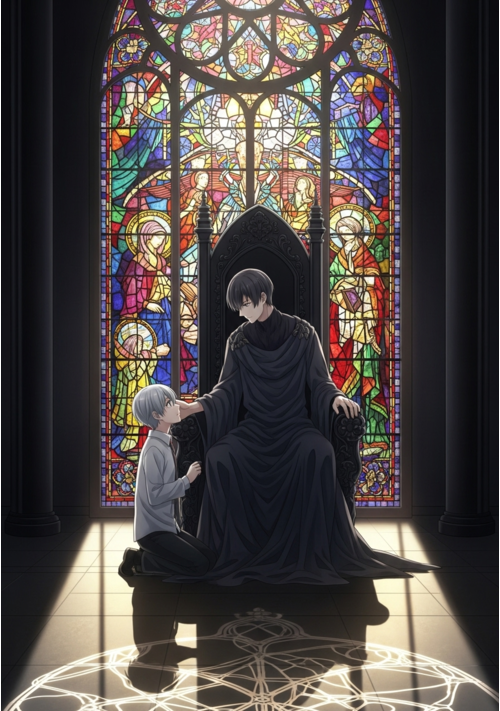
過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件
水凪しおん
BL
ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。
赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。
目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。
「ああ、終わった……食べられるんだ」
絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。
「ようやく会えた、我が魂の半身よ」
それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?
最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。
この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!
そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。
永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。
敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

隣国のΩに婚約破棄をされたので、お望み通り侵略して差し上げよう。
下井理佐
BL
救いなし。序盤で受けが死にます。
文章がおかしな所があったので修正しました。
大国の第一王子・αのジスランは、小国の王子・Ωのルシエルと幼い頃から許嫁の関係だった。
ただの政略結婚の相手であるとルシエルに興味を持たないジスランであったが、婚約発表の社交界前夜、ルシエルから婚約破棄するから受け入れてほしいと言われる。
理由を聞くジスランであったが、ルシエルはただ、
「必ず僕の国を滅ぼして」
それだけ言い、去っていった。
社交界当日、ルシエルは約束通り婚約破棄を皆の前で宣言する。

巷で噂の国宝級イケメンの辺境伯は冷徹なので、まっっったくモテませんが、この度婚約者ができました。
明太子
BL
オーディスは国宝級イケメンであるにも関わらず、冷徹な性格のせいで婚約破棄されてばかり。
新たな婚約者を探していたところ、パーティーで給仕をしていた貧乏貴族の次男セシルと出会い、一目惚れしてしまう。
しかし、恋愛偏差値がほぼ0のオーディスのアプローチは空回りするわ、前婚約者のフランチェスカの邪魔が入るわとセシルとの距離は縮まったり遠ざかったり…?
冷徹だったはずなのに溺愛まっしぐらのオーディスと元気だけどおっちょこちょいなセシルのドタバタラブコメです。

沈黙のΩ、冷血宰相に拾われて溺愛されました
ホワイトヴァイス
BL
声を奪われ、競売にかけられたΩ《オメガ》――ノア。
落札したのは、冷血と呼ばれる宰相アルマン・ヴァルナティス。
“番契約”を偽装した取引から始まったふたりの関係は、
やがて国を揺るがす“真実”へとつながっていく。
喋れぬΩと、血を信じない宰相。
ただの契約だったはずの絆が、
互いの傷と孤独を少しずつ融かしていく。
だが、王都の夜に潜む副宰相ルシアンの影が、
彼らの「嘘」を暴こうとしていた――。
沈黙が祈りに変わるとき、
血の支配が終わりを告げ、
“番”の意味が書き換えられる。
冷血宰相×沈黙のΩ、
偽りの契約から始まる救済と革命の物語。

【完結】マジで婚約破棄される5秒前〜婚約破棄まであと5秒しかありませんが、じゃあ悪役令息は一体どうしろと?〜
明太子
BL
公爵令息ジェーン・アンテノールは初恋の人である婚約者のウィリアム王太子から冷遇されている。
その理由は彼が侯爵令息のリア・グラマシーと恋仲であるため。
ジェーンは婚約者の心が離れていることを寂しく思いながらも卒業パーティーに出席する。
しかし、その場で彼はひょんなことから自身がリアを主人公とした物語(BLゲーム)の悪役だと気付く。
そしてこの後すぐにウィリアムから婚約破棄されることも。
婚約破棄まであと5秒しかありませんが、じゃあ一体どうしろと?
シナリオから外れたジェーンの行動は登場人物たちに思わぬ影響を与えていくことに。
※小説家になろうにも掲載しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















