24 / 35
1部 4章
ストラクを目指して 1
しおりを挟む
二頭の馬が軽快な調子で草原を駆けていく。その速さは、速いというほどではないが、辺りの眺望を楽しむことができるほど遅くもない。
時間を惜しんでいるディパルさんからすれば、もっと速度を上げたいところだろう。しかしオレが、これ以上加速させると手綱を操れなくなりそうだから、合わせてくれているのだ。
「――お、お兄ちゃんっ」
と、いきなりオレの前に座っているシルキアが、甲高い悲鳴を上げた。
声が聞こえたようで、左斜め前を走っているディパルさんが、首だけで振り返る。
「お尻っ! お尻いたぁい!」
妹の声は、本気だった。
……そうだよな。
そのうち言ってくるだろう、とは思っていた。
オレだって少し前からジクジク傷んできていたからだ。
オレたち兄妹は、これほど長時間、乗馬したことがない。
乗り方が下手なせいもあるだろうが、鞍に打ち付けられ続けた臀部は悲鳴を上げている。身体付きが薄い……臀部の肉付きがオレよりも薄い妹なら尚更だ。
灰色の馬が足を止めた。
オレも手綱を引く。栗毛が嘶いた。なんだよぉ、と文句でも吐いたのかもしれない。
「今日はこの辺りで野営をしましょう」
「……すみません」
謝ったのは、ディパルさんが急いでいることを、今はもう知っているから。
「休むことも重要です」
灰馬から降りたディパルさんは、手綱を掴んで歩き出す。
オレもすぐに降りて、手綱を握って後をついて行く。
やって来たのは、点々と生えている木のうちの一本の傍。
ディパルさんが枝の一本に手綱を縛り付けた。オレもそれに倣う。
「シルキア、お尻診せてください」
ディパルさんが、シルキアの傍で片膝をつきながら言った。
こくんと頷いた妹が、ディパルさんに臀部を向け、ズボンを躊躇いなく下ろす。続けて、木綿生地で織られた下着――モエねぇのおさがりである、本来であればマークベンチ家の財力では到底買えやしない高価な、肌に優しい柔らかなものだ――も脱いだ。
オレも、妹の状態を把握しておきたくて、ディパルさんの隣にしゃがむ。
お尻の、右側の肉に、痛々しい擦過傷ができていた。
「薬を塗りましょう。場所が場所なので包帯は巻けませんし、少し多めに」
ディパルさんが、腰に提げている小さな革袋を取り、口紐を解く。
「多めにって、いいんですか? 薬、貴重なものなのに」
どのような薬草、ハーブを材料に作っているものかわからないが、それがどんな種類のものであっても薬は貴重なものだ。薬草やハーブの店、診療所などがある町の中でなら、安価でなければ高価でもないが。とくにその町の近くに薬草やハーブの群生地があって採取が簡単であれば、さらに値は下がる。
《コテキ》もそうだった。ネルの母親がハーブ店を営んでいたが、町民相手にはほかの都市と比べてだいぶ安値で商売しているとグレンさんは言っていた。それは、町の近くに、ハーブがいつでも採取できる良質な森と川があったからだ。
しかし、今は町でもなければ、薬草もハーブも近くには生えていない。薬は簡単には手に入らない。使い切ってしまえば、またどこかで入手するまで、なくなってしまう。
使えばなくなる。
当たり前のことだけれど、人間、意外とそれを日常から肝に銘じられている者が少ないと、グレンさんは言っていた。
一度得たものはまたすぐにでも手に入ると、なぜか信じてしまいがちなのだ。
「構いません。ストラクが私にとっての終着ですから。貴重品もただの消費物です」
「そう、ですか」
確かに、その通りかもしれない。
先がないと自覚している者にとって、貴重なものなど時間以外にはないだろう。
財産も何もかも、生きていてこそ価値のあるものだ。まあ、死後、それらを受け継がせる者がいるのであれば、話は変わってくるが。
この人にはそういった人が……例えば血族……子どもとかは、いないのだろうか。
……いや、そんなこと、オレが考えることじゃないな。
とはいえ、いないのだとしたら、気にはなる。
カノジョ……ファムとの関係性が。
もちろん、勝手に気にするだけで、詮索するような真似はしないけれど。
藪蛇はごめんだ。
ディパルさんは、袋の中に右手を差し込むと、すぐに抜き出した。その人差し指には、薄緑色と乳白色の混ざった粘着質なものがくっ付いている。薬だ。
「とはいえ、量の調整はちゃんとしますよ。帰るまで何が起きるかはわかりません。もっと重傷を負ってしまうことになったときに足りなくては困りますので」
そう言うと、カノジョは薬をシルキアの傷に近付けていく。
指先が触れた瞬間、「ひゃあ!」と声を上げて妹が身体を大きく震わせた。
「いたぁい! 痛いよぉ!」
「ごめんなさい。沁みますよね」
謝りながらも、ディパルさんの指先は妹の震えるお尻の上を動く。
「シルキア、我慢だぞ我慢。薬塗ってくれてるんだから」
「うぅぅぅぅぅ、お兄ちゃ~ん」
涙目で見詰めてくる妹。
「大丈夫、大丈夫。すぅぐ終わるから」
「もう終わりましたよ。下着もズボンも穿いてください」
シルキアが、呻きながらの膨れっ面のまま、下着とズボンを上げた。ヒリヒリするのか、薬を塗られた違和感があるのか、妹はお尻を手で押さえたり撫でたりする。
「気になるのはわかりますが、触ってはダメですよ。擦れて、悪化してしまうので」
「そうだぞ。触っちゃダメ」
「だってぇ~」
「だ~め」
不満顔の妹をオレは抱き締めてやる。
シルキアは呻きながらオレの腹に頭をぐりぐりと擦り付けてきた。
兄妹のじゃれ合い。傍から見れば無意味に思えるだろうが、こういうことが大事なのだ。
お互いの不安を取り除くためにも。安心感を得るためにも。
「アクセル。キミは大丈夫ですか?」
「え?」
「お尻」
「あ……あ~、ちょっとは痛い、です」
悩んだ結果、隠すことはしないことにした。
旅なんて初めてだが、旅の心得のようなものは多少学んでいるつもりだ。
仲間に、同行者に、自らの体調についてできるだけ嘘は吐かないほうがいい。
嘘を吐いてその場をやり過ごしたとして、もしも体調が悪化してしまったら、更なる災難を生むことになるからだ。自分だけでなく、仲間たちにも。
相手が怪しい……例えば悪人かもしれない場合は、嘘の利点もあるけれど。
「念のため診せてください」
「……はい。お願いします」
羞恥心は芽生えた。
オレも、もうそういう年頃だと、自覚している。
母でもない女性に臀部を見られるだなんて。
しかし、そんなことを恥ずかしがっている状況ではない。
擦り傷でも、旅の中では甘くみてはダメだ。
オレはズボンと下着――シルキアの穿いているものとは違って、かなり粗雑な作りのものだ。荒く編まれた糸は草でできていて、ごわごわと硬い――を脱いで臀部を見せる。
「少し、荒れてますから。薬は塗っておきましょう」
「ありがとうございます、本当に」
ひりっとした痛み。痺れと熱。薬を塗られたのだ。
オレは下着とズボンを引っ張り上げる。
立ち上がったディパルさんは、少し離れたところにいるフィニセントさんへ顔を向けた。
「ファム、あなたは大丈夫ですか?」
フィニセントさんは答えず、空を眺めたまま。
「ファム」
ようやく、カノジョはこちらに顔を向けた。
変わらず無感動というか、子どもに思えない静かな目だ。
「大丈夫。痛いのは、慣れているから」
痛いのは。
慣れている?
頭の中で反芻したのは、意味がわからなかっただろう。
だって、どういう意味だ。
痛みに慣れるだなんて、そんなことあるのだろうか。
痛いものは、いつだって、痛いはずだ。
何か……何かの喩え?みたいなものだろうか。
「慣れているとしても、痛いものは痛いでしょう? 痛いのなら、診せてください」
「いらない。みられたくない」
みられたくない。
それは……。
傷を診られたくない?
身体を見られたくない?
フィニセントさんは、この問答はおしまいとばかりに、そっぽを向いてしまった。
ほんの少しの間を置いて小さく溜息を吐いたディパルさん。
本当にこの二人、どういう関係なのだろう。
「……野営の準備をしましょうか。アクセル、手伝ってくれますか?」
「も、もちろんですっ。やれること、何でもやらせてもらいますっ!」
「シルキアもっ! シルキアもお手伝いできるよっ!」
オレに同調して、妹も元気に主張した。お尻の傷など、どこかへ行ったように。
それができたのも、幼いながら使命感を抱いているからだろう。
オレたち兄妹は、恩を少しでも返すため、旅についてきたのだ。
ディパルさんを手伝えるのなら、やれることであれば、なんだってやってやるつもり。
「ありがとうございます」
ディパルさんが笑った。
それは、微笑と言うにしたってとても薄い笑みだったけれど。
多分、出会ってから初めて見る笑みだったからか、温かいものを感じられた。
時間を惜しんでいるディパルさんからすれば、もっと速度を上げたいところだろう。しかしオレが、これ以上加速させると手綱を操れなくなりそうだから、合わせてくれているのだ。
「――お、お兄ちゃんっ」
と、いきなりオレの前に座っているシルキアが、甲高い悲鳴を上げた。
声が聞こえたようで、左斜め前を走っているディパルさんが、首だけで振り返る。
「お尻っ! お尻いたぁい!」
妹の声は、本気だった。
……そうだよな。
そのうち言ってくるだろう、とは思っていた。
オレだって少し前からジクジク傷んできていたからだ。
オレたち兄妹は、これほど長時間、乗馬したことがない。
乗り方が下手なせいもあるだろうが、鞍に打ち付けられ続けた臀部は悲鳴を上げている。身体付きが薄い……臀部の肉付きがオレよりも薄い妹なら尚更だ。
灰色の馬が足を止めた。
オレも手綱を引く。栗毛が嘶いた。なんだよぉ、と文句でも吐いたのかもしれない。
「今日はこの辺りで野営をしましょう」
「……すみません」
謝ったのは、ディパルさんが急いでいることを、今はもう知っているから。
「休むことも重要です」
灰馬から降りたディパルさんは、手綱を掴んで歩き出す。
オレもすぐに降りて、手綱を握って後をついて行く。
やって来たのは、点々と生えている木のうちの一本の傍。
ディパルさんが枝の一本に手綱を縛り付けた。オレもそれに倣う。
「シルキア、お尻診せてください」
ディパルさんが、シルキアの傍で片膝をつきながら言った。
こくんと頷いた妹が、ディパルさんに臀部を向け、ズボンを躊躇いなく下ろす。続けて、木綿生地で織られた下着――モエねぇのおさがりである、本来であればマークベンチ家の財力では到底買えやしない高価な、肌に優しい柔らかなものだ――も脱いだ。
オレも、妹の状態を把握しておきたくて、ディパルさんの隣にしゃがむ。
お尻の、右側の肉に、痛々しい擦過傷ができていた。
「薬を塗りましょう。場所が場所なので包帯は巻けませんし、少し多めに」
ディパルさんが、腰に提げている小さな革袋を取り、口紐を解く。
「多めにって、いいんですか? 薬、貴重なものなのに」
どのような薬草、ハーブを材料に作っているものかわからないが、それがどんな種類のものであっても薬は貴重なものだ。薬草やハーブの店、診療所などがある町の中でなら、安価でなければ高価でもないが。とくにその町の近くに薬草やハーブの群生地があって採取が簡単であれば、さらに値は下がる。
《コテキ》もそうだった。ネルの母親がハーブ店を営んでいたが、町民相手にはほかの都市と比べてだいぶ安値で商売しているとグレンさんは言っていた。それは、町の近くに、ハーブがいつでも採取できる良質な森と川があったからだ。
しかし、今は町でもなければ、薬草もハーブも近くには生えていない。薬は簡単には手に入らない。使い切ってしまえば、またどこかで入手するまで、なくなってしまう。
使えばなくなる。
当たり前のことだけれど、人間、意外とそれを日常から肝に銘じられている者が少ないと、グレンさんは言っていた。
一度得たものはまたすぐにでも手に入ると、なぜか信じてしまいがちなのだ。
「構いません。ストラクが私にとっての終着ですから。貴重品もただの消費物です」
「そう、ですか」
確かに、その通りかもしれない。
先がないと自覚している者にとって、貴重なものなど時間以外にはないだろう。
財産も何もかも、生きていてこそ価値のあるものだ。まあ、死後、それらを受け継がせる者がいるのであれば、話は変わってくるが。
この人にはそういった人が……例えば血族……子どもとかは、いないのだろうか。
……いや、そんなこと、オレが考えることじゃないな。
とはいえ、いないのだとしたら、気にはなる。
カノジョ……ファムとの関係性が。
もちろん、勝手に気にするだけで、詮索するような真似はしないけれど。
藪蛇はごめんだ。
ディパルさんは、袋の中に右手を差し込むと、すぐに抜き出した。その人差し指には、薄緑色と乳白色の混ざった粘着質なものがくっ付いている。薬だ。
「とはいえ、量の調整はちゃんとしますよ。帰るまで何が起きるかはわかりません。もっと重傷を負ってしまうことになったときに足りなくては困りますので」
そう言うと、カノジョは薬をシルキアの傷に近付けていく。
指先が触れた瞬間、「ひゃあ!」と声を上げて妹が身体を大きく震わせた。
「いたぁい! 痛いよぉ!」
「ごめんなさい。沁みますよね」
謝りながらも、ディパルさんの指先は妹の震えるお尻の上を動く。
「シルキア、我慢だぞ我慢。薬塗ってくれてるんだから」
「うぅぅぅぅぅ、お兄ちゃ~ん」
涙目で見詰めてくる妹。
「大丈夫、大丈夫。すぅぐ終わるから」
「もう終わりましたよ。下着もズボンも穿いてください」
シルキアが、呻きながらの膨れっ面のまま、下着とズボンを上げた。ヒリヒリするのか、薬を塗られた違和感があるのか、妹はお尻を手で押さえたり撫でたりする。
「気になるのはわかりますが、触ってはダメですよ。擦れて、悪化してしまうので」
「そうだぞ。触っちゃダメ」
「だってぇ~」
「だ~め」
不満顔の妹をオレは抱き締めてやる。
シルキアは呻きながらオレの腹に頭をぐりぐりと擦り付けてきた。
兄妹のじゃれ合い。傍から見れば無意味に思えるだろうが、こういうことが大事なのだ。
お互いの不安を取り除くためにも。安心感を得るためにも。
「アクセル。キミは大丈夫ですか?」
「え?」
「お尻」
「あ……あ~、ちょっとは痛い、です」
悩んだ結果、隠すことはしないことにした。
旅なんて初めてだが、旅の心得のようなものは多少学んでいるつもりだ。
仲間に、同行者に、自らの体調についてできるだけ嘘は吐かないほうがいい。
嘘を吐いてその場をやり過ごしたとして、もしも体調が悪化してしまったら、更なる災難を生むことになるからだ。自分だけでなく、仲間たちにも。
相手が怪しい……例えば悪人かもしれない場合は、嘘の利点もあるけれど。
「念のため診せてください」
「……はい。お願いします」
羞恥心は芽生えた。
オレも、もうそういう年頃だと、自覚している。
母でもない女性に臀部を見られるだなんて。
しかし、そんなことを恥ずかしがっている状況ではない。
擦り傷でも、旅の中では甘くみてはダメだ。
オレはズボンと下着――シルキアの穿いているものとは違って、かなり粗雑な作りのものだ。荒く編まれた糸は草でできていて、ごわごわと硬い――を脱いで臀部を見せる。
「少し、荒れてますから。薬は塗っておきましょう」
「ありがとうございます、本当に」
ひりっとした痛み。痺れと熱。薬を塗られたのだ。
オレは下着とズボンを引っ張り上げる。
立ち上がったディパルさんは、少し離れたところにいるフィニセントさんへ顔を向けた。
「ファム、あなたは大丈夫ですか?」
フィニセントさんは答えず、空を眺めたまま。
「ファム」
ようやく、カノジョはこちらに顔を向けた。
変わらず無感動というか、子どもに思えない静かな目だ。
「大丈夫。痛いのは、慣れているから」
痛いのは。
慣れている?
頭の中で反芻したのは、意味がわからなかっただろう。
だって、どういう意味だ。
痛みに慣れるだなんて、そんなことあるのだろうか。
痛いものは、いつだって、痛いはずだ。
何か……何かの喩え?みたいなものだろうか。
「慣れているとしても、痛いものは痛いでしょう? 痛いのなら、診せてください」
「いらない。みられたくない」
みられたくない。
それは……。
傷を診られたくない?
身体を見られたくない?
フィニセントさんは、この問答はおしまいとばかりに、そっぽを向いてしまった。
ほんの少しの間を置いて小さく溜息を吐いたディパルさん。
本当にこの二人、どういう関係なのだろう。
「……野営の準備をしましょうか。アクセル、手伝ってくれますか?」
「も、もちろんですっ。やれること、何でもやらせてもらいますっ!」
「シルキアもっ! シルキアもお手伝いできるよっ!」
オレに同調して、妹も元気に主張した。お尻の傷など、どこかへ行ったように。
それができたのも、幼いながら使命感を抱いているからだろう。
オレたち兄妹は、恩を少しでも返すため、旅についてきたのだ。
ディパルさんを手伝えるのなら、やれることであれば、なんだってやってやるつもり。
「ありがとうございます」
ディパルさんが笑った。
それは、微笑と言うにしたってとても薄い笑みだったけれど。
多分、出会ってから初めて見る笑みだったからか、温かいものを感じられた。
0
あなたにおすすめの小説

前世で薬漬けだったおっさん、エルフに転生して自由を得る
がい
ファンタジー
ある日突然世界的に流行した病気。
その治療薬『メシア』の副作用により薬漬けになってしまった森野宏人(35)は、療養として母方の祖父の家で暮らしいた。
爺ちゃんと山に狩りの手伝いに行く事が楽しみになった宏人だったが、田舎のコミュニティは狭く、宏人の良くない噂が広まってしまった。
爺ちゃんとの狩りに行けなくなった宏人は、勢いでピルケースに入っているメシアを全て口に放り込み、そのまま意識を失ってしまう。
『私の名前は女神メシア。貴方には二つ選択肢がございます。』
人として輪廻の輪に戻るか、別の世界に行くか悩む宏人だったが、女神様にエルフになれると言われ、新たな人生、いや、エルフ生を楽しむ事を決める宏人。
『せっかくエルフになれたんだ!自由に冒険や旅を楽しむぞ!』
諸事情により不定期更新になります。
完結まで頑張る!

クラス転移したら種族が変化してたけどとりあえず生きる
アルカス
ファンタジー
16歳になったばかりの高校2年の主人公。
でも、主人公は昔から体が弱くなかなか学校に通えなかった。
でも学校には、行っても俺に声をかけてくれる親友はいた。
その日も体の調子が良くなり、親友と久しぶりの学校に行きHRが終わり先生が出ていったとき、クラスが眩しい光に包まれた。
そして僕は一人、違う場所に飛ばされいた。

辺境貴族ののんびり三男は魔道具作って自由に暮らします
雪月夜狐
ファンタジー
書籍化決定しました!
(書籍化にあわせて、タイトルが変更になりました。旧題は『辺境伯家ののんびり発明家 ~異世界でマイペースに魔道具開発を楽しむ日々~』です)
壮年まで生きた前世の記憶を持ちながら、気がつくと辺境伯家の三男坊として5歳の姿で異世界に転生していたエルヴィン。彼はもともと物作りが大好きな性格で、前世の知識とこの世界の魔道具技術を組み合わせて、次々とユニークな発明を生み出していく。
辺境の地で、家族や使用人たちに役立つ便利な道具や、妹のための可愛いおもちゃ、さらには人々の生活を豊かにする新しい魔道具を作り上げていくエルヴィン。やがてその才能は周囲の人々にも認められ、彼は王都や商会での取引を通じて新しい人々と出会い、仲間とともに成長していく。
しかし、彼の心にはただの「発明家」以上の夢があった。この世界で、誰も見たことがないような道具を作り、貴族としての責任を果たしながら、人々に笑顔と便利さを届けたい——そんな野望が、彼を新たな冒険へと誘う。

攻撃魔法を使えないヒーラーの俺が、回復魔法で最強でした。 -俺は何度でも救うとそう決めた-【[完]】
水無月いい人(minazuki)
ファンタジー
【HOTランキング一位獲得作品】
【一次選考通過作品】
---
とある剣と魔法の世界で、
ある男女の間に赤ん坊が生まれた。
名をアスフィ・シーネット。
才能が無ければ魔法が使えない、そんな世界で彼は運良く魔法の才能を持って産まれた。
だが、使用できるのは攻撃魔法ではなく回復魔法のみだった。
攻撃魔法を一切使えない彼は、冒険者達からも距離を置かれていた。
彼は誓う、俺は回復魔法で最強になると。
---------
もし気に入っていただけたら、ブクマや評価、感想をいただけると大変励みになります!
#ヒラ俺
この度ついに完結しました。
1年以上書き続けた作品です。
途中迷走してました……。
今までありがとうございました!
---
追記:2025/09/20
再編、あるいは続編を書くか迷ってます。
もし気になる方は、
コメント頂けるとするかもしれないです。
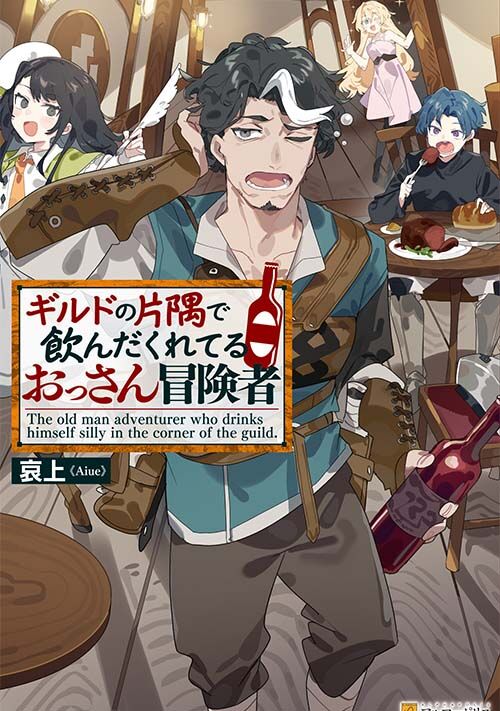
ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者
哀上
ファンタジー
チートを貰い転生した。
何も成し遂げることなく35年……
ついに前世の年齢を超えた。
※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。
※この小説は他サイトにも投稿しています。

地味スキル「ためて・放つ」が最強すぎた!~出来損ないはいらん!と追い出したくせに英雄に駆け上がってから戻れと言われても手遅れです~
かくろう
ファンタジー
【ためて・放つ】という地味スキルを一生に一度の儀式で授かってしまった主人公セージ。
そのせいで家から追放され、挙げ句に異母弟から殺されかけてしまう。
しかしあらゆるものを【ためる】でパワフルにできるこのスキルは、最高ランクの冒険者すらかすんでしまうほどのぶっ壊れ能力だった!
命からがら魔物の強襲から脱したセージは、この力を駆使して成り上がっていく事を決意する。
そして命の危機に瀕していた少女リンカニアと出会い、絆を深めていくうちに自分のスキルを共有できる事に気が付いた。
――これは、世界で類を見ない最強に成り上がっていく主人公と、彼の元へ集まってくる仲間達との物語である。

幸福の魔法使い〜ただの転生者が史上最高の魔法使いになるまで〜
霊鬼
ファンタジー
生まれつき魔力が見えるという特異体質を持つ現代日本の会社員、草薙真はある日死んでしまう。しかし何故か目を覚ませば自分が幼い子供に戻っていて……?
生まれ直した彼の目的は、ずっと憧れていた魔法を極めること。様々な地へ訪れ、様々な人と会い、平凡な彼はやがて英雄へと成り上がっていく。
これは、ただの転生者が、やがて史上最高の魔法使いになるまでの物語である。
(小説家になろう様、カクヨム様にも掲載をしています。)

三歳で婚約破棄された貧乏伯爵家の三男坊そのショックで現世の記憶が蘇る
マメシバ
ファンタジー
貧乏伯爵家の三男坊のアラン令息
三歳で婚約破棄され
そのショックで前世の記憶が蘇る
前世でも貧乏だったのなんの問題なし
なによりも魔法の世界
ワクワクが止まらない三歳児の
波瀾万丈
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















