12 / 46
12.なぜに基準がパンなのか
しおりを挟む
よく晴れたその日、ダリアが主に接客を行なっている我が家の茶葉専門店は賑わっていた。
朝一番、開店するや否や、観光客の群れがやって来て、大騒ぎ。耳にした話によれば、彼ら彼女らは遠い街からの観光客だとか。茶葉専門店が珍しいからか、皆、商品に夢中になっていた。そして、観光客たちは、大量の茶葉を購入していってくれた。
何にせよ、売り上げが上がるのはありがたいことだ。
ただ、妙に騒がしい集団だったので、同じ空気を吸っていて少しばかり疲れてしまった。
だが休みは訪れない。来店する客はまだ続く。
「ダリアさーん! 今日も美人っすねー!」
「あらあら、そういうお世辞は要らないわよ」
「いつものやつ、あるっすかー?」
「ハイピンカスのやつね。もちろんあるわよ」
「じゃあ、それ一袋!」
ダリアとそんなやり取りをするのは、隣町から二週間に一回くらいやって来る青年。名前はいつか聞いたものの忘れてしまった。が、彼が数年前から来店し続けてくれている常連客であることは間違いない。そんな彼は、いつも、妙な口説き文句と共にハイピンカスの茶葉を買っていくのだ。
「……あれは、常連客か」
「えぇ。よく分かったわね、シュヴェーアさん」
「慣れて、いる……そんな気がした……」
私はシュヴェーアと共にダリアの後ろ姿を眺める。
ちなみに、仕事をさぼっているわけではない。手伝いが必要になるタイミングを待っているのだ。
「聞いて下さい、ダリアさん! 今日、お母様が勝手に婚約者を決めてきたんです! さすがに酷くないですか!?」
「それは大変ねー」
「私にだって選択権はあるはずです! それなのに、お母様は勝手に! 許せません!」
「ねー。そのくらい好きにさせてほしいわよねー」
いつも口説き文句を持ってくる青年の相手が終わると、今度はたまに来る女性客の相手。
先日二十歳になったばかりの彼女は、母親がとても厳しい人らしく、それに関する不満をいつもぶちまけている。今日は婚約者の話だが、いつもその話というわけではない。が、母親の愚痴であることは毎回共通している。
「……何かと、ややこしいな」
「シュヴェーアさん、急に渋い顔になってるけど大丈夫?」
個人的には、シュヴェーアがいちいち客への感想を述べるのが面白かった。
面白い、なんて言ってはいけないかもしれないけれど、でも、彼の意見を聞けるのは興味深い機会だ。
「……あぁ」
「なら良かったわ」
その時、カウンターに立ち接客していたダリアがくるりとこちらを向いた。
「セリナ! ちょっと補充頼んで良いかしらー!?」
どうやら私の出番らしい。これだけ忙しくても人を頼らないダリアだから、私は手伝わせてもらえないまま営業時間が終わるかと思っていたが、案外そんなことはなかった。私は「今行く!」と言って、カウンターの方へと駆け出す。
母親の愚痴を言いに来る女性客は既に帰っていた。
ダリアの接客は一時的に落ち着いている。が、店内に人はいる。なので、恐らく、じきにまた接客が始まることだろう。
「このヌイグルミ袋、あそこの台に並べておいてくれる?」
「分かった」
ヌイグルミ袋というのは、中指の長さ程度の身長のクマのヌイグルミが入った茶葉のセットである。店内に陳列しておく商品の一つだ。ちなみに、そのクマのヌイグルミは様々な色や模様があり、数えたことはないが結構な種類存在していると思われる。中には、それを好んで集めている者もいるとか。
私は十袋ほど受け取り、カウンターの横の戸から店内へ出る。そして、置くべき場所に、ヌイグルミ袋を置いていく。一つ一つのヌイグルミが見えるよう、少しずつずらして置かねばならない。
「あ! それ、ヌイグルミ袋だよね!?」
並べている最中、背後からそんな声がかかった。
振り返ると、そこには一人の少女。
年は十代後半くらいだろうか、赤毛を二本の三つ編みにした、睫毛の長い女の子だ。
「……あ、はい」
「良かったぁ! また入ったんだ!」
どうやら彼女はヌイグルミ袋の存在を元々知っていたらしい。もしかしたら、過去に買ってくれたことがあるのかもしれない。
「ゆっくり見ていって下さい」
「うんうん! ありがとー!」
ヌイグルミ袋を並べる仕事は終わった。私のやることは一旦終了だ。ひとまず退こう、と思い、ダリアに「並べ終わった」と伝える。するとダリアは「じゃあ戻ってていいわよー」と返してくれた。予想通り、私の出番はひとまず終了のようだ。ならばすぐに退場しよう。
そうしてシュヴェーアのもとへ戻ると、彼は興味深そうに「……何を、していた?」と尋ねてくる。私はどう答えるのが相応しいのか迷いつつ、「ヌイグルミ袋を並べてきたの」と答えた。すると彼はますます不思議そうな顔で首を傾げる。
言ってから少し後悔。
というのも、いきなり『ヌイグルミ袋』なんて言葉を使ってしまったら彼は余計に理解できなくなるではないか。
それに気づかず、一般的でない単語を使ってしまったことを、私は悔やんだのだ。
「……仕事が、あるのだな。いつも……」
「まぁ、少しだけだけどね」
「……いや。凄いことだ……その年で……」
店の手伝い程度で褒められるなんて、驚きだ。
営んでいる店がある家の娘息子なら手伝いくらいはするものだと思っていたのだが。
「シュヴェーアさんの今までの知り合いには、手伝いしていない人が多かったの?」
ふと思い立ち、訳もなく尋ねてみる。
「……そう、だな。自由気ままに……暮らしていた、皆」
自由気ままに、か。
想像できないが、そんな人生も楽しいかもしれないな、と思いはする。
まったく別の人生というものには、誰もが、一度は憧れるものだろう。もっとも、今の人生に不満があるわけではないけれど。
「正直……そういう娘は、苦手だったが……」
「え、そうなの? どうして?」
「……パンを、くれない」
なぜに基準が『パン』なのか。
朝一番、開店するや否や、観光客の群れがやって来て、大騒ぎ。耳にした話によれば、彼ら彼女らは遠い街からの観光客だとか。茶葉専門店が珍しいからか、皆、商品に夢中になっていた。そして、観光客たちは、大量の茶葉を購入していってくれた。
何にせよ、売り上げが上がるのはありがたいことだ。
ただ、妙に騒がしい集団だったので、同じ空気を吸っていて少しばかり疲れてしまった。
だが休みは訪れない。来店する客はまだ続く。
「ダリアさーん! 今日も美人っすねー!」
「あらあら、そういうお世辞は要らないわよ」
「いつものやつ、あるっすかー?」
「ハイピンカスのやつね。もちろんあるわよ」
「じゃあ、それ一袋!」
ダリアとそんなやり取りをするのは、隣町から二週間に一回くらいやって来る青年。名前はいつか聞いたものの忘れてしまった。が、彼が数年前から来店し続けてくれている常連客であることは間違いない。そんな彼は、いつも、妙な口説き文句と共にハイピンカスの茶葉を買っていくのだ。
「……あれは、常連客か」
「えぇ。よく分かったわね、シュヴェーアさん」
「慣れて、いる……そんな気がした……」
私はシュヴェーアと共にダリアの後ろ姿を眺める。
ちなみに、仕事をさぼっているわけではない。手伝いが必要になるタイミングを待っているのだ。
「聞いて下さい、ダリアさん! 今日、お母様が勝手に婚約者を決めてきたんです! さすがに酷くないですか!?」
「それは大変ねー」
「私にだって選択権はあるはずです! それなのに、お母様は勝手に! 許せません!」
「ねー。そのくらい好きにさせてほしいわよねー」
いつも口説き文句を持ってくる青年の相手が終わると、今度はたまに来る女性客の相手。
先日二十歳になったばかりの彼女は、母親がとても厳しい人らしく、それに関する不満をいつもぶちまけている。今日は婚約者の話だが、いつもその話というわけではない。が、母親の愚痴であることは毎回共通している。
「……何かと、ややこしいな」
「シュヴェーアさん、急に渋い顔になってるけど大丈夫?」
個人的には、シュヴェーアがいちいち客への感想を述べるのが面白かった。
面白い、なんて言ってはいけないかもしれないけれど、でも、彼の意見を聞けるのは興味深い機会だ。
「……あぁ」
「なら良かったわ」
その時、カウンターに立ち接客していたダリアがくるりとこちらを向いた。
「セリナ! ちょっと補充頼んで良いかしらー!?」
どうやら私の出番らしい。これだけ忙しくても人を頼らないダリアだから、私は手伝わせてもらえないまま営業時間が終わるかと思っていたが、案外そんなことはなかった。私は「今行く!」と言って、カウンターの方へと駆け出す。
母親の愚痴を言いに来る女性客は既に帰っていた。
ダリアの接客は一時的に落ち着いている。が、店内に人はいる。なので、恐らく、じきにまた接客が始まることだろう。
「このヌイグルミ袋、あそこの台に並べておいてくれる?」
「分かった」
ヌイグルミ袋というのは、中指の長さ程度の身長のクマのヌイグルミが入った茶葉のセットである。店内に陳列しておく商品の一つだ。ちなみに、そのクマのヌイグルミは様々な色や模様があり、数えたことはないが結構な種類存在していると思われる。中には、それを好んで集めている者もいるとか。
私は十袋ほど受け取り、カウンターの横の戸から店内へ出る。そして、置くべき場所に、ヌイグルミ袋を置いていく。一つ一つのヌイグルミが見えるよう、少しずつずらして置かねばならない。
「あ! それ、ヌイグルミ袋だよね!?」
並べている最中、背後からそんな声がかかった。
振り返ると、そこには一人の少女。
年は十代後半くらいだろうか、赤毛を二本の三つ編みにした、睫毛の長い女の子だ。
「……あ、はい」
「良かったぁ! また入ったんだ!」
どうやら彼女はヌイグルミ袋の存在を元々知っていたらしい。もしかしたら、過去に買ってくれたことがあるのかもしれない。
「ゆっくり見ていって下さい」
「うんうん! ありがとー!」
ヌイグルミ袋を並べる仕事は終わった。私のやることは一旦終了だ。ひとまず退こう、と思い、ダリアに「並べ終わった」と伝える。するとダリアは「じゃあ戻ってていいわよー」と返してくれた。予想通り、私の出番はひとまず終了のようだ。ならばすぐに退場しよう。
そうしてシュヴェーアのもとへ戻ると、彼は興味深そうに「……何を、していた?」と尋ねてくる。私はどう答えるのが相応しいのか迷いつつ、「ヌイグルミ袋を並べてきたの」と答えた。すると彼はますます不思議そうな顔で首を傾げる。
言ってから少し後悔。
というのも、いきなり『ヌイグルミ袋』なんて言葉を使ってしまったら彼は余計に理解できなくなるではないか。
それに気づかず、一般的でない単語を使ってしまったことを、私は悔やんだのだ。
「……仕事が、あるのだな。いつも……」
「まぁ、少しだけだけどね」
「……いや。凄いことだ……その年で……」
店の手伝い程度で褒められるなんて、驚きだ。
営んでいる店がある家の娘息子なら手伝いくらいはするものだと思っていたのだが。
「シュヴェーアさんの今までの知り合いには、手伝いしていない人が多かったの?」
ふと思い立ち、訳もなく尋ねてみる。
「……そう、だな。自由気ままに……暮らしていた、皆」
自由気ままに、か。
想像できないが、そんな人生も楽しいかもしれないな、と思いはする。
まったく別の人生というものには、誰もが、一度は憧れるものだろう。もっとも、今の人生に不満があるわけではないけれど。
「正直……そういう娘は、苦手だったが……」
「え、そうなの? どうして?」
「……パンを、くれない」
なぜに基準が『パン』なのか。
0
あなたにおすすめの小説

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

【完結】使えない令嬢として一家から追放されたけど、あまりにも領民からの信頼が厚かったので逆転してざまぁしちゃいます
腕押のれん
ファンタジー
アメリスはマハス公国の八大領主の一つであるロナデシア家の三姉妹の次女として生まれるが、頭脳明晰な長女と愛想の上手い三女と比較されて母親から疎まれており、ついに追放されてしまう。しかしアメリスは取り柄のない自分にもできることをしなければならないという一心で領民たちに対し援助を熱心に行っていたので、領民からは非常に好かれていた。そのため追放された後に他国に置き去りにされてしまうものの、偶然以前助けたマハス公国出身のヨーデルと出会い助けられる。ここから彼女の逆転人生が始まっていくのであった!
私が死ぬまでには完結させます。
追記:最後まで書き終わったので、ここからはペース上げて投稿します。
追記2:ひとまず完結しました!

婚約破棄された翌日、兄が王太子を廃嫡させました
由香
ファンタジー
婚約破棄の場で「悪役令嬢」と断罪された伯爵令嬢エミリア。
彼女は何も言わずにその場を去った。
――それが、王太子の終わりだった。
翌日、王国を揺るがす不正が次々と暴かれる。
裏で糸を引いていたのは、エミリアの兄。
王国最強の権力者であり、妹至上主義の男だった。
「妹を泣かせた代償は、すべて払ってもらう」
ざまぁは、静かに、そして確実に進んでいく。

追放された悪役令嬢はシングルマザー
ララ
恋愛
神様の手違いで死んでしまった主人公。第二の人生を幸せに生きてほしいと言われ転生するも何と転生先は悪役令嬢。
断罪回避に奮闘するも失敗。
国外追放先で国王の子を孕んでいることに気がつく。
この子は私の子よ!守ってみせるわ。
1人、子を育てる決心をする。
そんな彼女を暖かく見守る人たち。彼女を愛するもの。
さまざまな思惑が蠢く中彼女の掴み取る未来はいかに‥‥
ーーーー
完結確約 9話完結です。
短編のくくりですが10000字ちょっとで少し短いです。

人質5歳の生存戦略! ―悪役王子はなんとか死ぬ気で生き延びたい!冤罪処刑はほんとムリぃ!―
ほしみ
ファンタジー
「え! ぼく、死ぬの!?」
前世、15歳で人生を終えたぼく。
目が覚めたら異世界の、5歳の王子様!
けど、人質として大国に送られた危ない身分。
そして、夢で思い出してしまった最悪な事実。
「ぼく、このお話知ってる!!」
生まれ変わった先は、小説の中の悪役王子様!?
このままだと、10年後に無実の罪であっさり処刑されちゃう!!
「むりむりむりむり、ぜったいにムリ!!」
生き延びるには、なんとか好感度を稼ぐしかない。
とにかく周りに気を使いまくって!
王子様たちは全力尊重!
侍女さんたちには迷惑かけない!
ひたすら頑張れ、ぼく!
――猶予は後10年。
原作のお話は知ってる――でも、5歳の頭と体じゃうまくいかない!
お菓子に惑わされて、勘違いで空回りして、毎回ドタバタのアタフタのアワアワ。
それでも、ぼくは諦めない。
だって、絶対の絶対に死にたくないからっ!
原作とはちょっと違う王子様たち、なんかびっくりな王様。
健気に奮闘する(ポンコツ)王子と、見守る人たち。
どうにか生き延びたい5才の、ほのぼのコミカル可愛いふわふわ物語。
(全年齢/ほのぼの/男性キャラ中心/嫌なキャラなし/1エピソード完結型/ほぼ毎日更新中)
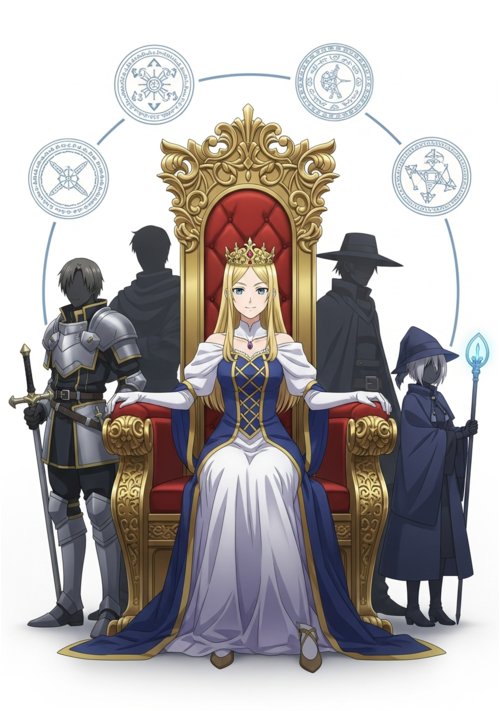
「君は悪役令嬢だ」と離婚されたけど、追放先で伝説の力をゲット!最強の女王になって国を建てたら、後悔した元夫が求婚してきました
黒崎隼人
ファンタジー
「君は悪役令嬢だ」――冷酷な皇太子だった夫から一方的に離婚を告げられ、すべての地位と財産を奪われたアリシア。悪役の汚名を着せられ、魔物がはびこる辺境の地へ追放された彼女が見つけたのは、古代文明の遺跡と自らが「失われた王家の末裔」であるという衝撃の真実だった。
古代魔法の力に覚醒し、心優しき領民たちと共に荒れ地を切り拓くアリシア。
一方、彼女を陥れた偽りの聖女の陰謀に気づき始めた元夫は、後悔と焦燥に駆られていく。
追放された令嬢が運命に抗い、最強の女王へと成り上がる。
愛と裏切り、そして再生の痛快逆転ファンタジー、ここに開幕!

王家を追放された落ちこぼれ聖女は、小さな村で鍛冶屋の妻候補になります
cotonoha garden
恋愛
「聖女失格です。王家にも国にも、あなたはもう必要ありません」——そう告げられた日、リーネは王女でいることさえ許されなくなりました。
聖女としても王女としても半人前。婚約者の王太子には冷たく切り捨てられ、居場所を失った彼女がたどり着いたのは、森と鉄の匂いが混ざる辺境の小さな村。
そこで出会ったのは、無骨で無口なくせに、さりげなく怪我の手当てをしてくれる鍛冶屋ユリウス。
村の事情から「書類上の仮妻」として迎えられたリーネは、鍛冶場の雑用や村人の看病をこなしながら、少しずつ「誰かに必要とされる感覚」を取り戻していきます。
かつては「落ちこぼれ聖女」とさげすまれた力が、今度は村の子どもたちの笑顔を守るために使われる。
そんな新しい日々の中で、ぶっきらぼうな鍛冶屋の優しさや、村人たちのさりげない気遣いが、冷え切っていたリーネの心をゆっくりと溶かしていきます。
やがて、国難を前に王都から使者が訪れ、「再び聖女として戻ってこい」と告げられたとき——
リーネが選ぶのは、きらびやかな王宮か、それとも鉄音の響く小さな家か。
理不尽な追放と婚約破棄から始まる物語は、
「大切にされなかった記憶」を持つ読者に寄り添いながら、
自分で選び取った居場所と、静かであたたかな愛へとたどり着く物語です。

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~
Mio
ファンタジー
妻から手紙が来た。
妻が死んで18年目の今日。
息子の誕生日。
「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」
息子は…17年前に死んだ。
手紙はもう一通あった。
俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。
------------------------------
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















