14 / 43
二部
第12話:拳で語る仲裁
しおりを挟む健太の、あまりにも場違いで、緊張感のない一言は、まるで凍てついた湖に投じられた小石のように、鉄槌山脈の固く冷たい空気に、奇妙な波紋を広げた。
一瞬の静寂。
そして、次の瞬間、二つの種族の怒りが、堰を切ったように、彼一人へと集中した。
「―――なんだと、貴様ッ!」
先に吼えたのは、ドワーフの青年、ゴルドだった。
彼の顔は、炉で熱せられた鉄のように真っ赤に染まり、自慢の髭が怒りでわなわなと震えている。
その手は、背負っていた巨大な戦鎚(ウォーハンマー)の柄を、今にも握りしめようとしていた。
彼の呼吸は荒く、まるで蒸気機関のように、フシュー、フシュー、と白い息を吐き出している。
「人間の、ひよっこ風情が…! 我らドワーフとエルフの、数百年にも及ぶ歴史の何が分かるというのだ! 知ったような口を利くな!」
「―――あなたも、同罪です!」
続いて、ルミナが、氷のように冷たい、しかし怒りに燃える声で健太を非難した。
彼女の普段の冷静さは完全に消え失せ、その翡翠色の瞳は、非難の色で鋭く尖っている。
握りしめられた白い拳は、血の気が引いて、さらに白く見えた。
「私たちの、森の民の苦しみが、あなたに分かって? 聖なる泉が枯れ、母なる森が、日に日にその生命力を失っていく、この絶望が! それを、ただ『めんどくさい』の一言で片付けるなど、万死に値する侮辱です!」
二つの異なる種族から放たれる、純度百パーセントの敵意と怒り。
その矢面に立たされながらも、健太は、全く動じる様子がなかった。
それどころか、心底不思議そうな顔で、二人を交互に見比べている。
「いや、だからさ」
健太は、ぽりぽりと頬を掻きながら言った。
「どっちも、自分の言いたいことばっかじゃん。エルフは『水返せ』、ドワーフは『水やらん』。それの繰り返し。そりゃ、話が進むわけないって。だから、めんどくさいって言ったんだけど、俺、なんも間違ってないよね?」
その、あまりにも単純で、子供でも分かるような正論は、かえって二人の怒りを増幅させた。
「黙れ!」
「黙りなさい!」
二人の声が、綺麗にハモる。
フィーナは、その一触即発の空気の中で、ただオロオロするばかりだった。
彼女は、王女として、調停の難しさを誰よりも知っている。
数百年にわたって蓄積された不信感と敵愾心は、そう簡単に解けるものではない。
ましてや、この男のように、相手の感情を逆撫でするようなやり方では、火に油を注ぐだけだ。
「ケ、ケンタさん! どうか、お二人のお気持ちも…!」
フィーナが、必死に仲裁に入ろうとする。
しかし、健太は、そんな彼女の心配を、ひらひらと手で制した。
「分かった、分かった。もう、理屈はいいや」
彼は、何かを決心したように、ポン、と手を叩いた。
「そもそも、水がどうなってるのか、この目で見てみないと、話になんねえわ。おい、髭の兄ちゃん」
健太は、ゴルドを顎でしゃくった。
「案内しろ。あんたらの里の、その問題の水源ってやつによ。俺が、直接、現場検証してやる」
「はあ!? なんで俺が、てめえみたいな人間に、我らの里を案内しなきゃならんのだ!」
ゴルドが、当然のように拒絶する。
健太は、やれやれ、といった風に、目の前にある、巨大な鋼鉄の門を見上げた。
「じゃあ、しょうがねえな。この門、今から壊すけど、文句ないよな?」
彼は、そう言うと、本当に、何の躊躇もなく、拳を固めて門に向かって振りかぶった。
その、あまりにも自然で、当然のような仕草に、ゴルドの顔が、さっと引きつった。
目の前の男が、口先だけのハッタリを言う人間ではないことを、彼は、本能で理解していた。
「……ま、待て! 待て待て待て!」
ゴルドは、慌てて健太の前に立ちはだかった。
「……分かった! 分かったよ! 案内すりゃいいんだろ、案内すりゃ! 我らの神聖な門に、傷一つでもつけてみろ、ただじゃおかねえからな!」
彼は、悔しそうに歯ぎしりしながら、背後の門番に、門を開けるよう合図した。
ゴゴゴゴゴ……という重々しい音を立てて、巨大な鋼鉄の門が、ゆっくりと開かれていく。
門の向こう側から、灼熱の熱気と、無数のハンマーが金属を叩く、甲高い残響音が、一斉に溢れ出してきた。
***
ドワーフの里は、地底に築かれた、巨大な都市だった。
門をくぐった先には、天然の巨大な洞窟が広がっており、その内部が、彼らの生活空間となっていた。
天井は、最も高い場所では百メートル以上はあろうかというほどの高さで、そこには、鍾乳石のように、巨大な鉱石の結晶がいくつもぶら下がっている。
その結晶が、洞窟のあちこちで燃え盛る炉の光を乱反射させ、壁面をオレンジ色や赤色に、きらきらと染め上げていた。
空気は、熱く、乾いていた。エルフの森の、ひんやりと澄んだ空気とは、まさに対極だ。
石炭が燃える匂い、溶けた鉄の匂い、そして、屈強な男たちの汗の匂いが、混じり合っている。
カン!カン!カン!という、リズミカルで、しかし耳をつんざくような金属音が、絶え間なく洞窟全体に響き渡っていた。
それは、無数の鍛冶場(フォージ)で、ドワーフの職人たちが、昼夜を問わず、鎚を振るい続けている音だった。
通路の両脇には、岩を直接くり抜いて作られた、無骨だが頑丈な家々が並んでいる。
エルフの里の、自然と調和した優美な建築とは違い、ここにあるのは、機能性と剛健さだけを追求した、実用一辺倒の世界だった。
「…これが、ドワーフの里…」
フィーナは、その力強い活気に満ちた光景に、圧倒されていた。
ルミナは、しかし、不快そうに眉をひそめていた。
彼女にとって、この熱気と騒音、そして鉄の匂いは、森の静寂とは相容れない、不快なものだったのだろう。
彼女は、思わず、袖で鼻と口を覆った。
その様子を、案内役のゴルドが、ちらりと見て、ふん、と鼻を鳴らした。
「どうだ、とんがり耳。てめえらの、昼寝しか能のない森とは、大違いだろうが。ここは、創造の場所だ。我らドワーフが、大地の恵みから、新たな価値を生み出す、聖なる仕事場よ」
「野蛮です」
ルミナは、即座に言い返した。
「大地を傷つけ、その心臓を抉り出し、ただ己の欲望のために鉄を叩く。あなたたちのやっていることは、森を蝕む病巣と同じです」
「んだと、こら!」
またしても、二人の間で火花が散る。
健太は、その間で、大きな欠伸を一つした。
「お前ら、仲良いな」
「「どこが(どこがです)!!」」
二人の声が、再び綺麗にハモった。
ゴルドに案内され、一行は、里のさらに奥深く、ドワーフたちにとっても重要な施設である、地下水脈の源流部へと向かった。
通路は、次第に狭く、そして下り坂になっていく。
周囲の壁には、照明代わりに、発光する苔が植えられており、ぼんやりとした緑色の光が、一行の足元を照らしていた。
ひんやりとした、湿った空気が漂い始め、遠くから、水の流れる音が聞こえてきた。
やがて、一行は、巨大な地底湖の前にたどり着いた。
天井から差し込む、わずかな光の筋が、湖面に反射して、神秘的な光景を作り出している。
水は、驚くほど澄んでおり、湖の底まで見通せそうだった。
「ここが、我らの里の生命線、古の水源だ」
ゴルドが、少しだけ誇らしげに言った。
「だがな、この水も、最近、少しずつ減り始めてやがる。原因は、山の地脈の変動だ。だから、我々は、新しい鉱脈を掘ると同時に、この水を安定して確保する必要があったんだ」
彼は、湖の奥を指さした。
「あの奥に、エルフの森へと繋がる古い水路があったのは知っていた。だが、俺たちにとっても、水は譲れねえ。だから、水路のほとんどを、岩で塞いだ。文句あっか」
ゴルドの言葉は、悪びれる様子もなく、開き直っているかのようだった。
ルミナは、悔しそうに唇を噛む。
健太は、しかし、そんな二人のやり取りには興味がない、といった風に、じっと、地底湖の、ある一点を見つめていた。
そして、まるで、全てを理解したかのように、ぽん、と手を打った。
「ああ、なるほどね。そういうことか」
彼は、湖の対岸にある、巨大な一枚岩の壁を指さした。
「問題は、あんたたちが塞いだとか、そういう話じゃねえんだ。原因は、あの岩盤だ」
「岩盤?」
ゴルドが、訝しげに聞き返す。
「そう。本来、この地底湖の水は、二手に分かれて流れるはずだったんだ。一つは、あんたらの里の方へ。もう一つは、エルフの森の方へ。だが、あのクソでかい岩盤が、ちょうど、エルフの森へ向かう方の水脈の、大元を、完全に塞いじまってる。だから、水が、あんたらの里の方にしか、流れなくなっちまってるんだよ」
健太の、あまりにも的確な、地質学者顔負けの分析に、ゴルドも、ルミナも、言葉を失った。
「ば、馬鹿な…! なぜ、お前にそんなことが…」
「んー、なんとなく?」
健太は、適当に答えた。
彼の無敵の能力は、おそらく、彼の五感や直感さえも、世界の理を読み解けるレベルにまで、引き上げているのだろう。
ゴルドは、それでも、信じられない、といった風に首を振った。
「だとしてもだ! あの岩盤は、ただの岩じゃねえ! この山脈で最も硬いと言われる、『神代岩(しんだいいわ)』だ! 我々ドワーフの、最高の技術と、ありったけの爆薬を使っても、傷一つ、つけられなかった、伝説の岩盤なんだぞ!」
***
健太は、ゴルドの必死の説明を、「へー、そうなんだ」と、気のない返事で聞き流した。
そして、彼は、おもむろに、シャツの袖をまくり始めた。
「な、何をする気だ、貴様!」ゴルドが、警戒して身構える。
健太は、そんな彼を一瞥すると、にやりと笑った。
「決まってんだろ」
彼は、一言、そう言うと、巨大な岩盤に向かって、ゆっくりと歩き出した。
その姿に、ようやく、彼の意図を察したルミナが、悲鳴のような声を上げた。
「待ちなさい、ケンタ! 無茶です! いくらあなたでも、山そのものである、あの岩盤を、どうこうできるはずが…!」
フィーナも、顔面蒼白で、彼の名前を呼んだ。
だが、健太は、振り返らなかった。
彼は、直径数十メートル、厚さも計り知れない、神代岩の壁の前に、静かに立った。
その圧倒的な質量を前にして、彼の姿は、あまりにも、小さく、ちっぽけに見えた。
ゴルドは、鼻で笑った。
「やめとけ、人間。無駄なことだ。その自慢の拳が、砕け散るのがオチだぜ」
健太は、そんなゴルドの嘲笑にも、全く意に介さなかった。
彼は、ただ、ゆっくりと、右の拳を握りしめる。
そして、その拳を、まるで、親しい友人の肩を叩くかのように、ごく、自然な動作で、岩盤の表面に、ぽん、と、軽く当てた。
何の力も、入っていない。
ただ、触れただけ。
最初の数秒間は、何も起きなかった。
洞窟の中には、水の滴る音と、三人の女性の、固唾をのむ呼吸の音だけが響いていた。
ゴルドが、「ほら、見たことか! だから言ったんだ!」と、勝ち誇ったように叫ぼうとした、まさに、その瞬間だった。
―――音が、なかった。
健太の拳が触れている、その一点から。
無音のまま、蜘蛛の巣のような、微細な亀裂が、凄まじい速度で、岩盤全体へと広がっていく。
それは、まるで、時間が早送りされているかのように、一瞬で、巨大な神代岩の全てを覆い尽くした。
そして、次の瞬間。
サラサラサラサラサラ…………。
巨大な岩盤が、まるで、風に吹かれた砂の城のように、内側から、静かに、崩れ落ち始めたのだ。
それは、破壊ではなかった。
消滅、と呼ぶべき現象だった。
岩としての構造、その存在そのものが、健太の力によって、より根源的な、ただの「砂粒」へと、分解されていく。
数秒後。
かつて、そこに、ドワーフの民が数百年かけても傷一つつけられなかった伝説の岩盤があったなどとは、誰も信じられないほど、跡形もなく、完全に消え去っていた。
後に残されたのは、舞い上がる粉塵と、呆然と立ち尽くす、三人の女性と、一人のドワーフだけだった。
そして、轟音。
ゴオオオオオオオオオオオオオオオッ!!
岩盤によって、数千年、あるいは数万年もの間、堰き止められていた膨大な量の地下水が、解放された喜びを叫ぶかのように、凄まじい勢いで、新たに開かれた流路へと、濁流となって流れ込み始めた。
その濁流は、二手に分かれた。
一つは、ドワーフの里の、渇いていた予備水路へと流れ込み、それを豊かな水で満たしていく。
そして、もう一つは、遥か彼方、東にある、エルフの森の方角へと、確かな流れとなって、向かっていく。
ルミナと、ゴルドは、その、神話の一場面のような光景を、ただ、口を開けたまま、見つめていた。
自分たちの、種族の、数百年にも及んだ、不毛な対立。その原因が、今、目の前の、この一人の男の、たった一撃(とも呼べないような軽い接触)によって、文字通り「消滅」してしまったのだ。
常識が、価値観が、自分たちが生きてきた世界の全てが、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていくような、感覚。
***
健太は、舞い上がる粉塵を手で払いながら、呆然とする四人に向き直った。
そして、まるで、宿題を終えた小学生のような、晴れやかな顔で、言った。
「ほら、解決。これで、あんたらの里にも、エルフの森にも、ちゃんと水が行くようになっただろ。もう、喧嘩すんなよ」
その、あまりにも屈託のない言葉に、最初に我に返ったのは、ゴルドだった。
彼は、目の前の男を見た。そして、新たに開かれた水路を、轟音を立てて流れていく水を見た。
自分の種族の、最高の技術。
最高の誇り。
それが、この男の前では、赤子の戯言にも等しい、無価値なものだった。
普通なら、それは、耐え難い屈辱のはずだ。
だが、今のゴルドの心を占めていたのは、屈辱ではなかった。
それは、職人としての、純粋なまでの、畏怖。
そして、自分の知らない、遥かに高次元の「創造」と「破壊」の御業を目の当たりにした、魂が震えるような、興奮だった。
ゴルドは、健太の前に、ずかずかと進み出ると、その場で、どさりと、膝をついた。そして、その頑固な頭を、深く、深く、下げた。
「…頼む!」
その声は、震えていた。
「俺を! ドワーフのゴルドを! あんたの旅に、連れて行ってくれ!」
「え?」
「俺は、見届けなきゃならねえ! あんたの、その、神の領域にある力の、秘密を! その力の先にあるものを! この目で見届けなきゃ、俺は、ドワーフの鍛冶師として、死んでも死にきれねえ!」
続いて、ルミナが、静かに、健太の前に進み出た。
彼女の翡翠色の瞳は、先ほどまでの怒りや警戒の色はなく、ただ、ひたむきな、強い決意の光を宿していた。
「…私も、行きます」
彼女は、静かに、しかし、きっぱりと言った。
「父には、反対されるでしょう。里の者たちも、止めるでしょう。ですが、私は、もう、決めたのです。この停滞した森の中で、ただ滅びを待つのは、もう、嫌なのです」
彼女は、健太の瞳を、真っ直ぐに見つめた。
「あなたの力は、破壊の力ではない。争いの原因そのものを取り除き、新たな流れを創り出す、調和の力。私は、あなたと共に、外の世界を知りたい。そして、この森が、世界が、どう変わっていくのかを、見届けたいのです」
新たな仲間が、二人。
フィーナは、その光景に、驚きながらも、胸が熱くなるのを感じていた。
健太は、そんな感動的な雰囲気を、ぶち壊すかのように、にやにやと笑いながら言った。
「お、マジで? 仲間、増えんの? これで、エルフの美少女と、ドワーフの…兄ちゃんがパーティー入りか。うん、ますますハーレムっぽくなってきたな!」
こうして、人間(無敵)、元王女(悲劇のヒロイン)、エルフ(クールビューティー)、そして、ドワーフ(熱血漢)という、本来ならば、決して交わることのなかったであろう、四つの異なる種族による、奇妙で、ちぐはぐで、しかし、無限の可能性を秘めたパーティーが、今、ここに、結成された。
彼らの、本当の冒険が、ここから始まる。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

40歳のおじさん 旅行に行ったら異世界でした どうやら私はスキル習得が早いようです
カムイイムカ(神威異夢華)
ファンタジー
部長に傷つけられ続けた私
とうとうキレてしまいました
なんで旅行ということで大型連休を取ったのですが
飛行機に乗って寝て起きたら異世界でした……
スキルが簡単に得られるようなので頑張っていきます

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
みこみこP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

備蓄スキルで異世界転移もナンノソノ
ちかず
ファンタジー
久しぶりの早帰りの金曜日の夜(但し、矢作基準)ラッキーの連続に浮かれた矢作の行った先は。
見た事のない空き地に1人。異世界だと気づかない矢作のした事は?
異世界アニメも見た事のない矢作が、自分のスキルに気づく日はいつ来るのだろうか。スキル【備蓄】で異世界に騒動を起こすもちょっぴりズレた矢作はそれに気づかずマイペースに頑張るお話。
鈍感な主人公が降り注ぐ困難もナンノソノとクリアしながら仲間を増やして居場所を作るまで。

異世界に移住することになったので、異世界のルールについて学ぶことになりました!
心太黒蜜きな粉味
ファンタジー
※完結しました。感想をいただけると、今後の励みになります。よろしくお願いします。
これは、今まで暮らしていた世界とはかなり異なる世界に移住することになった僕の話である。
ようやく再就職できた会社をクビになった僕は、不気味な影に取り憑かれ、異世界へと運ばれる。
気がつくと、空を飛んで、口から火を吐いていた!
これは?ドラゴン?
僕はドラゴンだったのか?!
自分がドラゴンの先祖返りであると知った僕は、超絶美少女の王様に「もうヒトではないからな!異世界に移住するしかない!」と告げられる。
しかも、この世界では衣食住が保障されていて、お金や結婚、戦争も無いというのだ。なんて良い世界なんだ!と思ったのに、大いなる呪いがあるって?
この世界のちょっと特殊なルールを学びながら、僕は呪いを解くため7つの国を巡ることになる。
※派手なバトルやグロい表現はありません。
※25話から1話2000文字程度で基本毎日更新しています。
※なろうでも公開しています。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!

最初から最強ぼっちの俺は英雄になります
総長ヒューガ
ファンタジー
いつも通りに一人ぼっちでゲームをしていた、そして疲れて寝ていたら、人々の驚きの声が聞こえた、目を開けてみるとそこにはゲームの世界だった、これから待ち受ける敵にも勝たないといけない、予想外の敵にも勝たないといけないぼっちはゲーム内の英雄になれるのか!
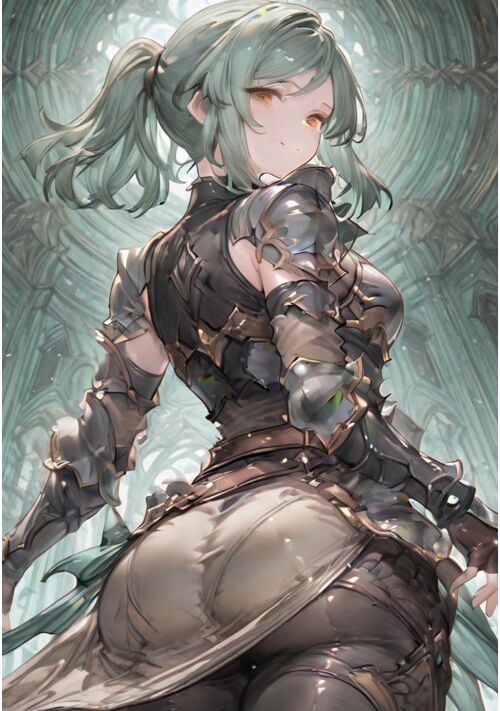
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















