19 / 43
四部
第17話:たった一人の戦場
しおりを挟む水の王国アクアフォールの王宮は、緊張と絶望に満ちていた。
謁見の間の中央に広げられた巨大な軍事地図。
その北を示す一点を、居並ぶ王国の将軍や大臣たちが、まるで死刑宣告でも見つめるかのように、暗い表情で睨みつけている。
季節は夏。
窓の外では、太陽の光が、この水の都が誇る美しい運河の水面に反射し、天井に、ゆらゆらと光の模様を映し出している。
水のせせらぎと、街の穏やかな喧騒が、風に乗って、この息の詰まるような部屋にまで届いていた。
だが、その平和な音は、かえって、この場にいる者たちの絶望感を際立たせるだけだった。
「―――ガレマール帝国の先遣隊が、三日前に、国境の砦を突破したとの報告が入っております」
騎士団長を務める、白髪の老将軍が、かすれた声で報告した。
「我が国の兵力は、全兵力を結集しても、わずか五千。そのほとんどは、実戦経験のない若い兵士たちです。対する帝国軍は、十万。しかも、百戦錬磨の正規軍。籠城したとしても、一週間と持たないでしょう。…もはや、万策、尽きましたな…」
重いため息が、部屋のあちこちから漏れた。
ある者は天を仰ぎ、ある者は固く目を閉じる。
誰もが、この美しき都が、北の軍事大国の鉄蹄に蹂躙される未来を、ありありと幻視していた。
その、通夜のような重苦しい雰囲気を、まるで意に介さない声が、唐突に響いた。
「よし」
声の主は、健太だった。
彼は、会議の間、ずっと、用意された高級そうな椅子が、自分の尻にフィットするかどうかを試すことに夢中だったが、ようやく話が一段落したとみて、ぽんと膝を打ったのだ。
「じゃあ、俺が、なんとかするわ」
その、あまりにも軽い、緊張感のかけらもない一言に、部屋にいた全員の視線が、一斉に彼へと突き刺さった。
国王が、すがるような目で問いかける。
「…おお、ケンタ殿。引き受けて、くださるか」
「うん。まあ、なんか、困ってるみたいだし」
健太は、あっさりと頷いた。
その返答に、隣に座っていたゴルドが、呆れたように、その見事な髭をわしづかみにした。
「はっ、言うと思ったぜ、この朴念仁が。で、どうするんだ? まさかとは思うが、一人で、あの十万の軍勢に、喧嘩を売りに行く、なんて言わねえだろうな?」
「うん」
健太は、ゴルドの問いに、にこやかに、そして、即答した。
「そのまさかだけど。一人で行ってくるわ」
「「「なっ!?」」」
今度こそ、健太以外の全員が、驚愕の声を上げた。
アクアフォールの老将軍が、血相を変えて立ち上がる。
「無謀だ! 若者よ、いくら貴殿が、神の如き力を持つと噂されていても、それは、あまりにも、無謀すぎる! それは、勇気ではない! ただの、自殺行為だ!」
「そうですよ、ケンタさん!」
フィーナも、青い顔で彼に詰め寄る。
「危険すぎます! 私たちも、一緒に行きます!」
「いやいや」
健太は、そんな彼女たちの心配を、ひらひらと手で制した。
「だってさ、その方が、早いじゃん。それに、みんなで行ったら、足手まとい、っていうか…まあ、俺、みんなを守りながらだと、全力を出せないかもしれないし?」
その言葉には、悪意はなかった。
ただ、純粋な事実として、そう言っただけだった。
だが、その言葉は、彼の仲間たちに、改めて、自分たちと彼との間にある、絶対的な力の差を、痛感させるものだった。
ルミナが、深いため息をついた。
その翡翠色の瞳には、諦観と、そして、どこか、この常識外れの男への信頼が入り混じった、複雑な色が浮かんでいた。
「…分かりました。どうせ、私たちが、何を言っても、あなたは、聞く耳を持たないのでしょう」
彼女は、やれやれ、といった風に、首を振った。
「…どうせ、やるんでしょ」
それは、もはや、このパーティーにおける、決定事項に対する、合言葉のようになっていた。
***
出陣の朝。
アクアフォールの、北の城壁の上に、健太は、たった一人で立っていた。
夏の朝の空気は、どこまでも澄み渡っている。
昇り始めた太陽が、眼下に広がる巨大な湖の水面を、黄金色の絵の具で染め上げていた。
キラキラと輝くその光景は、この世のものとは思えないほどに美しい。
だが、北から吹いてくる風は、その美しさとは不釣り合いな、不吉な匂いを運んできた。
遠い、鉄の匂い。
そして、大軍勢が巻き上げる、乾いた土埃の匂い。
戦の、匂いだ。
健太は、いつものように、簡素な旅人の服を着ているだけだった。
武器も、鎧も、持っていない。
彼が、これから、十万の軍勢と対峙しようとしているなどとは、その姿からは、到底、信じられないだろう。
彼の後ろには、仲間たちと、国王、そして、数人の将軍たちが、不安げな表情で、彼を見守っていた。
「ケンタさん…これを…」
フィーナが、お守りとして、王家に代々伝わる、小さな銀のペンダントを、彼に差し出した。水の精霊のご加護が宿っているという、由緒ある品だ。
健太は、そのペンダントを一瞥すると、にっと笑って、彼女の手に、そっと押し返した。
「気持ちだけ、貰っとくわ。大丈夫だって。俺、頑丈なのが取り柄だから」
その、根拠のない自信に満ちた笑顔に、フィーナは、不安ながらも、こくりと頷くことしかできなかった。
「…おい、朴念仁」
ゴルドが、ぶっきらぼうに言った。
「絶対に、死ぬなよ。てめえに借りを返すまでは、勝手に死ぬんじゃねえぞ」
「無茶だけは、しないでください」
ルミナも、静かに、しかし、その瞳には、強い心配の色を浮かべて、言った。
「あなたの命は、もはや、あなただけの者ではないのですから」
「ケンタさん…お気をつけて…」
セシルは、ただ、胸の前で、小さく手を組んで、祈っていた。
仲間たちの、それぞれの言葉を受け止め、健太は、ひらひらと、軽く手を振った。
「んじゃ、ちょっくら、行ってくらあ」
彼は、そう言うと、城壁の階段を降り、たった一人で、城門をくぐり、北の広大な平原へと、歩き出していった。
城壁の上から、仲間たちが見守っている。
巨大な城壁を背景に、平原を歩いていく彼の背中は、あまりにも、小さく、頼りなく見えた。
***
その頃、遥か北。
地平線の果てまでを埋め尽くす、鋼鉄の軍勢が、その進軍の足を、止めていた。
ガレマール帝国、北方方面侵攻軍。その数、十万。
整然と組まれた歩兵の方陣は、まるで、巨大な鉄の櫛のようだ。
その間を、重装鎧に身を包んだ騎士団が、騎馬の上で、微動だにせず、命令を待っている。
後方には、巨大な投石機や、破城槌といった、おぞましい攻城兵器が、まるで、古代の怪物のように、いくつも鎮座していた。
兵士たちの、統率された呼吸。
鎧の擦れる、かすかな音。軍馬の、いななき。
それらが、一つの巨大な生き物の、唸り声のように、大地を、低く、震わせていた。
その、圧倒的な軍勢の、さらに先頭。
一頭の、神々しいまでの純白の軍馬の上に、一人の女性が、静かに座っていた。
皇女ヒルデガルド。
雪のように白い肌。氷のように冷たい、サファイアの瞳。銀糸で縁取られた、漆黒の軍服。その姿は、まるで、戦場に舞い降りた、死を司る女神のようだった。
彼女の周りだけ、夏の熱い空気さえもが、凍てついているかのような、絶対零度のオーラを放っている。
彼女は、その氷の瞳で、遥か南、アクアフォールの、か細い城壁を、見据えていた。
「―――報告!」
一人の斥候が、馬を走らせ、彼女の元へとやってきた。
「前方より、敵性存在を確認! …数は、一名! 丸腰です!」
その報告に、ヒルデガルドの周囲に控えていた、歴戦の将軍たちが、思わず、嘲笑の声を上げた。
「一名だと? 降伏の使者か?」
「あるいは、自らの死に場所を求めて、さまよい出た、狂人ですかな、姫様」
しかし、ヒルデガルドは、笑わなかった。
彼女は、手に持っていた、精巧な魔道具の遠眼鏡を、すっと、目に当てた。
レンズの向こうに、平原を、一人で、のんびりと、こちらに向かって歩いてくる、若い男の姿が、はっきりと見えた。
その姿は、あまりにも、無防備。
あまりにも、緊張感がない。
狂人か、あるいは――。
ヒルデガルドの、美しい唇の端が、微かに、吊り上がった。
「…面白い」
彼女は、呟いた。
「全軍、停止。あの男が、何をしようとしているのか、見届けてやろう」
彼女の、その一言で、十万の軍勢は、まるで、一つの生き物のように、その動きを、完全に、停止させた。
***
健太は、帝国軍の、巨大な陣営の、ちょうど、矢が届くか、届かないか、という、絶妙な距離で、ぴたり、と足を止めた。
目の前には、地平線を埋め尽くす、鋼鉄と、殺意の壁。
普通なら、その圧倒的な威圧感だけで、気を失うか、発狂してしまうだろう。
だが、健太は、そんなことには、全く、興味がなかった。
彼は、ふぁ~あ、と、大きな欠伸を一つすると、その場に、どかっと、あぐらをかいて、座り込んだ。
その、あまりにも、予想外で、あまりにも、ふざけた行動に、帝国軍の最前列にいた兵士たちの間に、どよめきが走った。
「な、何をしているんだ、あの男は…」
「我々を、愚弄しているのか…?」
健太は、そんな彼らの困惑など、知ったこっちゃない、といった風に、目を閉じ、何やら、ぶつぶつと、呟き始めた。
それは、詠唱ではなかった。祈りでも、なかった。
ただの、彼が、その場のノリで、適当に考えた、お願い事のようなものだった。
「さて、と。…えーっと…。神様、仏様、ご先祖様。…この世界にある、全ての武器という武器は、人を殺したり、傷つけたりするためのモンじゃなくて、本当は、畑を耕したり、美味しい料理を作るための、平和な道具でしたー、みたいな感じに、なりませんかねぇ…? なったら、ウケるよなー…うん」
彼は、まるで、七夕の短冊に願い事を書くような、ごく、軽い気持ちで、心の中で、そう、念じた。
彼自身、それで、一体、何が起こるのかなんて、全く、分かってはいなかった。
ただ、彼の能力『絶対不干渉』は、彼の、その、無自覚で、無邪気で、しかし、絶対的な「願い」を、「世界のルールを書き換える命令」として、忠実に、実行した。
最初は、何も起こらなかった。
ただ、静寂があった。
帝国軍の、ある将軍が、「やはり、ただの、たわけか! 全軍、構え!」と、叫ぼうとした、その瞬間だった。
―――カシャン。
小さな、乾いた音が、どこかで響いた。
それを皮切りに、その音は、次々と、伝染していった。
カシャン。
カラン。
ポトリ。
グニャリ。
帝国軍の、最前列の兵士が、自分の手に持っていた、鋭利な刃を持つはずの、鋼鉄の剣を見た。
その剣の、切っ先が、まるで、熱した飴のように、ぐにゃり、と、だらしなく、垂れ下がっていた。
「な…なんだ、これは…!?」
彼が、驚いて、剣を振ろうとすると、剣身全体が、まるで、茹で過ぎたパスタのように、ふにゃふにゃになってしまった。
その、奇妙な現象は、一つの部隊だけではなかった。
地平線の果てまで続く、十万の軍勢、その全てで、同時に、起こっていたのだ。
兵士たちが、その身に纏っていた、硬いはずのプレートアーマーが、湿ったパン生地のように、ぐにゃぐにゃと、形を崩し始めた。
兜は、その重みを支えきれず、へしゃげて、兵士たちの視界を塞いだ。
弓兵たちが構えていた、強靭な弓の弦は、弾力のない、ただの、だらしない紐になった。矢の、鋭い鏃は、なぜか、ふわふわの、マシュマロのような感触に変わっていた。
後方で、威容を誇っていた、巨大な攻城兵器も、その構造を維持する「物理法則」そのものが、その場から消え失せたかのように、ゆっくりと、自重で、メキメキと音を立てながら、崩壊していく。
十万の軍勢は、その、暴力の象徴たる「武装」を、一滴の血も流すことなく、完全に、奪われた。
彼らはもはや、「軍隊」ではなかった。
ただの、「奇妙な形をした、鉄屑と、布切れを持った、十万人の、人の群れ」へと、成り下がっていた。
パニックが、波のように、広がっていく。
「う、腕が、鎧から抜けん!」
「俺の槍が、コンニャクに…!」
「何が起きたんだ、これは! 呪いか!?」
皇女ヒルデガルドもまた、その例外ではなかった。
彼女は、自らの腰に佩いていた、帝国の至宝にして、伝説の魔剣『グラム』が、鞘の中で、ただの、装飾過多な、鉛の棒になっていることに、気づいた。
彼女の、常に、氷のように冷静沈着だった、完璧な貌に、生まれて初めて、亀裂が走った。
驚愕。
混乱。
屈辱。
そして、目の前の、たった一人の男が引き起こした、理解不能な現象に対する、原始的な、恐怖。
「……ば…かな……」
その、美しい唇から、か細い、信じられない、といった響きの声が、漏れた。
健太は、そんな、大混乱に陥った、十万の軍勢を、一瞥すると、もう一度、大きな欠伸をした。
そして、彼は、ゆっくりと立ち上がると、ズボンの埃を、ぽんぽんと、手で払った。
まるで、ちょっとした、畑仕事でも終えたかのような、気軽さで。
彼は、もう、帝国軍には、何の興味も示さなかった。
ただ、アクアフォールの、美しい城壁の方へと、向き直ると、来た道を、のんびりと、とぼとぼと、歩き始めた。
「あーあ、腹減ったなー。今日の昼飯、なんだろなー」
そんな、呑気な呟きが、風に乗って、誰に聞こえるでもなく、消えていった。
彼の背後には、ただ、呆然と立ち尽くす、かつて、軍隊だったものの、残骸が、地平線の果てまで、広がっているだけだった。
それは、この世界の、誰もが語り継ぐことになる、「たった一人の戦場」と呼ばれる、あまりにも、シュールで、あまりにも、圧倒的な、神の悪戯のような、光景だった。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

40歳のおじさん 旅行に行ったら異世界でした どうやら私はスキル習得が早いようです
カムイイムカ(神威異夢華)
ファンタジー
部長に傷つけられ続けた私
とうとうキレてしまいました
なんで旅行ということで大型連休を取ったのですが
飛行機に乗って寝て起きたら異世界でした……
スキルが簡単に得られるようなので頑張っていきます

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。
みこみこP
ファンタジー
高校2年の夏。
高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。
地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。
しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

備蓄スキルで異世界転移もナンノソノ
ちかず
ファンタジー
久しぶりの早帰りの金曜日の夜(但し、矢作基準)ラッキーの連続に浮かれた矢作の行った先は。
見た事のない空き地に1人。異世界だと気づかない矢作のした事は?
異世界アニメも見た事のない矢作が、自分のスキルに気づく日はいつ来るのだろうか。スキル【備蓄】で異世界に騒動を起こすもちょっぴりズレた矢作はそれに気づかずマイペースに頑張るお話。
鈍感な主人公が降り注ぐ困難もナンノソノとクリアしながら仲間を増やして居場所を作るまで。

異世界に移住することになったので、異世界のルールについて学ぶことになりました!
心太黒蜜きな粉味
ファンタジー
※完結しました。感想をいただけると、今後の励みになります。よろしくお願いします。
これは、今まで暮らしていた世界とはかなり異なる世界に移住することになった僕の話である。
ようやく再就職できた会社をクビになった僕は、不気味な影に取り憑かれ、異世界へと運ばれる。
気がつくと、空を飛んで、口から火を吐いていた!
これは?ドラゴン?
僕はドラゴンだったのか?!
自分がドラゴンの先祖返りであると知った僕は、超絶美少女の王様に「もうヒトではないからな!異世界に移住するしかない!」と告げられる。
しかも、この世界では衣食住が保障されていて、お金や結婚、戦争も無いというのだ。なんて良い世界なんだ!と思ったのに、大いなる呪いがあるって?
この世界のちょっと特殊なルールを学びながら、僕は呪いを解くため7つの国を巡ることになる。
※派手なバトルやグロい表現はありません。
※25話から1話2000文字程度で基本毎日更新しています。
※なろうでも公開しています。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。
三矢さくら
ファンタジー
【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎
長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?
しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。
ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。
といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。
とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!
フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!

最初から最強ぼっちの俺は英雄になります
総長ヒューガ
ファンタジー
いつも通りに一人ぼっちでゲームをしていた、そして疲れて寝ていたら、人々の驚きの声が聞こえた、目を開けてみるとそこにはゲームの世界だった、これから待ち受ける敵にも勝たないといけない、予想外の敵にも勝たないといけないぼっちはゲーム内の英雄になれるのか!
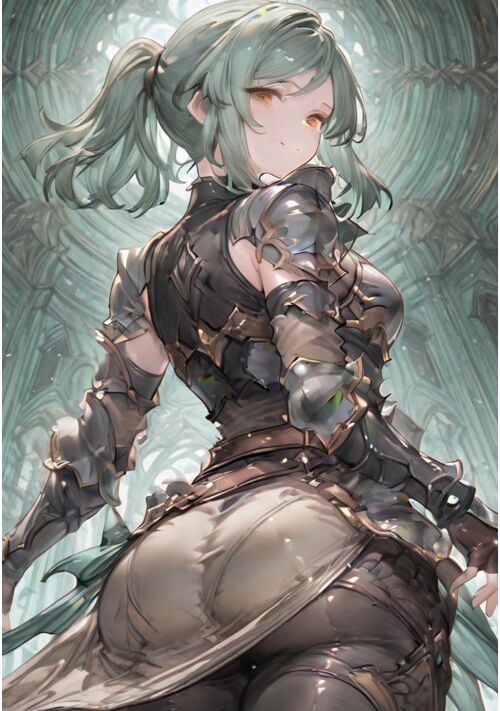
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















