1 / 47
第一話:古びたクリニックの扉
しおりを挟む
七月の太陽は、地上にある全てのものを焼き尽くさんばかりの勢いで、アスファルトを容赦なく照りつけていた。それは単なる熱線ではなく、質量を伴った暴力的な光の奔流となって、見る者の視界を白く染め上げる。大学病院という、徹底的に管理された冷房と無菌の砦から一歩外へ踏み出しただけで、本田未来の額には、まるで真珠のように大粒の汗がいくつも浮かび上がった。じっとりと肌にまとわりつく濃密な湿気は、ようやく過ぎ去ったはずの梅雨が残した、執念深い最後の置き土産のようだった。手にしたスマートフォンが示す電子地図は、無機質な青い光で現在地を点滅させながら、この駅から徒歩十五分ほどの、古い住宅街の一角を指し示している。そこが、今日から三ヶ月という決して短くはない期間、彼女が研修医としてその身を寄せることになる場所、「東堂漢方クリニック」のはずだった。
「本当に、この道で合っているのかしら……」
何度も、何度も、スマートフォンの画面と目の前に広がる現実の風景とを見比べては、未来は不安の入り混じった溜息と共に独りごちた。つい先ほどまで乗っていた電車の窓から見えていた、空を突き刺すかのようにそびえ立つ近代的なビル群や、ガラスと鉄骨で構成された巨大な構造物は、もうどこにも見当たらない。いま彼女の視界を占めているのは、どこまでも続く低い甍の波と、家々の窮屈な間から、まるで空を求めるように生命力たくましく枝葉を伸ばす木々の深い緑だけだった。コンクリートの苛烈な照り返しに満ちていた駅前の喧騒から、昔ながらのアーケードが残る商店街を抜け、いくつかの細い路地を曲がるうちに、辺りを満たす空気はその密度や匂い、そして纏う温度までを変え、まるで時間そのものの流れまでが緩やかになったかのように感じられた。
道の脇に目をやれば、盛りをとうに過ぎた紫陽花が、夏の陽射しに少し萎れながらも、なお重たげに瑠璃色の花房を垂れている。その広く厚い葉の上では、小さな雨蛙が一匹、まるで全世界を睥睨しているかのように微動だにせず鎮座していた。不意に風が吹き抜けるたび、どこかの家の庭先から、甘く、それでいてどこか官能的な梔子の香りがふわりと漂ってくる。みーん、みーんと、気の早い蝉の合唱が、降り注ぐ陽光に溶け込み、共鳴し、空間全体を震わせているようだった。
大学病院での日々は、絶え間ない緊張と隣り合わせの、秒刻みの戦争だった。ずらりと並んだ電子カルテの端末が青白い光を放つ医局、ポケットの中で昼夜を問わず鳴り止まないPHSの甲高い呼び出し音、最新鋭の医療機器が静かに威圧感を放つ検査室、そして何よりも、生命の瀬戸際に立たされた患者たちの苦悶と希望が渦巻く病棟。そこでは、人間の身体に関するあらゆる事象がデータ化され、数値化され、エビデンスに基づいた厳格なプロトコルに従って、一分一秒を争う冷徹な判断が下されていた。それが未来にとっての「医療」であり、彼女が揺るぎない真実だと信じてきた世界のすべてだった。
それに比べて、この圧倒的なまでの静けさはどうだろう。まるで知らないうちに時空の歪みに迷い込み、昭和のある夏の日にタイムスリップしてしまったかのような、不思議な錯覚に陥る。地図が示す最後の角を、期待と不安を胸に曲がった瞬間、未来は思わず足を止めた。
そこに、その建物はあった。
周囲に立ち並ぶごく普通の住宅群とは明らかに違う、独特の静謐な空気をその身にまとって、まるで永い時間の中から浮かび上がってきたかのように、ひっそりと佇んでいた。陽光を浴びて黒く鈍い光を放つ、太く頑強な梁と柱が巡らされた重厚な木造の平屋建て。丁寧に葺かれた瓦屋根の深い軒下には、南部鉄器であろうか、古雅な風鈴が吊るされ、風を待っていた。建物の手前には、人の手によって完璧に管理されているのか、それとも自然のなすがままに任されているのか判然としない、緑豊かな小さな庭が広がっていた。深い緑の苔に覆われた飛び石が玄関へと続き、季節の草花がそれぞれの生命を謳歌するように思い思いの方向に枝を伸ばしている。その中に、まるで庭の主のように、古びた石灯籠が一つ、静かに腰を下ろしていた。
そして、その建物の入り口に掲げられた、一枚板の重厚な看板。長年の風雨に耐えてきたことが見て取れるその木肌に、達筆すぎて、現代の感覚では少し読みにくいほどの力強い墨文字で、こう書かれていた。
『東堂漢方クリニック』
「……ここ、だわ」
未来はごくりと乾いた喉を鳴らした。
クリニック、という現代的な響きとはあまりにもかけ離れたその佇まいは、むしろ古民家を改装したカフェか、あるいは誰かの祖父母が暮らす田舎の家と呼ぶ方が、よほどしっくりくる。冷たく滑らかな自動ドアと、清潔感を象徴する真っ白な光沢を放つエントランスホールに慣れ親しんだ未来の目には、あまりにも異質で、非現実的な光景に映った。玄関は、引き戸だった。目の粗い、しかし温かみのある木で組まれた引き戸。中央にはめ込まれた時代物のガラスは、表面がわずかに波打っており、その向こうは薄暗く、中の様子をはっきりと窺い知ることはできない。
果たして、本当にこの場所で、現代に生きる人々のための医療が行われているというのだろうか。MRIも、CTスキャンも、血液検査の自動分析装置も、およそ彼女が「医療」と認識するために必要な機器が、この建物の中に存在するとは到底思えなかった。彼女がこれまで寝る間も惜しんで学び、積み上げてきた知識や技術は、この場所で一体何の役に立つというのだろう。胸の奥から湧き上がる一抹の不安と、それを上回るほど強烈な、未知への好奇心。未来は、白衣のポケットの中で、大学病院の部長から託された紹介状が放つ微かな存在感を指先で確かめると、意を決して苔むした飛び石を一歩、また一歩と渡った。
引き戸にそっと手をかける。ひんやりとした、乾いた木の感触が、汗ばんだ手のひらに心地よかった。カラカラ、という決して滑らかではない、しかしどこか懐かしい響きを立てて、扉はゆっくりと横に滑った。
その瞬間、未来の鼻腔を、今まで一度として嗅いだことのない濃密な匂いが満たした。
それは、単一の香料では決して表現できない、複雑で奥深い香りだった。乾いた土の匂い、永い年月を経て呼吸を続ける古い木の匂い、そして何十種類、いや何百種類もの植物の根や葉や花が混ざり合い、発酵し、熟成されたような、不思議と心を鎮めてくれる香りだった。薬草の匂い、と頭では瞬時に理解したが、アルコールの消毒液の匂いこそが清潔と安全の証だと信じてきた未来の常識は、この場所に来て早々に、根底から揺さぶられ始めていた。
中へ一歩、足を踏み入れる。外の強烈な陽光に慣れていた目が、ようやく室内の穏やかな薄闇に順応し始めた。
そこは、どうやら待合室らしかった。しかし、彼女の想像していた殺風景な空間とは全く異なり、ステンレスやプラスチックといった無機質な素材は一切見当たらなかった。床は、訪れる人々によって長年磨き込まれた結果であろう、深く美しい飴色に光る木の板張り。壁際には、小さな引き出しが無数に取り付けられた、巨大な木製の棚が部屋の主のように鎮座している。百味箪笥だ、と未来は教科書の片隅で見た知識を思い出した。あの小さな引き出しの一つ一つに、桂皮や甘草、当帰といった生薬の名前が書かれた紙が貼られ、その中には様々な薬草が眠っているのだろう。
受付らしき場所も、一枚板で作られた分厚い木のカウンターだった。しかし、そこに人影はない。呼び鈴の類も見当たらず、未来はどうしたものかと、部屋の中央で立ち尽くしてしまった。しん、と深く静まり返った空間に響くのは、壁にかかった大きな古時計が、こち、こち、とあくまでも律儀に、そして悠然と時を刻む音と、軒先の風鈴が時折風を拾って鳴る、ちりん、という涼やかで澄んだ音だけだった。
外の猛烈な暑さが嘘のように、室内はひんやりとしていた。それはエアコンが生み出す人工的で乾いた冷気ではない。太い柱と厚い土壁が、外の熱をじっくりと遮断しているような、身体に優しい自然な涼しさだった。窓にはガラスではなく障子がはめられ、夏の容赦ない日差しを和らかな光に変えて、室内に穏やかに拡散させている。その光と、柱や棚が作る深い影が織りなす繊細な濃淡は、まるで一枚の古びた水墨画の世界に迷い込んだかのようだった。
「ごめんください」
意を決して、未来は声を張った。思ったよりも、自分の声が静寂の中で大きく響き渡った気がした。
しかし、返事はない。
もう一度、今度は先ほどよりも少しだけ大きな声で呼びかける。
「すみません、今日から研修でお世話になります、本田未来と申します!どなたかいらっしゃいますか?」
すると、待合室の奥、診察室へと続くのであろう襖が、すっ、と衣擦れの音もなく静かに開いた。
そこに立っていたのは、一人の老人だった。
年の頃は七十をとうに越えているだろうか。未来が想像していたようなパリっとした白衣ではなく、何度も洗われて体に馴染んだ、くたびれた墨色の作務衣を身につけている。綺麗に剃り上げられた頭には、銀色の髪が短く残っていた。深く刻まれた目尻の皺は、彼がこれまでに重ねてきた年月の証であり、まるで常に穏やかに笑っているかのように見えた。その手には、小さな金属製の乳鉢と乳棒が握られており、今しがたまで何かをすり潰していたのだろう。ゴリ、ゴリ、という硬質な音の余韻と共に、先ほどよりも一層深く、そして香ばしい薬草の香りがふわりと漂ってきた。
「おお、あんたが大学病院から来た、ええと……未来先生、だったかな」
老人は、悪びれる様子など微塵も見せず、のんびりとした、それでいて芯のある口調で言った。
この人こそが、紹介状に書かれていた東堂宗右衛門先生に違いない。未来は慌てて背筋を伸ばし、深く、直角に頭を下げた。
「は、はい!本田未来です!本日から三ヶ月間、よろしくご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます!」
医局で叩き込まれた、マニュアル通りの完璧な挨拶。だが、東堂先生は「ふむ」と静かに一つ頷いただけで、未来が緊張と共に差し出した紹介状には目もくれず、ただ、彼女の顔をじっと見つめた。その視線は、決して人を値踏みするような不躾なものではない。まるで、庭の景色や空の雲の流れでも眺めるかのように、ただ静かで、それでいて彼女の内面までも見透かしてしまうかのような、深く、澄んだものだった。
「……暑い中、よう来なすった。さぞ、喉が渇いただろう。まあ、そこに座りなさい」
そう言って東堂先生が顎で示したのは、待合室の隅に置かれた、長年の使用で表面が滑らかになった使い古された長椅子だった。未来は一瞬戸惑いながらも、「は、はい。失礼します」と短く答え、その椅子の端に浅く腰掛けた。背筋は伸びたままだった。
東堂先生は、持っていた乳鉢をカウンターの上にことりと置くと、建物の裏手へと続く土間の方へ、ゆっくりとした足取りで消えていく。やがて、ことり、という涼やかな音と共に戻ってきた彼の手には、薄いガラスのコップが二つ。その中では、淡い褐色の液体が、手作りの不揃いな氷と共に涼やかな音を立てていた。
「さ、飲みなさい。自家製の麦茶だ」
「あ、ありがとうございます……!」
未来は恐縮しながらそのコップを受け取った。きんと冷えたガラスの感触が、火照った体に驚くほど心地よい。促されるままに一口飲むと、市販のペットボトルのものとは全く違う、深く香ばしい、焙煎された穀物の風味が口いっぱいに広がった。それは、ただの麦茶ではないような気がした。ごくりと飲み下すと、乾ききっていた喉から食道、そして胃の腑へと、冷たい液体が染み渡っていくのが分かる。体の芯から、じんわりと熱が引いていくような、不思議な感覚だった。
「……美味しい、です。なんだか、普通の麦茶と違うような……」
「ほう。分かるかね」
東堂先生は、自分も長椅子にどっかりと腰を下ろし、満足そうに目を細めた。「少しばかり、はと麦と、それから体の余計な熱を冷ますものを混ぜてある。あんたさん、ずいぶんと体の表面に熱を溜め込んで、息せき切ってやって来たからな。まずは、その上ずった熱を冷ましてやらんことには、話も始まらん」
「……え?」
未来は、思わず先生の顔を見返した。
体の表面の熱?たしかに外は猛烈に暑かったが、それは誰もが同じ条件のはずだ。彼は、未来の何を見てそう判断したというのだろう。脈をとられたわけでも、聴診器を当てられたわけでも、ましてやサーモグラフィーで見たわけでもない。ただ、待合室に入ってきた彼女の顔を、ほんの数秒見ただけで?
「あの、先生。こちらが大学病院からの紹介状と、私の履歴書になります」
話の奇妙な流れを断ち切るように、未来は慌てて鞄からクリアファイルに入った書類を取り出した。最先端の医療機器を誰よりも使いこなし、数々の症例をロジカルなレポートにまとめてきたという確固たる自負が、彼女の言葉を少しだけ早口にさせた。
しかし、東堂先生はその書類を受け取ろうともせず、ちりん、と軒先の風鈴が澄んだ音を立てたのに耳をすませるように、ふっと目を閉じた。
「風が、少し変わったな。こりゃ、夕立が来るかもしれん」
「は……?」
「あんたさん、大学病院では、ずいぶんと優秀な成績だったそうじゃないか。最新の機械を駆使して、目に見えんウイルスや細菌を見つけ出し、正しい薬でそれを的確に叩く。実に、見事なもんだ。大したもんじゃ」
それは、おそらく紹介状に書かれていた内容なのだろう。未来は少しだけ誇らしい気持ちになった。だが、先生の言葉は、彼女が全く予期しない方向に続いていった。
「だがな、未来先生。わしらは、そういうもんとは少し違う見方をする。例えば、風邪をひいた患者がここへ来たとしよう。あんたさんなら、まずウイルスの特定を考えるだろう。インフルエンザか、アデノか、それともライノかと。違うかね?」
「はい。原因となる病原体を特定し、それに最も有効な抗ウイルス薬や対症療法を選択するのが治療の基本です。それが、科学的根拠に基づいた現代医療ですから」
未来は、淀みなく答えた。それは、医学部で、そして臨床の現場で、彼女が金科玉条のごとく叩き込まれてきた医学の根幹そのものだった。
すると、東堂先生は、ゆっくりと目を開け、まるで子供に何か面白いことを教えるかのように、悪戯っぽく笑った。
「わしなら、こう考える。『おやおや、体の表面、つまりバリアが弱っているところに、良くない"気"、すなわち"邪気(じゃき)"が取りついて、悪さをしとるな』と」
「……じゃき?」
その単語を聞いた瞬間、未来の思考が、完全に停止した。
邪気。それは、漫画やファンタジー小説の世界で使われる言葉ではなかったか。目の前にいる医師免許を持った人間が、こともなげに、それを口にした。ここは、本当に認可された医療機関なのだろうか。もしかしたら、自分はとんでもない研修先を選んでしまったのではないか。そんな深刻な疑念が、むくむくと頭をもたげてくる。
未来の混乱をありありと見て取ったのか、東堂先生はカラカラと喉を鳴らして笑った。
「無理もない。あんたさんたちの医学は、顕微鏡の発明と共に、どんどん小さな世界へ、ミクロの世界へと進んでいった。細胞を、遺伝子を、分子レベルで解明しようとする。それは本当に素晴らしいことだ。だが、わしらの医学は、それとは違う方角をずっと向いておった。森羅万象、つまり、季節の移ろいや気候の変化、人間を取り巻く自然との関わりという、大きな視点、マクロな視点で体を丸ごと捉えようとしてきたんだ」
先生はゆっくりと立ち上がると、あの巨大な百味箪笥の前まで歩いて行った。そして、無数にある引き出しの一つに慣れた手つきで指をかけ、静かに開ける。ふわりと、また別の、甘さと苦さが複雑に絡み合った濃厚な香りが待合室に漂ってきた。
「病原体という『点』だけを追いかけるのが西洋医学なら、わしらは、なぜその人が病にならねばならなかったのか、その人の持って生まれた体質や日々の生活、心のありようまで含めた『全体』を見ていく。それが東洋医学の、ほんの入り口だ」
東堂先生は、指先でつまんだ赤褐色の乾燥した植物の根のようなものを、呆然としている未来の目の前に、そっと差し出した。シナモンのような、しかしもっと土臭く、力強い香りがした。
「さあ、未来先生。今日から三ヶ月、あんたがこれまで築き上げてきた常識が、全く通用しない世界へようこそ。難しいことは何も言わん。まずは、その優秀な頭で考えるのを少しだけ休んで、その目と、耳と、鼻で、目の前の患者さんと、そしてこの場所に満ちている『気』というものを、ただ、ただ感じてみることから始めなさい」
差し出された、ひとかけらの生薬。
その向こうに見える、穏やかで、それでいて全てを知っているかのような老医師の深い瞳。
こち、こち、と変わらず時を刻む古時計の音。ちりん、と風に歌う風鈴の音。そして、幾千もの薬草が静かな眠りにつきながら、出番を待っているこの空間。
未来は、自分が今、とてつもなく大きく、そして深い世界の、ほんの入り口に立ったばかりだということを、予感せずにはいられなかった。それは、西洋医学という名の、光に満ちた揺るぎない一本道をひたすらに歩いてきた彼女にとって、初めて目にする、薄暗く、それでいて無限の奥行きを感じさせる、全く別の道だった。
外で、遠雷が一つ、地の底から響くように低く轟いた。東堂先生の言った通り、夕立が来るのかもしれない。
湿り気を含んだ風が引き戸の隙間から流れ込み、空気が、また少し、その匂いを変えた気がした。
「本当に、この道で合っているのかしら……」
何度も、何度も、スマートフォンの画面と目の前に広がる現実の風景とを見比べては、未来は不安の入り混じった溜息と共に独りごちた。つい先ほどまで乗っていた電車の窓から見えていた、空を突き刺すかのようにそびえ立つ近代的なビル群や、ガラスと鉄骨で構成された巨大な構造物は、もうどこにも見当たらない。いま彼女の視界を占めているのは、どこまでも続く低い甍の波と、家々の窮屈な間から、まるで空を求めるように生命力たくましく枝葉を伸ばす木々の深い緑だけだった。コンクリートの苛烈な照り返しに満ちていた駅前の喧騒から、昔ながらのアーケードが残る商店街を抜け、いくつかの細い路地を曲がるうちに、辺りを満たす空気はその密度や匂い、そして纏う温度までを変え、まるで時間そのものの流れまでが緩やかになったかのように感じられた。
道の脇に目をやれば、盛りをとうに過ぎた紫陽花が、夏の陽射しに少し萎れながらも、なお重たげに瑠璃色の花房を垂れている。その広く厚い葉の上では、小さな雨蛙が一匹、まるで全世界を睥睨しているかのように微動だにせず鎮座していた。不意に風が吹き抜けるたび、どこかの家の庭先から、甘く、それでいてどこか官能的な梔子の香りがふわりと漂ってくる。みーん、みーんと、気の早い蝉の合唱が、降り注ぐ陽光に溶け込み、共鳴し、空間全体を震わせているようだった。
大学病院での日々は、絶え間ない緊張と隣り合わせの、秒刻みの戦争だった。ずらりと並んだ電子カルテの端末が青白い光を放つ医局、ポケットの中で昼夜を問わず鳴り止まないPHSの甲高い呼び出し音、最新鋭の医療機器が静かに威圧感を放つ検査室、そして何よりも、生命の瀬戸際に立たされた患者たちの苦悶と希望が渦巻く病棟。そこでは、人間の身体に関するあらゆる事象がデータ化され、数値化され、エビデンスに基づいた厳格なプロトコルに従って、一分一秒を争う冷徹な判断が下されていた。それが未来にとっての「医療」であり、彼女が揺るぎない真実だと信じてきた世界のすべてだった。
それに比べて、この圧倒的なまでの静けさはどうだろう。まるで知らないうちに時空の歪みに迷い込み、昭和のある夏の日にタイムスリップしてしまったかのような、不思議な錯覚に陥る。地図が示す最後の角を、期待と不安を胸に曲がった瞬間、未来は思わず足を止めた。
そこに、その建物はあった。
周囲に立ち並ぶごく普通の住宅群とは明らかに違う、独特の静謐な空気をその身にまとって、まるで永い時間の中から浮かび上がってきたかのように、ひっそりと佇んでいた。陽光を浴びて黒く鈍い光を放つ、太く頑強な梁と柱が巡らされた重厚な木造の平屋建て。丁寧に葺かれた瓦屋根の深い軒下には、南部鉄器であろうか、古雅な風鈴が吊るされ、風を待っていた。建物の手前には、人の手によって完璧に管理されているのか、それとも自然のなすがままに任されているのか判然としない、緑豊かな小さな庭が広がっていた。深い緑の苔に覆われた飛び石が玄関へと続き、季節の草花がそれぞれの生命を謳歌するように思い思いの方向に枝を伸ばしている。その中に、まるで庭の主のように、古びた石灯籠が一つ、静かに腰を下ろしていた。
そして、その建物の入り口に掲げられた、一枚板の重厚な看板。長年の風雨に耐えてきたことが見て取れるその木肌に、達筆すぎて、現代の感覚では少し読みにくいほどの力強い墨文字で、こう書かれていた。
『東堂漢方クリニック』
「……ここ、だわ」
未来はごくりと乾いた喉を鳴らした。
クリニック、という現代的な響きとはあまりにもかけ離れたその佇まいは、むしろ古民家を改装したカフェか、あるいは誰かの祖父母が暮らす田舎の家と呼ぶ方が、よほどしっくりくる。冷たく滑らかな自動ドアと、清潔感を象徴する真っ白な光沢を放つエントランスホールに慣れ親しんだ未来の目には、あまりにも異質で、非現実的な光景に映った。玄関は、引き戸だった。目の粗い、しかし温かみのある木で組まれた引き戸。中央にはめ込まれた時代物のガラスは、表面がわずかに波打っており、その向こうは薄暗く、中の様子をはっきりと窺い知ることはできない。
果たして、本当にこの場所で、現代に生きる人々のための医療が行われているというのだろうか。MRIも、CTスキャンも、血液検査の自動分析装置も、およそ彼女が「医療」と認識するために必要な機器が、この建物の中に存在するとは到底思えなかった。彼女がこれまで寝る間も惜しんで学び、積み上げてきた知識や技術は、この場所で一体何の役に立つというのだろう。胸の奥から湧き上がる一抹の不安と、それを上回るほど強烈な、未知への好奇心。未来は、白衣のポケットの中で、大学病院の部長から託された紹介状が放つ微かな存在感を指先で確かめると、意を決して苔むした飛び石を一歩、また一歩と渡った。
引き戸にそっと手をかける。ひんやりとした、乾いた木の感触が、汗ばんだ手のひらに心地よかった。カラカラ、という決して滑らかではない、しかしどこか懐かしい響きを立てて、扉はゆっくりと横に滑った。
その瞬間、未来の鼻腔を、今まで一度として嗅いだことのない濃密な匂いが満たした。
それは、単一の香料では決して表現できない、複雑で奥深い香りだった。乾いた土の匂い、永い年月を経て呼吸を続ける古い木の匂い、そして何十種類、いや何百種類もの植物の根や葉や花が混ざり合い、発酵し、熟成されたような、不思議と心を鎮めてくれる香りだった。薬草の匂い、と頭では瞬時に理解したが、アルコールの消毒液の匂いこそが清潔と安全の証だと信じてきた未来の常識は、この場所に来て早々に、根底から揺さぶられ始めていた。
中へ一歩、足を踏み入れる。外の強烈な陽光に慣れていた目が、ようやく室内の穏やかな薄闇に順応し始めた。
そこは、どうやら待合室らしかった。しかし、彼女の想像していた殺風景な空間とは全く異なり、ステンレスやプラスチックといった無機質な素材は一切見当たらなかった。床は、訪れる人々によって長年磨き込まれた結果であろう、深く美しい飴色に光る木の板張り。壁際には、小さな引き出しが無数に取り付けられた、巨大な木製の棚が部屋の主のように鎮座している。百味箪笥だ、と未来は教科書の片隅で見た知識を思い出した。あの小さな引き出しの一つ一つに、桂皮や甘草、当帰といった生薬の名前が書かれた紙が貼られ、その中には様々な薬草が眠っているのだろう。
受付らしき場所も、一枚板で作られた分厚い木のカウンターだった。しかし、そこに人影はない。呼び鈴の類も見当たらず、未来はどうしたものかと、部屋の中央で立ち尽くしてしまった。しん、と深く静まり返った空間に響くのは、壁にかかった大きな古時計が、こち、こち、とあくまでも律儀に、そして悠然と時を刻む音と、軒先の風鈴が時折風を拾って鳴る、ちりん、という涼やかで澄んだ音だけだった。
外の猛烈な暑さが嘘のように、室内はひんやりとしていた。それはエアコンが生み出す人工的で乾いた冷気ではない。太い柱と厚い土壁が、外の熱をじっくりと遮断しているような、身体に優しい自然な涼しさだった。窓にはガラスではなく障子がはめられ、夏の容赦ない日差しを和らかな光に変えて、室内に穏やかに拡散させている。その光と、柱や棚が作る深い影が織りなす繊細な濃淡は、まるで一枚の古びた水墨画の世界に迷い込んだかのようだった。
「ごめんください」
意を決して、未来は声を張った。思ったよりも、自分の声が静寂の中で大きく響き渡った気がした。
しかし、返事はない。
もう一度、今度は先ほどよりも少しだけ大きな声で呼びかける。
「すみません、今日から研修でお世話になります、本田未来と申します!どなたかいらっしゃいますか?」
すると、待合室の奥、診察室へと続くのであろう襖が、すっ、と衣擦れの音もなく静かに開いた。
そこに立っていたのは、一人の老人だった。
年の頃は七十をとうに越えているだろうか。未来が想像していたようなパリっとした白衣ではなく、何度も洗われて体に馴染んだ、くたびれた墨色の作務衣を身につけている。綺麗に剃り上げられた頭には、銀色の髪が短く残っていた。深く刻まれた目尻の皺は、彼がこれまでに重ねてきた年月の証であり、まるで常に穏やかに笑っているかのように見えた。その手には、小さな金属製の乳鉢と乳棒が握られており、今しがたまで何かをすり潰していたのだろう。ゴリ、ゴリ、という硬質な音の余韻と共に、先ほどよりも一層深く、そして香ばしい薬草の香りがふわりと漂ってきた。
「おお、あんたが大学病院から来た、ええと……未来先生、だったかな」
老人は、悪びれる様子など微塵も見せず、のんびりとした、それでいて芯のある口調で言った。
この人こそが、紹介状に書かれていた東堂宗右衛門先生に違いない。未来は慌てて背筋を伸ばし、深く、直角に頭を下げた。
「は、はい!本田未来です!本日から三ヶ月間、よろしくご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます!」
医局で叩き込まれた、マニュアル通りの完璧な挨拶。だが、東堂先生は「ふむ」と静かに一つ頷いただけで、未来が緊張と共に差し出した紹介状には目もくれず、ただ、彼女の顔をじっと見つめた。その視線は、決して人を値踏みするような不躾なものではない。まるで、庭の景色や空の雲の流れでも眺めるかのように、ただ静かで、それでいて彼女の内面までも見透かしてしまうかのような、深く、澄んだものだった。
「……暑い中、よう来なすった。さぞ、喉が渇いただろう。まあ、そこに座りなさい」
そう言って東堂先生が顎で示したのは、待合室の隅に置かれた、長年の使用で表面が滑らかになった使い古された長椅子だった。未来は一瞬戸惑いながらも、「は、はい。失礼します」と短く答え、その椅子の端に浅く腰掛けた。背筋は伸びたままだった。
東堂先生は、持っていた乳鉢をカウンターの上にことりと置くと、建物の裏手へと続く土間の方へ、ゆっくりとした足取りで消えていく。やがて、ことり、という涼やかな音と共に戻ってきた彼の手には、薄いガラスのコップが二つ。その中では、淡い褐色の液体が、手作りの不揃いな氷と共に涼やかな音を立てていた。
「さ、飲みなさい。自家製の麦茶だ」
「あ、ありがとうございます……!」
未来は恐縮しながらそのコップを受け取った。きんと冷えたガラスの感触が、火照った体に驚くほど心地よい。促されるままに一口飲むと、市販のペットボトルのものとは全く違う、深く香ばしい、焙煎された穀物の風味が口いっぱいに広がった。それは、ただの麦茶ではないような気がした。ごくりと飲み下すと、乾ききっていた喉から食道、そして胃の腑へと、冷たい液体が染み渡っていくのが分かる。体の芯から、じんわりと熱が引いていくような、不思議な感覚だった。
「……美味しい、です。なんだか、普通の麦茶と違うような……」
「ほう。分かるかね」
東堂先生は、自分も長椅子にどっかりと腰を下ろし、満足そうに目を細めた。「少しばかり、はと麦と、それから体の余計な熱を冷ますものを混ぜてある。あんたさん、ずいぶんと体の表面に熱を溜め込んで、息せき切ってやって来たからな。まずは、その上ずった熱を冷ましてやらんことには、話も始まらん」
「……え?」
未来は、思わず先生の顔を見返した。
体の表面の熱?たしかに外は猛烈に暑かったが、それは誰もが同じ条件のはずだ。彼は、未来の何を見てそう判断したというのだろう。脈をとられたわけでも、聴診器を当てられたわけでも、ましてやサーモグラフィーで見たわけでもない。ただ、待合室に入ってきた彼女の顔を、ほんの数秒見ただけで?
「あの、先生。こちらが大学病院からの紹介状と、私の履歴書になります」
話の奇妙な流れを断ち切るように、未来は慌てて鞄からクリアファイルに入った書類を取り出した。最先端の医療機器を誰よりも使いこなし、数々の症例をロジカルなレポートにまとめてきたという確固たる自負が、彼女の言葉を少しだけ早口にさせた。
しかし、東堂先生はその書類を受け取ろうともせず、ちりん、と軒先の風鈴が澄んだ音を立てたのに耳をすませるように、ふっと目を閉じた。
「風が、少し変わったな。こりゃ、夕立が来るかもしれん」
「は……?」
「あんたさん、大学病院では、ずいぶんと優秀な成績だったそうじゃないか。最新の機械を駆使して、目に見えんウイルスや細菌を見つけ出し、正しい薬でそれを的確に叩く。実に、見事なもんだ。大したもんじゃ」
それは、おそらく紹介状に書かれていた内容なのだろう。未来は少しだけ誇らしい気持ちになった。だが、先生の言葉は、彼女が全く予期しない方向に続いていった。
「だがな、未来先生。わしらは、そういうもんとは少し違う見方をする。例えば、風邪をひいた患者がここへ来たとしよう。あんたさんなら、まずウイルスの特定を考えるだろう。インフルエンザか、アデノか、それともライノかと。違うかね?」
「はい。原因となる病原体を特定し、それに最も有効な抗ウイルス薬や対症療法を選択するのが治療の基本です。それが、科学的根拠に基づいた現代医療ですから」
未来は、淀みなく答えた。それは、医学部で、そして臨床の現場で、彼女が金科玉条のごとく叩き込まれてきた医学の根幹そのものだった。
すると、東堂先生は、ゆっくりと目を開け、まるで子供に何か面白いことを教えるかのように、悪戯っぽく笑った。
「わしなら、こう考える。『おやおや、体の表面、つまりバリアが弱っているところに、良くない"気"、すなわち"邪気(じゃき)"が取りついて、悪さをしとるな』と」
「……じゃき?」
その単語を聞いた瞬間、未来の思考が、完全に停止した。
邪気。それは、漫画やファンタジー小説の世界で使われる言葉ではなかったか。目の前にいる医師免許を持った人間が、こともなげに、それを口にした。ここは、本当に認可された医療機関なのだろうか。もしかしたら、自分はとんでもない研修先を選んでしまったのではないか。そんな深刻な疑念が、むくむくと頭をもたげてくる。
未来の混乱をありありと見て取ったのか、東堂先生はカラカラと喉を鳴らして笑った。
「無理もない。あんたさんたちの医学は、顕微鏡の発明と共に、どんどん小さな世界へ、ミクロの世界へと進んでいった。細胞を、遺伝子を、分子レベルで解明しようとする。それは本当に素晴らしいことだ。だが、わしらの医学は、それとは違う方角をずっと向いておった。森羅万象、つまり、季節の移ろいや気候の変化、人間を取り巻く自然との関わりという、大きな視点、マクロな視点で体を丸ごと捉えようとしてきたんだ」
先生はゆっくりと立ち上がると、あの巨大な百味箪笥の前まで歩いて行った。そして、無数にある引き出しの一つに慣れた手つきで指をかけ、静かに開ける。ふわりと、また別の、甘さと苦さが複雑に絡み合った濃厚な香りが待合室に漂ってきた。
「病原体という『点』だけを追いかけるのが西洋医学なら、わしらは、なぜその人が病にならねばならなかったのか、その人の持って生まれた体質や日々の生活、心のありようまで含めた『全体』を見ていく。それが東洋医学の、ほんの入り口だ」
東堂先生は、指先でつまんだ赤褐色の乾燥した植物の根のようなものを、呆然としている未来の目の前に、そっと差し出した。シナモンのような、しかしもっと土臭く、力強い香りがした。
「さあ、未来先生。今日から三ヶ月、あんたがこれまで築き上げてきた常識が、全く通用しない世界へようこそ。難しいことは何も言わん。まずは、その優秀な頭で考えるのを少しだけ休んで、その目と、耳と、鼻で、目の前の患者さんと、そしてこの場所に満ちている『気』というものを、ただ、ただ感じてみることから始めなさい」
差し出された、ひとかけらの生薬。
その向こうに見える、穏やかで、それでいて全てを知っているかのような老医師の深い瞳。
こち、こち、と変わらず時を刻む古時計の音。ちりん、と風に歌う風鈴の音。そして、幾千もの薬草が静かな眠りにつきながら、出番を待っているこの空間。
未来は、自分が今、とてつもなく大きく、そして深い世界の、ほんの入り口に立ったばかりだということを、予感せずにはいられなかった。それは、西洋医学という名の、光に満ちた揺るぎない一本道をひたすらに歩いてきた彼女にとって、初めて目にする、薄暗く、それでいて無限の奥行きを感じさせる、全く別の道だった。
外で、遠雷が一つ、地の底から響くように低く轟いた。東堂先生の言った通り、夕立が来るのかもしれない。
湿り気を含んだ風が引き戸の隙間から流れ込み、空気が、また少し、その匂いを変えた気がした。
10
あなたにおすすめの小説
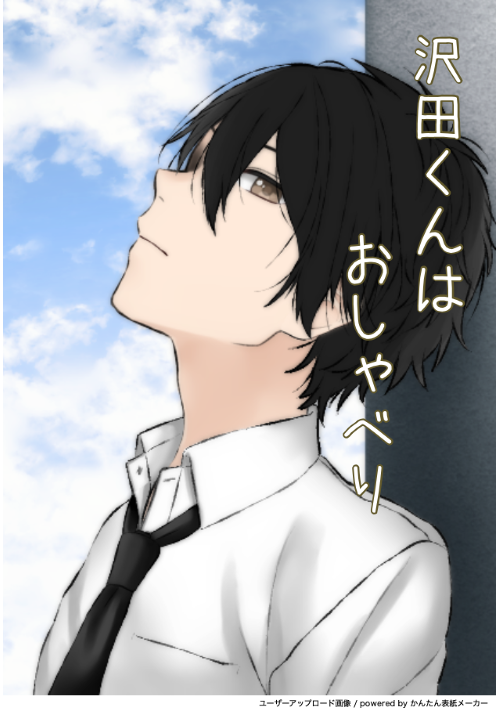
沢田くんはおしゃべり
ゆづ
青春
第13回ドリーム大賞奨励賞受賞✨ありがとうございました!!
【あらすじ】
空気を読む力が高まりすぎて、他人の心の声が聞こえるようになってしまった普通の女の子、佐藤景子。
友達から地味だのモブだの心の中で言いたい放題言われているのに言い返せない悔しさの日々の中、景子の唯一の癒しは隣の席の男子、沢田空の心の声だった。
【佐藤さん、マジ天使】(心の声)
無口でほとんどしゃべらない沢田くんの心の声が、まさかの愛と笑いを巻き起こす!
めちゃコミ女性向け漫画原作賞の優秀作品にノミネートされました✨
エブリスタでコメディートレンドランキング年間1位(ただし完結作品に限るッ!)
エブリスタ→https://estar.jp/novels/25774848


子持ち愛妻家の極悪上司にアタックしてもいいですか?天国の奥様には申し訳ないですが
霧内杳/眼鏡のさきっぽ
恋愛
胸がきゅんと、甘い音を立てる。
相手は、妻子持ちだというのに。
入社して配属一日目。
直属の上司で教育係だって紹介された人は、酷く人相の悪い人でした。
中高大と女子校育ちで男性慣れしてない私にとって、それだけでも恐怖なのに。
彼はちかよんなオーラバリバリで、仕事の質問すらする隙がない。
それでもどうにか仕事をこなしていたがとうとう、大きなミスを犯してしまう。
「俺が、悪いのか」
人のせいにするのかと叱責されるのかと思った。
けれど。
「俺の顔と、理由があって避け気味なせいだよな、すまん」
あやまってくれた彼に、胸がきゅんと甘い音を立てる。
相手は、妻子持ちなのに。
星谷桐子
22歳
システム開発会社営業事務
中高大女子校育ちで、ちょっぴり男性が苦手
自分の非はちゃんと認める子
頑張り屋さん
×
京塚大介
32歳
システム開発会社営業事務 主任
ツンツンあたまで目つき悪い
態度もでかくて人に恐怖を与えがち
5歳の娘にデレデレな愛妻家
いまでも亡くなった妻を愛している
私は京塚主任を、好きになってもいいのかな……?

裏長屋の若殿、限られた自由を満喫する
克全
歴史・時代
貧乏人が肩を寄せ合って暮らす聖天長屋に徳田新之丞と名乗る人品卑しからぬ若侍がいた。月のうち数日しか長屋にいないのだが、いる時には自ら竈で米を炊き七輪で魚を焼く小まめな男だった。

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。

つまらなかった乙女ゲームに転生しちゃったので、サクッと終わらすことにしました
蒼羽咲
ファンタジー
つまらなかった乙女ゲームに転生⁈
絵に惚れ込み、一目惚れキャラのためにハードまで買ったが内容が超つまらなかった残念な乙女ゲームに転生してしまった。
絵は超好みだ。内容はご都合主義の聖女なお花畑主人公。攻略イケメンも顔は良いがちょろい対象ばかり。てこたぁ逆にめちゃくちゃ住み心地のいい場所になるのでは⁈と気づき、テンションが一気に上がる!!
聖女など面倒な事はする気はない!サクッと攻略終わらせてぐーたら生活をGETするぞ!
ご都合主義ならチョロい!と、野望を胸に動き出す!!
+++++
・重複投稿・土曜配信 (たま~に水曜…不定期更新)

精霊に愛される(呪いにもにた愛)少女~全属性の加護を貰う~
如月花恋
ファンタジー
今この世界にはたくさんの精霊がいる
その精霊達から生まれた瞬間に加護を貰う
稀に2つ以上の属性の2体の精霊から加護を貰うことがある
まぁ大体は親の属性を受け継ぐのだが…
だが…全属性の加護を貰うなど不可能とされてきた…
そんな時に生まれたシャルロッテ
全属性の加護を持つ少女
いったいこれからどうなるのか…

あまりさんののっぴきならない事情
菱沼あゆ
キャラ文芸
強引に見合い結婚させられそうになって家出し、憧れのカフェでバイトを始めた、あまり。
充実した日々を送っていた彼女の前に、驚くような美形の客、犬塚海里《いぬづか かいり》が現れた。
「何故、こんなところに居る? 南条あまり」
「……嫌な人と結婚させられそうになって、家を出たからです」
「それ、俺だろ」
そーですね……。
カフェ店員となったお嬢様、あまりと常連客となった元見合い相手、海里の日常。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















