6 / 10
第6話 ケアマネ、【介護のプロ】を見つけ出す
しおりを挟む「【介護のプロ】が見つからなければ、何も始まりませんわ」
ネルは屋敷の庭で紅茶を飲みながら、向かいに座ったメイドのマリアンに熱心に説明した。
彼女の言う【介護のプロ】とは、オムツ交換や入浴介助などの実際の介護技術を持つ人を指す。
彼女の前世の職業は【ケアマネ】であるが、彼女自身は【介護のプロ】ではない。高齢者施設やヘルパー事業所等の現場で働いた経験がないのだ。というのも、彼女の元の資格は『保健師』といって、地域に住む住民の保健指導や健康管理といった仕事に従事してきた。
===Tips6===
【ケアマネの資格要件】
医師や薬剤師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、柔道整復師といった国家資格を持つ人や、生活相談員など介護施設などで相談援助業務などに従事している人で、一定以上の期間の実務経験があること。
この条件を満たすことで、試験の受験資格が与えられる。
一口に『ケアマネ』といっても、そのバックグラウンドとなる実務経験は様々なのだ。
=========
(私の元職が【介護のプロ】なら、もっと早く色々なことが解決できますのに……!)
ネルは歯痒い思いだった。だが、そこで立ち止まってはケアマネの名折れである。
彼女の内心の葛藤などつゆ知らず、マリアンがきょとんと首を傾げた。そもそも、彼女は【介護のプロ】というものにもピンときていないらしい。この世界には仕事として介護をしている人はいないので、当たり前といえば当たり前だ。
「その【介護のプロ】を見つけ出して、その人にアクトン夫人の介護をしてもらうんですか?」
マリアンの当然の疑問に、ネルはニコリと微笑んだ。
「もちろん、違いますわ」
「どういうことですか?」
ネルは身を乗り出して、マリアンの胸元を指差した。
「メイドと同じですわ」
意味が分からず、マリアンがまた首を傾げる。
「今では『メイド』と呼ばれる仕事に就く人は大勢いらっしゃいますけど、初めはそうではなかったということよ」
「……よくわかりません!」
「ふふふ。いいのよ。まずは、【介護のプロ】に会いに行きましょう」
「え! 心当たりがあるんですか?」
「ええ」
ネルはゆったりと立ち上がって、屋敷の中に戻っていった。さらに廊下を進み、裏に入る。それを見たマリアンは慌ててネルを引き止めた。
「お嬢様、そちらはいけません」
裏とは、使用人専用の階段や廊下を指す。屋敷の主人とその家族は、基本的に立ち入ってはならない場所である。
「今更でしょう? 厨房にも遊びに行くんですから」
「そうですけど……」
用事があって厨房に入っていくのとはわけが違う。彼女が向かっているのは、屋根裏の使用人寮なのだから。
「お嬢様!」
「どうしてこちらに!」
すれ違うメイドたちの驚く声に微笑みだけを返しながら、ネルはどんどん廊下を進んでいった。その先には、ある人物の部屋がある。
──コン、コン。
ネルは迷う素振りを一切見せずに、その扉を叩いた。
「はいはい。今日のおばあは休みよ。なんの用だい?」
中から扉を開いたのは、初老の女性だった。
彼女の名はモリー。『おばあ』と呼ばれる、最古参のメイドである。通常、この年齢のメイドは退職して屋敷を出ていくが、彼女はクラム伯爵夫人に請われてメイドの指導役として屋敷に残った。働くのは週3日だけで、残りの日は部屋で休むか遊びに出かける生活を送っている。
「あら! これは失礼いたしました、ネルお嬢様!」
ネルの顔を見たモリーは、慌てて礼をとった。
「おばあにご用事でしたか? お呼びいただいたら、すぐにお部屋にまいりましたのに」
「今日は休日でしょう? 部屋にいてくれて助かったわ」
「そりゃあ、もう、暇人ですから」
「少し、よろしいかしら?」
「え、ええ」
モリーは戸惑いながらもネルを室内に招き入れた。ネルは椅子に腰掛け、モリーは促されて仕方なくベッドに腰掛ける。
「今日は、モリーにお願いがあって来たの」
ネルは、神殿での調査を経て、この世界にも【介護のプロ】がいると確信した。なぜなら、神官の『聖なる力』でも老化に伴う異常を治療することはできない。つまり、この世界の高齢者にも介護が必要になる時が必ず来るからだ。
介護が仕事として成立していないのは、かつての日本がそうだったように、介護は家庭内の人員によって担われているからに過ぎない。
(平民なら家族が行う介護だけど、貴族は違う。使用人──『メイド』の仕事よ)
この屋敷に高齢者が暮らしていたのは、もう20年以上も前のことだ。現在勤めているほとんどのメイドには介護の経験がない。だから、このおばあを訪ねてきたのだ。
「モリーは、先々代の伯爵夫人のお世話を担当していたわよね?」
「はい、そうです」
「亡くなる日まで、献身的に介護をしてくれたと聞いたわ」
「それが私の仕事です。何より、私も大奥様にはたいへんお世話になりましたから……」
ネルは目尻に涙を滲ませたモリーの手をとった。
「その技術で、私の仕事を手伝ってほしいのよ!」
こうしてネルは【介護のプロ】を見つけ出した。といっても、身近な場所に既にいたのだが。
(往々にして、【社会資源】は身近なところにあるものよ)
と、ネルは内心でにんまりと微笑んだのだった。
* * *
使用人寮から戻ったネルは、さっそく母親である伯爵夫人にモリーに仕事を手伝ってもらう旨の了承を取り付けた。『モリーも歳なのだから、あまり無理はさせないように』と釘を刺されはしたが。
「はっ、そういえば!」
そして自室に戻って一人になり、ゴロンとベッドに転がったネルはあることを思い出した。
「神殿で『聖女』について聞いてくるのを忘れていたわ!」
仕事に必死になるあまり、すっかり忘れていたのだ。ネルは深い溜め息を吐きながら考えた。
「……うん。『聖女』のことはおいおい調べるとして、まずはこの仕事に集中しましょう。これで成果を上げれば、婚約破棄はともかく追放は回避できるかもしれないし!」
と、改めて決意したのだった。
この翌日、件の『聖女』に出会ってしまうとは、この時の彼女は思いもしなかったのだ──。
23
あなたにおすすめの小説

【完結】悪役令嬢の妹に転生しちゃったけど推しはお姉様だから全力で断罪破滅から守らせていただきます!
くま
恋愛
え?死ぬ間際に前世の記憶が戻った、マリア。
ここは前世でハマった乙女ゲームの世界だった。
マリアが一番好きなキャラクターは悪役令嬢のマリエ!
悪役令嬢マリエの妹として転生したマリアは、姉マリエを守ろうと空回り。王子や執事、騎士などはマリアにアプローチするものの、まったく鈍感でアホな主人公に周りは振り回されるばかり。
少しずつ成長をしていくなか、残念ヒロインちゃんが現る!!
ほんの少しシリアスもある!かもです。
気ままに書いてますので誤字脱字ありましたら、すいませんっ。
月に一回、二回ほどゆっくりペースで更新です(*≧∀≦*)

悪役令嬢になりたくないので、攻略対象をヒロインに捧げます
久乃り
恋愛
乙女ゲームの世界に転生していた。
その記憶は突然降りてきて、記憶と現実のすり合わせに毎日苦労する羽目になる元日本の女子高校生佐藤美和。
1周回ったばかりで、2週目のターゲットを考えていたところだったため、乙女ゲームの世界に入り込んで嬉しい!とは思ったものの、自分はヒロインではなく、ライバルキャラ。ルート次第では悪役令嬢にもなってしまう公爵令嬢アンネローゼだった。
しかも、もう学校に通っているので、ゲームは進行中!ヒロインがどのルートに進んでいるのか確認しなくては、自分の立ち位置が分からない。いわゆる破滅エンドを回避するべきか?それとも、、勝手に動いて自分がヒロインになってしまうか?
自分の死に方からいって、他にも転生者がいる気がする。そのひとを探し出さないと!
自分の運命は、悪役令嬢か?破滅エンドか?ヒロインか?それともモブ?
ゲーム修正が入らないことを祈りつつ、転生仲間を探し出し、この乙女ゲームの世界を生き抜くのだ!
他サイトにて別名義で掲載していた作品です。

私も異世界に転生してみたい ~令嬢やめて冒険者になります~
こひな
恋愛
巷で溢れる、異世界から召喚された強大な力を持つ聖女の話や、異世界での記憶を持つ令嬢のハッピーエンドが描かれた数々の書物。
…私にもそんな物語のような力があったら…
そんな書物の主人公に憧れる、平々凡々な読書好きな令嬢の奇想天外なお話です。

【完結】ヒロインに転生しましたが、モブのイケオジが好きなので、悪役令嬢の婚約破棄を回避させたつもりが、やっぱり婚約破棄されている。
樹結理(きゆり)
恋愛
「アイリーン、貴女との婚約は破棄させてもらう」
大勢が集まるパーティの場で、この国の第一王子セルディ殿下がそう宣言した。
はぁぁあ!? なんでどうしてそうなった!!
私の必死の努力を返してー!!
乙女ゲーム『ラベルシアの乙女』の世界に転生してしまった日本人のアラサー女子。
気付けば物語が始まる学園への入学式の日。
私ってヒロインなの!?攻略対象のイケメンたちに囲まれる日々。でも!私が好きなのは攻略対象たちじゃないのよー!!
私が好きなのは攻略対象でもなんでもない、物語にたった二回しか出てこないイケオジ!
所謂モブと言っても過言ではないほど、関わることが少ないイケオジ。
でもでも!せっかくこの世界に転生出来たのなら何度も見たイケメンたちよりも、レアなイケオジを!!
攻略対象たちや悪役令嬢と友好的な関係を築きつつ、悪役令嬢の婚約破棄を回避しつつ、イケオジを狙う十六歳、侯爵令嬢!
必死に悪役令嬢の婚約破棄イベントを回避してきたつもりが、なんでどうしてそうなった!!
やっぱり婚約破棄されてるじゃないのー!!
必死に努力したのは無駄足だったのか!?ヒロインは一体誰と結ばれるのか……。
※この物語は作者の世界観から成り立っております。正式な貴族社会をお望みの方はご遠慮ください。
※この作品は小説家になろう、カクヨムで完結済み。

〘完〙なぜかモブの私がイケメン王子に強引に迫られてます 〜転生したら推しのヒロインが不在でした〜
hanakuro
恋愛
転生してみたら、そこは大好きな漫画の世界だった・・・
OLの梨奈は、事故により突然その生涯閉じる。
しかし次に気付くと、彼女は伯爵令嬢に転生していた。しかも、大好きだった漫画の中のたったのワンシーンに出てくる名もないモブ。
モブならお気楽に推しのヒロインを観察して過ごせると思っていたら、まさかのヒロインがいない!?
そして、推し不在に落胆する彼女に王子からまさかの強引なアプローチが・・
王子!その愛情はヒロインに向けてっ!
私、モブですから!
果たしてヒロインは、どこに行ったのか!?
そしてリーナは、王子の強引なアプローチから逃れることはできるのか!?
イケメン王子に翻弄される伯爵令嬢の恋模様が始まる。
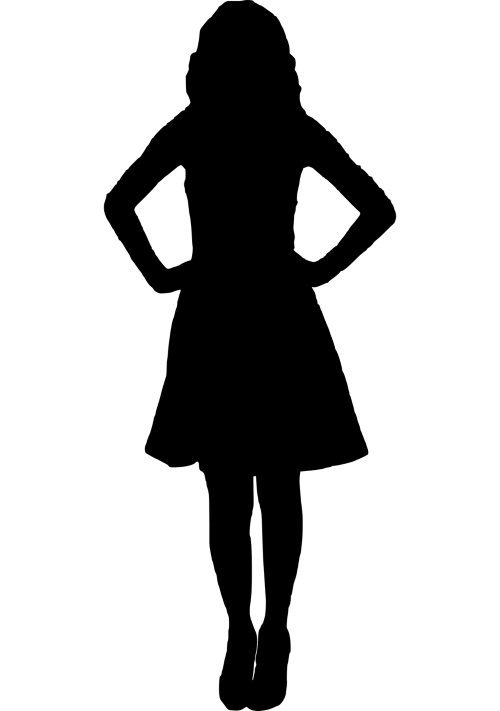
気がついたら婚約者アリの後輩魔導師(王子)と結婚していたんですが。
三谷朱花
恋愛
「おめでとう!」
朝、職場である王城に着くと、リサ・ムースは、魔導士仲間になぜか祝われた。
「何が?」
リサは祝われた理由に心当たりがなかった。
どうやら、リサは結婚したらしい。
……婚約者がいたはずの、ディランと。

婚約者を奪い返そうとしたらいきなり溺愛されました
宵闇 月
恋愛
異世界に転生したらスマホゲームの悪役令嬢でした。
しかも前世の推し且つ今世の婚約者は既にヒロインに攻略された後でした。
断罪まであと一年と少し。
だったら断罪回避より今から全力で奪い返してみせますわ。
と意気込んだはいいけど
あれ?
婚約者様の様子がおかしいのだけど…
※ 4/26
内容とタイトルが合ってないない気がするのでタイトル変更しました。

【長編版】孤独な少女が異世界転生した結果
下菊みこと
恋愛
身体は大人、頭脳は子供になっちゃった元悪役令嬢のお話の長編版です。
一話は短編そのまんまです。二話目から新しいお話が始まります。
純粋無垢な主人公テレーズが、年上の旦那様ボーモンと無自覚にイチャイチャしたり様々な問題を解決して活躍したりするお話です。
小説家になろう様でも投稿しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















