13 / 35
第13話:再会のノック
しおりを挟む
六月の陽射しはすでに夏の匂いを帯びていた。
グラウンドに響く乾いた音――それは、臨時監督・風祭修司によるノックの音だった。
「次、ライト! ちゃんと前に出ろ、後ろに逃げるな!」
「ショート、今の足運びじゃセカンドに間に合わねぇぞ!」
檄が飛ぶたび、部員たちは顔をしかめながらも必死にボールを追った。
厳しい練習に音を上げる者もいたが、修司のノックは的確で、どこか説得力があった。
「……にしても、なんだよあのノック。おっさんなのに、全然ブレねぇな」
セカンドの松井が苦笑いしながら汗を拭く。
ボールがバウンドする音が、リズムになって聞こえていた。
ゴン――ザザッ。ゴン――ザザッ。
桜が丘のグラウンドに、ひときわ鋭い打球音が響いている。ノックバットを握るのは、臨時監督の風祭修司。球児の親父だとあとから知ったけれど、小野寺翼にとっては、まず「ノックがエグいオヤジ」という印象が強かった。
初日の練習で、軽く膝が笑った。内野ゴロ、フライ、カット、バント処理……とにかく休む暇がない。
でも、不思議だった。
「きつい……けど、なんだろ、嫌な感じじゃねえな」
ボールの飛び方が、毎回違うのに、不思議と“意図”があるのがわかる。
右へ左へ追い回されながら、小野寺はあることに気づいた。
風祭監督のノックには、決まった“間”があった。
ワンバウンドで獲らせる球と、ライナー性のゴロ、その合間に深く打ち込むボール――
そこに、リズムがあった。
「ゴン……ザザッ、ゴン……ザザッ……ゴン!」
身体がついていかないのに、心が置いていかれない。
それは、今まで感じたことのない感覚だった。
これまでの練習では、「とりあえず打っておけ」みたいなノックが多かった。球の質もバラバラで、ただ疲れるだけの日もあった。
でも、今日は違う。
“獲らせたい”という意図が、ノックの中にある。
“走らせたい”じゃなく、“ちゃんとゴロに向かわせたい”という思いが伝わってくる。
(ちゃんと怖いけど、ちゃんと優しい……)
息を切らしながら、思わず笑っていた。
「ったく、すげぇオッサンだな……」
誰かに怒鳴られるのも、怒られるのも、最近は適当に聞き流すようになっていた。
けど、風祭監督のノックは、そうじゃない。
“お前らなら、もっとできるだろ”と、背中で叩かれているような感覚。
足が止まりそうになるたびに、またバットの音が響く。
「ほら小野寺! 一歩目が遅い!」
名前を呼ばれる。顔をちゃんと見られている。
それだけで、なんだか真面目にやらなきゃって気持ちになる。
(ヘタな優しさより、ちゃんとした怖さの方が、頼りになることもあるんだな)
ノックのリズムが、身体に刻まれていく。
今日、小野寺は初めて、練習後の筋肉痛を「心地いい」と思った。
一方、球児は無言でランニングメニューをこなしていた。
修司とは目を合わそうとせず、ただ黙々と体を動かしている。
「なあ、風祭」
石原が隣に並んできた。キャッチャーの彼は、チームの中で球児に一番近い位置にいる。
「……あれ、絶対お前の親父だよな?」
「……知らねぇよ」
そっけない一言。だが、その言葉の裏に隠されたざらついた感情は、石原にも伝わっていた。
キャッチャーの石原翔太は、気づいていた。
最初のノックが始まったときだった。臨時監督として現れた風祭修司の打球は、正確で、厳しくて、どこか愛情深かった。ボールはギリギリの場所を突き、足元をすくうように滑り、選手たちの反応を試すような動きをしていた。
「クセ、あるな……このノック」
ミット越しに構えながら、石原はそう呟いた。
似ていたのだ。
どこかで見たことのある、ステップ。
視線の動かし方。
ボールを打ち出すときの、わずかな手首のクセ。
そして何より、風祭球児と目線が交錯したときの、あの瞬間――
球児はふと顔をそらし、視線を落とした。
監督も、それ以上は何も言わず、次のノックに移った。
普通なら、見逃すような一瞬だ。
でも、石原のようにキャッチャーマスクの奥で、常に全体を見ている立場の人間には、見えた。
(あの人……風祭の親父さんじゃねぇのか?)
昼休み、石原は自分の捕手としての感を確かめる為に練習後の部室で再度、球児に聞いてみた。
「風祭、あれ絶対お前の親父だろ」
返ってきた言葉は、そっけなかった。
「……知らねぇよ」
けれど、石原は見た。
その一言を返すまでに、球児のまぶたがわずかに伏せられたことを。
言葉と心の間にある、微かな“揺らぎ”を。
キャッチャーは、投手のコンディションを“目”で読む。
コントロールがずれているか、握りが甘いか、緩んだ気持ちを、無意識の動作から見抜く。
だからこそ、石原にはわかった。
あの「知らねぇよ」は、拒絶でも無関心でもなく、
──ただの戸惑いだったのだと。
「へぇ、そっか」とだけ返して、それ以上は聞かなかった。
試合の日、マウンドで球児が黙っているときも、石原は声をかけなかった。
信頼とは、言葉の数で築くものじゃない。
ベンチで静かにメモをとるその背中を、マスク越しに見守るだけで、今はそれでいいと、石原は思っていた。
*
放課後のグラウンドには、もう誰の声も残っていなかった。かすかな風が赤土を揺らし、金属バットの鈍い音が遠くで誰かの練習を告げている。
千紗はひとり、ベンチの隅に腰を下ろしていた。膝の上に置いたのは、修司の持ち物と思われる、黒い表紙のノート。グラウンド整備用具の片づけ中、偶然荷物置き場で見つけたそれを、彼女はどうしても返す前にもう一度だけ見たかった。
“臨時監督・風祭修司”と小さく書かれた表紙をめくると、そこには手書きでびっしりと書かれたメモがあった。
《風祭球児:第2ステップの沈み込みが浅くなっている。フォークの落差は健在。疲労時に右肘が下がる癖、まだ直っていない》
ページをめくるごとに、球児のフォーム、球種、配球傾向、好きな飲み物に至るまで、詳細な記録が並んでいた。
──これを書いた人は、ずっと球児を見ていたのだ。
開いたページには、球児の名前が繰り返し綴られている。
「投球後の左足の流れが気になる」「牽制のタイミング、右肩が硬い」
それらは冷静な指摘でありながら、どこか必死なようでもあった。
ページの下部、インクがかすれて読みにくくなった箇所がある。
“背中を見ていた、ずっと。けれど、近づけなかった。”
それを目にした瞬間、千紗の指がふっと止まった。
そっと手でページの角をなぞる。
「……なんだか、ちょっと似てるね……お父さんと風祭くん」
思わず口をついて出たひとりごとは、誰に聞かせるでもない、静かな呟きだった。
黙って背中で何かを伝えようとする不器用さ。言葉にしないまま、でも誰かをずっと見つめているまなざし。千紗は、修司の筆跡に、あのぶっきらぼうで少し不器用な球児の姿を重ねていた。
ふと目を上げると、沈みかけた夕日がちょうどベンチの背後から差し込んできた。
彼女の頬をやさしく照らし、ノートのページの文字を、橙色に染める。
千紗はそっとノートを閉じると、胸の前で小さく抱きしめた。
まだ、風祭くんは知らない。
あんなふうに、誰かが彼を見ていたことも。
そして、見守ることが、時にどれほどの勇気を要するかということも。
けれど、それでも――その背中を、これからも見ていたい。
千紗のまなざしは、そんな静かな決意を宿していた。
夕日が、やわらかく最後の光を彼女の横顔に注いでいた。
■
放課後のグラウンド。夕焼けが、フェンスをオレンジ色に染めていた。
千紗はマネージャー用の小さな折りたたみ机に、静かに座っていた。ノートを開いて、ペンを走らせる。
ページの左上には、ちいさく「観察日記・その5」と書かれている。
ふと顔を上げると、ブルペンのほうに風祭球児の姿が見える。だがその視線は、ずっと地面のほうばかり向いていて――
そう、今日の球児は、一度も「親父さん」のほうを見ていなかった。
臨時監督として、グラウンドのど真ん中に立つ風祭修司。
その背中にも、どこか「言葉にできないもの」が揺れている気がした。
だが、千紗の視線は、あくまで「球児」のほうに寄り添っていた。
――“今日は一度も親父さんの方を見なかった。でも、ボール拾いのとき、ちょっと近づいた”
千紗のペン先が、さらさらと動く。
彼がネット際で転がったボールを拾うとき、ほんの一歩だけ、修司の立っている方向へと足を向けていた。
それに気づいたのは、おそらく千紗だけだ。
――“練習終わってから、グラブをぎゅっと握った音がした”
聞こえたのは、ごく微かな革の音。
練習が終わり、みんなが笑いながら水を飲んでいる横で、球児はひとりベンチに座り、グラブを両手で包み込むように握っていた。
その指の先に宿る力が、まるで言葉の代わりみたいだった。
千紗はそっと目を伏せ、最後のひと言を書く。
――「今日の風祭くん:黙ってたけど、たぶん、すこし泣いてた」
ページを閉じる音が、風にまぎれて消えていく。
けれど、手帳の中には今日という日が、確かに刻まれていた。
■
夜の帰り道。
千紗は一歩前に出て、歩く球児に声をかけた。
「ねえ、さっき……監督さんのノート、見ちゃった」
「……そっか」
球児は立ち止まり、ほんの一瞬だけ目を細めた。
「すごく、細かかった。フォームのことも、手首の使い方も、あとは……」
千紗は言葉を探し、そしてそっと言った。
「“好きだった麦茶は、冷たいの”って……」
球児の肩がほんの少しだけ揺れた。
「きっと、ちゃんと見てたんだよ。きっと、ずっと」
沈黙が落ちる。
球児は言葉を返さなかった。けれど、彼の手の中で握られたグラブが、ぎゅっと音を立てた。
それは、もう一度“野球”に触れたいと願う、少年の静かな決意の音だった。
*
夜の台所。湯気の立つマグカップから漂うコーヒーの香りが、古びた一室にやわらかく広がっていた。風祭修司は、ひとり机に向かっていた。白いページをめくる指先が、ごつごつとした節だらけの手をしている。
ノートの表紙には、何の装飾もない。ただ、ペンで小さく「練習用・風祭」とだけ書かれていた。
そのページをめくると、びっしりと並んだ文字。投球フォームの分析。体重移動のタイミング。プレートの踏み出し位置。さらにその下には、キャッチボールの際の癖、スライダーの抜けやすい回転の傾向──。
それは他の選手のデータではなかった。すべて、息子・風祭球児についてだった。
「左肩が早めに開くクセ、まだ治ってないかもしれん」
「ストレートの軌道、あいつはあれで“まっすぐ”って思ってる」
「キャッチャーの構えが外れたとき、手元が甘くなる傾向あり」
書きながら、修司は静かに息を吐く。
「……息子としては、もう俺のことを必要としてない。それでいいんだ。あいつはもう、ひとりで立てる」
だが、その手はページの隅に、こっそりこうも書いていた。
「球児──ストレートが好きだろ。最後の勝負球は、いつもそれだったもんな」
まるで、親としてではなく、一人の“元投手”として、ライバルを見るような視線。
ページをめくる手は不器用で、ペン先が何度か震えてにじんだ跡もある。それでも、修司の視線はまっすぐだった。
「選手としては、ちゃんと見てきたつもりだ。親にはなれなかったかもしれんが、野球人として──お前を否定したことは、一度もない」
修司はマグカップに口をつけ、冷えかけたコーヒーを少しだけすすった。
臨時監督として暫くの間、桜が丘のグラウンドに立つ。
そして息子に言うのだ。お前が投げたくなるまで、俺はただ“見てる”だけだと。
机の上で、夜風に一枚のページがふわりとめくれた。
グラウンドに響く乾いた音――それは、臨時監督・風祭修司によるノックの音だった。
「次、ライト! ちゃんと前に出ろ、後ろに逃げるな!」
「ショート、今の足運びじゃセカンドに間に合わねぇぞ!」
檄が飛ぶたび、部員たちは顔をしかめながらも必死にボールを追った。
厳しい練習に音を上げる者もいたが、修司のノックは的確で、どこか説得力があった。
「……にしても、なんだよあのノック。おっさんなのに、全然ブレねぇな」
セカンドの松井が苦笑いしながら汗を拭く。
ボールがバウンドする音が、リズムになって聞こえていた。
ゴン――ザザッ。ゴン――ザザッ。
桜が丘のグラウンドに、ひときわ鋭い打球音が響いている。ノックバットを握るのは、臨時監督の風祭修司。球児の親父だとあとから知ったけれど、小野寺翼にとっては、まず「ノックがエグいオヤジ」という印象が強かった。
初日の練習で、軽く膝が笑った。内野ゴロ、フライ、カット、バント処理……とにかく休む暇がない。
でも、不思議だった。
「きつい……けど、なんだろ、嫌な感じじゃねえな」
ボールの飛び方が、毎回違うのに、不思議と“意図”があるのがわかる。
右へ左へ追い回されながら、小野寺はあることに気づいた。
風祭監督のノックには、決まった“間”があった。
ワンバウンドで獲らせる球と、ライナー性のゴロ、その合間に深く打ち込むボール――
そこに、リズムがあった。
「ゴン……ザザッ、ゴン……ザザッ……ゴン!」
身体がついていかないのに、心が置いていかれない。
それは、今まで感じたことのない感覚だった。
これまでの練習では、「とりあえず打っておけ」みたいなノックが多かった。球の質もバラバラで、ただ疲れるだけの日もあった。
でも、今日は違う。
“獲らせたい”という意図が、ノックの中にある。
“走らせたい”じゃなく、“ちゃんとゴロに向かわせたい”という思いが伝わってくる。
(ちゃんと怖いけど、ちゃんと優しい……)
息を切らしながら、思わず笑っていた。
「ったく、すげぇオッサンだな……」
誰かに怒鳴られるのも、怒られるのも、最近は適当に聞き流すようになっていた。
けど、風祭監督のノックは、そうじゃない。
“お前らなら、もっとできるだろ”と、背中で叩かれているような感覚。
足が止まりそうになるたびに、またバットの音が響く。
「ほら小野寺! 一歩目が遅い!」
名前を呼ばれる。顔をちゃんと見られている。
それだけで、なんだか真面目にやらなきゃって気持ちになる。
(ヘタな優しさより、ちゃんとした怖さの方が、頼りになることもあるんだな)
ノックのリズムが、身体に刻まれていく。
今日、小野寺は初めて、練習後の筋肉痛を「心地いい」と思った。
一方、球児は無言でランニングメニューをこなしていた。
修司とは目を合わそうとせず、ただ黙々と体を動かしている。
「なあ、風祭」
石原が隣に並んできた。キャッチャーの彼は、チームの中で球児に一番近い位置にいる。
「……あれ、絶対お前の親父だよな?」
「……知らねぇよ」
そっけない一言。だが、その言葉の裏に隠されたざらついた感情は、石原にも伝わっていた。
キャッチャーの石原翔太は、気づいていた。
最初のノックが始まったときだった。臨時監督として現れた風祭修司の打球は、正確で、厳しくて、どこか愛情深かった。ボールはギリギリの場所を突き、足元をすくうように滑り、選手たちの反応を試すような動きをしていた。
「クセ、あるな……このノック」
ミット越しに構えながら、石原はそう呟いた。
似ていたのだ。
どこかで見たことのある、ステップ。
視線の動かし方。
ボールを打ち出すときの、わずかな手首のクセ。
そして何より、風祭球児と目線が交錯したときの、あの瞬間――
球児はふと顔をそらし、視線を落とした。
監督も、それ以上は何も言わず、次のノックに移った。
普通なら、見逃すような一瞬だ。
でも、石原のようにキャッチャーマスクの奥で、常に全体を見ている立場の人間には、見えた。
(あの人……風祭の親父さんじゃねぇのか?)
昼休み、石原は自分の捕手としての感を確かめる為に練習後の部室で再度、球児に聞いてみた。
「風祭、あれ絶対お前の親父だろ」
返ってきた言葉は、そっけなかった。
「……知らねぇよ」
けれど、石原は見た。
その一言を返すまでに、球児のまぶたがわずかに伏せられたことを。
言葉と心の間にある、微かな“揺らぎ”を。
キャッチャーは、投手のコンディションを“目”で読む。
コントロールがずれているか、握りが甘いか、緩んだ気持ちを、無意識の動作から見抜く。
だからこそ、石原にはわかった。
あの「知らねぇよ」は、拒絶でも無関心でもなく、
──ただの戸惑いだったのだと。
「へぇ、そっか」とだけ返して、それ以上は聞かなかった。
試合の日、マウンドで球児が黙っているときも、石原は声をかけなかった。
信頼とは、言葉の数で築くものじゃない。
ベンチで静かにメモをとるその背中を、マスク越しに見守るだけで、今はそれでいいと、石原は思っていた。
*
放課後のグラウンドには、もう誰の声も残っていなかった。かすかな風が赤土を揺らし、金属バットの鈍い音が遠くで誰かの練習を告げている。
千紗はひとり、ベンチの隅に腰を下ろしていた。膝の上に置いたのは、修司の持ち物と思われる、黒い表紙のノート。グラウンド整備用具の片づけ中、偶然荷物置き場で見つけたそれを、彼女はどうしても返す前にもう一度だけ見たかった。
“臨時監督・風祭修司”と小さく書かれた表紙をめくると、そこには手書きでびっしりと書かれたメモがあった。
《風祭球児:第2ステップの沈み込みが浅くなっている。フォークの落差は健在。疲労時に右肘が下がる癖、まだ直っていない》
ページをめくるごとに、球児のフォーム、球種、配球傾向、好きな飲み物に至るまで、詳細な記録が並んでいた。
──これを書いた人は、ずっと球児を見ていたのだ。
開いたページには、球児の名前が繰り返し綴られている。
「投球後の左足の流れが気になる」「牽制のタイミング、右肩が硬い」
それらは冷静な指摘でありながら、どこか必死なようでもあった。
ページの下部、インクがかすれて読みにくくなった箇所がある。
“背中を見ていた、ずっと。けれど、近づけなかった。”
それを目にした瞬間、千紗の指がふっと止まった。
そっと手でページの角をなぞる。
「……なんだか、ちょっと似てるね……お父さんと風祭くん」
思わず口をついて出たひとりごとは、誰に聞かせるでもない、静かな呟きだった。
黙って背中で何かを伝えようとする不器用さ。言葉にしないまま、でも誰かをずっと見つめているまなざし。千紗は、修司の筆跡に、あのぶっきらぼうで少し不器用な球児の姿を重ねていた。
ふと目を上げると、沈みかけた夕日がちょうどベンチの背後から差し込んできた。
彼女の頬をやさしく照らし、ノートのページの文字を、橙色に染める。
千紗はそっとノートを閉じると、胸の前で小さく抱きしめた。
まだ、風祭くんは知らない。
あんなふうに、誰かが彼を見ていたことも。
そして、見守ることが、時にどれほどの勇気を要するかということも。
けれど、それでも――その背中を、これからも見ていたい。
千紗のまなざしは、そんな静かな決意を宿していた。
夕日が、やわらかく最後の光を彼女の横顔に注いでいた。
■
放課後のグラウンド。夕焼けが、フェンスをオレンジ色に染めていた。
千紗はマネージャー用の小さな折りたたみ机に、静かに座っていた。ノートを開いて、ペンを走らせる。
ページの左上には、ちいさく「観察日記・その5」と書かれている。
ふと顔を上げると、ブルペンのほうに風祭球児の姿が見える。だがその視線は、ずっと地面のほうばかり向いていて――
そう、今日の球児は、一度も「親父さん」のほうを見ていなかった。
臨時監督として、グラウンドのど真ん中に立つ風祭修司。
その背中にも、どこか「言葉にできないもの」が揺れている気がした。
だが、千紗の視線は、あくまで「球児」のほうに寄り添っていた。
――“今日は一度も親父さんの方を見なかった。でも、ボール拾いのとき、ちょっと近づいた”
千紗のペン先が、さらさらと動く。
彼がネット際で転がったボールを拾うとき、ほんの一歩だけ、修司の立っている方向へと足を向けていた。
それに気づいたのは、おそらく千紗だけだ。
――“練習終わってから、グラブをぎゅっと握った音がした”
聞こえたのは、ごく微かな革の音。
練習が終わり、みんなが笑いながら水を飲んでいる横で、球児はひとりベンチに座り、グラブを両手で包み込むように握っていた。
その指の先に宿る力が、まるで言葉の代わりみたいだった。
千紗はそっと目を伏せ、最後のひと言を書く。
――「今日の風祭くん:黙ってたけど、たぶん、すこし泣いてた」
ページを閉じる音が、風にまぎれて消えていく。
けれど、手帳の中には今日という日が、確かに刻まれていた。
■
夜の帰り道。
千紗は一歩前に出て、歩く球児に声をかけた。
「ねえ、さっき……監督さんのノート、見ちゃった」
「……そっか」
球児は立ち止まり、ほんの一瞬だけ目を細めた。
「すごく、細かかった。フォームのことも、手首の使い方も、あとは……」
千紗は言葉を探し、そしてそっと言った。
「“好きだった麦茶は、冷たいの”って……」
球児の肩がほんの少しだけ揺れた。
「きっと、ちゃんと見てたんだよ。きっと、ずっと」
沈黙が落ちる。
球児は言葉を返さなかった。けれど、彼の手の中で握られたグラブが、ぎゅっと音を立てた。
それは、もう一度“野球”に触れたいと願う、少年の静かな決意の音だった。
*
夜の台所。湯気の立つマグカップから漂うコーヒーの香りが、古びた一室にやわらかく広がっていた。風祭修司は、ひとり机に向かっていた。白いページをめくる指先が、ごつごつとした節だらけの手をしている。
ノートの表紙には、何の装飾もない。ただ、ペンで小さく「練習用・風祭」とだけ書かれていた。
そのページをめくると、びっしりと並んだ文字。投球フォームの分析。体重移動のタイミング。プレートの踏み出し位置。さらにその下には、キャッチボールの際の癖、スライダーの抜けやすい回転の傾向──。
それは他の選手のデータではなかった。すべて、息子・風祭球児についてだった。
「左肩が早めに開くクセ、まだ治ってないかもしれん」
「ストレートの軌道、あいつはあれで“まっすぐ”って思ってる」
「キャッチャーの構えが外れたとき、手元が甘くなる傾向あり」
書きながら、修司は静かに息を吐く。
「……息子としては、もう俺のことを必要としてない。それでいいんだ。あいつはもう、ひとりで立てる」
だが、その手はページの隅に、こっそりこうも書いていた。
「球児──ストレートが好きだろ。最後の勝負球は、いつもそれだったもんな」
まるで、親としてではなく、一人の“元投手”として、ライバルを見るような視線。
ページをめくる手は不器用で、ペン先が何度か震えてにじんだ跡もある。それでも、修司の視線はまっすぐだった。
「選手としては、ちゃんと見てきたつもりだ。親にはなれなかったかもしれんが、野球人として──お前を否定したことは、一度もない」
修司はマグカップに口をつけ、冷えかけたコーヒーを少しだけすすった。
臨時監督として暫くの間、桜が丘のグラウンドに立つ。
そして息子に言うのだ。お前が投げたくなるまで、俺はただ“見てる”だけだと。
机の上で、夜風に一枚のページがふわりとめくれた。
0
あなたにおすすめの小説

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。
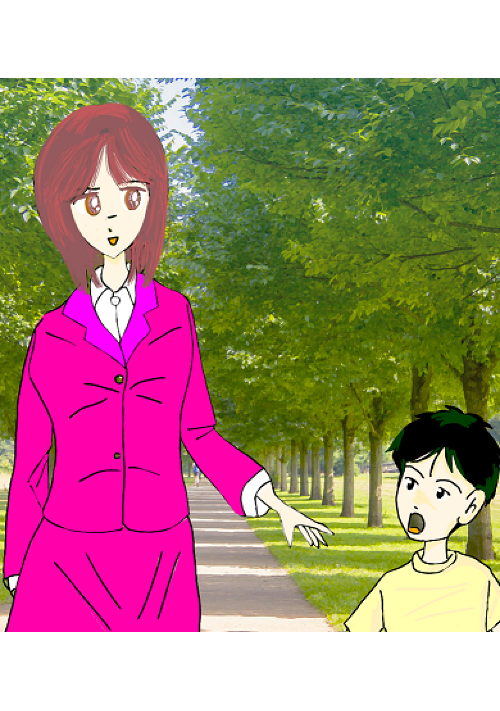
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

【完結済】25億で極道に売られた女。姐になります!
satomi
恋愛
昼夜問わずに働く18才の主人公南ユキ。
働けども働けどもその収入は両親に搾取されるだけ…。睡眠時間だって2時間程度しかないのに、それでもまだ働き口を増やせと言う両親。
早朝のバイトで頭は朦朧としていたけれど、そんな時にうちにやってきたのは白虎商事CEOの白川大雄さん。ポーンっと25億で私を買っていった。
そんな大雄さん、白虎商事のCEOとは別に白虎組組長の顔を持っていて、私に『姐』になれとのこと。
大丈夫なのかなぁ?

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話
登夢
恋愛
春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

【完結】イケメンが邪魔して本命に告白できません
竹柏凪紗
青春
高校の入学式、芸能コースに通うアイドルでイケメンの如月風磨が普通科で目立たない最上碧衣の教室にやってきた。女子たちがキャーキャー騒ぐなか、風磨は碧衣の肩を抱き寄せ「お前、今日から俺の女な」と宣言する。その真意とウソつきたちによって複雑になっていく2人の結末とは──

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。

中1でEカップって巨乳だから熱く甘く生きたいと思う真理(マリー)と小説家を目指す男子、光(みつ)のラブな日常物語
jun( ̄▽ ̄)ノ
大衆娯楽
中1でバスト92cmのブラはEカップというマリーと小説家を目指す男子、光の日常ラブ
★作品はマリーの語り、一人称で進行します。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















