30 / 35
第30話: 『背中に、全部乗せて』
しおりを挟む
決勝戦当日の朝。球場の空は、どこまでも澄んでいた。桜が丘ナインを乗せたバスが球場前に停まると、既に数多の観客が詰めかけ、スタンドにはテレビ局のカメラや地元紙の記者たちの姿も見えた。
「……人、多いな」
藤木が思わず呟くと、浜中が隣で肩をすくめた。
「そりゃあ、決勝戦だもんな」
その言葉に、全員が一斉に息をのんだ。緊張は、もう始まっていた。
ロッカールームに入ると、静けさが支配した。球児は、背番号“1”のユニフォームを丁寧にたたみ、そっと両手で持ち上げる。
──ここまで来た。
思い出すのは、東都学院で背番号をもらえなかった日々。ロッカーを荒らされたこと。誰も声をかけてくれなかったあの夕方。
でも、今は違う。
球児は深く息を吸って、静かにユニフォームに袖を通した。
「おい」
三島の声が、ロッカールームを切り裂いた。
「今日だけは、全員で“あいつの背中”に乗っかろうぜ」
いつもよりも低い声だった。だが、その一言で空気が変わった。
手を重ねる輪が、自然とできる。
「……いくぞ、桜が丘──!」
「オオオオッ!」
円陣の声が、グラウンドまで響き渡った。
プレイボール前のベンチ横――
朝露がまだ完全に消えきらない芝の上で、桜が丘ナインが円陣を組む。
中心に立つのは、主将・三島大地。
その足元には、泥の跳ね跡がまだ新しいスパイク。スパイクの先が、わずかに震えていた。
「球児の背中に乗っかるぞ!」
その一言を放った瞬間、喉の奥が乾いていたことに、三島はようやく気づいた。
東都学院――かつての名門、そして球児がいた場所。
相手の圧力は、ただの実力じゃない。名前が持つ“重み”が、すでにチームを呑み込もうとしていた。
「正直、怖ぇよ……」
心の中でつぶやいた三島は、円陣の中心で小さく息を呑んだ。
でも、それを顔に出してはいけない。自分は“主将”だ。誰よりも早く声を出し、誰よりも先に前を向く役割。
「……俺が最初に声を出せば、誰かが続いてくれる。
それが“主将”だろ、三島大地」
石原がうなずき、田代が拳を高く挙げる。
円陣がほどけ、各ポジションへと散っていくナインたち。
その背を見送りながら、三島は静かに自分のスパイクを見下ろした。
――少し、泥が乾いている。
それだけで、なぜか胸がじんと熱くなった。
試合前――
スパイクの紐が、片方だけ緩んでいた。
泥に染まり、草の香りが残るそれを、ベンチで静かに結び直す。
三島はグローブを脇に置いたまま、ふっと小さく笑った。
「勝ちたいんじゃねぇんだ。……勝たせたいんだよ、あいつに」
プレイボールの合図とともに始まった決勝戦。東都学院の1番打者が打席に立つ。相手のユニフォームの胸には、あの馴染みあるロゴが刻まれていた。
風祭球児はマウンドで軽く息を吐き、初球を構える。
キャッチャー・石原が小さくうなずき、ミットを構えた。
──初球、外角低めストレート。
乾いた音とともに、打球はセカンド正面。
「ワンアウト!」
三島の声が飛ぶ。
次の打者も詰まらせて内野ゴロ、そして三番。かつてのチームメイト、川島がベンチで腕を組んで立ち上がった。
「ちっ、こっちを捨てたくせに、いい顔しやがって……」
その視線に、球児は気づいていた。だが、一瞥もせず、次の打者に集中する。
三島が小さく口を開いた。
■
東都学院ベンチの片隅。川島栄伍は誰よりも早くユニフォームに袖を通し、グラブを手にしていた。
他の選手たちが軽口を叩きながらストレッチを始める中、彼の視線はただ一点──相手ベンチのマウンド方向に向けられている。
風祭球児。
“あいつ”がいる。それだけで、川島の呼吸は微かに乱れる。
「……なんで、あいつなんだよ」
つぶやきは声に出たのか、それとも胸の内だけだったのか。
ただ、その言葉は、まるでずっと胸に刺さっていた小骨のように喉奥から出た。
あれは、一年前のことだった。
風祭が二年生に上がった春、突如としてその才能は花開いた。
まっすぐ、そしてフォーク。剛と柔を併せ持つ投球に、周囲の注目は一気にそちらへ傾いた。
それまでは自分が“東都学院のエース”と呼ばれるはずだった。
努力してきた。練習量も、体づくりも、誰にも負けていなかったはずだ。
でも──
「……全部、もっていきやがった」
スカウトの視線。監督の声かけ。部内での空気。
川島は風祭がロッカーを開けるたび、何度も物がなくなっていることを知っていた。
知っていて、誰にも言わなかった。
いや、それだけじゃない。ロッカーに挟まれていた無記名のメモのうち、何枚かは──自分の手で書いた。
『お前なんて、誰も応援してねえよ』
『さっさと辞めろ。裏切り者』
今思えば、卑劣だった。陰湿だった。
でも、その時の自分には、それが“当然の防衛手段”だった。
「アイツがいたら、俺はエースになれなかった」
川島は、ふと自分の右手首を見る。
そのリストバンドの内側──誰にも見せない、黒ペンの細い文字。
『風祭を抑える。それで、俺の野球が正しかったと証明する』
震えるほどの執着だった。
正直、今日のこの舞台に立つまで、ずっとそれだけを目標にしていたと言っても過言ではない。
東都学院の名を背負うこと。
甲子園を目指すこと。
それ以上に、自分にとっては──
“あいつに勝つ”ことが、すべてだった。
川島は深く息を吐き、スタンドから聞こえてくるざわめきを背に、ゆっくりとマウンドに歩み出した。
試合は始まる。
野球ではなく、過去と現在、すべてを懸けた“決着”が──。
■
「気にすんな。今日のお前は、誰のためでもなく、自分のために投げろ」
球児はうなずき、投げた。
インハイ、力のあるストレート。
打者のバットが空を切る──三振!
「チェンジッ!」
歓声が沸き起こるベンチ。だが球児は、ただ静かに帽子を取った。
背中には、背番号“1”。
それを見つめる三島は、小さく笑って呟く。
「……やっぱ、乗っかって正解だわ」
戦いは、いま始まったばかりだった──。
■
決勝戦当日の朝。
試合開始の数時間前、静まり返った控室の隅で、石原翔太はお馴染みの“キャッチャーノート”を開いていた。
ページの端には、いつもと変わらぬ筆跡でこう記してあった。
「一球目、インロー。迷ったら、まず基本に戻る」
インローはキャッチャーにとって、もっとも信頼できる“入り口”の球。
打者の目線を下げ、意識を絞らせ、次の配球への布石にもなる。
だからこそ、これまで何度も風祭と組んできた中で、石原は“インロー”から試合を始めることが多かった。
けれど──
今日の相手は、あの東都学院。
そして、あのマウンドに立つのは、いつもよりほんの少しだけ背筋の伸びた風祭球児。
石原は視線を上げ、スパイクの紐を結び直す風祭の姿を横目で見た。
──あいつ、顔つきが違う。
覚悟という言葉は、簡単に使いたくない。
でも今日の風祭には、あきらかに“迷い”がなかった。
そのまなざしは、まるで「お前のどんなサインでも受けてやるよ」と言っているようだった。
いや、違う。
「俺が信じてるのは、お前のサインだ」──そう言っているような、そんな目だった。
石原は、キャッチャーミットの革を静かに撫で、ノートのインローの文字に二重線を引いた。
代わりに、ノートの余白にこう記した。
「変更:一球目、外角低め。試すためじゃない。信じるから、そこに投げさせる」
そしてプレイボール。
東都学院の先頭打者がバッターボックスに立つ。
スタンドからの声援とフラッシュの海の中、石原はしゃがみ込み、構えを示す。
外角、低め。
たった一球目。
されど一球目。
ここから、全てが始まる──その重みを、ふたりは誰よりもわかっていた。
風祭の腕が振り抜かれる。
白球は弧を描き、石原のミットに“音”を刻む。
ストライク。
石原はその音を、ただ黙って受け止め、ミットを外さず小さく頷いた。
「信頼ってやつは、確認じゃなくて証明だ。
ナイスピッチ、風祭」
それは、言葉にはしなかったけれど──
風祭に向けた、最高の合図だった。
■
夏の陽射しが、球場の芝に細く揺れる。
まるで風に揺らぐ海のように、青と緑が滲むその舞台に、プレイボールのコールが響いた。
――決勝戦の空は、どこまでも高く澄んでいた。
桜が丘ナインが守備につく。
それを見送るように、ベンチの一番奥に腰を下ろしたのは、監督・風祭修司だった。
帽子のつばを指で軽く整えながら、ゆっくりと深く息を吸う。
グラウンドの土の匂い、スタンドのざわめき、そして、選手たちのスパイクが鳴らすリズム。
それらすべてが、決勝の“初回”という緊張を静かに膨らませていく。
修司の膝には、いつものベンチメモ。
端が少し擦れたそのノートに、青のボールペンで一行目が書かれた。
「決勝・初回裏 風祭、マウンド」
スコアボードに灯る「0回」の文字が、試合の幕開けを告げる。
修司の視線の先、マウンドに立つ球児は、ロージンバッグを手に取っていた。
その背中――背番号「1」――が、ひときわ大きく見えた。
キャッチャーの石原が軽くうなずく。
その瞬間、球児の右腕が振り抜かれた。
乾いたミットの音が響く。
――外角低め、ストライク。
観客のざわめきが波紋のように広がる中、修司は黙って青ペンを走らせる。
「初球、外角低めストライク。石原との呼吸、完璧。ミット音良好」
次の球は、内角ギリギリ。
バッターが一歩引き気味にバットを止めたが、判定はボール。
スタンドから小さくため息が漏れる。
それでも修司の表情は変わらない。
彼の視線は、常に“試合の流れ”を見ていた。
ふたたび構え直す石原。
三球目はフォーク。
バッターが完全に振らされて、空振り。
そして四球目。
真っ直ぐ、高めに浮いた球を叩かれるが――
「小野寺っ!」
三塁の小野寺が一直線に飛びつき、グラブの先でしっかり掴む。
すぐさま立ち上がり、一塁へ送球。
スリーアウト、チェンジ。
スタンドが湧き、ナインたちが駆け足でベンチへ戻る。
その中で、球児は帽子のつばを指先で整えながら、短く石原にうなずいた。
ベンチへ戻った球児が修司の前を通る。
その時、修司は何も言わずに、わずかに眉を上げた。
その目は、ただ“誇らしさ”を浮かべていた。
そして再び、メモを開く。
「初回ゼロ。静かな立ち上がり。球児の目が、勝ちを見据えている。
石原との信頼、ここに極まる」
「もう俺の背中を見ていない。それでいい。
今日くらいは、父親として、あいつの背中を見ていたい」
その文字は、風にめくれそうになったページの中で、じっと静かに揺れていた。
グラウンドに広がる夏の匂いが、すべてを包み込むように、ベンチにも流れ込んでいた。
試合は、まだ始まったばかりだった。
けれど――その重みを誰よりも感じていたのは、他ならぬ修司だった。
「……人、多いな」
藤木が思わず呟くと、浜中が隣で肩をすくめた。
「そりゃあ、決勝戦だもんな」
その言葉に、全員が一斉に息をのんだ。緊張は、もう始まっていた。
ロッカールームに入ると、静けさが支配した。球児は、背番号“1”のユニフォームを丁寧にたたみ、そっと両手で持ち上げる。
──ここまで来た。
思い出すのは、東都学院で背番号をもらえなかった日々。ロッカーを荒らされたこと。誰も声をかけてくれなかったあの夕方。
でも、今は違う。
球児は深く息を吸って、静かにユニフォームに袖を通した。
「おい」
三島の声が、ロッカールームを切り裂いた。
「今日だけは、全員で“あいつの背中”に乗っかろうぜ」
いつもよりも低い声だった。だが、その一言で空気が変わった。
手を重ねる輪が、自然とできる。
「……いくぞ、桜が丘──!」
「オオオオッ!」
円陣の声が、グラウンドまで響き渡った。
プレイボール前のベンチ横――
朝露がまだ完全に消えきらない芝の上で、桜が丘ナインが円陣を組む。
中心に立つのは、主将・三島大地。
その足元には、泥の跳ね跡がまだ新しいスパイク。スパイクの先が、わずかに震えていた。
「球児の背中に乗っかるぞ!」
その一言を放った瞬間、喉の奥が乾いていたことに、三島はようやく気づいた。
東都学院――かつての名門、そして球児がいた場所。
相手の圧力は、ただの実力じゃない。名前が持つ“重み”が、すでにチームを呑み込もうとしていた。
「正直、怖ぇよ……」
心の中でつぶやいた三島は、円陣の中心で小さく息を呑んだ。
でも、それを顔に出してはいけない。自分は“主将”だ。誰よりも早く声を出し、誰よりも先に前を向く役割。
「……俺が最初に声を出せば、誰かが続いてくれる。
それが“主将”だろ、三島大地」
石原がうなずき、田代が拳を高く挙げる。
円陣がほどけ、各ポジションへと散っていくナインたち。
その背を見送りながら、三島は静かに自分のスパイクを見下ろした。
――少し、泥が乾いている。
それだけで、なぜか胸がじんと熱くなった。
試合前――
スパイクの紐が、片方だけ緩んでいた。
泥に染まり、草の香りが残るそれを、ベンチで静かに結び直す。
三島はグローブを脇に置いたまま、ふっと小さく笑った。
「勝ちたいんじゃねぇんだ。……勝たせたいんだよ、あいつに」
プレイボールの合図とともに始まった決勝戦。東都学院の1番打者が打席に立つ。相手のユニフォームの胸には、あの馴染みあるロゴが刻まれていた。
風祭球児はマウンドで軽く息を吐き、初球を構える。
キャッチャー・石原が小さくうなずき、ミットを構えた。
──初球、外角低めストレート。
乾いた音とともに、打球はセカンド正面。
「ワンアウト!」
三島の声が飛ぶ。
次の打者も詰まらせて内野ゴロ、そして三番。かつてのチームメイト、川島がベンチで腕を組んで立ち上がった。
「ちっ、こっちを捨てたくせに、いい顔しやがって……」
その視線に、球児は気づいていた。だが、一瞥もせず、次の打者に集中する。
三島が小さく口を開いた。
■
東都学院ベンチの片隅。川島栄伍は誰よりも早くユニフォームに袖を通し、グラブを手にしていた。
他の選手たちが軽口を叩きながらストレッチを始める中、彼の視線はただ一点──相手ベンチのマウンド方向に向けられている。
風祭球児。
“あいつ”がいる。それだけで、川島の呼吸は微かに乱れる。
「……なんで、あいつなんだよ」
つぶやきは声に出たのか、それとも胸の内だけだったのか。
ただ、その言葉は、まるでずっと胸に刺さっていた小骨のように喉奥から出た。
あれは、一年前のことだった。
風祭が二年生に上がった春、突如としてその才能は花開いた。
まっすぐ、そしてフォーク。剛と柔を併せ持つ投球に、周囲の注目は一気にそちらへ傾いた。
それまでは自分が“東都学院のエース”と呼ばれるはずだった。
努力してきた。練習量も、体づくりも、誰にも負けていなかったはずだ。
でも──
「……全部、もっていきやがった」
スカウトの視線。監督の声かけ。部内での空気。
川島は風祭がロッカーを開けるたび、何度も物がなくなっていることを知っていた。
知っていて、誰にも言わなかった。
いや、それだけじゃない。ロッカーに挟まれていた無記名のメモのうち、何枚かは──自分の手で書いた。
『お前なんて、誰も応援してねえよ』
『さっさと辞めろ。裏切り者』
今思えば、卑劣だった。陰湿だった。
でも、その時の自分には、それが“当然の防衛手段”だった。
「アイツがいたら、俺はエースになれなかった」
川島は、ふと自分の右手首を見る。
そのリストバンドの内側──誰にも見せない、黒ペンの細い文字。
『風祭を抑える。それで、俺の野球が正しかったと証明する』
震えるほどの執着だった。
正直、今日のこの舞台に立つまで、ずっとそれだけを目標にしていたと言っても過言ではない。
東都学院の名を背負うこと。
甲子園を目指すこと。
それ以上に、自分にとっては──
“あいつに勝つ”ことが、すべてだった。
川島は深く息を吐き、スタンドから聞こえてくるざわめきを背に、ゆっくりとマウンドに歩み出した。
試合は始まる。
野球ではなく、過去と現在、すべてを懸けた“決着”が──。
■
「気にすんな。今日のお前は、誰のためでもなく、自分のために投げろ」
球児はうなずき、投げた。
インハイ、力のあるストレート。
打者のバットが空を切る──三振!
「チェンジッ!」
歓声が沸き起こるベンチ。だが球児は、ただ静かに帽子を取った。
背中には、背番号“1”。
それを見つめる三島は、小さく笑って呟く。
「……やっぱ、乗っかって正解だわ」
戦いは、いま始まったばかりだった──。
■
決勝戦当日の朝。
試合開始の数時間前、静まり返った控室の隅で、石原翔太はお馴染みの“キャッチャーノート”を開いていた。
ページの端には、いつもと変わらぬ筆跡でこう記してあった。
「一球目、インロー。迷ったら、まず基本に戻る」
インローはキャッチャーにとって、もっとも信頼できる“入り口”の球。
打者の目線を下げ、意識を絞らせ、次の配球への布石にもなる。
だからこそ、これまで何度も風祭と組んできた中で、石原は“インロー”から試合を始めることが多かった。
けれど──
今日の相手は、あの東都学院。
そして、あのマウンドに立つのは、いつもよりほんの少しだけ背筋の伸びた風祭球児。
石原は視線を上げ、スパイクの紐を結び直す風祭の姿を横目で見た。
──あいつ、顔つきが違う。
覚悟という言葉は、簡単に使いたくない。
でも今日の風祭には、あきらかに“迷い”がなかった。
そのまなざしは、まるで「お前のどんなサインでも受けてやるよ」と言っているようだった。
いや、違う。
「俺が信じてるのは、お前のサインだ」──そう言っているような、そんな目だった。
石原は、キャッチャーミットの革を静かに撫で、ノートのインローの文字に二重線を引いた。
代わりに、ノートの余白にこう記した。
「変更:一球目、外角低め。試すためじゃない。信じるから、そこに投げさせる」
そしてプレイボール。
東都学院の先頭打者がバッターボックスに立つ。
スタンドからの声援とフラッシュの海の中、石原はしゃがみ込み、構えを示す。
外角、低め。
たった一球目。
されど一球目。
ここから、全てが始まる──その重みを、ふたりは誰よりもわかっていた。
風祭の腕が振り抜かれる。
白球は弧を描き、石原のミットに“音”を刻む。
ストライク。
石原はその音を、ただ黙って受け止め、ミットを外さず小さく頷いた。
「信頼ってやつは、確認じゃなくて証明だ。
ナイスピッチ、風祭」
それは、言葉にはしなかったけれど──
風祭に向けた、最高の合図だった。
■
夏の陽射しが、球場の芝に細く揺れる。
まるで風に揺らぐ海のように、青と緑が滲むその舞台に、プレイボールのコールが響いた。
――決勝戦の空は、どこまでも高く澄んでいた。
桜が丘ナインが守備につく。
それを見送るように、ベンチの一番奥に腰を下ろしたのは、監督・風祭修司だった。
帽子のつばを指で軽く整えながら、ゆっくりと深く息を吸う。
グラウンドの土の匂い、スタンドのざわめき、そして、選手たちのスパイクが鳴らすリズム。
それらすべてが、決勝の“初回”という緊張を静かに膨らませていく。
修司の膝には、いつものベンチメモ。
端が少し擦れたそのノートに、青のボールペンで一行目が書かれた。
「決勝・初回裏 風祭、マウンド」
スコアボードに灯る「0回」の文字が、試合の幕開けを告げる。
修司の視線の先、マウンドに立つ球児は、ロージンバッグを手に取っていた。
その背中――背番号「1」――が、ひときわ大きく見えた。
キャッチャーの石原が軽くうなずく。
その瞬間、球児の右腕が振り抜かれた。
乾いたミットの音が響く。
――外角低め、ストライク。
観客のざわめきが波紋のように広がる中、修司は黙って青ペンを走らせる。
「初球、外角低めストライク。石原との呼吸、完璧。ミット音良好」
次の球は、内角ギリギリ。
バッターが一歩引き気味にバットを止めたが、判定はボール。
スタンドから小さくため息が漏れる。
それでも修司の表情は変わらない。
彼の視線は、常に“試合の流れ”を見ていた。
ふたたび構え直す石原。
三球目はフォーク。
バッターが完全に振らされて、空振り。
そして四球目。
真っ直ぐ、高めに浮いた球を叩かれるが――
「小野寺っ!」
三塁の小野寺が一直線に飛びつき、グラブの先でしっかり掴む。
すぐさま立ち上がり、一塁へ送球。
スリーアウト、チェンジ。
スタンドが湧き、ナインたちが駆け足でベンチへ戻る。
その中で、球児は帽子のつばを指先で整えながら、短く石原にうなずいた。
ベンチへ戻った球児が修司の前を通る。
その時、修司は何も言わずに、わずかに眉を上げた。
その目は、ただ“誇らしさ”を浮かべていた。
そして再び、メモを開く。
「初回ゼロ。静かな立ち上がり。球児の目が、勝ちを見据えている。
石原との信頼、ここに極まる」
「もう俺の背中を見ていない。それでいい。
今日くらいは、父親として、あいつの背中を見ていたい」
その文字は、風にめくれそうになったページの中で、じっと静かに揺れていた。
グラウンドに広がる夏の匂いが、すべてを包み込むように、ベンチにも流れ込んでいた。
試合は、まだ始まったばかりだった。
けれど――その重みを誰よりも感じていたのは、他ならぬ修司だった。
0
あなたにおすすめの小説

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

【完結済】25億で極道に売られた女。姐になります!
satomi
恋愛
昼夜問わずに働く18才の主人公南ユキ。
働けども働けどもその収入は両親に搾取されるだけ…。睡眠時間だって2時間程度しかないのに、それでもまだ働き口を増やせと言う両親。
早朝のバイトで頭は朦朧としていたけれど、そんな時にうちにやってきたのは白虎商事CEOの白川大雄さん。ポーンっと25億で私を買っていった。
そんな大雄さん、白虎商事のCEOとは別に白虎組組長の顔を持っていて、私に『姐』になれとのこと。
大丈夫なのかなぁ?

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

【完結】イケメンが邪魔して本命に告白できません
竹柏凪紗
青春
高校の入学式、芸能コースに通うアイドルでイケメンの如月風磨が普通科で目立たない最上碧衣の教室にやってきた。女子たちがキャーキャー騒ぐなか、風磨は碧衣の肩を抱き寄せ「お前、今日から俺の女な」と宣言する。その真意とウソつきたちによって複雑になっていく2人の結末とは──
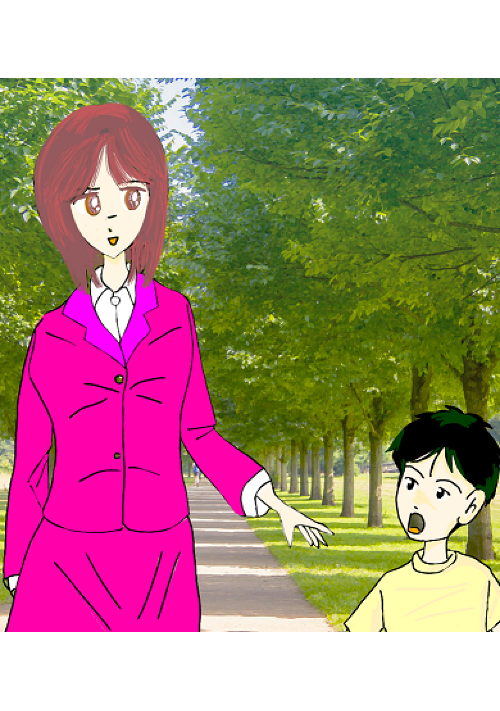
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















