32 / 35
第32話 :『一瞬と、永遠と』
しおりを挟む
午後の日差しが、白く乾いたグラウンドに斜めに差し込んでいた。アルプス席にはためく応援旗の布地が、風に打たれながら鈍く翻る。汗の匂いと、土の熱気が混ざりあい、球場全体に夏の重さが積もっている。
スコアボードに並ぶ数字は、わずかに動いたまま、静止していた。六回表。両チーム、点差はたったの「1」。そのたったひとつが、全員の呼吸を縛っていた。
マウンド上。風祭球児は、つま先の位置を何度も確かめながらプレートを踏みしめた。額に浮かぶ汗はもう、拭っても拭っても止まらない。キャッチャーミットの構えが、一呼吸遅れて浮かぶ。観客の拍手が一瞬だけやんだ。
――ボールが放たれる。
キュ、と切るような音を残してストレートがミットに突き刺さる。その瞬間だけ、球場の空気が収縮したように静まりかえった。次の瞬間、内野の土が跳ね、サードが一歩前に出る。スイング――ミス――ファウルボール。
高く上がった白球がバックネットへ落ちていくまで、誰も言葉を発しない。スパイクが土を蹴る音だけが、ぽつり、ぽつりと響く。
ベンチでは、マネージャーの千紗が手帳を両手で握りしめ、祈るように目を伏せていた。その隣、スコアブックをつける飯塚のペンが、乾いた音を立てながら欄外を少しだけ削る。
打者が構え直す。バッテリーはサインを交わす。ほんの、まばたき一つぶんの静寂ののち、二球目が投げられる。
打球は、センター前へのライナー。三島のスパイクが、乾いた音を鳴らしながら一歩目を刻む。風を割って、その背中が伸びる。芝の端に差し掛かったところで、三島の両足が宙を切る。グラブを伸ばす――。
ボールが革に収まる「ぱすっ」という音。
静寂と歓声が同時に弾ける。外野スタンドが波のように揺れる。三島が仰向けに倒れたまま、グラブを天に掲げる。ベンチから誰かが駆け出した。砂埃が舞い、背中に土が貼りつく。グラウンドの真ん中で、守りきった男が、しばらく動かなかった。
空は少しずつオレンジを帯びはじめ、スタンドに長く影が差していた。
「ここで踏ん張れ……ここを越えたら、流れはうちのもんだ」
三塁側ベンチで、修司が低くつぶやいた。
その言葉に、誰も返事はしない。ただ全員が、じっとグラウンドを見つめていた。
マウンドには、風祭球児。
帽子のつばを握りしめ、深く息を吐く。
スタンドからは「フレー! フレー!」と応援が響いていたが、球児の耳には届いていない。
聞こえるのは、自分の心音と……キャッチャーミットを叩く、石原のグラブの音だけだった。
「バッター、四番、サード──神野くん!」
瑞陵学園の四番。春の大会では二本塁打を放った強打者。
東都学院ではなく、こちらが王者のような風格を漂わせていた。
「初球、どうする?」
石原がマスク越しに囁く。小さく指を立てて、内角低めを示す。
球児は頷かない。ただ一瞬だけ目を伏せ、それから──ふっと口角を上げた。
投げた。
低く、ギリギリを突いたスライダー。
「ストライクッ!」
球審の声と同時に、観客席が沸く。
「ナイスボール!」
すかさず、三島の声がセンターから飛んできた。
球児はそれに背中で応えるように、マウンドの土をならした。
二球目、三球目。
外角のストレート、そしてカウントを整えるカーブ。
神野の表情に焦りは見えない。だが、バットのヘッドが少しだけ前に傾いた。
「ラストは……お前の一番信じてる球でいこう」
石原がミットを構える。外角低め、沈むフォーク。
球児の指先から、風のように滑り落ちるような軌道で、ボールが吸い込まれていく──
バットは、空を切った。
「スリーアウトッ!」
スタンドが沸き上がる。千紗がベンチで、ぎゅっとメモ帳を胸に抱えたまま小さく跳ねた。
「よっしゃああああ!」
小野寺がガッツポーズで飛び出し、浜中が手を叩いて叫ぶ。
だが、球児は何も言わない。
ただ、石原と目が合った瞬間、微笑むだけだった。
六回裏、桜が丘の攻撃。
先頭打者は三島。川島の投球に対し、冷静にボールを見極めていく。
「……三島、何か変わったな」
千紗がぽつりと呟いた。
「うん。あいつ、昔は“振りたいから振る”って感じだったけど……今日は“勝ちたいから選ぶ”って顔してる」
隣の飯塚が静かに答えた。
カウント2-2。川島が投じたスライダーを、三島はギリギリで見送った。
球審の右手は……動かない。
「フルカウント!」
三島は小さく頷き、胸を張る。そして、次の球──
快音。センター前へのクリーンヒット。
「ナイスバッティン、キャプテン!」
ベンチの声に、三島は少しだけ照れくさそうに手を上げて応えた。
続くバッターは小野寺。
強振した打球は左中間を破り、三島が一気に三塁へ──
だがここで、東都学院の鉄壁の守備が本領を見せる。
見事な中継プレーで、三島は本塁タッチアウト。
「ちっ……完璧な中継だったな」
ベンチに戻った三島が悔しげにヘルメットを取る。
「でも、ナイスランだよ。あの一歩目、俺には真似できない」
石原が笑って肩を叩いた。
「へへ……背中に、みんな乗ってるからな」
そう言った三島の笑顔には、悔しさと誇りがにじんでいた。
回は七回に入り、スコアは0-1。
試合は後半戦、緊張の糸がさらに強く張りつめていく。
球児は帽子のつばを深くかぶり、再びマウンドへと歩き出す。
「さあ……ここからだな」
ベンチで修司がつぶやいたその声は、まるで静かな決意のようだった。
■
ベンチの木製の長椅子は、夏の熱でほんのりと温かい。そこに座る千紗の膝の上、開かれたノートが、かすかに震えていた。ページの端を、わずかな風が揺らす。
試合は六回の表。スコアボードには、「1-0」。試合開始から動いた点は一つだけ。それが、全員の呼吸をしんと締めつけていた。
千紗はベンチの端に座り、サブノートとペンを持ったまま、まばたきの間に投げ込まれる一球一球を見つめていた。ミットに収まる音が、硬く、澄んで聞こえる。キャッチャーの石原が構えたミットに向かって、風祭球児のフォームが、ゆるやかに、それでいて確かな速さで展開される。
打者がファウルを打ち上げる。白球が高く上がり、スピンをまとったままバックネットの上空をかすめる。ベンチにいる全員が、無言でそれを見送る。ペンの先が、千紗の指の中で止まっていた。
次の一球で、球児は僅かな首の角度で何かを伝えた。石原のサインに頷く。それだけで、ベンチの空気がピリつく。
打者のスイング。打球はセンター方向、低い弾道。走る気配と、芝を蹴るスパイクの音が重なり合う。ベンチから見える視界の先、三島の背中が土を蹴って伸びる。
グラブが宙を切った。ボールが吸い込まれるように収まる。
千紗は目を見開いたまま、息を止めていた。ベンチ内に、一瞬の静寂。そしてすぐに、それを破るように立ち上がる声と拍手。キャッチャーの石原がマスクを脱ぎ、ベンチに走って戻ってきた。
その脇で、飯塚が小さくペンを動かし、スコアブックの“失点”欄をそのままにしている。欄の横に、ひとつだけ細く印が残る。
六回裏の攻撃。千紗はノートをそっと閉じた。風祭がヘルメットを被って素振りをしている姿が視界の先に映る。練習用バットの金属音が、地面に跳ね返るように響く。
球場の空が、ほんのりと赤く染まりはじめる。バックネットの影が長く伸びていく。カメラマンが三塁側スタンドに駆けていく。決勝戦――その響きだけが、試合の空気を重く、鋭く、震わせていた。
風祭が打席へと向かう。ヘルメットの後ろに差す夕日が、影を伸ばしていく。マウンド上の川島は、汗をぬぐい、舌打ちのような仕草をひとつだけして、ボールを持ち直す。
千紗は、静かにベンチの中で立ち上がった。声を出すわけでも、叫ぶわけでもなく。ただ両手を胸の前で組んで、まっすぐに風祭の背中を見つめていた。
その背中が、まっすぐ立っていた。どこか遠くから、風の音がかすかに聞こえた気がした。
■
夕暮れの風が、部室のカーテンをふわりと揺らした。
今日の夕焼けは、ちょっとだけ柔らかい色をしてる。
まるで、誰かが空のパレットに“安心”って色を足してくれたみたいだ──そんなことを思いながら、私は静かにノートを開いた。
――風祭くん、今日もマウンドに立ってた。
六回を終えて戻ってきた時、彼はいつもよりゆっくりとベンチに腰を下ろした。
少しだけ、肩が落ちていたのは疲れ? それとも、何かを乗り越えた証拠?
私は、そっと差し入れの麦茶を渡した。
彼は一言も言わずに受け取って、それから――
ほんの一瞬、私の目を見て、ふわっと笑った。
声には出さなかったけど、たぶんあれは「ありがとう」だったんだと思う。
今日の観察記録:
・七回表、投げる前に一度だけ空を見上げていた。風が止まってた。
・ピンチの場面で、石原くんと何か言葉を交わしてた。あれ、たぶん「任せた」って声。
・試合後、帽子を胸にあてる仕草が、どこか誇らしげだった。
でも――
・今日いちばんすごかったのは、風祭くんの背中じゃなくて、
それを支えてた“チームのみんなの声”だったかもしれない。
“風祭くんは、エースでヒーローで、でもちょっと不器用で”
“それでも、ちゃんと誰かを信じてる。信じさせてくれる”
“私は、そんな彼のことを、やっぱり好きだなって思った”
ノートの最後に、小さく書き足した。
「今日の風祭くん:ちょっとだけ笑った。その笑顔、たぶん……好きになった日の顔だった」
ページを閉じる頃、空は群青色に変わりかけていた。
だけど心は、今日もちゃんと、あたたかいまま。
■
ペン先が紙を走る音だけが、飯塚の世界だった。
七回表、二死走者なし。
スコアブックの罫線の上を、青のボールペンがなぞる。四球、犠打、盗塁──いくつもの試合の風景が、たった一冊のノートの上で再構築されていく。
「0」の列が続く。
でもそれは、ただの数字じゃない。打たせて取った一球。間一髪のダイブ。振り遅れたバット。それぞれに、鼓動があった。
飯塚は静かに視線を上げる。グラウンドの奥、マウンド上に立つ風祭球児の背中が、やや右肩を下げたまま止まっていた。キャッチャー石原のミットが構えられ、空気が張り詰める。
──ストライク。
審判の声が上がる前に、飯塚はそれを知っていた。球児の球筋を、何度も記してきた手応え。音。リズム。フォームの角度。
だが今日の試合は、何かが違っていた。
「全員で守ってる」──そう思ったのは、三回表の小野寺の三遊間へのダイブのときだ。打球が抜けると誰もが思った瞬間、土煙とともにグラブが地面を叩いた。ベンチにいた千紗が、思わずノートを落としたのを、飯塚は見ていた。
あれは、“叫び”だった。無音のなかの。
飯塚はスコアブックの余白をめくる。空白のページの右下に、こう書き込んだ。
>「守ってる。守られてる。その中心に、風祭球児がいる。」
彼はスコアを「記す」人間だ。点が入れば「1」、無失点なら「0」。打者は「三振」か「内野ゴロ」か。数字でしか残らないものばかりだ。
でも、記せないものがあった。
スパイクの音。手の震え。唇をかんだ三島の横顔。
千紗のノートのページを握る手。石原のミットの音。
そして、風祭の投げ終えたあと、静かに一歩だけ下がる癖。
飯塚はもう一度、ペンをとった。スコアとは関係のない欄に、余白を縫うようにして書き加える。
「この試合、ずっと黙って見てたけど……俺、今なら叫べるかもしれない」
ふ、と微笑んだ。誰にも聞こえない。聞かせるつもりもない。
けれどそれでも、余白は知っている。
このスコアブックは、数字じゃなく、誰かの想いで埋まっていくことを。
そのページの端が、少しだけ汗でふやけていた。
■
午後の陽が、三塁側ベンチの背中をあたためていた。
試合は緊迫の終盤へ。
スコアブックには、すでに汗染みが滲んでいる。
誰が書いたでもない、鉛筆の圧が違うページ。
たぶん、あいつがマウンドに立ったイニングだったんだろうな、と修司は思った。
静まり返るスタンドの向こう、
夕陽を浴びながら、ひとりマウンドに立つ背中が見える。
その背中を、何度見てきたか。
けれど、いまだに言葉にならない気持ちがある。
スコアブックの余白に、小さく書き足す。
「光の中にいるようで、あいつはいつも影を背負ってる」
「それでも、前を向くのは、きっと誰かの声があったからだ」
修司には、あの子の“変わった日”が分かっていた。
東都学院をやめて、肩を落として家に戻ってきたあの日。
玄関のドアが開いて、うつむいたまま靴を脱いだ彼に、
「おかえり」と言ってくれたのは、きっと球児の母親だった。
今は亡き母の声。
その声のあと、球児はなぜか、
少しだけ背筋を伸ばして、飯を食べた。
黙ったままだったけど、“また始めるんだろうな”と、そう思えた。
監督じゃなく、父としての直感だった。
東都学院に入部して、最初の月。
球児は、まだ校内のルールも、寮の部屋の空気も読みきれていなかった。
周囲の同期たちが笑いあいながら入浴の順番をじゃんけんで決めていた夜。
彼はひとり、スマホを握りしめて、グラウンドの片隅に立っていた。
電話が、鳴らなかったのだ。
病室のベッドに伏せていた母・涼子が、最後に球児と話したのは、ちょうど一週間前だった。
「元気でやってる?……あんまり張りつめすぎないでね」
そのときの声は、思っていたより弱くて。
でも、どこか優しくて──
“自分が死ぬことをもう分かってた”と、あとになって気づいた。
東都のグラウンドの片隅に座り込んでいた彼に、
監督が呼びに来たのは翌朝だった。
「……家に帰りなさい。今日が、山場だって、お父さんから連絡が来た」
荷物も持たず、スパイクのまま、彼は寮を出た。
駅までの道で、電話が鳴った。
表示されたのは、父さんの名。
出る前に、なんとなく分かった。
告別式の場で、球児は一言も泣かなかった。
というより、泣けなかった。
「もっと会いに行けばよかった」「あんな言い方をしなければよかった」
そんな後悔の粒が、胸の中で音もなく降り積もっていた。
帰宅後、机の引き出しに一冊だけあった、母のノート。
それは、病気が発覚してからの「自分用の日記」だった。
──六月二日
球児、入寮。すこし不安そうだったけど、笑って手を振ってくれた。
──六月十三日
練習きついって言ってた。でも、電話の向こうで声が大きくなってる。少し安心。
──六月十八日
熱がある。先生は無理しないでって。でも、あの子のためにまだ頑張りたい。
──六月二十二日(最後のページ)
もうすぐ、きっと見送ることになる。
球児、ごめんね。大好きだよ。
あなたは、ちゃんと前を向ける子だから。
その日から、球児は“誰にも何も言わない子”になった。
感情を見せるより、黙って投げる方を選んだ。
褒められても、怒鳴られても、まぶしいライトの中でも、
グラウンドに立つとき、彼はどこか遠くを見ていた。
──母が最後まで見ようとした、その“前”を。
今、桜が丘で背番号1を背負う球児は、
誰にもそれを語らない。
でも、スパイクの紐を結ぶとき、
胸ポケットに忍ばせているのは──母の遺した、最後の手紙だった。
手紙は、白い封筒に入っていた。
リビングの棚の引き出しの奥。
母が最後に自分で片づけた場所だった。
表に書かれていたのは、ただひとこと──
「球児へ」
それを見つけたのは、葬儀の翌日。
父のいない朝。
ひとりキッチンで水を飲んだあと、ふと手が伸びた。
――中身の全文(母・涼子の手書き文字)
球児へ
この手紙を読む頃、私はもうそばにいないかもしれません。
でも、それでいいと思っています。
あなたは、ちゃんと立てる子だから。
あなたが生まれたとき、最初に泣いたのは私でした。
声が小さくて、心配して、でもちゃんと目を開けてた。
「この子は、言葉じゃなくて目で話す子だな」と、すぐに思ったのを覚えています。
それは今も変わらないね。
言わなくても、分かるって思ってる。
本当は、もっと頼ってほしいなって思うときもあったけど……
野球を続けると決めたとき、私、すごく嬉しかったのよ。
ボールを握るときのあなたの顔が、昔から大好きだった。
練習で疲れても、笑って帰ってくると、心が軽くなりました。
あの笑顔、ちゃんと誰かの力になるって、信じてます。
人を疑うより、信じることを選べる人になってください。
傷つくこともあるけれど、それでも真っ直ぐでいてください。
泣きたい日は、こっそり泣いていいんだよ。
強くなるって、泣かないことじゃない。
立ち上がることだから。
もし、いつか本当に苦しくなったら、この手紙を読んでください。
そして思い出してください。
あなたは、世界でたったひとりの「風祭球児」です。
それだけで、十分誇らしい存在です。
どんな道を選んでも、あなたのことを、ずっと見守っています。
最後に。
あなたが生まれてくれて、本当に良かった。
心から、ありがとう。
おかあさんより
その手紙を、球児は今も持ち歩いている。
背番号1のユニフォームの下、胸元の内ポケット。
折り目は、何度も開かれた証拠のように、すっかり柔らかくなっていた。
彼がマウンドに立つとき、
投げる一球一球にこもる“強さ”の理由。
それは技術でも、根性でもない。
たった一通の、
「あなたでいてくれて、ありがとう」と綴られた──手紙だった。
グラウンドに目を戻す。
球児が、石原にサインを出されたあと、軽くうなずいた。
「このやろう……」
口に出したら照れくさくて、
でもそれ以上に誇らしくて。
背番号1のその姿が、もう“子ども”ではないことを思い知る。
ふと、手のひらに握っていた帽子が、少しくしゃっとしていた。
修司は苦笑いしながら、それを丁寧に膝に置き、深く息を吸い込む。
ベンチには影が差しているけれど、
その向こうに立っている球児の背中は、まぎれもなく光の中にいた。
もう、父の背中を追っているわけじゃない。
今は、誰かの声を背負って立っている。
それで、いい。
最後に一行、ベンチメモに書き足す。
「“風祭球児”という名前の選手がいる限り、このチームは、まだ大丈夫だ」
帽子をかぶり直した修司の視線は、静かにマウンドを見据えていた。
スコアボードに並ぶ数字は、わずかに動いたまま、静止していた。六回表。両チーム、点差はたったの「1」。そのたったひとつが、全員の呼吸を縛っていた。
マウンド上。風祭球児は、つま先の位置を何度も確かめながらプレートを踏みしめた。額に浮かぶ汗はもう、拭っても拭っても止まらない。キャッチャーミットの構えが、一呼吸遅れて浮かぶ。観客の拍手が一瞬だけやんだ。
――ボールが放たれる。
キュ、と切るような音を残してストレートがミットに突き刺さる。その瞬間だけ、球場の空気が収縮したように静まりかえった。次の瞬間、内野の土が跳ね、サードが一歩前に出る。スイング――ミス――ファウルボール。
高く上がった白球がバックネットへ落ちていくまで、誰も言葉を発しない。スパイクが土を蹴る音だけが、ぽつり、ぽつりと響く。
ベンチでは、マネージャーの千紗が手帳を両手で握りしめ、祈るように目を伏せていた。その隣、スコアブックをつける飯塚のペンが、乾いた音を立てながら欄外を少しだけ削る。
打者が構え直す。バッテリーはサインを交わす。ほんの、まばたき一つぶんの静寂ののち、二球目が投げられる。
打球は、センター前へのライナー。三島のスパイクが、乾いた音を鳴らしながら一歩目を刻む。風を割って、その背中が伸びる。芝の端に差し掛かったところで、三島の両足が宙を切る。グラブを伸ばす――。
ボールが革に収まる「ぱすっ」という音。
静寂と歓声が同時に弾ける。外野スタンドが波のように揺れる。三島が仰向けに倒れたまま、グラブを天に掲げる。ベンチから誰かが駆け出した。砂埃が舞い、背中に土が貼りつく。グラウンドの真ん中で、守りきった男が、しばらく動かなかった。
空は少しずつオレンジを帯びはじめ、スタンドに長く影が差していた。
「ここで踏ん張れ……ここを越えたら、流れはうちのもんだ」
三塁側ベンチで、修司が低くつぶやいた。
その言葉に、誰も返事はしない。ただ全員が、じっとグラウンドを見つめていた。
マウンドには、風祭球児。
帽子のつばを握りしめ、深く息を吐く。
スタンドからは「フレー! フレー!」と応援が響いていたが、球児の耳には届いていない。
聞こえるのは、自分の心音と……キャッチャーミットを叩く、石原のグラブの音だけだった。
「バッター、四番、サード──神野くん!」
瑞陵学園の四番。春の大会では二本塁打を放った強打者。
東都学院ではなく、こちらが王者のような風格を漂わせていた。
「初球、どうする?」
石原がマスク越しに囁く。小さく指を立てて、内角低めを示す。
球児は頷かない。ただ一瞬だけ目を伏せ、それから──ふっと口角を上げた。
投げた。
低く、ギリギリを突いたスライダー。
「ストライクッ!」
球審の声と同時に、観客席が沸く。
「ナイスボール!」
すかさず、三島の声がセンターから飛んできた。
球児はそれに背中で応えるように、マウンドの土をならした。
二球目、三球目。
外角のストレート、そしてカウントを整えるカーブ。
神野の表情に焦りは見えない。だが、バットのヘッドが少しだけ前に傾いた。
「ラストは……お前の一番信じてる球でいこう」
石原がミットを構える。外角低め、沈むフォーク。
球児の指先から、風のように滑り落ちるような軌道で、ボールが吸い込まれていく──
バットは、空を切った。
「スリーアウトッ!」
スタンドが沸き上がる。千紗がベンチで、ぎゅっとメモ帳を胸に抱えたまま小さく跳ねた。
「よっしゃああああ!」
小野寺がガッツポーズで飛び出し、浜中が手を叩いて叫ぶ。
だが、球児は何も言わない。
ただ、石原と目が合った瞬間、微笑むだけだった。
六回裏、桜が丘の攻撃。
先頭打者は三島。川島の投球に対し、冷静にボールを見極めていく。
「……三島、何か変わったな」
千紗がぽつりと呟いた。
「うん。あいつ、昔は“振りたいから振る”って感じだったけど……今日は“勝ちたいから選ぶ”って顔してる」
隣の飯塚が静かに答えた。
カウント2-2。川島が投じたスライダーを、三島はギリギリで見送った。
球審の右手は……動かない。
「フルカウント!」
三島は小さく頷き、胸を張る。そして、次の球──
快音。センター前へのクリーンヒット。
「ナイスバッティン、キャプテン!」
ベンチの声に、三島は少しだけ照れくさそうに手を上げて応えた。
続くバッターは小野寺。
強振した打球は左中間を破り、三島が一気に三塁へ──
だがここで、東都学院の鉄壁の守備が本領を見せる。
見事な中継プレーで、三島は本塁タッチアウト。
「ちっ……完璧な中継だったな」
ベンチに戻った三島が悔しげにヘルメットを取る。
「でも、ナイスランだよ。あの一歩目、俺には真似できない」
石原が笑って肩を叩いた。
「へへ……背中に、みんな乗ってるからな」
そう言った三島の笑顔には、悔しさと誇りがにじんでいた。
回は七回に入り、スコアは0-1。
試合は後半戦、緊張の糸がさらに強く張りつめていく。
球児は帽子のつばを深くかぶり、再びマウンドへと歩き出す。
「さあ……ここからだな」
ベンチで修司がつぶやいたその声は、まるで静かな決意のようだった。
■
ベンチの木製の長椅子は、夏の熱でほんのりと温かい。そこに座る千紗の膝の上、開かれたノートが、かすかに震えていた。ページの端を、わずかな風が揺らす。
試合は六回の表。スコアボードには、「1-0」。試合開始から動いた点は一つだけ。それが、全員の呼吸をしんと締めつけていた。
千紗はベンチの端に座り、サブノートとペンを持ったまま、まばたきの間に投げ込まれる一球一球を見つめていた。ミットに収まる音が、硬く、澄んで聞こえる。キャッチャーの石原が構えたミットに向かって、風祭球児のフォームが、ゆるやかに、それでいて確かな速さで展開される。
打者がファウルを打ち上げる。白球が高く上がり、スピンをまとったままバックネットの上空をかすめる。ベンチにいる全員が、無言でそれを見送る。ペンの先が、千紗の指の中で止まっていた。
次の一球で、球児は僅かな首の角度で何かを伝えた。石原のサインに頷く。それだけで、ベンチの空気がピリつく。
打者のスイング。打球はセンター方向、低い弾道。走る気配と、芝を蹴るスパイクの音が重なり合う。ベンチから見える視界の先、三島の背中が土を蹴って伸びる。
グラブが宙を切った。ボールが吸い込まれるように収まる。
千紗は目を見開いたまま、息を止めていた。ベンチ内に、一瞬の静寂。そしてすぐに、それを破るように立ち上がる声と拍手。キャッチャーの石原がマスクを脱ぎ、ベンチに走って戻ってきた。
その脇で、飯塚が小さくペンを動かし、スコアブックの“失点”欄をそのままにしている。欄の横に、ひとつだけ細く印が残る。
六回裏の攻撃。千紗はノートをそっと閉じた。風祭がヘルメットを被って素振りをしている姿が視界の先に映る。練習用バットの金属音が、地面に跳ね返るように響く。
球場の空が、ほんのりと赤く染まりはじめる。バックネットの影が長く伸びていく。カメラマンが三塁側スタンドに駆けていく。決勝戦――その響きだけが、試合の空気を重く、鋭く、震わせていた。
風祭が打席へと向かう。ヘルメットの後ろに差す夕日が、影を伸ばしていく。マウンド上の川島は、汗をぬぐい、舌打ちのような仕草をひとつだけして、ボールを持ち直す。
千紗は、静かにベンチの中で立ち上がった。声を出すわけでも、叫ぶわけでもなく。ただ両手を胸の前で組んで、まっすぐに風祭の背中を見つめていた。
その背中が、まっすぐ立っていた。どこか遠くから、風の音がかすかに聞こえた気がした。
■
夕暮れの風が、部室のカーテンをふわりと揺らした。
今日の夕焼けは、ちょっとだけ柔らかい色をしてる。
まるで、誰かが空のパレットに“安心”って色を足してくれたみたいだ──そんなことを思いながら、私は静かにノートを開いた。
――風祭くん、今日もマウンドに立ってた。
六回を終えて戻ってきた時、彼はいつもよりゆっくりとベンチに腰を下ろした。
少しだけ、肩が落ちていたのは疲れ? それとも、何かを乗り越えた証拠?
私は、そっと差し入れの麦茶を渡した。
彼は一言も言わずに受け取って、それから――
ほんの一瞬、私の目を見て、ふわっと笑った。
声には出さなかったけど、たぶんあれは「ありがとう」だったんだと思う。
今日の観察記録:
・七回表、投げる前に一度だけ空を見上げていた。風が止まってた。
・ピンチの場面で、石原くんと何か言葉を交わしてた。あれ、たぶん「任せた」って声。
・試合後、帽子を胸にあてる仕草が、どこか誇らしげだった。
でも――
・今日いちばんすごかったのは、風祭くんの背中じゃなくて、
それを支えてた“チームのみんなの声”だったかもしれない。
“風祭くんは、エースでヒーローで、でもちょっと不器用で”
“それでも、ちゃんと誰かを信じてる。信じさせてくれる”
“私は、そんな彼のことを、やっぱり好きだなって思った”
ノートの最後に、小さく書き足した。
「今日の風祭くん:ちょっとだけ笑った。その笑顔、たぶん……好きになった日の顔だった」
ページを閉じる頃、空は群青色に変わりかけていた。
だけど心は、今日もちゃんと、あたたかいまま。
■
ペン先が紙を走る音だけが、飯塚の世界だった。
七回表、二死走者なし。
スコアブックの罫線の上を、青のボールペンがなぞる。四球、犠打、盗塁──いくつもの試合の風景が、たった一冊のノートの上で再構築されていく。
「0」の列が続く。
でもそれは、ただの数字じゃない。打たせて取った一球。間一髪のダイブ。振り遅れたバット。それぞれに、鼓動があった。
飯塚は静かに視線を上げる。グラウンドの奥、マウンド上に立つ風祭球児の背中が、やや右肩を下げたまま止まっていた。キャッチャー石原のミットが構えられ、空気が張り詰める。
──ストライク。
審判の声が上がる前に、飯塚はそれを知っていた。球児の球筋を、何度も記してきた手応え。音。リズム。フォームの角度。
だが今日の試合は、何かが違っていた。
「全員で守ってる」──そう思ったのは、三回表の小野寺の三遊間へのダイブのときだ。打球が抜けると誰もが思った瞬間、土煙とともにグラブが地面を叩いた。ベンチにいた千紗が、思わずノートを落としたのを、飯塚は見ていた。
あれは、“叫び”だった。無音のなかの。
飯塚はスコアブックの余白をめくる。空白のページの右下に、こう書き込んだ。
>「守ってる。守られてる。その中心に、風祭球児がいる。」
彼はスコアを「記す」人間だ。点が入れば「1」、無失点なら「0」。打者は「三振」か「内野ゴロ」か。数字でしか残らないものばかりだ。
でも、記せないものがあった。
スパイクの音。手の震え。唇をかんだ三島の横顔。
千紗のノートのページを握る手。石原のミットの音。
そして、風祭の投げ終えたあと、静かに一歩だけ下がる癖。
飯塚はもう一度、ペンをとった。スコアとは関係のない欄に、余白を縫うようにして書き加える。
「この試合、ずっと黙って見てたけど……俺、今なら叫べるかもしれない」
ふ、と微笑んだ。誰にも聞こえない。聞かせるつもりもない。
けれどそれでも、余白は知っている。
このスコアブックは、数字じゃなく、誰かの想いで埋まっていくことを。
そのページの端が、少しだけ汗でふやけていた。
■
午後の陽が、三塁側ベンチの背中をあたためていた。
試合は緊迫の終盤へ。
スコアブックには、すでに汗染みが滲んでいる。
誰が書いたでもない、鉛筆の圧が違うページ。
たぶん、あいつがマウンドに立ったイニングだったんだろうな、と修司は思った。
静まり返るスタンドの向こう、
夕陽を浴びながら、ひとりマウンドに立つ背中が見える。
その背中を、何度見てきたか。
けれど、いまだに言葉にならない気持ちがある。
スコアブックの余白に、小さく書き足す。
「光の中にいるようで、あいつはいつも影を背負ってる」
「それでも、前を向くのは、きっと誰かの声があったからだ」
修司には、あの子の“変わった日”が分かっていた。
東都学院をやめて、肩を落として家に戻ってきたあの日。
玄関のドアが開いて、うつむいたまま靴を脱いだ彼に、
「おかえり」と言ってくれたのは、きっと球児の母親だった。
今は亡き母の声。
その声のあと、球児はなぜか、
少しだけ背筋を伸ばして、飯を食べた。
黙ったままだったけど、“また始めるんだろうな”と、そう思えた。
監督じゃなく、父としての直感だった。
東都学院に入部して、最初の月。
球児は、まだ校内のルールも、寮の部屋の空気も読みきれていなかった。
周囲の同期たちが笑いあいながら入浴の順番をじゃんけんで決めていた夜。
彼はひとり、スマホを握りしめて、グラウンドの片隅に立っていた。
電話が、鳴らなかったのだ。
病室のベッドに伏せていた母・涼子が、最後に球児と話したのは、ちょうど一週間前だった。
「元気でやってる?……あんまり張りつめすぎないでね」
そのときの声は、思っていたより弱くて。
でも、どこか優しくて──
“自分が死ぬことをもう分かってた”と、あとになって気づいた。
東都のグラウンドの片隅に座り込んでいた彼に、
監督が呼びに来たのは翌朝だった。
「……家に帰りなさい。今日が、山場だって、お父さんから連絡が来た」
荷物も持たず、スパイクのまま、彼は寮を出た。
駅までの道で、電話が鳴った。
表示されたのは、父さんの名。
出る前に、なんとなく分かった。
告別式の場で、球児は一言も泣かなかった。
というより、泣けなかった。
「もっと会いに行けばよかった」「あんな言い方をしなければよかった」
そんな後悔の粒が、胸の中で音もなく降り積もっていた。
帰宅後、机の引き出しに一冊だけあった、母のノート。
それは、病気が発覚してからの「自分用の日記」だった。
──六月二日
球児、入寮。すこし不安そうだったけど、笑って手を振ってくれた。
──六月十三日
練習きついって言ってた。でも、電話の向こうで声が大きくなってる。少し安心。
──六月十八日
熱がある。先生は無理しないでって。でも、あの子のためにまだ頑張りたい。
──六月二十二日(最後のページ)
もうすぐ、きっと見送ることになる。
球児、ごめんね。大好きだよ。
あなたは、ちゃんと前を向ける子だから。
その日から、球児は“誰にも何も言わない子”になった。
感情を見せるより、黙って投げる方を選んだ。
褒められても、怒鳴られても、まぶしいライトの中でも、
グラウンドに立つとき、彼はどこか遠くを見ていた。
──母が最後まで見ようとした、その“前”を。
今、桜が丘で背番号1を背負う球児は、
誰にもそれを語らない。
でも、スパイクの紐を結ぶとき、
胸ポケットに忍ばせているのは──母の遺した、最後の手紙だった。
手紙は、白い封筒に入っていた。
リビングの棚の引き出しの奥。
母が最後に自分で片づけた場所だった。
表に書かれていたのは、ただひとこと──
「球児へ」
それを見つけたのは、葬儀の翌日。
父のいない朝。
ひとりキッチンで水を飲んだあと、ふと手が伸びた。
――中身の全文(母・涼子の手書き文字)
球児へ
この手紙を読む頃、私はもうそばにいないかもしれません。
でも、それでいいと思っています。
あなたは、ちゃんと立てる子だから。
あなたが生まれたとき、最初に泣いたのは私でした。
声が小さくて、心配して、でもちゃんと目を開けてた。
「この子は、言葉じゃなくて目で話す子だな」と、すぐに思ったのを覚えています。
それは今も変わらないね。
言わなくても、分かるって思ってる。
本当は、もっと頼ってほしいなって思うときもあったけど……
野球を続けると決めたとき、私、すごく嬉しかったのよ。
ボールを握るときのあなたの顔が、昔から大好きだった。
練習で疲れても、笑って帰ってくると、心が軽くなりました。
あの笑顔、ちゃんと誰かの力になるって、信じてます。
人を疑うより、信じることを選べる人になってください。
傷つくこともあるけれど、それでも真っ直ぐでいてください。
泣きたい日は、こっそり泣いていいんだよ。
強くなるって、泣かないことじゃない。
立ち上がることだから。
もし、いつか本当に苦しくなったら、この手紙を読んでください。
そして思い出してください。
あなたは、世界でたったひとりの「風祭球児」です。
それだけで、十分誇らしい存在です。
どんな道を選んでも、あなたのことを、ずっと見守っています。
最後に。
あなたが生まれてくれて、本当に良かった。
心から、ありがとう。
おかあさんより
その手紙を、球児は今も持ち歩いている。
背番号1のユニフォームの下、胸元の内ポケット。
折り目は、何度も開かれた証拠のように、すっかり柔らかくなっていた。
彼がマウンドに立つとき、
投げる一球一球にこもる“強さ”の理由。
それは技術でも、根性でもない。
たった一通の、
「あなたでいてくれて、ありがとう」と綴られた──手紙だった。
グラウンドに目を戻す。
球児が、石原にサインを出されたあと、軽くうなずいた。
「このやろう……」
口に出したら照れくさくて、
でもそれ以上に誇らしくて。
背番号1のその姿が、もう“子ども”ではないことを思い知る。
ふと、手のひらに握っていた帽子が、少しくしゃっとしていた。
修司は苦笑いしながら、それを丁寧に膝に置き、深く息を吸い込む。
ベンチには影が差しているけれど、
その向こうに立っている球児の背中は、まぎれもなく光の中にいた。
もう、父の背中を追っているわけじゃない。
今は、誰かの声を背負って立っている。
それで、いい。
最後に一行、ベンチメモに書き足す。
「“風祭球児”という名前の選手がいる限り、このチームは、まだ大丈夫だ」
帽子をかぶり直した修司の視線は、静かにマウンドを見据えていた。
0
あなたにおすすめの小説
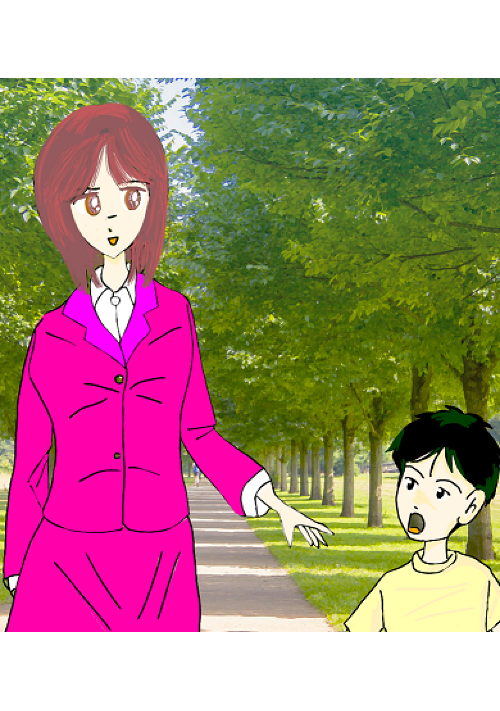
初恋の先生と結婚する為に幼稚園児からやり直すことになった俺
NOV
恋愛
俺の名前は『五十鈴 隆』 四十九歳の独身だ。
俺は最近、リストラにあい、それが理由で新たな職も探すことなく引きこもり生活が続いていた。
そんなある日、家に客が来る。
その客は喪服を着ている女性で俺の小・中学校時代の大先輩の鎌田志保さんだった。
志保さんは若い頃、幼稚園の先生をしていたんだが……
その志保さんは今から『幼稚園の先生時代』の先輩だった人の『告別式』に行くということだった。
しかし告別式に行く前にその亡くなった先輩がもしかすると俺の知っている先生かもしれないと思い俺に確認しに来たそうだ。
でも亡くなった先生の名前は『山本香織』……俺は名前を聞いても覚えていなかった。
しかし志保さんが帰り際に先輩の旧姓を言った途端、俺の身体に衝撃が走る。
旧姓「常谷香織」……
常谷……つ、つ、つねちゃん!! あの『つねちゃん』が……
亡くなった先輩、その人こそ俺が大好きだった人、一番お世話になった人、『常谷香織』先生だったのだ。
その時から俺の頭のでは『つねちゃん』との思い出が次から次へと甦ってくる。
そして俺は気付いたんだ。『つねちゃん』は俺の初恋の人なんだと……
それに気付くと同時に俺は卒園してから一度も『つねちゃん』に会っていなかったことを後悔する。
何で俺はあれだけ好きだった『つねちゃん』に会わなかったんだ!?
もし会っていたら……ずっと付き合いが続いていたら……俺がもっと大事にしていれば……俺が『つねちゃん』と結婚していたら……俺が『つねちゃん』を幸せにしてあげたかった……
あくる日、最近、頻繁に起こる頭痛に悩まされていた俺に今までで一番の激痛が起こった!!
あまりの激痛に布団に潜り込み目を閉じていたが少しずつ痛みが和らいできたので俺はゆっくり目を開けたのだが……
目を開けた瞬間、どこか懐かしい光景が目の前に現れる。
何で部屋にいるはずの俺が駅のプラットホームにいるんだ!?
母さんが俺よりも身長が高いうえに若く見えるぞ。
俺の手ってこんなにも小さかったか?
そ、それに……な、なぜ俺の目の前に……あ、あの、つねちゃんがいるんだ!?
これは夢なのか? それとも……

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話
登夢
恋愛
春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら
瀬々良木 清
ライト文芸
主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。
タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。
しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。
剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?

あるフィギュアスケーターの性事情
蔵屋
恋愛
この小説はフィクションです。
しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。
何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。
この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。
そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。
この物語はフィクションです。
実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

【完結】イケメンが邪魔して本命に告白できません
竹柏凪紗
青春
高校の入学式、芸能コースに通うアイドルでイケメンの如月風磨が普通科で目立たない最上碧衣の教室にやってきた。女子たちがキャーキャー騒ぐなか、風磨は碧衣の肩を抱き寄せ「お前、今日から俺の女な」と宣言する。その真意とウソつきたちによって複雑になっていく2人の結末とは──

美味しいコーヒーの愉しみ方 Acidity and Bitterness
碧井夢夏
ライト文芸
<第五回ライト文芸大賞 最終選考・奨励賞>
住宅街とオフィスビルが共存するとある下町にある定食屋「まなべ」。
看板娘の利津(りつ)は毎日忙しくお店を手伝っている。
最近隣にできたコーヒーショップ「The Coffee Stand Natsu」。
どうやら、店長は有名なクリエイティブ・ディレクターで、脱サラして始めたお店らしく……?
神の舌を持つ定食屋の娘×クリエイティブ界の神と呼ばれた男 2人の出会いはやがて下町を変えていく――?
定食屋とコーヒーショップ、時々美容室、を中心に繰り広げられる出会いと挫折の物語。
過激表現はありませんが、重めの過去が出ることがあります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















