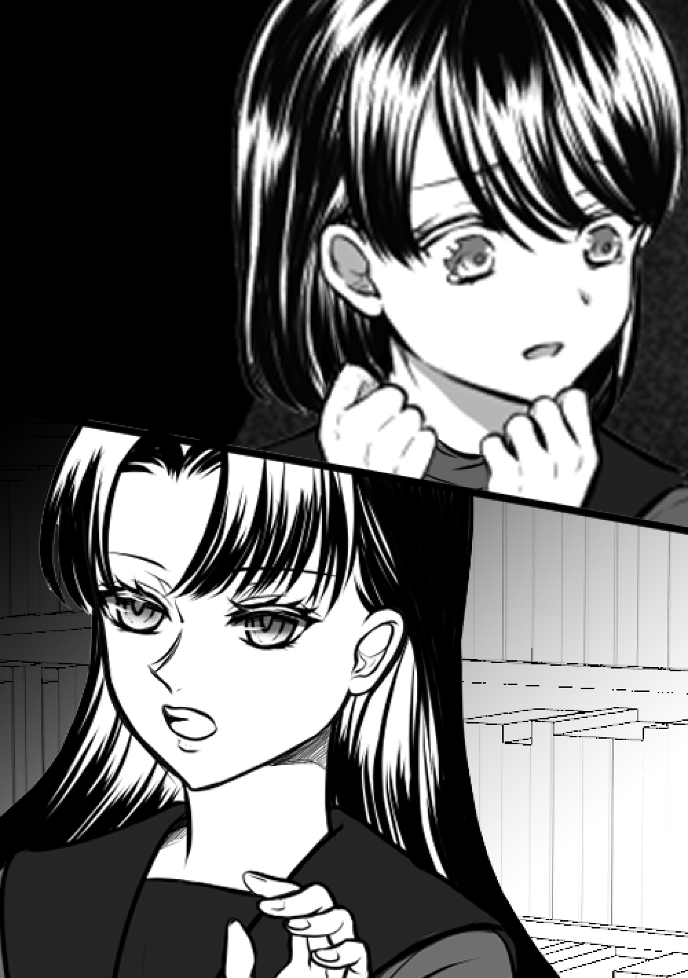1 / 30
1.島岡めぐみ
しおりを挟む
「島岡めぐみ」
死ななくてはならない――
島岡めぐみは死に場所を求め、校舎の中を彷徨っていた。
気が触れた様子も無く、一見ただ廊下を歩いているだけのようだが、内心は苛烈とまで言える自殺への思いを抱えていた。
発狂しそうな心をどうにか落ち着かせ、歩きながらも次々と、自殺できる場所を探すが、間近に迫った文化祭の準備の為だろうか、どこも人の気配がある。
階段を登り、校舎の奥へ、奥へと歩くと人の気配も薄らいでいく。廊下の角を曲がると、めぐみの視線は図書室へ向けられた。
読書を嗜まないめぐみにとって、この図書室は縁遠い場所だったが、わらにもすがる思いで図書室の扉に手をかける。鍵は閉まっていない。そっと中を覗くが誰の姿も無かった。
この時期に空き教室があるなんて、普通では考えられない事だ。そういえば、先日のHRでは図書室で文化祭の準備を禁止すると言っていた。数年前のこの時期に、この図書室で文化祭の準備をしていた生徒達が馬鹿騒ぎし、受験勉強に勤しむ生徒達から大いに顰蹙を買ったのが原因だそうだ。
季節は十月。いつまでも続くかと思っていた残暑も終わり、もうめっきり秋の空気に変わった。しかし、今のめぐみにはそんな季節の移ろいを楽しむ余裕なんて微塵も無かった。
めぐみは図書室を見回し、首を吊る事が出来そうな場所を探した。首を吊るにしても準備が必要だ。その間に誰かに見つかってしまう可能性がある。こうして、今ここに誰もいない事は奇跡に近い。いくら文化祭の準備で使用を禁止されていたとしても、ここで勉強をする生徒がいてもおかしくは無い。青葉学園の文化祭はとても盛り上がるが、中には興味の無い生徒だっているだろう。しかも今は十月。受験勉強に精を出している生徒がいてもおかしくない。しかし、今はそんな事を考えていても仕方ない。めぐみはこの幸運に感謝しながら図書室に飛び込むと、急いで中から鍵を閉めた。
久しぶりに入った図書室は独特の匂いがする。本の匂いとでも言っていいのだろうか。嗅ぎなれないが、別に嫌いな匂いではない。
めぐみは図書室中を見渡すと、カウンター奥の蔵書室が目に付いた。普段から読書をしないので、図書室は滅多に入らないが、以前図書委員のクラスメイトが学校を休んだ時、放課後に代理をした記憶がある。
その日は自習に来ている生徒はいたが、殆どだれも本を借りに来なかったので恐ろしく暇だった。本を読む習慣があれば、まだ良かったのだが、めぐみは読書に興味は無い。本を読むといえば、国語の教科書くらいのものだ。暇にかまけてスマートフォンで動画でも見ようかと思うが、自習している生徒の冷ややかな視線に耐えることが出来ず、そそくさとポケットにしまった。
暇だと思いながら、周囲をぐるりと見渡すと、ふと自分が座っているカウンターの後ろに蔵書室がある事に気がついた。勿論本に興味が無いので中を覗いたりはしなかったが、ここに部屋がある事だけは覚えていた。
めぐみは静かに図書カウンターの奥にある蔵書室へ近づくと、その扉にゆっくり手を伸ばした。
またしても鍵は開いていた。半分程扉を開け、中を覗く。そこは普段作っている教室の半分くらいの大きさで、中にはロッカーと本棚が一つと、後は普通の机と椅子が三つ。蔵書室と呼ぶにはいささか本が少ない気がする。まるで誰かの秘密基地のようだ。
しかし、めぐみにはもうそんな事どうでも良かった。その瞳には頑丈そうなカーテンレールが映っていた。
扉を閉め、周囲を確認する。首を吊る為のカーテンレール。足場の机と椅子もある。ここで決まりだ。たとえ図書室に誰かが入ってきても、蔵書室にまで入ってくる人間はそうはいないだろう。さらに、カウンターの奥にあるので物音がしても、気付かれにくい気がする。
昨日スマートフォンで首吊りの方法を調べたので、手際よく準備をしていく。
足場を作り、カーテンレールに紐を結び付けようとするが、ここで紐を忘れてきた事に気付いた。逸る気持ちを抑え、ポケットに入っているスマートフォンを手に取ると、首吊りについて調べ始める。そうすると、一つの記事が目に留まった。
『中学生がスカーフで首を吊り自殺』
めぐみは自分の胸元に目を向けると、赤いスカーフが目に入った。機械的にそのスカーフを外し、手に持つとカーテンレールに括り付け、準備は出来た。
スカーフに首をかけためぐみはまるで安堵したかのような表情を浮かべ、足もとの椅子を蹴り飛ばそうとした。
しかし、急に体が震えて思うように体が動かなくなった。
(――早く、首をつりたい)
(――怖い)
(――早く)
(――死にたくない)
気がつくと、めぐみは大粒の涙を零していた。死にたくない。しかし死ななければならないという、強烈な思いが体を支配していた。
体の震えは増し、バランスを保っている事も出来なくなってきた。足場の椅子もガタガタと揺れている。その揺れのせいで机の中に入っていた筆箱が音を立て床に落ちた。
めぐみは反射的に視線を向けると、筆箱に手を伸ばす白く美しい指がしっかりと映る。視線を手の先から顔へと移すと、恐ろしく黒く、そして美しい瞳の女子生徒と目が合った。
「島岡めぐみさん――」
その声は綺麗だが、まるで感情が無い機械の音声のようだ。
その姿を見るまで、全く気付かなかっためぐみは、声も出なかった。
金魚のように口をパクパクしていると、女子生徒がまた口を開いた。
「トイレから戻ったらまさかクラスメイトが今、正に首を吊ろうとしているなんて……流石に驚いたわ」
女子生徒はビックリしたという割には穏やかで、冷静な口調だった。
「とりあえず、島岡さん、下りて話しましょう。何かの拍子に足を踏み外したらあなた死んじゃうわよ」
そういうと、その女子生徒はめぐみの足元まで近寄った。
「と、とめないで――」
めぐみは肩で息をしながら拒絶する。しかし、女子生徒はお構いなく素早く机を登り、めぐみの体を下から抱きかかえた。
机に乗せた椅子の上なので、めぐみの方が高い位置にいる。しかし女子生徒が顔を向けると、すぐ近くに顔が迫っていた。
めぐみの身長は145センチと小柄だが、女子生徒は170センチを超えるかどうかという長身だった。
女子生徒はめぐみの体をやさしく包みながら、顔を見上げ、やさしく呟く。
「島岡さん――申し訳ないけど、この自殺、とめさせてもらうわ」
吐息が当たりそうなくらいに顔を近づける女子生徒から、どこかで嗅いだ事のあるような、特徴的な匂いがしており、めぐみは一瞬気を取られたが、今はそれどころではない。
邪魔をされてはいけないと、必死に言葉を絞りそうとする。
「ど、どうして、私は――」
女子生徒は人差し指を立てて口を開いた。
「理由は三つ。一つはここはで自殺されると、図書室が当面使用禁止となるわ。まあ、勝手に使うけど、あまりいい気はしないわ」
女子生徒の話し方は問答無用で、淀みない。めぐみもその迫力に押され、ただ黙って聞いているしかなかった。二本目の指が立つ。
「二つ目は、あなたが死んでしまったら私が学校を休んだ時に、図書委員を替わってくれる子がいなくなるの」
めぐみはその言葉を聞いて、ごくりと唾を飲み込む。
しばしの混乱の後、その声の主が、自分のクラスメイトだと気付いた。
黒く長い髪、深く美しい瞳。肌は絹のように滑らかで、白くまるでモデルのような長身。そして女性でも美しいと感じてしまうような綺麗な顔立ちをしている――クラスメイトの月原芹だった。
「三つ目は――」
月原が三本目の指を立て話し始めようとしたが、めぐみの言葉が被さった。
「月原さん――」
「今気がついたの。とりあえず、危ないから降りましょう」
月原は立てていた指を直し、再びめぐみの体を支える。
「ごめんなさ――
言い終わる前に、急に意識が遠のいていく。
どこかで、小さく「失敗か――」と声がした。
誰だろうか、目の前で自分を支えている月原か、それとも――
月原が何か、自分に向かって話している。しかし、しっかりと聞き取れない。
めぐみはそのまま意識を失った。
死ななくてはならない――
島岡めぐみは死に場所を求め、校舎の中を彷徨っていた。
気が触れた様子も無く、一見ただ廊下を歩いているだけのようだが、内心は苛烈とまで言える自殺への思いを抱えていた。
発狂しそうな心をどうにか落ち着かせ、歩きながらも次々と、自殺できる場所を探すが、間近に迫った文化祭の準備の為だろうか、どこも人の気配がある。
階段を登り、校舎の奥へ、奥へと歩くと人の気配も薄らいでいく。廊下の角を曲がると、めぐみの視線は図書室へ向けられた。
読書を嗜まないめぐみにとって、この図書室は縁遠い場所だったが、わらにもすがる思いで図書室の扉に手をかける。鍵は閉まっていない。そっと中を覗くが誰の姿も無かった。
この時期に空き教室があるなんて、普通では考えられない事だ。そういえば、先日のHRでは図書室で文化祭の準備を禁止すると言っていた。数年前のこの時期に、この図書室で文化祭の準備をしていた生徒達が馬鹿騒ぎし、受験勉強に勤しむ生徒達から大いに顰蹙を買ったのが原因だそうだ。
季節は十月。いつまでも続くかと思っていた残暑も終わり、もうめっきり秋の空気に変わった。しかし、今のめぐみにはそんな季節の移ろいを楽しむ余裕なんて微塵も無かった。
めぐみは図書室を見回し、首を吊る事が出来そうな場所を探した。首を吊るにしても準備が必要だ。その間に誰かに見つかってしまう可能性がある。こうして、今ここに誰もいない事は奇跡に近い。いくら文化祭の準備で使用を禁止されていたとしても、ここで勉強をする生徒がいてもおかしくは無い。青葉学園の文化祭はとても盛り上がるが、中には興味の無い生徒だっているだろう。しかも今は十月。受験勉強に精を出している生徒がいてもおかしくない。しかし、今はそんな事を考えていても仕方ない。めぐみはこの幸運に感謝しながら図書室に飛び込むと、急いで中から鍵を閉めた。
久しぶりに入った図書室は独特の匂いがする。本の匂いとでも言っていいのだろうか。嗅ぎなれないが、別に嫌いな匂いではない。
めぐみは図書室中を見渡すと、カウンター奥の蔵書室が目に付いた。普段から読書をしないので、図書室は滅多に入らないが、以前図書委員のクラスメイトが学校を休んだ時、放課後に代理をした記憶がある。
その日は自習に来ている生徒はいたが、殆どだれも本を借りに来なかったので恐ろしく暇だった。本を読む習慣があれば、まだ良かったのだが、めぐみは読書に興味は無い。本を読むといえば、国語の教科書くらいのものだ。暇にかまけてスマートフォンで動画でも見ようかと思うが、自習している生徒の冷ややかな視線に耐えることが出来ず、そそくさとポケットにしまった。
暇だと思いながら、周囲をぐるりと見渡すと、ふと自分が座っているカウンターの後ろに蔵書室がある事に気がついた。勿論本に興味が無いので中を覗いたりはしなかったが、ここに部屋がある事だけは覚えていた。
めぐみは静かに図書カウンターの奥にある蔵書室へ近づくと、その扉にゆっくり手を伸ばした。
またしても鍵は開いていた。半分程扉を開け、中を覗く。そこは普段作っている教室の半分くらいの大きさで、中にはロッカーと本棚が一つと、後は普通の机と椅子が三つ。蔵書室と呼ぶにはいささか本が少ない気がする。まるで誰かの秘密基地のようだ。
しかし、めぐみにはもうそんな事どうでも良かった。その瞳には頑丈そうなカーテンレールが映っていた。
扉を閉め、周囲を確認する。首を吊る為のカーテンレール。足場の机と椅子もある。ここで決まりだ。たとえ図書室に誰かが入ってきても、蔵書室にまで入ってくる人間はそうはいないだろう。さらに、カウンターの奥にあるので物音がしても、気付かれにくい気がする。
昨日スマートフォンで首吊りの方法を調べたので、手際よく準備をしていく。
足場を作り、カーテンレールに紐を結び付けようとするが、ここで紐を忘れてきた事に気付いた。逸る気持ちを抑え、ポケットに入っているスマートフォンを手に取ると、首吊りについて調べ始める。そうすると、一つの記事が目に留まった。
『中学生がスカーフで首を吊り自殺』
めぐみは自分の胸元に目を向けると、赤いスカーフが目に入った。機械的にそのスカーフを外し、手に持つとカーテンレールに括り付け、準備は出来た。
スカーフに首をかけためぐみはまるで安堵したかのような表情を浮かべ、足もとの椅子を蹴り飛ばそうとした。
しかし、急に体が震えて思うように体が動かなくなった。
(――早く、首をつりたい)
(――怖い)
(――早く)
(――死にたくない)
気がつくと、めぐみは大粒の涙を零していた。死にたくない。しかし死ななければならないという、強烈な思いが体を支配していた。
体の震えは増し、バランスを保っている事も出来なくなってきた。足場の椅子もガタガタと揺れている。その揺れのせいで机の中に入っていた筆箱が音を立て床に落ちた。
めぐみは反射的に視線を向けると、筆箱に手を伸ばす白く美しい指がしっかりと映る。視線を手の先から顔へと移すと、恐ろしく黒く、そして美しい瞳の女子生徒と目が合った。
「島岡めぐみさん――」
その声は綺麗だが、まるで感情が無い機械の音声のようだ。
その姿を見るまで、全く気付かなかっためぐみは、声も出なかった。
金魚のように口をパクパクしていると、女子生徒がまた口を開いた。
「トイレから戻ったらまさかクラスメイトが今、正に首を吊ろうとしているなんて……流石に驚いたわ」
女子生徒はビックリしたという割には穏やかで、冷静な口調だった。
「とりあえず、島岡さん、下りて話しましょう。何かの拍子に足を踏み外したらあなた死んじゃうわよ」
そういうと、その女子生徒はめぐみの足元まで近寄った。
「と、とめないで――」
めぐみは肩で息をしながら拒絶する。しかし、女子生徒はお構いなく素早く机を登り、めぐみの体を下から抱きかかえた。
机に乗せた椅子の上なので、めぐみの方が高い位置にいる。しかし女子生徒が顔を向けると、すぐ近くに顔が迫っていた。
めぐみの身長は145センチと小柄だが、女子生徒は170センチを超えるかどうかという長身だった。
女子生徒はめぐみの体をやさしく包みながら、顔を見上げ、やさしく呟く。
「島岡さん――申し訳ないけど、この自殺、とめさせてもらうわ」
吐息が当たりそうなくらいに顔を近づける女子生徒から、どこかで嗅いだ事のあるような、特徴的な匂いがしており、めぐみは一瞬気を取られたが、今はそれどころではない。
邪魔をされてはいけないと、必死に言葉を絞りそうとする。
「ど、どうして、私は――」
女子生徒は人差し指を立てて口を開いた。
「理由は三つ。一つはここはで自殺されると、図書室が当面使用禁止となるわ。まあ、勝手に使うけど、あまりいい気はしないわ」
女子生徒の話し方は問答無用で、淀みない。めぐみもその迫力に押され、ただ黙って聞いているしかなかった。二本目の指が立つ。
「二つ目は、あなたが死んでしまったら私が学校を休んだ時に、図書委員を替わってくれる子がいなくなるの」
めぐみはその言葉を聞いて、ごくりと唾を飲み込む。
しばしの混乱の後、その声の主が、自分のクラスメイトだと気付いた。
黒く長い髪、深く美しい瞳。肌は絹のように滑らかで、白くまるでモデルのような長身。そして女性でも美しいと感じてしまうような綺麗な顔立ちをしている――クラスメイトの月原芹だった。
「三つ目は――」
月原が三本目の指を立て話し始めようとしたが、めぐみの言葉が被さった。
「月原さん――」
「今気がついたの。とりあえず、危ないから降りましょう」
月原は立てていた指を直し、再びめぐみの体を支える。
「ごめんなさ――
言い終わる前に、急に意識が遠のいていく。
どこかで、小さく「失敗か――」と声がした。
誰だろうか、目の前で自分を支えている月原か、それとも――
月原が何か、自分に向かって話している。しかし、しっかりと聞き取れない。
めぐみはそのまま意識を失った。
0
あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております

視える僕らのシェアハウス
橘しづき
ホラー
安藤花音は、ごく普通のOLだった。だが25歳の誕生日を境に、急におかしなものが見え始める。
電車に飛び込んでバラバラになる男性、やせ細った子供の姿、どれもこの世のものではない者たち。家の中にまで入ってくるそれらに、花音は仕事にも行けず追い詰められていた。
ある日、駅のホームで電車を待っていると、霊に引き込まれそうになってしまう。そこを、見知らぬ男性が間一髪で救ってくれる。彼は花音の話を聞いて名刺を一枚手渡す。
『月乃庭 管理人 竜崎奏多』
不思議なルームシェアが、始まる。

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド
まみ夜
ホラー
ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。
事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。
一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。
その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。
そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。
ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。
そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。
第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。
表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。



怪奇蒐集帳(短編集)
naomikoryo
ホラー
この世には、知ってはいけない話がある。
怪談、都市伝説、語り継がれる呪い——
どれもがただの作り話かもしれない。
だが、それでも時々、**「本物」**が紛れ込むことがある。
本書は、そんな“見つけてしまった”怪異を集めた一冊である。
最後のページを閉じるとき、あなたは“何か”に気づくことになるだろう——。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】
絢郷水沙
ホラー
普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。
下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。
※全話オリジナル作品です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる