あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし
かずえ
歴史・時代
旧題:ふたり暮らし
長屋シリーズ一作目。
第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。
頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。
一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

日本の運命を変えた天才少年-日本が世界一の帝国になる日-
ましゅまろ
歴史・時代
――もしも、日本の運命を変える“少年”が現れたなら。
1941年、戦争の影が世界を覆うなか、日本に突如として現れた一人の少年――蒼月レイ。
わずか13歳の彼は、天才的な頭脳で、戦争そのものを再設計し、歴史を変え、英米独ソをも巻き込みながら、日本を敗戦の未来から救い出す。
だがその歩みは、同時に多くの敵を生み、命を狙われることも――。
これは、一人の少年の手で、世界一の帝国へと昇りつめた日本の物語。
希望と混乱の20世紀を超え、未来に語り継がれる“蒼き伝説”が、いま始まる。
※アルファポリス限定投稿
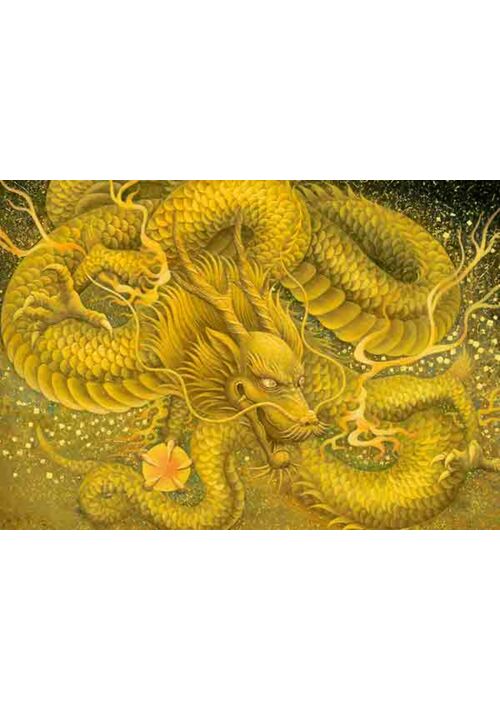
神典日月神示 真実の物語
蔵屋
歴史・時代
私は二人の方々の神憑りについて、今から25年前にその真実を知りました。
この方たちのお名前は
大本開祖•出口なお(でぐちなお)、
神典研究家で画家でもあった岡本天明(おかもとてんめい)です。
この日月神示(ひつきしんじ)または日尽神示(ひつくしんじ)は、神典研究家で画家でもあった岡本天明(おかもとてんめい)に「国常立尊(国之常立神)という高級神霊からの神示を自動書記によって記述したとされる書物のことです。
昭和19年から27年(昭和23・26年も無し)に一連の神示が降り、6年後の昭和33、34年に補巻とする1巻、さらに2年後に8巻の神示が降りたとされています。
その書物を纏めた書類です。
この書類は神国日本の未来の預言書なのだ。
私はこの日月神示(ひつきしんじ)に出会い、研究し始めてもう25年になります。
日月神示が降ろされた場所は麻賀多神社(まかたじんじゃ)です。日月神示の最初の第一帖と第二帖は第二次世界大戦中の昭和19年6月10日に、この神社の社務所で岡本天明が神憑りに合い自動書記さされたのです。
殆どが漢数字、独特の記号、若干のかな文字が混じった文体で構成され、抽象的な絵のみで書記されている「巻」もあります。
本巻38巻と補巻1巻の計39巻が既に発表されているが、他にも、神霊より発表を禁じられている「巻」が13巻あり、天明はこの未発表のものについて昭和36年に「或る時期が来れば発表を許されるものか、許されないのか、現在の所では不明であります」と語っています。
日月神示は、その難解さから、書記した天明自身も当初は、ほとんど読むことが出来なかったが、仲間の神典研究家や霊能者達の協力などで少しずつ解読が進み、天明亡き後も妻である岡本三典(1917年〈大正6年〉11月9日 ~2009年〈平成21年〉6月23日)の努力により、現在では一部を除きかなりの部分が解読されたと言われているます。しかし、一方では神示の中に「この筆示は8通りに読めるのであるぞ」と書かれていることもあり、解読法の一つに成功したという認識が関係者の間では一般的です。
そのために、仮訳という副題を添えての発表もありました。
なお、原文を解読して漢字仮名交じり文に書き直されたものは、特に「ひふみ神示」または「一二三神示」と呼ばれています。
縄文人の祝詞に「ひふみ祝詞(のりと)」という祝詞の歌があります。
日月神示はその登場以来、関係者や一部専門家を除きほとんど知られていなかったが、1990年代の初め頃より神典研究家で翻訳家の中矢伸一の著作などにより広く一般にも知られるようになってきたと言われています。
この小説は真実の物語です。
「神典日月神示(しんてんひつきしんじ)真実の物語」
どうぞ、お楽しみ下さい。
『神知りて 人の幸せ 祈るのみ
神の伝えし 愛善の道』

【読者賞】江戸の飯屋『やわらぎ亭』〜元武家娘が一膳でほぐす人と心〜
旅する書斎(☆ほしい)
歴史・時代
【第11回歴史・時代小説大賞 読者賞(読者投票1位)受賞】
文化文政の江戸・深川。
人知れず佇む一軒の飯屋――『やわらぎ亭』。
暖簾を掲げるのは、元武家の娘・おし乃。
家も家族も失い、父の形見の包丁一つで町に飛び込んだ彼女は、
「旨い飯で人の心をほどく」を信条に、今日も竈に火を入れる。
常連は、職人、火消し、子どもたち、そして──町奉行・遠山金四郎!?
変装してまで通い詰めるその理由は、一膳に込められた想いと味。
鯛茶漬け、芋がらの煮物、あんこう鍋……
その料理の奥に、江戸の暮らしと誇りが宿る。
涙も笑いも、湯気とともに立ち上る。
これは、舌と心を温める、江戸人情グルメ劇。

大東亜戦争を有利に
ゆみすけ
歴史・時代
日本は大東亜戦争に負けた、完敗であった。 そこから架空戦記なるものが増殖する。 しかしおもしろくない、つまらない。 であるから自分なりに無双日本軍を架空戦記に参戦させました。 主観満載のラノベ戦記ですから、ご感弁を

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















