35 / 56
第二話:霊 猫夜と犬飼
死神降臨
しおりを挟む
「悪かったって。勝手な約束したのは謝るから、そんな昔のこと言うなよ。悲しいじゃねえか」
この通りだと顔の前で拝んでみる。
「親兄弟からも探してもらえず勘当だったってんだから笑えるさ。殺され方を考えりゃあ死体も上がらないはずだよ」
「もしかしたら見つけられてたかもしれないぜ。それを知らなかったふりをされたのかもしれないねえ」
昭子と太郎が侍を追い込むような言い方をする。
「そんなに言うなよ。本当に悲しくなるじゃねえか」
侍が目元を拭った。
「これくらいにしてやるよ。今回だけは許してやる。次はあたしらもちゃんとその中に入れるんだよ」
涙目になりながら頷く侍を見て昭子がにっこりと笑った。
「よかったじゃねえか。さっさと謝ったからどうやって切られたか事細かに昭子さんに言われなくてすんで。まあ、侍さんは刀でこいつは猫の爪でだけどな」
と、猫がひっかく真似をした太郎は、自分たちが話しいている間にも登を痛めつけている二匹を見て、
「お。そろそろじゃねえか」
濃紺の空に指を向け、「ほら、来た」と、薄く紫色に光った空から黒いどろどろした何かがひらりひらりと舞い降りてくるのが見える。
「あら、本当だ。今日は死神のやつやけに早いじゃないか。そろそろ死ぬねあの男も」
黒いものとは、死神のことだ。昭子が降りてくる死神を確認してから登がどうなっているのかと見れば、血だらけになって息も絶え絶え這いつくばって逃げようとしているところだった。
「やれ早いな。瑞香さんのときは、あの男をいたぶるように、土を一心不乱に掘っているその上から纏わり付いたけど、今回はどうなんのかねえ」
侍は降ってくる死神を目で追いながら、楽しいお遊びが終わりを迎えようとしているのをつまらなく感じていた。
瑞香のときにも空から降ってきた黒いものは、今、登の頭上に降り立った死神と同じだ。
それは姿形はなく、柔らかい布のように風に揺れている。
しかし、司も登もそれを見て悲鳴をあげ、口からは泡、穴という穴から血を吐き、息をする度に内臓が口から出たり入ったりするのを己の目で見ると、発狂した。
這いつくばる指先からは指の骨が指先の皮を破いてずるりと出てきて、その手はくしゃりと音を立てて動きを止めた。肘が地につく。その勢いにおされて指先の皮をぶちぬいて腕の骨が飛び出した。顎が地につく。土がもぞりと動いた。何かが弾けるような軽い音を立てて土の中から白くて細いものが波を打ちながら立ち上る。迷わず鼻の穴から体内へ入り込む。そして内臓に食らいつき、外へ引き出してくる。登は悲鳴をあげ胃の中の内容物と内臓を辺りに吐き散らかす。
いつのまにか目の前には自分がかつて手にかけた小動物らが自分のことを取り囲んでいて、今吐き出した内容物を噛みちぎって食らいついていた。
罵声をあげても止まらない。その中にはもちろん猫夜と犬飼の姿もある。この二匹が先頭だって食らいついていた。
死神はこの動物らが登を殺すのを待ち、完全に生き絶えると動物らを離した。死神が横に長く伸びた。小動物の姿が薄くなっていく。
猫夜と犬飼を残し、ほかの動物が全て消えると死神は血まみれの体の上に被さると登を自分のうちに飲み込んだ。
死神が登の体から離れると登はむくりと起き上がる。
自分がどこにいるかわかっていないようだ。
目の前にいる猫夜と犬飼をその目の中に捉えると、肩をお大きく跳ね、尻を擦りながら後ずさる。その目には恐怖が映っている。
独り言を言い続け後退り続けるとふと氷のような冷たさが手に伝わる。
振り返ればそこにはまっ黒い闇が大きく口を開けて自分を飲み込もうとしていた。その中から聞き覚えのある動物の最期の声が聞こえてきた。
自分が手にかけたものが待ち構えている声だと理解するとさきほどの記憶が蘇った。
「俺は死んだんじゃねえのか。今殺されたじゃねえか。痛い。辛い。あんな痛い思いはもう嫌だ。あんな恐怖はもう嫌だ。なあ、猫夜、犬飼、助けてくれ。俺を助けてくれよ」
この後に及んでもまだ助けろという登に猫夜は、
「お前はこれから闇の中で、お前が今までに殺した動物たちにまた殺される。そこには我らも含まれている。お前は未来永劫殺され続けて苦しむんだよ」
「これ猫夜、それは俺の台詞じゃねえか」
太郎が自分の台詞を取られたとばかりに軽く猫夜の頭をはたく。
「なんなんだよお前らは」
登は何が何だかわからないまま、自分の後ろにぽっかり空いている穴から逃れようと今度は猫夜の方に這いつくばろうとしたところで、死神に捕まった。ひぃという悲鳴をあげる前に、登の体は凍り始めた。首から上だけは凍らず頭も正常に動いている。恐怖を感じるということだ。
闇の内から真っ赤な目をした犬が一匹ゆっくりとぬめりと現れ、真っ赤な口を大きく開き、登の腕をやんわりと噛む。そのまま弄ぶようにゆっくりと、恐怖を煽るように闇の内に引きずり込む。
登は泣き叫んでこの世に留まろうとするが体はすでに凍っていて動かない。気持ちだけがこの世に留まり、体は無情にも闇の中に飲み込まれていく。
嬉しそうに鳴き叫ぶ動物の声が闇から漏れる。すっぽりと登の体が闇に飲まれると闇は登の悲鳴を結び取るように萎んでいった。
この通りだと顔の前で拝んでみる。
「親兄弟からも探してもらえず勘当だったってんだから笑えるさ。殺され方を考えりゃあ死体も上がらないはずだよ」
「もしかしたら見つけられてたかもしれないぜ。それを知らなかったふりをされたのかもしれないねえ」
昭子と太郎が侍を追い込むような言い方をする。
「そんなに言うなよ。本当に悲しくなるじゃねえか」
侍が目元を拭った。
「これくらいにしてやるよ。今回だけは許してやる。次はあたしらもちゃんとその中に入れるんだよ」
涙目になりながら頷く侍を見て昭子がにっこりと笑った。
「よかったじゃねえか。さっさと謝ったからどうやって切られたか事細かに昭子さんに言われなくてすんで。まあ、侍さんは刀でこいつは猫の爪でだけどな」
と、猫がひっかく真似をした太郎は、自分たちが話しいている間にも登を痛めつけている二匹を見て、
「お。そろそろじゃねえか」
濃紺の空に指を向け、「ほら、来た」と、薄く紫色に光った空から黒いどろどろした何かがひらりひらりと舞い降りてくるのが見える。
「あら、本当だ。今日は死神のやつやけに早いじゃないか。そろそろ死ぬねあの男も」
黒いものとは、死神のことだ。昭子が降りてくる死神を確認してから登がどうなっているのかと見れば、血だらけになって息も絶え絶え這いつくばって逃げようとしているところだった。
「やれ早いな。瑞香さんのときは、あの男をいたぶるように、土を一心不乱に掘っているその上から纏わり付いたけど、今回はどうなんのかねえ」
侍は降ってくる死神を目で追いながら、楽しいお遊びが終わりを迎えようとしているのをつまらなく感じていた。
瑞香のときにも空から降ってきた黒いものは、今、登の頭上に降り立った死神と同じだ。
それは姿形はなく、柔らかい布のように風に揺れている。
しかし、司も登もそれを見て悲鳴をあげ、口からは泡、穴という穴から血を吐き、息をする度に内臓が口から出たり入ったりするのを己の目で見ると、発狂した。
這いつくばる指先からは指の骨が指先の皮を破いてずるりと出てきて、その手はくしゃりと音を立てて動きを止めた。肘が地につく。その勢いにおされて指先の皮をぶちぬいて腕の骨が飛び出した。顎が地につく。土がもぞりと動いた。何かが弾けるような軽い音を立てて土の中から白くて細いものが波を打ちながら立ち上る。迷わず鼻の穴から体内へ入り込む。そして内臓に食らいつき、外へ引き出してくる。登は悲鳴をあげ胃の中の内容物と内臓を辺りに吐き散らかす。
いつのまにか目の前には自分がかつて手にかけた小動物らが自分のことを取り囲んでいて、今吐き出した内容物を噛みちぎって食らいついていた。
罵声をあげても止まらない。その中にはもちろん猫夜と犬飼の姿もある。この二匹が先頭だって食らいついていた。
死神はこの動物らが登を殺すのを待ち、完全に生き絶えると動物らを離した。死神が横に長く伸びた。小動物の姿が薄くなっていく。
猫夜と犬飼を残し、ほかの動物が全て消えると死神は血まみれの体の上に被さると登を自分のうちに飲み込んだ。
死神が登の体から離れると登はむくりと起き上がる。
自分がどこにいるかわかっていないようだ。
目の前にいる猫夜と犬飼をその目の中に捉えると、肩をお大きく跳ね、尻を擦りながら後ずさる。その目には恐怖が映っている。
独り言を言い続け後退り続けるとふと氷のような冷たさが手に伝わる。
振り返ればそこにはまっ黒い闇が大きく口を開けて自分を飲み込もうとしていた。その中から聞き覚えのある動物の最期の声が聞こえてきた。
自分が手にかけたものが待ち構えている声だと理解するとさきほどの記憶が蘇った。
「俺は死んだんじゃねえのか。今殺されたじゃねえか。痛い。辛い。あんな痛い思いはもう嫌だ。あんな恐怖はもう嫌だ。なあ、猫夜、犬飼、助けてくれ。俺を助けてくれよ」
この後に及んでもまだ助けろという登に猫夜は、
「お前はこれから闇の中で、お前が今までに殺した動物たちにまた殺される。そこには我らも含まれている。お前は未来永劫殺され続けて苦しむんだよ」
「これ猫夜、それは俺の台詞じゃねえか」
太郎が自分の台詞を取られたとばかりに軽く猫夜の頭をはたく。
「なんなんだよお前らは」
登は何が何だかわからないまま、自分の後ろにぽっかり空いている穴から逃れようと今度は猫夜の方に這いつくばろうとしたところで、死神に捕まった。ひぃという悲鳴をあげる前に、登の体は凍り始めた。首から上だけは凍らず頭も正常に動いている。恐怖を感じるということだ。
闇の内から真っ赤な目をした犬が一匹ゆっくりとぬめりと現れ、真っ赤な口を大きく開き、登の腕をやんわりと噛む。そのまま弄ぶようにゆっくりと、恐怖を煽るように闇の内に引きずり込む。
登は泣き叫んでこの世に留まろうとするが体はすでに凍っていて動かない。気持ちだけがこの世に留まり、体は無情にも闇の中に飲み込まれていく。
嬉しそうに鳴き叫ぶ動物の声が闇から漏れる。すっぽりと登の体が闇に飲まれると闇は登の悲鳴を結び取るように萎んでいった。
0
あなたにおすすめの小説

17歳男子高生と32歳主婦の境界線
MisakiNonagase
恋愛
32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。
カレンと晴人はその後、どうなる?
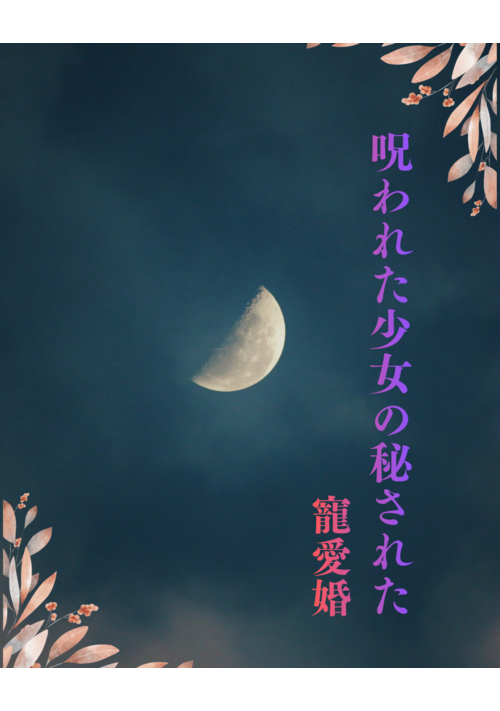
呪われた少女の秘された寵愛婚―盈月―
くろのあずさ
キャラ文芸
異常存在(マレビト)と呼ばれる人にあらざる者たちが境界が曖昧な世界。甚大な被害を被る人々の平和と安寧を守るため、軍は組織されたのだと噂されていた。
「無駄とはなんだ。お前があまりにも妻としての自覚が足らないから、思い出させてやっているのだろう」
「それは……しょうがありません」
だって私は――
「どんな姿でも関係ない。私の妻はお前だけだ」
相応しくない。私は彼のそばにいるべきではないのに――。
「私も……あなた様の、旦那様のそばにいたいです」
この身で願ってもかまわないの?
呪われた少女の孤独は秘された寵愛婚の中で溶かされる
2025.12.6
盈月(えいげつ)……新月から満月に向かって次第に円くなっていく間の月

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

私の守護霊さん
Masa&G
キャラ文芸
大学生活を送る彩音には、誰にも言えない秘密がある。
彼女のそばには、他人には姿の見えない“守護霊さん”がずっと寄り添っていた。
これは——二人で過ごした最後の一年を描く、かけがえのない物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















