1 / 2
前編
しおりを挟む
この国では孤児院が周辺国よりも多い。
それを不幸な子供を作らぬよう保護に力を入れているいい国と見るか、大切な我が子すら捨てなければ皆で心中するしかないようなまともな生活ができないような人が多い悪い国と見るかはおそらく育った環境によるだろう。
しかし国の思惑は実のところそのどちらとも関係ない。
忌み子として扱われることの多い、庶民の中の魔力持ちを効率よく見つけるためだ。
魔力は本来庶民が持ちうるはずはなく、代わりに貴族なら大概持っているものだ。
なので忌み子は身分を隠した、あるいは身分を笠に着た貴族の放蕩の結果であることもある。
そんな風に混じる可能性が零ではない以上、先祖返りや突然変異であることも。
そして魔力持ちの子供は、その制御できない魔力によって物を壊したり人を傷つけたりするので気味悪がれ、ごく一部の諸事情で貴族として扱われるようになる者以外、手に終えないと捨てられることが多い。
そして何の導きか野垂れ死にすることなく孤児院まで辿り着き、魔力を確認された子供は、将来国に使いつぶされることが決定する。
魔力を制御出来るようにするために生徒の大半が貴族である魔法学園に入れられ、進路の自由などなく、卒業すれば魔法でやれば効率よく出来るが貴族が嫌がる仕事に回される。
今は戦時中でないことがせめてもの救いだろうか。
彼女もそんなよくある運命をたどると思われた。
けれど彼女の母親は娘を手放さなかった。
しかし娘への愛情故ではない。
娘の父親の関心を取り戻すには子供の存在が必要だと思いこんでいたからだ。
忌み子としての能力がほとんど表に出なかったことも影響した。
潜在的には相当の量の力を持っていたのだが、ろくに食べさせられないような生活では生存本能が魔力も生命維持に使ってしまう。生きて生まれたことが奇蹟のような状況ではそれ以外に力を割り当てる余裕はない。
その特性は多かれ少なかれ忌み子に共通するもので、だからこそ孤児院が増えたのだろう。忌み子が孤児院にたどり着く確率は、魔力のない子供が捨てられたときより恐らくずっと高い。
それが彼女はずば抜けていたのだろう。
こうして捨てられはしなかったが愛されもしなかった生活は、それでもそれなりに続き、父親が母親を刺し殺し、それが握りつぶされた事で終わりを告げた。
何が彼らをそこまで追い詰めたのか分からない。
彼女は幸か不幸か母親が父親に殺されたということを知ることはなかった。
ぎりぎりだが、孤児院に入ることのできる年齢だった彼女は、少しの身の回りの物を持ち孤児院に向かう。
そこでようやく魔力を持っていることに気づかれた。
だとしたら魔法学園に行かせなければならない。
けれどその為に残された時間はあまりにも少ない。
忌み子として必要な知識も、人間として必要な常識も、父親が引き取ってくれなかったことによる不安定な彼女の気持ちも、何もかも無視して最低限表面上の作法だけを教え込まれ魔法学園にたたき込まれた。
そんな状況ではあったが、初めてたくさんの同世代が居る中に入った彼女はとても喜んだ。
ただ同じ年頃であっても周りはほぼ貴族である。
それでも果敢に友人を作ろうとした彼女はとても勇気ある存在だったのだろう。
けれども彼女は他人との関わり方を知らなかった。
今まで父親の居ないときはこき使われるか家の中で放置され、ごくたまに父親が居るときはほんの少し構われ、その時すら母親が父親に媚びる理由にされていることが大半だった。
なので結果やったことは異性に自覚なく媚びることだった。
それは母親の真似であり彼女としてはごく普通の行いであったし、同性とは異性を挟まなければ付き合えないものだとどこか思い込んでいた。
大半の人達はそんな彼女を冷ややかに見つめていたが、何故か媚びてくる相手には困っていないはずの高位貴族の子弟が引っかかった。
その結果襲われでもすれば性的な対象にみられていただけだと気づいただろうが、婚前に迂闊に相手と交渉を持ってはいけないという常識はそれでも彼らに残っていたため、彼女はそれを友情か庇護だと信じた。あるいは信じたがった。
どちらにしろ、誰だって冷たくしてくれる人よりは優しくしてくれる人に信頼を持つ。
結果成り立ったのがある種の共依存で、更に周りが見えない状況に陥る。
それを不幸な子供を作らぬよう保護に力を入れているいい国と見るか、大切な我が子すら捨てなければ皆で心中するしかないようなまともな生活ができないような人が多い悪い国と見るかはおそらく育った環境によるだろう。
しかし国の思惑は実のところそのどちらとも関係ない。
忌み子として扱われることの多い、庶民の中の魔力持ちを効率よく見つけるためだ。
魔力は本来庶民が持ちうるはずはなく、代わりに貴族なら大概持っているものだ。
なので忌み子は身分を隠した、あるいは身分を笠に着た貴族の放蕩の結果であることもある。
そんな風に混じる可能性が零ではない以上、先祖返りや突然変異であることも。
そして魔力持ちの子供は、その制御できない魔力によって物を壊したり人を傷つけたりするので気味悪がれ、ごく一部の諸事情で貴族として扱われるようになる者以外、手に終えないと捨てられることが多い。
そして何の導きか野垂れ死にすることなく孤児院まで辿り着き、魔力を確認された子供は、将来国に使いつぶされることが決定する。
魔力を制御出来るようにするために生徒の大半が貴族である魔法学園に入れられ、進路の自由などなく、卒業すれば魔法でやれば効率よく出来るが貴族が嫌がる仕事に回される。
今は戦時中でないことがせめてもの救いだろうか。
彼女もそんなよくある運命をたどると思われた。
けれど彼女の母親は娘を手放さなかった。
しかし娘への愛情故ではない。
娘の父親の関心を取り戻すには子供の存在が必要だと思いこんでいたからだ。
忌み子としての能力がほとんど表に出なかったことも影響した。
潜在的には相当の量の力を持っていたのだが、ろくに食べさせられないような生活では生存本能が魔力も生命維持に使ってしまう。生きて生まれたことが奇蹟のような状況ではそれ以外に力を割り当てる余裕はない。
その特性は多かれ少なかれ忌み子に共通するもので、だからこそ孤児院が増えたのだろう。忌み子が孤児院にたどり着く確率は、魔力のない子供が捨てられたときより恐らくずっと高い。
それが彼女はずば抜けていたのだろう。
こうして捨てられはしなかったが愛されもしなかった生活は、それでもそれなりに続き、父親が母親を刺し殺し、それが握りつぶされた事で終わりを告げた。
何が彼らをそこまで追い詰めたのか分からない。
彼女は幸か不幸か母親が父親に殺されたということを知ることはなかった。
ぎりぎりだが、孤児院に入ることのできる年齢だった彼女は、少しの身の回りの物を持ち孤児院に向かう。
そこでようやく魔力を持っていることに気づかれた。
だとしたら魔法学園に行かせなければならない。
けれどその為に残された時間はあまりにも少ない。
忌み子として必要な知識も、人間として必要な常識も、父親が引き取ってくれなかったことによる不安定な彼女の気持ちも、何もかも無視して最低限表面上の作法だけを教え込まれ魔法学園にたたき込まれた。
そんな状況ではあったが、初めてたくさんの同世代が居る中に入った彼女はとても喜んだ。
ただ同じ年頃であっても周りはほぼ貴族である。
それでも果敢に友人を作ろうとした彼女はとても勇気ある存在だったのだろう。
けれども彼女は他人との関わり方を知らなかった。
今まで父親の居ないときはこき使われるか家の中で放置され、ごくたまに父親が居るときはほんの少し構われ、その時すら母親が父親に媚びる理由にされていることが大半だった。
なので結果やったことは異性に自覚なく媚びることだった。
それは母親の真似であり彼女としてはごく普通の行いであったし、同性とは異性を挟まなければ付き合えないものだとどこか思い込んでいた。
大半の人達はそんな彼女を冷ややかに見つめていたが、何故か媚びてくる相手には困っていないはずの高位貴族の子弟が引っかかった。
その結果襲われでもすれば性的な対象にみられていただけだと気づいただろうが、婚前に迂闊に相手と交渉を持ってはいけないという常識はそれでも彼らに残っていたため、彼女はそれを友情か庇護だと信じた。あるいは信じたがった。
どちらにしろ、誰だって冷たくしてくれる人よりは優しくしてくれる人に信頼を持つ。
結果成り立ったのがある種の共依存で、更に周りが見えない状況に陥る。
15
あなたにおすすめの小説


ずっと一緒にいようね
仏白目
恋愛
あるいつもと同じ朝 おれは朝食のパンをかじりながらスマホでニュースの記事に目をとおしてた
「ねえ 生まれ変わっても私と結婚する?」
「ああ もちろんだよ」
「ふふっ 正直に言っていいんだよ?」
「えっ、まぁなぁ 同じ事繰り返すのもなんだし・・
次は別のひとがいいかも お前もそうだろ? なぁ?」
言いながらスマホの画面から視線を妻に向けると
「・・・・・」
失意の顔をした 妻と目が合った
「え・・・?」
「・・・・ 」
*作者ご都合主義の世界観のフィクションです。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
恋愛
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。


悪役令嬢だった彼女についての覚え書き
松本雀
恋愛
それは悲しみというより、むしろ一種の贅沢だったのかもしれない。日々の喧噪の中で、誰かの存在を「思い出す」という行為ほど、密やかで贅沢な時間はない。
◆◆◆
王太子との婚約を破棄され、「悪役」として物語から退場した彼女。
残された私は、その舞台にひとり立ち尽くす。ただの友人として、ただの照明係として。それでも記憶のなかで彼女は、今も確かに呼吸している。
これは、悪役令嬢の友人の記憶をなぞりながら辿った、ささやかな巡礼の記録。


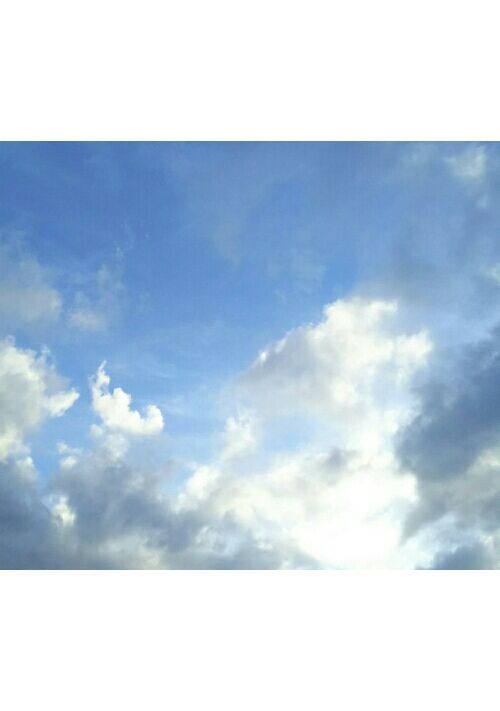
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















