76 / 96
明媚
しおりを挟む
「ああ……わかりません。遅くなるかも知れませんので、夕食は離れで頂きます」
何処と無く、歯切れが悪い様子に晃子が引っ掛かりを覚えたのは、今朝方のこと。
帰宅時間を、皆の前で宣言するという不思議ではあるが、なかなか効率的な習わしによって判明した光留の帰宅予定時刻にだ。
「ご用が長引くのでしょうか?」と、尋ねてはみたが、言葉を選んでいるのか「ん~、ええ」など、こちらも物が挟まった言い方。
2人が顔を会わせるのは、朝食と夕食時に限られている。もちろん、食後 談話をする程度の時間はあるのだが、やはり人の目もある為、込み入った話はない。
光留が部屋に現れることもなく、離れに晃子を呼ぶこともないのだから、正直、鹿鳴館で想いの丈を訴えてきたのは、何だったのだろう?と思う。
もしかしたら、晃子が過剰に考えているだけで本当は、そこまで興味を持っていないのではないか?と。何故なら根掘り葉掘り、行動を探っていた羽倉崎と比べ、淡白な様子が際立ち、そう思えてならないのだ。
そんな晃子の疑問に答えたのは、昼過ぎに津多子を訪ねて来たという客人だった。
肘掛けへ向けた顔が、失笑を浮かべ「まさか……」と漏らす。
「ガツガツ興味を示しては、プライドが許さないのでしょう。むしろ興味は、尽きることなく……と言った方が正しいかと」
口振りは、ずいぶんと落ち着いている。その上、司法官僚ゆえか? 小さな取っ掛かりから、話を引き出すのに長けているように感じた。元々晃子は、自分の考えを話すことが少ないが、近衛と会話をしていると些細なことから話を広げられ、会話が途切れることがない。
「近衛様は、光留様をよくご存知なのですね」
「まあ、親戚筋ということもあって、幼少の頃より存じておりますので。こんな風に晃子さんと、2人で夕食を頂いていることを知った時の顔まで、想像することが出来ますよ」
自身の人差し指を、両目尻に押し当てるとクイッと引き上げた。
「まあ、ふふ!面白い方」
「そういえば……夏の夜会で泰臣君と駒子さんと食事をご一緒しましたが、なかなか楽しいお嬢様で」
「ええ、思ったことをパッと口にされるのですが、それが嫌味でもないのです。羨ましい限り」
「貴女も、仰れば良いかと」
晃子は、静かな問いかけに首を振ると、箸を置いた。
「尋ねることが恥ずかしく、又、私が言うとトゲがあるように感じて……おそらく駒子さんとの、人となりの違いでしょう」
「そうですかね?私は、そのように感じませんが。それに、言葉にトゲがあっても光留さんには通用しませんよ?……あ、どうやら お戻りのようで」
近衛は、廊下を行き来する女中らの足音に、耳を傾ける仕草をする。
「光留さんのご両親の話をしておこうかと思ったのですが、又の機会にいたしましょう」
「それは、実の?」
「ええ、津多子夫人からも言われておりますので……ただ、ひとつ確認してもよろしいですか?」
「何でしょう?」
ブリキ製のストーブから、杉の葉がバチリと跳ねるのに目を向けた近衛は、ゆっくりと立ち上がり、テーブルに挿された寒椿を一輪抜き取った。
「光留さんに根負けして、こちらに居られるのか? それとも光留さんが良いと、思われているのか?ぜひ、お聞かせ願いたい」
「まあ……そのようなこと」
「言えませんか?いいえ、先程も申したように恥ずかしいことでもなく、むしろ当然口にするべきことです。ただ、ここで前者と言われても光留さんは、ありがとうと言われるでしょう。何事も正直で良いのですよ? 逆に後々、本当は……となった方が困りますので」
「まるで私が仕方なく、こちらにいるかのような言い種ですわね?」
「そう聞こえましたか?別に他意はありません。ただ言葉ほど、わかり易く嬉しいことはないのですよ?」
近衛は肩をすくめてみせると、手にした寒椿を差し出した。
「鹿鳴館の夏の夜は、晃子さんにとって嬉しいお言葉ではありませんでしたか?」
「ええ、それはとても……」
手のひらの中にある寒椿が、薄明かりを灯すように晃子の指先に渡った。
「近衛様は 光留様が、私をお見初めになられたと思われているのでしょう?」
「それ以外の何があるというのです?光留さんの貴女への執着は……」
白い寒椿を口許に寄せる晃子は、クスリと笑った。
「私達は、鹿鳴館で出会ったのです。ご存知?」
「もちろん、聞き及んでおります」
「それでは、先に見初めたのが光留様と何故、わかるのです?」
「……は?」
「法科を出られた方は、頭が固いと聞いたことがありますが……本当なのかしら?」
小首を傾げ、フロックコートの胸ポケットへ、白い花弁を差し込む「とてもお似合いです」と、見上げる晃子は薄紅の唇に 微笑を称え、ゆっくりと言葉を紡ぐ。
「とても澄み渡った青空と、手入れがされた華々に誘われるように、足を踏み入れました。本当に何気なく……私は、そこで数人の学友に囲まれ、からかいの的になっていた学生を見ました。学帽を取り上げられ、囃し立てられていたのですが、卑怯にもご生母を侮辱しているようでした」
思わぬ語りに近衛は、相づちも忘れ聞き入った。目の前の美貌の令嬢は言葉ほど、わかり易く嬉しいことはない――と、云うことを実践しているのかも知れない。
「言い返せないのは、髪の色のせいだったのでしょう。しかし、私は腹が立ちました。親を侮辱する卑怯者達が、許せないほどに私は、綺麗な若様に魅入ってしまいました」
「あ、あの……それは」
「勿論、お気持ちは知りませんでした。弟の学友であり、留学もされた立派な方です。憧れに近い感情かもしれませんね……大それた考えなどありません。ただ、光留様が優しく言葉をかけられると、恥ずかしく知られまいと皆様にも?と、言ってしまって……ふふ!今では笑い話ですが。私の目には、陽光射し込む木々の風景が この上なく明媚に映ったのです。きっと光留様のせいでしょう」
呆然と立ち尽くす近衛に、晃子は笑う。
『皆様、皆様と仰いますが、何故そんなに気になるのです?僕が他のご令嬢と、どんな言葉を交わしているのか、お気になさっているのですか?』
夏の夜、馬車に押し入り、こう言った光留に「そうです」と、言えたらどんなに良かったかと。
何処と無く、歯切れが悪い様子に晃子が引っ掛かりを覚えたのは、今朝方のこと。
帰宅時間を、皆の前で宣言するという不思議ではあるが、なかなか効率的な習わしによって判明した光留の帰宅予定時刻にだ。
「ご用が長引くのでしょうか?」と、尋ねてはみたが、言葉を選んでいるのか「ん~、ええ」など、こちらも物が挟まった言い方。
2人が顔を会わせるのは、朝食と夕食時に限られている。もちろん、食後 談話をする程度の時間はあるのだが、やはり人の目もある為、込み入った話はない。
光留が部屋に現れることもなく、離れに晃子を呼ぶこともないのだから、正直、鹿鳴館で想いの丈を訴えてきたのは、何だったのだろう?と思う。
もしかしたら、晃子が過剰に考えているだけで本当は、そこまで興味を持っていないのではないか?と。何故なら根掘り葉掘り、行動を探っていた羽倉崎と比べ、淡白な様子が際立ち、そう思えてならないのだ。
そんな晃子の疑問に答えたのは、昼過ぎに津多子を訪ねて来たという客人だった。
肘掛けへ向けた顔が、失笑を浮かべ「まさか……」と漏らす。
「ガツガツ興味を示しては、プライドが許さないのでしょう。むしろ興味は、尽きることなく……と言った方が正しいかと」
口振りは、ずいぶんと落ち着いている。その上、司法官僚ゆえか? 小さな取っ掛かりから、話を引き出すのに長けているように感じた。元々晃子は、自分の考えを話すことが少ないが、近衛と会話をしていると些細なことから話を広げられ、会話が途切れることがない。
「近衛様は、光留様をよくご存知なのですね」
「まあ、親戚筋ということもあって、幼少の頃より存じておりますので。こんな風に晃子さんと、2人で夕食を頂いていることを知った時の顔まで、想像することが出来ますよ」
自身の人差し指を、両目尻に押し当てるとクイッと引き上げた。
「まあ、ふふ!面白い方」
「そういえば……夏の夜会で泰臣君と駒子さんと食事をご一緒しましたが、なかなか楽しいお嬢様で」
「ええ、思ったことをパッと口にされるのですが、それが嫌味でもないのです。羨ましい限り」
「貴女も、仰れば良いかと」
晃子は、静かな問いかけに首を振ると、箸を置いた。
「尋ねることが恥ずかしく、又、私が言うとトゲがあるように感じて……おそらく駒子さんとの、人となりの違いでしょう」
「そうですかね?私は、そのように感じませんが。それに、言葉にトゲがあっても光留さんには通用しませんよ?……あ、どうやら お戻りのようで」
近衛は、廊下を行き来する女中らの足音に、耳を傾ける仕草をする。
「光留さんのご両親の話をしておこうかと思ったのですが、又の機会にいたしましょう」
「それは、実の?」
「ええ、津多子夫人からも言われておりますので……ただ、ひとつ確認してもよろしいですか?」
「何でしょう?」
ブリキ製のストーブから、杉の葉がバチリと跳ねるのに目を向けた近衛は、ゆっくりと立ち上がり、テーブルに挿された寒椿を一輪抜き取った。
「光留さんに根負けして、こちらに居られるのか? それとも光留さんが良いと、思われているのか?ぜひ、お聞かせ願いたい」
「まあ……そのようなこと」
「言えませんか?いいえ、先程も申したように恥ずかしいことでもなく、むしろ当然口にするべきことです。ただ、ここで前者と言われても光留さんは、ありがとうと言われるでしょう。何事も正直で良いのですよ? 逆に後々、本当は……となった方が困りますので」
「まるで私が仕方なく、こちらにいるかのような言い種ですわね?」
「そう聞こえましたか?別に他意はありません。ただ言葉ほど、わかり易く嬉しいことはないのですよ?」
近衛は肩をすくめてみせると、手にした寒椿を差し出した。
「鹿鳴館の夏の夜は、晃子さんにとって嬉しいお言葉ではありませんでしたか?」
「ええ、それはとても……」
手のひらの中にある寒椿が、薄明かりを灯すように晃子の指先に渡った。
「近衛様は 光留様が、私をお見初めになられたと思われているのでしょう?」
「それ以外の何があるというのです?光留さんの貴女への執着は……」
白い寒椿を口許に寄せる晃子は、クスリと笑った。
「私達は、鹿鳴館で出会ったのです。ご存知?」
「もちろん、聞き及んでおります」
「それでは、先に見初めたのが光留様と何故、わかるのです?」
「……は?」
「法科を出られた方は、頭が固いと聞いたことがありますが……本当なのかしら?」
小首を傾げ、フロックコートの胸ポケットへ、白い花弁を差し込む「とてもお似合いです」と、見上げる晃子は薄紅の唇に 微笑を称え、ゆっくりと言葉を紡ぐ。
「とても澄み渡った青空と、手入れがされた華々に誘われるように、足を踏み入れました。本当に何気なく……私は、そこで数人の学友に囲まれ、からかいの的になっていた学生を見ました。学帽を取り上げられ、囃し立てられていたのですが、卑怯にもご生母を侮辱しているようでした」
思わぬ語りに近衛は、相づちも忘れ聞き入った。目の前の美貌の令嬢は言葉ほど、わかり易く嬉しいことはない――と、云うことを実践しているのかも知れない。
「言い返せないのは、髪の色のせいだったのでしょう。しかし、私は腹が立ちました。親を侮辱する卑怯者達が、許せないほどに私は、綺麗な若様に魅入ってしまいました」
「あ、あの……それは」
「勿論、お気持ちは知りませんでした。弟の学友であり、留学もされた立派な方です。憧れに近い感情かもしれませんね……大それた考えなどありません。ただ、光留様が優しく言葉をかけられると、恥ずかしく知られまいと皆様にも?と、言ってしまって……ふふ!今では笑い話ですが。私の目には、陽光射し込む木々の風景が この上なく明媚に映ったのです。きっと光留様のせいでしょう」
呆然と立ち尽くす近衛に、晃子は笑う。
『皆様、皆様と仰いますが、何故そんなに気になるのです?僕が他のご令嬢と、どんな言葉を交わしているのか、お気になさっているのですか?』
夏の夜、馬車に押し入り、こう言った光留に「そうです」と、言えたらどんなに良かったかと。
0
あなたにおすすめの小説

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

不器用な大富豪社長は、闇オクで買った花嫁を寵愛する
獅月@体調不良
恋愛
「 御前を幸せにする為に、俺は買ったんだ 」
〜 闇オク花嫁 〜
毒親である母親の為だけに生きてきた彼女は、
借金を得た母の言葉を聞き、
闇オークションへ売られる事になった。
どんな形にしろ借金は返済出来るし、
母の今後の生活面も確保出来る。
そう、彼女自身が生きていなくとも…。
生きる希望を無くし、
闇オークションに出品された彼女は
100億で落札された。
人食を好む大富豪か、
それとも肉体を求めてか…。
どちらにしろ、借金返済に、
安堵した彼女だが…。
いざ、落札した大富豪に引き渡されると、
その容姿端麗の美しい男は、
タワマンの最上階から5階部分、全てが自宅であり、
毎日30万のお小遣いですら渡し、
一流シェフによる三食デザート付きの食事、
なにより、彼のいない時間は好きにしていいという自由時間を言い渡した。
何一つ手を出して来ない男に疑問と不満を抱く日々……だが……?
表紙 ニジジャーニーから作成
エブリスタ同時公開

魔法師団長の家政婦辞めたら溺愛されました
iru
恋愛
小説家になろうですでに完結済みの作品です。よければお気に入りブックマークなどお願いします。
両親と旅をしている途中、魔物に襲われているところを、魔法師団に助けられたティナ。
両親は亡くなってしまったが、両親が命をかけて守ってくれた自分の命を無駄にせず強く生きていこうと決めた。
しかし、肉親も家もないティナが途方に暮れていると、魔物から助けてくれ、怪我の入院まで面倒を見てくれた魔法師団の団長レオニスから彼の家政婦として住み込みで働かないと誘われた。
魔物から助けられた時から、ひどく憧れていたレオニスの誘いを、ティナはありがたく受ける事にした。
自分はただの家政婦だと強く言い聞かせて、日に日に膨らむ恋心を抑え込むティナだった。
一方、レオニスもティナにどんどん惹かれていっていた。
初めはなくなった妹のようで放っては置けないと家政婦として雇ったが、その健気な様子に強く惹かれていった。
恋人になりたいが、年上で雇い主。
もしティナも同じ気持ちでないなら仕事まで奪ってしまうのではないか。
そんな思いで一歩踏み出せないレオニスだった。
そんな中ある噂から、ティナはレオニスの家政婦を辞めて家を出る決意をする。
レオニスは思いを伝えてティナを引き止めることができるのか?
両片思いのすれ違いのお話です。
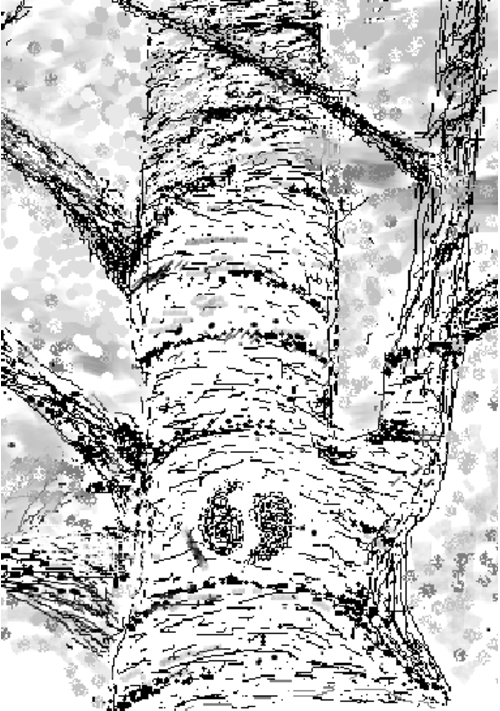
Pomegranate I
Uta Katagi
恋愛
婚約者の彼が突然この世を去った。絶望のどん底にいた詩に届いた彼からの謎のメッセージ。クラウド上に残されたファイルのパスワードと貸金庫の暗証番号のミステリーを解いた後に、詩が手に入れたものは?世代を超えて永遠の愛を誓った彼が遺したこの世界の驚愕の真理とは?詩は本当に彼と再会できるのか?
古代から伝承されたこの世界の秘密が遂に解き明かされる。最新の量子力学という現代科学の視点で古代ミステリーを暴いた長編ラブロマンス。これはもはや、ファンタジーの域を越えた究極の愛の物語。恋愛に憧れ愛の本質に悩み戸惑う人々に真実の愛とは何かを伝える作者渾身の超大作。
*本作品は「小説家になろう」にも掲載しています。

訳あり冷徹社長はただの優男でした
あさの紅茶
恋愛
独身喪女の私に、突然お姉ちゃんが子供(2歳)を押し付けてきた
いや、待て
育児放棄にも程があるでしょう
音信不通の姉
泣き出す子供
父親は誰だよ
怒り心頭の中、なしくずし的に子育てをすることになった私、橋本美咲(23歳)
これはもう、人生詰んだと思った
**********
この作品は他のサイトにも掲載しています

本日は桜・恋日和 ーツアーコンダクター 紫都の慕情の旅
光月海愛(こうつきみあ)
恋愛
旅は好きですか?
派遣添乗員(ツアーコンダクター)の桑崎紫都32歳。
もう、仕事がらみの恋愛はしないと思っていたのに…ーー
切ない過去を持つ男女四人の二泊三日の恋慕情。

【完結・おまけ追加】期間限定の妻は夫にとろっとろに蕩けさせられて大変困惑しております
紬あおい
恋愛
病弱な妹リリスの代わりに嫁いだミルゼは、夫のラディアスと期間限定の夫婦となる。
二年後にはリリスと交代しなければならない。
そんなミルゼを閨で蕩かすラディアス。
普段も優しい良き夫に困惑を隠せないミルゼだった…

王太子妃専属侍女の結婚事情
蒼あかり
恋愛
伯爵家の令嬢シンシアは、ラドフォード王国 王太子妃の専属侍女だ。
未だ婚約者のいない彼女のために、王太子と王太子妃の命で見合いをすることに。
相手は王太子の側近セドリック。
ところが、幼い見た目とは裏腹に令嬢らしからぬはっきりとした物言いのキツイ性格のシンシアは、それが元でお見合いをこじらせてしまうことに。
そんな二人の行く末は......。
☆恋愛色は薄めです。
☆完結、予約投稿済み。
新年一作目は頑張ってハッピーエンドにしてみました。
ふたりの喧嘩のような言い合いを楽しんでいただければと思います。
そこまで激しくはないですが、そういうのが苦手な方はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















