4 / 17
第一章:面影
第四話:交差点
しおりを挟む
誰もいない、屋上が好き。
変電室まで、パタパタと走っていく。雨風がしのげて、一人で過ごすには十分な場所だった。転ばなくて良かった、と蓮波綾は思っていた。
持ってきたオレンジジュースに口をつけると、ふーっと大きなため息が出た。膝を抱えて体育座りをするのが、彼女のクセだった。
スカートが汚れてしまうかもしれない、というような事に気が回るタイプではなかった。身なりに無関心なのだ。かと言って、それを指摘してくれるような身内や友人はいなかった。
どの位、ぼんやりと座っていただろうか。
「私は、望月君が好き」
綾は、自分に言い聞かせていた。
「ちょっと優しくされた位ですぐに勘違しちゃう所、おばさんにそっくりだよね。やっぱり親子なんだな」
昨日、望月リクから言われたその一言に、綾は酷く傷ついていた。実際、その通りだったからだ。人を怖いと思いながら、繋がりに飢えている。
けれど
再び、今度は強く自分に言い聞かせる。
あの人から私を救ってくれたのは、望月君だ。
私は、彼がいないと生きていけない。
絶対に。
あの人はお母さんと再婚してすぐに、私を犯すようになった。
「学校でもイジめられてるんでしょ?なら、僕にこんな事をされちゃうのもね。全部、綾ちゃんのせいなんだよ」
それがあの人の口癖だった。あの時の私は言われる通りだと思っていたから、痛くて怖かったけれど、受け入れていた。じわじわと自分が死んでゆくのを感じながら、何もしなかった。
お母さんは偽物の神様に祈ってばかりで、私の身に起きている事を知らない。
それどころか、あの人を神様の使いだと信じて頼り切っていた。
永遠に、この地獄は続くんだろうなって思った。今すぐここから逃げだせば、また話は変わるんだろうか。
でもその後は?
私も、お母さんと同じ。どうやって電気代を払ったら良いのか、分からない。
この命は、あとどのくらい頑張るつもりなんだろう。
もう、とっくに燃え尽きているのに。
毎日、そんな事ばかり考えていた。
高校受験のあの日までは。
◆
「蓮波?」
受験を終えてトボトボと帰宅の途に就こうとしていた時、声をかけて来たのがリクだった。あの人は私にしている事が露呈するのを恐れていた。体裁が大事だから、高校へ進学してくれと頼みこまれた。
お母さんは神様に祈れば全てがうまくいくと言って、あの人のいいなりだ。
彼に話掛けられたのは、あの日以来だった。私は男の人が、大嫌い。けれど初めて会話をした時から、この人の事は嫌いじゃなかった。
――確か名前は……
ぎこちなく固まって歩く綾に、リクが一方的に話しかけた。
「良かったね。この高校だったら、イジメもないよ。俺、引越しするんだ。同じ中学のヤツは居ないと思ってたけど、蓮波も一緒だったんだね」
私の名前、知ってるんだ。
綾はリクの顔をジッと見つめた。
あの日の事なんて、もう忘れちゃったかな。
女の子みたいな顔してる、と思った。だからあの時だって、嫌じゃなかったのかもしれない。
先生とよく二人で用具室にいた事を、綾は知っていた。元々は、いじめられっ子だった彼女の避難場所だったからだ。先生とリクが用具室でしていることも知っていた。あれが原因で、先生が学校を辞めていった事も。
最初は自分と同じことをされているのかと思って、怖かった。
けれど
同じ行為でも、意味が違う。
正解なのは私じゃなく、あなたの方。
「ねえ。男、嫌い?」
リクから唐突に言われた綾は、思わず反応してしまっていた。
「嫌い、大嫌い」
リクが笑顔になる。どうしてこの人は、笑ったりするんだろう。綾は歩みを止め、完全に立ち止まった。
リクの白くて長い指が伸びて来て、綾の手をそっと握った。
二人とも、とても冷たい手をしてる。
手を繋ぎながら二人で暫く歩いていると、こちらを見ずにリクが言った。
「俺、男が好きなんだ」
「……そう」
「俺たち、人と違うね」
綾は自然と、繋ぎ合う手に力を込めていた。
そっか。私たちは人と違うんだ。
普通じゃないんだ。
それだけ分かれば、良かったのかもしれない。ずっと、一人きりで生きてきたから。
「蓮波はさ」
「うん」
「男から、何かされてるよね」
最初は、学校で私が虐められている話をしているのかと思った。
空はどんよりと曇っていて、今にも雪が降りそうだ。綾は空を見上げると「違う」と小さく呟いた。
あんな事をされるくらいなら、クラスの男子みたいに殴ったり蹴ったりされた方がよっぽどマシだ。
違和感を感じて振り返ると、リクが立ち止まってじっと綾を見つめていた。笑顔が消えている。
「家から追い出しちゃえば?」
「えっ……」
「要らないよ、そんなヤツ」
雪がポツリポツリと舞い始め、高台をビュッと冷たい風が吹き付ける。綾は、この世にまるでリクと二人ぼっちになったような錯覚に陥っていた。
◆
綾はリクの指示通り、あの人との行為を録画すると、スマホごと児童相談所に送った。その中には、生々しい性暴力の記録が残っていた。
児童相談所に証拠が届いた頃、リクは警察に電話をかけ「友人が身内に性的暴行を受けている。証拠を児童相談所に送った」と通報をした。
すぐに児童相談所と警察の介入があって、あの人は逮捕された。後からわかった事だが、母親が入信していた新興宗教団体には被害者が複数おり、団体にも捜査が入ることとなった。裁判は、今もまだなお続いている。
養護施設で保護できる年齢を過ぎていたので、シェルターへの入所を勧められた。しかし頼れるものを失い、真実を突きつけられて、精神的に不安定な母親を見捨ててはおけなかった。
そう、入院が必要なほどに精神的に参ってしまっていたのは、綾の母親の方だったのである。
「娘には治療が必要なんです」
違うの、お母さん。
綾が直接話をしようとすると、未だに酷く取り乱してしまうので、福祉の介入は必須だった。もうずっと会話はしていない。福祉の人は、綾に母親から離れるよう説得を続けていた。
綾にはどうしても決断ができなかった。
綾にとって最も怖かったのは、暴発した母親が自死を選んでしまう事だった。だから一方的な思い込みで、母親が学校へちょくちょく相談の電話をしてしまっていても、黙ったまま耐えてきた。
これが、保健師の下田に話せていない家庭の事情だった。
それでも、あの人がいなくなった今の生活の方が、何倍も幸せ。
ずっと、不思議だった事がある。どうして、望月君は自分なんかに手を差し伸べてくれたんだろう。
リクは受験時の言葉通り、高校入学と同時に引っ越しをしいたが、苗字も変わっていた。
先生との一件が原因なんだろうか。学生であの事を知っているのは、私だけだ。
そしてその事は、望月君本人も知らない。
高校に入学して再び会った時、リクは淡々と「これからは、望月って呼んで」と言っただけだった。
「俺たち、人と違うね」
「俺、男が好きなんだ」
あの日の言葉が幾度となく蘇る。
望月君はもしかしたら、まだ先生の事を。
その事を本人に言うのは、止めようと思った。私たちは、似たもの同士。それだけでいい。他には何もいらない。
私たちは、二人ぼっち。
だって、普通じゃないから。
ほどなくして、儀式が始まった。
初めての日、綾はリクの望む全てを受け入れようと誓った。
けれど、たまに分からなくなる時がある。
私は?
私は一体、望月君とどうなっていきたいんだろう。
現実に引き戻された綾は、膝に顔を埋めた。目を閉じると半井ゼンジの顔が浮かんで来て、全身が熱くなる。胸がキュッとして、苦しい。
「後ろ、気をつけないと」
そうやって、言ってくれた。半井君の手は、大きくて優しい。
好きな人、いるのかな。考えただけで、今度は胸がチクチクと苦しくなってきた。震えるような、切ないため息がこぼれ落ちる。
考えるのは、今日だけ。
昼休みが終わったら、忘れる。
私は、望月君と二人ぼっちで生きてく。
キーンコーン、カーンコーン
昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
綾は立ち上がると、そのまま雨の降る屋上から出て、保健室へと向かった。
火照りを帯びた身体に、雨だれが染み渡る。
今までなら、ずぶ濡れでも何とも思わなかったのに。
心が揺れたその時、忘れるなよといいたげに腕の傷がキリッと痛んで、顔をしかめた。
「イヤイヤ切ったから、思った以上に力が入ったんじゃないの」
頭の中でリクの声がする。動揺して足を滑らせた綾は、階段から思いっきり転げ落ちてしまった。
「いた……」
「怪我してない?大丈夫?」
顔を上げると、空のお弁当箱を抱えた佐伯が、心配そうな顔をして覗き込んでいた。
◆
「どこも同じにしか見えないのって、俺だけ?」
「いや、俺もだよ」
放課後、新宿へと出てきたアラタと半井ゼンジは、予備校めぐりを終えてファーストフードで一休みしていた。
パンフレットに目を通してたゼンジが、アラタに話しかける。
「医学部を受けんのか」
うんざりとした顔で欠伸をしたアラタが答えた。
「歯学部だけどね。俺ん家、代々歯医者なんだよ。他にやりたい事もないしな……お前は?進路考えたりしてんの?」
「うーん、漠然となら」
「へえ、どこ」
「農学部とか?」
「意外。でも似合うかもな、牛のお産とかさ。その仏頂面でって考えると、ウケるわ」
「そんなに仏頂面かよ」
ゼンジは子供の頃から、感情を表に出すのが得意ではなかった。人間関係は狭く深くで良い。口下手な自覚もあったし、そういう所は父親譲りだと自分でも思う。身体を動かすのが好きだったから、スポーツを通してコミュニーケーションを図ってきた。
スポーツ………バスケ………更衣室。
男に向けられた、男共の性的な視線。
望月。
急に昼の出来事を思い出して、ゼンジはいたたまれない気持ちになっていた。
あれは事故だったんだと、誰かから肯定してもらいたい。
けれどこんな話を一体、誰にするんだ。
同級生と一緒にオナニーしてしまいました、なんて。
「なん、どしたん?深刻な顔しちゃって」
「今日の更衣室の事なんだけどさ。いっつもあんな感じなのか?」
ああーと言う顔をして、アラタはコーヒーに口を付けた
「あんな感じだよ。望月の事だろ」
「おん」
「なんつうの?ビッチキャラだよな。本人もあれで楽しんでるみたいでよ。童貞君を弄んで、何が楽しいんだか」
アラタとゼンジの目が合う
「悪い、お前の事を言いたかったわけじゃ……」
「うるせえよ」
妙にツボって、お互いにプッっと吹き出してしまった。腹を抱えながら、アラタが笑う。
「お前も大概に、ギャップが激しいんだよね。ま、奥手ってかさあー。あんな可愛い子にコクられても、フッちゃうんだもんなあ」
「俺にも好みってもんがあんだよ」
「あれでダメなら、どんなのだったら良いんだよ」
野路を思い浮かべたが、否応なしに望月の面影が上書きをしていってしまう。
冷たい頬。蛇のように這う舌。
熱に浮かされて赤く膨らんでいた、手首の傷。
切ない、喘ぎ声。
下半身が熱くなり始めたゼンジは、紙コップの氷を頬張ると、ボリボリ齧りながら「絶対に教えない」と言った。
アラタは、いつまでもヒーヒーと笑い続けていた。
「結構、長居しちゃったなー」
「お前がいつまでも笑ってっからだろ」
店を出ると、雨はかなり小降りになっていた。傘はささず、駅へ向かって歩いてゆく。
もう夕方になっていた。
ブラブラと二人で歩きながら、新宿駅の南口近くまできた時、アラタのスマホが鳴った。弥生からだった。電話口から聞こえる声は、不機嫌そのもの。ゴメンというジェスチャーをしながら、アラタが通りを離れていった。
ゼンジはぼんやりと、交差点から少し離れた場所で街を歩く人を見ていた。
傘をさしてる人、さしてない人
一人で歩いてる人、誰かと歩く人
たかだが特別快速で1時間ちょっとの場所なのに、こんなにも沢山の人がいる。帰宅ラッシュも重なって、通りは人でごった返していた。
俺の目の前を通り過ぎた人達は、きっとこの先、永遠にすれ違うことはないんだろう。というか、すれ違っても気が付かない。
俺も含めたこの風景全体が、舞台装置のようなもの。
人を見るのにも飽きてきて、オフィスビルに目を向けた時だった。
傘を差した望月リクの姿が目に入ったのは。
「えっ…」
最初、見間違いでもしたのかと思った。が、見慣れた制服と特徴的な口元。あの横顔は間違いなく、望月だ。
傘で隠れていて表情が分からないが、待ち合わせでもしているんだろうか。じっとそこに佇んだまま、動こうとしない。
ゼンジは、リクから目を離す事が出来なかった。
そのうちビルから若いサラリーマンが数人、賑やかに話ながら出てきた。
リクの傘が、彼らを追うようにして動く。アイツが待ち合わせをしているのではないことに、そこで初めて気づいた。
誰かの姿を、追っている。
サラリーマン達はそのまま交差点を渡ると、ビルの真向かいにあるカフェへと消えていった。
その瞬間、雨が完全に上がって、雲の切れ間から夕日が顔を覗かせた。
刺すような眩しさに目を窄めていたゼンジは、次の瞬間、信じられないものを見た。
人目も憚らず、とめどなく涙を流すリクの横顔。
夕日に照らされた涙はキラキラと輝き、足元からは光が反射している。
涙に濡れる、その横顔は神々しくさえあった。
あまりにも儚なく、美しい。
踊り場で見た、あの小さな後ろ姿が重なる。
紛れもない、望月リクという人間の素顔だった。
この街の、誰一人としてその美しさには気づいていない。すれ違う人々が、夕日に飲みこまれて影となって沈んでゆく。ゼンジは、この世界から切り離されてしまったかのような感覚を覚えていた。
リクの横顔が、酷く遠くに感じる。
捕まえておかないと、このまま消えてしまうそうだ。
触れてみたい、という思いが溢れ出てくる。
と、当時に激しい混乱がゼンジを襲っていた。
何が起きたのか分からない。
俺は、どうしてこんなに胸が苦しいんだろう。
無意識に、足が前へ出ていってしまう。
「おい、ゼンジ!」
肩を掴まれる感触と共に、アラタの声で我に返った。
「お前、大丈夫かよ。今、交差点に突っ込もうとしてたぞ。信号見ろよ!」
「え?ああ……悪い」
プァーっという音と共に、途切れることなく車が交差点を走り去ってゆく。
アラタの声を上の空で聞きながら、再びリクのいた方を見ると、彼は既に姿を消していた。
「ねえ。誰かを本当に好きになった事って、ある?」
帰りの車内、満員電車に揺られながらずっと望月の言葉が、俺の頭を駆け巡り続けていた。
俺はまだ、人を好きになるのがどういう事なのか、知らない。
◆
家路に着き、シャワー浴びてベッドに倒れ込んでも、まだ望月リクの事が頭から消えなかった。
泥のように疲れているのに、滅茶苦茶に引っ掻きまわされた情緒が、執拗に身体を追従してゆく。
「やめないで」
「ねえ、この傷っていつ出来たの?」
俺の傷痕を愛撫した、細くて長い指。
湿気と汗にまみれた二人の肌。
冷たい、踊り場の床。
疼くような快感がリフレインしてきて、気づけば硬くなった下半身に手をやっていた。
「ンッ…クッ」
自分の手なのに、望月にそうされているようで、扱くのを止められない。
「ねえ…ハァ…俺も、いい?」
俺の背中を何度も行き来した、望月のヌメヌメとしたアレの感触が蘇ってくる。
思わず熱いため息が、零れ落ちた。先端から出てくる上澄みのような液体を絡ませ、一心不乱に上下させる。
あの身体を押し倒して、一番深いところまで舐めてみたい。
「ああっ…もうっ」
リクの切ない声が脳内に響き渡る。
「アッ……ッッ!!」
怒張しきったソレ握りしめたゼンジは、ギュッと身を縮こませると、そのまま果てた。
果てる瞬間、脳裏に浮かんでいたのは、涙を流す望月の横顔だった。
あの横顔を俺は穢したいって思っているのか。
欲望と恋慕の狭間を、波のような罪悪感が押し寄せてくる。
「何がしてえんだよ、俺は」
自分の手にべっとりとついた分身を見つめながら、ゼンジは独り言ちた。
変電室まで、パタパタと走っていく。雨風がしのげて、一人で過ごすには十分な場所だった。転ばなくて良かった、と蓮波綾は思っていた。
持ってきたオレンジジュースに口をつけると、ふーっと大きなため息が出た。膝を抱えて体育座りをするのが、彼女のクセだった。
スカートが汚れてしまうかもしれない、というような事に気が回るタイプではなかった。身なりに無関心なのだ。かと言って、それを指摘してくれるような身内や友人はいなかった。
どの位、ぼんやりと座っていただろうか。
「私は、望月君が好き」
綾は、自分に言い聞かせていた。
「ちょっと優しくされた位ですぐに勘違しちゃう所、おばさんにそっくりだよね。やっぱり親子なんだな」
昨日、望月リクから言われたその一言に、綾は酷く傷ついていた。実際、その通りだったからだ。人を怖いと思いながら、繋がりに飢えている。
けれど
再び、今度は強く自分に言い聞かせる。
あの人から私を救ってくれたのは、望月君だ。
私は、彼がいないと生きていけない。
絶対に。
あの人はお母さんと再婚してすぐに、私を犯すようになった。
「学校でもイジめられてるんでしょ?なら、僕にこんな事をされちゃうのもね。全部、綾ちゃんのせいなんだよ」
それがあの人の口癖だった。あの時の私は言われる通りだと思っていたから、痛くて怖かったけれど、受け入れていた。じわじわと自分が死んでゆくのを感じながら、何もしなかった。
お母さんは偽物の神様に祈ってばかりで、私の身に起きている事を知らない。
それどころか、あの人を神様の使いだと信じて頼り切っていた。
永遠に、この地獄は続くんだろうなって思った。今すぐここから逃げだせば、また話は変わるんだろうか。
でもその後は?
私も、お母さんと同じ。どうやって電気代を払ったら良いのか、分からない。
この命は、あとどのくらい頑張るつもりなんだろう。
もう、とっくに燃え尽きているのに。
毎日、そんな事ばかり考えていた。
高校受験のあの日までは。
◆
「蓮波?」
受験を終えてトボトボと帰宅の途に就こうとしていた時、声をかけて来たのがリクだった。あの人は私にしている事が露呈するのを恐れていた。体裁が大事だから、高校へ進学してくれと頼みこまれた。
お母さんは神様に祈れば全てがうまくいくと言って、あの人のいいなりだ。
彼に話掛けられたのは、あの日以来だった。私は男の人が、大嫌い。けれど初めて会話をした時から、この人の事は嫌いじゃなかった。
――確か名前は……
ぎこちなく固まって歩く綾に、リクが一方的に話しかけた。
「良かったね。この高校だったら、イジメもないよ。俺、引越しするんだ。同じ中学のヤツは居ないと思ってたけど、蓮波も一緒だったんだね」
私の名前、知ってるんだ。
綾はリクの顔をジッと見つめた。
あの日の事なんて、もう忘れちゃったかな。
女の子みたいな顔してる、と思った。だからあの時だって、嫌じゃなかったのかもしれない。
先生とよく二人で用具室にいた事を、綾は知っていた。元々は、いじめられっ子だった彼女の避難場所だったからだ。先生とリクが用具室でしていることも知っていた。あれが原因で、先生が学校を辞めていった事も。
最初は自分と同じことをされているのかと思って、怖かった。
けれど
同じ行為でも、意味が違う。
正解なのは私じゃなく、あなたの方。
「ねえ。男、嫌い?」
リクから唐突に言われた綾は、思わず反応してしまっていた。
「嫌い、大嫌い」
リクが笑顔になる。どうしてこの人は、笑ったりするんだろう。綾は歩みを止め、完全に立ち止まった。
リクの白くて長い指が伸びて来て、綾の手をそっと握った。
二人とも、とても冷たい手をしてる。
手を繋ぎながら二人で暫く歩いていると、こちらを見ずにリクが言った。
「俺、男が好きなんだ」
「……そう」
「俺たち、人と違うね」
綾は自然と、繋ぎ合う手に力を込めていた。
そっか。私たちは人と違うんだ。
普通じゃないんだ。
それだけ分かれば、良かったのかもしれない。ずっと、一人きりで生きてきたから。
「蓮波はさ」
「うん」
「男から、何かされてるよね」
最初は、学校で私が虐められている話をしているのかと思った。
空はどんよりと曇っていて、今にも雪が降りそうだ。綾は空を見上げると「違う」と小さく呟いた。
あんな事をされるくらいなら、クラスの男子みたいに殴ったり蹴ったりされた方がよっぽどマシだ。
違和感を感じて振り返ると、リクが立ち止まってじっと綾を見つめていた。笑顔が消えている。
「家から追い出しちゃえば?」
「えっ……」
「要らないよ、そんなヤツ」
雪がポツリポツリと舞い始め、高台をビュッと冷たい風が吹き付ける。綾は、この世にまるでリクと二人ぼっちになったような錯覚に陥っていた。
◆
綾はリクの指示通り、あの人との行為を録画すると、スマホごと児童相談所に送った。その中には、生々しい性暴力の記録が残っていた。
児童相談所に証拠が届いた頃、リクは警察に電話をかけ「友人が身内に性的暴行を受けている。証拠を児童相談所に送った」と通報をした。
すぐに児童相談所と警察の介入があって、あの人は逮捕された。後からわかった事だが、母親が入信していた新興宗教団体には被害者が複数おり、団体にも捜査が入ることとなった。裁判は、今もまだなお続いている。
養護施設で保護できる年齢を過ぎていたので、シェルターへの入所を勧められた。しかし頼れるものを失い、真実を突きつけられて、精神的に不安定な母親を見捨ててはおけなかった。
そう、入院が必要なほどに精神的に参ってしまっていたのは、綾の母親の方だったのである。
「娘には治療が必要なんです」
違うの、お母さん。
綾が直接話をしようとすると、未だに酷く取り乱してしまうので、福祉の介入は必須だった。もうずっと会話はしていない。福祉の人は、綾に母親から離れるよう説得を続けていた。
綾にはどうしても決断ができなかった。
綾にとって最も怖かったのは、暴発した母親が自死を選んでしまう事だった。だから一方的な思い込みで、母親が学校へちょくちょく相談の電話をしてしまっていても、黙ったまま耐えてきた。
これが、保健師の下田に話せていない家庭の事情だった。
それでも、あの人がいなくなった今の生活の方が、何倍も幸せ。
ずっと、不思議だった事がある。どうして、望月君は自分なんかに手を差し伸べてくれたんだろう。
リクは受験時の言葉通り、高校入学と同時に引っ越しをしいたが、苗字も変わっていた。
先生との一件が原因なんだろうか。学生であの事を知っているのは、私だけだ。
そしてその事は、望月君本人も知らない。
高校に入学して再び会った時、リクは淡々と「これからは、望月って呼んで」と言っただけだった。
「俺たち、人と違うね」
「俺、男が好きなんだ」
あの日の言葉が幾度となく蘇る。
望月君はもしかしたら、まだ先生の事を。
その事を本人に言うのは、止めようと思った。私たちは、似たもの同士。それだけでいい。他には何もいらない。
私たちは、二人ぼっち。
だって、普通じゃないから。
ほどなくして、儀式が始まった。
初めての日、綾はリクの望む全てを受け入れようと誓った。
けれど、たまに分からなくなる時がある。
私は?
私は一体、望月君とどうなっていきたいんだろう。
現実に引き戻された綾は、膝に顔を埋めた。目を閉じると半井ゼンジの顔が浮かんで来て、全身が熱くなる。胸がキュッとして、苦しい。
「後ろ、気をつけないと」
そうやって、言ってくれた。半井君の手は、大きくて優しい。
好きな人、いるのかな。考えただけで、今度は胸がチクチクと苦しくなってきた。震えるような、切ないため息がこぼれ落ちる。
考えるのは、今日だけ。
昼休みが終わったら、忘れる。
私は、望月君と二人ぼっちで生きてく。
キーンコーン、カーンコーン
昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴った。
綾は立ち上がると、そのまま雨の降る屋上から出て、保健室へと向かった。
火照りを帯びた身体に、雨だれが染み渡る。
今までなら、ずぶ濡れでも何とも思わなかったのに。
心が揺れたその時、忘れるなよといいたげに腕の傷がキリッと痛んで、顔をしかめた。
「イヤイヤ切ったから、思った以上に力が入ったんじゃないの」
頭の中でリクの声がする。動揺して足を滑らせた綾は、階段から思いっきり転げ落ちてしまった。
「いた……」
「怪我してない?大丈夫?」
顔を上げると、空のお弁当箱を抱えた佐伯が、心配そうな顔をして覗き込んでいた。
◆
「どこも同じにしか見えないのって、俺だけ?」
「いや、俺もだよ」
放課後、新宿へと出てきたアラタと半井ゼンジは、予備校めぐりを終えてファーストフードで一休みしていた。
パンフレットに目を通してたゼンジが、アラタに話しかける。
「医学部を受けんのか」
うんざりとした顔で欠伸をしたアラタが答えた。
「歯学部だけどね。俺ん家、代々歯医者なんだよ。他にやりたい事もないしな……お前は?進路考えたりしてんの?」
「うーん、漠然となら」
「へえ、どこ」
「農学部とか?」
「意外。でも似合うかもな、牛のお産とかさ。その仏頂面でって考えると、ウケるわ」
「そんなに仏頂面かよ」
ゼンジは子供の頃から、感情を表に出すのが得意ではなかった。人間関係は狭く深くで良い。口下手な自覚もあったし、そういう所は父親譲りだと自分でも思う。身体を動かすのが好きだったから、スポーツを通してコミュニーケーションを図ってきた。
スポーツ………バスケ………更衣室。
男に向けられた、男共の性的な視線。
望月。
急に昼の出来事を思い出して、ゼンジはいたたまれない気持ちになっていた。
あれは事故だったんだと、誰かから肯定してもらいたい。
けれどこんな話を一体、誰にするんだ。
同級生と一緒にオナニーしてしまいました、なんて。
「なん、どしたん?深刻な顔しちゃって」
「今日の更衣室の事なんだけどさ。いっつもあんな感じなのか?」
ああーと言う顔をして、アラタはコーヒーに口を付けた
「あんな感じだよ。望月の事だろ」
「おん」
「なんつうの?ビッチキャラだよな。本人もあれで楽しんでるみたいでよ。童貞君を弄んで、何が楽しいんだか」
アラタとゼンジの目が合う
「悪い、お前の事を言いたかったわけじゃ……」
「うるせえよ」
妙にツボって、お互いにプッっと吹き出してしまった。腹を抱えながら、アラタが笑う。
「お前も大概に、ギャップが激しいんだよね。ま、奥手ってかさあー。あんな可愛い子にコクられても、フッちゃうんだもんなあ」
「俺にも好みってもんがあんだよ」
「あれでダメなら、どんなのだったら良いんだよ」
野路を思い浮かべたが、否応なしに望月の面影が上書きをしていってしまう。
冷たい頬。蛇のように這う舌。
熱に浮かされて赤く膨らんでいた、手首の傷。
切ない、喘ぎ声。
下半身が熱くなり始めたゼンジは、紙コップの氷を頬張ると、ボリボリ齧りながら「絶対に教えない」と言った。
アラタは、いつまでもヒーヒーと笑い続けていた。
「結構、長居しちゃったなー」
「お前がいつまでも笑ってっからだろ」
店を出ると、雨はかなり小降りになっていた。傘はささず、駅へ向かって歩いてゆく。
もう夕方になっていた。
ブラブラと二人で歩きながら、新宿駅の南口近くまできた時、アラタのスマホが鳴った。弥生からだった。電話口から聞こえる声は、不機嫌そのもの。ゴメンというジェスチャーをしながら、アラタが通りを離れていった。
ゼンジはぼんやりと、交差点から少し離れた場所で街を歩く人を見ていた。
傘をさしてる人、さしてない人
一人で歩いてる人、誰かと歩く人
たかだが特別快速で1時間ちょっとの場所なのに、こんなにも沢山の人がいる。帰宅ラッシュも重なって、通りは人でごった返していた。
俺の目の前を通り過ぎた人達は、きっとこの先、永遠にすれ違うことはないんだろう。というか、すれ違っても気が付かない。
俺も含めたこの風景全体が、舞台装置のようなもの。
人を見るのにも飽きてきて、オフィスビルに目を向けた時だった。
傘を差した望月リクの姿が目に入ったのは。
「えっ…」
最初、見間違いでもしたのかと思った。が、見慣れた制服と特徴的な口元。あの横顔は間違いなく、望月だ。
傘で隠れていて表情が分からないが、待ち合わせでもしているんだろうか。じっとそこに佇んだまま、動こうとしない。
ゼンジは、リクから目を離す事が出来なかった。
そのうちビルから若いサラリーマンが数人、賑やかに話ながら出てきた。
リクの傘が、彼らを追うようにして動く。アイツが待ち合わせをしているのではないことに、そこで初めて気づいた。
誰かの姿を、追っている。
サラリーマン達はそのまま交差点を渡ると、ビルの真向かいにあるカフェへと消えていった。
その瞬間、雨が完全に上がって、雲の切れ間から夕日が顔を覗かせた。
刺すような眩しさに目を窄めていたゼンジは、次の瞬間、信じられないものを見た。
人目も憚らず、とめどなく涙を流すリクの横顔。
夕日に照らされた涙はキラキラと輝き、足元からは光が反射している。
涙に濡れる、その横顔は神々しくさえあった。
あまりにも儚なく、美しい。
踊り場で見た、あの小さな後ろ姿が重なる。
紛れもない、望月リクという人間の素顔だった。
この街の、誰一人としてその美しさには気づいていない。すれ違う人々が、夕日に飲みこまれて影となって沈んでゆく。ゼンジは、この世界から切り離されてしまったかのような感覚を覚えていた。
リクの横顔が、酷く遠くに感じる。
捕まえておかないと、このまま消えてしまうそうだ。
触れてみたい、という思いが溢れ出てくる。
と、当時に激しい混乱がゼンジを襲っていた。
何が起きたのか分からない。
俺は、どうしてこんなに胸が苦しいんだろう。
無意識に、足が前へ出ていってしまう。
「おい、ゼンジ!」
肩を掴まれる感触と共に、アラタの声で我に返った。
「お前、大丈夫かよ。今、交差点に突っ込もうとしてたぞ。信号見ろよ!」
「え?ああ……悪い」
プァーっという音と共に、途切れることなく車が交差点を走り去ってゆく。
アラタの声を上の空で聞きながら、再びリクのいた方を見ると、彼は既に姿を消していた。
「ねえ。誰かを本当に好きになった事って、ある?」
帰りの車内、満員電車に揺られながらずっと望月の言葉が、俺の頭を駆け巡り続けていた。
俺はまだ、人を好きになるのがどういう事なのか、知らない。
◆
家路に着き、シャワー浴びてベッドに倒れ込んでも、まだ望月リクの事が頭から消えなかった。
泥のように疲れているのに、滅茶苦茶に引っ掻きまわされた情緒が、執拗に身体を追従してゆく。
「やめないで」
「ねえ、この傷っていつ出来たの?」
俺の傷痕を愛撫した、細くて長い指。
湿気と汗にまみれた二人の肌。
冷たい、踊り場の床。
疼くような快感がリフレインしてきて、気づけば硬くなった下半身に手をやっていた。
「ンッ…クッ」
自分の手なのに、望月にそうされているようで、扱くのを止められない。
「ねえ…ハァ…俺も、いい?」
俺の背中を何度も行き来した、望月のヌメヌメとしたアレの感触が蘇ってくる。
思わず熱いため息が、零れ落ちた。先端から出てくる上澄みのような液体を絡ませ、一心不乱に上下させる。
あの身体を押し倒して、一番深いところまで舐めてみたい。
「ああっ…もうっ」
リクの切ない声が脳内に響き渡る。
「アッ……ッッ!!」
怒張しきったソレ握りしめたゼンジは、ギュッと身を縮こませると、そのまま果てた。
果てる瞬間、脳裏に浮かんでいたのは、涙を流す望月の横顔だった。
あの横顔を俺は穢したいって思っているのか。
欲望と恋慕の狭間を、波のような罪悪感が押し寄せてくる。
「何がしてえんだよ、俺は」
自分の手にべっとりとついた分身を見つめながら、ゼンジは独り言ちた。
0
あなたにおすすめの小説
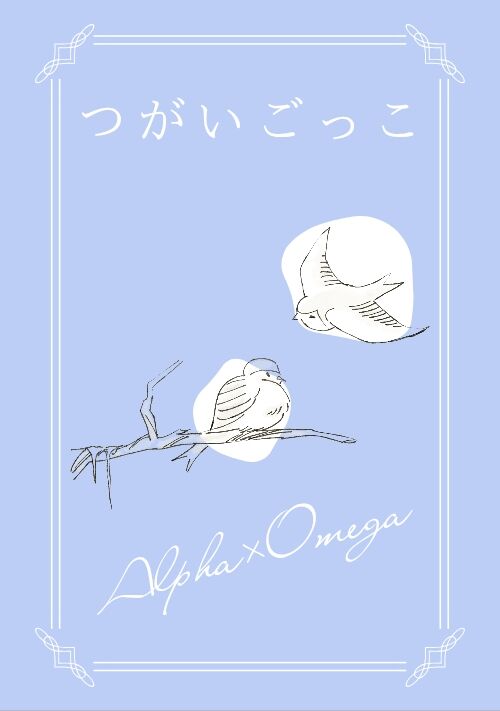
つがいごっこ~4歳のときに番ったらしいアルファと30歳で再会しまして~
深山恐竜
BL
俺は4歳のときにうなじを噛まれて番を得た。
子どもがたくさんいる遊び場で、気が付いたらそうなっていたとか。
相手は誰かわからない。
うなじに残る小さな歯型と、顔も知らない番。
しかし、そのおかげで、番がいないオメガに制限をかけられる社会で俺は自由に生きていた。
そんなある日、俺は番と再会する。
彼には俺の首筋を噛んだという記憶がなかった。
そのせいで、自由を謳歌していた俺とは反対に、彼は苦しんできたらしい。
彼はオメガのフェロモンも感じられず、しかし親にオメガと番うように強制されたことで、すっかりオメガを怖がるようになっていた。
「でも、あなただけは平気なんです。なんででしょう」
首を傾げる彼に、俺は提案する。
「なぁ、俺と番ごっこをしないか?」
偽物の番となった本物の番が繰り広げるラブストーリー。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。


処刑エンドの悪役公爵、隠居したいのに溺愛されてます
ひなた翠
BL
目が覚めたら、やり込んだBLゲームの悪役公爵になっていた。
しかも手には鞭。目の前には涙を浮かべた美少年。
——このままじゃ、王太子に処刑される。
前世は冴えない社畜サラリーマン。今世は冷徹な美貌を持つ高位貴族のアルファ。
中身と外見の落差に戸惑う暇もなく、エリオットは処刑回避のための「隠居計画」を立てる。
囚われのオメガ・レオンを王太子カイルに引き渡し、爵位も領地も全部手放して、ひっそり消える——はずだった。
ところが動くほど状況は悪化していく。
レオンを自由にしようとすれば「傍にいたい」と縋りつかれ、
カイルに会えば「お前の匂いは甘い」と迫られ、
隠居を申し出れば「逃げるな」と退路を塞がれる。
しかもなぜか、子供の頃から飲んでいた「ビタミン剤」を忘れるたび、身体がおかしくなる。
周囲のアルファたちの視線が絡みつき、カイルの目の色が変わり——
自分でも知らなかった秘密が暴かれたとき、逃げ場はもう、どこにもなかった。
誰にも愛されなかった男が、異世界で「本当の自分」を知り、運命の番と出会う——
ギャップ萌え×じれったさ×匂いフェチ全開の、オメガバース転生BL。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

だって、君は210日のポラリス
大庭和香
BL
モテ属性過多男 × モブ要素しかない俺
モテ属性過多の理央は、地味で凡庸な俺を平然と「恋人」と呼ぶ。大学の履修登録も丸かぶりで、いつも一緒。
一方、平凡な小市民の俺は、旅行先で両親が事故死したという連絡を受け、
突然人生の岐路に立たされた。
――立春から210日、夏休みの終わる頃。
それでも理央は、変わらず俺のそばにいてくれて――
📌別サイトで読み切りの形で投稿した作品を、連載形式に切り替えて投稿しています。
エピローグまで公開いたしました。14,000字程度になりました。読み切りの形のときより短くなりました……1000文字ぐらい書き足したのになぁ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















