8 / 17
第二章:すれ違う横顔
第八話:告白
しおりを挟む
週が明けても、梅雨が明けることはなかった。まるで東京だけが、時間が逆行しているかのように、雨が振り続けている。学校は、朝からどの教室にも照明が灯っていた。
半井ゼンジと望月リクの教室も、それは同じだった。
ザワザワ……
「――なんていうか……」
「笑えないよな」
「また傷、増えてない?」
「ちょっと怖いんだけど……」
「ウリやってるって噂、マジ?」
「おはよ。誰の話してんの?」
リクは、クラスメイトのヒソヒソ声へと応えるようにして、ニコッと笑うと手を振ってみせた。眼帯は外れたが、まだ右目の痣は生々しい。教室の空気がサーッと凍る。そそくさと背中を向けたかと思うと、一斉に沈黙してしまった。
リクは笑顔のまま声に出さす、口だけを動かした。
『バーカ』
そうしていつものように窓際の席に着くと、鞄を机に放り出して投げやりに座った。空はどす黒く曇っていて、また一雨来そうだった。
「え?弥生と喧嘩してた?」
「嘘だろ。気づいてなかったの?」
「いや……最近、見ないな……とは思ってたけど」
「えぇ……」
ゼンジがアラタと話ながら、教室に入ってくる。「弥生と仲直りしたんなら、期末テストの勉強……」とアラタに言いかけて、顔を上げたゼンジは絶句した。
呆然と見つめる視線の先には、傷だらけのリクが座っていた。
手に持っていたスマホが音を立てて落ち、教室の視線がにわかに集中する。
「――望月……」
目の傷痕もまだ痛々しいというのに、どう見てもロープで縛ったとしか思えない首の擦り傷と、赤紫の痣。手首も同様の状態になっていて満足に消毒もしてないのか、所々、血が滲んでいた。
本人も開き直っているのか、いつかのように長袖で隠そうはせず、半袖シャツのままだった。
硬直して立ち尽くしたまま自分を見ているゼンジに気づいたリクは、じっと見つめ返すと手首の傷をヒラヒラと振りながら嘲笑してみせた。
「おはよ、半井。何見てんの。もしかしてこういうの、興奮するタイプ?」
「……!」
ゼンジは脇目もふらずにツカツカとリクの方へ歩み寄っていくと、二の腕を力任せに掴んだ。ゼンジの目が燃えるような怒りを帯びて、カッと見開かれている。他人事のように、半井ってこういう顔もするんだ……とぼんやり俯瞰しているリクがいた。
「立て」
有無を言わさない激しい口調だった。そのまま、掴んだ腕をグッと引っ張り上げる。リクは何故だか、ゼンジから視線を逸らせて俯いてしまっていた。
「立てって言ってるだろ!望月!」
その声で、ぼんやりと我に返る。リクはゼンジから引き摺られるようにして、教室から出ようとしている所だった。ゼンジの力が強すぎて、振り払おうにも振り払えない。
だけどさ
いくら半井がそんな事したって、俺は絶対に変わらないよ。
お前になんか、一生分からない。何も、出来ない。
俺は、玩具でいたいんだ。徹底的に破壊してもらいたいんだよ。
それをしなかった、お前が悪いんじゃないか。半井。
時間にして、5分あるかないかの出来事だった。後から教室に入ってきたクラスメイトが出ていく二人とすれ違って、ポカーンとしながらその後姿を見ていた。
再び、教室がざわめきだす。
「え、何?何?あの二人。どういう事?」
「半井君、めっちゃキレてたよね」
「てか、あの二人が喋ってるトコ、初めて見た」
「でもあれ?この間、一緒に帰ってなかった?」
アラタは、クラスメイトのヒソヒソ話を聞きながら、なんとも言えない居心地の悪さを感じていた。ゼンジの落としたスマホを拾いあげると、机に置いてやった。そうして着席すると誰にも聞こえぬよう、小さなため息をついた。
◆
半井ゼンジが着替えに使っていた、旧校舎の踊り場。初めて望月リクと関係をもった場所。
ゼンジは力任せにリクを引きずってそこに連れてくると、かび臭く湿った体育マットに、彼の小さくて白い身体を叩きつけた。
恐ろしく醒めた声で、ゼンジが言う。
「いい加減にしろよ。そんな事して何が楽しい」
持っていた鞄から、ミネラルウォーターを取り出す。リクの茶色くサラサラとした髪の上からドバドバとかけ、空になったペットボトルをリクに向かって叩きつけた。
傷痕に水が滲みて、ヒリヒリとした痛みがリクを襲っていた。なのに全てが他人事で、もう一人の剥がれた自分がその様子を眺めている。リクは惨めな自分を嘲りながら、場違いな事を考えていた。
今ここで、思いっきり半井に首絞められながらヤりたいな。滅茶苦茶に気持ち良さそう。怒ってるコイツの表情、エロくてゾクゾクするもん。その顔で俺を便所みたいにしてくんないかなあ……
お前になんか、一生分からない。何も、出来ない。
何、青くっさい事思っちゃってんの、俺。マジでウケる。
アホみてえな事考えながら、ガチガチに勃起してんのが本来の俺だろ?
ずぶ濡れのリクは、思わず自嘲的な笑みをこぼしてしまっていた。痛々しい姿を晒し、自虐的に鼻でせせら笑うリクの様子は、ゼンジの怒りに火を注ぐには十分すぎる程だった。
どうして、そうまでして自分を痛めつける?
交通事故に遭って、背中に傷を作った時より、胸が痛む。俺の事じゃないのに。言い争う、祖母と母親を見ていた時より、悲しい。お前は家族じゃなく、他人なのに。
ゼンジは、その切れ長の瞳から涙を流していた。震える声で、リクに語りかける。
「なんで、分かんないんだよ……どうして、伝わらな……」
途中からもう言葉にならない。肉体的に大人として完成しつつあるゼンジが、同級生であるリクの前で嗚咽する姿は、過渡期独特のアンバランスさを孕んでいた。危うくも、美しい。今にも壊れてしまいそうな、そういった類のもの。
リクもまたそんなゼンジの姿を見て、生まれて初めての感情に飲み込まれ困惑していた。
触れてみたい。
どうしようもなく甘く、切ない、涙がこみ上げてくるような感情。
先生にも抱いたことのない、感情。
あの日、家で眠ってしまっていた半井に、口づけをした。
俺はなんであんな事をした?分からない。
溢れ出しそうになって、無意識に蓋をしてしまった。
柔らかく締め付けられるような胸の痛みが、濁流のように押し寄せてくる。このままでは、俺は飲み込まれてしまう。俺は死んでしまう。リクは激しい混乱で、平衡感覚を失ったような感覚に囚われていた。泣きじゃくるゼンジ以外の全てが、ぐにゃりとひしゃげて見える。
その瞬間だった。
ゼンジが、ずぶ濡れのリクを思い切り抱きしめたのは。涙で濡れた唇が重なる。温かい唇だった。ゼンジの吐息と共に入ってきたのは、リクが生まれてから一度も味わったことのない、何かだった。
ペルソナが外れ、素顔の望月リクが姿を現す。
彼は混乱の果てに、酷く怯えきっていた。
「やめろよ!離せ!」
リクは叫んでいた。
激しくもがき出したリクを離さないよう、ゼンジは抱きしめる腕を強めた。そうして出来たばかりの傷に、愛おしそうな口づけをする。
さっきかけられた水とはまるで違う。
半井の涙が濡らしていった傷は、ヤスリで擦られているみたいに痛い。
「――望月……」
ゼンジの真剣な声が聞こえてきた。リクの顔は最早、青ざめていた。
やめろ……その先を言うな。
これ以上、俺の中に入ってこないでくれ!
「望月、好きだ」
「――嫌だ……」
「好きだ」
暴れるリクをそっと引き寄せ、再び唇を重ねる。もうこれ以上、何をどう伝えたらいいのか分からない。それはゼンジにとっても初めての感情だった。
確かに、中学の時のあれは初恋だったんだろうと思う。けれども、彼女が転校してしまった後、俺は失う恐怖になんか怯えなかった。少しの間、寂しかっただけ。
なのに、今は。
俺は、望月を失うのが怖い。
ドンッ!
こんな小さな身体のどこにそれ程の力があるんだ、と言わんばかりの勢いで、リクがゼンジを突き飛ばした。息は酷く乱れ、幽霊のように白い身体が小刻みに震えている。
下唇を噛んだリクの表情は、恐怖で強張っていた。
「やめろって言ってんだろ!ちょっとくらい俺にチンコ弄ってもらったからって、勘違いしてんじゃねえよ!」
「……俺だって、勘違いであって欲しかった」
ゼンジの頬をツ――……と再び涙が伝った。髪を結んでいたゴムが落ちて、緩いくせ毛が肩に垂れる。その面影が先生……飯山ハルキと重なって、リクは悲鳴を上げそうになった。
どうしてそれを言うのが先生じゃなくて、お前なんだよ!
「うるさい!俺は、お前のモノじゃない!」
「……分かってる」
「お前になんか、一生分からない。何も、出来ない!」
リクの肩はなおも小刻みに震えていた。目には涙を浮かべている。
「どうして入ってくるのがお前なんだよ……お前は、俺を殺せないくせに!」
大粒の涙をこぼし悲痛な叫び声を上げたリクは、踊り場から走り去っていってしまった。
ゼンジはリクの心を、素手でズタズタにしてしまったような気がして、その場に座り込んでしまった。絶望したような表情で、手のひらを見つめる。
心の置き場を、もう何処にもっていったら良いのか分からない。
「……俺だって、どうしてお前なのか、分かんねえよ」
そう独りごちるとカビ臭いマットにもたれかかって、両手で顔を覆った。
◆
「望月君、どうしたの、怪我……」
「起きろよ」
掛け布団を乱暴に剥ぎ取られる。保健室で横になっていた蓮波綾は、首と手首に傷を作り、ずぶ濡れになっている望月リクの姿をじっと見つめていた。
まるで、昔の私みたい。何があったの、望月君。
キーンコーンカーンコーン――……
終業のチャイムが鳴る。生徒たちの廊下へ出てきた賑わいが、ドア越しに交差し始めた。リクは綾の腕を掴むと、無理やり立たせて腕を引っ張った。
儀式をするんだろうか。
刺すような胸の痛みに、綾は顔を歪めていた。職員室の前での一件以来、彼女はリクと会話をしていなかった。
あれから、望月君は学校を休んだ。登校してきたのは、先週の終わりから。心配はしていたけど、私には自分から連絡を取る勇気がない。
連絡が取れた所で何を話したらいいのか、分からない。
二人は知り合ってから一度も、学校の外で会った事がない。高校に入ってからは、スマホで連絡をとった事もなかった。
イライラとした様子のリクにされるがまま、腕を引っ張られ保健室から出ようとした所で聞き慣れた声が聞こえてきた。
「綾ちゃん、先生がプリント渡してって……」
声の主は、佐伯遥だった。遥は、綾とリクが知り合いだと言う程度の事しか知らない。何が起きているのか理解が追いつかない表情で、二人を見るのが精々だった。
遥はともすると、リクよりも背が高かった。リクは思いきり鉢合わせしそうになって、すくんだ彼女の身体をわざと邪険に押しのけた。後ずさった遥はリクの手首を見て、凍りついたような表情になった。
「蓮波とベタベタつるんでるからこういうの、好きだと思ったんだけど。違うんだ」
リクが苛立ちを隠そうともせずに言う。遥の表情が一瞬で曇り、視線を綾へ送った。ビックリとした表情の綾がリクを見ると、どうやれば二人が傷つくか、予め見透かしていたかのような鋭い口調が保健室に響き渡った。
「蓮波はさ、優しくされるとすぐに勘違いしちゃうんだ。だから、女の事だって平気で好きになるよ。知らなかった?節操ないんだ。おばさんの再婚相手とだって、やりまくってたんだから」
リクは絶句する二人を引き剥がすように綾を引っ張ると、保健室を飛び出して行ってしまった。呆然と立ち尽くす遥の手から、プリントがバラバラと落ちる。走り去る肩越しに彼女が泣き出してしまったのを、綾は感じていた。
「……どうしてあんな酷い事、言うの?」
儀式に使っていた用具室に連れて来られた綾の顔色は、青いを通り越して白くなっていた。心臓が射られたように痛い。けれども、それ以上に強い感情がすぐに押し寄せてくる。綾は身体を硬直させると、小刻みに震え始めた。
あの事だけは、誰にも言わないって。望月君、約束してくれてたのに。
恥ずかしさと惨めさで、涙が溢れてくる。綾は、反射的にリクの手を振り払った。涙の滲む目で、リクを睨みつける。思えば二人が出会ってからこんな風に、話をするのは初めての事だった。
二人の会話はいつでも感情のない機械人形のようで、現実味がなかった。更にはお互いに、それが当たり前だと思っているような節すらあった。
自己完結しきった共依存関係。それがリクと綾だった。
半井ゼンジが二人の前に現れるまでは。
「先に酷い事をしたのは、お前だろ!俺を一人にしたじゃないか!」
興奮した様子で、リクが怒鳴り返す。綾には、リクが何をそんなに怒っているのか、サッパリ理解が出来なかった。つい先週だって職員室の前で右目を怪我した彼を、保健室に連れて行こうとしたばかりだ。
彼女には普通ではないなりに、リクを大事に想っている自負がある。
おそらく初めて自覚する激しい憤りに、俯いていてスカートを握っていると、足元に向かって乱雑に剃刀が投げつけられてきた。
リクは綾を見ようともせずに、ただ彼女を傷つけるためだけに言った。
「ねえ、早く儀式。やって」
二人の儀式。
二人の秘密
それは私たちの日常のはずだった。この世の中で二人ぼっちだと確認するための、二人だけで生きていく事を確認するための儀式。なのに、手が震えて剃刀を上手く持てない。
躊躇ったまま動けないでいると、リクはおかしそうに笑いながら、綾のカミソリを持つ手に自分の手を添えた。
「ねえ、知ってた?半井って、俺の事が好きなんだ。キス以上の事もしたよ」
望月君は傷ついて泣く、私の顔が見たいんだろうか。確かに、私は半井君の事が好きだ。けれど、あの人の選ぶ相手が、別に私でなくても構わない。内に秘めている限り、好きでいるのは自由だと思う。
「俺たちは、二人じゃなきゃ生きられない。約束、したじゃないか。早くやってよ。蓮波」
少し前まで、何の違和感もなかった言葉。
けれど……
それってこの世の終わりを二人で生きてくって、意味なんじゃないの。
二人で死のうって、意味なんじゃないの?
望月君は、本当にそれでいいの?
深呼吸をして、目を瞑った綾はこれで最後にしようと覚悟を決めて、剃刀で手首を切った。パクッと割れた傷痕から、血がポタポタと流れ始める。リクはいつものように血を啜りながらズボンの中を弄り始めた。
しかし
リクの下半身は、何の反応もしていなかった。首を傾げたリクは、ピクリともしない下半身をいつものように扱き始めた。
「――望月、好きだ」
「……俺だって、勘違いであって欲しかった」
目を閉じていると、さっきの半井の顔が浮かんでは消えてゆく。そしてその存在は、頭にこびりついたままずっと消えない。
唇の感触、傷口を伝っていった涙。
今まで、感じたこともないような痛み。
首と手首についた傷が、ヤスリで擦られてるようにヒリヒリと痛むのを無視したかったリクは、自分に言い聞かせた。
痛めつけられれば痛めつけられるほど、感じるんだ。
こんなに傷ついてるって、ゾクゾクするんだ。
蓮波が剃刀で傷をつければ、一人じゃないって安心するんだ。
ああ……でも今更。何をしたって。
この世界を、俺は血を流しながらでしか、生きられない。
「いい加減にしろよ。そんな事して何が楽しい」
半井の瞳。
「……るさい……」
「……え?」
「うるっさいんだよ!もう黙れ!!」
綾の傷口から口を離したリクは、ゼンジの幻影を振り払おうとして、力任せに彼女の頬をビンタしてしまった。綾の身体が跳ねるようにしてよろけて、傍に放置してあった机ごと倒れ込んでゆく。
ついに、やってしまった。
蓮波に手をあげたら、もう二度と儀式は成立しなくなる。俺はまた一人になる。
分かっていたはずなのに。
何もかも、終わりだ。全部、半井のせいだ。アイツがあんな事を言って、泣いたりするから……
「う……」
どうしようもなくいたたまれない気持ちになったリクは、その場から逃げ出したくなっていた。適当にベルトを締めると、綾の様子などお構いなしに慌てて踵を返していた。ガタガタと椅子を避ける音がする。
「まっ待って」
そう叫んでリクを抱きしめたのは、綾だった。彼女の方から、そんな事をしてくるのは初めてだった。いや、二人の自己完結しきった関係性の中で、そんなのはあり得ない事だった。
揺らがない決心をしたかのように、踊り場でのゼンジみたいな抱きしめ方をしてくる。綾との一方的な関係に満足しきっていたリクは、居心地の悪さに吐き気を覚えていた。
男が嫌いだって言うから、一緒にいたのに。
――なんなんだよ……
お前まで、俺の中に入ってこようとするのかよ!
綾は、泣いていた。大きな黒い瞳から、涙がポロポロとこぼれている。
「望月君、ごめんね。ずっと、気が付かなくて」
「何が?知らない。離してよ……」
「本当に死にたかったのは、望月君だったんだよね」
リクの身体がピクッと反応する。その後、何もかもを諦めたように力が抜けていった。綾はなおもリクを抱きしめながら、言葉を続けた。涙が後から後から、彼女の頬を伝ってゆく。
「だけど、ごめんなさい。私、一緒には死ねない。私、お母さんともう一度ちゃんと話したい。お母さんを、抱きしめたい……いつか、お母さんからも抱きしめてもらいたい」
「……おばさんは、蓮波を許してないよ。こんな事になったのは、蓮波、お前のせいだって思ってる。でも、そんな考え許されないから、おかしくなったんじゃないの」
「分かってる。それでも、お母さんが好きなの」
「俺が殴ったから、そんな事言ってんの?」
「違う」
綾は制服の肩の辺りに濡れた感触を感じて、リクから離れた。仄暗い部屋の微かな光がまだ血の滲むその細い首を照らす。光は、その先にあるリクの顔も照らしていった。
リクは涙を流しながら、笑っていた。
その繊細な表情は今まで見たことがないほど、穏やかで、優しく、静かな憂いを含んでいた。
「もういいよ……そっか。バレちゃってたか。俺が、死のうとしてた事。蓮波はさ、俺が死んだら半井の傍にいてやれよ。アイツ、お前の事好きになると思うよ」
「望月君……」
届かないのは分かってる。だけど。
綾は手を伸ばさずにはいられなかった。リクがどうしようもないほど傷ついている事は分かっていた。けれども、どちらかがどうしようもないほど傷つくか。どちらか、もしくは二人で死ぬ以外に、この閉じた関係を終わらせる方法など最初からなかったのだ。
だから、呪文のようにお互いに唱え続けてきたのだ。
二人だけで生きていこうと。
綾の手が虚しく宙を舞う。
「バイバイ」
それだけ言うと、リクは用具室から走り去って行ってしまった。
綾はリクが全てを終わらせようとしている、と感じていた。
◆
「何が起きてるワケ?」
「望月、あの暗い子。蓮波だっけ?とさっき一緒にいたの、見たぜ」
「え?イミフ。どういう関係なの……一体……」
机に突っ伏したままの半井ゼンジを尻目に、クラスのヒソヒソ話は止まらない。止めろという方に、無理があるだろう。それぐらい、接点のまるでなかった三人が起こした突然のゴタゴタは、学年中の話題になっていた。
アラタと弥生が気を遣って、教室の外に連れ出そうとしたが、ゼンジは首を振っただけだった。結局、望月リクは鞄を置いたまま、教室には戻らなかった。
誰が見ても丸わかりの泣きはらした目をしたゼンジが教室に戻ってきたのは、三限目に入ってからだった。
雲が厚く垂れこめ、ムワッとするような湿ったの匂いが身体を包んでくる。
「半井…………半井君いますか!」
教室の入り口で絞り出すような大声を出したのは、蓮波綾だった。先程つけた手首の切り傷もそのままに、酷く焦っている。慌てて教室まで駆けつけたのだろう。何回転んだのか、膝には擦り傷まで出来ていた。
「蓮波……」
顔を上げたゼンジに気づいた綾は、駆け寄ってくるとハァハァ言ってる荒い息を、何とか落ち着かせようと唾を何度も飲み込んだ。そして聞こえないくらい小さな……だが、しっかりとした声でゼンジに訴えた。
「望月君、死のうとしてる。」
ゴロゴロ……と雷鳴のようなものが聞こえ、大粒の雨が降り始めた。
半井ゼンジと望月リクの教室も、それは同じだった。
ザワザワ……
「――なんていうか……」
「笑えないよな」
「また傷、増えてない?」
「ちょっと怖いんだけど……」
「ウリやってるって噂、マジ?」
「おはよ。誰の話してんの?」
リクは、クラスメイトのヒソヒソ声へと応えるようにして、ニコッと笑うと手を振ってみせた。眼帯は外れたが、まだ右目の痣は生々しい。教室の空気がサーッと凍る。そそくさと背中を向けたかと思うと、一斉に沈黙してしまった。
リクは笑顔のまま声に出さす、口だけを動かした。
『バーカ』
そうしていつものように窓際の席に着くと、鞄を机に放り出して投げやりに座った。空はどす黒く曇っていて、また一雨来そうだった。
「え?弥生と喧嘩してた?」
「嘘だろ。気づいてなかったの?」
「いや……最近、見ないな……とは思ってたけど」
「えぇ……」
ゼンジがアラタと話ながら、教室に入ってくる。「弥生と仲直りしたんなら、期末テストの勉強……」とアラタに言いかけて、顔を上げたゼンジは絶句した。
呆然と見つめる視線の先には、傷だらけのリクが座っていた。
手に持っていたスマホが音を立てて落ち、教室の視線がにわかに集中する。
「――望月……」
目の傷痕もまだ痛々しいというのに、どう見てもロープで縛ったとしか思えない首の擦り傷と、赤紫の痣。手首も同様の状態になっていて満足に消毒もしてないのか、所々、血が滲んでいた。
本人も開き直っているのか、いつかのように長袖で隠そうはせず、半袖シャツのままだった。
硬直して立ち尽くしたまま自分を見ているゼンジに気づいたリクは、じっと見つめ返すと手首の傷をヒラヒラと振りながら嘲笑してみせた。
「おはよ、半井。何見てんの。もしかしてこういうの、興奮するタイプ?」
「……!」
ゼンジは脇目もふらずにツカツカとリクの方へ歩み寄っていくと、二の腕を力任せに掴んだ。ゼンジの目が燃えるような怒りを帯びて、カッと見開かれている。他人事のように、半井ってこういう顔もするんだ……とぼんやり俯瞰しているリクがいた。
「立て」
有無を言わさない激しい口調だった。そのまま、掴んだ腕をグッと引っ張り上げる。リクは何故だか、ゼンジから視線を逸らせて俯いてしまっていた。
「立てって言ってるだろ!望月!」
その声で、ぼんやりと我に返る。リクはゼンジから引き摺られるようにして、教室から出ようとしている所だった。ゼンジの力が強すぎて、振り払おうにも振り払えない。
だけどさ
いくら半井がそんな事したって、俺は絶対に変わらないよ。
お前になんか、一生分からない。何も、出来ない。
俺は、玩具でいたいんだ。徹底的に破壊してもらいたいんだよ。
それをしなかった、お前が悪いんじゃないか。半井。
時間にして、5分あるかないかの出来事だった。後から教室に入ってきたクラスメイトが出ていく二人とすれ違って、ポカーンとしながらその後姿を見ていた。
再び、教室がざわめきだす。
「え、何?何?あの二人。どういう事?」
「半井君、めっちゃキレてたよね」
「てか、あの二人が喋ってるトコ、初めて見た」
「でもあれ?この間、一緒に帰ってなかった?」
アラタは、クラスメイトのヒソヒソ話を聞きながら、なんとも言えない居心地の悪さを感じていた。ゼンジの落としたスマホを拾いあげると、机に置いてやった。そうして着席すると誰にも聞こえぬよう、小さなため息をついた。
◆
半井ゼンジが着替えに使っていた、旧校舎の踊り場。初めて望月リクと関係をもった場所。
ゼンジは力任せにリクを引きずってそこに連れてくると、かび臭く湿った体育マットに、彼の小さくて白い身体を叩きつけた。
恐ろしく醒めた声で、ゼンジが言う。
「いい加減にしろよ。そんな事して何が楽しい」
持っていた鞄から、ミネラルウォーターを取り出す。リクの茶色くサラサラとした髪の上からドバドバとかけ、空になったペットボトルをリクに向かって叩きつけた。
傷痕に水が滲みて、ヒリヒリとした痛みがリクを襲っていた。なのに全てが他人事で、もう一人の剥がれた自分がその様子を眺めている。リクは惨めな自分を嘲りながら、場違いな事を考えていた。
今ここで、思いっきり半井に首絞められながらヤりたいな。滅茶苦茶に気持ち良さそう。怒ってるコイツの表情、エロくてゾクゾクするもん。その顔で俺を便所みたいにしてくんないかなあ……
お前になんか、一生分からない。何も、出来ない。
何、青くっさい事思っちゃってんの、俺。マジでウケる。
アホみてえな事考えながら、ガチガチに勃起してんのが本来の俺だろ?
ずぶ濡れのリクは、思わず自嘲的な笑みをこぼしてしまっていた。痛々しい姿を晒し、自虐的に鼻でせせら笑うリクの様子は、ゼンジの怒りに火を注ぐには十分すぎる程だった。
どうして、そうまでして自分を痛めつける?
交通事故に遭って、背中に傷を作った時より、胸が痛む。俺の事じゃないのに。言い争う、祖母と母親を見ていた時より、悲しい。お前は家族じゃなく、他人なのに。
ゼンジは、その切れ長の瞳から涙を流していた。震える声で、リクに語りかける。
「なんで、分かんないんだよ……どうして、伝わらな……」
途中からもう言葉にならない。肉体的に大人として完成しつつあるゼンジが、同級生であるリクの前で嗚咽する姿は、過渡期独特のアンバランスさを孕んでいた。危うくも、美しい。今にも壊れてしまいそうな、そういった類のもの。
リクもまたそんなゼンジの姿を見て、生まれて初めての感情に飲み込まれ困惑していた。
触れてみたい。
どうしようもなく甘く、切ない、涙がこみ上げてくるような感情。
先生にも抱いたことのない、感情。
あの日、家で眠ってしまっていた半井に、口づけをした。
俺はなんであんな事をした?分からない。
溢れ出しそうになって、無意識に蓋をしてしまった。
柔らかく締め付けられるような胸の痛みが、濁流のように押し寄せてくる。このままでは、俺は飲み込まれてしまう。俺は死んでしまう。リクは激しい混乱で、平衡感覚を失ったような感覚に囚われていた。泣きじゃくるゼンジ以外の全てが、ぐにゃりとひしゃげて見える。
その瞬間だった。
ゼンジが、ずぶ濡れのリクを思い切り抱きしめたのは。涙で濡れた唇が重なる。温かい唇だった。ゼンジの吐息と共に入ってきたのは、リクが生まれてから一度も味わったことのない、何かだった。
ペルソナが外れ、素顔の望月リクが姿を現す。
彼は混乱の果てに、酷く怯えきっていた。
「やめろよ!離せ!」
リクは叫んでいた。
激しくもがき出したリクを離さないよう、ゼンジは抱きしめる腕を強めた。そうして出来たばかりの傷に、愛おしそうな口づけをする。
さっきかけられた水とはまるで違う。
半井の涙が濡らしていった傷は、ヤスリで擦られているみたいに痛い。
「――望月……」
ゼンジの真剣な声が聞こえてきた。リクの顔は最早、青ざめていた。
やめろ……その先を言うな。
これ以上、俺の中に入ってこないでくれ!
「望月、好きだ」
「――嫌だ……」
「好きだ」
暴れるリクをそっと引き寄せ、再び唇を重ねる。もうこれ以上、何をどう伝えたらいいのか分からない。それはゼンジにとっても初めての感情だった。
確かに、中学の時のあれは初恋だったんだろうと思う。けれども、彼女が転校してしまった後、俺は失う恐怖になんか怯えなかった。少しの間、寂しかっただけ。
なのに、今は。
俺は、望月を失うのが怖い。
ドンッ!
こんな小さな身体のどこにそれ程の力があるんだ、と言わんばかりの勢いで、リクがゼンジを突き飛ばした。息は酷く乱れ、幽霊のように白い身体が小刻みに震えている。
下唇を噛んだリクの表情は、恐怖で強張っていた。
「やめろって言ってんだろ!ちょっとくらい俺にチンコ弄ってもらったからって、勘違いしてんじゃねえよ!」
「……俺だって、勘違いであって欲しかった」
ゼンジの頬をツ――……と再び涙が伝った。髪を結んでいたゴムが落ちて、緩いくせ毛が肩に垂れる。その面影が先生……飯山ハルキと重なって、リクは悲鳴を上げそうになった。
どうしてそれを言うのが先生じゃなくて、お前なんだよ!
「うるさい!俺は、お前のモノじゃない!」
「……分かってる」
「お前になんか、一生分からない。何も、出来ない!」
リクの肩はなおも小刻みに震えていた。目には涙を浮かべている。
「どうして入ってくるのがお前なんだよ……お前は、俺を殺せないくせに!」
大粒の涙をこぼし悲痛な叫び声を上げたリクは、踊り場から走り去っていってしまった。
ゼンジはリクの心を、素手でズタズタにしてしまったような気がして、その場に座り込んでしまった。絶望したような表情で、手のひらを見つめる。
心の置き場を、もう何処にもっていったら良いのか分からない。
「……俺だって、どうしてお前なのか、分かんねえよ」
そう独りごちるとカビ臭いマットにもたれかかって、両手で顔を覆った。
◆
「望月君、どうしたの、怪我……」
「起きろよ」
掛け布団を乱暴に剥ぎ取られる。保健室で横になっていた蓮波綾は、首と手首に傷を作り、ずぶ濡れになっている望月リクの姿をじっと見つめていた。
まるで、昔の私みたい。何があったの、望月君。
キーンコーンカーンコーン――……
終業のチャイムが鳴る。生徒たちの廊下へ出てきた賑わいが、ドア越しに交差し始めた。リクは綾の腕を掴むと、無理やり立たせて腕を引っ張った。
儀式をするんだろうか。
刺すような胸の痛みに、綾は顔を歪めていた。職員室の前での一件以来、彼女はリクと会話をしていなかった。
あれから、望月君は学校を休んだ。登校してきたのは、先週の終わりから。心配はしていたけど、私には自分から連絡を取る勇気がない。
連絡が取れた所で何を話したらいいのか、分からない。
二人は知り合ってから一度も、学校の外で会った事がない。高校に入ってからは、スマホで連絡をとった事もなかった。
イライラとした様子のリクにされるがまま、腕を引っ張られ保健室から出ようとした所で聞き慣れた声が聞こえてきた。
「綾ちゃん、先生がプリント渡してって……」
声の主は、佐伯遥だった。遥は、綾とリクが知り合いだと言う程度の事しか知らない。何が起きているのか理解が追いつかない表情で、二人を見るのが精々だった。
遥はともすると、リクよりも背が高かった。リクは思いきり鉢合わせしそうになって、すくんだ彼女の身体をわざと邪険に押しのけた。後ずさった遥はリクの手首を見て、凍りついたような表情になった。
「蓮波とベタベタつるんでるからこういうの、好きだと思ったんだけど。違うんだ」
リクが苛立ちを隠そうともせずに言う。遥の表情が一瞬で曇り、視線を綾へ送った。ビックリとした表情の綾がリクを見ると、どうやれば二人が傷つくか、予め見透かしていたかのような鋭い口調が保健室に響き渡った。
「蓮波はさ、優しくされるとすぐに勘違いしちゃうんだ。だから、女の事だって平気で好きになるよ。知らなかった?節操ないんだ。おばさんの再婚相手とだって、やりまくってたんだから」
リクは絶句する二人を引き剥がすように綾を引っ張ると、保健室を飛び出して行ってしまった。呆然と立ち尽くす遥の手から、プリントがバラバラと落ちる。走り去る肩越しに彼女が泣き出してしまったのを、綾は感じていた。
「……どうしてあんな酷い事、言うの?」
儀式に使っていた用具室に連れて来られた綾の顔色は、青いを通り越して白くなっていた。心臓が射られたように痛い。けれども、それ以上に強い感情がすぐに押し寄せてくる。綾は身体を硬直させると、小刻みに震え始めた。
あの事だけは、誰にも言わないって。望月君、約束してくれてたのに。
恥ずかしさと惨めさで、涙が溢れてくる。綾は、反射的にリクの手を振り払った。涙の滲む目で、リクを睨みつける。思えば二人が出会ってからこんな風に、話をするのは初めての事だった。
二人の会話はいつでも感情のない機械人形のようで、現実味がなかった。更にはお互いに、それが当たり前だと思っているような節すらあった。
自己完結しきった共依存関係。それがリクと綾だった。
半井ゼンジが二人の前に現れるまでは。
「先に酷い事をしたのは、お前だろ!俺を一人にしたじゃないか!」
興奮した様子で、リクが怒鳴り返す。綾には、リクが何をそんなに怒っているのか、サッパリ理解が出来なかった。つい先週だって職員室の前で右目を怪我した彼を、保健室に連れて行こうとしたばかりだ。
彼女には普通ではないなりに、リクを大事に想っている自負がある。
おそらく初めて自覚する激しい憤りに、俯いていてスカートを握っていると、足元に向かって乱雑に剃刀が投げつけられてきた。
リクは綾を見ようともせずに、ただ彼女を傷つけるためだけに言った。
「ねえ、早く儀式。やって」
二人の儀式。
二人の秘密
それは私たちの日常のはずだった。この世の中で二人ぼっちだと確認するための、二人だけで生きていく事を確認するための儀式。なのに、手が震えて剃刀を上手く持てない。
躊躇ったまま動けないでいると、リクはおかしそうに笑いながら、綾のカミソリを持つ手に自分の手を添えた。
「ねえ、知ってた?半井って、俺の事が好きなんだ。キス以上の事もしたよ」
望月君は傷ついて泣く、私の顔が見たいんだろうか。確かに、私は半井君の事が好きだ。けれど、あの人の選ぶ相手が、別に私でなくても構わない。内に秘めている限り、好きでいるのは自由だと思う。
「俺たちは、二人じゃなきゃ生きられない。約束、したじゃないか。早くやってよ。蓮波」
少し前まで、何の違和感もなかった言葉。
けれど……
それってこの世の終わりを二人で生きてくって、意味なんじゃないの。
二人で死のうって、意味なんじゃないの?
望月君は、本当にそれでいいの?
深呼吸をして、目を瞑った綾はこれで最後にしようと覚悟を決めて、剃刀で手首を切った。パクッと割れた傷痕から、血がポタポタと流れ始める。リクはいつものように血を啜りながらズボンの中を弄り始めた。
しかし
リクの下半身は、何の反応もしていなかった。首を傾げたリクは、ピクリともしない下半身をいつものように扱き始めた。
「――望月、好きだ」
「……俺だって、勘違いであって欲しかった」
目を閉じていると、さっきの半井の顔が浮かんでは消えてゆく。そしてその存在は、頭にこびりついたままずっと消えない。
唇の感触、傷口を伝っていった涙。
今まで、感じたこともないような痛み。
首と手首についた傷が、ヤスリで擦られてるようにヒリヒリと痛むのを無視したかったリクは、自分に言い聞かせた。
痛めつけられれば痛めつけられるほど、感じるんだ。
こんなに傷ついてるって、ゾクゾクするんだ。
蓮波が剃刀で傷をつければ、一人じゃないって安心するんだ。
ああ……でも今更。何をしたって。
この世界を、俺は血を流しながらでしか、生きられない。
「いい加減にしろよ。そんな事して何が楽しい」
半井の瞳。
「……るさい……」
「……え?」
「うるっさいんだよ!もう黙れ!!」
綾の傷口から口を離したリクは、ゼンジの幻影を振り払おうとして、力任せに彼女の頬をビンタしてしまった。綾の身体が跳ねるようにしてよろけて、傍に放置してあった机ごと倒れ込んでゆく。
ついに、やってしまった。
蓮波に手をあげたら、もう二度と儀式は成立しなくなる。俺はまた一人になる。
分かっていたはずなのに。
何もかも、終わりだ。全部、半井のせいだ。アイツがあんな事を言って、泣いたりするから……
「う……」
どうしようもなくいたたまれない気持ちになったリクは、その場から逃げ出したくなっていた。適当にベルトを締めると、綾の様子などお構いなしに慌てて踵を返していた。ガタガタと椅子を避ける音がする。
「まっ待って」
そう叫んでリクを抱きしめたのは、綾だった。彼女の方から、そんな事をしてくるのは初めてだった。いや、二人の自己完結しきった関係性の中で、そんなのはあり得ない事だった。
揺らがない決心をしたかのように、踊り場でのゼンジみたいな抱きしめ方をしてくる。綾との一方的な関係に満足しきっていたリクは、居心地の悪さに吐き気を覚えていた。
男が嫌いだって言うから、一緒にいたのに。
――なんなんだよ……
お前まで、俺の中に入ってこようとするのかよ!
綾は、泣いていた。大きな黒い瞳から、涙がポロポロとこぼれている。
「望月君、ごめんね。ずっと、気が付かなくて」
「何が?知らない。離してよ……」
「本当に死にたかったのは、望月君だったんだよね」
リクの身体がピクッと反応する。その後、何もかもを諦めたように力が抜けていった。綾はなおもリクを抱きしめながら、言葉を続けた。涙が後から後から、彼女の頬を伝ってゆく。
「だけど、ごめんなさい。私、一緒には死ねない。私、お母さんともう一度ちゃんと話したい。お母さんを、抱きしめたい……いつか、お母さんからも抱きしめてもらいたい」
「……おばさんは、蓮波を許してないよ。こんな事になったのは、蓮波、お前のせいだって思ってる。でも、そんな考え許されないから、おかしくなったんじゃないの」
「分かってる。それでも、お母さんが好きなの」
「俺が殴ったから、そんな事言ってんの?」
「違う」
綾は制服の肩の辺りに濡れた感触を感じて、リクから離れた。仄暗い部屋の微かな光がまだ血の滲むその細い首を照らす。光は、その先にあるリクの顔も照らしていった。
リクは涙を流しながら、笑っていた。
その繊細な表情は今まで見たことがないほど、穏やかで、優しく、静かな憂いを含んでいた。
「もういいよ……そっか。バレちゃってたか。俺が、死のうとしてた事。蓮波はさ、俺が死んだら半井の傍にいてやれよ。アイツ、お前の事好きになると思うよ」
「望月君……」
届かないのは分かってる。だけど。
綾は手を伸ばさずにはいられなかった。リクがどうしようもないほど傷ついている事は分かっていた。けれども、どちらかがどうしようもないほど傷つくか。どちらか、もしくは二人で死ぬ以外に、この閉じた関係を終わらせる方法など最初からなかったのだ。
だから、呪文のようにお互いに唱え続けてきたのだ。
二人だけで生きていこうと。
綾の手が虚しく宙を舞う。
「バイバイ」
それだけ言うと、リクは用具室から走り去って行ってしまった。
綾はリクが全てを終わらせようとしている、と感じていた。
◆
「何が起きてるワケ?」
「望月、あの暗い子。蓮波だっけ?とさっき一緒にいたの、見たぜ」
「え?イミフ。どういう関係なの……一体……」
机に突っ伏したままの半井ゼンジを尻目に、クラスのヒソヒソ話は止まらない。止めろという方に、無理があるだろう。それぐらい、接点のまるでなかった三人が起こした突然のゴタゴタは、学年中の話題になっていた。
アラタと弥生が気を遣って、教室の外に連れ出そうとしたが、ゼンジは首を振っただけだった。結局、望月リクは鞄を置いたまま、教室には戻らなかった。
誰が見ても丸わかりの泣きはらした目をしたゼンジが教室に戻ってきたのは、三限目に入ってからだった。
雲が厚く垂れこめ、ムワッとするような湿ったの匂いが身体を包んでくる。
「半井…………半井君いますか!」
教室の入り口で絞り出すような大声を出したのは、蓮波綾だった。先程つけた手首の切り傷もそのままに、酷く焦っている。慌てて教室まで駆けつけたのだろう。何回転んだのか、膝には擦り傷まで出来ていた。
「蓮波……」
顔を上げたゼンジに気づいた綾は、駆け寄ってくるとハァハァ言ってる荒い息を、何とか落ち着かせようと唾を何度も飲み込んだ。そして聞こえないくらい小さな……だが、しっかりとした声でゼンジに訴えた。
「望月君、死のうとしてる。」
ゴロゴロ……と雷鳴のようなものが聞こえ、大粒の雨が降り始めた。
0
あなたにおすすめの小説
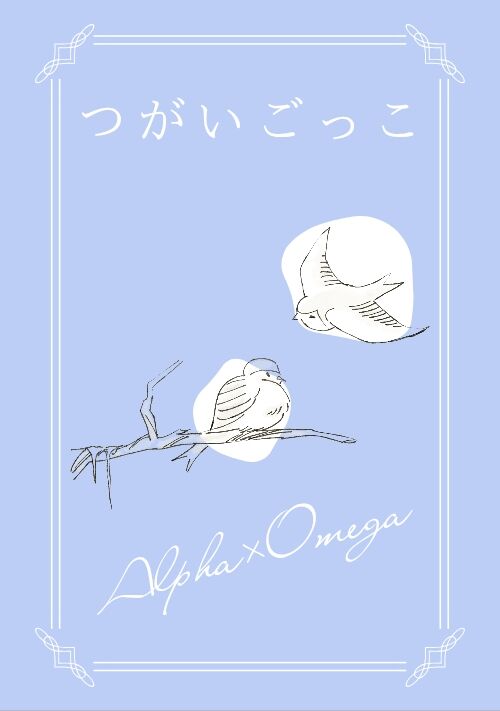
つがいごっこ~4歳のときに番ったらしいアルファと30歳で再会しまして~
深山恐竜
BL
俺は4歳のときにうなじを噛まれて番を得た。
子どもがたくさんいる遊び場で、気が付いたらそうなっていたとか。
相手は誰かわからない。
うなじに残る小さな歯型と、顔も知らない番。
しかし、そのおかげで、番がいないオメガに制限をかけられる社会で俺は自由に生きていた。
そんなある日、俺は番と再会する。
彼には俺の首筋を噛んだという記憶がなかった。
そのせいで、自由を謳歌していた俺とは反対に、彼は苦しんできたらしい。
彼はオメガのフェロモンも感じられず、しかし親にオメガと番うように強制されたことで、すっかりオメガを怖がるようになっていた。
「でも、あなただけは平気なんです。なんででしょう」
首を傾げる彼に、俺は提案する。
「なぁ、俺と番ごっこをしないか?」
偽物の番となった本物の番が繰り広げるラブストーリー。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。


処刑エンドの悪役公爵、隠居したいのに溺愛されてます
ひなた翠
BL
目が覚めたら、やり込んだBLゲームの悪役公爵になっていた。
しかも手には鞭。目の前には涙を浮かべた美少年。
——このままじゃ、王太子に処刑される。
前世は冴えない社畜サラリーマン。今世は冷徹な美貌を持つ高位貴族のアルファ。
中身と外見の落差に戸惑う暇もなく、エリオットは処刑回避のための「隠居計画」を立てる。
囚われのオメガ・レオンを王太子カイルに引き渡し、爵位も領地も全部手放して、ひっそり消える——はずだった。
ところが動くほど状況は悪化していく。
レオンを自由にしようとすれば「傍にいたい」と縋りつかれ、
カイルに会えば「お前の匂いは甘い」と迫られ、
隠居を申し出れば「逃げるな」と退路を塞がれる。
しかもなぜか、子供の頃から飲んでいた「ビタミン剤」を忘れるたび、身体がおかしくなる。
周囲のアルファたちの視線が絡みつき、カイルの目の色が変わり——
自分でも知らなかった秘密が暴かれたとき、逃げ場はもう、どこにもなかった。
誰にも愛されなかった男が、異世界で「本当の自分」を知り、運命の番と出会う——
ギャップ萌え×じれったさ×匂いフェチ全開の、オメガバース転生BL。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

だって、君は210日のポラリス
大庭和香
BL
モテ属性過多男 × モブ要素しかない俺
モテ属性過多の理央は、地味で凡庸な俺を平然と「恋人」と呼ぶ。大学の履修登録も丸かぶりで、いつも一緒。
一方、平凡な小市民の俺は、旅行先で両親が事故死したという連絡を受け、
突然人生の岐路に立たされた。
――立春から210日、夏休みの終わる頃。
それでも理央は、変わらず俺のそばにいてくれて――
📌別サイトで読み切りの形で投稿した作品を、連載形式に切り替えて投稿しています。
エピローグまで公開いたしました。14,000字程度になりました。読み切りの形のときより短くなりました……1000文字ぐらい書き足したのになぁ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















