9 / 17
第二章:すれ違う横顔
第九話:温度差
しおりを挟む「望月君、死のうとしてる」
「……どういう事だ?」
息を切らしながら絞り出すようにして訴えかける蓮波綾に、半井ゼンジはそう答えるのがやっとだった。
望月リクに自分の想いを打ち明けてしまった事すら、受け止めきれずにゼンジは混乱していた。そんな彼にとって、リクが死のうとしている等という話は、理解の範疇を完全に超えてしまっていた。
ポカーンとしているゼンジの腕を掴んだ綾は、ありったけの力を込めて懇願した。
「半井君、お願い。助けて」
瞬間、リクの放った悲痛な叫びがシンクロする。
「どうしてお前なんだよ……お前は、俺を殺せないくせに!」
確かにアイツは、俺を殺せないと言った。リクの首と手首についていた、痛々しい傷痕が頭をもたげる。俺はずっと望月に対して、嫌悪感しか抱いて来なかった。アイツを知るようになってからは、別の苛立ちに振り回された。
白々しく笑いながら、今にも燃え尽きそうな命に、自ら手をかけてるようにしか見えなかった。
緩やかな自殺をみせつけられているのに、俺は指をくわえて見ているしか出来なかった。
もっとハッキリ、助けを求めて欲しかった。
たとえそれが俺の自分勝手で、一方的な願望だとしても。
そうする事でいつからか、俺自身が触れて欲しいと願っていたのかもしれない。
「ちょっと、思い当たる所がある。蓮波は、保健室で傷の手当だけしてもらえ。望月の鞄持って、下駄箱んとこにいるから」
おもむろに立ち上がったゼンジが言うと、綾は頷いて保健室に向かって行った。教室は、相変わらずヒソヒソ声でひしめいている。その声をかき消すように、窓際のリクの席へと向かうと鞄を持って、そのまま教室を後にした。
「……望月君、引っ越したって言ってたけど。こんなに近いと思わなかった……」
綾は、改めてリクの事を何も知ろうとしてこなかった自分に、自責の念を覚えながら呟いた。二人は、リクの家に向かっていた。雨の降る住宅街を、言葉少なに歩いてゆく。背が高いゼンジの持つ傘が、彼女の持つ傘の上で揺れていた。
「同じ、中学だったのか?」
「――……うん」
含みのある言い方で、綾が頷く。
ゼンジはリクが何故、綾にあげた筈の自分のタオルを持っていたのか、聞き出せずにいた。
同じように綾もまた、リクと自分の関係について、何を何処まで話せば良いのか迷っていた。
どちらも話を切り出す事が出来ないまま、ただ歩き続けてしまい、気がつくとリクの家の前まで来てしまっていた。立派な門構えの、古風な屋敷。もうじき梅雨も明けると言うのに、そこはかとなく空気が冷たい。
「あ、表札」
綾が、少し驚いた様子で声をあげた。表札をじっと見ている。
「ここだよ。望月んち。親戚か何かの家なのか?この奥の離れに、アイツ住んでて」
「……桐生って、望月君の、前の苗字」
「前の苗字?それってどういう……」
そう言いかけたゼンジの後ろを、スラっとした長身の男性が通り過ぎ、門の中に入っていこうとしていた。
「すみません、ちょっと。そこを通して頂きたいんですが」
男性は、20代前半だろうか。色素の薄い髪と大きなつり目が、リクとそっくりだった。ただ、リクが常に自分を誤魔化しているような所があるとしたならば。その男性は、何と言えば良いのだろうか。最初から感情など持ち合わせていないような、醒めきった雰囲気を漂わせていた。
思わず後ずさったゼンジの身体がぶつかった綾は後ずさると、その男性をじっと見つめた。男性は門をくぐり抜け、そのまま母屋へ向かおうをしている。
「……あのっ!望月君のお兄さんですか?」
口を開いたのは綾だった。振り返った男性はやはり、リクとよく似た美しい造形をしている。
「望月……そのような者はウチにはおりませんが」
「でも望月、お宅の離れに住んでますよね?」
綾につられて、ゼンジが口を開く。男はそうしている間も醒めきった様子で、二人の制服姿を眺めていた。母屋の扉が開く音に男は母屋の方へ向き直ると、二人をこれ以上見ようとはせず平坦な口調で返した。
「さあ、申し訳ありません。遠縁の子でも、引き取っているんじゃないんでしょうか。私も、住まいはこちらではないので。何も知りません」
それだけ言うと、扉の開く方へ歩いて行ってしまった。玄関には着物姿の女性がおり、男に向かって名前らしきものを呼びかけているのが聞こえる。
「カイ」
ガラガラという音と共に扉は閉められ、ゼンジと綾は何とも言えない気持ちで顔を見合わせた。
雨は益々、冷たく降り注いでいた。
「……やっぱり戻ってきてないか」
男の様子を見たせいからか、ゼンジは思わずそう独りごちてしまった。二人は、リクの住む離れに来ていた。鍵がかかっていないので、誰でも入れる。鞄をダイニングテーブルに置いたゼンジは、一通り家の中を見て回った。
綾は、全く使われてないダイニングテーブルをさすりながら、辺りをじっと見回している。
「望月君、引っ越して来た時から、そのつもりだったんだ」
綾が悲しげにそう呟いた時、ゼンジはリクのベッドの上にある自分のタオルを見つけて、立ち尽くしていた。
「蓮波、ちょっと」
ゼンジが、部屋から声をかける。声のする方へやってきた綾は、タオルがまず目に入ったのだろう。「あ」と小さな声を出すと、ベットへ駆け寄った。
「望月君、戻ってくる。これ取りに」
そう言うと、安堵の籠もったため息をついた。タオルを手に取り、大事そうに抱える。ゼンジは、ずっと抱いていた疑問を投げかけずにはいられなかった。
「そのタオル、なんで望月が持ってるんだ?お前に、あげたはずなんだけど」
「……」
「……話しにくいなら、無理して話さないでもいいけど」
「飯山先生」
「え?」
「望月君と付き合ってた人……今は先生を辞めてる。その人と、似てるの。半井君」
「どういう事?」
「最初は半井君が先生に似てたから、タオルが欲しかったんだと思う。望月君、ずっと平気なフリしてたの。先生がいなくなっても」
なんとなく話が繋がる。あの日、新宿で望月が見つめていた男の事だ。右目に大きな痣を作って来た日のリクの言葉が蘇る。
剥がれ落ちた、眼帯。
腫れ上がった目から、零れ落ちていた涙。
「……………先生………どうして、居なくなっちゃったの?」
俺の胸に倒れ込む直前、アイツはそう言った。
けれど、それと望月が死のうとしている事がどう繋がるのか、よく分からない。蓮波の言葉は、抽象的というか断片の寄せ集めみたいで、分かりにくい。俺だって話すのは上手じゃないから、人の事は言えないけれど。
「多分、望月君は、私と同じだったんだと思う」
「……?」
「――……虐待、されてたと思う。自分は生きてちゃいけないって、思ってたんだと思う」
ゼンジの脳裏を、先程すれ違ったカイと呼ばれる男の姿が過っていった。重なるようにして、殺風景過ぎるこの部屋は、皮肉にもリクが生きた証を残さないよう、生活をしていた証になってしまっている事に気づく。
最初から死ぬつもりだったのか。
自分の言動を含む様々な欠片の寄せ集めが、望月を傷つけ、追い詰めてしまった。ようやくゼンジは理解した。したけれども。そうなったら今度は、悔やまずにはいられなかった。
好きだなんて、言わなければ良かったのか。
「なあ、蓮波。その飯山って人、心当たりがあるんだけど。顔を見れば分かるか」
「うん」
「……さっきの男がいる間は、戻ってこないと思う。望月。だったら、飯山って人んとこへ話聞きに行かないか?」
綾は無言で頷くと、ゼンジと共に部屋を後にした。
◆
ザーザー降りの雨の中、無言でオフィスビルの入口を見つめる、半井ゼンジと蓮波綾の姿があった。二人とも無口なので、沈黙は苦にならない。そう言えば、今日の蓮波は顔を赤らめたり、どもったりしないな……そんな事をゼンジは考えていた。
「半井君のタオル」
突然、綾が口を開く。ゼンジは黙ったまま、彼女の立つ方を見た。
「あれ、望月君の宝物なんだよ」
「……えっ?」
「私達、ずっと二人きりで生きてきたの。いつか、二人で死ぬつもりで。だけど、半井君と話すようになって変わった。望月君も、私も」
「――……」
「望月君が死のうとしてるって言ったの、間違いのような気がする。望月君、本当は生きたいんだと思う。生きたいって、思うようになってしまったんだと思う。半井君がいるから」
オフィスビルから、若いサラリーマン達が出てくる。一人、長身で髪を括った男性が出てきた。なんか……この間も見た気がする。
「飯山先生!」
綾が細い声で叫んで、長身の男性の元に走って行った。
「――……蓮波さん?」
飯山と呼ばれた男性は、酷く驚いた表情で綾を見つめていた。飯山先生は、どことなく俺と似ていた。
「そんな事言われても……俺と桐生君について、話す事なんて何もないよ」
喫茶店でアイスコーヒーにミルクを入れながら、飯山は困りきった表情で答えた。そりゃ確かに、とゼンジは思う。中学生と成人男性の恋愛なんて、表に出れば犯罪でしかない。リクのあの態度を見ても、肉体関係がなかったという方に無理があった。
そんな後ろ暗い大人の事情をものともせず、綾が切り込む。
「でも望月君と、付き合ってましたよね?私、見た事あるんです。体育館の用具室。いつも、あそこで……」
「ちょっちょっ!蓮波さん、声、声抑えて」
慌てて口に指を当てた飯山は深い溜め息をつくと、これ以上は誤魔化せないと思ったのか、タバコに火を付けながら答えた。
「確かに付き合ってたよ」
「飯山さんは望月の事を、本当に好きでしたか?」
タバコの煙を燻らせながら、飯山が言葉を選んでいる。そう言えば、ずっと何も飲んでいなかった事に気づいたゼンジは、急に喉の乾きを感じて注文したアイスティーに口を付けた。
「温度差」
トントン、と灰皿に灰を落としながらハルキが答える。そうして、ストローをくわえながら、リクと最後に関係を持った日に思いを馳せていた。
-----二年前-----
その日も、二人はいつものように用具室でセックスをしようとしていた。ここ二週間ばかり、ご無沙汰だった。何でもプレゼントをしたいとかで、桐生リクの方から珍しくセックスを断っていたのだ。
行為への要求は、エスカレートする一方だった。つい先日はタバコの火を押し付けてくれ、とせがまれたばかりだ。飯山ハルキは、リクとの関係に疲れを感じ始めていた。
担任にそれとなく聞いても、桐生リクの家に虐待の噂や事実はないと返ってくる。
だったら、なんだってあんなに自分を痛めつけたがるんだ。
SMを勘違いしているのかとも思ったが、そもそもSMと自分のそれは違う、とリクは言い張って聞かない。
なんだかなあ……タバコを吸いたい気分で、飯山は防球ネットにもたれかかった。5分程して、学生服を着たリクが入ってきた。チュッと小鳥が啄むようなキスをしたかと思うと、堪えきれないと言わんばかりに、スーツのズボンを脱がせにかかる。
結局、性欲に流される俺も俺だ。その様子に堪らなく欲情してしまっている。
「桐生、口でズボン脱がせて」
コクンと頷いた、その細い首筋を目で追うだけで、スボンの中身が、はち切れそうなくらいにパンパンになってくるのを感じた。口で器用にベルトを外したかと思うと、ボタンまではなかなか上手く外せないようで苦戦していた。
こういう時のリクは、本当に愛おしい。歯茎を指先で撫でてやりながら、ボタンを外すのを手伝ってやる。興奮してきたのか、ハァ……と小さい喘ぎ声を上げながら、薄い唇でズボンのチャックを噛んだ。
ズボンの一番盛り上がっている部分に、チャックがつかえて中々下げられない。
「早くして、桐生」
そう言って、リクの顔をズボンの膨らみに押し付けると、ビクンッと小さな身体が反応した。カチッカチッと一つずつ、チャックを下げていく。そうして全部下げきらないうちに、収まりきらなくなった飯山のソレが、リクの頬を勢いよく弾いた。
「先生……好き」
そう言うと、リクは飯山のソレを愛おしそうに口へ含んだ。裏側の筋から丁寧に舐めていく。タマを舐められている時に、妙な感覚がする事に飯山は気づいた。何か……当たってるような気がするんだけど。
リクの舌は、先端のくびれにまで一気に移動して来たかと思うと、その勢いで強く吸った。皮が擦れて、飯山のソレがグッと硬くなる。
ズボッ……チュッジュル
リクの舌が、先端のくびれを愛撫し始めた。右手で残りの部分を扱き、左手では自分の下半身を弄っている。舌が這い回る度に、とてつもない快感がみぞおちにせり上がってくるのを、飯山は感じていた。
と、同時にやはり妙な感覚がする。
なんだか、パチンコ玉でも口に含みながら舐められているみたいだ。
「ちょっ……ちょっと桐生、タンマ。口に入れてるもん出して。変な感じがする」
チュポッという音と共に塊から口を離したリクは、飯山に向かって舌を出しながら微笑んでみせた。
二週間もかけて用意したプレゼント。
舌には、1cm大のピアスがしてあった。
「何やってんだ……お前……」
飯山が絶句してリクに尋ねると、問題があることを全く理解できていないような返事が返ってきた。
「え、プレゼント。気持ちいいでしょ?来週にはスプリットタンにしてもらうんだ。先生、知ってる?」
悪びれもせず、むしろ喜んで貰ってるとすら思っている様子のリクは、再び飯山のモノにむしゃぶりつこうとしていた。飯山はリクの肩を掴むと、自分のモノから彼を離した。
「そういうことじゃなくて!お前まだ中学生だぞ。今の勢いでそんな事したら、後々取り返しがつかなくなったって、絶対に後悔する。分かってんのか?」
「――……どの口でそれ言ってんの?」
リクの声は、恐ろしく冷静だった。
飯山が怯んで、用具室に澱んだ澱のような空気が漂う。自分でも、偽善者丸出しな事を言っている自覚はある。
けれど、桐生は今ここで止めないと。絶対にエスカレートしていく。それはだけはもう、断言してもいい。
「もうこういうのは、二度とするな。取り返しがつかなくなる前に……」
飯山が言い終わらないうちに、今にも壊れそうなくらい悲痛な声で、リクが叫んだ。
「今だってもう十分、取り返しなんてついてないよ。先生。俺の事、面倒くさくなってるでしょ?」
その言葉を飯山は否定できなかった。
二人の中にあった何かが、プツンと切れてしまった瞬間だった。
その後、桐生リクは無表情のまま、一言二言言い残して用具室から去っていった。
翌週には、二人の肉体関係は学校関係者に知れ渡る所となった。
-----現在-----
飯山が「すまない」と言いながら、タバコの煙を吐き出した。鎮痛な面持ちで座っている二人に向かって、言葉を続ける。
「俺は、好きだったよ。けど、普通の恋人にするような事はさせてくれない。痛めつけてくれ。そればっかりになってきてね……俺には、ちょっともう理解が出来なかった。怖くなったんだよ」
「そう言う風に接する事を、望月は恋愛だと思っていたって事ですか?」
うーんという顔つきで飯山が、ゼンジを見た。
「何とも言えないんだよね、それが。彼、最初から破滅願望ありきで近寄ってきたような節があったから……そういや、最後に何か妙な事を口走ってたな」
綾が、顔を上げて飯山に訴えた。
「どんな事でも良いから、教えて下さい」
ゼンジも頭を下げる。困惑した表情の飯山は頭をかくと、二人に伝えた。
「桐生ね……俺は、兄貴と母さんの子供になれなかったって言ってたんだよ」
◆
雨は、ますますザーザーとその雨足を強めるばかりで、まるで空が泣いているかのようだった。
ラッシュが始まる少し前の電車に、間に合って乗り込む。あれから蓮波綾は、何かを決心したような顔つきで、黙ったまま正面を見据えていた。
飯山が最後に言っていた言葉が関係しているのかもしれない。
半井ゼンジは、自分が関わっても無駄な相手と関わってしまったような気がして、気後れしてしまっていた。
これ以上、深入りして頑張ってみた所で、飯山と同じ結末になるのではないか。性格はおおよそ似てないが、飯山と自分はおそらく同じ種類の人間だ。
雨が電車の窓を叩きつけるように、斜めの雨だれを残してゆく。
乗車してからどのくらい経っただろうか。綾が、視線を動かさずに話始めた。
「望月君は、やっぱり私と同じだったんだと思う」
「――……虐待の事?」
「うん」
ゼンジは言葉を上手く選べず、彼女の横顔を見ているしかなかった。綾が、少し間を置いて続ける。
「私、ずっと不思議だったの。どうして、望月君が助けてくれたのか。ようやく分かった。私達、本当に世界で二人ぼっちだったんだと思う」
「……二人ぼっち?」
「そう。お互いに、一人ぼっちだったの。だから」
立川駅に到着して、人が水流のように渦を巻きながら行き交う様子を、ぼんやりとゼンジは眺めていた。電車が再び走り出す。
「半井君」
正面を向いていた綾が、ゼンジを見つめていた。まだ、一度も染めたことのない黒髪。大きな黒目。ゼンジは、綾を初めて美しいと思った。
「私、やらなきゃいけないことがあるの。それをしなくちゃ、先に進めない。私は、望月君の居場所になりたい」
「蓮波は、望月の事が好きなのか?」
「うん、好きだよ」
そう言って、綾は初めて笑顔を見せた。大きな黒目が、吹っ切れたように輝く。
「だけど、胸が苦しくなる好きとは違う。そういう好きは、半井君だった」
二人の空間だけが、まるで時が止まってしまったかのようだった。
眠る人
スマホを眺める人
イヤホンをする人
くたびれ果てた人
電車の中にはいる人の数だけ、日常が切り取られて押し込められている。二人にとっては非日常であった今日も、中に紛れてしまえば、取るに足らないちっぽけな日常だ。
「半井君は、望月君の事を好き?」
「――……うん。胸が苦しくなる方の好きだけどな。俺なんかじゃ、きっと何も分かってやれない。どうすれば良いのかも、全然分からない」
「……だから、半井君を好きになったんじゃないかな」
「……?」
「――……分かりあえたら、前の私たちみたいに死ぬしかないねって、なるから」
どちらともなく手を差し出すと、二人はそっと手を繋いだ。俺も、決心をしなくちゃいけない。いや、出来なくてもいい。とにかく前へ、進んでいかないと。
誰かを好きになるっていうのは、苦しくて辛いものだった。それでも、俺は望月の側にいたい。大事だと伝えたい。
「蓮波、ありがとう。俺の事、好きになってくれて」
「私も、ありがとう。半井君の事、好きになれて本当に良かった」
そう言うと綾は、その黒目いっぱいに涙をためながら、最高の笑顔で微笑んだ。ゼンジも、笑顔を返す。
そうして繋いでいた手を離すと、それぞれの駅で降りていった。
それぞれの役割を果たすために。
0
あなたにおすすめの小説
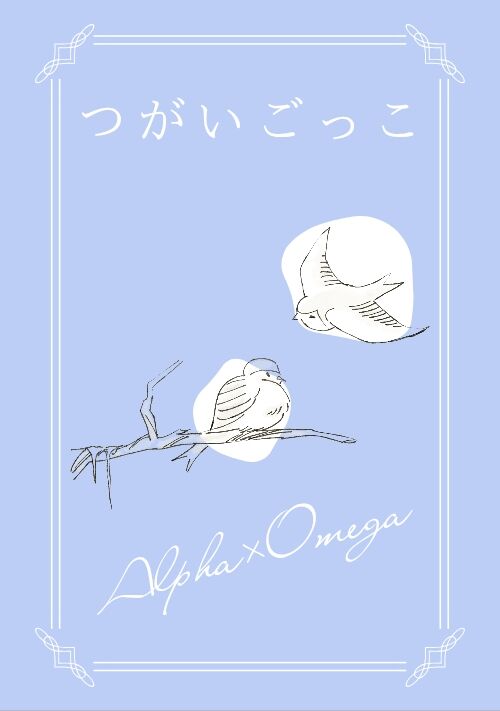
つがいごっこ~4歳のときに番ったらしいアルファと30歳で再会しまして~
深山恐竜
BL
俺は4歳のときにうなじを噛まれて番を得た。
子どもがたくさんいる遊び場で、気が付いたらそうなっていたとか。
相手は誰かわからない。
うなじに残る小さな歯型と、顔も知らない番。
しかし、そのおかげで、番がいないオメガに制限をかけられる社会で俺は自由に生きていた。
そんなある日、俺は番と再会する。
彼には俺の首筋を噛んだという記憶がなかった。
そのせいで、自由を謳歌していた俺とは反対に、彼は苦しんできたらしい。
彼はオメガのフェロモンも感じられず、しかし親にオメガと番うように強制されたことで、すっかりオメガを怖がるようになっていた。
「でも、あなただけは平気なんです。なんででしょう」
首を傾げる彼に、俺は提案する。
「なぁ、俺と番ごっこをしないか?」
偽物の番となった本物の番が繰り広げるラブストーリー。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。


処刑エンドの悪役公爵、隠居したいのに溺愛されてます
ひなた翠
BL
目が覚めたら、やり込んだBLゲームの悪役公爵になっていた。
しかも手には鞭。目の前には涙を浮かべた美少年。
——このままじゃ、王太子に処刑される。
前世は冴えない社畜サラリーマン。今世は冷徹な美貌を持つ高位貴族のアルファ。
中身と外見の落差に戸惑う暇もなく、エリオットは処刑回避のための「隠居計画」を立てる。
囚われのオメガ・レオンを王太子カイルに引き渡し、爵位も領地も全部手放して、ひっそり消える——はずだった。
ところが動くほど状況は悪化していく。
レオンを自由にしようとすれば「傍にいたい」と縋りつかれ、
カイルに会えば「お前の匂いは甘い」と迫られ、
隠居を申し出れば「逃げるな」と退路を塞がれる。
しかもなぜか、子供の頃から飲んでいた「ビタミン剤」を忘れるたび、身体がおかしくなる。
周囲のアルファたちの視線が絡みつき、カイルの目の色が変わり——
自分でも知らなかった秘密が暴かれたとき、逃げ場はもう、どこにもなかった。
誰にも愛されなかった男が、異世界で「本当の自分」を知り、運命の番と出会う——
ギャップ萌え×じれったさ×匂いフェチ全開の、オメガバース転生BL。

冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

2度目の恋 ~忘れられない1度目の恋~
青ムギ
BL
「俺は、生涯お前しか愛さない。」
その言葉を言われたのが社会人2年目の春。
あの時は、確かに俺達には愛が存在していた。
だが、今はー
「仕事が忙しいから先に寝ててくれ。」
「今忙しいんだ。お前に構ってられない。」
冷たく突き放すような言葉ばかりを言って家を空ける日が多くなる。
貴方の視界に、俺は映らないー。
2人の記念日もずっと1人で祝っている。
あの人を想う一方通行の「愛」は苦しく、俺の心を蝕んでいく。
そんなある日、体の不調で病院を受診した際医者から余命宣告を受ける。
あの人の電話はいつも着信拒否。診断結果を伝えようにも伝えられない。
ーもういっそ秘密にしたまま、過ごそうかな。ー
※主人公が悲しい目にあいます。素敵な人に出会わせたいです。
表紙のイラストは、Picrew様の[君の世界メーカー]マサキ様からお借りしました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















