10 / 17
第二章:すれ違う横顔
第十話:埋もれてしまった少年
しおりを挟む
僕は、生まれた時からいない子だった。お母さんは、一回も名前を呼んでくれた事がない。お父さんは、名前を呼んでくれた。たまに本を買ってくれたり、お菓子をくれる。お父さんの事は好きだった。
けれどもお父さんは、ほとんど家に帰って来なかった。
家は、全てがお兄ちゃんを中心に回ってた。
お兄ちゃんは小学校から私立に通っていて、いつもキレイな制服を着ていた。横に並ぶお母さんも、いつだってきれいな着物を着てた。僕にはお母さんとお兄ちゃんが、この世に二人っきりで生きているように見えてた。
けれど、他の家がどうなのか分からない。
僕は、お風呂場で寝起きしてた。
お兄ちゃんには立派な部屋があって、羨ましかった。
ご飯はお風呂場で正座をして、一人で食べるものだと思っていた。冬に暖房がないのも夏に冷房がないのも、それは当たり前の事だと思っていた。お風呂場がカビないよう、お手伝いさんがいつも窓を開けていたから、冬は辛いなって思ったっけ。
お手伝いさんにとっても、僕はいない子だった。ご飯は用意してくれるけど、一度も話をしたことがない。
僕は、自分がもしかしたら幽霊なんじゃないかって、思ったことがある。
お兄ちゃんの制服が変わった頃、僕も小学校へ通うようになった。制服のない学校で、同級生達が夢中になる話題をまるで知らなかった。ゲームとかアニメとか。家の事は話すな、と言われてたから黙って本ばかり読んでいた。
ただ、お兄ちゃんのノートをたまにこっそりと見るのが好きだったから、勉強はとても楽しいと思った。
僕が三年生になったある日、先生が「今日の授業は午前中までですよー」って言った。皆、喜んでいるけど何が嬉しいのか、僕には分からない。家にいるより、学校の方が良かった。
けれど、先生が「桐生君は、いつも本当にお勉強、頑張ってるわね」って言ってくれたんだ。連絡帳に、授業参観に是非来てあげてくださいって書いてくれたんだ。
僕はそれが堪らなく嬉しくて、誰かに見せたいと思ってしまった。
いつもは、帰ったらすぐにお風呂場に行かなきゃいけない。だけど、その日は連絡帳を見せたかったから、お兄ちゃんを探した。お母さんとは、一度も口を聞いた事がない。
明日お父さんが帰ってくるって、お手伝いさんが話していたのは知っていたんだけど。嬉しくて、誰かに見せたかったんだよ。
家は古くて大きいから、どこもかしこも襖だらけ。いつも、迷路へ迷い込んだような気持ちになる。いくつめの襖を開けようとした時だろう。人が動いている音がしたから、なんだろうと思って止まった。
「……?」
襖の隙間から覗き見る。お母さんの着物から、足とお尻が出ているのが見えた。肌があんまりにも白いから、僕はびっくりして息の仕方を忘れてしまった。
すぐに、もう一人いる事に気づいた。
お兄ちゃんだ。
身体が固まって動けない。どうしてだろう。目を閉じる事も出来なかった。
ズボンを脱いだお兄ちゃんが、お母さんのお尻に向かって腰を打ち付けてた。その度に、お母さんが「ヒッ」って苦しそうな声を出してる。二人がぐったりして動かなくなってようやく、足が動くようになった僕は、こっそりそこから逃げ出した。
お兄ちゃんが、お母さんをいじめてる。
僕は、すごく怖くなってお風呂場で膝を抱えてた。ご飯も食べられなくて、ひたすらお父さんが帰ってくるのを待った。
連絡帳の事は、すっかり忘れてしまっていた。
翌日、お父さんが帰ってきた。
僕は、お父さんに話したんだ。怖かったから。お兄ちゃんに、お母さんをいじめないであげてって。どんな風に?って聞かれたから、見たことを全部、話したんだ。
それからだ。
「そこで見てろ」
ってお母さんをいじめる度に、お兄ちゃんから言われるようになったのは。
柱に括り付けられて、口の中にタオルを押し込まれる。僕を縛り付ける時、お兄ちゃんはすごく嬉しそうだった。お母さんは、いつだって僕に興味がない。そこら辺に転がってる石ころでも見てるみたいな顔をして、僕を見る。
「母さん、コイツの前でいつもみたいにしてよ」
お母さんは、ほんの少しだけ僕の方を見ると、お兄ちゃんのおちんちんを舐めだした。人に見られてると興奮するって笑ってた。顔がどんどん紅くなる。そんなお母さんを変態と言う時も、お兄ちゃんはすごく嬉しそうだった。
僕は、ただひたすらに怖かった。
目を閉じると、おちんちんをつねられる。
お母さんが、お兄ちゃんをいじめてる日もあった。上に乗って、お餅つきみたいな事をしてる。苦しそうな声で必ず、お兄ちゃんの名前を呼ぶ。
「カイ……」
僕は、お母さんから名前を呼んで貰った事がない。
縛られるのは、怖い。口の中にタオルを押し込まれるのも、苦しい。つねられるのは、痛い。でも、助けてくれる人がいない。だから、我慢するしかなかった。
なんで、お互いに裸でいじめ合うんだろう。
それを僕に見せて、喜んでるんだろう。
そうして散々いじめ合った後で、お兄ちゃんが必ず言うんだ。
「お前は、僕と母さんの子供になれなかったね」
って。
やっぱり嬉しそうな顔をして。
二人の子供じゃなかったから、僕はこんな事をされるの?二人の子供だったら、名前を呼んでもらえるの?聞きたくても、聞けなかった。僕から話しかける事は、許されてなかったから。
お母さんはいじめられてる間だけ、僕を見て悲鳴みたいな声を出してた。けれども、いじめが終わると、すぐにそこら辺の石ころでも見てるみたいな顔になる。
お父さんは僕が言いつけたその日から、家に帰って来なくなった。
ただ一人「リク」って、名前を呼んでくれたお父さん。
こうなっちゃったのは全部、僕のせいなの?
◆
やっぱり餃子パーティーは正義だと、飯山ハルキは思う。土日に二人で作って、沢山ストックしておいた、普通の餃子とシソ餃子を鉄板プレートで焼きながら、ビールで乾杯をする。明日は瀬能ゴウの定休日。だから、餃子。
どうでもいい話をしながら、ケラケラと笑いあってる時が好きだ。一番の幸せだと思う。
二本目のビールを開けながら今日あった出来事を、ハルキは愚痴っぽく話してしまっていた。ゴウなら、絶対に聞いてくれる。そういう信頼があった。
「いきなりだよ?いきなり、桐生リクの事を話して欲しいって来られてさあ。困っちゃったよ。何か、高校でも問題起こしたみたいで」
ゴウが「アラー」とでも言いたげな顔をして、話を聞いていた。半分は、呆れも入っているようだったが。
「そんで、過去の関係を洗いざらい話したわけ?」
「いや……流石に全部は無理でしょ。でも、要点をかいつまんでいくつか。聞きたいのは、そっちじゃなかったっぽいけどね」
「っていうと?」
「家の事じゃないかな。一応は、僕も教師だったわけだし。付き合ってた時に、虐待を疑ってたのは事実なんだよ。けれど、あの辺じゃ名家でね。桐生の家って。父親が入り婿だったって事と、年の離れた兄がいるくらいしか、本当に話が入ってこなかったんだよな」
「ふうん……で、その二人は桐生君のお友達なの?」
「友達っていうか……何だろ。訳あり、みたいな感じ。蓮波って子は、事件にもなったよ。ゴウちゃんも知ってるだろ?新興宗教の」
「ああ……」
うんざりとした面持ちで、ゴウがビールに口をつける。あれは、本当に胸糞悪い事件だった。再婚相手の子供を性的虐待していたばかりか、若い女性信者や、果ては子どもにまで手をつけていたっていう話だ。
未だに、ネットニュースの記事になる。教団が組織ぐるみでやっていた疑いがあるとかで、裁判が長引いているからだ。
ゴウは気を取り直して聞いた。
「で、男の子の方はどうだったの?」
「少し、俺と見た目が似てたよ。背が高くて、目がシュッとしてるとことか。あっちのほうが暗い感じだったけど」
ゴウはプッと吹き出しながら、シソ餃子にポン酢をかけた。
「悪いけど、ハルキ。キャラと見た目が、全然合ってないんだよね。黙ってるだけなら、いかにもなイケメンなのに。男の子の方が、解釈としては正解なんじゃない」
「……人の事、残念みたいに言うなよ」
「僕も会ってみたかったなー!ナカライ君。キュンキュンしちゃいそう」
「え?嘘でしょ?」
急に不安げな表情をして固まってしまったハルキの頬に、チュッとゴウがキスをした。
「うわっ餃子くさ」
「なんだそれ。ワイン飲むか?白で良いよな、取ってくる」
立ち上がってキッチンへ向かったハルキを見届けると、ゴウはスマホを取り出して神妙な面持ちで見つめた。
この数日どうにも気になることがあったのだが、自分から言っていいものとも思えなかった。ハルキは、リクの話をするのを露骨に避けていた。それは気を遣っての事かもしれないけれども。
まあ、自ら脛の傷に塩を塗り込むような過去の話なんて、したくないのが本音だよね。
それにしたって。
リクが良くないのと一緒にいると警告したにも関わらず、知らん顔はないだろう。面倒な事を回避したがるハルキの欠点を、ゴウは好きになれなかった。
白ワインとグラスをもったハルキが、ゴウのスマホを覗き込んでいる。
「どしたの?」
振り返ったゴウは真面目な顔でハルキを見つめると、改まった様子で話しだした。
「聞きたくないなら、これ以上は話さないけどさ。桐生君、信誠会の構成員と関係してるよ」
ハルキの顔が、にわかに曇る。テーブルにワインとグラスを置くと、席に着いた。
「何、その信誠会って。ヤクザ?」
「……まあ、そうだね。地下賭博をシノギにしてるらしくて。売春、クスリなんでもござれって感じらしいんだわ。ニチョの兄さんの店からもさ、一人そっちに行って、行方不明になっちゃった子がいて」
「意味が分かんないな。地下賭博で売春?」
「奥で、ハプバーみたいなのをやってるのよ。むしろ、そっちが本業。SMショーやったり。で、連れ出しとクスリ。これでワンセット」
カランッ……
箸が床へ転げ落ちてゆく音がする。ハルキは口を開けたまま、絶句していた。ゴウは立ち上がると、あらかた食べ終わった鉄板に、水を流し込みながら話を続けた。鉄板はジュージューと湯けむりをあげている。
「このまま知らん顔でもいいけどさ、ハルキ。あの子、ほっといたら取り返しがつかなくなると思うよ。元恋人じゃなくてもいいわ。元教師として、そこら辺どうなの?」
ハルキは立ち上がると慌ててスマホを取り出し、LINEで誰かに連絡をしはじめた。すぐに通話コールが鳴る。
「あ、もしもし。今日はどうも。飯山です。半井君……で良かったよね。桐生……じゃなかった望月の事で、大事な話があるんだけど」
話ながら、ハルキは寝室へと入っていった。
これで知らん顔するなら、嫌いになるところだったわ。思わず安堵のため息がこぼれてしまうのを、ゴウは感じていた。換気扇の下でタバコに火をつける。そうして口から煙をくゆらせながら、自分の若い頃に思いを馳せていた。
◆
コンビニで買い物を済ませた長野セツナは、アパートに戻る途中でずぶ濡れの望月リクを見かけて、飛び上がるほど驚いた。一体、どこでどう調べたのか。このアパートに引っ越して来たのは、たった一ヶ月前の話だ。
首と手首の傷痕が、痛々しさを際立たせている。さして治安の良くない新宿近辺のアパートだったが、それでも通行人がジロジロと見ていた。リクに名前を呼ばれそうになったので仕方なく、アパートに連れて来たのだった。
寒さで震えて、捨て猫みたいになっているリクにバスタオルを投げると、とりあえずベッドで横になるよう促す。
着ているものを全て脱いだリクは、身体を拭くとベッドに潜り込み、そのまま眠ってしまった。セツナはつい昨日の出来事を、遠い過去のような感覚で思い出していた。
昨日は、こちらから事前に手錠と首輪を用意していた。二日も続けて、しかもリクの方から会いたがるなんて出来事は初めだ。セツナは浮かれていた。
けれど
リクも少しは自分を見てくれてるのかと、ぬか喜びした俺がバカだった。
安ホテルでリクが鞄から出したのは、いつの時代のだよ!と叫びたくなるような麻の縄だった。
「……なにこれ。マジで言ってんの?てか、こんなんどっから持ってきたんだよ」
「え?家の納屋。マジで言ってる。これで締めて」
締め方が分からないと言って逃げようとしたが、リクを相手にそれは無駄もいいところだった。ご丁寧に動画を用意していて、それを見本にしろと言われる。
首と繋がるようにして、両手を後ろに組んで縛るやり方だった。
恐る恐る締めていくウチに、リクの身体が赤く火照りだした。それを見ていたセツナは、あっけなくに欲情に流されてしまった。
「……ハァ……ねえ、縄に水かけて」
身悶えしながら、リクが言う。動く度に縄が擦れて、肌には薄っすらと血が滲んだ。
「水かけると、縄が余計に締まるんだって」
言われた通り水をかけてやると、四つん這いになったリクがセツナを誘った。舌が口の脇から出ていて、チロチロと動いている。既に目はトロンとしていて、呼応するように尻の入り口もヒクヒクとセツナを誘っていた。
まるで淫靡な獣だ。
我慢できなくなったセツナは交尾の如く、後ろから自分の塊でリクの尻を貫いた。
「ィイ……!……アゥグッ!」
首が締まっているのか、リクの喘ぎ声がおかしくなる。おかしくなればなるほど、下の締め付けもきつくなった。この間みたいに呼吸しなくなるとか言うのがなければ、これほどの絶景もないもんだ、とセツナは思っていた。
リクの白い身体に、赤い蛇の入れ墨がしてあるように見える。
「背中ッ……!噛んで!……ハァ、アッ……血が出るくらい、噛んで!」
殆ど悲鳴のようなリクの声が聞こえた。思い切り右の肩甲骨の辺りを噛んでやると、リクが痙攣をしながら白くて濃い分身をほとばしらせた。
締め付けが、更にきつくなる。
「ァア……ダメだ……でっ出る!中に出すぞ!……ッ!」
セツナが後ろで組んである縄を引っ張りながら、その身体を震わせる。背中の咬み傷からツーッと血を流したリクが、細い腰を思い切りのけぞらせてきた。チカッと目の前を火花が散って、そのまま二人で果てた。
結局、一回では飽き足らず四回もしてしまった。
リクは誰とも一緒に浴室には入らない。いつも一人でシャワーを浴びて、中のものを掻き出してくるのだが、改めて見るその裸体は酷い有様だった。
まだ右目の痣も痛々しいというのに、今しがた出来たばかりの傷で、どれだけ拭いても拭いバスタオルに血が付着する。止血はするな、と言いたいのだろう。リクはバスタオルを持つセツナの手を雑に振り払った。
セツナは罪悪感の絶頂にいた。
リクは殊の外、満足そうだったが。
ハッと我に返ったセツナが、シャツを羽織りながら髪をセットする。寝ている間にチラッと見えた傷痕は、まだ直視出来ない状態だった。
ヤってる最中は、すげえ興奮すんのになあ……
「どっかいくの?」
ベッドから、細い手が出てきてヒラヒラと舞う。そのうち、茶色の髪が毛布から出てきた。鏡越しに、リクとセツナの目が合う。
これ以上は到底無理と言った所で、リクは絶対に自分を壊してくれと訴えてくる。この先、こんな毎日が続くのかと思うと、セツナは心底うんざりとした気持ちになっていた。
去年は、ここまで酷くなかった筈なんだけど。
酷くなる前に、俺が捨てられただけかもしんねえから、分かんねえんだよなあ……。
だったらいっそ。
セツナは、複雑な事を考えるのが苦手だった。
「リク。お前、バイトしろよ。好きなだけ変態に殴ってもらいながらセックス出来て、2万もらえるぜ」
「セツナ、俺が誰かとすんの嫌じゃないの?」
「……前はな」
目が合ったときから、リクの顔からは血の気が引いていた。
捨てられる時の予兆はいつだって同じ。
俺の満足は誰かを疲弊させる。
セツナを見る顔が、キュッと強張る。
「――……あっそ」
「まあ、悪い話じゃないだろ。考えといてくれよ」
そう言うとセツナは、トイレに籠もったきり出てこなくなった。
「バーカ、バーカ」
鼻歌でも歌ってるように口ずさんだ裸のリクが、ベッドから出てくる。
好きなだけ殴ってもらいながら、セックスしてお金が貰えるのか……それは実に素晴らしい話だ。けど、うっかり全然知らないやつに殺されちゃうってのもなあ。
テーブルに雑然と置かれているタバコに火をつける。
リクは、死を儀式として捉えているところがあった。だから蓮波綾にも、あんなに遠回しなやり方で心中を迫っていたのである。一応、本人の自覚する所では。
きっと兄貴と母親のあんなものを、小さい頃から無理やり鑑賞させられてきたからだ。近親相姦してる俺たちを見ていろ、とかさ。気色悪いにも程がある。
気色悪すぎて壊れたんだ、俺は。
誰も居なくなった家で、今でも兄貴と母親は毎日セックスをしているだろう。
「へーんたい、へーんたい」
パンツを履いたリクは背中の咬み傷に手をやって、痛みがそこにある事を確認すると、眉を切なげにしかめた。
どうして俺は、こんな事しか出来ないんだろう。
「立てって言ってるだろ!望月!」
「いい加減にしろよ。そんな事して何が楽しい」
半井ゼンジは本気で怒ってた。俺はあんな風にして、他人から中に入ってこられた事がない。相手の中へ入ってみたいと思ったのも、初めてだ。
アイツは、俺の背中の咬み傷を見たら何て言っただろうか。
いっそ軽蔑してほしかった。
嫌ったままでいてほしかった。
そうすれば俺は、溺れている事に気づかないで済んだのに。
泣きじゃくる半井の姿が脳裏に浮かぶ度、今すぐにでも自分を破壊してしまいたい衝動が襲ってくる。
なんで、俺のためなんかで泣くんだよ。
――……誰か、助けて。
「望月君、ごめんね。ずっと、気が付かなくて」
「本当に死にたかったのは、望月君だったんだよね」
うるさい!蓮波。お前にだけは、そんな風に憐れまれたくないんだよ!
ふと、自分が綾に向けてきた態度に、兄の面影をみたリクは激しい吐き気に襲われた。
あんな狂ったのと、一緒にするな!
今にも破裂しそうな感情が暴走を始め、頭を抱える。
痛い!頭が割れそうだ!
「そんで決めてくれた?」
目をトロンとさせたセツナが、トイレから出てきた。やたら早口で聞いてくる。
こめかみを押さえながら振り返ったリクは、トイレから薬品が焦げたような臭いに気づいてイラッとした声を上げた。
「ハァ?キマってんの、自分じゃない。一生カタギになれないやつが、一丁前に罪悪感で苦しむとか。すごく滑稽だよ」
軽蔑の眼差しをセツナへ向けズボンを履いて、ベルトを締める。
「お前だって同じだろ?どう見ても、マトモになんか生きてねえじゃん。いい加減、覚悟決めろよ」
「……とっくに決めてるよ、そんなの」
そう吐き捨てると、まだ半乾きのシャツを着ながらリクは鏡を見た。
売春と薬物による、なにかしらの事故死。
それって非常に俺らしいっちゃ、俺らしい最期だよな。
自殺は、惨め過ぎるから嫌だ。
とっとと廃人になって、そのまま野垂れ死にたい。
そうしたら、もう何も見ないで済む。
リクは髪をかき上げながら痣を見て、これなら今日からでも変態の商品として使い物になりそうだ、と考えた。
終幕は早ければ早い方がいい。
儀式は、もういらない。
「バイトするよ。荷物だけ、家へ取りに行ってくる」
それこそラリって使い物にならないセツナを残して、リクは部屋を去っていった。
◆
雨はそのまま降り続いている。もうこの家ともお別れ。離れに生活感を残してこなかったのは、彼の中にある儀式へのこだわりと同種の何かだった。
誰かに気づいて欲しいという、虚しい叫び。
ずっと一人ぼっちだったけど、あのダイニングの窓から見る月明かりだけは好きだったな。
望月リクは、日の暮れた雨雲を見上げた。
「あっめあめ、ふっれふれ、かあさんと~♪」
歌いながら跳ねるようにして、水たまりを避けていった。門をくぐってからは鼻歌に変える。人気のない母屋を横目に、リクは胸のすくような解放感を覚えた。
ああ、どのくらいぶりだろう。こんなに楽しい気持ちなのは。もうすぐ、全てが終わる。何もなくなるんだ。
ようやく俺は、暗闇の中を一人で眠る事が出来る。
もう誰も、俺の中には入ってこない。
くだらない何かを求めないで済む。
離れの扉を開けてダイニングを通り過ぎようとすると、そこには半井ゼンジが佇んでいた。
けれどもお父さんは、ほとんど家に帰って来なかった。
家は、全てがお兄ちゃんを中心に回ってた。
お兄ちゃんは小学校から私立に通っていて、いつもキレイな制服を着ていた。横に並ぶお母さんも、いつだってきれいな着物を着てた。僕にはお母さんとお兄ちゃんが、この世に二人っきりで生きているように見えてた。
けれど、他の家がどうなのか分からない。
僕は、お風呂場で寝起きしてた。
お兄ちゃんには立派な部屋があって、羨ましかった。
ご飯はお風呂場で正座をして、一人で食べるものだと思っていた。冬に暖房がないのも夏に冷房がないのも、それは当たり前の事だと思っていた。お風呂場がカビないよう、お手伝いさんがいつも窓を開けていたから、冬は辛いなって思ったっけ。
お手伝いさんにとっても、僕はいない子だった。ご飯は用意してくれるけど、一度も話をしたことがない。
僕は、自分がもしかしたら幽霊なんじゃないかって、思ったことがある。
お兄ちゃんの制服が変わった頃、僕も小学校へ通うようになった。制服のない学校で、同級生達が夢中になる話題をまるで知らなかった。ゲームとかアニメとか。家の事は話すな、と言われてたから黙って本ばかり読んでいた。
ただ、お兄ちゃんのノートをたまにこっそりと見るのが好きだったから、勉強はとても楽しいと思った。
僕が三年生になったある日、先生が「今日の授業は午前中までですよー」って言った。皆、喜んでいるけど何が嬉しいのか、僕には分からない。家にいるより、学校の方が良かった。
けれど、先生が「桐生君は、いつも本当にお勉強、頑張ってるわね」って言ってくれたんだ。連絡帳に、授業参観に是非来てあげてくださいって書いてくれたんだ。
僕はそれが堪らなく嬉しくて、誰かに見せたいと思ってしまった。
いつもは、帰ったらすぐにお風呂場に行かなきゃいけない。だけど、その日は連絡帳を見せたかったから、お兄ちゃんを探した。お母さんとは、一度も口を聞いた事がない。
明日お父さんが帰ってくるって、お手伝いさんが話していたのは知っていたんだけど。嬉しくて、誰かに見せたかったんだよ。
家は古くて大きいから、どこもかしこも襖だらけ。いつも、迷路へ迷い込んだような気持ちになる。いくつめの襖を開けようとした時だろう。人が動いている音がしたから、なんだろうと思って止まった。
「……?」
襖の隙間から覗き見る。お母さんの着物から、足とお尻が出ているのが見えた。肌があんまりにも白いから、僕はびっくりして息の仕方を忘れてしまった。
すぐに、もう一人いる事に気づいた。
お兄ちゃんだ。
身体が固まって動けない。どうしてだろう。目を閉じる事も出来なかった。
ズボンを脱いだお兄ちゃんが、お母さんのお尻に向かって腰を打ち付けてた。その度に、お母さんが「ヒッ」って苦しそうな声を出してる。二人がぐったりして動かなくなってようやく、足が動くようになった僕は、こっそりそこから逃げ出した。
お兄ちゃんが、お母さんをいじめてる。
僕は、すごく怖くなってお風呂場で膝を抱えてた。ご飯も食べられなくて、ひたすらお父さんが帰ってくるのを待った。
連絡帳の事は、すっかり忘れてしまっていた。
翌日、お父さんが帰ってきた。
僕は、お父さんに話したんだ。怖かったから。お兄ちゃんに、お母さんをいじめないであげてって。どんな風に?って聞かれたから、見たことを全部、話したんだ。
それからだ。
「そこで見てろ」
ってお母さんをいじめる度に、お兄ちゃんから言われるようになったのは。
柱に括り付けられて、口の中にタオルを押し込まれる。僕を縛り付ける時、お兄ちゃんはすごく嬉しそうだった。お母さんは、いつだって僕に興味がない。そこら辺に転がってる石ころでも見てるみたいな顔をして、僕を見る。
「母さん、コイツの前でいつもみたいにしてよ」
お母さんは、ほんの少しだけ僕の方を見ると、お兄ちゃんのおちんちんを舐めだした。人に見られてると興奮するって笑ってた。顔がどんどん紅くなる。そんなお母さんを変態と言う時も、お兄ちゃんはすごく嬉しそうだった。
僕は、ただひたすらに怖かった。
目を閉じると、おちんちんをつねられる。
お母さんが、お兄ちゃんをいじめてる日もあった。上に乗って、お餅つきみたいな事をしてる。苦しそうな声で必ず、お兄ちゃんの名前を呼ぶ。
「カイ……」
僕は、お母さんから名前を呼んで貰った事がない。
縛られるのは、怖い。口の中にタオルを押し込まれるのも、苦しい。つねられるのは、痛い。でも、助けてくれる人がいない。だから、我慢するしかなかった。
なんで、お互いに裸でいじめ合うんだろう。
それを僕に見せて、喜んでるんだろう。
そうして散々いじめ合った後で、お兄ちゃんが必ず言うんだ。
「お前は、僕と母さんの子供になれなかったね」
って。
やっぱり嬉しそうな顔をして。
二人の子供じゃなかったから、僕はこんな事をされるの?二人の子供だったら、名前を呼んでもらえるの?聞きたくても、聞けなかった。僕から話しかける事は、許されてなかったから。
お母さんはいじめられてる間だけ、僕を見て悲鳴みたいな声を出してた。けれども、いじめが終わると、すぐにそこら辺の石ころでも見てるみたいな顔になる。
お父さんは僕が言いつけたその日から、家に帰って来なくなった。
ただ一人「リク」って、名前を呼んでくれたお父さん。
こうなっちゃったのは全部、僕のせいなの?
◆
やっぱり餃子パーティーは正義だと、飯山ハルキは思う。土日に二人で作って、沢山ストックしておいた、普通の餃子とシソ餃子を鉄板プレートで焼きながら、ビールで乾杯をする。明日は瀬能ゴウの定休日。だから、餃子。
どうでもいい話をしながら、ケラケラと笑いあってる時が好きだ。一番の幸せだと思う。
二本目のビールを開けながら今日あった出来事を、ハルキは愚痴っぽく話してしまっていた。ゴウなら、絶対に聞いてくれる。そういう信頼があった。
「いきなりだよ?いきなり、桐生リクの事を話して欲しいって来られてさあ。困っちゃったよ。何か、高校でも問題起こしたみたいで」
ゴウが「アラー」とでも言いたげな顔をして、話を聞いていた。半分は、呆れも入っているようだったが。
「そんで、過去の関係を洗いざらい話したわけ?」
「いや……流石に全部は無理でしょ。でも、要点をかいつまんでいくつか。聞きたいのは、そっちじゃなかったっぽいけどね」
「っていうと?」
「家の事じゃないかな。一応は、僕も教師だったわけだし。付き合ってた時に、虐待を疑ってたのは事実なんだよ。けれど、あの辺じゃ名家でね。桐生の家って。父親が入り婿だったって事と、年の離れた兄がいるくらいしか、本当に話が入ってこなかったんだよな」
「ふうん……で、その二人は桐生君のお友達なの?」
「友達っていうか……何だろ。訳あり、みたいな感じ。蓮波って子は、事件にもなったよ。ゴウちゃんも知ってるだろ?新興宗教の」
「ああ……」
うんざりとした面持ちで、ゴウがビールに口をつける。あれは、本当に胸糞悪い事件だった。再婚相手の子供を性的虐待していたばかりか、若い女性信者や、果ては子どもにまで手をつけていたっていう話だ。
未だに、ネットニュースの記事になる。教団が組織ぐるみでやっていた疑いがあるとかで、裁判が長引いているからだ。
ゴウは気を取り直して聞いた。
「で、男の子の方はどうだったの?」
「少し、俺と見た目が似てたよ。背が高くて、目がシュッとしてるとことか。あっちのほうが暗い感じだったけど」
ゴウはプッと吹き出しながら、シソ餃子にポン酢をかけた。
「悪いけど、ハルキ。キャラと見た目が、全然合ってないんだよね。黙ってるだけなら、いかにもなイケメンなのに。男の子の方が、解釈としては正解なんじゃない」
「……人の事、残念みたいに言うなよ」
「僕も会ってみたかったなー!ナカライ君。キュンキュンしちゃいそう」
「え?嘘でしょ?」
急に不安げな表情をして固まってしまったハルキの頬に、チュッとゴウがキスをした。
「うわっ餃子くさ」
「なんだそれ。ワイン飲むか?白で良いよな、取ってくる」
立ち上がってキッチンへ向かったハルキを見届けると、ゴウはスマホを取り出して神妙な面持ちで見つめた。
この数日どうにも気になることがあったのだが、自分から言っていいものとも思えなかった。ハルキは、リクの話をするのを露骨に避けていた。それは気を遣っての事かもしれないけれども。
まあ、自ら脛の傷に塩を塗り込むような過去の話なんて、したくないのが本音だよね。
それにしたって。
リクが良くないのと一緒にいると警告したにも関わらず、知らん顔はないだろう。面倒な事を回避したがるハルキの欠点を、ゴウは好きになれなかった。
白ワインとグラスをもったハルキが、ゴウのスマホを覗き込んでいる。
「どしたの?」
振り返ったゴウは真面目な顔でハルキを見つめると、改まった様子で話しだした。
「聞きたくないなら、これ以上は話さないけどさ。桐生君、信誠会の構成員と関係してるよ」
ハルキの顔が、にわかに曇る。テーブルにワインとグラスを置くと、席に着いた。
「何、その信誠会って。ヤクザ?」
「……まあ、そうだね。地下賭博をシノギにしてるらしくて。売春、クスリなんでもござれって感じらしいんだわ。ニチョの兄さんの店からもさ、一人そっちに行って、行方不明になっちゃった子がいて」
「意味が分かんないな。地下賭博で売春?」
「奥で、ハプバーみたいなのをやってるのよ。むしろ、そっちが本業。SMショーやったり。で、連れ出しとクスリ。これでワンセット」
カランッ……
箸が床へ転げ落ちてゆく音がする。ハルキは口を開けたまま、絶句していた。ゴウは立ち上がると、あらかた食べ終わった鉄板に、水を流し込みながら話を続けた。鉄板はジュージューと湯けむりをあげている。
「このまま知らん顔でもいいけどさ、ハルキ。あの子、ほっといたら取り返しがつかなくなると思うよ。元恋人じゃなくてもいいわ。元教師として、そこら辺どうなの?」
ハルキは立ち上がると慌ててスマホを取り出し、LINEで誰かに連絡をしはじめた。すぐに通話コールが鳴る。
「あ、もしもし。今日はどうも。飯山です。半井君……で良かったよね。桐生……じゃなかった望月の事で、大事な話があるんだけど」
話ながら、ハルキは寝室へと入っていった。
これで知らん顔するなら、嫌いになるところだったわ。思わず安堵のため息がこぼれてしまうのを、ゴウは感じていた。換気扇の下でタバコに火をつける。そうして口から煙をくゆらせながら、自分の若い頃に思いを馳せていた。
◆
コンビニで買い物を済ませた長野セツナは、アパートに戻る途中でずぶ濡れの望月リクを見かけて、飛び上がるほど驚いた。一体、どこでどう調べたのか。このアパートに引っ越して来たのは、たった一ヶ月前の話だ。
首と手首の傷痕が、痛々しさを際立たせている。さして治安の良くない新宿近辺のアパートだったが、それでも通行人がジロジロと見ていた。リクに名前を呼ばれそうになったので仕方なく、アパートに連れて来たのだった。
寒さで震えて、捨て猫みたいになっているリクにバスタオルを投げると、とりあえずベッドで横になるよう促す。
着ているものを全て脱いだリクは、身体を拭くとベッドに潜り込み、そのまま眠ってしまった。セツナはつい昨日の出来事を、遠い過去のような感覚で思い出していた。
昨日は、こちらから事前に手錠と首輪を用意していた。二日も続けて、しかもリクの方から会いたがるなんて出来事は初めだ。セツナは浮かれていた。
けれど
リクも少しは自分を見てくれてるのかと、ぬか喜びした俺がバカだった。
安ホテルでリクが鞄から出したのは、いつの時代のだよ!と叫びたくなるような麻の縄だった。
「……なにこれ。マジで言ってんの?てか、こんなんどっから持ってきたんだよ」
「え?家の納屋。マジで言ってる。これで締めて」
締め方が分からないと言って逃げようとしたが、リクを相手にそれは無駄もいいところだった。ご丁寧に動画を用意していて、それを見本にしろと言われる。
首と繋がるようにして、両手を後ろに組んで縛るやり方だった。
恐る恐る締めていくウチに、リクの身体が赤く火照りだした。それを見ていたセツナは、あっけなくに欲情に流されてしまった。
「……ハァ……ねえ、縄に水かけて」
身悶えしながら、リクが言う。動く度に縄が擦れて、肌には薄っすらと血が滲んだ。
「水かけると、縄が余計に締まるんだって」
言われた通り水をかけてやると、四つん這いになったリクがセツナを誘った。舌が口の脇から出ていて、チロチロと動いている。既に目はトロンとしていて、呼応するように尻の入り口もヒクヒクとセツナを誘っていた。
まるで淫靡な獣だ。
我慢できなくなったセツナは交尾の如く、後ろから自分の塊でリクの尻を貫いた。
「ィイ……!……アゥグッ!」
首が締まっているのか、リクの喘ぎ声がおかしくなる。おかしくなればなるほど、下の締め付けもきつくなった。この間みたいに呼吸しなくなるとか言うのがなければ、これほどの絶景もないもんだ、とセツナは思っていた。
リクの白い身体に、赤い蛇の入れ墨がしてあるように見える。
「背中ッ……!噛んで!……ハァ、アッ……血が出るくらい、噛んで!」
殆ど悲鳴のようなリクの声が聞こえた。思い切り右の肩甲骨の辺りを噛んでやると、リクが痙攣をしながら白くて濃い分身をほとばしらせた。
締め付けが、更にきつくなる。
「ァア……ダメだ……でっ出る!中に出すぞ!……ッ!」
セツナが後ろで組んである縄を引っ張りながら、その身体を震わせる。背中の咬み傷からツーッと血を流したリクが、細い腰を思い切りのけぞらせてきた。チカッと目の前を火花が散って、そのまま二人で果てた。
結局、一回では飽き足らず四回もしてしまった。
リクは誰とも一緒に浴室には入らない。いつも一人でシャワーを浴びて、中のものを掻き出してくるのだが、改めて見るその裸体は酷い有様だった。
まだ右目の痣も痛々しいというのに、今しがた出来たばかりの傷で、どれだけ拭いても拭いバスタオルに血が付着する。止血はするな、と言いたいのだろう。リクはバスタオルを持つセツナの手を雑に振り払った。
セツナは罪悪感の絶頂にいた。
リクは殊の外、満足そうだったが。
ハッと我に返ったセツナが、シャツを羽織りながら髪をセットする。寝ている間にチラッと見えた傷痕は、まだ直視出来ない状態だった。
ヤってる最中は、すげえ興奮すんのになあ……
「どっかいくの?」
ベッドから、細い手が出てきてヒラヒラと舞う。そのうち、茶色の髪が毛布から出てきた。鏡越しに、リクとセツナの目が合う。
これ以上は到底無理と言った所で、リクは絶対に自分を壊してくれと訴えてくる。この先、こんな毎日が続くのかと思うと、セツナは心底うんざりとした気持ちになっていた。
去年は、ここまで酷くなかった筈なんだけど。
酷くなる前に、俺が捨てられただけかもしんねえから、分かんねえんだよなあ……。
だったらいっそ。
セツナは、複雑な事を考えるのが苦手だった。
「リク。お前、バイトしろよ。好きなだけ変態に殴ってもらいながらセックス出来て、2万もらえるぜ」
「セツナ、俺が誰かとすんの嫌じゃないの?」
「……前はな」
目が合ったときから、リクの顔からは血の気が引いていた。
捨てられる時の予兆はいつだって同じ。
俺の満足は誰かを疲弊させる。
セツナを見る顔が、キュッと強張る。
「――……あっそ」
「まあ、悪い話じゃないだろ。考えといてくれよ」
そう言うとセツナは、トイレに籠もったきり出てこなくなった。
「バーカ、バーカ」
鼻歌でも歌ってるように口ずさんだ裸のリクが、ベッドから出てくる。
好きなだけ殴ってもらいながら、セックスしてお金が貰えるのか……それは実に素晴らしい話だ。けど、うっかり全然知らないやつに殺されちゃうってのもなあ。
テーブルに雑然と置かれているタバコに火をつける。
リクは、死を儀式として捉えているところがあった。だから蓮波綾にも、あんなに遠回しなやり方で心中を迫っていたのである。一応、本人の自覚する所では。
きっと兄貴と母親のあんなものを、小さい頃から無理やり鑑賞させられてきたからだ。近親相姦してる俺たちを見ていろ、とかさ。気色悪いにも程がある。
気色悪すぎて壊れたんだ、俺は。
誰も居なくなった家で、今でも兄貴と母親は毎日セックスをしているだろう。
「へーんたい、へーんたい」
パンツを履いたリクは背中の咬み傷に手をやって、痛みがそこにある事を確認すると、眉を切なげにしかめた。
どうして俺は、こんな事しか出来ないんだろう。
「立てって言ってるだろ!望月!」
「いい加減にしろよ。そんな事して何が楽しい」
半井ゼンジは本気で怒ってた。俺はあんな風にして、他人から中に入ってこられた事がない。相手の中へ入ってみたいと思ったのも、初めてだ。
アイツは、俺の背中の咬み傷を見たら何て言っただろうか。
いっそ軽蔑してほしかった。
嫌ったままでいてほしかった。
そうすれば俺は、溺れている事に気づかないで済んだのに。
泣きじゃくる半井の姿が脳裏に浮かぶ度、今すぐにでも自分を破壊してしまいたい衝動が襲ってくる。
なんで、俺のためなんかで泣くんだよ。
――……誰か、助けて。
「望月君、ごめんね。ずっと、気が付かなくて」
「本当に死にたかったのは、望月君だったんだよね」
うるさい!蓮波。お前にだけは、そんな風に憐れまれたくないんだよ!
ふと、自分が綾に向けてきた態度に、兄の面影をみたリクは激しい吐き気に襲われた。
あんな狂ったのと、一緒にするな!
今にも破裂しそうな感情が暴走を始め、頭を抱える。
痛い!頭が割れそうだ!
「そんで決めてくれた?」
目をトロンとさせたセツナが、トイレから出てきた。やたら早口で聞いてくる。
こめかみを押さえながら振り返ったリクは、トイレから薬品が焦げたような臭いに気づいてイラッとした声を上げた。
「ハァ?キマってんの、自分じゃない。一生カタギになれないやつが、一丁前に罪悪感で苦しむとか。すごく滑稽だよ」
軽蔑の眼差しをセツナへ向けズボンを履いて、ベルトを締める。
「お前だって同じだろ?どう見ても、マトモになんか生きてねえじゃん。いい加減、覚悟決めろよ」
「……とっくに決めてるよ、そんなの」
そう吐き捨てると、まだ半乾きのシャツを着ながらリクは鏡を見た。
売春と薬物による、なにかしらの事故死。
それって非常に俺らしいっちゃ、俺らしい最期だよな。
自殺は、惨め過ぎるから嫌だ。
とっとと廃人になって、そのまま野垂れ死にたい。
そうしたら、もう何も見ないで済む。
リクは髪をかき上げながら痣を見て、これなら今日からでも変態の商品として使い物になりそうだ、と考えた。
終幕は早ければ早い方がいい。
儀式は、もういらない。
「バイトするよ。荷物だけ、家へ取りに行ってくる」
それこそラリって使い物にならないセツナを残して、リクは部屋を去っていった。
◆
雨はそのまま降り続いている。もうこの家ともお別れ。離れに生活感を残してこなかったのは、彼の中にある儀式へのこだわりと同種の何かだった。
誰かに気づいて欲しいという、虚しい叫び。
ずっと一人ぼっちだったけど、あのダイニングの窓から見る月明かりだけは好きだったな。
望月リクは、日の暮れた雨雲を見上げた。
「あっめあめ、ふっれふれ、かあさんと~♪」
歌いながら跳ねるようにして、水たまりを避けていった。門をくぐってからは鼻歌に変える。人気のない母屋を横目に、リクは胸のすくような解放感を覚えた。
ああ、どのくらいぶりだろう。こんなに楽しい気持ちなのは。もうすぐ、全てが終わる。何もなくなるんだ。
ようやく俺は、暗闇の中を一人で眠る事が出来る。
もう誰も、俺の中には入ってこない。
くだらない何かを求めないで済む。
離れの扉を開けてダイニングを通り過ぎようとすると、そこには半井ゼンジが佇んでいた。
0
あなたにおすすめの小説
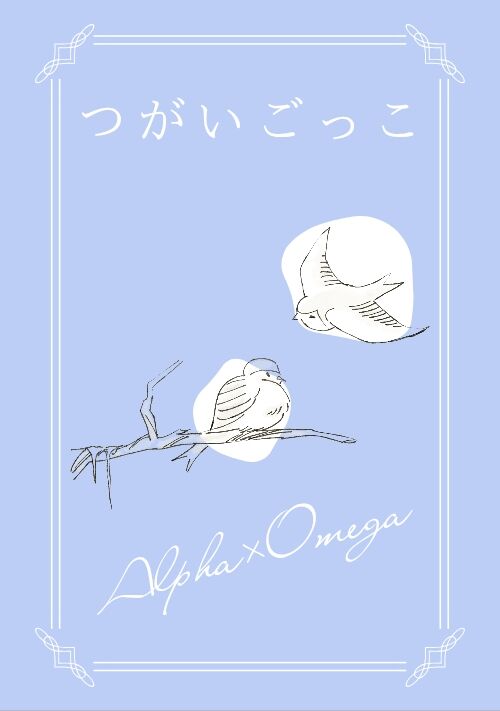
つがいごっこ~4歳のときに番ったらしいアルファと30歳で再会しまして~
深山恐竜
BL
俺は4歳のときにうなじを噛まれて番を得た。
子どもがたくさんいる遊び場で、気が付いたらそうなっていたとか。
相手は誰かわからない。
うなじに残る小さな歯型と、顔も知らない番。
しかし、そのおかげで、番がいないオメガに制限をかけられる社会で俺は自由に生きていた。
そんなある日、俺は番と再会する。
彼には俺の首筋を噛んだという記憶がなかった。
そのせいで、自由を謳歌していた俺とは反対に、彼は苦しんできたらしい。
彼はオメガのフェロモンも感じられず、しかし親にオメガと番うように強制されたことで、すっかりオメガを怖がるようになっていた。
「でも、あなただけは平気なんです。なんででしょう」
首を傾げる彼に、俺は提案する。
「なぁ、俺と番ごっこをしないか?」
偽物の番となった本物の番が繰り広げるラブストーリー。

番を拒み続けるΩと、執着を隠しきれないαが同じ学園で再会したら逃げ場がなくなった話 ――優等生αの過保護な束縛は恋か支配か
雪兎
BL
第二性が存在する世界。
Ωであることを隠し、平穏な学園生活を送ろうと決めていた転校生・湊。
しかし入学初日、彼の前に現れたのは――
幼い頃に「番になろう」と言ってきた幼馴染のα・蓮だった。
成績優秀、容姿端麗、生徒から絶大な信頼を集める完璧なα。
だが湊だけが知っている。
彼が異常なほど執着深いことを。
「大丈夫、全部管理してあげる」
「君が困らないようにしてるだけだよ」
座席、時間割、交友関係、体調管理。
いつの間にか整えられていく環境。
逃げ場のない距離。
番を拒みたいΩと、手放す気のないα。
これは保護か、それとも束縛か。
閉じた学園の中で、二人の関係は静かに歪み始める――。

伝説のS級おじさん、俺の「匂い」がないと発狂して国を滅ぼすらしいい
マンスーン
BL
ギルドの事務職員・三上薫は、ある日、ギルドロビーで発作を起こしかけていた英雄ガルド・ベルンシュタインから抱きしめられ、首筋を猛烈に吸引。「見つけた……俺の酸素……!」と叫び、離れなくなってしまう。
最強おじさん(変態)×ギルドの事務職員(平凡)
世界観が現代日本、異世界ごちゃ混ぜ設定になっております。


冤罪で堕とされた最強騎士、狂信的な男たちに包囲される
マンスーン
BL
王国最強の聖騎士団長から一転、冤罪で生存率0%の懲罰部隊へと叩き落とされたレオン。
泥にまみれてもなお気高く、圧倒的な強さを振るう彼に、狂った執着を抱く男たちが集結する。

処刑エンドの悪役公爵、隠居したいのに溺愛されてます
ひなた翠
BL
目が覚めたら、やり込んだBLゲームの悪役公爵になっていた。
しかも手には鞭。目の前には涙を浮かべた美少年。
——このままじゃ、王太子に処刑される。
前世は冴えない社畜サラリーマン。今世は冷徹な美貌を持つ高位貴族のアルファ。
中身と外見の落差に戸惑う暇もなく、エリオットは処刑回避のための「隠居計画」を立てる。
囚われのオメガ・レオンを王太子カイルに引き渡し、爵位も領地も全部手放して、ひっそり消える——はずだった。
ところが動くほど状況は悪化していく。
レオンを自由にしようとすれば「傍にいたい」と縋りつかれ、
カイルに会えば「お前の匂いは甘い」と迫られ、
隠居を申し出れば「逃げるな」と退路を塞がれる。
しかもなぜか、子供の頃から飲んでいた「ビタミン剤」を忘れるたび、身体がおかしくなる。
周囲のアルファたちの視線が絡みつき、カイルの目の色が変わり——
自分でも知らなかった秘密が暴かれたとき、逃げ場はもう、どこにもなかった。
誰にも愛されなかった男が、異世界で「本当の自分」を知り、運命の番と出会う——
ギャップ萌え×じれったさ×匂いフェチ全開の、オメガバース転生BL。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる
結衣可
BL
戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。
冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。
憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。
誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。
鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

だって、君は210日のポラリス
大庭和香
BL
モテ属性過多男 × モブ要素しかない俺
モテ属性過多の理央は、地味で凡庸な俺を平然と「恋人」と呼ぶ。大学の履修登録も丸かぶりで、いつも一緒。
一方、平凡な小市民の俺は、旅行先で両親が事故死したという連絡を受け、
突然人生の岐路に立たされた。
――立春から210日、夏休みの終わる頃。
それでも理央は、変わらず俺のそばにいてくれて――
📌別サイトで読み切りの形で投稿した作品を、連載形式に切り替えて投稿しています。
エピローグまで公開いたしました。14,000字程度になりました。読み切りの形のときより短くなりました……1000文字ぐらい書き足したのになぁ。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















