1 / 4
1 生きてる光と死んでるひかる
しおりを挟む
六車線の大きな幹線道路は、今日もかなり混んでいた。
光は、道をまたぐ歩道橋のまんなかにしゃがみこんで、らんかんのすきまから、下を通る車をぼんやりながめていた。
古い歩道橋は、下を大型車が通るたびにずんずん揺れる。ダンプなんかが通ったら、まるで地震みたいだ。
――あんなでっかい車に轢かれたら、ぼくなんて、きっとぺちゃんこだろうな。
つぶれたカエルみたいに、アスファルトの路面にへばりつく自分を、想像してみる。
「……きもちわりい」
轢かれたら、痛いかな。痛いだろうな。でも、きっと一瞬だ。わあッって思ったら、もうぺっちゃんこのぐっちゃぐちゃだ。
首吊りや飛び降りと、どっちが痛いだろう。
でもぼく、三階以上の高いところにのぼると、怖くて目もあけていられないし……。
本当のことを言えば、この歩道橋を渡るのだって、怖いのだ。渡っているあいだは、いつも足の裏がむずむずする。
それなのに光は、もう三〇分近くも、歩道橋のまんなかにしゃがみこんでいた。
半透明のプラスチック板でできたらんかんは、ちょうど光の目の高さだ。
だが下のほうには隙間があいていて、しゃがめばそこから下の道路が見える。
ランドセルがわりのリュックをかかえ、ずっと歩道橋でしゃがみこんでいる光を、通りがかった人たちは、みんな、不思議そうな、どこか気味悪そうな顔でながめていた。
けれど、誰ひとりとして、光に声をかけようとはしなかった。
月曜日の午後一時半。
ふつうなら、小学生がこんなところにひとりきりでいるはずはないのに。
光は、小学六年の男子としては、ごくふつうの背丈だ。
同じクラスの男子には、体格が良くて、しょっちゅう中学生や高校生にまちがわれているヤツもいる。女子だって、毎日ばっちりメイクしてきて、とても小学生に見えない子が多い。
けれど光は、服装もトレーナーにハーフのカーゴパンツと、ありきたり。どこから見ても、ただの小学生だ。
なのに通りかかる大人たちは、そんな光が、ふつうなら学校にいるはずの時間に、たったひとり、歩道橋の上にしゃがみこんでいても、ふしぎともなんとも思わないらしい。
いや、光の様子がなにかおかしいと思っているから、そんなヘンな子供にはかかわりたくないと、足早に光のそばから逃げていくのだろう。
――だいじょうぶ。ほら、誰もぼくを止めやしない。
ぼくが死んだって、誰もなんとも思わない。
いいや、ぼくが死ねば、きっとみんなうまくいくんだ。
のろのろと、光は立ち上がった。
リュックを足元に置き、錆びて、塗装のはげたらんかんに、手をかける。
らんかんは高いけれど、あちこちに大きなビスや金具の出っぱりがあって、うまく足をかければ乗り越えられそうだ。
ふるえる爪先を、金具のかどに乗せる。
――遺書……、どうしようかな。やっぱり、書こうかな。
遺書がなかったら、光の死は自殺としてあつかわれないかもしれない。
でも、そのほうがいいかもしれないと、光は思った。
一人息子が自殺したと知るより、ぐうぜん事故で死んでしまったと思っているほうが、お母さんはまだ気がらくなんじゃないだろうか。
お母さん。お母さん、寂しがるかな。ぼくがいなくなったら。
――だめだ。だめだ、よけいなこと考えちゃ。
ぐずぐずしてたら、どんどん踏ん切りがつかなくなる。
勇気があるうちに、飛び降りるんだ。
そうすれば、みんな、終わる。
全部、らくになれるんだから……!
「ねえあんた、死にたいの?」
突然、高い声がした。
「自殺するの? じゃあそのからだ、いらないんだ? だったらあたしにちょうだいよ」
「――え?」
光はふりかえった。
冷たく、鉄みたいなにおいのする風が、一気に光の全身をおしつつむ。
ぞうッと、足の先から頭のてっぺんまで、からだ中の皮膚が鳥肌立った。髪の毛まで全部、逆立つ。
「あんた、そのからだ、いらないんでしょ? だったらあたしがもらっても、いいよね?」
そこには、全身を真っ赤に染めて、右肩から腰、右足までをぐちゃぐちゃにつぶされた、若い女の幽霊が立っていた。
長い黒髪の下、奇妙なくらいきれいな左半分の顔で、幽霊がにィッと笑う。
光に向かって、右手をさしのべて。その手は、手首から先が奇妙な角度に折れ曲がり、おもちゃみたいにぶらぶら揺れていた。
「ね、ちょうだい?」
光は返事ができなかった。
そのまま、白目をむいて気絶した。
気がついた時、光は見慣れた自分の部屋にいた。
一年生の時から使っている学習机にベッド、本棚に乱雑につっこんであるコミックス。
まちがいなく、自分の部屋だ。
「あれえ……。ぼく、いつの間に帰ってきたんだろ」
さっきまで、歩道橋の上にいたはずなのに。
光はベッドの上に起き上がった。
服もちゃんと着ているし、リュックも机の横に置いてある。おかしなところはなにひとつない。
「へ……へんだな。なんか、へんな夢でも見てたのかな、ぼく」
怖い夢だった。全然知らない女の人の幽霊が出てきて、その幽霊がまた、妙にリアルで――。
「夢じゃないわよ」
いきなり、天井のあたりから声が降ってきた。
「うわああっ!?」
思わず見上げた先には、あの女の幽霊が浮かんでいた。
血に染まり、ぐちゃぐちゃにつぶれた右半身もそのままだ。
その身体の向こうには、天井の様子が透けて見えている。
「うっ、うわ、うわっ、うわわわ……っ」
幽霊を指さしたまま、光はまともな言葉も出せなかった。
「なによ、失礼ね。あたしは化け物か。――て、ああ、このカッコじゃ、たしかにおバケだわね」
幽霊は、ささっと両手で自分の顔をなでた。
すると、あまりにも無惨だった右半分の傷がきれいになくなり、服にしみついた血の汚れも一瞬で消えてしまった。
サックスブルーのおしゃれなブラウスに黒のパンツルックがかっこいい。
そして両手を離すと、左半分と同じく、若くてうつくしい女性の顔がぱっとあらわれた。
黒いロングヘアにほっそりとした顔立ち。髪と同じ色の瞳と、きれいにルージュでいろどられた唇。
……きれいなおねえさん。
光は思わず、その顔に見とれてしまった。
とはいうものの、その顔はやっぱり半分透けて、うしろの天井が見えていたのだが。
「だ、誰?」
「なによ、覚えてないの? あたしがあんたをここまで連れてきてやったんじゃない」
「連れてきたって……」
幽霊はふわふわと宙に浮かんだまま、かっこう良く足を組んだ。まるで見えない椅子に座っているみたいに。
「ぶっ倒れて動かないあんたのからだを、あたしがかわりに動かして、ここまで歩かせてきたの。家までの道順は、ちゃんとからだが覚えてるものだからね」
「ぼくのからだを動かしたって……お、おねぇ――おばさんが!?」
「だーれがオバサンだっ! あたしはまだ二十五だ!」
「二十五才……。やっぱ、おばさんじゃん」
「だまれ、このガキ!」
幽霊は光の真上で思いきり足を蹴りあげた。
だがその爪先は、すかっと空振りしてしまう。
彼女の足は、光の頭をすーっとすり抜けてしまったのだ。
「ち! やっぱダメか」
幽霊は悔しそうに舌打ちをした。
「や、やっぱって……、もし当たってたら、どうするつもりだったんだよ!? そんな、とんがった靴はいて、あぶないじゃんか!」
「うっさいな。あんたが避ければいいだけの話でしょ」
「よけらんないよ。いきなり蹴られたりしたら――」
「マジ? やっだ、どんくさぁ!」
幽霊は宙に浮いたまま、けらけら笑った。
「な……なんだよ! なだよ、そんなに笑うことないだろ!」
光はどなった。
だんだん腹が立ってくる。
だいたいこいつ、本当に幽霊なんだろうか?
いや、普通の人間じゃないことだけは、わかる。
浮いてるし、半分透けてるし、オカルトやホラーの関係者なことだけはたしかだろう。
でも。
「あ、あんた、誰? なんでぼくに声をかけたの」
「言ったじゃない。あんた、自殺するつもりなんでしょ? そのからだ、捨てるつもりだったら、あたしがもらおうと思ったの。ごらんのとおり、あたしはもう死んじゃって、自分のからだがないもんだからさ」
――やっぱり、マジで幽霊なんだ。
光のからだをのっとって、生き返ろうというつもりなんだろうか。
光は、頭のうしろあたりがすうっと冷たくなるのを感じた。
けれど、今度はどうにか気絶せずにがまんする。
今、見えているのが、最初に見た血まみれのぐっちゃぐちゃな姿ではなくて、きれいでかっこいい女の人だから、がまんできたのかもしれない。
本当に、きれいな人だ。
テレビなどで見る女優か、雑誌のモデルみたいだ。
こんなに若くてきれいな人が、もう死んでいるなんて。
「交通事故だったのよ」
まるで光の頭の中を読みとったみたいに、幽霊は言った。
「先週の日曜日、自分で車を運転して、さっきの道を通ったの。そしたら、わき見運転の車にぶつけられちゃって。ちょうどあの歩道橋の真下あたりでね」
「ふうん、そっか……」
車の事故なら、あの血だらけの姿も当然だ。
でも、やっぱり。
「ぼくには、関係ないじゃんか。化けて出るなら……その、車ぶつけた相手んとこに出てよ」
「無理よ。そいつも事故で死んじゃったもん」
けろりとして、幽霊は言った。
「ね。あんた、名前は?」
「い、井上 光……」
つい、光は答えてしまった。
「ヒカル? ヒカルくん? ぐうぜんね、あたしもひかるっていうのよ!」
「……だから、いやなんだ」
幽霊に聞こえないよう、光はこっそりつぶやいた。
「え? なんか言った?」
「だから――きらいなんだよ、この名前! 光なんて、女みたいじゃないか!」
言ってから、光はしまった、と思った。
こういうことを言うと、大人は必ず、
「そんなことを言ってはいけません」
「お父さんとお母さんがいっしょうけんめい考えてくれた名前です、もっと大切にしなくちゃ」
と、叱るのだ。
だが幽霊――ひかるは、にやにや笑って、こう言ったのだ。
「そんなにいやなら、別の名前にすれば?」
「えっ!? できるわけないじゃん、そんなこと」
「かんたんよぉ。別の名前を使う仕事につきゃあいいのよ。わかりやすいのは、マンガ家とか小説家とか、ものを書く仕事ね。たいがい、ペンネームってのを使うじゃない。その仕事で一流になれば、誰もあんたを本名で呼んだりしないわよ。ペンネームが、あんたにとって一番重要な名前になるんだもの」
「ペンネーム……」
「ま、戸籍上の名前は、よっぽどの理由がないかぎり、変えられないけどね。……て、関係ないか。あんた、どうせ死ぬんだもんね」
ひかるは身を乗り出すように、ふうっと光の目の前まで近づいてきた。なんだか、とてもわくわくしてるみたいな表情だ。
「でもさ、同じ死ぬんでも、飛び降りや交通事故はやめなさいよ。アレは痛いわよぉ。からだもつぶれてめちゃくちゃになっちゃうし。経験者が言うんだから、まちがいない!」
「う……」
たしかに、その言葉には説得力があった。あの血まみれのひかるの姿を見ているだけに、なおさらだ。
「それよりも、もっとらくな方法があるよ。あたしとあんたが、入れ替わるの」
「いれかわる!?」
「そう。あたしがあんたのからだに入って、あんたは今のあたしみたいに、魂だけの存在、つまり幽霊になるわけ。幽霊になるんだから、死んだも同じ、自殺したいっていうあんたの希望もかなえられるんじゃない?」
「そ、そりゃ、そうかもしれないけど……。でも、どうやって?」
ひかるはちょっと考えこんだ。どう説明すればいいのか、困っているらしい。
「とにかく、やってみればわかるわよ。さっきはうまくいったんだから」
「さっき?」
「言ったじゃない。気絶してひっくりかえったあんたのからだを、あたしが動かして、ここまで連れてきたって。つまり気絶したあんたのからだの中にあたしが入って、あたしの意志どおりに、そのからだを動かしたのよ」
「そんな! 人のからだ、勝手に使わないでよ」
「じゃあなあに、あのまま何時間も、歩道橋のまんなかにひっくり返っていたかったっての!? ひとがせっかく親切にしてあげたってのに!!」
かんしゃくを起こしたみたいに、ひかるは大声をはりあげた。
そしていきなり、両手を光へ向かって突き出す。
「あーもう、ごちゃごちゃうるさいっ! あんたはとにかく、じっとしてりゃいいのよ!」
ひかるの手が、まっすぐ光の目の前に突き出された。指先をそろえ、まるで光の両眼をえぐろうとするみたいに。いや、水泳の飛び込みみたいに。
「うわっ!?」
光は思わず、ぎゅっと目をつぶってしまった。
その瞬間、異様な感覚が光をおそった。
からだを内側からねじられるような、ひっくり返されて全部裏返しになるような。からだ中の毛という毛が、全部上に向かってひっぱられているみたいだ。
痛くて苦しくて、ぐらぐらめまいがして。脱水中の洗濯物が、きっとこんな気持ちだろう。
そして、ぱっと目をあけた時。
目の前には、光自身がいた。
ベッドに座り、にやっと笑って宙を見上げている。
「えっ!? ぼ、ぼく!?」
まちがいない。そこにいるのはたしかに光だった。
――じゃあ、ここにいるのは!?
光はあわてて自分のからだを見回した。
目の前にかざした両手は、半分透けて、向こう側に部屋の光景が見えていた。……さっきのひかるとまったく同じく。
「どう? 幽霊になった気分は」
光が――いや、ひかるが言った。
ひかるの説明したとおり、光の意識は自分のからだから追い出されてしまったらしい。今、光のからだに入っているのは、ひかるの意識なのだろう。
目の前にあるのは、光の顔、光のからだ、着ている服だって、なにひとつ変わっていない。
でも。
……ぼく、こんな顔、してたっけ?
どうだ、見たかというような表情をして、にやっと自信ありげに笑うその顔は、鏡や写真で見るいつもの自分とは、まったく違う。まるで別の人間みたいだ。
表情だけで、こんなにも違って見えるなんて。
「ね、かんたんでしょ」
光が、いや、光のからだに入ったひかるが、言った。
その声もたしかに光のものだったが、しゃべり方は全然違う。
ひかるはとてもうれしそうだった。
両手をなでたり、大きくのびをしたり、座ったまま足をばたばたさせてみたり、からだの動きを確かめているようだ。
「そういやあたし、昔から一度、男の子になってみたかったんだあ。そうだ、せっかくだから、どっか遊びに行こうかな! あんた、いつもどこで、なにして遊んでんの?」
ひかるはベッドから立ち上がった。
「あ、でも、このカッコ、だっさいなあ! もうちょっとマシな服、ないの?」
そして、壁につくりつけになっている洋服たんすを開け、光の服をかたっぱしから引っぱり出す。
「ち、ちょっと……! ひとのからだで、勝手なことしないでよ!」
あわてる光を、ひかるはにやっと勝ち誇ったような笑いを浮かべて見上げた。
「あんたは幽霊なんだから、これはもう、あたしのからだよ。――あ、と、あたし、じゃないか。オレ、かな? オレ」
ひかるはでかけることはやめたようだが、今度は本棚に並んだマンガをいろいろ物色し始めた。散らかした服も片づけないままだ。
「あんたは望んだとおり幽霊になったんだから、もうここにとどまってる必要もないし。好きなとこに行っちゃっていいのよ」
「行くって、どこへ……」
「天国とか地獄とか、いろいろあるじゃん。ま、あたしもまだ行ったことないから、良くわかんないけどさ」
「い、いやだよ! 地獄なんて、行きたくない!」
「なによ。あんた、死にたかったんでしょ? 願いがかなったんだから、文句ないでしょ!」
「いやだいやだいやだ! ぼくのからだ、返せよ!!」
光は大声でわめいた。
からだがあったら、手足をふりまわしてめちゃくちゃにあばれるところだ。
「人のからだ、勝手に使うな! 返せよ!!」
空中に浮かんだ光は、そこからひかるに思いきりぶつかっていった。
――あ、ぼく、今は幽霊だから、蹴ったり撲ったり、できないんだっけ!?
でも、勢いがついて、もう止まらない。
そのまま光の姿は、ひかるに重なった。
その瞬間、また、からだ中がしぼられるみたいな、あの感じが光を襲った。
「う、うわっ! うわあっ!?」
おなかの奥から一気に吐き気がこみあげてくる。
それを、どうにか押し殺そうとした時。
「あ……!」
光のからだは、もとどおりになっていた。
両手をさする。それからほほ、あご、髪の毛もひっぱってみる。ちょっと痛い。
ちゃんとからだがある。
「良かったあ……」
光は大きくため息をついた。
「あーあ、やっぱりだめか」
ふたたび半透明の幽霊になったひかるも、がっかりしたようにため息をついた。
「もともとのからだの持ち主であるあんたが、そうやってからだから離れたくないってがんばってると、あたしもからだの中に入れないのよね。さっきみたいに、あんたが気絶してるとか寝てるとかしてないと、すぐに追い出されちゃうの」
ひかるはまた、空中にこしかけるように、かっこよく足を組んだ。
「実は、あんたのほかにも二、三人、ためしてみたんだけど、全然だめだったの。からだの中に入るどころか、家の中までくっついてくこともできなくて。その人の後ろから玄関入ろうとしたら、ドアを通り抜けられなかったの。閉じたドアにどかん!て、顔からぶつかっちゃってさ、まるでテレビのコントみたいだった」
あはは、と、ひかるは気楽そうに笑った。
「じゃあ、なんでぼくだけ……」
「やっぱ、アレじゃない? あんたが死にたがってたから」
にやりとしたその表情は、やっぱりかっこいいや、と光は思った。
「ねえ。あんた、なんで死にたいの?」
光はうつむいた。
黙り込み、答えない。ひかるを見ようともしない。
「ま、言いたくなきゃ、言わなくてもいいけどね」
ひかるも、たいして興味もなさそうに言った。
さーて、どうしよっかなあなんて一人言をつぶやきながら、ひかるはそこにふわふわ浮いたままだった。
「な……、なに、してんの?」
「ああ、気にしなくていいよ。無視してくれてかまわないから」
「無視できるわけないだろ! あんた、ぼくにとりつくのはあきらめたんだろ!? だったら、さっさと別の人を探しに行けよ。なんで、いつまでもぼくの部屋にいるのさ!?」
「あんたがもう一度死にたくなるのを、待ってんの」
ひかるは、平然と言った。
「え……!?」
「だってあんた、理想的なんだもの。友達も少ないみたいだし、いっしょに暮らしてる家族はお母さん一人きりでしょ?」
「ど、どうしてそんなこと、知ってんだよ!?」
「キッチンの食器。二人分しかないじゃない。それに男物の服や靴も見あたらないし。あんた、お父さんとは別々にくらしてんでしょ。兄弟もいないみたいね」
「う、うん……。そうだよ」
光のお父さんとお母さんは、三年前に離婚していた。
光はお母さんといっしょに暮らし、お父さんとはもう二年以上会っていない。ちらっと聞いた話では、お父さんはもう別の女の人と再婚したらしい。
「家族や友達が多いと、入れ替わったあと、その人たちみんなをだましてなきゃいけないじゃない? だます相手は少ないほうがらくだもん」
だませるわけないじゃんか、と、光は言おうとした。
学校のクラスメイトや先生ならともかく、お母さんが、光が別人と入れ替わったことに気づかないはずがない、と。
……でも、言えなかった。
本当に、そうだろうか?
もしも本当に光とひかるが入れ替わったとしても、お母さんはそれに気がついてくれるだろうか?
はっきり、そうだと言い切れる、自信がなかった。
――たとえば、お母さんが誰か別の人に入れ替わってて、ぼくのお母さんのふりしてるだけだとしたら……ぼくに、それがわかるだろうか?
そこまで、ぼくはお母さんのこと、よく知ってただろうか。
お母さんとちゃんと話をしてたかな。
お母さんはいつも仕事で忙しいし、帰りが遅いこともしょっちゅうだ。
光も、学校であったことやその日一日のこと、自分からお母さんに話すことなんかめったにない。お母さんにしつこく質問されて、うん、とか、そうだよ、とか、いい加減に返事をするだけだ。
だって小六にもなって、男が、お母さんと仲良くおしゃべりするなんて。
女の子ならともかく、そんなのなんだかはずかしくって、できやしない。
お母さんのほうも、光のそんな気まずい思いに気がついているのか、なんとなく話しかけにくそうにしている。
二人で話す時間は、ますます減る一方だ。
これじゃ、おたがい、相手が別人と入れ替わってたとしても、まったく気づかないんじゃないだろうか。
「それに、自殺志望の人間をもういっぺん探して回るの、めんどくさいし。そいつが借金まみれのおっさんとか、汚職がばれて警察につかまる寸前の役人とかだったら、もう目もあてらんないじゃん。あたしだってそりゃ、もういっぺん死ぬしかないわよ。でもあんたなら、まだ夢も希望もある小学生だもんね!」
――夢や希望があったら、誰が自殺なんかするもんか。
うつむき、光は両手をぎゅっとにぎりしめた。
「自殺ってね、たいがい一回じゃ成功しないもんなのよ」
ひかるが言った。
「あんたも必ず、もう一回やろうとするはずよ。あたしはそれを待つことにする。それがいちばん、効率がいいもん」
「ま、まさか、ぼくがもう一回、どっかから飛びおりようとするまで、ずっとそうやって、くっついて回るつもり!?」
「そうよ」
けろっとして、ひかるは言った。
「安心しなさい。あたしの姿は、あんた以外の人間には見えないはずだから。て言うか、あたしが見えた人間、今まで一人もいなかったもん。あんたが幽霊にとりつかれてるなんて、誰にもわかりゃしないわ」
それに第一、と、けらけら笑う。
「あんた、もう半分死んでるみたいな顔してるじゃん。幽霊にとりつかれようがなんだろうが、今さらたいして変わりゃしないって!」
ひかるは窓を指さした。
外はかなり暗くなり、窓ガラスは鏡のように部屋の中の様子を映している。
そこに、ひかるは映っていなかった。
映っているのは、光の姿だけだった。
「ぼく……」
窓ガラスに映る自分の姿に、光は目を向けた。
その顔は、表情も乏しく生気がなく、口元は力なく半開き、目はどんよりとして、たしかに半分死んでいるみたいな顔だった。
「光、光! いつまで寝てるの、起きなさい!」
お母さんに揺り起こされて、光はのろのろと目を開けた。
「んー……。もう朝なの……? まだ眠いよ――」
半分ねぼけたまま、光は大きくあくびをした。それでもなかなかまぶたが開かない。
「あたりまえでしょ。ゆうべ、あんなに夜更かししたんだから。またマンガばっかり読んでたんでしょ」
「え?」
そんなことないよ、と、光は言おうとした。
だってゆうべは、起きているのもいやになって、さっさと布団をかぶって寝てしまったのだ。
起きていると、そのあいだずっと、光が自殺したくなるのを待っているひかるを、そのわくわくしている顔を、見ていなければならないから。
「こんなに出しっぱなしにして。学校から帰ってきたら、ちゃんと片づけなさいよ」
お母さんは、ベッドの枕元や床の上に散らばったマンガのコミックスを、ぱたぱたとてきとうに積み重ねた。
「今はこのままでいいわ。片づけてたら、学校に遅れちゃうもの。そのかわり、晩ご飯までにきちんと片づけておかなかったら、このマンガ、全部捨てちゃうからね。ゲーム機も、テレビにつなぎっぱなしにしてたらいけないって、いつも言ってるじゃない!」
――そんなばかな!
ゆうべ、マンガなんか読んでいたおぼえはない。まして、ゲームなんて。
そう考え、光はようやく気がついた。
天井のほうを、ぱっと見上げる。
やはりそこには、きれいなロングヘアのひかるが、半透明の姿でふわふわ浮いていた。
「や。おはよ」
にっこり笑いながら、その顔はどこか眠たそうだ。
――ひかるっ!
どなろうとして、光はあわてて口をおさえた。
ちょっと不思議そうな顔をして、お母さんが光を見ている。
お母さんは、ひかるの存在にまったく気がついてない。
「お、お母さん! もう出てってよ! ぼく、着替えるから!」
「光?」
「ほら、早く! 急がないとほんとに遅刻しちゃうってば!」
光は、お母さんの背中を押すようにして、むりやり部屋の外へ追い出した。
ドアをしっかりと閉め、それから部屋の中へ向き直る。
「――ひかる!」
「なによ。目上の人間を呼び捨て!?」
「ひかるは人間じゃないだろ、幽霊じゃんか!」
いや、そんなことはどうでもいい。
「ゆうべ、ぼくのからだを勝手に使ったろ!?」
ひかるは、にらみつける光と目を合わせないよう、しらじらしく視線をそらした。
「ぼくが寝てるあいだ、ぼくのからだに入って、ゲームしたりマンガ読んだり、一晩中遊んでたんだろ!?」
「だってさあ、おもしろそうだったんだもん、そのマンガ」
今度は完全に開き直り、ひかるは言った。
「あんたが持ってるゲームも、あたし、やったことないやつばっかだったし。ねえ、そのゲームのさ、3面がどうしてもクリアできないのよ。あとでやり方、教えて?」
「か、勝手なことばっか、言うなよッ!!」
光は思わず大声を出した。
すると、
「光、どうしたの?」
びっくりしたようなお母さんの声が聞こえてくる。
「ばかねえ。あたしの声はあんたのお母さんには聞こえないけど、あんたの声はふつうに回りに聞こえてるのよ」
光はあわてて、両手で口をふさいだ。
これじゃ、家の中ではひかると言い争いをすることもできない。
「と、とにかく、ぼく、もう学校行くから。ぼくが帰ってくるまでに、この家から出てってよ!」
「無理よ。あたし、ずーっとあんたにとりついてるって、決めちゃったもん」
「そんな……っ!」
「あ、さすがにトイレやお風呂はのぞかないから。そのくらいのプライバシーは守ってあげる。着替えの時もね」
ほら、早く着替えなさい、と、ひかるはぱっと後ろを向いた。
しかたなく、光はもそもそと着替え始めた。
「終わった? ほんと、あんたってとろくさいのねえ」
「ねえ。もしかして、学校までついてくるつもり?」
「当然じゃない」
にっこり笑って、ひかるはうなずいた。
「あんたのことは、なんでも知っておかなくちゃね。入れかわった時に、よけいな失敗しなくてすむようにさ」
光は黙りこんだ。
もう、なにを言ってもむだみたいだ。光がなにを言ったって、ひかるは光のそばを離れないだろう。
――いいさ。勝手にしろよ。
胸の中で、光はやけっぱちにつぶやいた。
学校でもどこでも、ついてくればいい。そして、全部見ればいいんだ。
ぼくがいつも、クラスでどんな思いをしているか。
それがわかれば、ひかるだって絶対に、光と入れかわろうなんて思わなくなるに決まってる。
――そうさ! わけもなく自殺したいなんて、思うもんか!!
光は、机の横にほうりだしてあったリュックを手に取った。
時間割をたしかめ、必要な教科書やノートをリュックにつめこむ。
「あら。どうしたのよ。急に静かになっちゃって」
「だって、ぼくの声はふつうに聞こえるんだろ。ひかるの声は誰にも聞こえないのに、ぼくがひかるに話しかけてたら、ぼくはブツブツ一人言ばっか言ってる、キモいヤツになっちゃうじゃん」
「そりゃまあ、そうだけど。でも、あたしとあんたしかいない時だったら――」
「とにかく。ぼくは、学校じゃひかるを無視するからね。そうしろって言ったのは、ひかるなんだから」
ふうん、と、ひかるはつまらなさそうに光を見下ろした。
光はもう、返事もしなかった。
さっさとしたくをして、部屋を出る。
キッチンには、朝ご飯の用意ができていた。
「いただきます」
ぼそぼそとつぶやいて、光はトーストにかじりついた。
食欲なんて全然ないけれど、機械的に食べ物を口に入れ、飲み込む。
そのあいだにお母さんも、会社に出勤する用意をしている。スーツに着替え、きれいにお化粧をする。
玄関を出るのは、たいがい二人いっしょだ。
光の家は、賃貸マンションの一室だ。2LDK、けして広くはないけれど、二人で住むには充分だ。
いや、お母さんのお給料では、これ以上広い部屋に住むのは無理だ。
「気をつけていってらっしゃい。お母さんも、今日はできるだけ早く帰ってくるから」
「うん、わかってる」
「忘れ物はない? 家の鍵、ちゃんと持った?」
お母さんの言うことは、いつも同じだ。
「この前みたいに、学校で鍵を失くしたりしないでね。合い鍵つくるのだって、お金かかるんだから」
――違うよ、お母さん……と、言いかけて、光はぎゅっと唇をかんだ。
本当のことをお母さんに言って、どうなるだろう。
どうにもならない。ただ、お母さんを哀しませるだけだ。
「うん。わかってる」
光はいつもと同じく、ただそれだけを答えた。
「携帯もちゃんと持ってるわね? ああ、もうバスに遅れちゃう。じゃあね、光。車に気をつけるのよ」
お母さんは腕時計を見ながら、マンションの階段をあわてて駆け下りていった。
「ぼくも……行かなくちゃ」
一言つぶやいて、光も歩き出した。まるで足を引きずるように。
「ちょっと、どうかしたの? あんた、学校行きたくないの?」
頭の上、ややななめうしろにふわふわ浮かんでいるひかるの声にも、なにも答えない。
うつむいて、だまって、歩き続ける。
「今日、テストでもあんの? あ、わかった。インフルエンザかなんかの予防接種でしょ。あんた、度胸なさそうだもんねえ」
――ついてくれば、わかるさ。
市立明京小学校、六年B組。
朝のホームルームが始まる前の教室は、動物園みたいな騒がしさだ。
とっくみあい、格闘技ごっこをしている生徒、対戦ゲームに夢中の生徒――学校にゲーム機を持ってきてはいけません、と、先生からしつこく言われているのだが――、スマホでゲームをしている生徒もいる。防犯のため、ケータイやスマートフォンを持ち歩くことは禁止されていないのだ。
女子の中には、鏡をのぞきこんでメイクを直している子もいる。
校則が何十年も前に作られた古いものなので、「学校にお化粧をしてきてはいけません」という一文がないのだ。校則ができた当時の小学生は、誰もメイクなんかしていなかっただろうから。
メイクをして登校する子は、最初は2、3人だった。
だが、いつのまにか
「あの子がメイクしてかわいくなってるのに、あたしがすっぴんじゃはずかしい」
と、クラス中に伝染して、今ではクラスの女子の半数以上がなんらかのメイクをしている。すっぴんの子は、親がアタマが古くて許してくれないと、文句ばかり言っている。
みんなが数人ずつのグループになって、好き勝手にしゃべっているため、教室全体がうわぁ…ん、といううなり声につつまれているみたいだ。
だが、
「……おはよう」
光が教室のドアを開けた瞬間、そのうなりが、ぴたりと止んだ。
教室全体が、凍りついたみたいに静かになる。
クラスメイトたちの視線が、一斉に光へそそがれた。
――こいつ、また来たよ。うぜぇー!
――うっそぉ、信じらんない。まだ生きてる。
声にならない声が、光のからだじゅうに突き刺さった。
――あーやだやだ。キモぉ! なんでこいつ、うちのクラスなわけ!?
――さっさと不登校になれよ、ばぁか!!
そしてみんなは、また一斉に光から目をそらした。
光がのろのろと自分の席へ向かっても、誰も光に声をかけようとしない。
光なんてまるで目に入らない、存在していないかのように、無視する。
だが本当は、見ていないわけではないのだ。
光と視線が合わないよう、顔を伏せながら、ちらちらと光の様子を盗み見ている。
光が今、どんな顔をしているのか、たしかめようとしているのだ。
光がどんなに傷ついているか、つらそうな顔をしているか、みんな、それが見たくてたまらないのだ。
くすくすくす……と、低い笑い声が聞こえる。とうとう我慢できなくなったらしい。
まるで動物園の珍獣みたいに観察されながら、光は自分の席にたどりついた。
が、座ることができない。
机にも椅子にも、ゴミが山積みされていた。
どうやら、ゴミ箱を光の机の上でひっくり返したらしい。
くすくす笑いがさらに大きくなる。
その笑いのほうへ光が目を向けても、もう相手も視線をそらしたりしない。
みんな、光の不幸を心底おもしろそうに笑っている。
実際、おもしろくてたまらないんだろう。
他人を傷つけ、相手の哀しい顔をながめることは、クラスの中でいちばんおもしろいゲームだ。
しかもその相手が絶対に反撃してこないとわかっている場合は。
光は顔をはっきりとあげることもできなかった。
笑っているヤツらを真正面からにらんだりしたら、今度は殴られる。
てめえ、なに見てんだよ、キモい、こっち見んな、と、五、六人、それもガタイのいい、腕力が自慢のヤツらばかりに取り囲まれ、さんざん殴られ、蹴られた。
反撃なんかできるわけがない。
そんなことが何度もあって、いい加減、からだでおぼえた。
光はリュックをまだ汚れていない床に置くと、だまって教室のすみへ向かった。
掃除用具入れからぞうきんとモップを持ってこようと思ったのだ。
だが、
「さわんじゃねえよ」
掃除用具が入ったスチールロッカーの前に、一人の男子生徒が立ちはだかった。
「てめえがさわったら、井上菌がつくだろうがよ! クラスの備品を汚染する気か、てめえ!」
クラスの中でもひときわ声が大きく、体格もいい、森本だ。
――そうか。あのゴミも、やっぱり森本がやらせたんだ。
きっと自分でゴミ箱にさわるなんてことはしなかっただろう。
いつもまわりにくっついている、金子や福田、水沢あたりの子分に命令して、やらせたはずだ。
「それって、ヘンだよ。森本くん」
言ってもどうにもならないとわかっていながら、つい、光は口を開いてしまった。
「この教室の掃除は、もう何日もずっと、ぼくひとりでやってるじゃないか。ぼく、先週もここのモップやバケツにさわって、教室を掃除したよ。先週の放課後はさわって良くて、どうして今朝はさわっちゃいけないんだよ」
「う……うるせえ、井上、てめええッ!!」
森本の顔が真っ赤になった。
光に反論されたことが、よっぽど我慢できなかったらしい。……しかも、どう考えたって、光の言っていることが正しいし。
それでも森本は、自分一人で光に手を出すなんてことは、絶対にしない。ここが森本の頭のいいところだ。
ぱっとうしろをふりかえり、そばにひかえている子分たちに、あごをしゃくって合図する。
「なんだよ、井上。そんなにゾーキンがほしいのかよ!」
「だったらてめえの服で拭けよ!」
「そうだそうだ、てめえの服なんか、どうせゾーキンといっしょじゃんか!!」
3人の男子が、いっせいに光に飛びかかった。
両脇から光の腕をつかまえ、光の席のそばまで引きずり戻す。
「い、痛いっ! 痛い、なにすんだよ、はなせよ!」
クラス中の生徒が、その光景を笑いながら見ていた。
「おら、拭けよ! さっさと拭いて、キレイにしろよ!!」
「なんだよ、いやがんじゃねえよ! 掃除すんの、手伝ってやってんじゃねえかよ!」
光は机の上に上半身を押さえつけられた。ゴミの山の上に。
「はーい、おそうじおそうじー!!」
金子だろうか、福田だろうか、浮かれて歌うように声をはりあげた。
左右から背中を押さえつけられ、光は汚れた机に押しつけられる。森本もそれに手を貸した。
彼らは光のからだでぞうきんがけを始めたのだ。
「おらおら、もっと力こめて拭けよ! ちっともきれいになってねえぞ!」
「井上、おめえ、これなめろよ! なめてキレイにしろよ!!」
教室中が笑い声に包まれた。
クラスメイトはみんな、いじめられている光を見て、とても楽しそうに笑っていた。
「やぁだぁ、きったねえー!」
「なんかぁ、ちょー笑えるんですけどー!」
「よく平気だよねー、あいつー!」
「そりゃそうだよぉ、だって井上だもーん。あははははーっ!!」
――平気じゃない。こんなことされて、平気な人間なんか、いるもんか。
光の苦しみは、誰にも届かない。
森本や子分たちも、本当に楽しそうだ。遠足や運動会よりも、ずっと、ずっと。
彼らにとって、光をいじめること以上に楽しいことなんか、ないのだろう。
やがて、ホームルーム開始を知らせるチャイムが鳴り響いた。
「どうしたの、みんな。早く席についてほしいなー」
クラス担任の相沢先生が教室に入ってくる。
相沢先生は、まだ独身の若い女の先生だ。
森本たちはようやく、光から手を離した。
「先生、おはよーございまーす!」
せいいっぱい明るく元気そうな声を出して、森本は先生ににっこり笑ってみせた。
子分たちもみんな、急いで自分の席に戻る。
光はのろのろとからだを起こした。
机にごりごり押しつけられて、からだ中があちこち痛い。服はどろどろに汚れてしまった。
それでも椅子にはまだ、ゴミが山積みされている。
その上に座るしかない。
「じゃあ、出席をとるからねー」
相沢先生は黒板の前に立ち、みんなに明るく声をかけた。
それから、あいうえお順で生徒ひとりひとりの名前を呼び上げる。
いつもどおりのホームルームの始まりだ。
井上光くん、と、光の名を呼んで、先生はようやく光の様子に気がついた。
「井上くん……。ど、どうしたの?」
「いいえ、なんでもありません」
なんでもないはずがない。
顔も服も汚れて、すり傷もいっぱいできている。机はゴミがなすりつけられて、真っ黒だ。
それでも光は、即座に「なんでもありません」と答えた。
「そう……」
相沢先生は、うつむいた。逃げるように、光から目をそらす。
教室のあちこちから、くすくす、くすっ、と、小さく笑い声が聞こえた。
みんな、お互いに突っつきあったり、こっそり光を指さしたりして、楽しそうに笑っている。
相沢先生は、半分こわごわと、光の席のそばまで近づいてきた。
「ね、ねえ、井上くん――」
消えそうな声で、光に話しかける。
けれど、光をちゃんと見ようとはしない。おどおどと目を伏せたままだ。
「本当に、先生に相談したいこと、なんにもないのね? よけいなことかもしれないけど、もしかしたら、なにか、先生にもできることがあるかもしれないし――」
光はなにも答えなかった。
相沢先生の言葉は、
「あなたのことで、先生にできることはなんにもないから、相談なんかしてこないでね」
という意味だ。
その証拠に、光がそのままなにも言わないでいると、相沢先生はあきらかにほっとしたようだった。
「じゃ、授業を始めよっか。みんな、教科書を出してくれるかなあ?」
そしてなにごともなかったように、一時間目の授業が始まった。
国語、算数、ただ時間だけがのろのろとすぎていく。
理科の授業では、実験のためにいくつかの班にわかれた。
が、仲のいい人どうしで班をつくっていいと相沢先生が言い出したため、光はどこの班にも入れなかった。
相沢先生も、光が一人、理科教室のすみに取り残されていることには気がついていたが、もうなにも言わなかった。
井上くんをどこかの班に入れてあげて、なんて言い出したら、クラスじゅうが大騒ぎになって、授業ができなくなるからだ。
6年B組38人全員が実験できなくなるより、光以外の37人が無事に実験をやりとげるほうが、ずっといい。
お昼、給食の時間になると、ふつうの生徒は
「今日のおかず、なんだったっけ? 自分の好きなやつだといいけど」
なんてことを、考える。
でも光の考えることは、
「今日は、ちゃんと給食食べられるかなあ」
だ。
給食にゴミを入れられる、給食のトレイをわざとひっくりかえされるなんて、しょっちゅうだ。
さいわい、給食センターから専用トラックで運ばれてくる給食は、クラスに配られるころにはわりあい冷めていて、頭からぶっかけられても、やけどすることはない。
「お、今日は酢豚かあ!」
大きななべをのぞきこみ、給食用のエプロンをかけた森本がうれしそうに言った。
「ほーら、井上くーん。サービスしてあげたぜえ?」
にやにや笑いながら、森本は給食トレイを光の目の前に突き出した。
お皿の上には、酢豚のにんじんとたまねぎだけがよりわけられ、山盛りになっていた。
ほかにはパンも牛乳もない。にんじんとたまねぎだけだ。
「おら、食えよ! 残すんじゃねえぞ!!」
「給食残すヤツは、昼休み居残りなー!」
どうしていいかわからない光のまわりを取り囲み、森本たちは大声ではやしたてた。
相沢先生は、自分の給食を食べ終えると、さっさと職員室へ逃げてしまっていた。
光が椅子から立ち上がろうとすると、
「てめえ、逃げんじゃねえよ!」
森本はどん!と、光の肩を乱暴にどつき、無理やり座らせる。
「違うよ……。スプーンもフォークもないし――」
「てめえに使わせるスプーンなんかねえよ! 手で食えよ、手で!!」
「おら、食えよ! 食えよ!!」
「くーえ、くーえ、くーえっ! くーえっ!!」
いつのまにか、クラスじゅうが手をたたき、声をそろえてはやしたてていた。
森本たちはますます興奮し、光の頭をつかんで、給食トレイに押しつけた。
酢豚のケチャップソースの中に、光の顔が押しつけられる。目の中にソースが入って、ものすごく痛い。
森本たちは、笑っていた。
クラス全員が、笑っていた。光がもがき苦しむ様子を見て、とても楽しそうに、うれしそうに。
みんな、今日も大満足のようだった。
「ふーん、なるほどね」
ぼそっとひかるがつぶやいた。
放課後、とぼとぼと家に帰る光の上に浮かんで、光の姿を見下ろしている。
光の服はどろどろに汚れ、まるでゴミ捨て場から這い出してきたみたいだ。スニーカーには黒の油性ペンでらくがきされていた。
「あんた、それで自殺しようとしてたんだ」
光はようやく、ひかるを見上げた。
まわりに人影はない。
今なら、ひかると話をしても大丈夫だ。
「わかったろ? ひかるだって、ぼくと入れかわったりしたら、すぐに自殺するしかないだろ?」
かすかに笑いながら、光は言った。
もう、笑うしかない。
「早く帰ろうよ。家ん中だったら、ひかるとゆっくり話ができるからさ」
それから光は、足早に自宅マンションへ戻った。
部屋に入るとまず、汚された服を着替えて、洗濯機へ放り込む。
「洗濯はぼくの仕事なんだ。学校から帰ると、まずこうして、洗濯機回すの。だから、お母さんには気づかれなくてすんでるんだよ」
だけど、と、光はため息をついた。
「あの靴は……どうしようかなあ。油性のペンで書かれちゃったから、洗っても落ちないなあ。しばらく隠しておくしかないか」
全自動洗濯機がうなりをあげて回り出す。
光は自分の部屋に入った。
ひかるもふわふわとついてくる。
部屋に入ると、光はすぐにベッドに横になった。
正直言って、からだじゅうがあちこち痛くて、椅子に座るのもつらいのだ。
ひかるは天井付近にふわふわ浮いて、ぽそっとつぶやいた。
「あんたのクラス担任もだらしないわねえ。あたしとそうかわんない年令だろうけどさ、でも、まがりなりにも教員試験パスしてんだから、もうちょっとまともな指導とか、できないのかな」
「しょうがないよ。相沢先生は、森本の親が怖いんだ」
「え?」
「ぼくだって、最初は先生に相談したんだよ。そしたら――」
相沢先生は、森本やその子分たちを職員室に呼び出し、話をした。
それはたぶん、お説教とか、そんなきついものではなかっただろう。相沢先生は、クラスのみんなに対して、いつも友達みたいな話し方をする。
きっと森本たちにも、
「先生、森本くんたちがほんとは優しい子だって、ちゃんとわかってるのよ。ただちょっと、ふざけちゃっただけよね? もう、やめてくれるよね?」
くらいのことしか言わなかったに違いない。
そうしたら、次の日、いきなり森本の母親が学校にどなりこんできたのだ。
「先生、うちの子がいじめをしてるってお叱りになったそうですね!? どこにそんな証拠があるんです! うちの子は絶対にいじめなんかしていないって、言ってます! タカヒロは、いじめなんかできるような子じゃありません、本当に心の優しい、いい子なんですよ!!」
森本の母親は校長室にまで押しかけて、廊下にまでひびきわたるほどの大声で、どなり続けた。
「うちの子にいじめられたって告げ口した子を、ここに呼んでください! 先生はどうせ、その子の言い分だけを聞いて、一方的にうちの子が悪いって決めつけたんでしょう! だから、その告げ口した子と、うちの子と、ここに二人並べて、どっちが本当のことを言ってるか、たしかめなくちゃ。もちろん、それぞれの親の立ち会いのもとで!!」
「い、いや、お母さん、もう少し穏便に……」
「なにをおっしゃるんですか、校長先生! うちの子が、うその証言で無実の罪を着せられそうなんですよ!!」
母親が抗議しているあいだ、森本は母親のうしろで、ずっと泣きまねをしていた。
「さあ、そのうそつきの生徒と、その親をここに呼んでください! さあ、早く!!」
相沢先生はこどもみたいに泣きながら、光を校長室へ連れていった。
「ぼくん家、お父さんがいなくて、お母さんが働いてるからさ。お母さんが学校に来るには、会社を休まなくちゃいけないんだ。ただでさえお母さん、仕事が忙しくて、熱があってふらふらしてる時でも、無理して会社に行ってるのに、ぼくのために会社休んで学校に来て、なんて言えないよ」
「光――。じゃ、あんた……」
「ぼくが、あやまったんだ。校長室で、森本の親に」
なんと言ってあやまればいいのかは、相沢先生が教えてくれた。
「森本くんがぼくをいじめたというのは、ぼくのかんちがいでした。森本くんはぼくと仲良く遊んでくれていたのに、ぼくが体力がなかったため、その遊びについていけなかったんです。いじめられたというのは、全部ぼくの被害妄想です」
と。
「ねえ、ひかる。ひがいもーそーって、なに?」
「たいしてひどい目にあってもいないのに、自分だけがめちゃくちゃいじめられてる、ひどい目にあわされてるって、思い込むことよ。ま、あんたのことじゃあ、ないわね」
「そっか。やっぱりぼくが悪いんじゃないんだ」
「当たり前でしょ。いじめで一番悪いのは、いじめてるヤツに決まってるじゃない」
ひかるの言葉に、光は少しだけ安心したように笑った。
「毎日毎日キモいだのウザいだの言われ続けてるからさ、ほんとにぼくがキモくてウザいのが悪いんだって、なんかそんな気がしてきてたんだよ」
「ばっかね、あんた。だいたい、『キモい』とか『ウザい』とか、ほんとの意味はなに? 具体的には、どういうヤツのことを言うの? 国語辞典の説明みたいに、はっきり文章にして言ってごらん!?」
「えっ? えっと……。つまり、それは、なんとなく……」
光は答えにつまった。
そんなふうにあらためて質問されると、返事ができない。
――そうか。ぼくも、そしてきっとみんなも、たいして深く考えもせずに、こういう言葉を使ってるんだ。
ひかるは、そんな光に、それ見たか、と言うような顔をした。
「でも、そいつの親も、いったいなに考えてんのかしら。自分のこどもがうそついてんのも見抜けないなんて!」
「しかたないよ。森本の親も、きっと森本を守ろうとして、いっしょうけんめいなんだと思う」
ため息をつくように、光は言った。
「森本は五年生の時、ずっといじめられてたんだ」
「え……」
「先生と、森本の親が何度も話し合いして、いじめのリーダーになってるやつの親も学校に呼び出された。クラスでも、授業つぶして、何回も話し合いをしたんだ。六年になって、クラス替えがあって、森本へのいじめはなくなった。あいつ――きっと、勉強したんだと思う」
「勉強って、まさか……」
「そう。自分がいじめの被害者にならない、一番の方法。自分以外の誰かを、さきにいじめることだよ」
それから、光に対するいじめはいっさいの歯止めがかからなくなった。
最初は森本とそのグループだけだったのが、あっという間にクラス全員がいじめに加わるようになった。
相沢先生には、それを止めることは無理だった。
光と仲の良かった友達でさえ、いっせいに光に背を向けた。
「ほかの先生たちも、みんな知ってる。でも、誰も止めないんだ」
「どうして!?」
「だってぼくたち、六年生だよ。あと4ヶ月ちょっとで卒業なんだ。うちのクラスでなにが起きてても、あと4ヶ月、だまって見ないふりをしていれば、ぼくたちは卒業して、自動的に明京小学校からいなくなるんだ。そうなりゃ、なんの問題もなくなるじゃないか」
「それであんた、自殺して、本当のことを世の中にうったえようとしたわけ?」
「ううん、違う」
光は力なく首を横にふった。
「自殺する時は、遺書なんか書くなって、森本におどされてるんだ」
「――なんだって!?」
「遺書に自分たちの名前なんか書き残したら、家に火ぃつけてやるって」
「ち、ちょっと……! あんた、そこまでされて、なんでだまってんの!? そんなの、立派な犯罪じゃない!! そいつの言うとおり、告発もなんにもしないで、ただだまって死ぬつもりだったの!?」
「だって、しょうがないじゃないか!」
光はどなった。
「ぼくにどうしろって言うんだよ! 1対37だよ! 先生も、誰もぼくを助けてくれない。それどころか、学校の先生はみんな、森本たちの味方なんだ! 森本の親にどなりこまれるのが怖いから!」
涙があふれる。
次から次にこぼれ落ちて、とまらない。
今までずっとかくしてきた気持ちが、一気に胸の奥からあふれ出してくる。
「ぼくだって、ほんとは死にたくない。死ぬのは怖いよ。でも、これからずっと、毎日毎日いじめられ続けるのは、もっと怖いんだ……っ!!」
「光――」
声もなく泣き続ける光に、ひかるがそっと声をかけた。
「光。死ぬ覚悟があるなら、一週間――ううん、三日でいい。あたしにからだを貸して」
「え……? ど、どういうこと、ひかる……」
「このままだまって死ぬなんて、あんたもくやしいでしょう?」
いつのまにかひかるが、天井から、光の目の前まで降りてきていた。
あいかわらず半透明だけれど、まっすぐに光を見つめている。
「どうせ死ぬなら、あいつらに一発くらい仕返ししてから、死にたいでしょ!?」
「う、うん。そりゃ、できるなら……」
ひかるはにやっと笑った。
その笑顔は、見ている光がぞくっとするくらいの、強い自信にあふれていた。
「あたしにまかせなさい。反撃の方法を、教えてあげる」
光は、道をまたぐ歩道橋のまんなかにしゃがみこんで、らんかんのすきまから、下を通る車をぼんやりながめていた。
古い歩道橋は、下を大型車が通るたびにずんずん揺れる。ダンプなんかが通ったら、まるで地震みたいだ。
――あんなでっかい車に轢かれたら、ぼくなんて、きっとぺちゃんこだろうな。
つぶれたカエルみたいに、アスファルトの路面にへばりつく自分を、想像してみる。
「……きもちわりい」
轢かれたら、痛いかな。痛いだろうな。でも、きっと一瞬だ。わあッって思ったら、もうぺっちゃんこのぐっちゃぐちゃだ。
首吊りや飛び降りと、どっちが痛いだろう。
でもぼく、三階以上の高いところにのぼると、怖くて目もあけていられないし……。
本当のことを言えば、この歩道橋を渡るのだって、怖いのだ。渡っているあいだは、いつも足の裏がむずむずする。
それなのに光は、もう三〇分近くも、歩道橋のまんなかにしゃがみこんでいた。
半透明のプラスチック板でできたらんかんは、ちょうど光の目の高さだ。
だが下のほうには隙間があいていて、しゃがめばそこから下の道路が見える。
ランドセルがわりのリュックをかかえ、ずっと歩道橋でしゃがみこんでいる光を、通りがかった人たちは、みんな、不思議そうな、どこか気味悪そうな顔でながめていた。
けれど、誰ひとりとして、光に声をかけようとはしなかった。
月曜日の午後一時半。
ふつうなら、小学生がこんなところにひとりきりでいるはずはないのに。
光は、小学六年の男子としては、ごくふつうの背丈だ。
同じクラスの男子には、体格が良くて、しょっちゅう中学生や高校生にまちがわれているヤツもいる。女子だって、毎日ばっちりメイクしてきて、とても小学生に見えない子が多い。
けれど光は、服装もトレーナーにハーフのカーゴパンツと、ありきたり。どこから見ても、ただの小学生だ。
なのに通りかかる大人たちは、そんな光が、ふつうなら学校にいるはずの時間に、たったひとり、歩道橋の上にしゃがみこんでいても、ふしぎともなんとも思わないらしい。
いや、光の様子がなにかおかしいと思っているから、そんなヘンな子供にはかかわりたくないと、足早に光のそばから逃げていくのだろう。
――だいじょうぶ。ほら、誰もぼくを止めやしない。
ぼくが死んだって、誰もなんとも思わない。
いいや、ぼくが死ねば、きっとみんなうまくいくんだ。
のろのろと、光は立ち上がった。
リュックを足元に置き、錆びて、塗装のはげたらんかんに、手をかける。
らんかんは高いけれど、あちこちに大きなビスや金具の出っぱりがあって、うまく足をかければ乗り越えられそうだ。
ふるえる爪先を、金具のかどに乗せる。
――遺書……、どうしようかな。やっぱり、書こうかな。
遺書がなかったら、光の死は自殺としてあつかわれないかもしれない。
でも、そのほうがいいかもしれないと、光は思った。
一人息子が自殺したと知るより、ぐうぜん事故で死んでしまったと思っているほうが、お母さんはまだ気がらくなんじゃないだろうか。
お母さん。お母さん、寂しがるかな。ぼくがいなくなったら。
――だめだ。だめだ、よけいなこと考えちゃ。
ぐずぐずしてたら、どんどん踏ん切りがつかなくなる。
勇気があるうちに、飛び降りるんだ。
そうすれば、みんな、終わる。
全部、らくになれるんだから……!
「ねえあんた、死にたいの?」
突然、高い声がした。
「自殺するの? じゃあそのからだ、いらないんだ? だったらあたしにちょうだいよ」
「――え?」
光はふりかえった。
冷たく、鉄みたいなにおいのする風が、一気に光の全身をおしつつむ。
ぞうッと、足の先から頭のてっぺんまで、からだ中の皮膚が鳥肌立った。髪の毛まで全部、逆立つ。
「あんた、そのからだ、いらないんでしょ? だったらあたしがもらっても、いいよね?」
そこには、全身を真っ赤に染めて、右肩から腰、右足までをぐちゃぐちゃにつぶされた、若い女の幽霊が立っていた。
長い黒髪の下、奇妙なくらいきれいな左半分の顔で、幽霊がにィッと笑う。
光に向かって、右手をさしのべて。その手は、手首から先が奇妙な角度に折れ曲がり、おもちゃみたいにぶらぶら揺れていた。
「ね、ちょうだい?」
光は返事ができなかった。
そのまま、白目をむいて気絶した。
気がついた時、光は見慣れた自分の部屋にいた。
一年生の時から使っている学習机にベッド、本棚に乱雑につっこんであるコミックス。
まちがいなく、自分の部屋だ。
「あれえ……。ぼく、いつの間に帰ってきたんだろ」
さっきまで、歩道橋の上にいたはずなのに。
光はベッドの上に起き上がった。
服もちゃんと着ているし、リュックも机の横に置いてある。おかしなところはなにひとつない。
「へ……へんだな。なんか、へんな夢でも見てたのかな、ぼく」
怖い夢だった。全然知らない女の人の幽霊が出てきて、その幽霊がまた、妙にリアルで――。
「夢じゃないわよ」
いきなり、天井のあたりから声が降ってきた。
「うわああっ!?」
思わず見上げた先には、あの女の幽霊が浮かんでいた。
血に染まり、ぐちゃぐちゃにつぶれた右半身もそのままだ。
その身体の向こうには、天井の様子が透けて見えている。
「うっ、うわ、うわっ、うわわわ……っ」
幽霊を指さしたまま、光はまともな言葉も出せなかった。
「なによ、失礼ね。あたしは化け物か。――て、ああ、このカッコじゃ、たしかにおバケだわね」
幽霊は、ささっと両手で自分の顔をなでた。
すると、あまりにも無惨だった右半分の傷がきれいになくなり、服にしみついた血の汚れも一瞬で消えてしまった。
サックスブルーのおしゃれなブラウスに黒のパンツルックがかっこいい。
そして両手を離すと、左半分と同じく、若くてうつくしい女性の顔がぱっとあらわれた。
黒いロングヘアにほっそりとした顔立ち。髪と同じ色の瞳と、きれいにルージュでいろどられた唇。
……きれいなおねえさん。
光は思わず、その顔に見とれてしまった。
とはいうものの、その顔はやっぱり半分透けて、うしろの天井が見えていたのだが。
「だ、誰?」
「なによ、覚えてないの? あたしがあんたをここまで連れてきてやったんじゃない」
「連れてきたって……」
幽霊はふわふわと宙に浮かんだまま、かっこう良く足を組んだ。まるで見えない椅子に座っているみたいに。
「ぶっ倒れて動かないあんたのからだを、あたしがかわりに動かして、ここまで歩かせてきたの。家までの道順は、ちゃんとからだが覚えてるものだからね」
「ぼくのからだを動かしたって……お、おねぇ――おばさんが!?」
「だーれがオバサンだっ! あたしはまだ二十五だ!」
「二十五才……。やっぱ、おばさんじゃん」
「だまれ、このガキ!」
幽霊は光の真上で思いきり足を蹴りあげた。
だがその爪先は、すかっと空振りしてしまう。
彼女の足は、光の頭をすーっとすり抜けてしまったのだ。
「ち! やっぱダメか」
幽霊は悔しそうに舌打ちをした。
「や、やっぱって……、もし当たってたら、どうするつもりだったんだよ!? そんな、とんがった靴はいて、あぶないじゃんか!」
「うっさいな。あんたが避ければいいだけの話でしょ」
「よけらんないよ。いきなり蹴られたりしたら――」
「マジ? やっだ、どんくさぁ!」
幽霊は宙に浮いたまま、けらけら笑った。
「な……なんだよ! なだよ、そんなに笑うことないだろ!」
光はどなった。
だんだん腹が立ってくる。
だいたいこいつ、本当に幽霊なんだろうか?
いや、普通の人間じゃないことだけは、わかる。
浮いてるし、半分透けてるし、オカルトやホラーの関係者なことだけはたしかだろう。
でも。
「あ、あんた、誰? なんでぼくに声をかけたの」
「言ったじゃない。あんた、自殺するつもりなんでしょ? そのからだ、捨てるつもりだったら、あたしがもらおうと思ったの。ごらんのとおり、あたしはもう死んじゃって、自分のからだがないもんだからさ」
――やっぱり、マジで幽霊なんだ。
光のからだをのっとって、生き返ろうというつもりなんだろうか。
光は、頭のうしろあたりがすうっと冷たくなるのを感じた。
けれど、今度はどうにか気絶せずにがまんする。
今、見えているのが、最初に見た血まみれのぐっちゃぐちゃな姿ではなくて、きれいでかっこいい女の人だから、がまんできたのかもしれない。
本当に、きれいな人だ。
テレビなどで見る女優か、雑誌のモデルみたいだ。
こんなに若くてきれいな人が、もう死んでいるなんて。
「交通事故だったのよ」
まるで光の頭の中を読みとったみたいに、幽霊は言った。
「先週の日曜日、自分で車を運転して、さっきの道を通ったの。そしたら、わき見運転の車にぶつけられちゃって。ちょうどあの歩道橋の真下あたりでね」
「ふうん、そっか……」
車の事故なら、あの血だらけの姿も当然だ。
でも、やっぱり。
「ぼくには、関係ないじゃんか。化けて出るなら……その、車ぶつけた相手んとこに出てよ」
「無理よ。そいつも事故で死んじゃったもん」
けろりとして、幽霊は言った。
「ね。あんた、名前は?」
「い、井上 光……」
つい、光は答えてしまった。
「ヒカル? ヒカルくん? ぐうぜんね、あたしもひかるっていうのよ!」
「……だから、いやなんだ」
幽霊に聞こえないよう、光はこっそりつぶやいた。
「え? なんか言った?」
「だから――きらいなんだよ、この名前! 光なんて、女みたいじゃないか!」
言ってから、光はしまった、と思った。
こういうことを言うと、大人は必ず、
「そんなことを言ってはいけません」
「お父さんとお母さんがいっしょうけんめい考えてくれた名前です、もっと大切にしなくちゃ」
と、叱るのだ。
だが幽霊――ひかるは、にやにや笑って、こう言ったのだ。
「そんなにいやなら、別の名前にすれば?」
「えっ!? できるわけないじゃん、そんなこと」
「かんたんよぉ。別の名前を使う仕事につきゃあいいのよ。わかりやすいのは、マンガ家とか小説家とか、ものを書く仕事ね。たいがい、ペンネームってのを使うじゃない。その仕事で一流になれば、誰もあんたを本名で呼んだりしないわよ。ペンネームが、あんたにとって一番重要な名前になるんだもの」
「ペンネーム……」
「ま、戸籍上の名前は、よっぽどの理由がないかぎり、変えられないけどね。……て、関係ないか。あんた、どうせ死ぬんだもんね」
ひかるは身を乗り出すように、ふうっと光の目の前まで近づいてきた。なんだか、とてもわくわくしてるみたいな表情だ。
「でもさ、同じ死ぬんでも、飛び降りや交通事故はやめなさいよ。アレは痛いわよぉ。からだもつぶれてめちゃくちゃになっちゃうし。経験者が言うんだから、まちがいない!」
「う……」
たしかに、その言葉には説得力があった。あの血まみれのひかるの姿を見ているだけに、なおさらだ。
「それよりも、もっとらくな方法があるよ。あたしとあんたが、入れ替わるの」
「いれかわる!?」
「そう。あたしがあんたのからだに入って、あんたは今のあたしみたいに、魂だけの存在、つまり幽霊になるわけ。幽霊になるんだから、死んだも同じ、自殺したいっていうあんたの希望もかなえられるんじゃない?」
「そ、そりゃ、そうかもしれないけど……。でも、どうやって?」
ひかるはちょっと考えこんだ。どう説明すればいいのか、困っているらしい。
「とにかく、やってみればわかるわよ。さっきはうまくいったんだから」
「さっき?」
「言ったじゃない。気絶してひっくりかえったあんたのからだを、あたしが動かして、ここまで連れてきたって。つまり気絶したあんたのからだの中にあたしが入って、あたしの意志どおりに、そのからだを動かしたのよ」
「そんな! 人のからだ、勝手に使わないでよ」
「じゃあなあに、あのまま何時間も、歩道橋のまんなかにひっくり返っていたかったっての!? ひとがせっかく親切にしてあげたってのに!!」
かんしゃくを起こしたみたいに、ひかるは大声をはりあげた。
そしていきなり、両手を光へ向かって突き出す。
「あーもう、ごちゃごちゃうるさいっ! あんたはとにかく、じっとしてりゃいいのよ!」
ひかるの手が、まっすぐ光の目の前に突き出された。指先をそろえ、まるで光の両眼をえぐろうとするみたいに。いや、水泳の飛び込みみたいに。
「うわっ!?」
光は思わず、ぎゅっと目をつぶってしまった。
その瞬間、異様な感覚が光をおそった。
からだを内側からねじられるような、ひっくり返されて全部裏返しになるような。からだ中の毛という毛が、全部上に向かってひっぱられているみたいだ。
痛くて苦しくて、ぐらぐらめまいがして。脱水中の洗濯物が、きっとこんな気持ちだろう。
そして、ぱっと目をあけた時。
目の前には、光自身がいた。
ベッドに座り、にやっと笑って宙を見上げている。
「えっ!? ぼ、ぼく!?」
まちがいない。そこにいるのはたしかに光だった。
――じゃあ、ここにいるのは!?
光はあわてて自分のからだを見回した。
目の前にかざした両手は、半分透けて、向こう側に部屋の光景が見えていた。……さっきのひかるとまったく同じく。
「どう? 幽霊になった気分は」
光が――いや、ひかるが言った。
ひかるの説明したとおり、光の意識は自分のからだから追い出されてしまったらしい。今、光のからだに入っているのは、ひかるの意識なのだろう。
目の前にあるのは、光の顔、光のからだ、着ている服だって、なにひとつ変わっていない。
でも。
……ぼく、こんな顔、してたっけ?
どうだ、見たかというような表情をして、にやっと自信ありげに笑うその顔は、鏡や写真で見るいつもの自分とは、まったく違う。まるで別の人間みたいだ。
表情だけで、こんなにも違って見えるなんて。
「ね、かんたんでしょ」
光が、いや、光のからだに入ったひかるが、言った。
その声もたしかに光のものだったが、しゃべり方は全然違う。
ひかるはとてもうれしそうだった。
両手をなでたり、大きくのびをしたり、座ったまま足をばたばたさせてみたり、からだの動きを確かめているようだ。
「そういやあたし、昔から一度、男の子になってみたかったんだあ。そうだ、せっかくだから、どっか遊びに行こうかな! あんた、いつもどこで、なにして遊んでんの?」
ひかるはベッドから立ち上がった。
「あ、でも、このカッコ、だっさいなあ! もうちょっとマシな服、ないの?」
そして、壁につくりつけになっている洋服たんすを開け、光の服をかたっぱしから引っぱり出す。
「ち、ちょっと……! ひとのからだで、勝手なことしないでよ!」
あわてる光を、ひかるはにやっと勝ち誇ったような笑いを浮かべて見上げた。
「あんたは幽霊なんだから、これはもう、あたしのからだよ。――あ、と、あたし、じゃないか。オレ、かな? オレ」
ひかるはでかけることはやめたようだが、今度は本棚に並んだマンガをいろいろ物色し始めた。散らかした服も片づけないままだ。
「あんたは望んだとおり幽霊になったんだから、もうここにとどまってる必要もないし。好きなとこに行っちゃっていいのよ」
「行くって、どこへ……」
「天国とか地獄とか、いろいろあるじゃん。ま、あたしもまだ行ったことないから、良くわかんないけどさ」
「い、いやだよ! 地獄なんて、行きたくない!」
「なによ。あんた、死にたかったんでしょ? 願いがかなったんだから、文句ないでしょ!」
「いやだいやだいやだ! ぼくのからだ、返せよ!!」
光は大声でわめいた。
からだがあったら、手足をふりまわしてめちゃくちゃにあばれるところだ。
「人のからだ、勝手に使うな! 返せよ!!」
空中に浮かんだ光は、そこからひかるに思いきりぶつかっていった。
――あ、ぼく、今は幽霊だから、蹴ったり撲ったり、できないんだっけ!?
でも、勢いがついて、もう止まらない。
そのまま光の姿は、ひかるに重なった。
その瞬間、また、からだ中がしぼられるみたいな、あの感じが光を襲った。
「う、うわっ! うわあっ!?」
おなかの奥から一気に吐き気がこみあげてくる。
それを、どうにか押し殺そうとした時。
「あ……!」
光のからだは、もとどおりになっていた。
両手をさする。それからほほ、あご、髪の毛もひっぱってみる。ちょっと痛い。
ちゃんとからだがある。
「良かったあ……」
光は大きくため息をついた。
「あーあ、やっぱりだめか」
ふたたび半透明の幽霊になったひかるも、がっかりしたようにため息をついた。
「もともとのからだの持ち主であるあんたが、そうやってからだから離れたくないってがんばってると、あたしもからだの中に入れないのよね。さっきみたいに、あんたが気絶してるとか寝てるとかしてないと、すぐに追い出されちゃうの」
ひかるはまた、空中にこしかけるように、かっこよく足を組んだ。
「実は、あんたのほかにも二、三人、ためしてみたんだけど、全然だめだったの。からだの中に入るどころか、家の中までくっついてくこともできなくて。その人の後ろから玄関入ろうとしたら、ドアを通り抜けられなかったの。閉じたドアにどかん!て、顔からぶつかっちゃってさ、まるでテレビのコントみたいだった」
あはは、と、ひかるは気楽そうに笑った。
「じゃあ、なんでぼくだけ……」
「やっぱ、アレじゃない? あんたが死にたがってたから」
にやりとしたその表情は、やっぱりかっこいいや、と光は思った。
「ねえ。あんた、なんで死にたいの?」
光はうつむいた。
黙り込み、答えない。ひかるを見ようともしない。
「ま、言いたくなきゃ、言わなくてもいいけどね」
ひかるも、たいして興味もなさそうに言った。
さーて、どうしよっかなあなんて一人言をつぶやきながら、ひかるはそこにふわふわ浮いたままだった。
「な……、なに、してんの?」
「ああ、気にしなくていいよ。無視してくれてかまわないから」
「無視できるわけないだろ! あんた、ぼくにとりつくのはあきらめたんだろ!? だったら、さっさと別の人を探しに行けよ。なんで、いつまでもぼくの部屋にいるのさ!?」
「あんたがもう一度死にたくなるのを、待ってんの」
ひかるは、平然と言った。
「え……!?」
「だってあんた、理想的なんだもの。友達も少ないみたいだし、いっしょに暮らしてる家族はお母さん一人きりでしょ?」
「ど、どうしてそんなこと、知ってんだよ!?」
「キッチンの食器。二人分しかないじゃない。それに男物の服や靴も見あたらないし。あんた、お父さんとは別々にくらしてんでしょ。兄弟もいないみたいね」
「う、うん……。そうだよ」
光のお父さんとお母さんは、三年前に離婚していた。
光はお母さんといっしょに暮らし、お父さんとはもう二年以上会っていない。ちらっと聞いた話では、お父さんはもう別の女の人と再婚したらしい。
「家族や友達が多いと、入れ替わったあと、その人たちみんなをだましてなきゃいけないじゃない? だます相手は少ないほうがらくだもん」
だませるわけないじゃんか、と、光は言おうとした。
学校のクラスメイトや先生ならともかく、お母さんが、光が別人と入れ替わったことに気づかないはずがない、と。
……でも、言えなかった。
本当に、そうだろうか?
もしも本当に光とひかるが入れ替わったとしても、お母さんはそれに気がついてくれるだろうか?
はっきり、そうだと言い切れる、自信がなかった。
――たとえば、お母さんが誰か別の人に入れ替わってて、ぼくのお母さんのふりしてるだけだとしたら……ぼくに、それがわかるだろうか?
そこまで、ぼくはお母さんのこと、よく知ってただろうか。
お母さんとちゃんと話をしてたかな。
お母さんはいつも仕事で忙しいし、帰りが遅いこともしょっちゅうだ。
光も、学校であったことやその日一日のこと、自分からお母さんに話すことなんかめったにない。お母さんにしつこく質問されて、うん、とか、そうだよ、とか、いい加減に返事をするだけだ。
だって小六にもなって、男が、お母さんと仲良くおしゃべりするなんて。
女の子ならともかく、そんなのなんだかはずかしくって、できやしない。
お母さんのほうも、光のそんな気まずい思いに気がついているのか、なんとなく話しかけにくそうにしている。
二人で話す時間は、ますます減る一方だ。
これじゃ、おたがい、相手が別人と入れ替わってたとしても、まったく気づかないんじゃないだろうか。
「それに、自殺志望の人間をもういっぺん探して回るの、めんどくさいし。そいつが借金まみれのおっさんとか、汚職がばれて警察につかまる寸前の役人とかだったら、もう目もあてらんないじゃん。あたしだってそりゃ、もういっぺん死ぬしかないわよ。でもあんたなら、まだ夢も希望もある小学生だもんね!」
――夢や希望があったら、誰が自殺なんかするもんか。
うつむき、光は両手をぎゅっとにぎりしめた。
「自殺ってね、たいがい一回じゃ成功しないもんなのよ」
ひかるが言った。
「あんたも必ず、もう一回やろうとするはずよ。あたしはそれを待つことにする。それがいちばん、効率がいいもん」
「ま、まさか、ぼくがもう一回、どっかから飛びおりようとするまで、ずっとそうやって、くっついて回るつもり!?」
「そうよ」
けろっとして、ひかるは言った。
「安心しなさい。あたしの姿は、あんた以外の人間には見えないはずだから。て言うか、あたしが見えた人間、今まで一人もいなかったもん。あんたが幽霊にとりつかれてるなんて、誰にもわかりゃしないわ」
それに第一、と、けらけら笑う。
「あんた、もう半分死んでるみたいな顔してるじゃん。幽霊にとりつかれようがなんだろうが、今さらたいして変わりゃしないって!」
ひかるは窓を指さした。
外はかなり暗くなり、窓ガラスは鏡のように部屋の中の様子を映している。
そこに、ひかるは映っていなかった。
映っているのは、光の姿だけだった。
「ぼく……」
窓ガラスに映る自分の姿に、光は目を向けた。
その顔は、表情も乏しく生気がなく、口元は力なく半開き、目はどんよりとして、たしかに半分死んでいるみたいな顔だった。
「光、光! いつまで寝てるの、起きなさい!」
お母さんに揺り起こされて、光はのろのろと目を開けた。
「んー……。もう朝なの……? まだ眠いよ――」
半分ねぼけたまま、光は大きくあくびをした。それでもなかなかまぶたが開かない。
「あたりまえでしょ。ゆうべ、あんなに夜更かししたんだから。またマンガばっかり読んでたんでしょ」
「え?」
そんなことないよ、と、光は言おうとした。
だってゆうべは、起きているのもいやになって、さっさと布団をかぶって寝てしまったのだ。
起きていると、そのあいだずっと、光が自殺したくなるのを待っているひかるを、そのわくわくしている顔を、見ていなければならないから。
「こんなに出しっぱなしにして。学校から帰ってきたら、ちゃんと片づけなさいよ」
お母さんは、ベッドの枕元や床の上に散らばったマンガのコミックスを、ぱたぱたとてきとうに積み重ねた。
「今はこのままでいいわ。片づけてたら、学校に遅れちゃうもの。そのかわり、晩ご飯までにきちんと片づけておかなかったら、このマンガ、全部捨てちゃうからね。ゲーム機も、テレビにつなぎっぱなしにしてたらいけないって、いつも言ってるじゃない!」
――そんなばかな!
ゆうべ、マンガなんか読んでいたおぼえはない。まして、ゲームなんて。
そう考え、光はようやく気がついた。
天井のほうを、ぱっと見上げる。
やはりそこには、きれいなロングヘアのひかるが、半透明の姿でふわふわ浮いていた。
「や。おはよ」
にっこり笑いながら、その顔はどこか眠たそうだ。
――ひかるっ!
どなろうとして、光はあわてて口をおさえた。
ちょっと不思議そうな顔をして、お母さんが光を見ている。
お母さんは、ひかるの存在にまったく気がついてない。
「お、お母さん! もう出てってよ! ぼく、着替えるから!」
「光?」
「ほら、早く! 急がないとほんとに遅刻しちゃうってば!」
光は、お母さんの背中を押すようにして、むりやり部屋の外へ追い出した。
ドアをしっかりと閉め、それから部屋の中へ向き直る。
「――ひかる!」
「なによ。目上の人間を呼び捨て!?」
「ひかるは人間じゃないだろ、幽霊じゃんか!」
いや、そんなことはどうでもいい。
「ゆうべ、ぼくのからだを勝手に使ったろ!?」
ひかるは、にらみつける光と目を合わせないよう、しらじらしく視線をそらした。
「ぼくが寝てるあいだ、ぼくのからだに入って、ゲームしたりマンガ読んだり、一晩中遊んでたんだろ!?」
「だってさあ、おもしろそうだったんだもん、そのマンガ」
今度は完全に開き直り、ひかるは言った。
「あんたが持ってるゲームも、あたし、やったことないやつばっかだったし。ねえ、そのゲームのさ、3面がどうしてもクリアできないのよ。あとでやり方、教えて?」
「か、勝手なことばっか、言うなよッ!!」
光は思わず大声を出した。
すると、
「光、どうしたの?」
びっくりしたようなお母さんの声が聞こえてくる。
「ばかねえ。あたしの声はあんたのお母さんには聞こえないけど、あんたの声はふつうに回りに聞こえてるのよ」
光はあわてて、両手で口をふさいだ。
これじゃ、家の中ではひかると言い争いをすることもできない。
「と、とにかく、ぼく、もう学校行くから。ぼくが帰ってくるまでに、この家から出てってよ!」
「無理よ。あたし、ずーっとあんたにとりついてるって、決めちゃったもん」
「そんな……っ!」
「あ、さすがにトイレやお風呂はのぞかないから。そのくらいのプライバシーは守ってあげる。着替えの時もね」
ほら、早く着替えなさい、と、ひかるはぱっと後ろを向いた。
しかたなく、光はもそもそと着替え始めた。
「終わった? ほんと、あんたってとろくさいのねえ」
「ねえ。もしかして、学校までついてくるつもり?」
「当然じゃない」
にっこり笑って、ひかるはうなずいた。
「あんたのことは、なんでも知っておかなくちゃね。入れかわった時に、よけいな失敗しなくてすむようにさ」
光は黙りこんだ。
もう、なにを言ってもむだみたいだ。光がなにを言ったって、ひかるは光のそばを離れないだろう。
――いいさ。勝手にしろよ。
胸の中で、光はやけっぱちにつぶやいた。
学校でもどこでも、ついてくればいい。そして、全部見ればいいんだ。
ぼくがいつも、クラスでどんな思いをしているか。
それがわかれば、ひかるだって絶対に、光と入れかわろうなんて思わなくなるに決まってる。
――そうさ! わけもなく自殺したいなんて、思うもんか!!
光は、机の横にほうりだしてあったリュックを手に取った。
時間割をたしかめ、必要な教科書やノートをリュックにつめこむ。
「あら。どうしたのよ。急に静かになっちゃって」
「だって、ぼくの声はふつうに聞こえるんだろ。ひかるの声は誰にも聞こえないのに、ぼくがひかるに話しかけてたら、ぼくはブツブツ一人言ばっか言ってる、キモいヤツになっちゃうじゃん」
「そりゃまあ、そうだけど。でも、あたしとあんたしかいない時だったら――」
「とにかく。ぼくは、学校じゃひかるを無視するからね。そうしろって言ったのは、ひかるなんだから」
ふうん、と、ひかるはつまらなさそうに光を見下ろした。
光はもう、返事もしなかった。
さっさとしたくをして、部屋を出る。
キッチンには、朝ご飯の用意ができていた。
「いただきます」
ぼそぼそとつぶやいて、光はトーストにかじりついた。
食欲なんて全然ないけれど、機械的に食べ物を口に入れ、飲み込む。
そのあいだにお母さんも、会社に出勤する用意をしている。スーツに着替え、きれいにお化粧をする。
玄関を出るのは、たいがい二人いっしょだ。
光の家は、賃貸マンションの一室だ。2LDK、けして広くはないけれど、二人で住むには充分だ。
いや、お母さんのお給料では、これ以上広い部屋に住むのは無理だ。
「気をつけていってらっしゃい。お母さんも、今日はできるだけ早く帰ってくるから」
「うん、わかってる」
「忘れ物はない? 家の鍵、ちゃんと持った?」
お母さんの言うことは、いつも同じだ。
「この前みたいに、学校で鍵を失くしたりしないでね。合い鍵つくるのだって、お金かかるんだから」
――違うよ、お母さん……と、言いかけて、光はぎゅっと唇をかんだ。
本当のことをお母さんに言って、どうなるだろう。
どうにもならない。ただ、お母さんを哀しませるだけだ。
「うん。わかってる」
光はいつもと同じく、ただそれだけを答えた。
「携帯もちゃんと持ってるわね? ああ、もうバスに遅れちゃう。じゃあね、光。車に気をつけるのよ」
お母さんは腕時計を見ながら、マンションの階段をあわてて駆け下りていった。
「ぼくも……行かなくちゃ」
一言つぶやいて、光も歩き出した。まるで足を引きずるように。
「ちょっと、どうかしたの? あんた、学校行きたくないの?」
頭の上、ややななめうしろにふわふわ浮かんでいるひかるの声にも、なにも答えない。
うつむいて、だまって、歩き続ける。
「今日、テストでもあんの? あ、わかった。インフルエンザかなんかの予防接種でしょ。あんた、度胸なさそうだもんねえ」
――ついてくれば、わかるさ。
市立明京小学校、六年B組。
朝のホームルームが始まる前の教室は、動物園みたいな騒がしさだ。
とっくみあい、格闘技ごっこをしている生徒、対戦ゲームに夢中の生徒――学校にゲーム機を持ってきてはいけません、と、先生からしつこく言われているのだが――、スマホでゲームをしている生徒もいる。防犯のため、ケータイやスマートフォンを持ち歩くことは禁止されていないのだ。
女子の中には、鏡をのぞきこんでメイクを直している子もいる。
校則が何十年も前に作られた古いものなので、「学校にお化粧をしてきてはいけません」という一文がないのだ。校則ができた当時の小学生は、誰もメイクなんかしていなかっただろうから。
メイクをして登校する子は、最初は2、3人だった。
だが、いつのまにか
「あの子がメイクしてかわいくなってるのに、あたしがすっぴんじゃはずかしい」
と、クラス中に伝染して、今ではクラスの女子の半数以上がなんらかのメイクをしている。すっぴんの子は、親がアタマが古くて許してくれないと、文句ばかり言っている。
みんなが数人ずつのグループになって、好き勝手にしゃべっているため、教室全体がうわぁ…ん、といううなり声につつまれているみたいだ。
だが、
「……おはよう」
光が教室のドアを開けた瞬間、そのうなりが、ぴたりと止んだ。
教室全体が、凍りついたみたいに静かになる。
クラスメイトたちの視線が、一斉に光へそそがれた。
――こいつ、また来たよ。うぜぇー!
――うっそぉ、信じらんない。まだ生きてる。
声にならない声が、光のからだじゅうに突き刺さった。
――あーやだやだ。キモぉ! なんでこいつ、うちのクラスなわけ!?
――さっさと不登校になれよ、ばぁか!!
そしてみんなは、また一斉に光から目をそらした。
光がのろのろと自分の席へ向かっても、誰も光に声をかけようとしない。
光なんてまるで目に入らない、存在していないかのように、無視する。
だが本当は、見ていないわけではないのだ。
光と視線が合わないよう、顔を伏せながら、ちらちらと光の様子を盗み見ている。
光が今、どんな顔をしているのか、たしかめようとしているのだ。
光がどんなに傷ついているか、つらそうな顔をしているか、みんな、それが見たくてたまらないのだ。
くすくすくす……と、低い笑い声が聞こえる。とうとう我慢できなくなったらしい。
まるで動物園の珍獣みたいに観察されながら、光は自分の席にたどりついた。
が、座ることができない。
机にも椅子にも、ゴミが山積みされていた。
どうやら、ゴミ箱を光の机の上でひっくり返したらしい。
くすくす笑いがさらに大きくなる。
その笑いのほうへ光が目を向けても、もう相手も視線をそらしたりしない。
みんな、光の不幸を心底おもしろそうに笑っている。
実際、おもしろくてたまらないんだろう。
他人を傷つけ、相手の哀しい顔をながめることは、クラスの中でいちばんおもしろいゲームだ。
しかもその相手が絶対に反撃してこないとわかっている場合は。
光は顔をはっきりとあげることもできなかった。
笑っているヤツらを真正面からにらんだりしたら、今度は殴られる。
てめえ、なに見てんだよ、キモい、こっち見んな、と、五、六人、それもガタイのいい、腕力が自慢のヤツらばかりに取り囲まれ、さんざん殴られ、蹴られた。
反撃なんかできるわけがない。
そんなことが何度もあって、いい加減、からだでおぼえた。
光はリュックをまだ汚れていない床に置くと、だまって教室のすみへ向かった。
掃除用具入れからぞうきんとモップを持ってこようと思ったのだ。
だが、
「さわんじゃねえよ」
掃除用具が入ったスチールロッカーの前に、一人の男子生徒が立ちはだかった。
「てめえがさわったら、井上菌がつくだろうがよ! クラスの備品を汚染する気か、てめえ!」
クラスの中でもひときわ声が大きく、体格もいい、森本だ。
――そうか。あのゴミも、やっぱり森本がやらせたんだ。
きっと自分でゴミ箱にさわるなんてことはしなかっただろう。
いつもまわりにくっついている、金子や福田、水沢あたりの子分に命令して、やらせたはずだ。
「それって、ヘンだよ。森本くん」
言ってもどうにもならないとわかっていながら、つい、光は口を開いてしまった。
「この教室の掃除は、もう何日もずっと、ぼくひとりでやってるじゃないか。ぼく、先週もここのモップやバケツにさわって、教室を掃除したよ。先週の放課後はさわって良くて、どうして今朝はさわっちゃいけないんだよ」
「う……うるせえ、井上、てめええッ!!」
森本の顔が真っ赤になった。
光に反論されたことが、よっぽど我慢できなかったらしい。……しかも、どう考えたって、光の言っていることが正しいし。
それでも森本は、自分一人で光に手を出すなんてことは、絶対にしない。ここが森本の頭のいいところだ。
ぱっとうしろをふりかえり、そばにひかえている子分たちに、あごをしゃくって合図する。
「なんだよ、井上。そんなにゾーキンがほしいのかよ!」
「だったらてめえの服で拭けよ!」
「そうだそうだ、てめえの服なんか、どうせゾーキンといっしょじゃんか!!」
3人の男子が、いっせいに光に飛びかかった。
両脇から光の腕をつかまえ、光の席のそばまで引きずり戻す。
「い、痛いっ! 痛い、なにすんだよ、はなせよ!」
クラス中の生徒が、その光景を笑いながら見ていた。
「おら、拭けよ! さっさと拭いて、キレイにしろよ!!」
「なんだよ、いやがんじゃねえよ! 掃除すんの、手伝ってやってんじゃねえかよ!」
光は机の上に上半身を押さえつけられた。ゴミの山の上に。
「はーい、おそうじおそうじー!!」
金子だろうか、福田だろうか、浮かれて歌うように声をはりあげた。
左右から背中を押さえつけられ、光は汚れた机に押しつけられる。森本もそれに手を貸した。
彼らは光のからだでぞうきんがけを始めたのだ。
「おらおら、もっと力こめて拭けよ! ちっともきれいになってねえぞ!」
「井上、おめえ、これなめろよ! なめてキレイにしろよ!!」
教室中が笑い声に包まれた。
クラスメイトはみんな、いじめられている光を見て、とても楽しそうに笑っていた。
「やぁだぁ、きったねえー!」
「なんかぁ、ちょー笑えるんですけどー!」
「よく平気だよねー、あいつー!」
「そりゃそうだよぉ、だって井上だもーん。あははははーっ!!」
――平気じゃない。こんなことされて、平気な人間なんか、いるもんか。
光の苦しみは、誰にも届かない。
森本や子分たちも、本当に楽しそうだ。遠足や運動会よりも、ずっと、ずっと。
彼らにとって、光をいじめること以上に楽しいことなんか、ないのだろう。
やがて、ホームルーム開始を知らせるチャイムが鳴り響いた。
「どうしたの、みんな。早く席についてほしいなー」
クラス担任の相沢先生が教室に入ってくる。
相沢先生は、まだ独身の若い女の先生だ。
森本たちはようやく、光から手を離した。
「先生、おはよーございまーす!」
せいいっぱい明るく元気そうな声を出して、森本は先生ににっこり笑ってみせた。
子分たちもみんな、急いで自分の席に戻る。
光はのろのろとからだを起こした。
机にごりごり押しつけられて、からだ中があちこち痛い。服はどろどろに汚れてしまった。
それでも椅子にはまだ、ゴミが山積みされている。
その上に座るしかない。
「じゃあ、出席をとるからねー」
相沢先生は黒板の前に立ち、みんなに明るく声をかけた。
それから、あいうえお順で生徒ひとりひとりの名前を呼び上げる。
いつもどおりのホームルームの始まりだ。
井上光くん、と、光の名を呼んで、先生はようやく光の様子に気がついた。
「井上くん……。ど、どうしたの?」
「いいえ、なんでもありません」
なんでもないはずがない。
顔も服も汚れて、すり傷もいっぱいできている。机はゴミがなすりつけられて、真っ黒だ。
それでも光は、即座に「なんでもありません」と答えた。
「そう……」
相沢先生は、うつむいた。逃げるように、光から目をそらす。
教室のあちこちから、くすくす、くすっ、と、小さく笑い声が聞こえた。
みんな、お互いに突っつきあったり、こっそり光を指さしたりして、楽しそうに笑っている。
相沢先生は、半分こわごわと、光の席のそばまで近づいてきた。
「ね、ねえ、井上くん――」
消えそうな声で、光に話しかける。
けれど、光をちゃんと見ようとはしない。おどおどと目を伏せたままだ。
「本当に、先生に相談したいこと、なんにもないのね? よけいなことかもしれないけど、もしかしたら、なにか、先生にもできることがあるかもしれないし――」
光はなにも答えなかった。
相沢先生の言葉は、
「あなたのことで、先生にできることはなんにもないから、相談なんかしてこないでね」
という意味だ。
その証拠に、光がそのままなにも言わないでいると、相沢先生はあきらかにほっとしたようだった。
「じゃ、授業を始めよっか。みんな、教科書を出してくれるかなあ?」
そしてなにごともなかったように、一時間目の授業が始まった。
国語、算数、ただ時間だけがのろのろとすぎていく。
理科の授業では、実験のためにいくつかの班にわかれた。
が、仲のいい人どうしで班をつくっていいと相沢先生が言い出したため、光はどこの班にも入れなかった。
相沢先生も、光が一人、理科教室のすみに取り残されていることには気がついていたが、もうなにも言わなかった。
井上くんをどこかの班に入れてあげて、なんて言い出したら、クラスじゅうが大騒ぎになって、授業ができなくなるからだ。
6年B組38人全員が実験できなくなるより、光以外の37人が無事に実験をやりとげるほうが、ずっといい。
お昼、給食の時間になると、ふつうの生徒は
「今日のおかず、なんだったっけ? 自分の好きなやつだといいけど」
なんてことを、考える。
でも光の考えることは、
「今日は、ちゃんと給食食べられるかなあ」
だ。
給食にゴミを入れられる、給食のトレイをわざとひっくりかえされるなんて、しょっちゅうだ。
さいわい、給食センターから専用トラックで運ばれてくる給食は、クラスに配られるころにはわりあい冷めていて、頭からぶっかけられても、やけどすることはない。
「お、今日は酢豚かあ!」
大きななべをのぞきこみ、給食用のエプロンをかけた森本がうれしそうに言った。
「ほーら、井上くーん。サービスしてあげたぜえ?」
にやにや笑いながら、森本は給食トレイを光の目の前に突き出した。
お皿の上には、酢豚のにんじんとたまねぎだけがよりわけられ、山盛りになっていた。
ほかにはパンも牛乳もない。にんじんとたまねぎだけだ。
「おら、食えよ! 残すんじゃねえぞ!!」
「給食残すヤツは、昼休み居残りなー!」
どうしていいかわからない光のまわりを取り囲み、森本たちは大声ではやしたてた。
相沢先生は、自分の給食を食べ終えると、さっさと職員室へ逃げてしまっていた。
光が椅子から立ち上がろうとすると、
「てめえ、逃げんじゃねえよ!」
森本はどん!と、光の肩を乱暴にどつき、無理やり座らせる。
「違うよ……。スプーンもフォークもないし――」
「てめえに使わせるスプーンなんかねえよ! 手で食えよ、手で!!」
「おら、食えよ! 食えよ!!」
「くーえ、くーえ、くーえっ! くーえっ!!」
いつのまにか、クラスじゅうが手をたたき、声をそろえてはやしたてていた。
森本たちはますます興奮し、光の頭をつかんで、給食トレイに押しつけた。
酢豚のケチャップソースの中に、光の顔が押しつけられる。目の中にソースが入って、ものすごく痛い。
森本たちは、笑っていた。
クラス全員が、笑っていた。光がもがき苦しむ様子を見て、とても楽しそうに、うれしそうに。
みんな、今日も大満足のようだった。
「ふーん、なるほどね」
ぼそっとひかるがつぶやいた。
放課後、とぼとぼと家に帰る光の上に浮かんで、光の姿を見下ろしている。
光の服はどろどろに汚れ、まるでゴミ捨て場から這い出してきたみたいだ。スニーカーには黒の油性ペンでらくがきされていた。
「あんた、それで自殺しようとしてたんだ」
光はようやく、ひかるを見上げた。
まわりに人影はない。
今なら、ひかると話をしても大丈夫だ。
「わかったろ? ひかるだって、ぼくと入れかわったりしたら、すぐに自殺するしかないだろ?」
かすかに笑いながら、光は言った。
もう、笑うしかない。
「早く帰ろうよ。家ん中だったら、ひかるとゆっくり話ができるからさ」
それから光は、足早に自宅マンションへ戻った。
部屋に入るとまず、汚された服を着替えて、洗濯機へ放り込む。
「洗濯はぼくの仕事なんだ。学校から帰ると、まずこうして、洗濯機回すの。だから、お母さんには気づかれなくてすんでるんだよ」
だけど、と、光はため息をついた。
「あの靴は……どうしようかなあ。油性のペンで書かれちゃったから、洗っても落ちないなあ。しばらく隠しておくしかないか」
全自動洗濯機がうなりをあげて回り出す。
光は自分の部屋に入った。
ひかるもふわふわとついてくる。
部屋に入ると、光はすぐにベッドに横になった。
正直言って、からだじゅうがあちこち痛くて、椅子に座るのもつらいのだ。
ひかるは天井付近にふわふわ浮いて、ぽそっとつぶやいた。
「あんたのクラス担任もだらしないわねえ。あたしとそうかわんない年令だろうけどさ、でも、まがりなりにも教員試験パスしてんだから、もうちょっとまともな指導とか、できないのかな」
「しょうがないよ。相沢先生は、森本の親が怖いんだ」
「え?」
「ぼくだって、最初は先生に相談したんだよ。そしたら――」
相沢先生は、森本やその子分たちを職員室に呼び出し、話をした。
それはたぶん、お説教とか、そんなきついものではなかっただろう。相沢先生は、クラスのみんなに対して、いつも友達みたいな話し方をする。
きっと森本たちにも、
「先生、森本くんたちがほんとは優しい子だって、ちゃんとわかってるのよ。ただちょっと、ふざけちゃっただけよね? もう、やめてくれるよね?」
くらいのことしか言わなかったに違いない。
そうしたら、次の日、いきなり森本の母親が学校にどなりこんできたのだ。
「先生、うちの子がいじめをしてるってお叱りになったそうですね!? どこにそんな証拠があるんです! うちの子は絶対にいじめなんかしていないって、言ってます! タカヒロは、いじめなんかできるような子じゃありません、本当に心の優しい、いい子なんですよ!!」
森本の母親は校長室にまで押しかけて、廊下にまでひびきわたるほどの大声で、どなり続けた。
「うちの子にいじめられたって告げ口した子を、ここに呼んでください! 先生はどうせ、その子の言い分だけを聞いて、一方的にうちの子が悪いって決めつけたんでしょう! だから、その告げ口した子と、うちの子と、ここに二人並べて、どっちが本当のことを言ってるか、たしかめなくちゃ。もちろん、それぞれの親の立ち会いのもとで!!」
「い、いや、お母さん、もう少し穏便に……」
「なにをおっしゃるんですか、校長先生! うちの子が、うその証言で無実の罪を着せられそうなんですよ!!」
母親が抗議しているあいだ、森本は母親のうしろで、ずっと泣きまねをしていた。
「さあ、そのうそつきの生徒と、その親をここに呼んでください! さあ、早く!!」
相沢先生はこどもみたいに泣きながら、光を校長室へ連れていった。
「ぼくん家、お父さんがいなくて、お母さんが働いてるからさ。お母さんが学校に来るには、会社を休まなくちゃいけないんだ。ただでさえお母さん、仕事が忙しくて、熱があってふらふらしてる時でも、無理して会社に行ってるのに、ぼくのために会社休んで学校に来て、なんて言えないよ」
「光――。じゃ、あんた……」
「ぼくが、あやまったんだ。校長室で、森本の親に」
なんと言ってあやまればいいのかは、相沢先生が教えてくれた。
「森本くんがぼくをいじめたというのは、ぼくのかんちがいでした。森本くんはぼくと仲良く遊んでくれていたのに、ぼくが体力がなかったため、その遊びについていけなかったんです。いじめられたというのは、全部ぼくの被害妄想です」
と。
「ねえ、ひかる。ひがいもーそーって、なに?」
「たいしてひどい目にあってもいないのに、自分だけがめちゃくちゃいじめられてる、ひどい目にあわされてるって、思い込むことよ。ま、あんたのことじゃあ、ないわね」
「そっか。やっぱりぼくが悪いんじゃないんだ」
「当たり前でしょ。いじめで一番悪いのは、いじめてるヤツに決まってるじゃない」
ひかるの言葉に、光は少しだけ安心したように笑った。
「毎日毎日キモいだのウザいだの言われ続けてるからさ、ほんとにぼくがキモくてウザいのが悪いんだって、なんかそんな気がしてきてたんだよ」
「ばっかね、あんた。だいたい、『キモい』とか『ウザい』とか、ほんとの意味はなに? 具体的には、どういうヤツのことを言うの? 国語辞典の説明みたいに、はっきり文章にして言ってごらん!?」
「えっ? えっと……。つまり、それは、なんとなく……」
光は答えにつまった。
そんなふうにあらためて質問されると、返事ができない。
――そうか。ぼくも、そしてきっとみんなも、たいして深く考えもせずに、こういう言葉を使ってるんだ。
ひかるは、そんな光に、それ見たか、と言うような顔をした。
「でも、そいつの親も、いったいなに考えてんのかしら。自分のこどもがうそついてんのも見抜けないなんて!」
「しかたないよ。森本の親も、きっと森本を守ろうとして、いっしょうけんめいなんだと思う」
ため息をつくように、光は言った。
「森本は五年生の時、ずっといじめられてたんだ」
「え……」
「先生と、森本の親が何度も話し合いして、いじめのリーダーになってるやつの親も学校に呼び出された。クラスでも、授業つぶして、何回も話し合いをしたんだ。六年になって、クラス替えがあって、森本へのいじめはなくなった。あいつ――きっと、勉強したんだと思う」
「勉強って、まさか……」
「そう。自分がいじめの被害者にならない、一番の方法。自分以外の誰かを、さきにいじめることだよ」
それから、光に対するいじめはいっさいの歯止めがかからなくなった。
最初は森本とそのグループだけだったのが、あっという間にクラス全員がいじめに加わるようになった。
相沢先生には、それを止めることは無理だった。
光と仲の良かった友達でさえ、いっせいに光に背を向けた。
「ほかの先生たちも、みんな知ってる。でも、誰も止めないんだ」
「どうして!?」
「だってぼくたち、六年生だよ。あと4ヶ月ちょっとで卒業なんだ。うちのクラスでなにが起きてても、あと4ヶ月、だまって見ないふりをしていれば、ぼくたちは卒業して、自動的に明京小学校からいなくなるんだ。そうなりゃ、なんの問題もなくなるじゃないか」
「それであんた、自殺して、本当のことを世の中にうったえようとしたわけ?」
「ううん、違う」
光は力なく首を横にふった。
「自殺する時は、遺書なんか書くなって、森本におどされてるんだ」
「――なんだって!?」
「遺書に自分たちの名前なんか書き残したら、家に火ぃつけてやるって」
「ち、ちょっと……! あんた、そこまでされて、なんでだまってんの!? そんなの、立派な犯罪じゃない!! そいつの言うとおり、告発もなんにもしないで、ただだまって死ぬつもりだったの!?」
「だって、しょうがないじゃないか!」
光はどなった。
「ぼくにどうしろって言うんだよ! 1対37だよ! 先生も、誰もぼくを助けてくれない。それどころか、学校の先生はみんな、森本たちの味方なんだ! 森本の親にどなりこまれるのが怖いから!」
涙があふれる。
次から次にこぼれ落ちて、とまらない。
今までずっとかくしてきた気持ちが、一気に胸の奥からあふれ出してくる。
「ぼくだって、ほんとは死にたくない。死ぬのは怖いよ。でも、これからずっと、毎日毎日いじめられ続けるのは、もっと怖いんだ……っ!!」
「光――」
声もなく泣き続ける光に、ひかるがそっと声をかけた。
「光。死ぬ覚悟があるなら、一週間――ううん、三日でいい。あたしにからだを貸して」
「え……? ど、どういうこと、ひかる……」
「このままだまって死ぬなんて、あんたもくやしいでしょう?」
いつのまにかひかるが、天井から、光の目の前まで降りてきていた。
あいかわらず半透明だけれど、まっすぐに光を見つめている。
「どうせ死ぬなら、あいつらに一発くらい仕返ししてから、死にたいでしょ!?」
「う、うん。そりゃ、できるなら……」
ひかるはにやっと笑った。
その笑顔は、見ている光がぞくっとするくらいの、強い自信にあふれていた。
「あたしにまかせなさい。反撃の方法を、教えてあげる」
1
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

転生妃は後宮学園でのんびりしたい~冷徹皇帝の胃袋掴んだら、なぜか溺愛ルート始まりました!?~
☆ほしい
児童書・童話
平凡な女子高生だった私・茉莉(まり)は、交通事故に遭い、目覚めると中華風異世界・彩雲国の後宮に住む“嫌われ者の妃”・麗霞(れいか)に転生していた!
麗霞は毒婦だと噂され、冷徹非情で有名な若き皇帝・暁からは見向きもされない最悪の状況。面倒な権力争いを避け、前世の知識を活かして、後宮の学園で美味しいお菓子でも作りのんびり過ごしたい…そう思っていたのに、気まぐれに献上した「プリン」が、甘いものに興味がないはずの皇帝の胃袋を掴んでしまった!
「…面白い。明日もこれを作れ」
それをきっかけに、なぜか暁がわからの好感度が急上昇! 嫉妬する他の妃たちからの嫌がらせも、持ち前の雑草魂と現代知識で次々解決! 平穏なスローライフを目指す、転生妃の爽快成り上がり後宮ファンタジー!

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

モブの私が理想語ったら主役級な彼が翌日その通りにイメチェンしてきた話……する?
待鳥園子
児童書・童話
ある日。教室の中で、自分の理想の男の子について語った澪。
けど、その篤実に同じクラスの主役級男子鷹羽日向くんが、自分が希望した理想通りにイメチェンをして来た!
……え? どうして。私の話を聞いていた訳ではなくて、偶然だよね?
何もかも、私の勘違いだよね?
信じられないことに鷹羽くんが私に告白してきたんだけど、私たちはすんなり付き合う……なんてこともなく、なんだか良くわからないことになってきて?!
【第2回きずな児童書大賞】で奨励賞受賞出来ました♡ありがとうございます!
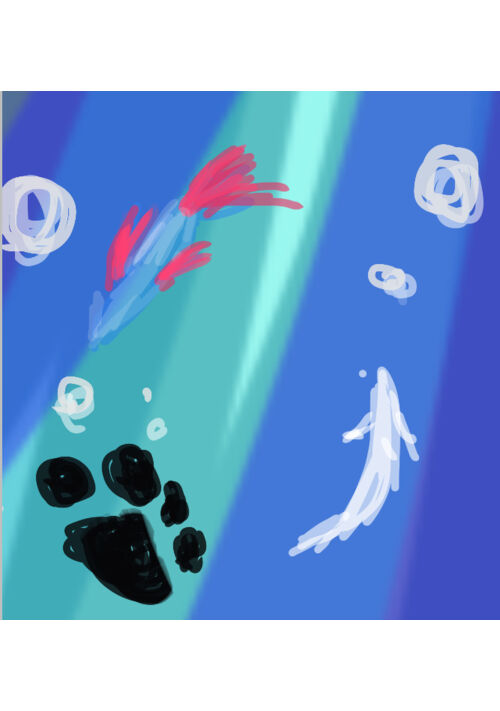
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎

ホントのキモチ!
望月くらげ
児童書・童話
中学二年生の凜の学校には人気者の双子、樹と蒼がいる。
樹は女子に、蒼は男子に大人気。凜も樹に片思いをしていた。
けれど、大人しい凜は樹に挨拶すら自分からはできずにいた。
放課後の教室で一人きりでいる樹と出会った凜は勢いから告白してしまう。
樹からの返事は「俺も好きだった」というものだった。
けれど、凜が樹だと思って告白したのは、蒼だった……!
今さら間違いだったと言えず蒼と付き合うことになるが――。
ホントのキモチを伝えることができないふたり(さんにん?)の
ドキドキもだもだ学園ラブストーリー。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















