2 / 4
2 ザ・反撃!
しおりを挟む
2 ザ・反撃!
始まりは、夏休みの宿題。理科の自由研究だった。
「ぼく、昆虫採集したんだ。夏休みのほとんどを、九州のばあちゃん家ですごしたからさ。ばあちゃん家、わりと田舎のほうで、田んぼとか雑木林とかも残ってて、カブト虫とかセミとか、ふつうにつかまえられたんだよ」
それでも、たいした虫をつかまえたわけじゃない。
カブト虫が2、3匹に、あとはカナブンとかトンボとか、めずらしくもないものばかりだった。
「だけどさ、みんな、すっげーびっくりしてた。だって、カブト虫なんてふつう、デパートかペットショップで買ってくるモノだもん。それを、ぼくは自分でつかまえて、自分で標本にしたんだ。標本の作り方は、じいちゃんが教えてくれた。先生もほめてくれて――理科の自由研究じゃ、ぼくのがクラスで一番に選ばれたんだよ」
でもね、と、光はうつむいた。
朝の通学路、大勢の人たちとすれ違う。
人目を気にしながら、ぼそぼそと光はこれまでのことをひかるに説明していた。
言葉がとぎれても、ひかるはだまったままだった。
あいかわらず光のちょっとうしろあたりにふわふわ浮きながら、光がまた話し始めるのを待っていた。
「森本が、ぼくの昆虫標本は環境破壊だって、言い出してさ」
ただでさえ数が減っている昆虫を、わざとつかまえて、標本にするなんて、とんでもない。こいつは日本の自然を破壊してるんだ。森本は光を指さして、そう叫んだ。
「てめえみてーなヤツがいるから、日本の自然には生き物がいなくなっちまうんだよ!」
森本の言葉に、金子や福田など、子分たちがすぐに同調した。
「そうだそうだ! 井上は、環境破壊してるんだ!」
「てめえ、知らねえのか。こういう小さい虫だってな、自然の生態系の中で大事な役割をはたしてんだぞ! 理科の授業でちゃんとやったじゃねえかよ!!」
彼らは、光を環境破壊の悪魔だと決めつけた。
学校全体でリサイクルや街の環境美化にとりくんでいるのに、光が一人でそれらをすべてだめにしてしまう、と。
「はあ!? なによ、それ!? たった一匹二匹の昆虫つかまえただけで、自然破壊だあ!? そいつら、ノーミソ煮えてんじゃないの!?」
とうとうがまんできなくなったのか、ひかるが大きな声を張り上げた。
ストレートなひかるの言葉に、光も小さく笑ってしまった。
「ちがうよ。あいつら、ぼくがうらやましかったんだ」
「え?」
「ほら、ぼくん家、あんまり金持ちじゃないだろ。お小遣いの額とかも、少ないほうでさ。ゲームやマンガも、発売当日には買ってもらえないんだ。買ってもらっても、中古だったりしてさ。みんなより、いつもちょっと遅れてんだよ。……でもそのぼくが、『貧乏でかわいそうな井上』が、クラスん中の誰もやったことないようなことを、やったんだ。みんな、生きてる虫にさわったことだって、ほとんどないはずだし。森本は、それが許せなかったんだよ」
光が、いつまでも「貧乏でかわいそうな井上」でいれば、森本はきっと光をいじめたりはしなかったろう。
自分が見くだして憐れんでいた井上光が、自分にはできないことをやってみせた。それが、森本にはどうしてもがまんできなかったのだ。
「そして――あとは、きのう言ったとおり。何回か殴られたりモノを奪られたりしたあと、先生に相談したけど、森本の親が学校にどなりこんできて、反対にぼくが森本にあやまらされたんだ」
あの時の森本の顔を、光は一生忘れないだろう。
親のうしろにかくれながら、先生たちには見つからないよう、うれしそうに笑い、光に向かって歯を剥きだして見せた森本の顔を。
「あいつら、なんでぼくをいじめ始めたのかなんて、とっくに忘れてんじゃないかな。今はもう、ぼくを――誰かをいじめてんのが楽しくて楽しくて、しょうがないんだよ。やめられなくなっちゃったんだ」
たぶん光がいなくなっても、森本たちは誰かをいじめることをやめられないだろう。
クラスの中に次のターゲットを見つけ、そいつをいじめるにちがいない。
やがて光とひかるは、初めて出会ったあの歩道橋にさしかかった。
その時、リュックのポケットからヴーッ、ヴーッ、ヴーッとスマホのバイブ音が聞こえてきた。
「え? あんた、スマホなんか持ってんの?」
「うん。クラスの緊急連絡網とか、スマホのメッセージアプリで回ってくるから」
とは言うものの、光はリュックのポケットからスマホを出そうとはしなかった。
着信を知らせるバイブレーションも、ちょっと鳴ってはすぐ止まり、またすぐに鳴りだしては止まってしまう。それが、何度も何度も繰り返された。
「メッセージが着いてんじゃないの? 見なくていいの?」
光は立ち止まり、ちょっと困ったようにひかるを見上げた。
ひかるもすぐに、その着信がなんであるのか、気がついたらしい。
「光。からだ、貸してよ。それ、全部あたしが消してあげるから」
「え……。い、いいよ。そのくらい、自分でできる」
「いいじゃん。どうせ今日一日、学校にいるあいだは、あんた、あたしにからだ貸してくれるって、約束したじゃない。今から入れかわってたって、いいでしょ?」
「う、うん……」
光は迷った。
きのう、ひかるはこう言った。
「あたしがあんたのからだに入ってれば、クラスでいじめられてるのは、もう井上光じゃない。あたし、成瀬ひかるなのよ」
「でも……! それじゃ、ひかるがつらい思いするじゃないか」
「ばぁーか! あたしは大人なのよ、オトナ! たかが小学生のがきんちょに少々いやがらせされたからって、そんなん、ヘでもないっての!!」
――ひかるは美人でかっこいいけれど、どうも口が悪い。
「あんた、もしかしてあたしが、そのまま借りたからだを返さないんじゃないかって、疑ってる?」
「えっ!? そ、そんなこと、ない、よ……」
光はもそもそと口ごもった。
100%ひかるを信じているとは言い切れない、自分が情けない。
「まあ、しょうがないよね。あたしとあんたは、知り合って間もないし。それで相手を完全に信用しろったって、無理な話よ」
けれどひかるは、たいして気にした様子もなく、あっさり言った。
「でも大丈夫。そのからだは、やっぱりあんたのものなんだから。あんたが、あたしにからだを渡したくないって強く思えば、あたしの意識なんかすぐに追い出されちゃうはずよ。ほら、このあいだだって、そうだったじゃない」
「あ、ああ……そうだね」
ふわりと、ひかるが光の目の前に立った。
光をまっすぐに見つめて、言う。
「あたしを信じるも信じないも、あんたの自由。でも、できるなら、今はあたしのこと、信じてほしいな」
「ひかる……」
信じるも信じないも、ひかるを受け入れるも受け入れないも、光の自由。光自身が決めること。
なんだか、とても大きな決断を任されたような気がする。
肩の上をぎゅっと強く抑えつけられるような、それでいて胸の奥からなにかが音をたててわきあがってくるような、身体中が急に大きくふくれあがるような、そんな不思議な感覚だった。
「うん、わかった。ぼく、ひかるを信じるよ」
ひかるをまっすぐに見つめ、光は言った。
「光」
ひかるも、にこっと笑う。
それから二人は、歩道橋を急いで駆け下りた。
入れかわる瞬間を誰かに見られたりしないよう、ビルのかげにかくれる。
「じゃ、ちょっとだけ、がまんしてね。すぐすむから」
このまえと同じく、ひかるがまるで水泳の飛び込みみたいに、両手をそろえて突き出した。
光は思わず、両目をぎゅっとつぶってしまった。
ひかるが、からだの中に入ってくる。
全身がぎゅうううっとねじられ、しぼられるみたいな、あの感覚が光をおそった。
からだじゅうがうらがえしにされ、大きなローラーでおしつぶされているみたいだ。
やがてその苦しさが、突然、ふっと消えた。
からだがふわっとうきあがる。もうなにも感じない。
そして光は、半透明の幽霊になっていた。
「光。大丈夫?」
からだのある光が――いや、ひかるが、光を見上げている。
「う、うん、平気……」
ぼそぼそと光は答えた。
その声も、自分の中から出ているのか、どこか空の遠くのほうから響いているのか、はっきりしない。
「なんか、ヘンなの……。暑いとか寒いとか、なんにも感じないや……」
「しょうがないよ。からだがないんだもの」
ひかるはリュックをおろし、中からスマートフォンを出した。
そのあいだにも、スマホは振動を続け、次々に短いメッセージを受信している。
「ふん」
スマホを操作したひかるは、その文面を見て、鼻先で笑った。
「まあ、なんつーワンパターン、ステレオタイプないやがらせ! 脳みそが貧弱な、なによりの証拠ね。ほかにことば知らないのかしら、この連中」
見たくない、と、光は思った。
でも、ちらっと目を向けた瞬間に、スマホの画面が見えてしまう。
見たこともない名前で送りつけられたそのメッセージは、画面いっぱいに「死ね死ね死ね……」と繰り返されていた。
「同じ嫌がらせだって、もうちょっとアタマひねれってのよね。ほんと、語彙がとぼしくて、知性のかけらもないわ。小学生のがきだから、しょうがないけどさ」
「ご、い……?」
「知ってる言葉の種類、量って意味。ボキャブラリイってことばなら、聞いたことある?」
「うん。――意味はよくわかんないけど」
「ボキャブラリイが豊富だって言えば、いろんなことばを知ってて、意味も正しく使いこなせるって意味になるのよ。あたしが小六のころは、もうちょっとボキャブラリイが豊富だったわよ」
なんだかちょっと奇妙だった。
見下ろしている姿はたしかに井上光、小学六年の男の子なのに、話している言葉はまるっきり若い女性――大人の女性のものだ。
ひかるは慣れた手つきで、おかしなメッセージを送りつけてくる発信者を次々にブロックしていく。
「光。学校の電話番号、このスマホに入ってる?」
「え? うん。明京小学校で登録してある」
「め、い、きょ……ああ、あったあった」
そして、ひかるはいきなり、学校に電話をかけた。
「もしもし。六年B組の井上光の母ですが。相沢先生はいらっしゃいますでしょうか」
「ちょっと、ひかる。なにしてんの――」
おどろく光に、ひかるはだまってろ、と軽く手をふる。
「あ、相沢先生ですか? おはようございます。井上光の母です。うちの子がいつもお世話になっております――」
知らん顔して、ひかるは話し続けた。
声はたしかに光のものだが、ちょっと高い裏声になり、そのしゃべり方は完全に大人の女性だ。
こんな話し方で「井上光の母です」なんて名乗られたら、誰も疑わないだろう。
「実はゆうべ、うちの子が歯が痛いって言い出しまして。ええ、虫歯みたいなんですよ。それで、歯医者さんに連れていってから、登校させますので、今日はちょっと遅刻させてください」
――虫歯? 歯医者? ひかるはいったいなにを言い出したんだろう?
「はい。歯医者さんがどれほど混んでるか、わかりませんから……。でも、午前中にはちゃんと学校に到着するようにさせますので。はい。よろしくお願いいたします」
ていねいにあいさつして、ひかるは電話を切った。
「さーてと、これで時間の余裕ができたわ。ちょっと準備があるから、お店に寄るよ。あんたのお小遣い、貸してね」
「ええっ!? な、なにすんの、ひかる!?」
「まあ、だまって見てなさい。たいしたモンは買わないから、心配いらないって」
ひかるは光を見上げ、にやっと笑った。
それはあの、見ているだけでぞくぞくしてくるくらい、自信にあふれたひかるの笑顔だった。
光が――いや、ひかるが学校に着いたのは、三時間めと四時間めのあいだの休み時間だった。
「ひかる、急がないと。四時間めは体育なんだよ。ジャージに着替えなきゃ」
光は、今朝までのひかると同じく、ひかるのななめうしろにふわふわ浮かんでいた。
ずっと自分のうしろ姿を見下ろしているのは、なんだかとっても妙な気分だった。
「更衣室とか、あんの?」
「女子にはね。去年、使ってない教室を更衣室に変えたんだ。小学校高学年にもなって、男子と女子が同じ部屋で着替えるのはおかしいって、PTAの誰かが言い出したんだってさ」
森本たちによって、その更衣室に閉じこめられたことがあることは、光はだまっていた。
「ふうん」
ひかるはたいして興味もなさそうに、うなずいた。
「まさか、ひかる。女子更衣室で着替えるつもり!?」
「ばかなこと言ってんじゃないわよ。ちゃんと小六男子、井上光のふりをしてやるから、安心しなさいって」
教室のドアに手をかけて、ひかるはにやっと笑った。
「まあ、だまって見てなさい。絶対、ばれやしないから」
そしてひかるは、六年B組のドアを開けた。
休み時間でさわがしかった教室が、一瞬、時間が止まったみたいに静まり返る。
クラスにいた男子全員が、いっせいに光を――いや、ひかるを見た。
その、目。
あざけりと悪意に満ちた目。
クラスメイト、いや、同じ人間を見ている目じゃない。
あれは、なにか人間以外のもの――こわれかけたおんぼろのおもちゃ、あるいはもう殺すしかない、ハエ取り紙にひっかかったハエとか、ゴキブリとか、そういうものを見る、目だ。
光は、この目が怖かった。
そして、どうしても納得できなかった。
ぼくだって同じ小学生、同じ人間なのに、どうしてぼくだけが、こんな目で見られなくちゃいけないんだろう、と。
どんなに考えても、その理由がわからない。
わからないから、よけいに怖い。
みんな、にやにやと光を馬鹿にして笑いながら、ひかるをじっとながめている。
けれどひかるは、そんな笑いも、クラスメイトたちの視線も、まったく気にしなかった。
まるで教室に誰もいないみたいに、まっすぐ前を見て、自分の――光の席へ近づいていく。
そこには、森本たちがいた。
彼らの手には、絵の具のチューブがにぎられていた。
森本たちは、光が教室に置いてあった図工用の絵の具を、ひとつ残らず机の上にしぼり出していたのだ。
光の机は絵の具でどろどろのぐちゃぐちゃ、もとの木目なんて、まったく見えなくなっていた。
――ひどい。
光は宙に浮いたまま、幽霊をとおりこして、氷のかたまりかなにかになってしまいそうな気がした。
あの汚れを落とすの、いったいどうしたらいいんだろう。
ぼくの絵の具だって、みんななくなっちゃった。これから図工の時間、ぼく、どうすればいいんだよ。
森本も金子も水沢も、絵の具をほうりだすことも忘れていた。
遅刻すると連絡のあった光が、こんなに早く学校に来るなんて、思っていなかったのだろう。もしかしたら、光がこのまま、学校を休むと思っていたのかもしれない。
悪事の現場を見られたことで、森本たちは一瞬、しまった、という顔をした。
だがすぐに、にやにやとヒカルを馬鹿にした笑いを浮かべる。
彼らも知っているのだ。
先生たちも自分たちの味方であり、光がなにを言おうとも、自分たちが誰からも叱られない、ということを。
――ほら、見ろよ、ひかる。いくらひかるがかっこいいこと言ったって、やっぱりなにもできないじゃないか。
光は目をつぶった。
たとえ、からだを動かしているのが自分じゃないとわかっていても、これ以上、自分がいじめられているところなんか、見たくない。
けれど。
「そっかあ。おまえ、ほんとにいっしょうけんめいだなあ、森本ぉ!」
ひかるが言った。
「……え?」
明るく、よく響くその声。
光は思わず目をあけた。
目の前で光が、いや、ひかるが、にっこりと笑っていた。自信に満ちて力強く、少しも怖れずに。
「わかってるよ、森本。おまえ、オレがきらいなんだろ? オレに、爪のアカくらいでも好かれちゃ困ると思って、いっしょうけんめいオレをいじめてんだよな?」
ひかるはずんずん森本に近づいていった。
「安心しろ。オレも、おまえが大っきらいだよ」
「えっ!?」
光はあわてた。
「な、なに言ってんだよ、ひかる! そんなこと言ったら、ますますいじめられちゃうじゃんか!」
けれどひかるは、幽霊になった光の言うことなんて、まるで聞いていなかった。
森本の目の前につめ寄り、にたァッと笑う。
それは、上から見ている光でさえ、ぞおッと背すじが寒くなるような、冷たく、意地の悪い笑い方だった。
「心配すんな。オレは一生、おまえを許さねえよ。大人になっても、ずっとずっとおまえを憎んで、恨み続けてやるからな」
「な……っ。なに言ってんだ、てめえ……」
「オレは死ぬまで忘れねえぞ。おまえが、一対一じゃケンカもできねえ、ひきょう者の、人間のクズだってことをな!!」
クラスメイトたちを見回し、ひかるはどなった。
「おまえら全員、おんなじだ! キライなヤツに面と向かってキライって言う勇気もねえ、かげでこそこそいやがらせのメッセージ送るくらいしかできねえ、ひきょう者! てめえらがどんなに忘れようとしたって、オレは一生覚えてるぞ! てめえらがそういう臆病者、ウジ虫みてえなヤツらだってな!!」
「だ、だから……だから、なんだよっ!」
森本がどなり返した。
「てめえがオレらを恨んでたからって、なんだってんだよ! てめえひとりがバカみてーにわめいたからって、オレらが、てめえのことなんかおぼえてるわけねえだろ!」
「ほんとに、そうか?」
ひかるはまた、にたあっと、あのおそろしい、残酷な笑いを浮かべた。
「おまえら、本当に平気か? 一生、誰かに心底憎まれてんだぞ。大学行こうが、大人になって結婚しようが、ずっと、ずうーっと、誰かに憎まれて、恨まれ続けてんだぜ? おっかなくないか?」
まわりの生徒たちの顔を、ひとりひとりたしかめるように、ひかるは見回した。
「オレのこと、本当に忘れられるか? オレは顔もわかんねえ、SNSの文字だけの相手じゃねえ。こうしておまえらの前にちゃんと立ってる、生きた人間なんだ。その人間に、自分と同じ人間に、恨まれても憎まれても平気で生きていけるほど、おまえらは本当に強いのか? 自分ひとりじゃ誰かをいじめることもできねえくせに!」
――な、な、なに言ってんだよ、ひかる!
光はあわてて、自分のからだに飛びついた。そのからだを動かしている、ひかるに。
「やめてよ、ひかる! なんでわざわざ、みんなにきらわれるようなことばっか、言うんだよ!」
けれどひかるは、光の必死の声も、きれいさっぱり無視した。
光はなにもできない。
どついたりけとばしたり、最悪の実力行使に出ようとしても、光のパンチやキックは、すかッ、すかッと、からだをすり抜けてしまう。
――ああ、そうだ。ぼく、今、幽霊なんだ。
魂だけの、死んだも同じの存在。だから、なんにもできないんだ……!!
「な……、なに言ってんだ、てめえ。バカじゃねえの?」
森本が、ひかるに言った。その口元がひくひくゆがんでいる。
クラス中が異様な空気に包まれていた。まるで見えない火花が、バチバチと無数にはぜているみたいだ。
とても、怖い。
空気のように透けて、誰にもその存在を認識されていない光でさえ、とても怖かった。
もう、おしまいだ。ひかるは――光のからだは、ぼこぼこにされるだろう。クラス男子18人全員に、よってたかって殴られる。
今度こそ、ケガじゃすまないかもしれない。いつも来るメッセージのとおり、本当に殺されるかもしれない。
――ぼくのからだが、死ぬ。殺される。ぼくは本当に、幽霊になっちゃうんだ……!
けれど。
「こ……、こいつ、アタマおかしいよ。ぜってー、フツーじゃねえ」
誰かが、おびえた声で言った。
光をかこむ輪の、うしろのほう。
そこで声をあげたのは、クラスの中でもあまり目立たない生徒だった。
「木島……」
光は思わず、そいつの名前を呼んだ。
――木島。なに、こわがってんの、おまえ?
木島は、怖がっていた。
目を伏せて、おどおどびくびくして、ネズミみたいだ。
それは、光のことを見て見ぬふりを続ける相沢先生の表情に、そっくりだった。
「こんなヤツの相手することなんか、ねえよ。無視しようぜ、無視。な? それよか、みんな、早く校庭に出よう。なっ!?」
まるで助けを求めるように、木島はクラスメイトたちを見回した。
「あ、ああ……。ああ、そうだよな」
「こんなヘンなヤツなんか、ほっとこうぜ。オレらには関係ねーよ」
「森本。おまえももう、井上なんかにかまうなよ。あんまりそいつの近くにいると、おまえも井上菌に感染して、アタマおかしくなんぞ!」
クラスメイトたちは、ジャージに着替えおわっていた者から先に、ばたばたと教室を飛び出していった。お化け屋敷から逃げ出すように。
「ふ、ふんっ!」
森本もえらそうにあごをあげて、ひかるを見下ろそうとした。が、真正面からにらみ返すひかるに、ひどく落ち着かない様子を見せる。
「ば、ばーか! 死ね! 死ね、死ね、死ねっ!」
同じことばをわめきながら、森本も教室を逃げ出す。
口から白い泡を飛ばしながら、たったひとつのことばをわめき続けるその様子は、まるで、ほかのことばがなにも言えなくなってしまった、こわれかけのロボットみたいだった。
「あ、も、森本くん!」
金子や水沢、子分たちも、あわててそのあとを追いかけた。
やがて教室には、二人のヒカル以外、誰もいなくなった。
「な……、なんで? なんであいつら、ぼくに――いや、ひかるに、なにもしなかったんだ?」
光は、ぼそっとつぶやいた。
「怖かったからよ」
ひかるが答える。
宙に浮いた光を見上げ、ひかるはにこっと笑ってみせた。
「あいつら、怖かったんだよ。あたしに、憎んでやる、恨んでやるって言われたことがね」
「そんな……。どうして? 1対18だよ? 怖いわけないじゃん」
「怖いのよ、それでも。だって、あいつら、誰ひとりとして、面と向かって『おまえがきらいだ、おまえを一生憎んでやる』なんて言われたこと、ないんだから」
説明しながら、ひかるは絵の具で汚された机を、よっこらしょ、とかかえ上げた。
「この机、もう使い物になんないからさ。予備の机ととっかえちゃおうよ。どっかに空き教室とか、ない?」
「使ってない机なら、階段の下に少しつんであるよ」
光のことばにしたがって、ひかるは汚い机をかかえて教室を出た。
服に絵の具がつかないように気をつけながら、机を持って階段を下りていく。
「ねえ、光。あんただってさ、人から嫌われるのは、つらいでしょ?」
「え? うん、そりゃあ……」
いじめられて、なによりつらいのは、クラス全員から、先生もふくめた学校の全員からきらわれていると感じることだ。
そこまで他人からきらわれる自分は、生きている価値なんかないと、本気で思えてしまう。
「みんな、ふつうはほかの人に、『あんたがきらい』なんて言わないよね。心の中では、どんなにそいつのことをきらってて、陰じゃさんざん悪口言い放題でもさ、本人の前でだけは、絶対『キライ』とは言わないでしょ?」
「うん――」
「だから、真正面から『てめえがだいきらいだ』ってはっきり宣言されると、ほんとに怖くなっちゃうのよ。ふつうはしないことをするくらいだから、こいつ、いったいどこまでおれのことを嫌い抜いてるんだろう、おれは、こいつにどんだけ激しく憎まれてるんだろうって。みんな、他人から嫌われた経験が、ないからね」
――ひとからきらわれた、経験?
ひかるの言っていることは、光にはよく意味がわからない。
「誰かに嫌われるのって、やっぱりいやなことだよね。傷つくよね。でも人間は、世界中の人から好かれるはずなんかない。誰か仲のいい相手がいれば、たいがい同じ数の相手から嫌われてるもんなのよ。それもしょうがない、そういうもんだってあきらめて、覚悟して、生きていくしかないの。きらいなヤツに会っちゃったら、『ああ、いやなヤツに会っちゃったなあ』って、どっちも嫌な思いして、どっちも傷ついて、それでもがまんしてね」
わかる? と、ひかるは光を見上げた。
「う、うん。なんとなく……」
たぶん大人は、みんな、そういうふうに生きているんだろう。光はそう思う。
「でも、あんたをいじめてるあの連中は、それががまんできないの。他人から傷つけられることが、怖くて怖くて、どうしようもないんだよ」
傷つけられるのが怖いから、先に相手を傷つける。傷つけられないように、まわりに同調する。
たとえそれが悪いことだとわかっていても、まわりと同じことをするしかない。自分ひとりが違うことをすると、みんなから攻撃されてしまうから。
それが、光がいじめられていた、本当の理由だった。
「だから、あいつらを思いきり傷つけてやったの。集団にならなきゃなんにもできないひきょう者、オレはおまえらが大っきらいだって、宣言してね。あいつらはなにも言い返せない。だって、自分がそういうひきょうな弱虫だって、自分自身がいちばん良く知ってるんだものね」
ひかるは、汚れた机を、階段下の使われていない机や椅子の中にまぎれこませ、別の机をかかえあげた。
「さーて、あたしも急いで着替えなくちゃ。光、体操着はどこ?」
「リュックの中だよ」
机を持って、誰もいない教室にもどり、ひかるはさっさとジャージに着替えた。
「体育の授業にも、出るつもり?」
「当然!」
四時間めの始まりを告げるチャイムが鳴る。
ひかるはなんだかとてもうれしそうに、教室を出た。
「なんか……すげえ楽しそうだね、ひかる」
「まあね。体育の授業なんて、ひさしぶりだもん! 大人になるとさ、思いっきりからだ動かしてあばれることなんか、なくなっちゃうからね」
にこにこと楽しそうな笑顔を浮かべているのは、井上光の顔、からだだ。
でもその表情は、ひかるのものなのだ。
二人が、昇降口に向かって階段を下りようとした時。
一人の女の子が、階段をのぼってきた。
「あ、井上」
女の子は、光の顔を見ると、ひどく怒ったような表情を見せた。
「あんた、早退しないで、体育に出る気?」
にらまれて、ひかるは一瞬、返事に困ったようだった。ちらっと光を見上げ、口の動きだけで小さく「誰?」ときいてくる。
「高倉。同じクラスの子」
光も小さな声で答えた。――たかくら、なに、だっけ? 下の名前までは覚えていない。
高倉はひかるとすれちがうように、階段をのぼってきた。
そして、
「井上。あんた、やりすぎだよ」
ぶっきらぼうに、高倉は言った。
「さっき、あんたが教室でどなってたの、あたしも聞いちゃったの。あんなことひどい言ったら、あんた、ますますいじめられるじゃん。どうしてあんなこと言ったんだよ!」
「高倉……」
「校庭行くの、やめな。今、森本たち全員で、あんたをどうやっていじめるか、話し合ってるよ。あんた、このまま家に帰んなよ!」
「オレはなんにも悪いことはしてない」
ひかるははっきりと言い切った。
「オレはただ、ほんとのことを言っただけだ。あいつらがきらいだって。きらいだからてめえらを殴るとも、いじめられた復讐をしてやるとも、言ってない」
「それは――そうだけど。でも、おまえがきらいだなんて、言ってどうなるんだよ! たとえきらいでも、いじめられないためには、みんなと仲良くやってくしかないでしょ!?」
「あいつらと仲良くなって、そんで今度はオレも、あいつらといっしょに別の誰かをいじめてろって言うのか?」
ひかるの冷たい言い方に、高倉はもうなにも言えなくなってしまった。
「ち……ちょっと、ひかる! そんな言い方するなよ! 高倉がかわいそうじゃんか!」
光は大声で言った。
どうせひかるは、さっきと同じく全然聞いてくれないだろうけれど、それでもだまっていられない。
ひかるはちらっと、光を見上げた。
そして、ちょっとあきれたような顔をして見せる。
でも、それ以上、高倉にひどいことを言うのは、やめてくれた。
ひかるはだまって高倉の横をとおりぬけ、階段をおりていこうとした。
「井上……!」
「おまえが気ぃ使ってくれてんのは、わかってる。サンキュ。でもさ、オレと口きいてんのがばれたら、今度はおまえがいじめられんじゃねえの?」
「それは……。あんたがだまってたら、バレないでしょ」
まあね、と、ひかるは小さく笑った。
「おまえは、校庭行かねえの?」
「あたしは――今日、体育休み。外、風が強いし、見学じゃなくて、教室で自習してていいって、先生が言ったから」
「ふうん」
それ以上はなにも聞かず、ひかるはだまって階段を下りはじめた。
高倉も、ぱっとひかるに背中を向けて、まるで逃げるように教室へ行ってしまった。
「あ、高倉!」
光は思わず、高倉を追いかけようとした。
「むだだってば。あんたの声は、あの子には聞こえないよ」
階段の下から、ひかるが小さな声で言った。
「あ……。そうか――」
光はため息をついた。
「あんた、ほんとにお人好しだね」
ため息をつくように笑って、ひかるが言った。
「あの子だって、あんたのいじめに加わってたんでしょ。なんでそんな子に、気ぃ使ってあげる必要があるの?」
「それは、そうだけど……。でもさっきは、高倉、ぼくのために、あんなこと言ってくれたんだしさ」
「あんまりいいアイディアとは思えないけどね。あれじゃ、いじめられないためには不登校になるしかないって、言ってるようなもんじゃない。緊急避難としては、その方法もアリだけどさ。逃げてるだけじゃ、問題は解決しないわ。家に引きこもっていれば、いじめられることはないけど、今度は、自分は逃げたんだって負い目をしょいこむことになるんだもの。自分の負い目と戦うより、他人と戦うほうがずっとかんたんよ」
でも、高倉に言えることは、それだけだったにちがいない。
高倉だって、いじめられるのは怖いはずだ。
だから、みんなといっしょにいる時に、光に声をかけたことは一度もない。森本たちがどんなにひどいいじめをしていても、だまって、なにも見ないふりをしていた。ほかのクラスメイトや、相沢先生と同じように。
それでも、
「ぼくに言ったことが、高倉にできるせいいっぱいだったんだと思う。ぼく、高倉のその気持ちは、認めてあげたいんだ」
「あんたって……」
半分あきれたように、それでもなんだかうれしそうに、ひかるは笑った。
ちょっと肩をすくめ、ふうっとため息をつく。
そのしぐさは、とてもおとなっぽくて、かっこ良かった。もっともからだは、光のものなのだが。
――なんだろう。ひかる、ぼくになにを言いたいんだろ?
ぼくが底抜けのお人好しだってこと、ひかるにとっては、悪いことじゃなかったんだろうか?
そう思うと、光もなんだかうれしい。
誰かに――ひかるに、自分は悪い人間じゃないと思ってもらえることが、うれしかった。
けれどひかるは、それ以上はなにも言わなかった。
「さ、行こう! 授業に遅れるよ」
「あ、待ってよ、ひかる!」
ひかるがいきおい良く走りだす。
光も、あわててそのあとについていくしかなかった。
今日の体育は、ミニサッカーだった。
男女それぞれが赤と白の二つにわかれ、試合をする。
背の順で並び、交互に赤チーム白チームに分かれたため、今度は光も、理科の実験班のように仲間はずれにされることはなかった。――うわべだけは。
「じゃあ、始めるよー! ちょっと寒いけど、みんな、元気良くねー!」
相沢先生の合図で、サッカーが始まった。
光も、みんなと同じくコートの中に立つ。
――いや、ひかるだ。からだは12才の井上光だが、それを動かす魂は、25才の成瀬ひかるなのだ。
光はその姿を、宙にただよいながら、ただ眺めているしかなかった。
森本や福田が、ちらちらとひかるを見ている。
ほかの男子もみんな、薄笑いを浮かべて、なにかを確かめ合うように、おたがいうなずいたり、こっそりひかるを指さしたりしている。
「だいじょうぶなの、ひかる!?」
すうっとひかるのそばに近づいて、光は言った。
森本たちは、絶対なにかをたくらんでる。
授業中、先生の見ている前で、殴ったりけったりはしないだろう。
でも、そのほかのこと、けがをするような暴力でなければ、なにをしたって平気だと思っているはずだ。
「ねえ、ぼくと入れかわろう。ぼくなら、もう慣れてるから。なにされたって、がまんできるよ」
ひかるはちらっと光を見上げ、そして小さく首を横にふった。まわりの人間に見つからないよう、ほんの少しだけ。
そして、ボールを追いかけて、走りだす。
「ひかる――!」
森本たちのいじめは、とても単純だった。
ひかるにいっさい、ボールを回さなかったのだ。
ひかると同じ赤チームのメンバーも、光には絶対パスを出さない。まるでひかるなんかいない、見えない、というように。
ひかるがボールを取りに行こうとすると、みんな、あわてて大きくボールを蹴る。その先にいるのが、敵の白チームだって、関係ない
。
これでは、ひかる対残りの男子全員で、試合をしているみたいだ。
しかもみんな、ひかるがボールにさわれないよう、パスを回し合うだけで、ろくにシュートもしない。まるっきりサッカーになっていない。
「なるほどね」
ひかるが小さくつぶやくのが、光にだけは聞こえた。
そして、いきなりボールに向かって猛ダッシュした。
「あっ、来やがった!」
ボールがぽーんと大きく蹴られる。
それを追って、ひかるは走った。
そして、叫ぶ。パスを受けようとした木島に向かって。
「おら、どけよ! オレにさわられたら、井上菌に感染しちまうんだろ!?」
「えっ!?」
木島はびくっとふるえた。
「おら、どけどけどけっ! てめえら、オレにさわったら、汚染されるぞ! 汚染されたら、今度はてめえらがバイキンだぞーっ!!」
ひかるの前にいた男子たちが、反射的に、ぱっとよけた。
それは、光自身、何度も体験してきたことだった。
井上光にさわるな。あいつはバイキンだ。みんながそう言い合い、光の前からわざと、ぱっと飛びのく。
万が一光にさわってしまったら、さわったやつまで、バイキンだバイキンだとはやしたてられ、みんなからさけられてしまう。
木島もよけた。
ボールは、誰もいなくなったスペースを、てんてんと転がっていく。
ひかるはそこへ走り込んだ。
Jリーガーみたいにかっこいいポーズをキメて、ボールを足で押さえる。
そしてゆうゆうと、クラス全員を見回した。
でも、誰もボールをとりにいけない。
だって、井上光にさわってはいけない。それが、六年B組のルールだから。
軽々とドリブルしながら、ひかるは走りだした。
まるで、たったひとりでボールを蹴って遊んでいるみたいだ。
ほかの生徒は、グラウンドに突っ立ったまま、それをだまって見ているしかなかった。
「……な、なにしてるの、みんな?」
相沢先生が、おろおろと声をかける。
誰にもとめられることなく、ひかるは一気にゴール前まで走った。
シュートするために、足を大きくふりあげる。
ゴールキーパーが身構えた。――キーパーは、金子だ。
その時、ひかるはまた叫んだ。
「オレがさわったボールだぞ! おまえ、さわってもいいのかよ!?」
「――えっ!?」
金子は一瞬、どうしていいかわからない、という顔をした。助けを求めるように、森本や水沢を見る。
けれど彼らにも、どうしていいかわからなかったに違いない。
ひかるは嫌味なくらいゆっくりと、ボールをゴールに蹴りこんだ。
キーパーは一歩も動けなかった。
ゴールに転がったボールを、ひかるは自分で拾い、また蹴り始めた。今度は反対のゴールに向かって。
ほかの生徒は、誰も、何もしない。
サッカーは、めちゃくちゃになった。
ボールを蹴って走っているのは、ひかるひとりきりだ。
ほかの生徒たちは、ただ、立っているだけだ。冷たい風の吹く校庭で、まるで小さな並木みたいに立ち尽くし、その場から一歩も動かない。
ひかるがそばを走り抜けると、みんな、まるで見てはいけないものを見たように、あわてて目を伏せる。そしてまわりのクラスメイトたちに、ちらちらと視線を向ける。自分はどうしたらいい? とたずねるみたいに。
でもそれに対する答は、どこからもないのだ。
みんな、ただじっと立っているしかなかった。
「ね、ねえ、みんな、どうしちゃったのかな? どうしてサッカーしないの?」
相沢先生はいっしょうけんめい、みんなに声をかけた。
でも、それに対する返事もない。
さすがに、
「井上光がさわったボールなんか、汚くてさわれません」
とは、先生には言えないのだろう。
どうしようもなくて、相沢先生はとうとう、ひかるに頼み込んだ。
「ねえ、井上くん。ほかのみんなにも、ボールをパスしてくれないかしら? みんなにも、サッカーさせてあげてちょうだい」
――先生が、頼み事!
井上光に、
「みんなにもサッカーをさせてあげてちょうだい」
だって!?
数人の小さなグループでやった理科の実験だって、ぼくは、なにもできなかったのに!
「はい、わかりました。先生」
ひかるは素直にうなずいた。
そして、ぽーんと大きくボールを蹴る。
その先には、森本がいた。
森本はまったく動かなかった。まるで棒っきれみたいに、硬直したままだった。
ボールは、森本の横をころころところがっていった。
ひかるは相沢先生のほうにふりかえった。
そして、「ね?」というように、軽く肩をすくめてみせる。
先生も、もうなにも言えなかった。
4時間めが終わるまで、ひかるはたったひとりで、楽しそうにボールを蹴り続けた。
ほかの生徒たちは、ただそれを、うらめしそうにながめていることしかできなかった。
やがてチャイムが鳴りひびく。
六年B組にとって、おそらく今まででもっとも長くつらい四時間めが、ようやく終わった。
「すごいや、すごいや、ひかる!」
光は思いきり声をはりあげた。どうせひかるにしか聞こえない。
「あの時の森本の顔、見た!? すっげー顔してたよ! 真っ赤になって、口とか鼻とか、ぴくぴくふるえちゃってさ!」
のろのろと校庭から引き上げるクラスメイトたち。
みんな、吹きさらしの校庭にじっと立っていたせいで、ひどく寒そうだ。鼻水をたらしているやつもいる。
「ぼくじゃあんなこと、考えつきもしなかった。今までずっと、ただ仲間はずれにされるのが、つらくて、悔しくてさ――」
「まだまだ、こんなもんじゃないからね!」
ひかるは走りながら、小さな声で答えた。
ふるえながら戻ってくるクラスメイトたちより先に、元気いっぱい、昇降口へ駆け込む。
みんなは、ひかるを追いかける元気もないらしい。
「光。給食はどこに届くの?」
「え? でもぼく、今週は当番じゃないよ」
「いいから、案内しなさいってば」
「どうすんのさ、ひかる? ぼく、給食当番のエプロンだって持ってないのに」
ひかるは、なにを言ったって聞いてくれなかった。
「こんにちわあ! 六年B組の給食、取りにきましたー!」
光に案内させて、ひかるは給食室に飛び込んだ。
「あー、はいはい。そこのワゴンよ」
給食のおばちゃんが、クラスごとに用意されたワゴンを指さした。
ワゴンには、主菜の大きななべや、フライなどの入った副菜の平たいなべ、パンがならんだ箱などがきちんと積まれている。
「あら。きみ、当番のエプロンはどうしたの?」
「ごめんなさい、忘れてきちゃいました!」
「しょうがないわね。今度からは忘れないようにね」
おばちゃんたちは、それ以上はなにも言わなかった。
さすがに、給食室のおばちゃんたちにまでは、六年B組のいじめのことは知られていないらしい。
給食室にはすでに、ほかのクラスの生徒たちも給食を取りにきている。かなりの混雑だ。
どこのクラスから何人の当番が来ているかなんて、よくわからない。
だから、ひかるがたったひとりでB組の給食を運び出しても、誰も気にしなかった。
今度は光も、ひかるがなにをしようとしているのか、すぐにわかった。
「ひかる、そこの廊下、曲がって。車椅子用のエレベーターがあるんだ。ほんとは使っちゃいけないけど、でもそのエレベーターを使えば、森本たちより早く教室に戻れるよ!」
「オッケー! あんたも察しがいいじゃん、光!」
重たいワゴンを押しながら、ひかるは全速力で走った。
エレベーターで急いで4階まで上がり、B組の教室に飛び込む。
光の思ったとおり、教室にはまだ誰も戻ってきていなかった。
女子はまだ更衣室にいるのだろう。
男子は、もしかしたら、昇降口かどこかに集まって、光へのしかえしを話し合っているのかもしれないが。
――でも、そんなのもう、怖くない!
ひかるが、主菜のシチューをつぎわけるおたまを持って、にっこりと笑う。
光もうなずいて、笑い返した。
ひかるがプラスチックのうつわに、あったかいクリームシチューをなみなみとよそった時、教室のドアが開いた。
まだジャージ姿の男子たちが、ぞろぞろと教室に入ってくる。
「遅いぞ、おまえら。せっかくの給食だってのに、なにやってんだよ」
おたまをしっかり握りしめて、ひかるはなべのそばでふんぞりかえった。
「て、てめえ……っ!」
「おまえらがあんまり遅いから、オレ、待ちきれなくて、給食運んできてやったぞ。ほら」
ひかるは、あんまり熱くない副菜のなべや、パンが並んだトレイを、ぽんぽんと軽くたたいた。
そして、わざとらしく、
「あっ、悪りい! オレ、なべにさわっちゃったよー!!」
「い、井上、てめえ――っ!」
「ごめんなあ。もうこれで、給食も井上菌に汚染されちゃったよなあ? おまえら、どうする?」
――どうするも、こうするも、ない。
井上菌に汚染されたものには、六年B組の生徒は、誰もさわってはいけないのだから。
いや、そんなルールにだって、抜け道はある。たとえば、
「井上光がさわったのは、なべとかおたまとか、食器だけだから、給食のパンやミルクなど、食べ物そのものは汚染されていない」
とかなんとか、へ理屈をこねることはできるはずだ。
だって森本たちは、光に暴力をふるう時は、汚染もへったくれも気にせずに、ばんばん光のからだにふれて、殴ったり蹴ったりしたのだから。
けれど、誰もそんな考えは思いつかないようだった。
思いついても、言えないのかもしれない。
「そんなみじめないいわけしてまで、給食が食いたいのか。こんな汚染された給食を!」
と、誰かが怒って言い出せば、今度は自分がいじめのターゲットにされてしまいかねない。
やがて、更衣室から女子たちも戻ってくる。
けれど彼女たちも、一歩教室に入るなり、その異様な空気に気がついた。みんなドアの近くにひとかたまりになって、自分の席にも戻れずに立ちつくす。
その中には、高倉の姿もあった。
おびえて落ち着かない様子の女子たちにまじって、高倉はひとり、妙にしらけたような顔をしていた。なんだか、こうなることがわかっていたような表情だ。
更衣室で、今日の体育の授業がどんなことになったか聞いて、給食ももしかしたら、と、予想していたのかもしれない。
「ま、とにかくよそってあげるよ。給食を汚染しちゃったおわびにさ、今日の給食は、みんなオレがくばってあげるから」
ほら、みんな席についたついた、と、ひかるは生徒たちに明るく声をかけた。
そして、生徒たちが着席するより早く、ぱっぱと給食トレイを机の上にのせていく。続いてパン、牛乳と駆け足でくばり、最後にトレイを押しながら、シチューと副菜のコロッケをくばった。
みんなはだまって、あったかくておいしそうな料理が、自分の目の前に置かれていくのを見つめているしかなかった。
やがてひかるが給食を配り終えるころには、相沢先生も教室に入ってきた。
「みんな……、なんか、静かね」
生徒たちは、全員がきちんと着席して、口も開かずに、ただじっと給食を見つめている。
「はい、先生」
ひかるは先生の分の給食もきちんとそろえて、先生の机にのせた。
「あ、ありがとう、井上くん。……井上くん、今日、給食当番だった?」
その質問に、ひかるは答えなかった。
相沢先生はすぐに、はっとなにかに気づいたようだった。そして、ひどく困ったような顔をして、目をそらす。
――そうか。先生、ぼくがみんなにむりやり給食当番をやらされてると思ったんだ。教室の掃除とか、ずっとぼくひとりがやらされてるから。
だから、相沢先生は、ひかるのことを叱れない。
先生の目から見れば、今も井上光はいじめの被害者なのだ。
「じゃあ、いただきましょう」
決まりどおり、あいさつをする。
けれど、スプーンとフォークを手にとったのは、ひかると相沢先生だけだった。
「みんな……? どうしたの?」
誰も、一口も食べようとしない。
ぎゅっとからだをこわばらせて、だんだん冷めていく給食を、見つめている。みんな、泣きそうな目をして、けんめいに空腹をがまんしている。
給食をおいしそうに食べているのは、ひかるだけだった。
――食べられないよな、みんな。
食べてしまったら、そいつは裏切り者だ。井上光の同類にされてしまう。
いいや、井上光がここまで強気で反撃に出てきたからには、その裏切り者が、今度はたったひとりのいじめのターゲットにされてしまうだろう。
いじめでなにがおもしろいかといえば、相手が絶対に反撃してこないとわかっていることだ。
どんなにそいつをいじめて、殴っても、殴り返されない。自分は全然痛くない。
だから、ひとりの人間をいつまでも殴り続けていられるのだ。
だが今、井上光は、殴り返してきた。
たったひとりで、37人のクラスメイトを相手に、いや、学校中を相手に。
――怖いんだ、みんな。
今まで自分がやってきたこと、それに対して、しかえしされることが、今、怖くて怖くてしかたがないんだ。
教室の中をふわふわただよいながら、光は、クラスメイトひとりひとりの顔を、じっと見つめていった。
幽霊みたいな存在になり、いじめの当事者の立場をはなれて、ようやく光は、クラスメイト全員の顔を、はっきりと見ることができた。
それまではみんな、「いじめの集団」というのっぺらぼうのかたまりみたいに思えて、ひとりひとりの顔なんて、ほとんどわからなくなっていたのだ。
でもこうして空中から見下ろすと、みんなひとりひとり、違った顔、違った姿をしているのがよくわかる。
「いじめの集団」なんて化け物みたいなひとかたまりじゃない。みんなそれぞれ、ひとりの人間だ。
――みんな、怖いんだ。いじめた相手に復讐されることが、今度は自分がいじめのターゲットにされることが。
怖くて怖くて、なにをどうしていいかもわからなくて。
なんだか、とてもかわいそうだ。
森本ですら、光はかわいそうだと思った。
もちろん、森本たちが自分になにをしたか、忘れることはできない。
ひかるが言わなくとも、きっと大人になっても、彼らのことは大きらいなままだろう。
でも、怒りや悔しさで顔を真っ赤にした森本は、今にも泣きそうに見えた。まるで森本のほうが、誰かにひどくいじめられているみたいだ。
森本たちは今、自分たちで決めたいじめのルールに、自分たちががんじがらめにしばられて、逃げ出せなくなっている。
――逃げることができないんだ。
このクラスにいるかぎり、誰も、いじめから逃げられない。いじめのリーダーである森本も、相沢先生も。
やがて、昼休み終了五分前のチャイムが鳴った。
「え? もうそんな時間なんだ」
光は、黒板の上にかけられた時計を見た。
幽霊になったせいだろう、光はまったくおなかが空かない。
そのため、時間の感覚もなんだかあいまいになっているみたいだ。
「えっと、みんな……。給食、片づけてもいいかな? いいよね? しょうがないもの、五時間めが始まっちゃうし……」
ぼそぼそと、いいわけみたいに相沢先生が言った。
みんな、しかたなく、一口も食べていない給食を片づけ始める。
結局、給食を食べられたのは、生徒ではひかるひとりきりだった。
五時間め、六時間めも、B組の教室はしんと静まり返ったままだった。
算数の授業で、相沢先生が「この問題がわかる人?」と言っても、答えて手をあげる生徒はひとりもいない。
みんな、先生なんか見ていない。となり、ななめ、まわりのクラスメイトの様子ばかり気にしている。
誰かがしゃしゃり出て、目立とうとしてないか。反対に誰かが自分のことを、ひとりだけ目立ちやがって、と、にらんでいないか。そればかりをたしかめているのだ。
空気がはりつめて、なんだか、今にもなにかが爆発しそうなふんいきだ。すごく、居心地が悪い。
幽霊になった光でさえ、そう感じた。
クラスメイトたちも、教科書の上に顔を伏せて、早く終われ、早く終われ、と必死で念じているみたいだった。
6時間めの終わりを告げるチャイムが鳴った時、生徒たちも、そして先生も、ひどく疲れ切ったように、大きくためいきをついた。
長かった一日が、めちゃくちゃな一日が、ようやく終わる。
掃除当番が、だまって教室の掃除を始めた。今日は、光ひとりにおしつける気はないらしい。
――そうだよな。そんなことしたら、ひかるにどんなしかえしされるか、わかんないし。
当番ではない生徒たちは、あわてて教室を出ていった。まるで逃げるみたいに。
森本たちも、いつものグループひとかたまりになって、教室を出ていこうとした。
井上光へのしかえしは後回し、今は光のいないところへ行って、少し冷静になってゆっくり方法を話し合おう、とでも決めたのかもしれない。
あるいは、井上光の顔さえ見えなければ、どんなひどいことだってできる、早くかくれて、またいじめを始めよう、と。
けれど。
「あ、そうだ、森本ぉ!」
ひかるがわざわざ、森本たちを呼び止めた。
「オレさあ、今日、うっかりスマホこわしちゃったんだよなあ」
「えっ!?」
ひかるの手には、画面が割れた銀色のスマートフォンが握られていた。
「えっ、う、うそっ!?」
光もあせった。
あのスマホは、旧式の携帯電話では緊急連絡網のメッセージアプリがうまく動かないからと、夏休み前に買ってもらったばかりだ。
「あーあ、もったいねえことしちゃったなあ。こんなにすぐこわしちまったから、母さん、次のはなかなか買ってくれないだろうなあ。買ってもらえるのはたぶん、卒業して、中学に入学する、お祝いかな」
「い、井上、てめえ……っ」
「だから、いくらメッセージ送ってもらっても、オレ、いっさい受信できねえから」
ひかるははっきりと言い切った。
たしかに、いたずらメッセージを受信したくないなら、いちばん確実な方法は、携帯電話やスマホを持たないことだ。
「クラスの連絡網とかで知らせがあるんなら、オレん家に直接、電話かけてくれよな。でも、うちって、母子家庭だろ。女の人とこどもしかいない家だからさ。電話はいつも留守電状態なんだ。はっきり名前言わない電話にゃ、絶対出るなって、母さんに言われてんだよ。みんなも、オレん家に電話する時は、最初にしっかり自分の名前言ってくれよな」
こんなことを言われたら、家の電話に無言電話などのいやがらせもできない。
ひかるは軽々とリュックを肩にかついだ。
そしてひとり、悠々と教室を出ていった。
「ひかる! ひかる、ちょっと待ってよ!」
光はあわててそのあとを追った。
ひかるは急いで校舎を出て、走りだした。
学校の外、誰にも見られない場所でなければ、ふたりで落ち着いて話すことはできない。
今朝、ふたりが入れかわったビルの陰まで一気に走って、ひかるはようやく立ち止まった。
「あー、苦しい。でも、気持ちいいー! こんなにいっぱい走ったのなんて、何年ぶりかな!」
でも幽霊状態の光は、苦しくもなんともない。
「ひかる、ひかる! どうすんだよ、あのスマホ! お母さんからのメッセージもあのスマホで受け取ってたのに!」
「だいじょうぶだってば。ほら、よく見なさい」
ひかるは、さっきのこわれたスマホをポケットから取り出した。
――なにか、へんだ。
「あ、あれ……? なに、これ――」
「赤ちゃん用のおもちゃ。100均ショップとかでも、良く売ってるじゃない。それの、ペンギンやウサギのプリントシールをけずって、メタルカラーのサインペンで銀色に塗っただけ」
よく見れば、マジックの塗り残しやムラもわかる。
でも、半分手の中に握ってかくした状態で、一瞬だけぱっと見せられたら、これが100円ショップのおもちゃだなんて、誰も気づかないだろう。
「ほら。あんたのスマホはこっち」
ひかるはもうひとつ、スマートフォンを取り出した。
こっちは間違いなく、お母さんに買ってもらった、本物のスマホだ。
「すごいや、ひかる……」
思わず、光はつぶやいた。
「そっか。今朝、学校に行く前にお店に寄ってたのは、これのためだったんだね!?」
「そうよ。あんたのスマホがこわれたってことになったら、あいつらだって、こわれたスマホにメッセージ送り続けるような、ばかなまねはしないでしょ。でも、本物は絶対に見つけられちゃだめよ。もしうそだってバレたら――」
「うん! うん、わかってる! ひかる、ほんっとにすごいよー!!」
「たいしたことじゃないわよ、このくらい。それにまだ、最後の仕上げが残ってるしね」
「最後の仕上げ?」
そうよ、とうなずいて、ひかるはどこかに電話をかけた。
「あ、もしもし、お母さん? うん、ぼく、ヒカル。――ごめんね、仕事中に電話しちゃってさ」
――お母さんに電話? ひかる、いったいなにをする気だろう。
でも、光はもう、ひかるのやることにいちいち質問しようとはしなかった。
「今日、学校で連絡があってさ。明日、お弁当持ってかなくちゃいけないんだ。給食センターが断水なんだって」
もちろん、そんな話は学校でも全然出なかった。
でも、ひかるを信じていれば、だいじょうぶだ。絶対、うまくいく。
電話からお母さんの声が聞こえる。
「あらそう。じゃ、お弁当用のおかずも買って帰らなくちゃね。光、なにがいい?」
「ん? なんでもいいよ。お母さんにまかせる」
じゃあね、と、ひかるは電話を切った。
「ねえ光。学校を出たら、このからだ、あんたに返すって約束だったけどさ。家まで、あたしが動かしてもいい? 家についたら、ちゃんといれかわるから」
「ひかる――」
「思いっきり走るって、気持ちいいね。こんな気持ちよさ、あたし、ずっと忘れてた」
ひかるはうれしそうに、ちょっとはずかしそうに、笑ってみせた。
「もうちょっとだけ、走りたいんだ。いいでしょ?」
――走ることが、気持ちいい?
そんなこと、考えたこともなかった。
走ったり、歩道橋の階段を一段飛ばしに駆けあがったり、そんなこと、ちっとも特別なことじゃない。なにも考えなくても、からだが勝手に動くことだ。
でも。
「ひかる」
ひかるはちょっと不安そうに、光を見上げている。
――ひかるが、そんなに楽しいのなら。
ひかるは幽霊だ。ひかるには、もうからだがない。
だから、光にとっては当たり前のことでも、うれしくて楽しくてしかたがないのだろう。
「うん、いいよ」
光はうなずいた。
「家に帰るまでなら。そのかわり、寄り道しないでよ」
「わかった。約束する!」
言ったとたん、ひかるは走りだした。さっきよりもずっと早く、うれしそうに。
歩道橋の階段も、まるで背中に羽根がはえたみたいに、かるがると駆け上がっていく。
「あ、待ってよ、ひかる!」
光もふわふわしながら、あわててそのあとをおいかけた。
家に帰りつくと、約束どおり、ひかるは光にからだをあけわたした。
「……なんか、へんな感じ」
もとどおりになったからだをながめて、光はつぶやいた。
ほほをさわると、指先が冷たい。柱の角に足をぶつけると、とっても痛い。
そんな当たり前の感覚が、なんだかとても不思議な、初めて味わうようなものに思える。
なにもかもが新しくて、どきどきすることばかりのようだ。
幽霊になって、すべての感覚をうしなっていたのは、ほんの半日ほどのことだったのに。
――ひかるも、こんな感じだったのかな。
それをたずねようとすると、
「ああ、やっぱりちょっと疲れちゃったかな。あたし、少し寝る」
ひかるは宙に浮いたまま、くるっと光に背中を向けた。
「幽霊も疲れるの?」
「うん、まあね」
「あれ……ひかる? なんだか、少しからだが薄くなってない?」
「え、そう?」
半透明のひかるの姿。それが、朝よりももっと透けているように見える。
夕方になって、部屋の中が薄暗いせいだろうか。
ひかるは背中を向けたまま、なにも答えなかった。
「眠っちゃったの、ひかる?」
光はそれ以上、ひかるに話しかけるのをやめた。疲れているなら、そっとしておいたほうがいいと思ったのだ。
「宿題でもやろうかな」
机に向かい、算数のドリルを広げる。
部屋の中は、しんと静まりかえっていた。光がえんぴつで文字を書く、小さな音しか聞こえない。
ふりかえってたしかめなければ、ひかるがそこにいることも、光にはつたわってこない。
――ひかるの寝息が聞こえたらいいのにな。
光はふと、そんなことを思った。
やがて、夕方六時をすぎるころ、お母さんが帰ってきた。
「ただいま、光。遅くなってごめんね。すぐご飯にするから」
晩ご飯のおかずはサケのホイル焼きに野菜炒め、かぼちゃの煮物。光の大好物ばかり――というわけではなかった。どちらかというと、苦手なおかずばかりだ。
でも、
「おいしい」
かぼちゃの煮物を口に入れて、光は言った。
「これ、おいしいね、お母さん」
「え? ……どうしたの、光。あんた、煮物なんかあんまり食べなかったのに」
「うん、でも――今日、おなかすいてんのかな。なんか、すごくおいしいんだ」
ご飯も、おつけものも、おみそしるも。そうか、ぼく、毎日こんなおいしいご飯食べてたんだ、と思う。
「お母さんって、料理じょうずだよね」
「やあね。どうしたのよ、いきなり。おこづかいの値上げなら、だめよ」
「そんなんじゃないよ」
これも、ひかるが教えてくれたことなのだ。
幽霊になって、触覚も味覚も、からだじゅうのすべての感覚を一度なくしているから、ふたたび感じ取ったその感覚が、とても新鮮に、大切なものに思える。
――でも、それはきっと、ひかるにとっても同じじゃないだろうか?
本当に死んでしまったひかるだから、生きたからだで感じ取る感覚は、もっとすてきで、貴重なものに思えたんじゃないだろうか。
――だから、ひかる、あんなこと言ったんだ。もう少し、走りたいって……。
「明日のお弁当、なにがいい? おにぎり? それともサンドイッチ、つくろうか」
「え、ううん、いいよ。ふつうのご飯でさ。運動会や遠足じゃないんだもん」
「そう? でも、お母さんもはりきんなくちゃね。せっかく光にほめてもらったんだもの」
お母さんは光の顔を見つめ、にっこりと笑った。
「良かった。このごろ、光、なんだか元気がなかったから。お母さんも心配だったんだ。学校でなにかいやなことでもあったんじゃないかって。でも、やっと笑ってくれたね」
「お母さん……」
「ねえ光。なにか、つらいことがあったら、お母さんにはかくさないで。どんなことでも、お母さんに話してね。ふたりっきりの家族なんだから」
「うん」
――どうしよう。全部言ってしまおうか。学校のこと、いじめのこと。
光は迷った。
でも、いじめのことを全部お母さんにうちあけたら、ひかるのことも話さなくてはいけないだろう。
ひかるの姿は、お母さんには見えない。見えないものを、どうやって信じてもらったらいいだろう。
それに、ひかるは言っていた。まだ、最後の仕上げが残ってる、と。
ひかるには、まだ考えがあるのだ。
お母さんに話すのは、ひかるがすべての計画をやり終えてからでも、いい。
「お母さん。今はまだ、なにも言えないんだ」
まっすぐにお母さんを見て、光は言った。
「でも、言える時がきたら、必ず全部、お母さんに話すよ。だから、今はもうちょっと、待って」
「光……」
お母さんは一瞬、どうしようという顔をした。
けれどすぐに、光を見つめてうなずいた。
「わかった。あんたがそう言うなら、お母さんも、今はなにも聞かないよ」
「お母さん!」
「でも、いつか必ず、お母さんに話してね。これだけは忘れないで、光。どんなことがあったって、お母さんはあんたの味方。絶対に、あんたを守るからね」
うん、と、光はうなずいたつもりだった。けれどそれは、声にならなかった。
涙をがまんするだけで、せいいっぱいだった。
始まりは、夏休みの宿題。理科の自由研究だった。
「ぼく、昆虫採集したんだ。夏休みのほとんどを、九州のばあちゃん家ですごしたからさ。ばあちゃん家、わりと田舎のほうで、田んぼとか雑木林とかも残ってて、カブト虫とかセミとか、ふつうにつかまえられたんだよ」
それでも、たいした虫をつかまえたわけじゃない。
カブト虫が2、3匹に、あとはカナブンとかトンボとか、めずらしくもないものばかりだった。
「だけどさ、みんな、すっげーびっくりしてた。だって、カブト虫なんてふつう、デパートかペットショップで買ってくるモノだもん。それを、ぼくは自分でつかまえて、自分で標本にしたんだ。標本の作り方は、じいちゃんが教えてくれた。先生もほめてくれて――理科の自由研究じゃ、ぼくのがクラスで一番に選ばれたんだよ」
でもね、と、光はうつむいた。
朝の通学路、大勢の人たちとすれ違う。
人目を気にしながら、ぼそぼそと光はこれまでのことをひかるに説明していた。
言葉がとぎれても、ひかるはだまったままだった。
あいかわらず光のちょっとうしろあたりにふわふわ浮きながら、光がまた話し始めるのを待っていた。
「森本が、ぼくの昆虫標本は環境破壊だって、言い出してさ」
ただでさえ数が減っている昆虫を、わざとつかまえて、標本にするなんて、とんでもない。こいつは日本の自然を破壊してるんだ。森本は光を指さして、そう叫んだ。
「てめえみてーなヤツがいるから、日本の自然には生き物がいなくなっちまうんだよ!」
森本の言葉に、金子や福田など、子分たちがすぐに同調した。
「そうだそうだ! 井上は、環境破壊してるんだ!」
「てめえ、知らねえのか。こういう小さい虫だってな、自然の生態系の中で大事な役割をはたしてんだぞ! 理科の授業でちゃんとやったじゃねえかよ!!」
彼らは、光を環境破壊の悪魔だと決めつけた。
学校全体でリサイクルや街の環境美化にとりくんでいるのに、光が一人でそれらをすべてだめにしてしまう、と。
「はあ!? なによ、それ!? たった一匹二匹の昆虫つかまえただけで、自然破壊だあ!? そいつら、ノーミソ煮えてんじゃないの!?」
とうとうがまんできなくなったのか、ひかるが大きな声を張り上げた。
ストレートなひかるの言葉に、光も小さく笑ってしまった。
「ちがうよ。あいつら、ぼくがうらやましかったんだ」
「え?」
「ほら、ぼくん家、あんまり金持ちじゃないだろ。お小遣いの額とかも、少ないほうでさ。ゲームやマンガも、発売当日には買ってもらえないんだ。買ってもらっても、中古だったりしてさ。みんなより、いつもちょっと遅れてんだよ。……でもそのぼくが、『貧乏でかわいそうな井上』が、クラスん中の誰もやったことないようなことを、やったんだ。みんな、生きてる虫にさわったことだって、ほとんどないはずだし。森本は、それが許せなかったんだよ」
光が、いつまでも「貧乏でかわいそうな井上」でいれば、森本はきっと光をいじめたりはしなかったろう。
自分が見くだして憐れんでいた井上光が、自分にはできないことをやってみせた。それが、森本にはどうしてもがまんできなかったのだ。
「そして――あとは、きのう言ったとおり。何回か殴られたりモノを奪られたりしたあと、先生に相談したけど、森本の親が学校にどなりこんできて、反対にぼくが森本にあやまらされたんだ」
あの時の森本の顔を、光は一生忘れないだろう。
親のうしろにかくれながら、先生たちには見つからないよう、うれしそうに笑い、光に向かって歯を剥きだして見せた森本の顔を。
「あいつら、なんでぼくをいじめ始めたのかなんて、とっくに忘れてんじゃないかな。今はもう、ぼくを――誰かをいじめてんのが楽しくて楽しくて、しょうがないんだよ。やめられなくなっちゃったんだ」
たぶん光がいなくなっても、森本たちは誰かをいじめることをやめられないだろう。
クラスの中に次のターゲットを見つけ、そいつをいじめるにちがいない。
やがて光とひかるは、初めて出会ったあの歩道橋にさしかかった。
その時、リュックのポケットからヴーッ、ヴーッ、ヴーッとスマホのバイブ音が聞こえてきた。
「え? あんた、スマホなんか持ってんの?」
「うん。クラスの緊急連絡網とか、スマホのメッセージアプリで回ってくるから」
とは言うものの、光はリュックのポケットからスマホを出そうとはしなかった。
着信を知らせるバイブレーションも、ちょっと鳴ってはすぐ止まり、またすぐに鳴りだしては止まってしまう。それが、何度も何度も繰り返された。
「メッセージが着いてんじゃないの? 見なくていいの?」
光は立ち止まり、ちょっと困ったようにひかるを見上げた。
ひかるもすぐに、その着信がなんであるのか、気がついたらしい。
「光。からだ、貸してよ。それ、全部あたしが消してあげるから」
「え……。い、いいよ。そのくらい、自分でできる」
「いいじゃん。どうせ今日一日、学校にいるあいだは、あんた、あたしにからだ貸してくれるって、約束したじゃない。今から入れかわってたって、いいでしょ?」
「う、うん……」
光は迷った。
きのう、ひかるはこう言った。
「あたしがあんたのからだに入ってれば、クラスでいじめられてるのは、もう井上光じゃない。あたし、成瀬ひかるなのよ」
「でも……! それじゃ、ひかるがつらい思いするじゃないか」
「ばぁーか! あたしは大人なのよ、オトナ! たかが小学生のがきんちょに少々いやがらせされたからって、そんなん、ヘでもないっての!!」
――ひかるは美人でかっこいいけれど、どうも口が悪い。
「あんた、もしかしてあたしが、そのまま借りたからだを返さないんじゃないかって、疑ってる?」
「えっ!? そ、そんなこと、ない、よ……」
光はもそもそと口ごもった。
100%ひかるを信じているとは言い切れない、自分が情けない。
「まあ、しょうがないよね。あたしとあんたは、知り合って間もないし。それで相手を完全に信用しろったって、無理な話よ」
けれどひかるは、たいして気にした様子もなく、あっさり言った。
「でも大丈夫。そのからだは、やっぱりあんたのものなんだから。あんたが、あたしにからだを渡したくないって強く思えば、あたしの意識なんかすぐに追い出されちゃうはずよ。ほら、このあいだだって、そうだったじゃない」
「あ、ああ……そうだね」
ふわりと、ひかるが光の目の前に立った。
光をまっすぐに見つめて、言う。
「あたしを信じるも信じないも、あんたの自由。でも、できるなら、今はあたしのこと、信じてほしいな」
「ひかる……」
信じるも信じないも、ひかるを受け入れるも受け入れないも、光の自由。光自身が決めること。
なんだか、とても大きな決断を任されたような気がする。
肩の上をぎゅっと強く抑えつけられるような、それでいて胸の奥からなにかが音をたててわきあがってくるような、身体中が急に大きくふくれあがるような、そんな不思議な感覚だった。
「うん、わかった。ぼく、ひかるを信じるよ」
ひかるをまっすぐに見つめ、光は言った。
「光」
ひかるも、にこっと笑う。
それから二人は、歩道橋を急いで駆け下りた。
入れかわる瞬間を誰かに見られたりしないよう、ビルのかげにかくれる。
「じゃ、ちょっとだけ、がまんしてね。すぐすむから」
このまえと同じく、ひかるがまるで水泳の飛び込みみたいに、両手をそろえて突き出した。
光は思わず、両目をぎゅっとつぶってしまった。
ひかるが、からだの中に入ってくる。
全身がぎゅうううっとねじられ、しぼられるみたいな、あの感覚が光をおそった。
からだじゅうがうらがえしにされ、大きなローラーでおしつぶされているみたいだ。
やがてその苦しさが、突然、ふっと消えた。
からだがふわっとうきあがる。もうなにも感じない。
そして光は、半透明の幽霊になっていた。
「光。大丈夫?」
からだのある光が――いや、ひかるが、光を見上げている。
「う、うん、平気……」
ぼそぼそと光は答えた。
その声も、自分の中から出ているのか、どこか空の遠くのほうから響いているのか、はっきりしない。
「なんか、ヘンなの……。暑いとか寒いとか、なんにも感じないや……」
「しょうがないよ。からだがないんだもの」
ひかるはリュックをおろし、中からスマートフォンを出した。
そのあいだにも、スマホは振動を続け、次々に短いメッセージを受信している。
「ふん」
スマホを操作したひかるは、その文面を見て、鼻先で笑った。
「まあ、なんつーワンパターン、ステレオタイプないやがらせ! 脳みそが貧弱な、なによりの証拠ね。ほかにことば知らないのかしら、この連中」
見たくない、と、光は思った。
でも、ちらっと目を向けた瞬間に、スマホの画面が見えてしまう。
見たこともない名前で送りつけられたそのメッセージは、画面いっぱいに「死ね死ね死ね……」と繰り返されていた。
「同じ嫌がらせだって、もうちょっとアタマひねれってのよね。ほんと、語彙がとぼしくて、知性のかけらもないわ。小学生のがきだから、しょうがないけどさ」
「ご、い……?」
「知ってる言葉の種類、量って意味。ボキャブラリイってことばなら、聞いたことある?」
「うん。――意味はよくわかんないけど」
「ボキャブラリイが豊富だって言えば、いろんなことばを知ってて、意味も正しく使いこなせるって意味になるのよ。あたしが小六のころは、もうちょっとボキャブラリイが豊富だったわよ」
なんだかちょっと奇妙だった。
見下ろしている姿はたしかに井上光、小学六年の男の子なのに、話している言葉はまるっきり若い女性――大人の女性のものだ。
ひかるは慣れた手つきで、おかしなメッセージを送りつけてくる発信者を次々にブロックしていく。
「光。学校の電話番号、このスマホに入ってる?」
「え? うん。明京小学校で登録してある」
「め、い、きょ……ああ、あったあった」
そして、ひかるはいきなり、学校に電話をかけた。
「もしもし。六年B組の井上光の母ですが。相沢先生はいらっしゃいますでしょうか」
「ちょっと、ひかる。なにしてんの――」
おどろく光に、ひかるはだまってろ、と軽く手をふる。
「あ、相沢先生ですか? おはようございます。井上光の母です。うちの子がいつもお世話になっております――」
知らん顔して、ひかるは話し続けた。
声はたしかに光のものだが、ちょっと高い裏声になり、そのしゃべり方は完全に大人の女性だ。
こんな話し方で「井上光の母です」なんて名乗られたら、誰も疑わないだろう。
「実はゆうべ、うちの子が歯が痛いって言い出しまして。ええ、虫歯みたいなんですよ。それで、歯医者さんに連れていってから、登校させますので、今日はちょっと遅刻させてください」
――虫歯? 歯医者? ひかるはいったいなにを言い出したんだろう?
「はい。歯医者さんがどれほど混んでるか、わかりませんから……。でも、午前中にはちゃんと学校に到着するようにさせますので。はい。よろしくお願いいたします」
ていねいにあいさつして、ひかるは電話を切った。
「さーてと、これで時間の余裕ができたわ。ちょっと準備があるから、お店に寄るよ。あんたのお小遣い、貸してね」
「ええっ!? な、なにすんの、ひかる!?」
「まあ、だまって見てなさい。たいしたモンは買わないから、心配いらないって」
ひかるは光を見上げ、にやっと笑った。
それはあの、見ているだけでぞくぞくしてくるくらい、自信にあふれたひかるの笑顔だった。
光が――いや、ひかるが学校に着いたのは、三時間めと四時間めのあいだの休み時間だった。
「ひかる、急がないと。四時間めは体育なんだよ。ジャージに着替えなきゃ」
光は、今朝までのひかると同じく、ひかるのななめうしろにふわふわ浮かんでいた。
ずっと自分のうしろ姿を見下ろしているのは、なんだかとっても妙な気分だった。
「更衣室とか、あんの?」
「女子にはね。去年、使ってない教室を更衣室に変えたんだ。小学校高学年にもなって、男子と女子が同じ部屋で着替えるのはおかしいって、PTAの誰かが言い出したんだってさ」
森本たちによって、その更衣室に閉じこめられたことがあることは、光はだまっていた。
「ふうん」
ひかるはたいして興味もなさそうに、うなずいた。
「まさか、ひかる。女子更衣室で着替えるつもり!?」
「ばかなこと言ってんじゃないわよ。ちゃんと小六男子、井上光のふりをしてやるから、安心しなさいって」
教室のドアに手をかけて、ひかるはにやっと笑った。
「まあ、だまって見てなさい。絶対、ばれやしないから」
そしてひかるは、六年B組のドアを開けた。
休み時間でさわがしかった教室が、一瞬、時間が止まったみたいに静まり返る。
クラスにいた男子全員が、いっせいに光を――いや、ひかるを見た。
その、目。
あざけりと悪意に満ちた目。
クラスメイト、いや、同じ人間を見ている目じゃない。
あれは、なにか人間以外のもの――こわれかけたおんぼろのおもちゃ、あるいはもう殺すしかない、ハエ取り紙にひっかかったハエとか、ゴキブリとか、そういうものを見る、目だ。
光は、この目が怖かった。
そして、どうしても納得できなかった。
ぼくだって同じ小学生、同じ人間なのに、どうしてぼくだけが、こんな目で見られなくちゃいけないんだろう、と。
どんなに考えても、その理由がわからない。
わからないから、よけいに怖い。
みんな、にやにやと光を馬鹿にして笑いながら、ひかるをじっとながめている。
けれどひかるは、そんな笑いも、クラスメイトたちの視線も、まったく気にしなかった。
まるで教室に誰もいないみたいに、まっすぐ前を見て、自分の――光の席へ近づいていく。
そこには、森本たちがいた。
彼らの手には、絵の具のチューブがにぎられていた。
森本たちは、光が教室に置いてあった図工用の絵の具を、ひとつ残らず机の上にしぼり出していたのだ。
光の机は絵の具でどろどろのぐちゃぐちゃ、もとの木目なんて、まったく見えなくなっていた。
――ひどい。
光は宙に浮いたまま、幽霊をとおりこして、氷のかたまりかなにかになってしまいそうな気がした。
あの汚れを落とすの、いったいどうしたらいいんだろう。
ぼくの絵の具だって、みんななくなっちゃった。これから図工の時間、ぼく、どうすればいいんだよ。
森本も金子も水沢も、絵の具をほうりだすことも忘れていた。
遅刻すると連絡のあった光が、こんなに早く学校に来るなんて、思っていなかったのだろう。もしかしたら、光がこのまま、学校を休むと思っていたのかもしれない。
悪事の現場を見られたことで、森本たちは一瞬、しまった、という顔をした。
だがすぐに、にやにやとヒカルを馬鹿にした笑いを浮かべる。
彼らも知っているのだ。
先生たちも自分たちの味方であり、光がなにを言おうとも、自分たちが誰からも叱られない、ということを。
――ほら、見ろよ、ひかる。いくらひかるがかっこいいこと言ったって、やっぱりなにもできないじゃないか。
光は目をつぶった。
たとえ、からだを動かしているのが自分じゃないとわかっていても、これ以上、自分がいじめられているところなんか、見たくない。
けれど。
「そっかあ。おまえ、ほんとにいっしょうけんめいだなあ、森本ぉ!」
ひかるが言った。
「……え?」
明るく、よく響くその声。
光は思わず目をあけた。
目の前で光が、いや、ひかるが、にっこりと笑っていた。自信に満ちて力強く、少しも怖れずに。
「わかってるよ、森本。おまえ、オレがきらいなんだろ? オレに、爪のアカくらいでも好かれちゃ困ると思って、いっしょうけんめいオレをいじめてんだよな?」
ひかるはずんずん森本に近づいていった。
「安心しろ。オレも、おまえが大っきらいだよ」
「えっ!?」
光はあわてた。
「な、なに言ってんだよ、ひかる! そんなこと言ったら、ますますいじめられちゃうじゃんか!」
けれどひかるは、幽霊になった光の言うことなんて、まるで聞いていなかった。
森本の目の前につめ寄り、にたァッと笑う。
それは、上から見ている光でさえ、ぞおッと背すじが寒くなるような、冷たく、意地の悪い笑い方だった。
「心配すんな。オレは一生、おまえを許さねえよ。大人になっても、ずっとずっとおまえを憎んで、恨み続けてやるからな」
「な……っ。なに言ってんだ、てめえ……」
「オレは死ぬまで忘れねえぞ。おまえが、一対一じゃケンカもできねえ、ひきょう者の、人間のクズだってことをな!!」
クラスメイトたちを見回し、ひかるはどなった。
「おまえら全員、おんなじだ! キライなヤツに面と向かってキライって言う勇気もねえ、かげでこそこそいやがらせのメッセージ送るくらいしかできねえ、ひきょう者! てめえらがどんなに忘れようとしたって、オレは一生覚えてるぞ! てめえらがそういう臆病者、ウジ虫みてえなヤツらだってな!!」
「だ、だから……だから、なんだよっ!」
森本がどなり返した。
「てめえがオレらを恨んでたからって、なんだってんだよ! てめえひとりがバカみてーにわめいたからって、オレらが、てめえのことなんかおぼえてるわけねえだろ!」
「ほんとに、そうか?」
ひかるはまた、にたあっと、あのおそろしい、残酷な笑いを浮かべた。
「おまえら、本当に平気か? 一生、誰かに心底憎まれてんだぞ。大学行こうが、大人になって結婚しようが、ずっと、ずうーっと、誰かに憎まれて、恨まれ続けてんだぜ? おっかなくないか?」
まわりの生徒たちの顔を、ひとりひとりたしかめるように、ひかるは見回した。
「オレのこと、本当に忘れられるか? オレは顔もわかんねえ、SNSの文字だけの相手じゃねえ。こうしておまえらの前にちゃんと立ってる、生きた人間なんだ。その人間に、自分と同じ人間に、恨まれても憎まれても平気で生きていけるほど、おまえらは本当に強いのか? 自分ひとりじゃ誰かをいじめることもできねえくせに!」
――な、な、なに言ってんだよ、ひかる!
光はあわてて、自分のからだに飛びついた。そのからだを動かしている、ひかるに。
「やめてよ、ひかる! なんでわざわざ、みんなにきらわれるようなことばっか、言うんだよ!」
けれどひかるは、光の必死の声も、きれいさっぱり無視した。
光はなにもできない。
どついたりけとばしたり、最悪の実力行使に出ようとしても、光のパンチやキックは、すかッ、すかッと、からだをすり抜けてしまう。
――ああ、そうだ。ぼく、今、幽霊なんだ。
魂だけの、死んだも同じの存在。だから、なんにもできないんだ……!!
「な……、なに言ってんだ、てめえ。バカじゃねえの?」
森本が、ひかるに言った。その口元がひくひくゆがんでいる。
クラス中が異様な空気に包まれていた。まるで見えない火花が、バチバチと無数にはぜているみたいだ。
とても、怖い。
空気のように透けて、誰にもその存在を認識されていない光でさえ、とても怖かった。
もう、おしまいだ。ひかるは――光のからだは、ぼこぼこにされるだろう。クラス男子18人全員に、よってたかって殴られる。
今度こそ、ケガじゃすまないかもしれない。いつも来るメッセージのとおり、本当に殺されるかもしれない。
――ぼくのからだが、死ぬ。殺される。ぼくは本当に、幽霊になっちゃうんだ……!
けれど。
「こ……、こいつ、アタマおかしいよ。ぜってー、フツーじゃねえ」
誰かが、おびえた声で言った。
光をかこむ輪の、うしろのほう。
そこで声をあげたのは、クラスの中でもあまり目立たない生徒だった。
「木島……」
光は思わず、そいつの名前を呼んだ。
――木島。なに、こわがってんの、おまえ?
木島は、怖がっていた。
目を伏せて、おどおどびくびくして、ネズミみたいだ。
それは、光のことを見て見ぬふりを続ける相沢先生の表情に、そっくりだった。
「こんなヤツの相手することなんか、ねえよ。無視しようぜ、無視。な? それよか、みんな、早く校庭に出よう。なっ!?」
まるで助けを求めるように、木島はクラスメイトたちを見回した。
「あ、ああ……。ああ、そうだよな」
「こんなヘンなヤツなんか、ほっとこうぜ。オレらには関係ねーよ」
「森本。おまえももう、井上なんかにかまうなよ。あんまりそいつの近くにいると、おまえも井上菌に感染して、アタマおかしくなんぞ!」
クラスメイトたちは、ジャージに着替えおわっていた者から先に、ばたばたと教室を飛び出していった。お化け屋敷から逃げ出すように。
「ふ、ふんっ!」
森本もえらそうにあごをあげて、ひかるを見下ろそうとした。が、真正面からにらみ返すひかるに、ひどく落ち着かない様子を見せる。
「ば、ばーか! 死ね! 死ね、死ね、死ねっ!」
同じことばをわめきながら、森本も教室を逃げ出す。
口から白い泡を飛ばしながら、たったひとつのことばをわめき続けるその様子は、まるで、ほかのことばがなにも言えなくなってしまった、こわれかけのロボットみたいだった。
「あ、も、森本くん!」
金子や水沢、子分たちも、あわててそのあとを追いかけた。
やがて教室には、二人のヒカル以外、誰もいなくなった。
「な……、なんで? なんであいつら、ぼくに――いや、ひかるに、なにもしなかったんだ?」
光は、ぼそっとつぶやいた。
「怖かったからよ」
ひかるが答える。
宙に浮いた光を見上げ、ひかるはにこっと笑ってみせた。
「あいつら、怖かったんだよ。あたしに、憎んでやる、恨んでやるって言われたことがね」
「そんな……。どうして? 1対18だよ? 怖いわけないじゃん」
「怖いのよ、それでも。だって、あいつら、誰ひとりとして、面と向かって『おまえがきらいだ、おまえを一生憎んでやる』なんて言われたこと、ないんだから」
説明しながら、ひかるは絵の具で汚された机を、よっこらしょ、とかかえ上げた。
「この机、もう使い物になんないからさ。予備の机ととっかえちゃおうよ。どっかに空き教室とか、ない?」
「使ってない机なら、階段の下に少しつんであるよ」
光のことばにしたがって、ひかるは汚い机をかかえて教室を出た。
服に絵の具がつかないように気をつけながら、机を持って階段を下りていく。
「ねえ、光。あんただってさ、人から嫌われるのは、つらいでしょ?」
「え? うん、そりゃあ……」
いじめられて、なによりつらいのは、クラス全員から、先生もふくめた学校の全員からきらわれていると感じることだ。
そこまで他人からきらわれる自分は、生きている価値なんかないと、本気で思えてしまう。
「みんな、ふつうはほかの人に、『あんたがきらい』なんて言わないよね。心の中では、どんなにそいつのことをきらってて、陰じゃさんざん悪口言い放題でもさ、本人の前でだけは、絶対『キライ』とは言わないでしょ?」
「うん――」
「だから、真正面から『てめえがだいきらいだ』ってはっきり宣言されると、ほんとに怖くなっちゃうのよ。ふつうはしないことをするくらいだから、こいつ、いったいどこまでおれのことを嫌い抜いてるんだろう、おれは、こいつにどんだけ激しく憎まれてるんだろうって。みんな、他人から嫌われた経験が、ないからね」
――ひとからきらわれた、経験?
ひかるの言っていることは、光にはよく意味がわからない。
「誰かに嫌われるのって、やっぱりいやなことだよね。傷つくよね。でも人間は、世界中の人から好かれるはずなんかない。誰か仲のいい相手がいれば、たいがい同じ数の相手から嫌われてるもんなのよ。それもしょうがない、そういうもんだってあきらめて、覚悟して、生きていくしかないの。きらいなヤツに会っちゃったら、『ああ、いやなヤツに会っちゃったなあ』って、どっちも嫌な思いして、どっちも傷ついて、それでもがまんしてね」
わかる? と、ひかるは光を見上げた。
「う、うん。なんとなく……」
たぶん大人は、みんな、そういうふうに生きているんだろう。光はそう思う。
「でも、あんたをいじめてるあの連中は、それががまんできないの。他人から傷つけられることが、怖くて怖くて、どうしようもないんだよ」
傷つけられるのが怖いから、先に相手を傷つける。傷つけられないように、まわりに同調する。
たとえそれが悪いことだとわかっていても、まわりと同じことをするしかない。自分ひとりが違うことをすると、みんなから攻撃されてしまうから。
それが、光がいじめられていた、本当の理由だった。
「だから、あいつらを思いきり傷つけてやったの。集団にならなきゃなんにもできないひきょう者、オレはおまえらが大っきらいだって、宣言してね。あいつらはなにも言い返せない。だって、自分がそういうひきょうな弱虫だって、自分自身がいちばん良く知ってるんだものね」
ひかるは、汚れた机を、階段下の使われていない机や椅子の中にまぎれこませ、別の机をかかえあげた。
「さーて、あたしも急いで着替えなくちゃ。光、体操着はどこ?」
「リュックの中だよ」
机を持って、誰もいない教室にもどり、ひかるはさっさとジャージに着替えた。
「体育の授業にも、出るつもり?」
「当然!」
四時間めの始まりを告げるチャイムが鳴る。
ひかるはなんだかとてもうれしそうに、教室を出た。
「なんか……すげえ楽しそうだね、ひかる」
「まあね。体育の授業なんて、ひさしぶりだもん! 大人になるとさ、思いっきりからだ動かしてあばれることなんか、なくなっちゃうからね」
にこにこと楽しそうな笑顔を浮かべているのは、井上光の顔、からだだ。
でもその表情は、ひかるのものなのだ。
二人が、昇降口に向かって階段を下りようとした時。
一人の女の子が、階段をのぼってきた。
「あ、井上」
女の子は、光の顔を見ると、ひどく怒ったような表情を見せた。
「あんた、早退しないで、体育に出る気?」
にらまれて、ひかるは一瞬、返事に困ったようだった。ちらっと光を見上げ、口の動きだけで小さく「誰?」ときいてくる。
「高倉。同じクラスの子」
光も小さな声で答えた。――たかくら、なに、だっけ? 下の名前までは覚えていない。
高倉はひかるとすれちがうように、階段をのぼってきた。
そして、
「井上。あんた、やりすぎだよ」
ぶっきらぼうに、高倉は言った。
「さっき、あんたが教室でどなってたの、あたしも聞いちゃったの。あんなことひどい言ったら、あんた、ますますいじめられるじゃん。どうしてあんなこと言ったんだよ!」
「高倉……」
「校庭行くの、やめな。今、森本たち全員で、あんたをどうやっていじめるか、話し合ってるよ。あんた、このまま家に帰んなよ!」
「オレはなんにも悪いことはしてない」
ひかるははっきりと言い切った。
「オレはただ、ほんとのことを言っただけだ。あいつらがきらいだって。きらいだからてめえらを殴るとも、いじめられた復讐をしてやるとも、言ってない」
「それは――そうだけど。でも、おまえがきらいだなんて、言ってどうなるんだよ! たとえきらいでも、いじめられないためには、みんなと仲良くやってくしかないでしょ!?」
「あいつらと仲良くなって、そんで今度はオレも、あいつらといっしょに別の誰かをいじめてろって言うのか?」
ひかるの冷たい言い方に、高倉はもうなにも言えなくなってしまった。
「ち……ちょっと、ひかる! そんな言い方するなよ! 高倉がかわいそうじゃんか!」
光は大声で言った。
どうせひかるは、さっきと同じく全然聞いてくれないだろうけれど、それでもだまっていられない。
ひかるはちらっと、光を見上げた。
そして、ちょっとあきれたような顔をして見せる。
でも、それ以上、高倉にひどいことを言うのは、やめてくれた。
ひかるはだまって高倉の横をとおりぬけ、階段をおりていこうとした。
「井上……!」
「おまえが気ぃ使ってくれてんのは、わかってる。サンキュ。でもさ、オレと口きいてんのがばれたら、今度はおまえがいじめられんじゃねえの?」
「それは……。あんたがだまってたら、バレないでしょ」
まあね、と、ひかるは小さく笑った。
「おまえは、校庭行かねえの?」
「あたしは――今日、体育休み。外、風が強いし、見学じゃなくて、教室で自習してていいって、先生が言ったから」
「ふうん」
それ以上はなにも聞かず、ひかるはだまって階段を下りはじめた。
高倉も、ぱっとひかるに背中を向けて、まるで逃げるように教室へ行ってしまった。
「あ、高倉!」
光は思わず、高倉を追いかけようとした。
「むだだってば。あんたの声は、あの子には聞こえないよ」
階段の下から、ひかるが小さな声で言った。
「あ……。そうか――」
光はため息をついた。
「あんた、ほんとにお人好しだね」
ため息をつくように笑って、ひかるが言った。
「あの子だって、あんたのいじめに加わってたんでしょ。なんでそんな子に、気ぃ使ってあげる必要があるの?」
「それは、そうだけど……。でもさっきは、高倉、ぼくのために、あんなこと言ってくれたんだしさ」
「あんまりいいアイディアとは思えないけどね。あれじゃ、いじめられないためには不登校になるしかないって、言ってるようなもんじゃない。緊急避難としては、その方法もアリだけどさ。逃げてるだけじゃ、問題は解決しないわ。家に引きこもっていれば、いじめられることはないけど、今度は、自分は逃げたんだって負い目をしょいこむことになるんだもの。自分の負い目と戦うより、他人と戦うほうがずっとかんたんよ」
でも、高倉に言えることは、それだけだったにちがいない。
高倉だって、いじめられるのは怖いはずだ。
だから、みんなといっしょにいる時に、光に声をかけたことは一度もない。森本たちがどんなにひどいいじめをしていても、だまって、なにも見ないふりをしていた。ほかのクラスメイトや、相沢先生と同じように。
それでも、
「ぼくに言ったことが、高倉にできるせいいっぱいだったんだと思う。ぼく、高倉のその気持ちは、認めてあげたいんだ」
「あんたって……」
半分あきれたように、それでもなんだかうれしそうに、ひかるは笑った。
ちょっと肩をすくめ、ふうっとため息をつく。
そのしぐさは、とてもおとなっぽくて、かっこ良かった。もっともからだは、光のものなのだが。
――なんだろう。ひかる、ぼくになにを言いたいんだろ?
ぼくが底抜けのお人好しだってこと、ひかるにとっては、悪いことじゃなかったんだろうか?
そう思うと、光もなんだかうれしい。
誰かに――ひかるに、自分は悪い人間じゃないと思ってもらえることが、うれしかった。
けれどひかるは、それ以上はなにも言わなかった。
「さ、行こう! 授業に遅れるよ」
「あ、待ってよ、ひかる!」
ひかるがいきおい良く走りだす。
光も、あわててそのあとについていくしかなかった。
今日の体育は、ミニサッカーだった。
男女それぞれが赤と白の二つにわかれ、試合をする。
背の順で並び、交互に赤チーム白チームに分かれたため、今度は光も、理科の実験班のように仲間はずれにされることはなかった。――うわべだけは。
「じゃあ、始めるよー! ちょっと寒いけど、みんな、元気良くねー!」
相沢先生の合図で、サッカーが始まった。
光も、みんなと同じくコートの中に立つ。
――いや、ひかるだ。からだは12才の井上光だが、それを動かす魂は、25才の成瀬ひかるなのだ。
光はその姿を、宙にただよいながら、ただ眺めているしかなかった。
森本や福田が、ちらちらとひかるを見ている。
ほかの男子もみんな、薄笑いを浮かべて、なにかを確かめ合うように、おたがいうなずいたり、こっそりひかるを指さしたりしている。
「だいじょうぶなの、ひかる!?」
すうっとひかるのそばに近づいて、光は言った。
森本たちは、絶対なにかをたくらんでる。
授業中、先生の見ている前で、殴ったりけったりはしないだろう。
でも、そのほかのこと、けがをするような暴力でなければ、なにをしたって平気だと思っているはずだ。
「ねえ、ぼくと入れかわろう。ぼくなら、もう慣れてるから。なにされたって、がまんできるよ」
ひかるはちらっと光を見上げ、そして小さく首を横にふった。まわりの人間に見つからないよう、ほんの少しだけ。
そして、ボールを追いかけて、走りだす。
「ひかる――!」
森本たちのいじめは、とても単純だった。
ひかるにいっさい、ボールを回さなかったのだ。
ひかると同じ赤チームのメンバーも、光には絶対パスを出さない。まるでひかるなんかいない、見えない、というように。
ひかるがボールを取りに行こうとすると、みんな、あわてて大きくボールを蹴る。その先にいるのが、敵の白チームだって、関係ない
。
これでは、ひかる対残りの男子全員で、試合をしているみたいだ。
しかもみんな、ひかるがボールにさわれないよう、パスを回し合うだけで、ろくにシュートもしない。まるっきりサッカーになっていない。
「なるほどね」
ひかるが小さくつぶやくのが、光にだけは聞こえた。
そして、いきなりボールに向かって猛ダッシュした。
「あっ、来やがった!」
ボールがぽーんと大きく蹴られる。
それを追って、ひかるは走った。
そして、叫ぶ。パスを受けようとした木島に向かって。
「おら、どけよ! オレにさわられたら、井上菌に感染しちまうんだろ!?」
「えっ!?」
木島はびくっとふるえた。
「おら、どけどけどけっ! てめえら、オレにさわったら、汚染されるぞ! 汚染されたら、今度はてめえらがバイキンだぞーっ!!」
ひかるの前にいた男子たちが、反射的に、ぱっとよけた。
それは、光自身、何度も体験してきたことだった。
井上光にさわるな。あいつはバイキンだ。みんながそう言い合い、光の前からわざと、ぱっと飛びのく。
万が一光にさわってしまったら、さわったやつまで、バイキンだバイキンだとはやしたてられ、みんなからさけられてしまう。
木島もよけた。
ボールは、誰もいなくなったスペースを、てんてんと転がっていく。
ひかるはそこへ走り込んだ。
Jリーガーみたいにかっこいいポーズをキメて、ボールを足で押さえる。
そしてゆうゆうと、クラス全員を見回した。
でも、誰もボールをとりにいけない。
だって、井上光にさわってはいけない。それが、六年B組のルールだから。
軽々とドリブルしながら、ひかるは走りだした。
まるで、たったひとりでボールを蹴って遊んでいるみたいだ。
ほかの生徒は、グラウンドに突っ立ったまま、それをだまって見ているしかなかった。
「……な、なにしてるの、みんな?」
相沢先生が、おろおろと声をかける。
誰にもとめられることなく、ひかるは一気にゴール前まで走った。
シュートするために、足を大きくふりあげる。
ゴールキーパーが身構えた。――キーパーは、金子だ。
その時、ひかるはまた叫んだ。
「オレがさわったボールだぞ! おまえ、さわってもいいのかよ!?」
「――えっ!?」
金子は一瞬、どうしていいかわからない、という顔をした。助けを求めるように、森本や水沢を見る。
けれど彼らにも、どうしていいかわからなかったに違いない。
ひかるは嫌味なくらいゆっくりと、ボールをゴールに蹴りこんだ。
キーパーは一歩も動けなかった。
ゴールに転がったボールを、ひかるは自分で拾い、また蹴り始めた。今度は反対のゴールに向かって。
ほかの生徒は、誰も、何もしない。
サッカーは、めちゃくちゃになった。
ボールを蹴って走っているのは、ひかるひとりきりだ。
ほかの生徒たちは、ただ、立っているだけだ。冷たい風の吹く校庭で、まるで小さな並木みたいに立ち尽くし、その場から一歩も動かない。
ひかるがそばを走り抜けると、みんな、まるで見てはいけないものを見たように、あわてて目を伏せる。そしてまわりのクラスメイトたちに、ちらちらと視線を向ける。自分はどうしたらいい? とたずねるみたいに。
でもそれに対する答は、どこからもないのだ。
みんな、ただじっと立っているしかなかった。
「ね、ねえ、みんな、どうしちゃったのかな? どうしてサッカーしないの?」
相沢先生はいっしょうけんめい、みんなに声をかけた。
でも、それに対する返事もない。
さすがに、
「井上光がさわったボールなんか、汚くてさわれません」
とは、先生には言えないのだろう。
どうしようもなくて、相沢先生はとうとう、ひかるに頼み込んだ。
「ねえ、井上くん。ほかのみんなにも、ボールをパスしてくれないかしら? みんなにも、サッカーさせてあげてちょうだい」
――先生が、頼み事!
井上光に、
「みんなにもサッカーをさせてあげてちょうだい」
だって!?
数人の小さなグループでやった理科の実験だって、ぼくは、なにもできなかったのに!
「はい、わかりました。先生」
ひかるは素直にうなずいた。
そして、ぽーんと大きくボールを蹴る。
その先には、森本がいた。
森本はまったく動かなかった。まるで棒っきれみたいに、硬直したままだった。
ボールは、森本の横をころころところがっていった。
ひかるは相沢先生のほうにふりかえった。
そして、「ね?」というように、軽く肩をすくめてみせる。
先生も、もうなにも言えなかった。
4時間めが終わるまで、ひかるはたったひとりで、楽しそうにボールを蹴り続けた。
ほかの生徒たちは、ただそれを、うらめしそうにながめていることしかできなかった。
やがてチャイムが鳴りひびく。
六年B組にとって、おそらく今まででもっとも長くつらい四時間めが、ようやく終わった。
「すごいや、すごいや、ひかる!」
光は思いきり声をはりあげた。どうせひかるにしか聞こえない。
「あの時の森本の顔、見た!? すっげー顔してたよ! 真っ赤になって、口とか鼻とか、ぴくぴくふるえちゃってさ!」
のろのろと校庭から引き上げるクラスメイトたち。
みんな、吹きさらしの校庭にじっと立っていたせいで、ひどく寒そうだ。鼻水をたらしているやつもいる。
「ぼくじゃあんなこと、考えつきもしなかった。今までずっと、ただ仲間はずれにされるのが、つらくて、悔しくてさ――」
「まだまだ、こんなもんじゃないからね!」
ひかるは走りながら、小さな声で答えた。
ふるえながら戻ってくるクラスメイトたちより先に、元気いっぱい、昇降口へ駆け込む。
みんなは、ひかるを追いかける元気もないらしい。
「光。給食はどこに届くの?」
「え? でもぼく、今週は当番じゃないよ」
「いいから、案内しなさいってば」
「どうすんのさ、ひかる? ぼく、給食当番のエプロンだって持ってないのに」
ひかるは、なにを言ったって聞いてくれなかった。
「こんにちわあ! 六年B組の給食、取りにきましたー!」
光に案内させて、ひかるは給食室に飛び込んだ。
「あー、はいはい。そこのワゴンよ」
給食のおばちゃんが、クラスごとに用意されたワゴンを指さした。
ワゴンには、主菜の大きななべや、フライなどの入った副菜の平たいなべ、パンがならんだ箱などがきちんと積まれている。
「あら。きみ、当番のエプロンはどうしたの?」
「ごめんなさい、忘れてきちゃいました!」
「しょうがないわね。今度からは忘れないようにね」
おばちゃんたちは、それ以上はなにも言わなかった。
さすがに、給食室のおばちゃんたちにまでは、六年B組のいじめのことは知られていないらしい。
給食室にはすでに、ほかのクラスの生徒たちも給食を取りにきている。かなりの混雑だ。
どこのクラスから何人の当番が来ているかなんて、よくわからない。
だから、ひかるがたったひとりでB組の給食を運び出しても、誰も気にしなかった。
今度は光も、ひかるがなにをしようとしているのか、すぐにわかった。
「ひかる、そこの廊下、曲がって。車椅子用のエレベーターがあるんだ。ほんとは使っちゃいけないけど、でもそのエレベーターを使えば、森本たちより早く教室に戻れるよ!」
「オッケー! あんたも察しがいいじゃん、光!」
重たいワゴンを押しながら、ひかるは全速力で走った。
エレベーターで急いで4階まで上がり、B組の教室に飛び込む。
光の思ったとおり、教室にはまだ誰も戻ってきていなかった。
女子はまだ更衣室にいるのだろう。
男子は、もしかしたら、昇降口かどこかに集まって、光へのしかえしを話し合っているのかもしれないが。
――でも、そんなのもう、怖くない!
ひかるが、主菜のシチューをつぎわけるおたまを持って、にっこりと笑う。
光もうなずいて、笑い返した。
ひかるがプラスチックのうつわに、あったかいクリームシチューをなみなみとよそった時、教室のドアが開いた。
まだジャージ姿の男子たちが、ぞろぞろと教室に入ってくる。
「遅いぞ、おまえら。せっかくの給食だってのに、なにやってんだよ」
おたまをしっかり握りしめて、ひかるはなべのそばでふんぞりかえった。
「て、てめえ……っ!」
「おまえらがあんまり遅いから、オレ、待ちきれなくて、給食運んできてやったぞ。ほら」
ひかるは、あんまり熱くない副菜のなべや、パンが並んだトレイを、ぽんぽんと軽くたたいた。
そして、わざとらしく、
「あっ、悪りい! オレ、なべにさわっちゃったよー!!」
「い、井上、てめえ――っ!」
「ごめんなあ。もうこれで、給食も井上菌に汚染されちゃったよなあ? おまえら、どうする?」
――どうするも、こうするも、ない。
井上菌に汚染されたものには、六年B組の生徒は、誰もさわってはいけないのだから。
いや、そんなルールにだって、抜け道はある。たとえば、
「井上光がさわったのは、なべとかおたまとか、食器だけだから、給食のパンやミルクなど、食べ物そのものは汚染されていない」
とかなんとか、へ理屈をこねることはできるはずだ。
だって森本たちは、光に暴力をふるう時は、汚染もへったくれも気にせずに、ばんばん光のからだにふれて、殴ったり蹴ったりしたのだから。
けれど、誰もそんな考えは思いつかないようだった。
思いついても、言えないのかもしれない。
「そんなみじめないいわけしてまで、給食が食いたいのか。こんな汚染された給食を!」
と、誰かが怒って言い出せば、今度は自分がいじめのターゲットにされてしまいかねない。
やがて、更衣室から女子たちも戻ってくる。
けれど彼女たちも、一歩教室に入るなり、その異様な空気に気がついた。みんなドアの近くにひとかたまりになって、自分の席にも戻れずに立ちつくす。
その中には、高倉の姿もあった。
おびえて落ち着かない様子の女子たちにまじって、高倉はひとり、妙にしらけたような顔をしていた。なんだか、こうなることがわかっていたような表情だ。
更衣室で、今日の体育の授業がどんなことになったか聞いて、給食ももしかしたら、と、予想していたのかもしれない。
「ま、とにかくよそってあげるよ。給食を汚染しちゃったおわびにさ、今日の給食は、みんなオレがくばってあげるから」
ほら、みんな席についたついた、と、ひかるは生徒たちに明るく声をかけた。
そして、生徒たちが着席するより早く、ぱっぱと給食トレイを机の上にのせていく。続いてパン、牛乳と駆け足でくばり、最後にトレイを押しながら、シチューと副菜のコロッケをくばった。
みんなはだまって、あったかくておいしそうな料理が、自分の目の前に置かれていくのを見つめているしかなかった。
やがてひかるが給食を配り終えるころには、相沢先生も教室に入ってきた。
「みんな……、なんか、静かね」
生徒たちは、全員がきちんと着席して、口も開かずに、ただじっと給食を見つめている。
「はい、先生」
ひかるは先生の分の給食もきちんとそろえて、先生の机にのせた。
「あ、ありがとう、井上くん。……井上くん、今日、給食当番だった?」
その質問に、ひかるは答えなかった。
相沢先生はすぐに、はっとなにかに気づいたようだった。そして、ひどく困ったような顔をして、目をそらす。
――そうか。先生、ぼくがみんなにむりやり給食当番をやらされてると思ったんだ。教室の掃除とか、ずっとぼくひとりがやらされてるから。
だから、相沢先生は、ひかるのことを叱れない。
先生の目から見れば、今も井上光はいじめの被害者なのだ。
「じゃあ、いただきましょう」
決まりどおり、あいさつをする。
けれど、スプーンとフォークを手にとったのは、ひかると相沢先生だけだった。
「みんな……? どうしたの?」
誰も、一口も食べようとしない。
ぎゅっとからだをこわばらせて、だんだん冷めていく給食を、見つめている。みんな、泣きそうな目をして、けんめいに空腹をがまんしている。
給食をおいしそうに食べているのは、ひかるだけだった。
――食べられないよな、みんな。
食べてしまったら、そいつは裏切り者だ。井上光の同類にされてしまう。
いいや、井上光がここまで強気で反撃に出てきたからには、その裏切り者が、今度はたったひとりのいじめのターゲットにされてしまうだろう。
いじめでなにがおもしろいかといえば、相手が絶対に反撃してこないとわかっていることだ。
どんなにそいつをいじめて、殴っても、殴り返されない。自分は全然痛くない。
だから、ひとりの人間をいつまでも殴り続けていられるのだ。
だが今、井上光は、殴り返してきた。
たったひとりで、37人のクラスメイトを相手に、いや、学校中を相手に。
――怖いんだ、みんな。
今まで自分がやってきたこと、それに対して、しかえしされることが、今、怖くて怖くてしかたがないんだ。
教室の中をふわふわただよいながら、光は、クラスメイトひとりひとりの顔を、じっと見つめていった。
幽霊みたいな存在になり、いじめの当事者の立場をはなれて、ようやく光は、クラスメイト全員の顔を、はっきりと見ることができた。
それまではみんな、「いじめの集団」というのっぺらぼうのかたまりみたいに思えて、ひとりひとりの顔なんて、ほとんどわからなくなっていたのだ。
でもこうして空中から見下ろすと、みんなひとりひとり、違った顔、違った姿をしているのがよくわかる。
「いじめの集団」なんて化け物みたいなひとかたまりじゃない。みんなそれぞれ、ひとりの人間だ。
――みんな、怖いんだ。いじめた相手に復讐されることが、今度は自分がいじめのターゲットにされることが。
怖くて怖くて、なにをどうしていいかもわからなくて。
なんだか、とてもかわいそうだ。
森本ですら、光はかわいそうだと思った。
もちろん、森本たちが自分になにをしたか、忘れることはできない。
ひかるが言わなくとも、きっと大人になっても、彼らのことは大きらいなままだろう。
でも、怒りや悔しさで顔を真っ赤にした森本は、今にも泣きそうに見えた。まるで森本のほうが、誰かにひどくいじめられているみたいだ。
森本たちは今、自分たちで決めたいじめのルールに、自分たちががんじがらめにしばられて、逃げ出せなくなっている。
――逃げることができないんだ。
このクラスにいるかぎり、誰も、いじめから逃げられない。いじめのリーダーである森本も、相沢先生も。
やがて、昼休み終了五分前のチャイムが鳴った。
「え? もうそんな時間なんだ」
光は、黒板の上にかけられた時計を見た。
幽霊になったせいだろう、光はまったくおなかが空かない。
そのため、時間の感覚もなんだかあいまいになっているみたいだ。
「えっと、みんな……。給食、片づけてもいいかな? いいよね? しょうがないもの、五時間めが始まっちゃうし……」
ぼそぼそと、いいわけみたいに相沢先生が言った。
みんな、しかたなく、一口も食べていない給食を片づけ始める。
結局、給食を食べられたのは、生徒ではひかるひとりきりだった。
五時間め、六時間めも、B組の教室はしんと静まり返ったままだった。
算数の授業で、相沢先生が「この問題がわかる人?」と言っても、答えて手をあげる生徒はひとりもいない。
みんな、先生なんか見ていない。となり、ななめ、まわりのクラスメイトの様子ばかり気にしている。
誰かがしゃしゃり出て、目立とうとしてないか。反対に誰かが自分のことを、ひとりだけ目立ちやがって、と、にらんでいないか。そればかりをたしかめているのだ。
空気がはりつめて、なんだか、今にもなにかが爆発しそうなふんいきだ。すごく、居心地が悪い。
幽霊になった光でさえ、そう感じた。
クラスメイトたちも、教科書の上に顔を伏せて、早く終われ、早く終われ、と必死で念じているみたいだった。
6時間めの終わりを告げるチャイムが鳴った時、生徒たちも、そして先生も、ひどく疲れ切ったように、大きくためいきをついた。
長かった一日が、めちゃくちゃな一日が、ようやく終わる。
掃除当番が、だまって教室の掃除を始めた。今日は、光ひとりにおしつける気はないらしい。
――そうだよな。そんなことしたら、ひかるにどんなしかえしされるか、わかんないし。
当番ではない生徒たちは、あわてて教室を出ていった。まるで逃げるみたいに。
森本たちも、いつものグループひとかたまりになって、教室を出ていこうとした。
井上光へのしかえしは後回し、今は光のいないところへ行って、少し冷静になってゆっくり方法を話し合おう、とでも決めたのかもしれない。
あるいは、井上光の顔さえ見えなければ、どんなひどいことだってできる、早くかくれて、またいじめを始めよう、と。
けれど。
「あ、そうだ、森本ぉ!」
ひかるがわざわざ、森本たちを呼び止めた。
「オレさあ、今日、うっかりスマホこわしちゃったんだよなあ」
「えっ!?」
ひかるの手には、画面が割れた銀色のスマートフォンが握られていた。
「えっ、う、うそっ!?」
光もあせった。
あのスマホは、旧式の携帯電話では緊急連絡網のメッセージアプリがうまく動かないからと、夏休み前に買ってもらったばかりだ。
「あーあ、もったいねえことしちゃったなあ。こんなにすぐこわしちまったから、母さん、次のはなかなか買ってくれないだろうなあ。買ってもらえるのはたぶん、卒業して、中学に入学する、お祝いかな」
「い、井上、てめえ……っ」
「だから、いくらメッセージ送ってもらっても、オレ、いっさい受信できねえから」
ひかるははっきりと言い切った。
たしかに、いたずらメッセージを受信したくないなら、いちばん確実な方法は、携帯電話やスマホを持たないことだ。
「クラスの連絡網とかで知らせがあるんなら、オレん家に直接、電話かけてくれよな。でも、うちって、母子家庭だろ。女の人とこどもしかいない家だからさ。電話はいつも留守電状態なんだ。はっきり名前言わない電話にゃ、絶対出るなって、母さんに言われてんだよ。みんなも、オレん家に電話する時は、最初にしっかり自分の名前言ってくれよな」
こんなことを言われたら、家の電話に無言電話などのいやがらせもできない。
ひかるは軽々とリュックを肩にかついだ。
そしてひとり、悠々と教室を出ていった。
「ひかる! ひかる、ちょっと待ってよ!」
光はあわててそのあとを追った。
ひかるは急いで校舎を出て、走りだした。
学校の外、誰にも見られない場所でなければ、ふたりで落ち着いて話すことはできない。
今朝、ふたりが入れかわったビルの陰まで一気に走って、ひかるはようやく立ち止まった。
「あー、苦しい。でも、気持ちいいー! こんなにいっぱい走ったのなんて、何年ぶりかな!」
でも幽霊状態の光は、苦しくもなんともない。
「ひかる、ひかる! どうすんだよ、あのスマホ! お母さんからのメッセージもあのスマホで受け取ってたのに!」
「だいじょうぶだってば。ほら、よく見なさい」
ひかるは、さっきのこわれたスマホをポケットから取り出した。
――なにか、へんだ。
「あ、あれ……? なに、これ――」
「赤ちゃん用のおもちゃ。100均ショップとかでも、良く売ってるじゃない。それの、ペンギンやウサギのプリントシールをけずって、メタルカラーのサインペンで銀色に塗っただけ」
よく見れば、マジックの塗り残しやムラもわかる。
でも、半分手の中に握ってかくした状態で、一瞬だけぱっと見せられたら、これが100円ショップのおもちゃだなんて、誰も気づかないだろう。
「ほら。あんたのスマホはこっち」
ひかるはもうひとつ、スマートフォンを取り出した。
こっちは間違いなく、お母さんに買ってもらった、本物のスマホだ。
「すごいや、ひかる……」
思わず、光はつぶやいた。
「そっか。今朝、学校に行く前にお店に寄ってたのは、これのためだったんだね!?」
「そうよ。あんたのスマホがこわれたってことになったら、あいつらだって、こわれたスマホにメッセージ送り続けるような、ばかなまねはしないでしょ。でも、本物は絶対に見つけられちゃだめよ。もしうそだってバレたら――」
「うん! うん、わかってる! ひかる、ほんっとにすごいよー!!」
「たいしたことじゃないわよ、このくらい。それにまだ、最後の仕上げが残ってるしね」
「最後の仕上げ?」
そうよ、とうなずいて、ひかるはどこかに電話をかけた。
「あ、もしもし、お母さん? うん、ぼく、ヒカル。――ごめんね、仕事中に電話しちゃってさ」
――お母さんに電話? ひかる、いったいなにをする気だろう。
でも、光はもう、ひかるのやることにいちいち質問しようとはしなかった。
「今日、学校で連絡があってさ。明日、お弁当持ってかなくちゃいけないんだ。給食センターが断水なんだって」
もちろん、そんな話は学校でも全然出なかった。
でも、ひかるを信じていれば、だいじょうぶだ。絶対、うまくいく。
電話からお母さんの声が聞こえる。
「あらそう。じゃ、お弁当用のおかずも買って帰らなくちゃね。光、なにがいい?」
「ん? なんでもいいよ。お母さんにまかせる」
じゃあね、と、ひかるは電話を切った。
「ねえ光。学校を出たら、このからだ、あんたに返すって約束だったけどさ。家まで、あたしが動かしてもいい? 家についたら、ちゃんといれかわるから」
「ひかる――」
「思いっきり走るって、気持ちいいね。こんな気持ちよさ、あたし、ずっと忘れてた」
ひかるはうれしそうに、ちょっとはずかしそうに、笑ってみせた。
「もうちょっとだけ、走りたいんだ。いいでしょ?」
――走ることが、気持ちいい?
そんなこと、考えたこともなかった。
走ったり、歩道橋の階段を一段飛ばしに駆けあがったり、そんなこと、ちっとも特別なことじゃない。なにも考えなくても、からだが勝手に動くことだ。
でも。
「ひかる」
ひかるはちょっと不安そうに、光を見上げている。
――ひかるが、そんなに楽しいのなら。
ひかるは幽霊だ。ひかるには、もうからだがない。
だから、光にとっては当たり前のことでも、うれしくて楽しくてしかたがないのだろう。
「うん、いいよ」
光はうなずいた。
「家に帰るまでなら。そのかわり、寄り道しないでよ」
「わかった。約束する!」
言ったとたん、ひかるは走りだした。さっきよりもずっと早く、うれしそうに。
歩道橋の階段も、まるで背中に羽根がはえたみたいに、かるがると駆け上がっていく。
「あ、待ってよ、ひかる!」
光もふわふわしながら、あわててそのあとをおいかけた。
家に帰りつくと、約束どおり、ひかるは光にからだをあけわたした。
「……なんか、へんな感じ」
もとどおりになったからだをながめて、光はつぶやいた。
ほほをさわると、指先が冷たい。柱の角に足をぶつけると、とっても痛い。
そんな当たり前の感覚が、なんだかとても不思議な、初めて味わうようなものに思える。
なにもかもが新しくて、どきどきすることばかりのようだ。
幽霊になって、すべての感覚をうしなっていたのは、ほんの半日ほどのことだったのに。
――ひかるも、こんな感じだったのかな。
それをたずねようとすると、
「ああ、やっぱりちょっと疲れちゃったかな。あたし、少し寝る」
ひかるは宙に浮いたまま、くるっと光に背中を向けた。
「幽霊も疲れるの?」
「うん、まあね」
「あれ……ひかる? なんだか、少しからだが薄くなってない?」
「え、そう?」
半透明のひかるの姿。それが、朝よりももっと透けているように見える。
夕方になって、部屋の中が薄暗いせいだろうか。
ひかるは背中を向けたまま、なにも答えなかった。
「眠っちゃったの、ひかる?」
光はそれ以上、ひかるに話しかけるのをやめた。疲れているなら、そっとしておいたほうがいいと思ったのだ。
「宿題でもやろうかな」
机に向かい、算数のドリルを広げる。
部屋の中は、しんと静まりかえっていた。光がえんぴつで文字を書く、小さな音しか聞こえない。
ふりかえってたしかめなければ、ひかるがそこにいることも、光にはつたわってこない。
――ひかるの寝息が聞こえたらいいのにな。
光はふと、そんなことを思った。
やがて、夕方六時をすぎるころ、お母さんが帰ってきた。
「ただいま、光。遅くなってごめんね。すぐご飯にするから」
晩ご飯のおかずはサケのホイル焼きに野菜炒め、かぼちゃの煮物。光の大好物ばかり――というわけではなかった。どちらかというと、苦手なおかずばかりだ。
でも、
「おいしい」
かぼちゃの煮物を口に入れて、光は言った。
「これ、おいしいね、お母さん」
「え? ……どうしたの、光。あんた、煮物なんかあんまり食べなかったのに」
「うん、でも――今日、おなかすいてんのかな。なんか、すごくおいしいんだ」
ご飯も、おつけものも、おみそしるも。そうか、ぼく、毎日こんなおいしいご飯食べてたんだ、と思う。
「お母さんって、料理じょうずだよね」
「やあね。どうしたのよ、いきなり。おこづかいの値上げなら、だめよ」
「そんなんじゃないよ」
これも、ひかるが教えてくれたことなのだ。
幽霊になって、触覚も味覚も、からだじゅうのすべての感覚を一度なくしているから、ふたたび感じ取ったその感覚が、とても新鮮に、大切なものに思える。
――でも、それはきっと、ひかるにとっても同じじゃないだろうか?
本当に死んでしまったひかるだから、生きたからだで感じ取る感覚は、もっとすてきで、貴重なものに思えたんじゃないだろうか。
――だから、ひかる、あんなこと言ったんだ。もう少し、走りたいって……。
「明日のお弁当、なにがいい? おにぎり? それともサンドイッチ、つくろうか」
「え、ううん、いいよ。ふつうのご飯でさ。運動会や遠足じゃないんだもん」
「そう? でも、お母さんもはりきんなくちゃね。せっかく光にほめてもらったんだもの」
お母さんは光の顔を見つめ、にっこりと笑った。
「良かった。このごろ、光、なんだか元気がなかったから。お母さんも心配だったんだ。学校でなにかいやなことでもあったんじゃないかって。でも、やっと笑ってくれたね」
「お母さん……」
「ねえ光。なにか、つらいことがあったら、お母さんにはかくさないで。どんなことでも、お母さんに話してね。ふたりっきりの家族なんだから」
「うん」
――どうしよう。全部言ってしまおうか。学校のこと、いじめのこと。
光は迷った。
でも、いじめのことを全部お母さんにうちあけたら、ひかるのことも話さなくてはいけないだろう。
ひかるの姿は、お母さんには見えない。見えないものを、どうやって信じてもらったらいいだろう。
それに、ひかるは言っていた。まだ、最後の仕上げが残ってる、と。
ひかるには、まだ考えがあるのだ。
お母さんに話すのは、ひかるがすべての計画をやり終えてからでも、いい。
「お母さん。今はまだ、なにも言えないんだ」
まっすぐにお母さんを見て、光は言った。
「でも、言える時がきたら、必ず全部、お母さんに話すよ。だから、今はもうちょっと、待って」
「光……」
お母さんは一瞬、どうしようという顔をした。
けれどすぐに、光を見つめてうなずいた。
「わかった。あんたがそう言うなら、お母さんも、今はなにも聞かないよ」
「お母さん!」
「でも、いつか必ず、お母さんに話してね。これだけは忘れないで、光。どんなことがあったって、お母さんはあんたの味方。絶対に、あんたを守るからね」
うん、と、光はうなずいたつもりだった。けれどそれは、声にならなかった。
涙をがまんするだけで、せいいっぱいだった。
1
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

転生妃は後宮学園でのんびりしたい~冷徹皇帝の胃袋掴んだら、なぜか溺愛ルート始まりました!?~
☆ほしい
児童書・童話
平凡な女子高生だった私・茉莉(まり)は、交通事故に遭い、目覚めると中華風異世界・彩雲国の後宮に住む“嫌われ者の妃”・麗霞(れいか)に転生していた!
麗霞は毒婦だと噂され、冷徹非情で有名な若き皇帝・暁からは見向きもされない最悪の状況。面倒な権力争いを避け、前世の知識を活かして、後宮の学園で美味しいお菓子でも作りのんびり過ごしたい…そう思っていたのに、気まぐれに献上した「プリン」が、甘いものに興味がないはずの皇帝の胃袋を掴んでしまった!
「…面白い。明日もこれを作れ」
それをきっかけに、なぜか暁がわからの好感度が急上昇! 嫉妬する他の妃たちからの嫌がらせも、持ち前の雑草魂と現代知識で次々解決! 平穏なスローライフを目指す、転生妃の爽快成り上がり後宮ファンタジー!

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

モブの私が理想語ったら主役級な彼が翌日その通りにイメチェンしてきた話……する?
待鳥園子
児童書・童話
ある日。教室の中で、自分の理想の男の子について語った澪。
けど、その篤実に同じクラスの主役級男子鷹羽日向くんが、自分が希望した理想通りにイメチェンをして来た!
……え? どうして。私の話を聞いていた訳ではなくて、偶然だよね?
何もかも、私の勘違いだよね?
信じられないことに鷹羽くんが私に告白してきたんだけど、私たちはすんなり付き合う……なんてこともなく、なんだか良くわからないことになってきて?!
【第2回きずな児童書大賞】で奨励賞受賞出来ました♡ありがとうございます!
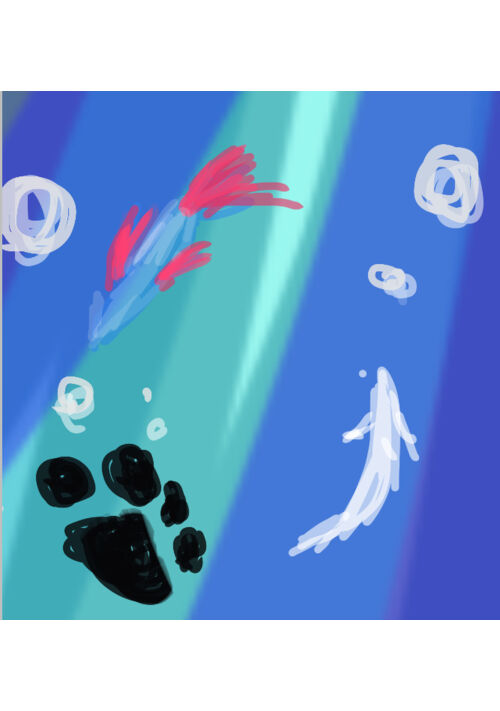
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎

ホントのキモチ!
望月くらげ
児童書・童話
中学二年生の凜の学校には人気者の双子、樹と蒼がいる。
樹は女子に、蒼は男子に大人気。凜も樹に片思いをしていた。
けれど、大人しい凜は樹に挨拶すら自分からはできずにいた。
放課後の教室で一人きりでいる樹と出会った凜は勢いから告白してしまう。
樹からの返事は「俺も好きだった」というものだった。
けれど、凜が樹だと思って告白したのは、蒼だった……!
今さら間違いだったと言えず蒼と付き合うことになるが――。
ホントのキモチを伝えることができないふたり(さんにん?)の
ドキドキもだもだ学園ラブストーリー。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















