3 / 4
3 大人の覚悟
しおりを挟む
次の日、光はお母さんにつくってもらったお弁当を持って、家を出た。
「お弁当の袋、あんまり揺らしちゃだめよ」
「うん、わかってる。行ってきまーす!」
ひかるもあいかわらずふわふわと、光のあとをついてきた。
「だいじょうぶ、ひかる?」
「うん、もう平気。さーて、今日もがんばるよっ!」
ひかるははりきって答えた。
きのうは少し薄くなっているみたいに見えた姿も、今朝はいつもと変わらない。それとも、明るい光の下で見ているから、透明度の変化がわかりにくいだけだろうか。
でも、これだけ元気なら、心配はいらないな、と光は思った。
ゆうべはベッドに入る前に、もう一度ひかると入れかわった。
「ひかる。夜9時までなら、ぼくのからだ、使ってていいよ」
「え、どうして? あ、わかった。宿題をあたしにやらせる気でしょ」
「そんなんじゃないよ。ただ……、マンガ、読みかけなんだろ?」
光は本棚に並べたマンガのコミックスを指さした。おととい、ひかるが勝手に光のからだを使って、読みふけっていたマンガだ。
「ゲームも、やっていいよ。わかんないとこは、教えてあげる。宿題はさっき全部やっちゃったから、今夜は寝るまで遊んでても、だいじょうぶだよ」
「ほんと!? ありがと、光!」
そして、お風呂からあがったあと、からだをひかるに貸したのだ。
ひかるはゲームに夢中になった。
「だめだよ、ひかる! そこでジャンプして、崖の上のアイテム、とらなくちゃ! そのアイテムがないと、3面のボスは絶対倒せないんだ」
「そうなの!? よーし、今度こそぉ!」
そのゲームは一年も前に発売されたもので、光はとっくに飽きていた。
でも、ひかるはコントローラを握りしめ、懸命にクリアをめざした。
「ヘンなの。大人のくせに、ゲームやマンガに夢中なんてさ。こどもみたいじゃん」
「別にいいじゃない。大人になったって、楽しいものは楽しいんだから」
半透明になった光を見上げ、ひかるはにこっと笑ってみせた。
そんなこと、想像したこともなかった。
光の知っている大人は、みんな、いつもとてもつまらなさそうで、この世に楽しいことなんてなにひとつない、とでも言いそうな顔をしていた。
大人になってしまったら、こどもの時にはこんなに楽しいゲームやマンガ、公園でのサッカーも昆虫採集も、全部、つまらなくなってしまうのかもしれないと、光は思っていたのだ。
それが大人になることなんだ、と。
でも、ひかるは違う。
光が飽きてしまったマンガだってゲームだって、目をきらきらさせて手にとっている。いいや、ただ走ることだってジャンプすることだって、とても楽しそうだ。
それが、光にはなぜだかとても、うれしかった。
ひかるがこんなに喜ぶなら、もうちょっと、からだを貸してあげてもいいかな。そう思う。
――ひかるが喜ぶと、ぼくもうれしい。
それは、なんだかちょっとくすぐったくて、笑い出したくなるような、胸の奥がぎゅっとなるような、ふしぎな感覚だった。
「光、もう9時半よ。ゲームはもう終わりにして、早く寝なさい」
ドアの外からお母さんの声が聞こえて、ようやくふたりはゲームをやめた。
「はあーい!」
ベッドに入る前に、ふたたび入れかわる。
からだ中を裏返しにされるようなあの感じにも、もうだいぶ慣れてきた。
パジャマに着替えようとした時、ひかるがふと、机の上を指さした。
「あら、光。あんた、ずいぶんいいもの持ってんじゃない?」
「ああ、それ……」
それは、ヘッドフォンタイプのデジタルオーディオプレイヤーだった。
パソコンなどで音楽をダウンロードし、数㎝角のメモリカードに記憶する。それを再生するためのデジタル機器だ。
オフホワイトの細長いメカは、手の中にかんたんに握りこめてしまうほど、小さくて軽い。
「それ、だいぶ前に、九州のばあちゃんがまちがえて贈ってくれたんだよ」
「まちがえた?」
「ほら、ちょっと前のゲーム機のコントローラに、なんとなく似てない? あのコードレスコントローラのゲーム機がほしいって、ぼく、ばあちゃんに言ったことがあるんだ。そしたらばあちゃん、まちがえて、これを誕生日のプレゼントに贈ってくれてさ」
「うーん……。まあ、似てると言えば、似てる、かもね……」
似ているのは、コントローラだけ。
ばあちゃんは、テレビのCMに映っているコントローラのほかに、ゲーム機本体があるんだっていうことを、理解していなかったわけだ。
プレゼントがまちがっていたことは、ひかるはばあちゃんに今でも言っていない。
「ほんとはぼく、あんまり音楽とか聴かないんだけど。でもさ、テレビの録画のタイマー予約もろくにできないばあちゃんが、いっしょうけんめい電器屋さんでこれ探して、買ってくれたんだって思うと、すっげーうれしかった」
「そう」
ロングヘアのきれいな姿に戻ったひかるは、優しくほほえんで、うなずいた。
「やっぱり、へんかな、ぼく。……ばかなのかな」
「ううん。そんなことない。あんたのその気持ちは、とっても大切なものだと思う」
そんなふうに言われると、すごく照れくさい。
見上げたひかるの笑顔も、なんだかいつもよりずっときれいに思えてしまう。
「でも、これがあるなら、話が早いわ。明日、これ、学校に持ってくからね」
「え。だめだよ。こういうの、学校に持ってっちゃいけないんだ」
「いいから。先生に取り上げられるようなヘマは、絶対しないわよ」
だめだと言うなら、食物アレルギーでもないのに学校にお弁当を持っていくのも、だめなはずだ。
光はそう思い、あまり強くひかるを止めなかった。
ひかるにはきっと、なにか考えがあるのだ。
そして今朝、学校へ行く途中、またいつものビルの陰で、ふたりは入れかわった。
ひかるが光のからだに入り、光は半透明の幽霊になる。
入れかわるとすぐに、ひかるは早足で歩き出した。きゅっと唇をかみしめて、まっすぐに前を向き、ためらう様子もない。
光も、遅れないようにふわふわとついていく。
そして、ななめ上から声をかけた。
「ねえ、ひかる。怖くないの?」
「なにが?」
「だって、きのうのことくらいで、森本たちがおとなしくなるわけないじゃん。絶対、なんかしかえししようとするに決まってるよ」
ひかるは光を見上げ、口のはしをきゅっとあげて、笑った。
「なんだ、そんなこと。怖くないよ。きのうのこと、あんただって全部見てたでしょ。あの連中がなにやったって――」
「そうじゃないよ!」
光は思わず、大きな声を出した。
「……わかってる。森本たちがなにやったって、ひかるはすぐにやり返せるよね。ひかるは頭がいいし、勇気もあるし――。でも、そうしたら森本たちはまた、ひかるにやり返そうとするよ。それに対して、ひかるがまたしかえししたら……、いつまでたっても、止まらないよ。おたがいにしかえしのくりかえしになっちゃう」
いじめやしかえしの連鎖が止まらなくなったら。
毎日毎日、おたがいに、今日はあいつにどんないやがらせをしてやろう、あいつは自分にどんなひどいことをする気だろうと、そればかりを考えてすごすなんて。
「そんなの……、やだよ」
光はぽつりとつぶやいた。
「わかってるよ」
ひかるは、短く答えた。
その目には、あの強い自信が満ちている。
「そうさせないために、あんたのコレを借りたのよ」
ひかるの手には、あのデジタルオーディオプレイヤーがあった。
そんなものがなんの役に立つの? と、光がたずねる前に、
「ほんと、不便だよね。こどもってさ。制約ばっか多くって」
ぽつっと、ひとりごとみたいにひかるは言った。
「え、どういうこと?」
制約て、いろんな決まりや、行動をしばるもののことだ。
それなら、大人のほうがずっと多いのに。責任とか、やらなきゃいけないこととか。
わからない? と、ひかるは光を見上げ、小さく首をかしげてみせた。
そのしぐさが、なんだかとっても女の子っぽくて、可愛い。
光はちょっとドキドキしてしまった。
――ヘ、ヘンなの。だってこれは、ぼくのからだなのに。ぼくのからだ、ぼくの顔を見て、可愛い、なんてさ。
「あたしがこのへんで死んだ日、あたし、一人で映画観に行ってたのよ」
「一人で?」
「そう。でもかんちがいしないでよ。あたしにだって、たくさん友達はいたんだから。いっしょにご飯食べたり、旅行に行ったり――。でも、映画に行く時は、たいがい一人なの。あたしの友達、みんな女の子らしく、ラブコメとかロマンチックな純愛映画が好きでさ。でもあたしは、爆発ドカドカ乱闘バキバキのアクション映画のほうが好きなのよ」
「ひ、ひかる……」
光は思わずためいきをついた。その言葉が、あんまりにもひかるらしくて。
「だからって、どっちかの好みにあわせて、片方は全然興味ない映画を観るなんて、ばかばかしいと思わない? だからあたし、映画観る時はたいてい一人なの。友達も、誰かほかの人さそって映画に行くはずよ」
「でも、それって……」
「目的に合わせて友達を都合良く使い分けてるみたいで、いや?」
「う……」
そのとおりだと、光は思った。
でもそんなことを言ったら、ひかるをけなしているみたいだ。だからだまっていたのに、そのものずばりを言い当てられてしまった。
光はしかたなくうなずく。
「そうだよね。子供の社会のルールじゃ、きっとそうだと思う」
「子供の社会?」
「でもね、大人の社会じゃ、違うの。そういうのは、相手の好みや個性を尊重してるって言うのよ」
「……そ、んちょう?」
ひかるはにこっと笑った。
「そう。目的や時間に合わせて付き合う人を変えるのは、悪いことでもなんでもないの。当たり前のことなんだよ。友達だからって、いつもいつもべったりいっしょにいなきゃいけないなんてこと、ないんだ」
ゆっくりと歩きながら、ひかるは言った。すれちがう人には聞こえないよう、小さな声で。
「うまく趣味の合う人がいなかったら、べつにひとりでいたっていい。ひとりで映画観たり、お店に入ったり、旅行したり……それはちっとも、おかしなことじゃないの」
たしかにそうだ。
ファミレスでもファーストフードでも、ひとりで食事している大人なんて別に珍しくない。それを、誰も不思議だなんて思わない。
でも、子供にはそれは無理だ。
映画館だって、光の年令じゃあ、ひとりで入ろうとしたらきっと、まわりはおかしいと思うだろう。
「でも、こどもにはそれは許されないよね。まわりの大人はみんな言うもの、『クラス全員、仲良くしなきゃいけません』『ひとりでも多く友達を作りましょう』……そんなのむりだって、わかってるのにね」
「うん……。そうなんだ。ぼくもそれ、おかしいって思ってたんだ」
先生たちは言う。いじめをなくすには、いじめている子といじめられている子が仲良く友達になればいいんだって。
でも、そんなこと、絶対に無理だ。
光は、森本たちとなんか、絶対に仲良くなりたくなんか、ない。
森本たちと仲良くなるってことは、あいつらのいじめのグループにくわわるっていうことだ。
いじめられるつらさは、誰よりも光自身が知っている。
その自分が、友達づきあいを保つためにほかの誰かをいじめなきゃいけないなら。
――友達なんか、いらないよ。
ひとりでいれば、誰もいじめずにいられるなら。
ひとりっきりでいたって、いいんだ。
たしかに、ひとりで遊んだり、本を読んだりするのは、ちょっと淋しい。
でも、誰かといっしょにすごすためだけに、ほかの誰かを犠牲にするくらいなら、そんな淋しさなんて、ちっともつらくない。
そうだ。クラスの中で誰も光と口をきいてくれなくたって、もうそんなこと、なんでもない。
向こうが口をきいてくれないんじゃない、話す必要がないから自分が黙っているだけだと思えばいい。
ただ、理由もなく殴られたり、持ち物を壊されたり、そういう目に見える大きな被害さえなければ、一日中ひとりでいることくらい、どうということはないんだ。
――あとは、光のかわりに殴られるやつが出てこなければ、それで充分だ。
でも、そんなことはどうしても言えなかった。
「ぼく、友達いりません」
なんて。
ひかるはその光の気持ちを、わかってくれている。
「自分で選んでひとりで行動する子は、『協調性がない』『内向的』『コミュニケーション能力に問題あり』って決めつけられちゃう。子供はね、ひとりでなにかするってこと、許されないのよ。特に学校の中じゃね」
「うん……」
たぶん、そうだろう。
めだった友達がいない生徒の通信簿には、きっとそういうコメントがつけられてしまうにちがいない。
「人とコミュニケーションすることは、大事だよ。友達だって、いっぱいいればきっと楽しい。学校で言われることは、うそじゃないよ」
「でも――」
「うそじゃない。それはね、理想なの」
説明するひかるの表情は――光の顔であるのに――とても大人びて見えた。
やっぱりひかるは大人なんだ。そう思う。光のわからないことを、こうして教えてくれる。
「理想は理想。やっぱり現実とは、少しズレちゃってんだよね」
ちょっとため息をついて、ひかるは言った。
「世界中の人と仲良くなれたら、そりゃあ、いいよね。でもそんなこと、絶対むり。誰だって、キライなヤツや苦手なヤツはいる。でも学校ん中じゃそれは許されない。同じクラスになった以上、なにがなんでも仲良しになんなきゃいけないなんてね。大人はいつもそうやって、子供に建て前ばっかり押しつけるんだ」
「たてまえ……?」
「人間が集団になれば、キライなヤツが出てくるのは当然。それが本音。大人はちゃんと、本音に従って生きてる。キライなヤツはキライ、仲良く友達になる必要なんかないってね。でもこどもには、同じことを許さないんだよね」
つまり、光が森本たちとは友達になんかなりたくない、あいつらと仲良しごっこするために誰かをいじめるくらいなら、卒業までずっと誰とも口をきかなくてもいいと思うのも――本音なんだろうか?
大人には、そういう生き方も許されているの?
「一人でいることは、たしかに淋しいよ。不安なこともいっぱいある。たとえば病気になっても、誰も看病してくれない。どんなにつらくたって、一人で病院行って、一人で寝てなきゃいけない。おなかすいたって、誰もおかゆ作ってくれない。自分でキッチンに立って、作らなくちゃ」
「うん……」
だから、大人たちは言うのだろう。一人でいてはいけません、できるだけたくさん友達を作りなさい、と。
「それでも、一人でいたいと思うなら、一人きりでだって、かまわないんだよ」
ひかるはごくふつうの顔をして、にこっと笑った。
「誰かといっしょにいることは、とても安心だよね。困った時には助けてもらえる。そのかわり、いっしょにいる人に合わせなくちゃいけないことも、いっぱいある。お互いに我慢して、遠慮したり気ぃ使ったり……。そういううざったさを我慢して、誰かといっしょにいる安心を選ぶか。それともひとりでいる気ままさを選んで、不安を我慢するか。どっちを選ぶかは、本人の自由」
「自由――」
「そう。大人には、それがあるの。自分の生き方を自分で決める、自由」
たしかに、子供にはそれがない。自分一人で生きていくことなんかできないし、まわりの大人たちはみんな、ああしなさいこうしなさいと、命令ばかりしてくる。それに従わない子供は「悪い子」になってしまう。
大人になれば、もう誰からも命令されない。
「もちろん、選んだ生き方が一〇〇%カンペキに幸せなんてこと、ありえない。どんな道を選んだって、うまくいかないこと、不都合なこと、つらいこと哀しいこと、いっぱいある。それをみぃんな受け入れて、これが自分の選んだことなんだってちゃんと納得しなきゃいけない。誰かのせいにしちゃいけない。その覚悟が必要なんだよ、大人にはね」
大人の、覚悟。
自分のことは、自分で考えて、自分で決める。その結果は、悪いことも苦しいこともみんなふくめて、自分で受けとめる。人のせいにしない。
自分の決断、自分の力で生きられる。
そのかわり、誰も守ってくれない。
それが、大人の覚悟。
――それがあるから、ひかるはそんなふうに、笑っていられるの?
なにも怖くないよって、言えるの?
その疑問を、光が口にしようとした時。
「ほら、急ごう! このままじゃ、遅刻しちゃうぞ!」
ひかるは全速力で走りだした。
「あ、待ってよ、ひかる!」
光も、そのあとを追いかけるしかなかった。
いっしょうけんめい走ったおかげか、ひかると光は、どうにか遅刻せずに教室に入ることができた。
六年B組の教室は、気味が悪いくらい静かだった。
ひかるが入っていくと、みんな、じっとその姿を目で追いかける。
けれどもう、にやにや笑ったり、ばかにしたような顔はしていない。
それどころか、みんな、ひどく気味の悪いもの、おっかないものを見てしまったような顔をしている。たとえて言うなら、車に轢かれてしまった犬や猫の死骸だ。怖いし、気持ち悪いし、けして見たいものじゃない。なのにどうしても、目がそっちへ行ってしまう。そんな感じだった。
そんな視線の中を、ひかるは少しも怖がらず、まっすぐに自分の席へ歩いていった。
――どうしてだろう。ひかるは本当に、なにも怖くないんだろうか。
ひかるのうしろをふわふわとついていきながら、光は思った。
ぼくなんて、世界中、怖いものだらけなのに。
ひかるが一度死んでしまった幽霊だから? それとも……大人だから?
大人になれば、ひかるみたいに、怖いものなんてなにもなくなるの?
でも、同じ大人でも、相沢先生はいつもびくびくおどおどしている。ほかの先生たちだって、そうだ。
いじめのリーダーである森本になにか言われるよりも、被害者の光に話しかけられるほうが、先生たちにはつらく、怖ろしいことのようだ。
光がなにか言おうとすると、相沢先生はいつも真っ青になって、泣きそうな表情になる。おねがいだから、私にこんな怖いものを見せないで、とでも言いだしそうだった。
――ひかるは本当に、なんにも怖くないの? なにがあっても、平気なの?
怖くても我慢する、という方法を、ひかるは選んだから?
今、それをひかるにたずねることはできない。
それが、光にはひどくもどかしかった。
やがてチャイムが鳴り、いつものように相沢先生が教室に入ってきた。
「みんな、おはよう」
相沢先生は友達みたいに生徒たちへ話しかけるけれど、けして生徒ひとりひとりと目を合わせようとしない。光はそのことに気がついた。
それどころか先生は、いつも、どこか違うところばかりを見ている。
クラスメイトたちは、それに気がついていないのだろう。
今までは、みんな、光をいじめることに夢中で、先生の様子なんてろくに見ていなかった。そして今は、ひかるのことが怖くて、先生なんかにかまっていられない。
そして、授業が始まった。
息がつまるような重苦しい静けさは、授業が始まっても、変わらなかった。
聞こえるのは、先生の声だけだ。みんな、おしゃべりもしない。
だからと言って、みんな、授業に集中しているわけでもない。
生徒たちは全員、ひどく上の空だった。
ある者はうつむいたまま石みたいに固まって、身動きひとつしない。ある者は反対に、まわりを気にして、きょろきょろよそ見ばかりしている。
窓ぎわの席の高倉は、じっとなにかを考え込んでいるみたいだった。
その表情はひどく不機嫌そうで、世界中のなにもかもに対して、腹が立ってしょうがない、という顔に見える。
森本はうしろのほうの席で、ずっとひかるの背中をにらんでいた。その顔には、反省の様子なんてちっともうかがえない。
――やっぱりそうだ。あいつ、またなにかやるつもりだ。
いざとなったら、ぼくがひかると入れかわろう。光はそう覚悟を決めた。
ひかるはぼくのために、いろんなことを考えて、やってくれた。ぼくのために、ひかるにつらい思いをさせることなんて、できない。
あのからだはもともと光のものだ、光が強くからだに戻りたいと念じれば、ひかるの意識を追い出すこともできるはずだ。ひかるだってそう言っていた。
そうして、時間だけがのろのろとすぎていった。
何回かチャイムが鳴り、気がつけば、午前中の授業は終わりになっていた。
「え? もう四時間めも終わり?」
幽霊になった光は、おなかもすかない。そのせいか、時間の流れがどうもぴんとこない。
チャイムが鳴ると同時に、森本が椅子を蹴って立ち上がった。
先生がまた教室を出てもいないのに、福田や金子たちを引きつれて、教室を飛び出していく。
「なんだ、あいつら……? 給食当番でもないくせに」
ちょっと考えて、光はすぐに彼らの目的に気がついた。
森本たちは、ひかるより先に給食を持ってくるつもりなのだ。きのうみたいなことになっては、たまらないから。
光の予想どおり、森本たちは給食のワゴンをがっちり取り囲んで運んできた。
教室の中へ運び入れると、まるでバリケードみたいに、その前に並んで立ちふさがった。
森本はひかるをにらみつけて、言った。
「残念だったな。てめえに食わせるメシなんか、ねえよ!」
クラス全員が、ふたたび森本の味方についていた。
もともとの給食当番がパンや牛乳をくばり始める。が、ひかるの席は避けて通る。おかずをつぎわける者も同じだ。
ひかるの姿など見えない、声も聞こえない、というように、無視している。
相沢先生は、まるで自分がいじめられているみたいな顔をして、声も出せずにおろおろしているだけだ。
おかずやパンがのったトレイを持って、森本がひかるの横を通り過ぎる。福田や金子も同じように、そのあとに続いた。
みんな、勝ち誇った表情だ。
ひかるをのぞいて、クラスメイト全員に給食がくばられた。相沢先生の机にも、トレイがのせられる。
そしていつもどおり、日直の合図で全員声をそろえて「いただきます」を言う。
「ざまあみろ。これからずっと、卒業するまでてめえは給食抜きだ」
森本がひかるをあざ笑った。
そうだそうだ、と、まわりの生徒たちもいっせいにはやしたてる。おまえになんか給食食わせてたまるか、と。
「別にかまわねえよ」
けろりとして、ひかるは言った。
「オレ、家から弁当持ってきたから」
そしてリュックの中から、お弁当を取り出す。
――すごいや、ひかる!
空中で、光は思わずバンザイしそうになった。
ひかるには、森本たちの考えなんて、とっくに全部お見通しだったのだ。
「今日のおかずはなにかなーっと。やったぁ、母さん、オレの好きなもんばっか入れてくれてる! とりのからあげに、きんぴらに……おにぎりは、めんたいこだ!」
お弁当箱のふたを開け、ひかるは明るい声ではしゃいだ。
クラス全員が声も出せずに、ひかるを見つめていた。
「どしたんだよ? おまえら、給食食べないの?」
運の悪いことに、今日の給食は、生徒たちに一番評判の悪いもやしのスープにサバの竜田揚げだった。ひかるのお弁当にくらべると、さらに魅力がなくなってしまう。
みんな、ひかるがおいしそうにお弁当を食べるのを、ひどく恨めしそうに横目でながめていた。
「井上くん……。だめよ、ひとりだけお弁当持ってきたりしちゃ」
今にも泣きそうな声で、相沢先生が言った。
「学校は、みんなでいっしょに、同じことをする場所です。ひとりだけ違うことをしたら、だめなのよ」
「でも先生。オレの分の給食はないって、みんな言ってますよ」
怒りもせず、ひかるは淡々と答える。
「給食がないんだから、弁当持ってくるしかないでしょう」
「それは……」
相沢先生は、さらに泣きそうになった。いや、もう泣いていた。
「わかりました。明日から、井上くんの分の給食がなかったら、先生のをあげます。だからもう、お弁当は持ってこないで。みんなも、お願いね」
はーい……という元気のない声が、まばらにあがった。
森本たちも、まさか先生の分の給食を用意しないわけにはいかないだろう。だって相沢先生は、今までずっと森本たちの味方だったのだから。
今だって、ひかるから給食を取り上げたクラスの連中を叱らずに、ひかるに「だめ」と言った。
相沢先生の給食をひかるに食べさせるくらいなら、最初からひかるにも給食をくばるはずだ。
またも、ひかるの思い通りになった。ひかるが勝ったのだ。
でもそのせいで、クラスの空気はさらに悪くなった。
ひかるをにらむみんなの目が、ものすごく憎らしそうに、恨めしそうになっている。
ひかるのせいで先生から叱られた、先生が泣いているのもすべてひかるのせいだと、みんなは思っているのかもしれない。
昼休みが終わり、午後の授業が始まっても、クラスのふんいきは最悪のままだった。
クラス中、今にもバチバチ火花が飛びそうに、緊張している。
相沢先生も、教科書を読む声がとても小さくて、ほとんど聞き取れないくらいだ。
その中で、ただひかる一人だけが、落ちついてのんびりした表情だった。
――どうしてそんなに落ちついていられるのさ、ひかる。
光の問いかけは、声にならない。
もうすぐ、ひどいことが起こる。誰にだってわかる。もう止められない。
――なのに、どうしてそんなに平気なの、ひかる!
覚悟、してるから?
森本たちにやり返しちゃった以上、もっとひどいめに合わされるのも、覚悟してるってこと?
それが……、大人の覚悟なの?
なんか、ちがう。
光はそう思った。
もしも本当に、ひかるの言う覚悟が、光の考えているとおりのものだとしたら。
それは――なんか、ちがうよ、ひかる。
どこがどうって、うまく言えないけど、やっぱりちがうと思うんだ。
けれど今、それをひかるに言うこともできない。
光の声はひかる以外には聞こえないけれど、ひかるも光の言葉が聞こえたよ、と態度であらわすことはできないからだ。
光が一方的にしゃべっていたって、ひかるにこの思いがつたわるとも思えない。
そうしているうちに、とうとう終業チャイムが鳴ってしまった。
「おい、てめえ。なに考えてんだよッ!」
森本がどなった。
ひかるのまわりを、十数人の男子生徒がとりかこんでいる。
ホームルームが終わると同時に、ひかるを逃がすまいといっせいにかこんでしまったのだ。
女子たちは、教室のすみにひとかたまりになっている。
相沢先生はさっさと教室から逃げ出してしまっていた。
「ざけんじゃねェぞっ!」
「なにチョーシこいてんだよ!」
「なんとか言えよ、てめえッ!!」
森本が力まかせにひかるの肩を突き飛ばす。
「――ひかる!」
光は思わず叫んだ。
「乱暴すんなよ、森本! 相手は女の人なんだぞ!」
森本の腕をつかんで止めようとしても、実体を持たない光の両手は、森本のからだを通り抜けてしまう。
「答えろよ、おらァッ!!」
森本はいきなりひかるの服をつかんだ。
その脅しにも、ひかるは顔色ひとつ変えなかった。
「おまえ、オレにさわっていいのか? 井上菌に感染すんじゃなかったのかよ」
「うるせえッ!」
悲鳴みたいに森本はわめいた。顔は真っ赤で、目も充血している。
反対にひかるは、ひどく淡々としていた。怒りも恐怖も、なんの感情も読みとれない。
そんなひかるの表情に、森本はますます腹を立てる。
「ふ、ふざけんな、てめえーッ!!」
森本は力いっぱい、ひかるを突き飛ばした。
ひかるは後ろの机にぶつかり、はでな音をたてて床に倒れ込む。
きゃあッ、と、女子たちが小さく悲鳴をあげた。
でも、誰も動こうとしない。ふつう、教室でケンカが始まったら、止めてくれる先生を呼びに行くものなのに。
でもこれは、ふつうのケンカじゃない。
みんな、知っているのだ。これはいじめの延長であり、このクラスにいるモノはみんな、いじめに加わっていたということを。
ただ一人、いじめの被害者だった井上光をのぞいて、全員が加害者だということを。
「オレが、なにしたって言うんだ?」
ひかるはゆっくりと立ち上がり、静かに言った。
おちついて、けして大きくはないけれど、その場にいる者みんなの耳にはっきりと届く声だった。
「オレはたしかに、おまえらがキライだ。でもオレはおまえらを殴ってないし、持ち物をとったりこわしたり、してない。昨日の給食だって、みんな平等にくばったし、サッカーも、先生に注意されたらすぐに、森本、おまえにボール回してやったじゃないか。給食食わなかったのも、サッカーやらなかったのも、みんな、おまえらの勝手だ。オレのせいじゃない」
ひかるの言っていることは、正しい。
――でも、ひかる。そうじゃないんだよ。
光はそう叫びたかった。
いくらひかるが正しくたって、それはただの理屈だ。そのとおりにいかないことなんて、山ほどある。
第一、なんでもかんでも理屈どおりになるのなら、いじめなんて起きるわけないじゃないか!
「それともおまえらは、オレが自分の身を守るのも、いけないって言うのか? オレは――井上光は、クラス全員のうさばらしの道具として、文句も言わずに、ただ毎日毎日、死ぬまでいじめられ続けてりゃあいいって、そう言うのか!?」
「あ……ああ、そうだよ!!」
森本がめちゃくちゃに叫んだ。
「てめえはそのために、このクラスにいるんだ!! そう決まってんだよ! 違うと思うなら、まわりに訊いてみろ!!」
――そんな!
この状況で、ひかるをかばえる者なんて、いるはずがない。そんなことをしたら、今度は自分がいじめられてしまうから。
光の考えどおり、森本の言葉を否定する者はひとりもいなかった。
クラスメイトたちはみんな顔を伏せ、石みたいに固まって、互いに視線を合わせようともしない。
「そら見ろ。これで決まり、多数決だ!」
勝ち誇って、森本はわめいた。
「井上光はいじめられ役、決定っ! 卒業するまでずっと、おれらのサンドバッグになるのが、おまえの役目だ!!」
「そ……そ、そうだ! 井上はサンドバッグ!」
「サンドバッグ、サンドバッグ!」
森本に同調し、一人、また一人と声をあげる。
福田が、金子が、手を叩いてはやしたてる。その声はうわずってふるえ、顔はまだ恐怖にひきつっていた。
けれどこの騒ぎにやがてクラス全員がくわわれば、もう彼らに怖いものはなくなるだろう。
クラスの運営は多数決で行われる。その多数決で「井上光はクラスのサンドバッグ」と決まったのなら、それに逆らうひかるのほうが悪いことになってしまう。
「わかったか、井上! 今度なにかしやがったら、マジぶっ殺してやっかんな! てめえはただだまって、おれらにぶっとばされてりゃいいんだよッ!!」
森本がこぶしをふりあげた。
――逃げて、ひかる! 殴られるよ!
いいや、それより早く、ひかると入れかわらなくちゃ! ひかるのかわりに、ぼくが殴られれば……!!
その時、ひかるがさっと右手をあげた。
森本が、ひかるをとりかこんでいた男子たちが、びくっとからだをふるわせる。殴られるとでも思ったのだろうか。
しかし、ひかるは右手になにかを握っていた。
それは光の部屋にあった、デジタルオーディオプレイヤーだった。
プレイヤーを高く持ち上げたまま、ひかるは指先でスイッチを操作した。
『――井上光はいじめられ役、決定っ! 卒業するまでずっと、おれらのサンドバッグになるのが、おまえの役目だ!!』
さっきの森本の声が、再生されて大きく響き渡った。
『てめえはただだまって、おれらにぶっとばされてりゃいいんだよッ!!』
「な……、なんだよ、それっ!?」
ひかるはだまって、プレイヤーを森本の目の前に突き出した。
森本もそれがなんであるか、すぐにわかったらしい。
「おまえの言ったことは、みんなこれで録音した」
ひかるはゆっくりと、感情のない声で言った。鏡みたいに澄んでおちついた目で、まっすぐに森本を見ている。
「だ、だから、なんだ! それ持って、先生たちに言いつけんのかよ! そんなことしたって無駄だって、まーだわかんねえのか、てめえ!」
先生たちはみんな、ただ光が我慢してくれることを願っている。
そうして6年B組の生徒がさっさと卒業して、問題が目の前から消えてくれることだけを。
「わかってるよ」
ひかるの表情はなにもかわらない。まるで仮面みたいだ。
けれどそれは、昨日見せた、ひどく底意地の悪いあの笑顔よりもずっと、何倍も怖かった。まるで人間じゃないみたいだった。
「学校も教育委員会も、そんなもん、誰があてにするかよ。今度おまえらがオレになにかしたら、オレはこのメモリーカードを持って、警察に駆け込んでやるッ!!」
――警察!?
クラス中が、息を呑んだ。
光も、絶句した。
「これだけはっきりした証拠があるんだ、オレが告訴すれば、警察はかならず動いてくれる。これはもう、れっきとした暴力事件だ、犯罪だ! 森本、おまえの親は、おまえがいじめなんかしていないって校長室でどなってたけど、警察が取り調べに行っても、まだ同じようにおまえを信じて、かばってくれるかな?」
「な……っ」
森本はもう、声もない。真っ赤だった顔は、今にも気絶しそうなくらい、青白くなっていた。
「オレの親は、かならずオレを信じてくれる。オレといっしょに、警察に行ってくれるはずだ。子供がここまで、命がけでやってんだ。信じない親なんかいるもんか!」
ひかるは断言した。
それを否定する声は、もうどこからも聞こえなかった。
息苦しいほどの沈黙が、教室中に広がっていった。
「こ……こわしちゃえ――」
かすれる声が、聞こえた。
「こわしちゃえよ、あんな機械……。そうすりゃ、証拠なんか、なんもなくなるんだからさ……」
がたがたとみっともなくふるえながら、福田がひかるのオーディオプレイヤーを指さしていた。
顔中に脂汗が浮いて、森本と同じくらい、福田も真っ青だ。
「し、証拠がなけりゃいいんだよ! そうすりゃ井上だって、警察なんか行けねえんだからさ!」
「そ――そうだ! そうだ、壊せ!」
「そいつを取り上げろ! 井上に勝手なことさせんな!!」
怒鳴り声があがった。
ひかるをとりかこむ輪の中から、最初はじわじわと、福田と同じようにひどく怯えた声があがる。
森本たちだけでなく、木島などほかの男子生徒も叫び出す。
やがてそれは、自暴自棄になったみたいなむちゃくちゃな大声になる。
「メモリーをこわせッ!!」
「ボコボコにしろ、二度と口がきけねえようにしちまえッ!!」
――な、なに言ってんだ、みんな!
光は思わず、ひかるの前に立ちはだかろうとした。
両手を広げ、ひかるをかばう。
けれど幽霊の光には、クラスメイトを止めることなんかできない。ひかるにつかみかかろうとする連中の腕は、光をかんたんに突き抜けてしまう。
光の姿さえ、彼らの目には見えていないのだ。
ただ一人、ひかるをのぞいて。
――ひかる、逃げて! 逃げて!!
光は懸命に叫んだ。
けれどひかるは、にこっと笑っただけだった。
まるで光に、安心して、大丈夫だよ、と語りかけるみたいに。
そしてひかるは、ふたたび声をはりあげた。
「おまえら、録音してんのが、これ一個だけだと思ってんのか!?」
「……え――っ!?」
煮えたぎる鍋みたいだった教室が、一瞬、しんと静まり返った。
「この教室ん中に、もしかしたらオレの協力者がいるかもしれねえぞ。オレに頼まれて、同じようなデジタルプレイヤーで、今のやりとりを全部録音してるヤツが……いないとでも思ってるのか?」
ひかるはわざと、ひとつひとつの言葉をくぎって、ゆっくりとしゃべった。
自分をとりかこむ生徒たち一人一人の顔を、まっすぐに、突き刺すように見ていく。
「6年B組、オレをのぞいた37人全員が、心をひとつにして、オレをいじめることを楽しんでると、おまえら、本気で信じてるか? なかにはいるはずだぜ。いじめなんてかっこ悪りい、もういい加減やめてえなって思ってるヤツがさ。そういうヤツがこっそりオレの協力者になって、ポケットに録音機械を隠し持ってるかもしれないぜ? たとえオレのメモリーカードがこわされたって、そいつが録音してくれた証拠がある。オレはなんにも困らないぜ」
「う……うそだ――。うそつくんじゃねえ、てめえッ!」
「うそだと思うなら、その証拠を出してみな? 誰もオレに協力してねえって、その証拠をさ」
ひかるの言葉に、生徒たちは男子も女子もいっせいに、自分のまわりを見回した。
自分のとなりに立っている、同じクラスメイトを。
そして、誰かと目が合うと、あわてて首を横にふる。――ううん、ちがう。自分は井上の協力者なんかじゃない、と。
みんな、必死の表情だった。
ここで井上光の協力者だとうたがわれたら、自分もいっしょにぼこぼこに殴られてしまう。
金子も福田も、森本までが、おおげさに首を横にふっていた。
けれどそれを見る目は、疑いに満ちている。ちがう、と言う言葉を、誰も信じていない。
そうだ。誰も信じられない。
このクラスの中で、本当に信じ合っている友達なんか、いない。
みんな、自分がいじめられないために、光のいじめに同調していただけなのだから。
「おまえら、ほんとバカだなあ。こんな時に、『はぁい、ボクが井上くんの協力者でーす!』なんて名乗り出るヤツがいるかよ」
ひかるはもう一度クラスメイトたちを見回し、にこっと笑いかけた。――まるで、その中に本当に自分の協力者がいるみたいに。
「いいんだぜ、今はウソついてたってさ。知らん顔してていいよ。おまえの安全を最優先しろよ。みんなといっしょにオレの悪口言ってても、オレ、ちっとも気にしねえからさ。おまえがケガしねえことのほうが、大事だよ」
ひかるの目は、誰を見てるかわからない。
森本たちが、ひかるが誰を見ているのか確かめようとすると、さっと目をそらしてしまう。
「デジタルプレイヤーも、見つからないようにうまく隠せよ。メモリーカードだけ、あとでこっそりオレに送ってくれればいいからさ」
「メモリーカード――」
その言葉に、福田たちがはっと気がついたように顔をあげた。メモリーカードを奪えばいいと、思いついたのだろう。
「あのさあ。オレが、おまえらの目の前で証拠を手渡ししてもらうと、思うのか?」
からかうように、ひかるは言った。
「家へ郵送してもらうに決まってんじゃん! おまえら、どうするよ? オレん家のポストを二十四時間見張るか? もしそうするなら、オレ、母さんの会社に送ってもらうだけだから」
「か、会社……」
「それを、どうやって止める? 母さんのバッグをひったくるか? そんなことしてみろ、オレが告訴しなくたって、おまえらは犯罪者だ!」
もう誰も、なにも言えなかった。
ひかるが一歩、前へ出る。
見えない腕に押されるように、森本が一歩、後ろへ下がった。
「オレはおまえに、なんにもする気はねえよ。森本」
静かに、ひかるは言った。
「もうオレをほっといてくれ。オレにかかわるな。オレのかわりに、誰かをいじめるな。オレが言いてえのは、ただそれだけだよ。できんだろ、そのくらい!」
強く言われても、森本はもう、返事もできなかった。
「ま、もし別のヤツがいじめられたとしても、そいつだって、オレと同じことをするはずだけどな」
そしてひかるは、もう一度デジタルオーディオプレイヤーをみんなに見えるように、持ち上げた。
「わかるよな、みんな。もうこのクラスで、いじめはできない。しない、やめた、じゃねえ。もう二度と、できないんだよ!」
やがてそれをハーフパンツのポケットにしまうと、リュックを肩にかつぎ、ひかるは一人、教室を出ていこうとした。
誰もそれを止めない。
ひかるの姿を目で追おうともしない。
そしてひかるは――井上光は、六年B組の教室をあとにした。
――わからない。
とぼとぼと自宅に向かって歩きながら、光は胸の中で、何度もくりかえした。
わからない。ほんとうにあれで、良かったんだろうか。
光は見てしまった。
あの眼。教室にいた全員の、あの眼。
それは光を見ているのではなかった。
隣にいるクラスメイト、6年B組の生徒ひとりひとりに向けられていた。
かつて光を見たのと同じ、怯えと嫌悪に満ちた眼。
見てはいけないもの、見たくないのに、どうしても目に入ってしまう、怖くてしかたがないものを見る、眼。
クラス全員が怯えていた。同じクラスメイトたちに、今朝までは仲良く友達としてつきあっていた相手に。
――こいつは、今も自分の声を録音してるんじゃないのか? なんでもないふりしているくせに、かげでこっそり、いじめの証拠を集めているんじゃないのか!?
大丈夫か、自分は大丈夫か!? こいつらに恨まれるようなことを、なにかやっていないか!? 回りの人間から憎まれていないと、本当に言い切れるか!?
誰も信じられない。声も出せない。
自分以外のクラスメイト、37人全員が、いっせいに怖ろしい敵に見えたことだろう。
それはたしかに、かつて光が味わわされた恐怖と、よく似ているけれど。
それでも、思わずにいられない。
これで、ほんとうに良かったんだろうか。
「――ひかる」
校門を出てすぐに、光はひかるを呼び止めようとした。
ひかるはちらっと、半透明になってふわふわ宙に浮いている光を、見上げた。けれど、足を止めようとはしない。
もっとも、立ち止まったところで、まわりにほかの人がいる町中では、光と話もできないのだが。
「ひかる!」
光が大声をはりあげて、ようやく、ひかるは立ち止まった。
「ぼくのからだ、返してよ」
六車線の大通り、流れる車の列をながめながら、ひかるが言った。
「あたしがやったこと、気に入らない?」
「え……?」
「これで明日から、あんたへのいじめはなくなるはずよ。少なくとも、意味もなく殴られたり、死ね、死ねって言われたり、クラス中の雑用を押しつけられたりすることはない。――ま、あんたと友達になろうってヤツも、いなくなるだろうけどね」
光は答えなかった。宙に浮いたまま、唇をぎゅっと噛みしめる。
「それともあんた、あのクラスの連中と、仲良しこよしになりたかったの?」
「……ちがう」
いじめがなくなれば、それで良かった。
ふつうに学校に行って、勉強して、物を盗られることも服を汚されることもなく、無事に毎日を過ごせれば。――そして、光のかわりにいじめられるヤツが出なければ、じゅうぶんだと思っていた。
ひかるはたしかに、その願いを叶えてくれたのだ。
……けれど。
「あれじゃ――。ぼくだけじゃない、あれじゃあ、クラス全員、ひとりも友達がいなくなっちゃったじゃないか!」
「しょうがないじゃない。もともとそういうクラスだったんだもの」
ひかるはきっぱりと言い切った。
「他人へのいじめや陰口でしか仲間意識をたもてないなんて、そんなのは友達でもなんでもない。ただの卑怯者の集まりよ」
「でも――! でも、だって……!!」
「じゃあ、あんたはいったいどうしたかったの」
ひかるの目が、まっすぐに光を見上げた。
「あのままずっといじめられ続けて、自殺に追い込まれても良かったの? あんたが死んじまったら、あんたのお母さんはどうなんのよ。クラスの連中だって、一生消えない負い目をせおうのよ。自分は、クラスメイトを殺しちまったってね。その前にあんたが不登校になっても、あんたの命だけは助かるけど、それじゃあいつらは反省なんかしない。別の誰かをいじめるだけよ。誰かが命をなくすまでね」
「それは――」
ちがう、とは、光は言えなかった。
「これで、少なくとも誰かが自殺することだけは、ない。最悪の事態だけは、さけられたのよ」
「最悪の、事態……」
ひかるの言うことは、まちがいじゃない。
光の、そしてクラスみんなの命がすくわれた。
でも。
「言ったでしょう。人間は生きているかぎり、傷つかないわけにはいかないのよ。誰もがみんな、一〇〇%しあわせになれる選択肢なんて、ありえない。どんな方法を選んだって、みんな傷ついて、ぼろぼろになる。それでも、より傷の小さいほう、少しでもマシなほうを選んで、生きていくしかないのよ」
「少しでも、マシなほうを……」
光はもう、なにも言い返せなかった。
「……ぼくのからだを、返して」
それだけを、光はぽつりと言った。
OK、というように、ひかるはうなずく。
人目につかないビルの陰で、二人は入れかわった。
「ついてこないで」
自分の身体を取り戻すと、光はこわばった声で言った。
幽霊に戻ったひかるを、もう見ようともしない。
「たぶん……、こうなるだろうなって、わかってたよ」
ひとりごとみたいに、ひかるが言う。
かすかにほほえむような、今にも泣いてしまいそうな、優しい声だった。
その言葉も、光は聞こえないふりをした。
「あたしのやり方じゃあ、あんたは絶対怒るだろうって、わかってた。――あんた、そういう子だもん。ちゃんと、別の誰かのために、喜んだり怒ったりしてあげられる子だもんね」
――わかっていたの? ひかる。
光は胸の中でつぶやいた。
けれど立ち止まり、ふりかえって、ひかるの顔を見る勇気がない。
わかっていたの? ひかるのしたことに、ぼくが怒って、ひかるを許さないだろうってわかっていて……それでもやりとげたの?
ぼくを助けるために。
……それが、大人の覚悟なの?
そうやって自分が選んだ道で、自分も、まわりも、傷ついて、傷つけられて。
その痛さも苦しさも、哀しさ、つらさ、みにくさ、みんな、受け入れて生きていくことが。
それが、大人の覚悟なの?
ひかる。
その答を、光は聞けなかった。
聞ける勇気が、覚悟が、なかった。
光はリュックをしっかりとせおうと、逃げるように走りだした。
もう一度ふりかえることすら、できなかった。
ふたたびきれいな女の人の幽霊に戻ったひかるは、歩道橋のそばにたたずみ、だまってその後ろ姿を見送っていた。
「お弁当の袋、あんまり揺らしちゃだめよ」
「うん、わかってる。行ってきまーす!」
ひかるもあいかわらずふわふわと、光のあとをついてきた。
「だいじょうぶ、ひかる?」
「うん、もう平気。さーて、今日もがんばるよっ!」
ひかるははりきって答えた。
きのうは少し薄くなっているみたいに見えた姿も、今朝はいつもと変わらない。それとも、明るい光の下で見ているから、透明度の変化がわかりにくいだけだろうか。
でも、これだけ元気なら、心配はいらないな、と光は思った。
ゆうべはベッドに入る前に、もう一度ひかると入れかわった。
「ひかる。夜9時までなら、ぼくのからだ、使ってていいよ」
「え、どうして? あ、わかった。宿題をあたしにやらせる気でしょ」
「そんなんじゃないよ。ただ……、マンガ、読みかけなんだろ?」
光は本棚に並べたマンガのコミックスを指さした。おととい、ひかるが勝手に光のからだを使って、読みふけっていたマンガだ。
「ゲームも、やっていいよ。わかんないとこは、教えてあげる。宿題はさっき全部やっちゃったから、今夜は寝るまで遊んでても、だいじょうぶだよ」
「ほんと!? ありがと、光!」
そして、お風呂からあがったあと、からだをひかるに貸したのだ。
ひかるはゲームに夢中になった。
「だめだよ、ひかる! そこでジャンプして、崖の上のアイテム、とらなくちゃ! そのアイテムがないと、3面のボスは絶対倒せないんだ」
「そうなの!? よーし、今度こそぉ!」
そのゲームは一年も前に発売されたもので、光はとっくに飽きていた。
でも、ひかるはコントローラを握りしめ、懸命にクリアをめざした。
「ヘンなの。大人のくせに、ゲームやマンガに夢中なんてさ。こどもみたいじゃん」
「別にいいじゃない。大人になったって、楽しいものは楽しいんだから」
半透明になった光を見上げ、ひかるはにこっと笑ってみせた。
そんなこと、想像したこともなかった。
光の知っている大人は、みんな、いつもとてもつまらなさそうで、この世に楽しいことなんてなにひとつない、とでも言いそうな顔をしていた。
大人になってしまったら、こどもの時にはこんなに楽しいゲームやマンガ、公園でのサッカーも昆虫採集も、全部、つまらなくなってしまうのかもしれないと、光は思っていたのだ。
それが大人になることなんだ、と。
でも、ひかるは違う。
光が飽きてしまったマンガだってゲームだって、目をきらきらさせて手にとっている。いいや、ただ走ることだってジャンプすることだって、とても楽しそうだ。
それが、光にはなぜだかとても、うれしかった。
ひかるがこんなに喜ぶなら、もうちょっと、からだを貸してあげてもいいかな。そう思う。
――ひかるが喜ぶと、ぼくもうれしい。
それは、なんだかちょっとくすぐったくて、笑い出したくなるような、胸の奥がぎゅっとなるような、ふしぎな感覚だった。
「光、もう9時半よ。ゲームはもう終わりにして、早く寝なさい」
ドアの外からお母さんの声が聞こえて、ようやくふたりはゲームをやめた。
「はあーい!」
ベッドに入る前に、ふたたび入れかわる。
からだ中を裏返しにされるようなあの感じにも、もうだいぶ慣れてきた。
パジャマに着替えようとした時、ひかるがふと、机の上を指さした。
「あら、光。あんた、ずいぶんいいもの持ってんじゃない?」
「ああ、それ……」
それは、ヘッドフォンタイプのデジタルオーディオプレイヤーだった。
パソコンなどで音楽をダウンロードし、数㎝角のメモリカードに記憶する。それを再生するためのデジタル機器だ。
オフホワイトの細長いメカは、手の中にかんたんに握りこめてしまうほど、小さくて軽い。
「それ、だいぶ前に、九州のばあちゃんがまちがえて贈ってくれたんだよ」
「まちがえた?」
「ほら、ちょっと前のゲーム機のコントローラに、なんとなく似てない? あのコードレスコントローラのゲーム機がほしいって、ぼく、ばあちゃんに言ったことがあるんだ。そしたらばあちゃん、まちがえて、これを誕生日のプレゼントに贈ってくれてさ」
「うーん……。まあ、似てると言えば、似てる、かもね……」
似ているのは、コントローラだけ。
ばあちゃんは、テレビのCMに映っているコントローラのほかに、ゲーム機本体があるんだっていうことを、理解していなかったわけだ。
プレゼントがまちがっていたことは、ひかるはばあちゃんに今でも言っていない。
「ほんとはぼく、あんまり音楽とか聴かないんだけど。でもさ、テレビの録画のタイマー予約もろくにできないばあちゃんが、いっしょうけんめい電器屋さんでこれ探して、買ってくれたんだって思うと、すっげーうれしかった」
「そう」
ロングヘアのきれいな姿に戻ったひかるは、優しくほほえんで、うなずいた。
「やっぱり、へんかな、ぼく。……ばかなのかな」
「ううん。そんなことない。あんたのその気持ちは、とっても大切なものだと思う」
そんなふうに言われると、すごく照れくさい。
見上げたひかるの笑顔も、なんだかいつもよりずっときれいに思えてしまう。
「でも、これがあるなら、話が早いわ。明日、これ、学校に持ってくからね」
「え。だめだよ。こういうの、学校に持ってっちゃいけないんだ」
「いいから。先生に取り上げられるようなヘマは、絶対しないわよ」
だめだと言うなら、食物アレルギーでもないのに学校にお弁当を持っていくのも、だめなはずだ。
光はそう思い、あまり強くひかるを止めなかった。
ひかるにはきっと、なにか考えがあるのだ。
そして今朝、学校へ行く途中、またいつものビルの陰で、ふたりは入れかわった。
ひかるが光のからだに入り、光は半透明の幽霊になる。
入れかわるとすぐに、ひかるは早足で歩き出した。きゅっと唇をかみしめて、まっすぐに前を向き、ためらう様子もない。
光も、遅れないようにふわふわとついていく。
そして、ななめ上から声をかけた。
「ねえ、ひかる。怖くないの?」
「なにが?」
「だって、きのうのことくらいで、森本たちがおとなしくなるわけないじゃん。絶対、なんかしかえししようとするに決まってるよ」
ひかるは光を見上げ、口のはしをきゅっとあげて、笑った。
「なんだ、そんなこと。怖くないよ。きのうのこと、あんただって全部見てたでしょ。あの連中がなにやったって――」
「そうじゃないよ!」
光は思わず、大きな声を出した。
「……わかってる。森本たちがなにやったって、ひかるはすぐにやり返せるよね。ひかるは頭がいいし、勇気もあるし――。でも、そうしたら森本たちはまた、ひかるにやり返そうとするよ。それに対して、ひかるがまたしかえししたら……、いつまでたっても、止まらないよ。おたがいにしかえしのくりかえしになっちゃう」
いじめやしかえしの連鎖が止まらなくなったら。
毎日毎日、おたがいに、今日はあいつにどんないやがらせをしてやろう、あいつは自分にどんなひどいことをする気だろうと、そればかりを考えてすごすなんて。
「そんなの……、やだよ」
光はぽつりとつぶやいた。
「わかってるよ」
ひかるは、短く答えた。
その目には、あの強い自信が満ちている。
「そうさせないために、あんたのコレを借りたのよ」
ひかるの手には、あのデジタルオーディオプレイヤーがあった。
そんなものがなんの役に立つの? と、光がたずねる前に、
「ほんと、不便だよね。こどもってさ。制約ばっか多くって」
ぽつっと、ひとりごとみたいにひかるは言った。
「え、どういうこと?」
制約て、いろんな決まりや、行動をしばるもののことだ。
それなら、大人のほうがずっと多いのに。責任とか、やらなきゃいけないこととか。
わからない? と、ひかるは光を見上げ、小さく首をかしげてみせた。
そのしぐさが、なんだかとっても女の子っぽくて、可愛い。
光はちょっとドキドキしてしまった。
――ヘ、ヘンなの。だってこれは、ぼくのからだなのに。ぼくのからだ、ぼくの顔を見て、可愛い、なんてさ。
「あたしがこのへんで死んだ日、あたし、一人で映画観に行ってたのよ」
「一人で?」
「そう。でもかんちがいしないでよ。あたしにだって、たくさん友達はいたんだから。いっしょにご飯食べたり、旅行に行ったり――。でも、映画に行く時は、たいがい一人なの。あたしの友達、みんな女の子らしく、ラブコメとかロマンチックな純愛映画が好きでさ。でもあたしは、爆発ドカドカ乱闘バキバキのアクション映画のほうが好きなのよ」
「ひ、ひかる……」
光は思わずためいきをついた。その言葉が、あんまりにもひかるらしくて。
「だからって、どっちかの好みにあわせて、片方は全然興味ない映画を観るなんて、ばかばかしいと思わない? だからあたし、映画観る時はたいてい一人なの。友達も、誰かほかの人さそって映画に行くはずよ」
「でも、それって……」
「目的に合わせて友達を都合良く使い分けてるみたいで、いや?」
「う……」
そのとおりだと、光は思った。
でもそんなことを言ったら、ひかるをけなしているみたいだ。だからだまっていたのに、そのものずばりを言い当てられてしまった。
光はしかたなくうなずく。
「そうだよね。子供の社会のルールじゃ、きっとそうだと思う」
「子供の社会?」
「でもね、大人の社会じゃ、違うの。そういうのは、相手の好みや個性を尊重してるって言うのよ」
「……そ、んちょう?」
ひかるはにこっと笑った。
「そう。目的や時間に合わせて付き合う人を変えるのは、悪いことでもなんでもないの。当たり前のことなんだよ。友達だからって、いつもいつもべったりいっしょにいなきゃいけないなんてこと、ないんだ」
ゆっくりと歩きながら、ひかるは言った。すれちがう人には聞こえないよう、小さな声で。
「うまく趣味の合う人がいなかったら、べつにひとりでいたっていい。ひとりで映画観たり、お店に入ったり、旅行したり……それはちっとも、おかしなことじゃないの」
たしかにそうだ。
ファミレスでもファーストフードでも、ひとりで食事している大人なんて別に珍しくない。それを、誰も不思議だなんて思わない。
でも、子供にはそれは無理だ。
映画館だって、光の年令じゃあ、ひとりで入ろうとしたらきっと、まわりはおかしいと思うだろう。
「でも、こどもにはそれは許されないよね。まわりの大人はみんな言うもの、『クラス全員、仲良くしなきゃいけません』『ひとりでも多く友達を作りましょう』……そんなのむりだって、わかってるのにね」
「うん……。そうなんだ。ぼくもそれ、おかしいって思ってたんだ」
先生たちは言う。いじめをなくすには、いじめている子といじめられている子が仲良く友達になればいいんだって。
でも、そんなこと、絶対に無理だ。
光は、森本たちとなんか、絶対に仲良くなりたくなんか、ない。
森本たちと仲良くなるってことは、あいつらのいじめのグループにくわわるっていうことだ。
いじめられるつらさは、誰よりも光自身が知っている。
その自分が、友達づきあいを保つためにほかの誰かをいじめなきゃいけないなら。
――友達なんか、いらないよ。
ひとりでいれば、誰もいじめずにいられるなら。
ひとりっきりでいたって、いいんだ。
たしかに、ひとりで遊んだり、本を読んだりするのは、ちょっと淋しい。
でも、誰かといっしょにすごすためだけに、ほかの誰かを犠牲にするくらいなら、そんな淋しさなんて、ちっともつらくない。
そうだ。クラスの中で誰も光と口をきいてくれなくたって、もうそんなこと、なんでもない。
向こうが口をきいてくれないんじゃない、話す必要がないから自分が黙っているだけだと思えばいい。
ただ、理由もなく殴られたり、持ち物を壊されたり、そういう目に見える大きな被害さえなければ、一日中ひとりでいることくらい、どうということはないんだ。
――あとは、光のかわりに殴られるやつが出てこなければ、それで充分だ。
でも、そんなことはどうしても言えなかった。
「ぼく、友達いりません」
なんて。
ひかるはその光の気持ちを、わかってくれている。
「自分で選んでひとりで行動する子は、『協調性がない』『内向的』『コミュニケーション能力に問題あり』って決めつけられちゃう。子供はね、ひとりでなにかするってこと、許されないのよ。特に学校の中じゃね」
「うん……」
たぶん、そうだろう。
めだった友達がいない生徒の通信簿には、きっとそういうコメントがつけられてしまうにちがいない。
「人とコミュニケーションすることは、大事だよ。友達だって、いっぱいいればきっと楽しい。学校で言われることは、うそじゃないよ」
「でも――」
「うそじゃない。それはね、理想なの」
説明するひかるの表情は――光の顔であるのに――とても大人びて見えた。
やっぱりひかるは大人なんだ。そう思う。光のわからないことを、こうして教えてくれる。
「理想は理想。やっぱり現実とは、少しズレちゃってんだよね」
ちょっとため息をついて、ひかるは言った。
「世界中の人と仲良くなれたら、そりゃあ、いいよね。でもそんなこと、絶対むり。誰だって、キライなヤツや苦手なヤツはいる。でも学校ん中じゃそれは許されない。同じクラスになった以上、なにがなんでも仲良しになんなきゃいけないなんてね。大人はいつもそうやって、子供に建て前ばっかり押しつけるんだ」
「たてまえ……?」
「人間が集団になれば、キライなヤツが出てくるのは当然。それが本音。大人はちゃんと、本音に従って生きてる。キライなヤツはキライ、仲良く友達になる必要なんかないってね。でもこどもには、同じことを許さないんだよね」
つまり、光が森本たちとは友達になんかなりたくない、あいつらと仲良しごっこするために誰かをいじめるくらいなら、卒業までずっと誰とも口をきかなくてもいいと思うのも――本音なんだろうか?
大人には、そういう生き方も許されているの?
「一人でいることは、たしかに淋しいよ。不安なこともいっぱいある。たとえば病気になっても、誰も看病してくれない。どんなにつらくたって、一人で病院行って、一人で寝てなきゃいけない。おなかすいたって、誰もおかゆ作ってくれない。自分でキッチンに立って、作らなくちゃ」
「うん……」
だから、大人たちは言うのだろう。一人でいてはいけません、できるだけたくさん友達を作りなさい、と。
「それでも、一人でいたいと思うなら、一人きりでだって、かまわないんだよ」
ひかるはごくふつうの顔をして、にこっと笑った。
「誰かといっしょにいることは、とても安心だよね。困った時には助けてもらえる。そのかわり、いっしょにいる人に合わせなくちゃいけないことも、いっぱいある。お互いに我慢して、遠慮したり気ぃ使ったり……。そういううざったさを我慢して、誰かといっしょにいる安心を選ぶか。それともひとりでいる気ままさを選んで、不安を我慢するか。どっちを選ぶかは、本人の自由」
「自由――」
「そう。大人には、それがあるの。自分の生き方を自分で決める、自由」
たしかに、子供にはそれがない。自分一人で生きていくことなんかできないし、まわりの大人たちはみんな、ああしなさいこうしなさいと、命令ばかりしてくる。それに従わない子供は「悪い子」になってしまう。
大人になれば、もう誰からも命令されない。
「もちろん、選んだ生き方が一〇〇%カンペキに幸せなんてこと、ありえない。どんな道を選んだって、うまくいかないこと、不都合なこと、つらいこと哀しいこと、いっぱいある。それをみぃんな受け入れて、これが自分の選んだことなんだってちゃんと納得しなきゃいけない。誰かのせいにしちゃいけない。その覚悟が必要なんだよ、大人にはね」
大人の、覚悟。
自分のことは、自分で考えて、自分で決める。その結果は、悪いことも苦しいこともみんなふくめて、自分で受けとめる。人のせいにしない。
自分の決断、自分の力で生きられる。
そのかわり、誰も守ってくれない。
それが、大人の覚悟。
――それがあるから、ひかるはそんなふうに、笑っていられるの?
なにも怖くないよって、言えるの?
その疑問を、光が口にしようとした時。
「ほら、急ごう! このままじゃ、遅刻しちゃうぞ!」
ひかるは全速力で走りだした。
「あ、待ってよ、ひかる!」
光も、そのあとを追いかけるしかなかった。
いっしょうけんめい走ったおかげか、ひかると光は、どうにか遅刻せずに教室に入ることができた。
六年B組の教室は、気味が悪いくらい静かだった。
ひかるが入っていくと、みんな、じっとその姿を目で追いかける。
けれどもう、にやにや笑ったり、ばかにしたような顔はしていない。
それどころか、みんな、ひどく気味の悪いもの、おっかないものを見てしまったような顔をしている。たとえて言うなら、車に轢かれてしまった犬や猫の死骸だ。怖いし、気持ち悪いし、けして見たいものじゃない。なのにどうしても、目がそっちへ行ってしまう。そんな感じだった。
そんな視線の中を、ひかるは少しも怖がらず、まっすぐに自分の席へ歩いていった。
――どうしてだろう。ひかるは本当に、なにも怖くないんだろうか。
ひかるのうしろをふわふわとついていきながら、光は思った。
ぼくなんて、世界中、怖いものだらけなのに。
ひかるが一度死んでしまった幽霊だから? それとも……大人だから?
大人になれば、ひかるみたいに、怖いものなんてなにもなくなるの?
でも、同じ大人でも、相沢先生はいつもびくびくおどおどしている。ほかの先生たちだって、そうだ。
いじめのリーダーである森本になにか言われるよりも、被害者の光に話しかけられるほうが、先生たちにはつらく、怖ろしいことのようだ。
光がなにか言おうとすると、相沢先生はいつも真っ青になって、泣きそうな表情になる。おねがいだから、私にこんな怖いものを見せないで、とでも言いだしそうだった。
――ひかるは本当に、なんにも怖くないの? なにがあっても、平気なの?
怖くても我慢する、という方法を、ひかるは選んだから?
今、それをひかるにたずねることはできない。
それが、光にはひどくもどかしかった。
やがてチャイムが鳴り、いつものように相沢先生が教室に入ってきた。
「みんな、おはよう」
相沢先生は友達みたいに生徒たちへ話しかけるけれど、けして生徒ひとりひとりと目を合わせようとしない。光はそのことに気がついた。
それどころか先生は、いつも、どこか違うところばかりを見ている。
クラスメイトたちは、それに気がついていないのだろう。
今までは、みんな、光をいじめることに夢中で、先生の様子なんてろくに見ていなかった。そして今は、ひかるのことが怖くて、先生なんかにかまっていられない。
そして、授業が始まった。
息がつまるような重苦しい静けさは、授業が始まっても、変わらなかった。
聞こえるのは、先生の声だけだ。みんな、おしゃべりもしない。
だからと言って、みんな、授業に集中しているわけでもない。
生徒たちは全員、ひどく上の空だった。
ある者はうつむいたまま石みたいに固まって、身動きひとつしない。ある者は反対に、まわりを気にして、きょろきょろよそ見ばかりしている。
窓ぎわの席の高倉は、じっとなにかを考え込んでいるみたいだった。
その表情はひどく不機嫌そうで、世界中のなにもかもに対して、腹が立ってしょうがない、という顔に見える。
森本はうしろのほうの席で、ずっとひかるの背中をにらんでいた。その顔には、反省の様子なんてちっともうかがえない。
――やっぱりそうだ。あいつ、またなにかやるつもりだ。
いざとなったら、ぼくがひかると入れかわろう。光はそう覚悟を決めた。
ひかるはぼくのために、いろんなことを考えて、やってくれた。ぼくのために、ひかるにつらい思いをさせることなんて、できない。
あのからだはもともと光のものだ、光が強くからだに戻りたいと念じれば、ひかるの意識を追い出すこともできるはずだ。ひかるだってそう言っていた。
そうして、時間だけがのろのろとすぎていった。
何回かチャイムが鳴り、気がつけば、午前中の授業は終わりになっていた。
「え? もう四時間めも終わり?」
幽霊になった光は、おなかもすかない。そのせいか、時間の流れがどうもぴんとこない。
チャイムが鳴ると同時に、森本が椅子を蹴って立ち上がった。
先生がまた教室を出てもいないのに、福田や金子たちを引きつれて、教室を飛び出していく。
「なんだ、あいつら……? 給食当番でもないくせに」
ちょっと考えて、光はすぐに彼らの目的に気がついた。
森本たちは、ひかるより先に給食を持ってくるつもりなのだ。きのうみたいなことになっては、たまらないから。
光の予想どおり、森本たちは給食のワゴンをがっちり取り囲んで運んできた。
教室の中へ運び入れると、まるでバリケードみたいに、その前に並んで立ちふさがった。
森本はひかるをにらみつけて、言った。
「残念だったな。てめえに食わせるメシなんか、ねえよ!」
クラス全員が、ふたたび森本の味方についていた。
もともとの給食当番がパンや牛乳をくばり始める。が、ひかるの席は避けて通る。おかずをつぎわける者も同じだ。
ひかるの姿など見えない、声も聞こえない、というように、無視している。
相沢先生は、まるで自分がいじめられているみたいな顔をして、声も出せずにおろおろしているだけだ。
おかずやパンがのったトレイを持って、森本がひかるの横を通り過ぎる。福田や金子も同じように、そのあとに続いた。
みんな、勝ち誇った表情だ。
ひかるをのぞいて、クラスメイト全員に給食がくばられた。相沢先生の机にも、トレイがのせられる。
そしていつもどおり、日直の合図で全員声をそろえて「いただきます」を言う。
「ざまあみろ。これからずっと、卒業するまでてめえは給食抜きだ」
森本がひかるをあざ笑った。
そうだそうだ、と、まわりの生徒たちもいっせいにはやしたてる。おまえになんか給食食わせてたまるか、と。
「別にかまわねえよ」
けろりとして、ひかるは言った。
「オレ、家から弁当持ってきたから」
そしてリュックの中から、お弁当を取り出す。
――すごいや、ひかる!
空中で、光は思わずバンザイしそうになった。
ひかるには、森本たちの考えなんて、とっくに全部お見通しだったのだ。
「今日のおかずはなにかなーっと。やったぁ、母さん、オレの好きなもんばっか入れてくれてる! とりのからあげに、きんぴらに……おにぎりは、めんたいこだ!」
お弁当箱のふたを開け、ひかるは明るい声ではしゃいだ。
クラス全員が声も出せずに、ひかるを見つめていた。
「どしたんだよ? おまえら、給食食べないの?」
運の悪いことに、今日の給食は、生徒たちに一番評判の悪いもやしのスープにサバの竜田揚げだった。ひかるのお弁当にくらべると、さらに魅力がなくなってしまう。
みんな、ひかるがおいしそうにお弁当を食べるのを、ひどく恨めしそうに横目でながめていた。
「井上くん……。だめよ、ひとりだけお弁当持ってきたりしちゃ」
今にも泣きそうな声で、相沢先生が言った。
「学校は、みんなでいっしょに、同じことをする場所です。ひとりだけ違うことをしたら、だめなのよ」
「でも先生。オレの分の給食はないって、みんな言ってますよ」
怒りもせず、ひかるは淡々と答える。
「給食がないんだから、弁当持ってくるしかないでしょう」
「それは……」
相沢先生は、さらに泣きそうになった。いや、もう泣いていた。
「わかりました。明日から、井上くんの分の給食がなかったら、先生のをあげます。だからもう、お弁当は持ってこないで。みんなも、お願いね」
はーい……という元気のない声が、まばらにあがった。
森本たちも、まさか先生の分の給食を用意しないわけにはいかないだろう。だって相沢先生は、今までずっと森本たちの味方だったのだから。
今だって、ひかるから給食を取り上げたクラスの連中を叱らずに、ひかるに「だめ」と言った。
相沢先生の給食をひかるに食べさせるくらいなら、最初からひかるにも給食をくばるはずだ。
またも、ひかるの思い通りになった。ひかるが勝ったのだ。
でもそのせいで、クラスの空気はさらに悪くなった。
ひかるをにらむみんなの目が、ものすごく憎らしそうに、恨めしそうになっている。
ひかるのせいで先生から叱られた、先生が泣いているのもすべてひかるのせいだと、みんなは思っているのかもしれない。
昼休みが終わり、午後の授業が始まっても、クラスのふんいきは最悪のままだった。
クラス中、今にもバチバチ火花が飛びそうに、緊張している。
相沢先生も、教科書を読む声がとても小さくて、ほとんど聞き取れないくらいだ。
その中で、ただひかる一人だけが、落ちついてのんびりした表情だった。
――どうしてそんなに落ちついていられるのさ、ひかる。
光の問いかけは、声にならない。
もうすぐ、ひどいことが起こる。誰にだってわかる。もう止められない。
――なのに、どうしてそんなに平気なの、ひかる!
覚悟、してるから?
森本たちにやり返しちゃった以上、もっとひどいめに合わされるのも、覚悟してるってこと?
それが……、大人の覚悟なの?
なんか、ちがう。
光はそう思った。
もしも本当に、ひかるの言う覚悟が、光の考えているとおりのものだとしたら。
それは――なんか、ちがうよ、ひかる。
どこがどうって、うまく言えないけど、やっぱりちがうと思うんだ。
けれど今、それをひかるに言うこともできない。
光の声はひかる以外には聞こえないけれど、ひかるも光の言葉が聞こえたよ、と態度であらわすことはできないからだ。
光が一方的にしゃべっていたって、ひかるにこの思いがつたわるとも思えない。
そうしているうちに、とうとう終業チャイムが鳴ってしまった。
「おい、てめえ。なに考えてんだよッ!」
森本がどなった。
ひかるのまわりを、十数人の男子生徒がとりかこんでいる。
ホームルームが終わると同時に、ひかるを逃がすまいといっせいにかこんでしまったのだ。
女子たちは、教室のすみにひとかたまりになっている。
相沢先生はさっさと教室から逃げ出してしまっていた。
「ざけんじゃねェぞっ!」
「なにチョーシこいてんだよ!」
「なんとか言えよ、てめえッ!!」
森本が力まかせにひかるの肩を突き飛ばす。
「――ひかる!」
光は思わず叫んだ。
「乱暴すんなよ、森本! 相手は女の人なんだぞ!」
森本の腕をつかんで止めようとしても、実体を持たない光の両手は、森本のからだを通り抜けてしまう。
「答えろよ、おらァッ!!」
森本はいきなりひかるの服をつかんだ。
その脅しにも、ひかるは顔色ひとつ変えなかった。
「おまえ、オレにさわっていいのか? 井上菌に感染すんじゃなかったのかよ」
「うるせえッ!」
悲鳴みたいに森本はわめいた。顔は真っ赤で、目も充血している。
反対にひかるは、ひどく淡々としていた。怒りも恐怖も、なんの感情も読みとれない。
そんなひかるの表情に、森本はますます腹を立てる。
「ふ、ふざけんな、てめえーッ!!」
森本は力いっぱい、ひかるを突き飛ばした。
ひかるは後ろの机にぶつかり、はでな音をたてて床に倒れ込む。
きゃあッ、と、女子たちが小さく悲鳴をあげた。
でも、誰も動こうとしない。ふつう、教室でケンカが始まったら、止めてくれる先生を呼びに行くものなのに。
でもこれは、ふつうのケンカじゃない。
みんな、知っているのだ。これはいじめの延長であり、このクラスにいるモノはみんな、いじめに加わっていたということを。
ただ一人、いじめの被害者だった井上光をのぞいて、全員が加害者だということを。
「オレが、なにしたって言うんだ?」
ひかるはゆっくりと立ち上がり、静かに言った。
おちついて、けして大きくはないけれど、その場にいる者みんなの耳にはっきりと届く声だった。
「オレはたしかに、おまえらがキライだ。でもオレはおまえらを殴ってないし、持ち物をとったりこわしたり、してない。昨日の給食だって、みんな平等にくばったし、サッカーも、先生に注意されたらすぐに、森本、おまえにボール回してやったじゃないか。給食食わなかったのも、サッカーやらなかったのも、みんな、おまえらの勝手だ。オレのせいじゃない」
ひかるの言っていることは、正しい。
――でも、ひかる。そうじゃないんだよ。
光はそう叫びたかった。
いくらひかるが正しくたって、それはただの理屈だ。そのとおりにいかないことなんて、山ほどある。
第一、なんでもかんでも理屈どおりになるのなら、いじめなんて起きるわけないじゃないか!
「それともおまえらは、オレが自分の身を守るのも、いけないって言うのか? オレは――井上光は、クラス全員のうさばらしの道具として、文句も言わずに、ただ毎日毎日、死ぬまでいじめられ続けてりゃあいいって、そう言うのか!?」
「あ……ああ、そうだよ!!」
森本がめちゃくちゃに叫んだ。
「てめえはそのために、このクラスにいるんだ!! そう決まってんだよ! 違うと思うなら、まわりに訊いてみろ!!」
――そんな!
この状況で、ひかるをかばえる者なんて、いるはずがない。そんなことをしたら、今度は自分がいじめられてしまうから。
光の考えどおり、森本の言葉を否定する者はひとりもいなかった。
クラスメイトたちはみんな顔を伏せ、石みたいに固まって、互いに視線を合わせようともしない。
「そら見ろ。これで決まり、多数決だ!」
勝ち誇って、森本はわめいた。
「井上光はいじめられ役、決定っ! 卒業するまでずっと、おれらのサンドバッグになるのが、おまえの役目だ!!」
「そ……そ、そうだ! 井上はサンドバッグ!」
「サンドバッグ、サンドバッグ!」
森本に同調し、一人、また一人と声をあげる。
福田が、金子が、手を叩いてはやしたてる。その声はうわずってふるえ、顔はまだ恐怖にひきつっていた。
けれどこの騒ぎにやがてクラス全員がくわわれば、もう彼らに怖いものはなくなるだろう。
クラスの運営は多数決で行われる。その多数決で「井上光はクラスのサンドバッグ」と決まったのなら、それに逆らうひかるのほうが悪いことになってしまう。
「わかったか、井上! 今度なにかしやがったら、マジぶっ殺してやっかんな! てめえはただだまって、おれらにぶっとばされてりゃいいんだよッ!!」
森本がこぶしをふりあげた。
――逃げて、ひかる! 殴られるよ!
いいや、それより早く、ひかると入れかわらなくちゃ! ひかるのかわりに、ぼくが殴られれば……!!
その時、ひかるがさっと右手をあげた。
森本が、ひかるをとりかこんでいた男子たちが、びくっとからだをふるわせる。殴られるとでも思ったのだろうか。
しかし、ひかるは右手になにかを握っていた。
それは光の部屋にあった、デジタルオーディオプレイヤーだった。
プレイヤーを高く持ち上げたまま、ひかるは指先でスイッチを操作した。
『――井上光はいじめられ役、決定っ! 卒業するまでずっと、おれらのサンドバッグになるのが、おまえの役目だ!!』
さっきの森本の声が、再生されて大きく響き渡った。
『てめえはただだまって、おれらにぶっとばされてりゃいいんだよッ!!』
「な……、なんだよ、それっ!?」
ひかるはだまって、プレイヤーを森本の目の前に突き出した。
森本もそれがなんであるか、すぐにわかったらしい。
「おまえの言ったことは、みんなこれで録音した」
ひかるはゆっくりと、感情のない声で言った。鏡みたいに澄んでおちついた目で、まっすぐに森本を見ている。
「だ、だから、なんだ! それ持って、先生たちに言いつけんのかよ! そんなことしたって無駄だって、まーだわかんねえのか、てめえ!」
先生たちはみんな、ただ光が我慢してくれることを願っている。
そうして6年B組の生徒がさっさと卒業して、問題が目の前から消えてくれることだけを。
「わかってるよ」
ひかるの表情はなにもかわらない。まるで仮面みたいだ。
けれどそれは、昨日見せた、ひどく底意地の悪いあの笑顔よりもずっと、何倍も怖かった。まるで人間じゃないみたいだった。
「学校も教育委員会も、そんなもん、誰があてにするかよ。今度おまえらがオレになにかしたら、オレはこのメモリーカードを持って、警察に駆け込んでやるッ!!」
――警察!?
クラス中が、息を呑んだ。
光も、絶句した。
「これだけはっきりした証拠があるんだ、オレが告訴すれば、警察はかならず動いてくれる。これはもう、れっきとした暴力事件だ、犯罪だ! 森本、おまえの親は、おまえがいじめなんかしていないって校長室でどなってたけど、警察が取り調べに行っても、まだ同じようにおまえを信じて、かばってくれるかな?」
「な……っ」
森本はもう、声もない。真っ赤だった顔は、今にも気絶しそうなくらい、青白くなっていた。
「オレの親は、かならずオレを信じてくれる。オレといっしょに、警察に行ってくれるはずだ。子供がここまで、命がけでやってんだ。信じない親なんかいるもんか!」
ひかるは断言した。
それを否定する声は、もうどこからも聞こえなかった。
息苦しいほどの沈黙が、教室中に広がっていった。
「こ……こわしちゃえ――」
かすれる声が、聞こえた。
「こわしちゃえよ、あんな機械……。そうすりゃ、証拠なんか、なんもなくなるんだからさ……」
がたがたとみっともなくふるえながら、福田がひかるのオーディオプレイヤーを指さしていた。
顔中に脂汗が浮いて、森本と同じくらい、福田も真っ青だ。
「し、証拠がなけりゃいいんだよ! そうすりゃ井上だって、警察なんか行けねえんだからさ!」
「そ――そうだ! そうだ、壊せ!」
「そいつを取り上げろ! 井上に勝手なことさせんな!!」
怒鳴り声があがった。
ひかるをとりかこむ輪の中から、最初はじわじわと、福田と同じようにひどく怯えた声があがる。
森本たちだけでなく、木島などほかの男子生徒も叫び出す。
やがてそれは、自暴自棄になったみたいなむちゃくちゃな大声になる。
「メモリーをこわせッ!!」
「ボコボコにしろ、二度と口がきけねえようにしちまえッ!!」
――な、なに言ってんだ、みんな!
光は思わず、ひかるの前に立ちはだかろうとした。
両手を広げ、ひかるをかばう。
けれど幽霊の光には、クラスメイトを止めることなんかできない。ひかるにつかみかかろうとする連中の腕は、光をかんたんに突き抜けてしまう。
光の姿さえ、彼らの目には見えていないのだ。
ただ一人、ひかるをのぞいて。
――ひかる、逃げて! 逃げて!!
光は懸命に叫んだ。
けれどひかるは、にこっと笑っただけだった。
まるで光に、安心して、大丈夫だよ、と語りかけるみたいに。
そしてひかるは、ふたたび声をはりあげた。
「おまえら、録音してんのが、これ一個だけだと思ってんのか!?」
「……え――っ!?」
煮えたぎる鍋みたいだった教室が、一瞬、しんと静まり返った。
「この教室ん中に、もしかしたらオレの協力者がいるかもしれねえぞ。オレに頼まれて、同じようなデジタルプレイヤーで、今のやりとりを全部録音してるヤツが……いないとでも思ってるのか?」
ひかるはわざと、ひとつひとつの言葉をくぎって、ゆっくりとしゃべった。
自分をとりかこむ生徒たち一人一人の顔を、まっすぐに、突き刺すように見ていく。
「6年B組、オレをのぞいた37人全員が、心をひとつにして、オレをいじめることを楽しんでると、おまえら、本気で信じてるか? なかにはいるはずだぜ。いじめなんてかっこ悪りい、もういい加減やめてえなって思ってるヤツがさ。そういうヤツがこっそりオレの協力者になって、ポケットに録音機械を隠し持ってるかもしれないぜ? たとえオレのメモリーカードがこわされたって、そいつが録音してくれた証拠がある。オレはなんにも困らないぜ」
「う……うそだ――。うそつくんじゃねえ、てめえッ!」
「うそだと思うなら、その証拠を出してみな? 誰もオレに協力してねえって、その証拠をさ」
ひかるの言葉に、生徒たちは男子も女子もいっせいに、自分のまわりを見回した。
自分のとなりに立っている、同じクラスメイトを。
そして、誰かと目が合うと、あわてて首を横にふる。――ううん、ちがう。自分は井上の協力者なんかじゃない、と。
みんな、必死の表情だった。
ここで井上光の協力者だとうたがわれたら、自分もいっしょにぼこぼこに殴られてしまう。
金子も福田も、森本までが、おおげさに首を横にふっていた。
けれどそれを見る目は、疑いに満ちている。ちがう、と言う言葉を、誰も信じていない。
そうだ。誰も信じられない。
このクラスの中で、本当に信じ合っている友達なんか、いない。
みんな、自分がいじめられないために、光のいじめに同調していただけなのだから。
「おまえら、ほんとバカだなあ。こんな時に、『はぁい、ボクが井上くんの協力者でーす!』なんて名乗り出るヤツがいるかよ」
ひかるはもう一度クラスメイトたちを見回し、にこっと笑いかけた。――まるで、その中に本当に自分の協力者がいるみたいに。
「いいんだぜ、今はウソついてたってさ。知らん顔してていいよ。おまえの安全を最優先しろよ。みんなといっしょにオレの悪口言ってても、オレ、ちっとも気にしねえからさ。おまえがケガしねえことのほうが、大事だよ」
ひかるの目は、誰を見てるかわからない。
森本たちが、ひかるが誰を見ているのか確かめようとすると、さっと目をそらしてしまう。
「デジタルプレイヤーも、見つからないようにうまく隠せよ。メモリーカードだけ、あとでこっそりオレに送ってくれればいいからさ」
「メモリーカード――」
その言葉に、福田たちがはっと気がついたように顔をあげた。メモリーカードを奪えばいいと、思いついたのだろう。
「あのさあ。オレが、おまえらの目の前で証拠を手渡ししてもらうと、思うのか?」
からかうように、ひかるは言った。
「家へ郵送してもらうに決まってんじゃん! おまえら、どうするよ? オレん家のポストを二十四時間見張るか? もしそうするなら、オレ、母さんの会社に送ってもらうだけだから」
「か、会社……」
「それを、どうやって止める? 母さんのバッグをひったくるか? そんなことしてみろ、オレが告訴しなくたって、おまえらは犯罪者だ!」
もう誰も、なにも言えなかった。
ひかるが一歩、前へ出る。
見えない腕に押されるように、森本が一歩、後ろへ下がった。
「オレはおまえに、なんにもする気はねえよ。森本」
静かに、ひかるは言った。
「もうオレをほっといてくれ。オレにかかわるな。オレのかわりに、誰かをいじめるな。オレが言いてえのは、ただそれだけだよ。できんだろ、そのくらい!」
強く言われても、森本はもう、返事もできなかった。
「ま、もし別のヤツがいじめられたとしても、そいつだって、オレと同じことをするはずだけどな」
そしてひかるは、もう一度デジタルオーディオプレイヤーをみんなに見えるように、持ち上げた。
「わかるよな、みんな。もうこのクラスで、いじめはできない。しない、やめた、じゃねえ。もう二度と、できないんだよ!」
やがてそれをハーフパンツのポケットにしまうと、リュックを肩にかつぎ、ひかるは一人、教室を出ていこうとした。
誰もそれを止めない。
ひかるの姿を目で追おうともしない。
そしてひかるは――井上光は、六年B組の教室をあとにした。
――わからない。
とぼとぼと自宅に向かって歩きながら、光は胸の中で、何度もくりかえした。
わからない。ほんとうにあれで、良かったんだろうか。
光は見てしまった。
あの眼。教室にいた全員の、あの眼。
それは光を見ているのではなかった。
隣にいるクラスメイト、6年B組の生徒ひとりひとりに向けられていた。
かつて光を見たのと同じ、怯えと嫌悪に満ちた眼。
見てはいけないもの、見たくないのに、どうしても目に入ってしまう、怖くてしかたがないものを見る、眼。
クラス全員が怯えていた。同じクラスメイトたちに、今朝までは仲良く友達としてつきあっていた相手に。
――こいつは、今も自分の声を録音してるんじゃないのか? なんでもないふりしているくせに、かげでこっそり、いじめの証拠を集めているんじゃないのか!?
大丈夫か、自分は大丈夫か!? こいつらに恨まれるようなことを、なにかやっていないか!? 回りの人間から憎まれていないと、本当に言い切れるか!?
誰も信じられない。声も出せない。
自分以外のクラスメイト、37人全員が、いっせいに怖ろしい敵に見えたことだろう。
それはたしかに、かつて光が味わわされた恐怖と、よく似ているけれど。
それでも、思わずにいられない。
これで、ほんとうに良かったんだろうか。
「――ひかる」
校門を出てすぐに、光はひかるを呼び止めようとした。
ひかるはちらっと、半透明になってふわふわ宙に浮いている光を、見上げた。けれど、足を止めようとはしない。
もっとも、立ち止まったところで、まわりにほかの人がいる町中では、光と話もできないのだが。
「ひかる!」
光が大声をはりあげて、ようやく、ひかるは立ち止まった。
「ぼくのからだ、返してよ」
六車線の大通り、流れる車の列をながめながら、ひかるが言った。
「あたしがやったこと、気に入らない?」
「え……?」
「これで明日から、あんたへのいじめはなくなるはずよ。少なくとも、意味もなく殴られたり、死ね、死ねって言われたり、クラス中の雑用を押しつけられたりすることはない。――ま、あんたと友達になろうってヤツも、いなくなるだろうけどね」
光は答えなかった。宙に浮いたまま、唇をぎゅっと噛みしめる。
「それともあんた、あのクラスの連中と、仲良しこよしになりたかったの?」
「……ちがう」
いじめがなくなれば、それで良かった。
ふつうに学校に行って、勉強して、物を盗られることも服を汚されることもなく、無事に毎日を過ごせれば。――そして、光のかわりにいじめられるヤツが出なければ、じゅうぶんだと思っていた。
ひかるはたしかに、その願いを叶えてくれたのだ。
……けれど。
「あれじゃ――。ぼくだけじゃない、あれじゃあ、クラス全員、ひとりも友達がいなくなっちゃったじゃないか!」
「しょうがないじゃない。もともとそういうクラスだったんだもの」
ひかるはきっぱりと言い切った。
「他人へのいじめや陰口でしか仲間意識をたもてないなんて、そんなのは友達でもなんでもない。ただの卑怯者の集まりよ」
「でも――! でも、だって……!!」
「じゃあ、あんたはいったいどうしたかったの」
ひかるの目が、まっすぐに光を見上げた。
「あのままずっといじめられ続けて、自殺に追い込まれても良かったの? あんたが死んじまったら、あんたのお母さんはどうなんのよ。クラスの連中だって、一生消えない負い目をせおうのよ。自分は、クラスメイトを殺しちまったってね。その前にあんたが不登校になっても、あんたの命だけは助かるけど、それじゃあいつらは反省なんかしない。別の誰かをいじめるだけよ。誰かが命をなくすまでね」
「それは――」
ちがう、とは、光は言えなかった。
「これで、少なくとも誰かが自殺することだけは、ない。最悪の事態だけは、さけられたのよ」
「最悪の、事態……」
ひかるの言うことは、まちがいじゃない。
光の、そしてクラスみんなの命がすくわれた。
でも。
「言ったでしょう。人間は生きているかぎり、傷つかないわけにはいかないのよ。誰もがみんな、一〇〇%しあわせになれる選択肢なんて、ありえない。どんな方法を選んだって、みんな傷ついて、ぼろぼろになる。それでも、より傷の小さいほう、少しでもマシなほうを選んで、生きていくしかないのよ」
「少しでも、マシなほうを……」
光はもう、なにも言い返せなかった。
「……ぼくのからだを、返して」
それだけを、光はぽつりと言った。
OK、というように、ひかるはうなずく。
人目につかないビルの陰で、二人は入れかわった。
「ついてこないで」
自分の身体を取り戻すと、光はこわばった声で言った。
幽霊に戻ったひかるを、もう見ようともしない。
「たぶん……、こうなるだろうなって、わかってたよ」
ひとりごとみたいに、ひかるが言う。
かすかにほほえむような、今にも泣いてしまいそうな、優しい声だった。
その言葉も、光は聞こえないふりをした。
「あたしのやり方じゃあ、あんたは絶対怒るだろうって、わかってた。――あんた、そういう子だもん。ちゃんと、別の誰かのために、喜んだり怒ったりしてあげられる子だもんね」
――わかっていたの? ひかる。
光は胸の中でつぶやいた。
けれど立ち止まり、ふりかえって、ひかるの顔を見る勇気がない。
わかっていたの? ひかるのしたことに、ぼくが怒って、ひかるを許さないだろうってわかっていて……それでもやりとげたの?
ぼくを助けるために。
……それが、大人の覚悟なの?
そうやって自分が選んだ道で、自分も、まわりも、傷ついて、傷つけられて。
その痛さも苦しさも、哀しさ、つらさ、みにくさ、みんな、受け入れて生きていくことが。
それが、大人の覚悟なの?
ひかる。
その答を、光は聞けなかった。
聞ける勇気が、覚悟が、なかった。
光はリュックをしっかりとせおうと、逃げるように走りだした。
もう一度ふりかえることすら、できなかった。
ふたたびきれいな女の人の幽霊に戻ったひかるは、歩道橋のそばにたたずみ、だまってその後ろ姿を見送っていた。
1
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

転生妃は後宮学園でのんびりしたい~冷徹皇帝の胃袋掴んだら、なぜか溺愛ルート始まりました!?~
☆ほしい
児童書・童話
平凡な女子高生だった私・茉莉(まり)は、交通事故に遭い、目覚めると中華風異世界・彩雲国の後宮に住む“嫌われ者の妃”・麗霞(れいか)に転生していた!
麗霞は毒婦だと噂され、冷徹非情で有名な若き皇帝・暁からは見向きもされない最悪の状況。面倒な権力争いを避け、前世の知識を活かして、後宮の学園で美味しいお菓子でも作りのんびり過ごしたい…そう思っていたのに、気まぐれに献上した「プリン」が、甘いものに興味がないはずの皇帝の胃袋を掴んでしまった!
「…面白い。明日もこれを作れ」
それをきっかけに、なぜか暁がわからの好感度が急上昇! 嫉妬する他の妃たちからの嫌がらせも、持ち前の雑草魂と現代知識で次々解決! 平穏なスローライフを目指す、転生妃の爽快成り上がり後宮ファンタジー!

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

モブの私が理想語ったら主役級な彼が翌日その通りにイメチェンしてきた話……する?
待鳥園子
児童書・童話
ある日。教室の中で、自分の理想の男の子について語った澪。
けど、その篤実に同じクラスの主役級男子鷹羽日向くんが、自分が希望した理想通りにイメチェンをして来た!
……え? どうして。私の話を聞いていた訳ではなくて、偶然だよね?
何もかも、私の勘違いだよね?
信じられないことに鷹羽くんが私に告白してきたんだけど、私たちはすんなり付き合う……なんてこともなく、なんだか良くわからないことになってきて?!
【第2回きずな児童書大賞】で奨励賞受賞出来ました♡ありがとうございます!
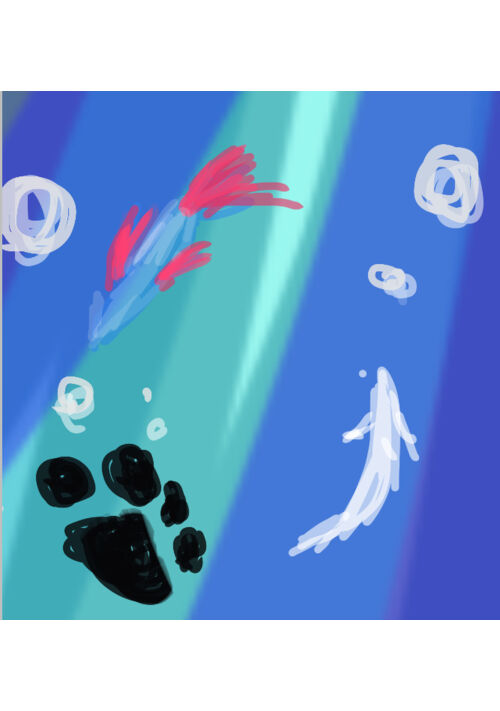
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎

ホントのキモチ!
望月くらげ
児童書・童話
中学二年生の凜の学校には人気者の双子、樹と蒼がいる。
樹は女子に、蒼は男子に大人気。凜も樹に片思いをしていた。
けれど、大人しい凜は樹に挨拶すら自分からはできずにいた。
放課後の教室で一人きりでいる樹と出会った凜は勢いから告白してしまう。
樹からの返事は「俺も好きだった」というものだった。
けれど、凜が樹だと思って告白したのは、蒼だった……!
今さら間違いだったと言えず蒼と付き合うことになるが――。
ホントのキモチを伝えることができないふたり(さんにん?)の
ドキドキもだもだ学園ラブストーリー。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















