4 / 4
4 それでもぼくは生きていく
しおりを挟む
次の日も、その次の日も、光はあの歩道橋を通らなかった。
登校も下校もわざと遠回りして、信号のある大きな交差点を通った。歩道橋の見える場所までも近づかない。
ひかるに会いたくなかった。
会えばなにか言いたくなるけれど、なにを言えばいいのかもわからない。
ひかるのことを考えるだけで、どうしていいかわからなくなる。大声で叫びだしそうになってしまう。
逃げるしかなかったのだ。
だから、あの次の日、教室であったことを、ひかるに報告することはできなかった。
次の日、クラスの三分の一が欠席した。
森本も金子も休んでいた。きっと、怖かったのだろう。女子は半分近くの生徒が欠席していた。
出席した生徒も、みんなひどく顔色が悪くて、おちつきがなかった。まるで、みんな病人みたいだった。
全員、自分の席についたままうつむいて、顔をあげようともしない。
たまたま誰かと目があってしまうと、逃げるように顔をそむける。
たまに光を見る者もいるが、光と目が合うと、あわてて目をそらす。光が今もクラス中の話し声を録音しているとでも、思っているのだろうか。
インフルエンザでも流行してるみたいなクラスの様子に、相沢先生もとても驚いていた。
けれど、生徒たちに理由をたずねようとはしなかった。欠席した生徒の親からは「病気です」とかなんとか、連絡は入っていたのだろうし。
高倉は出席していたけれど、光と目が合うと、怒ったような顔をして、すぐにぷいっと横を向いてしまった。
――ま、あいつが女のくせに愛想悪いのは、もともとか。
教室はお葬式みたいに静まり返り、ものすごく居心地が悪かった。
みんな、ひかるのせいだ。光はそう思った。
――ひかるなんか、だいっきらいだ。エラそうなことばっか言って、結局、ぼくのクラスをめちゃくちゃにしただけじゃないか。
だいたい、ひかるなんて、ぼくのからだを乗っ取ろうとした、ずうずうしいヤツなんだ。
口ではぼくを助けたなんて言ってるけど、ほんとはなにを考えてるか、わかるもんか。
見ろよ、この教室。みんな休んじゃって、ガラガラで、こんなの見たことない。
こんなことになったのも、みんな、ひかるのせいなんだ。
言ってやるべきだろうか。ひかるに、これがあんたがやったことの結果だって。
もう一度ひかるを、この教室に連れてきて、見せてやるべきなんじゃないか。
――いいや、そんなことしたって、何の意味もないだろう。
光は小さく首をふり、自分の考えを否定した。
ひかるはきっと、こうなることもわかっていたはずだ。光が怒って、ひかるを許さないことも、最初からわかっていたと言ったのだから。
――そうだ。もう、ひかるに会う必要なんか、ない。
それよりは、これからどうするかを、考えなくちゃ。
……どうするかって、でも、いったいなにを?
六年B組の教室は、とても静かだった。
授業中によけいなおしゃべりをする生徒もいないし、休み時間にもなんのさわぎも起こらない。ケンカも、もちろん、いじめも。
教室の外から見れば、生徒たちはみんなおちついて、とてもいい子たちに見えるだろう。
給食当番はみんなに平等に給食をくばったし、放課後のそうじも、当番の生徒たちがきちんとやった。誰かひとりにむりやり押しつけるなんてことは、なかった。
理科の授業では、実験班を、今度は出席番号順に分けたので、光もふつうに顕微鏡をのぞくことができた。
ふつうに勉強して、トラブルなく一日をすごすこと。光のかわりに誰かがいじめられたりしないこと。
それはたしかに、光が望んだとおりの一日だった。
――ひかるはほんとうに、ぼくの願いをかなえてくれたんだ。
けして、うれしいとすなおによろこべはしない。
どんよりと沈んだ教室を見回すと、息が止まりそうに胸が苦しくなる。
怯えきったクラスメイトたちの目を見ると、光も泣きたいくらい、つらい。
……それでも。
やがて週末をすぎ、翌週の月曜になると、金子や福田、そして木島も登校してきた。
森本はまだ、休んでいた。
金子たちはふたりともひどく不安そうで、おちつきがなかった。
木島はひどくおどおどして、きょろきょろまわりを見回してばかりだ。顔色も悪く、今にも吐きそうだ。
光はあえて、彼らを無視した。
休み時間も一人ですごし、誰とも口をきかない。
そうやって、福田たちに態度で示してやろうと思ったのだ。ぼくはもう、おまえらなんかに興味はない、おまえらがぼくをほっといてくれるなら、ぼくもおまえらをほっといてやる、と。
おどおどきょろきょろが止まらない木島に、光の考えはつたわっていないのかもしれないが。
「ばかだな、木島。あんなにびくびくして、まるでニワトリみてえ。あれじゃ今度は、木島がいじめられるかもしんないぞ……」
「そこまであんたが心配する必要、ないんじゃない?」
「えっ!?」
突然の声に、光はびっくりして、思わず飛びあがりそうになってしまった。
木島について考えていたことが、つい声になっていたらしい。
「い、今のはべつに――!」
光はあわててまわりを見回した。
「気にすることないって。木島だって、いじめられたくなきゃ、井上のまねすればいいって、わかってるはずだもん」
妙にしらけた声で言ったのは、高倉だった。
「高倉……」
「ほら。あたしも持ってるし」
高倉は、メタリックピンクの小さな機械をポケットから取り出した。メーカーはちがうが、光のものと同じようなデジタルオーディオプレイヤーだった。
「イトコのお姉ちゃんにもらったの。新しいのに買い換えたって言うからさ、いらなくなった古いのをね」
「へえ……」
「もしかして、気がついてないの? 今、女子の半分は持ってるよ」
「――マジ?」
「だからみんな、前みたいにおしゃべりとか始めてんじゃん。ま、録音されても困んないように、天気の話くらいしかしないけどさ」
「天気の話、ね……」
光は小さく苦笑いした。
今日は寒いですね、ええ、そうですね、なんて、まるで知らない人どうしのあいさつみたいだ。
それでも、教室に少しずつ話し声が戻っていることに、光もようやく気がついた。
光と高倉がしゃべっているのが気になるのか、ちらちらこっちを見ている生徒もいる。
だが、ほとんどの生徒は関心なさそうな顔をしていた。よけいなことには首をつっこまないようにしているのだろう。
以前なら、男子と女子がちょっと口をきいただけで、すぐおおげさにさわぎたて、意地悪くからかうヤツがいたのに。
「でも考えたら、前だって、似たような話しかしてないしね。テレビのこととか、マンガのこととかさ。大事なことは、誰も話してなかったよ」
あまり感情のない声で、それこそお天気の話でもするみたいに、高倉は言った。
「このプレイヤーもらう時、あんたのやったこと、イトコに全部話したんだ。そしたらお姉ちゃん、『そいつ、すげーヤなヤツだね』って。『ヤなヤツ、マジ、友達になりたくないね。……でも、すげーアタマいいね』ってさ」
高倉は、まっすぐに光を見た。
「あたしもそう思う。井上、あんたって、マジで嫌なヤツだよね」
「……うん」
光はうなずいた。
――そうだ。ぼくはいやなヤツだ。
ひかるはぼくを守って、ぼくのために戦ってくれたのに。ぼくが望んでいたとおりの結果をもたらしてくれたのに。
ぼくはそれに、感謝することもできない。今もまだ、ひかるを許せないでいるんだ。
ぼくは……ひかるに守ってもらう価値なんて、きっと、なかったのに。
「でもあたし、あんたのしたことに、感謝してる」
はっきりと、高倉は言った。
「……え?」
「あたし……。ずっと、怖かった。あんたがいつか自殺するんじゃないかと思って」
するんじゃないか――じゃなくて、ほんとうに、しようと思ってたんだよ。その言葉を、光はぐっと飲み込んだ。
「そうなったらどうしようって、ずっと、怖かったんだ。いじめ自殺とかってなったら、きっとマスコミとかもいっぱい来て、大さわぎになっちゃう。そんな中で、クラス全員、顔隠しながら、あんたのお葬式とか行かされたりしてさ……。ほんとにそうなっちゃったらどうしようって、そんなことばっか、考えてたんだ。すげーヤなヤツだよね、あたしもさ。あんたがいじめられてるの、止めもしなかったくせに……!」
「高倉……」
高倉はちょっと、泣いているのかもしれない。光はそう思った。
「でもさ。あんた、もう自殺なんかしないよね」
「うん」
「ほかのヤツもさ、不登校してる森本だって、そうやって家ん中に引きこもってりゃ、とりあえず安全だしさ。少なくとも自殺だけはしないよね。あんたが森本ん家までおっかけてって、いじめのしかえししないかぎり」
「しないよ、そんなこと。めんどくさい」
ちょっとだけ、高倉は笑った。
「井上なら、そう言うと思った」
その笑顔に、光もなんだかほっとした。
やがてチャイムが鳴り、次の授業が始まった。
光はあわてて自分の席についた。高倉も、窓ぎわの席に戻る。
六年B組の教室はあいかわらず静かで、体育の時間なども、まったく活気がなかった。
それでも大きなトラブルはなく、また平穏に一日が終わった。
――これで、良かったんだろうか。
また遠回りして家に帰りながら、光は考えた。
高倉が言ったことを、ひかるに教えてあげようか。
クラスの中にも一人は、ひかるに感謝している子がいるって。
何度か立ち止まり、あの歩道橋へ行こうとした。
でも、どんな顔をしてひかるに会えばいいのか、わからない。
ひかるに会う、勇気がない。
結局、光はそのまま家に帰った。
マンションの玄関を開けるとすぐ、スマホが鳴った。
「あ、もしもし、光? ごめんね、お母さん、帰るの少し遅くなりそうなの。晩ご飯は……」
「うん、いいよ。カップメンでも食べてる」
お母さんが残業で遅くなるのは、今までにも何度かあった。そのたびに、光は一人でずっと留守番をしていた。
光はゲームやマンガで時間をつぶし、夕方になると、お湯を沸かしてカップメンを作った。
宿題を終わらせて、お風呂の用意をしても、お母さんをまだ帰ってこなかった。
お母さんが帰ってきたのは、夜九時近くになってからだった。
「ごめんね、光。遅くなっちゃって。ごはん、どうした?」
「うん、カップラーメン食べたよ」
「それだけじゃ、おなかすくでしょ。なにか、夜食作ろうか。お母さんもおなかすいたし」
「お母さん……。いいよ、ぼくがやる」
光は立ち上がった。お母さんをキッチンの椅子に座らせる。
「て言っても、カップメンくらいしか作れないけどさ。あ、それとも、パンでも焼こうか」
「どうしたの、光。急に親切になっちゃって」
お母さんは優しく、くすくす笑った。
「うん……」
光は少し、ためらった。
でも、思いきってお母さんにたずねてみる。
「お母さん、仕事、たいへん?」
「光……。どうしたの、いきなり」
「お父さんがいたころは、お母さん、働いてなかったじゃん。毎日、家にいてさ。それが、離婚してから急に働かなくちゃいけなくなって、家に帰ってきても、ぼくしかいないし、ぼく、あんまり家のこととか手伝ってないし……。やっぱり、たいへんだよね」
「光――」
お母さんの表情がくもった。少し哀しそうな目をして、光を見る。
「光……。お父さんとお母さんが離婚しないほうが良かったって、そう思ってる?」
「ううん!」
光は強く首を横にふった。
「離婚する前、お父さんとお母さん、毎日ケンカばっかりしてたよね。ぼくの前じゃ、二人とも、できるだけふつうの顔してたけど……。知ってたよ、ぼくも。お母さん……良く泣いてたよね。そんなつらい思いするなら、むりしていっしょにいることなんかない。少しくらい淋しくても、別れちゃったほうが良かったって、思ってる」
お母さんはじっと光の顔を見ていた。そして、小さくうなずく。
「そうよ。お母さんも、そう思ったの」
「だからお父さんと別れたんだよね。それがお母さんの、選択だったんだね」
「そうよ」
お母さんはうなずいた。
「お母さんは、まちがってないよ。自分で決めたことの責任を、ちゃんと自分ではたしてる。だからお母さんは、まちがってないよ」
お母さんは、自分が選んだ結果をちゃんと受け入れている。お父さんと二人で背負っていた責任を、今はたった一人で背負い続けて、それでもけんめいにがんばっている。
それがお母さんの、覚悟だ。
「光……」
お母さんは指先で、そっと目元をぬぐった。そうして、涙まじりの笑顔で笑顔で、光を見る。
「ありがとう、光。お母さんも、離婚はまちがいじゃないって思ってる。でも……あんたにそう言ってもらうと、ほんとうにうれしいわ」
光はポケットから、あのデジタルオーディオプレイヤーを出した。
ひかるが録音してくれた、いじめの証拠を。
「お母さん。ぼく、学校でずっと、いじめられてたんだ」
あの日の会話が再生された。
森本の声、福田の声、そして光の――ひかるの、声。
お母さんは息を飲んだ。大きく目を見開き、叫び声をおさえつけるように、片手で口をふさいだ。
「ごめん、お母さん。ぼく、ずっと言えなかった――!!」
その夜、光はお母さんと、夜遅くまでいろんなことを話しあった。
これからどうするの、と質問されて、光は、今はまだ、なにもするつもりはないよ、と答えた。
「さっきも言ったけど、今はクラスん中、けっこうおちついてるんだよ。いじめのリーダーだった森本ってヤツは、ずっと学校休んでるし。このままなにも起きないなら、ぼくはそれでいいと思うんだ」
「そう……。光がそう決めたんなら、お母さんも、もうなにも言わないわ」
お母さんは光の両手をにぎって、力強く言った。
「でも、あんた一人の力ではどうにもならないと思ったら、今度はもう、隠さないで。必ずお母さんに言ってね。お母さん、光のためなら、なんだってする。警察でも裁判所でも、どこへだって行くからね」
「お母さん」
光も、お母さんの手をぎゅっとにぎりかえした。
「光が戦うなら、お母さんもいっしょに戦う。二人っきりの家族なんだもの」
「うん。ありがとう、お母さん」
こんなに長いあいだ、お母さんと話をしたのは、ひさしぶりだった。
お母さんに、すなおにありがとうと言えたのも。
「あ……」
――そうだ。やっぱり、言わなくちゃ。
ひかるにも、「ありがとう」って、言わなくちゃ。
「お母さん、ごめん。ぼく、ちょっと出かけてくる」
「えっ? こんな夜中に?」
いけません、と言いかけたお母さんを、光はまっすぐに見上げた。
「だめなんだ。今すぐ行かなくちゃ、だめなんだよ」
今なら言える。でも、明日になったらまた、勇気がなくなってしまうかもしれない。
言わなくちゃ。ひかるに、会わなくちゃ。
「ほんの少しだけ。用事がすんだら、すぐに帰ってくる。約束するよ。だからお願い、お母さん!」
真剣な光の表情に、やがてお母さんも、あきらめたようにため息をついた。
「すぐ帰ってくるのよ。ケータイは持っていきなさい」
「うん! ありがとう、お母さん!」
光はジージャンをつかんで、ぱっと玄関へ向かった。
「なにかあったら、かならず連絡するのよ。お母さんが迎えに行くから」
「うん、わかってる。すぐに帰ってくるよ!」
靴をはくのももどかしく、光はマンションを飛び出した。
まっくらな夜の街を、あの歩道橋に向かって走る。
風はひどく冷たかった。もう冬が近いのだ。
けれどそんなことも、光はまったく気にならなかった。
やがて、六車線の大通りが見えてくる。
深夜になっても、幹線道路の交通量はあまり減っていない。大きなトラックが、昼間以上のスピードでどんどん走っていく。
そして、あの歩道橋の上に、ひかるはいた。
ひかるはとてもきれいだった。
長い髪が風にふわりとまいあがる。次々と足元を通りすぎる自動車のライトに照らされて、それはまるでひかるの翼みたいだった。
ひかる、と、光は大きな声で呼びかけようとした。
けれど全速力で走ってきたせいで、ぜいぜい息が切れて、うまく声が出ない。
「光」
さきにひかるのほうが、光の名を呼んだ。
「どうして、来たの?」
「どうしてって――」
苦しい息をおさえながら、どうにか光は声を出した。
「……迎えに、来たんだよ」
ゆっくりと、ひかるへ手を差し出す。
そして、気がついた。
ひかるの姿が、薄くなっている。
半透明の幽霊の姿が、さらに薄く、透けてしまっている。黒っぽいかっこいいパンツスーツは、ほとんど暗闇に溶けて、輪郭もはっきりわからないくらいだ。
「ど、どうしたの、ひかる……」
ひかるはなにも答えなかった。
だまって、優しい笑顔で、光を見ている。
「ね、ねえ。帰ろう。いっしょに家へ帰ろうよ、ひかる」
光は言った。
でも、その声が、みっともなくふるえだす。うわずって、まるで自分の声じゃないみたいだ。
「光――」
「帰ろう、ひかる! ゲーム、まだクリアしてないじゃんか! マンガだって――あれ、まだ連載中だよ。来週には、コミックスの最新刊が出るんだ。続きが読みたいって、ひかる、言ってたじゃんか!」
「ねえ、光」
「帰ろう、早く! また、ぼくのからだ、貸してあげるから!」
光は必死にしゃべり続けた。ひかるが口を開こうとするたびに、声をはりあげて、ひかるの言葉をかき消してしまう。
なにも聞きたくなかった。ひかるになにも言わせたくない。
聞いてしまったら――きっと、取り返しのつかないことになる。
「早く帰らないと、お母さんが心配する。だから、早くおいでよ、ひかる!」
ひかるは静かに、首を横にふった。
「家へは、あんたひとりで帰りなさい。あたしは……行けない」
「ど……どうして――。どうしてだよ、ひかる!」
今まで、ずっといっしょだったのに。
ひとつのからだを二人で使って、いっしょにゲームしたりマンガ読んだり、いろんなことを話したり。
とても楽しかった。
ひかるだって、とてもとても、楽しそうだったのに。
「ごめんよ、ひかる……。ぼくのこと、キライになっちゃったんだね。当然だよね。ぼく、ひかるにあんなひどいこと言っちゃって……」
光はこらえきれず、うつむいた。
そのほほに、すぅっと冷たい風のようなものがふれた。
ひかるの手だった。
「大好きよ。光」
光は顔をあげた。
ひかるが、光を見つめている。
今にも泣きそうな、けれどとてもきれいな笑顔で。
「じゃあ……、じゃあ、どうして――!」
「だってあたしは、もう死んじゃったんだもの」
透きとおったひかるの手は、たしかに光のほほにふれている。
けれど光は、それを感じることはできない。ただかすかに、冷たい風を感じるだけだ。
「あたしはもう、この世界のどこにもいないの。あんたが見てるあたしは、ただのまぼろしなのよ」
「う――うそだ!」
光は叫んだ。
「うそだ! そんなの、うそだ!!」
「いいえ。本当よ。光」
だって、ひかるはここにいるのに。
いろんなことを光に教えてくれて、今もこうして光と話をしているのに。
ひかるがまぼろしだと言うなら、どうしてこんなに苦しいんだ。胸の奥から熱い鋭い痛みがこみあげてきて、息もできないくらい、哀しいんだ。
「そんなこと、言わないでよ。ひかる……」
ぼろぼろと涙があふれてきた。
それでも光は、けんめいに笑おうとした。
なんでもないふりをして、笑って、そうして全部じょうだんだと思い込もうとした。
「そうだ、ひかる。ぼくのからだ、ひかるにあげるよ」
「――光!」
「言ってたじゃないか、ひかる。ぼくのからだがほしいって。だから、このからだをあげるよ。ぼくが幽霊になって、ひかるは生き返ればいい。そうすれば――」
「光」
静かに、ひかるは光の言葉をさえぎった。
「そんなこと、言っちゃだめだよ」
「どうして!? だって、ぼくはそれでいいんだ! ひかる……ひかる、あんなに楽しそうだったじゃないか。走ったり、ジャンプしたり、サッカーだって――! ぼくは、それを見てるだけで良かったんだ。ひかるが楽しいなら、ぼくだって楽しい。ぼく……ぼくは――!」
ひかるに、笑っていてもらいたいんだ。
ひかるが笑ってくれるなら、どんなことだって、できるよ。
「ぼくが、ひかるのためにしてあげられること……これしか、ないからさ。だから、ひかる――」
ひかるはもう一度、静かに首を横にふった。
「あんたに教えなきゃいけないことが、もうひとつ、残ってたね」
「ひかる……」
「ねえ、光。人はね、誰かの命を奪うことだけは、絶対にしちゃいけない。人の命を奪う権利は、この世の誰にも、ないんだよ」
ひかるは泣いていた。
涙が、すうっと銀の糸みたいに、ひかるのほほをこぼれていった。
「この世に生まれてきた以上、その命をむだにすることは、誰にも許されない。自分自身にもね。あんたの命を奪うことは、あたしにも、あんた自身にも、絶対に許されないの」
「だって……だって、ひかる――!」
ひかるの命は、奪われてしまったじゃないか。脇見運転していた、無責任なドライバーに。
「どうしてだか、わかる? 一度奪われた命は、もう二度と戻らないからだよ。あたしの命は、もう、誰にも取り戻せないの」
ひかるの姿が、ますます薄くなっていく。
声が遠ざかる。
「光。あたしのことなんか、もう、忘れちゃいな」
そんなこと、できない。光はそう叫ぼうとした。
どうして、ひかるのことを忘れられるだろう。
けれど。
「いいんだよ。忘れちゃいな。だってあたしは、もう死んじゃったんだから」
いやだよ、ひかる。
どうしてそんなことを言うの。
ぼくはまだ、ひかるといっしょにいたいよ。
もっともっと、ひかるといっしょに過ごしたい。二人でいろんなことを話して、いっぱい遊んで、いっぱい笑って。
そうだよ――ぼくは、ぼくは……!!
「あたしは、消えなきゃいけない。死んだ人間は死んだ人間、もうこの世界のどこにもいないの。あんたの目に、映っていちゃいけないんだよ」
もう、声が出ない。ひかるの名前が呼べない。
ひかるの姿が見えない。
行かないで、ひかる。
ぼくのそばから、いなくならないで。
「大好きよ、光」
ひかるは優しくささやいた。
冷たいひかるの手が、光のほほを包む。
くちびるがふれた。
その瞬間、光はたしかに、ひかるのぬくもりを感じた。
あたたかく、やさしい、ひかるのくちびるを感じた。
そしてひかるは消えてしまった。
それから、季節はあっという間に過ぎていった。
光の住む街にも、何度か雪が降り、冷たい冬が駆け抜けていった。
気がつけば、南のほうからちらほらと桜のたよりが届くようになり、そして、市立明京小学校も卒業式の日を迎えていた。
光は、四月から進学する市内の公立中学の制服を着て、卒業式に出席した。
六年B組38人全員が、なんとか無事にこの日を迎えることができた。
三学期もほとんど不登校だった森本も、卒業式にだけは出てきた。足りない出席日数をおぎなうために、春休み、特別に補習授業を受けるらしい。
出席番号順に名前を呼ばれ、ひとりひとり校長先生から卒業証書を受け取る。
光は胸をはって、どうどうと証書を受け取った。
保護者席にいるお母さんも、誇らしそうに光の姿を見つめていた。
式が終わると、今度は教室で、小学生最後の通信簿を受け取る。
ふつうならそのあと、担任の先生から、一年間の総まとめや、中学生になるにあたってのこころがまえなど、いろんなお話があるのだろう。
けれど相沢先生はほとんどなにも言わず、さっさと最後のホームルームを切り上げた。
「それじゃあみんな、春休みもじゅうぶんからだに気をつけてね。中学へ行っても、がんばってください」
先生のあいさつが終わると、生徒たちも自分の荷物をまとめ、次々に教室を出ていく。
光も早く帰ろうとした。
この教室にいたって、楽しい思い出がうかんでくるわけでもない。
――むしろ、ロクでもないことばっか、思い出すよな。
結局、卒業まで友達はできなかったし、福田や金子は、今でも光を怖がって、怪物でも見るかのような目で見る。森本なんか、不登校で卒業すらあぶなかった。
それでも、いい。
いやなことは、終わったんだ。もう思い出さなければいい。
教室を出ようとした時、ドアのそばに高倉が立っているのに気がついた。
高倉は、ほとんどの女子が着ている公立中学の制服ではなかった。見慣れない、ちょっとおしゃれなセーラー服を着ている。
「そっか。高倉、私立中学、受験したんだっけ。合格おめでとう」
高倉はあいかわらず素っ気なく、ぼそっと「ありがと」と言った。
「あたしが合格できたの、半分はあんたのおかげでもあるんだけどね」
「え、ぼくの?」
高倉はうなずいた。
「あたしさ、最初は受験するの、迷ってたんだ。勉強、めんどくさいし、受かる自信もなかったし。でも――公立中学に行ったら、またこいつらと三年間、いっしょじゃん」
二人は教室を見回した。
同じ小学校の出身者は、たいがい中学の学区も同じだ。
クラスは替わり、ほかの小学校出身者もおおぜいくわわるが、大半の生徒が同じ学校に顔をそろえることになる。
「絶対、いやだったの。こんなヤツらとまた三年間、つきあわなきゃいけないなんて。だからあたし、めちゃめちゃ勉強したよ。なにがなんでも、私立に合格してやるって。公立よりお金かかってたいへんだけど、親にもいっしょうけんめい頼んだ。あんたがあの時、さわぎを起こさなきゃ、あたし、きっと覚悟が決まらなかった。ずっと迷って、もしかしたら受験もしなかったかもしれない。あんたがあれだけのことやったから、あたしも思いきって受験決めたの。井上があれだけやったんだから、あたしにも絶対できるって、思って」
光はだまって、ちょっと横を向いてしまった。
あらためてそんなことを言われると、なんだかとても照れくさい。
――言わなきゃ、いけないかな。高倉に、私立に行ってもがんばれよって。
「井上は、地元の中学に行くの?」
「うん。ぼくん家、私立に通えるほど、お金ないしさ」
「そう。でも、今の井上なら、どこに行ってもきっと大丈夫だね」
小声でそんなことを話しているうちに、教室に残っている生徒の数は、どんどん減っていった。
ふと気がつくと、相沢先生が光たちのそばに来ていた。
「相沢先生……」
「ごめんなさいね、井上くん。きみには、本当に迷惑かけちゃって」
あいかわらず誰の目も見ないようにしながら、相沢先生は言った。
言葉のひとつひとつが聞き取りにくいくらいの早口だった。ほんとうは光となんか話もしたくない、という気持ちが見え見えだ。
「いいえ――」
どう返事していいかわからず、光はつい、ぶすっと答えてしまった。
「でもね、もう二度と、こんなことないから。あなたたちとも、これっきり会うこともなくなると思うわ」
「え? どういうことですか?」
「先生ね、この三月で学校、辞めることにしたの。――教師を辞めるの」
まるで同じ大人に話すみたいに、相沢先生は言った。
「無理だったみたい、わたしには。やりたいこととできることは違うって、よくわかったわ」
「教師を辞めて、どうするんですか?」
「親元に帰って、お見合いでもして、結婚するわ。それくらいしか、ないもの」
相沢先生はむりやり笑顔を作ろうとした。
けれどその笑いはとてもぎこちなくて、口元がひくひくしている。
「どうせこんなクラス、何年経ったって、同窓会やろうなんて思う子はひとりもいないだろうし。あなたたちとも、ほんとにもう、これっきりね。ごめんなさいね、一年間、なんの力にもなってあげられなくて。でも井上くんなら、わたしの手助けなんて、きっと必要なかったわよね?」
ええ、そうですね、と答えるのすら、腹が立って、光はもうなにも言わなかった。
「二人とも、ご家族が待ってらっしゃるわよ。急ぎなさい」
相沢先生は、窓の外を見下ろした。
校庭には保護者たちが立ち、それぞれの子供たちが出てくるのを待っている。
「はい、先生」
「さようなら、相沢先生」
二人のあいさつに、相沢先生も小さくお辞儀を返した。そして逃げるように、早足で教室から出ていった。
「――なに、あれ」
相沢先生が出ていくとすぐに、我慢できなくなったみたいに、高倉が言った。
「先生を辞めるって……結局、逃げるんじゃん! この一年、なんにもしなかったくせに。自分がなんにもできなかったの、まるで井上のせいみたいに言って……!」
光もうなずいた。
「そうだよ。先生は、逃げるんだ」
相沢先生が出ていったドアをにらみながら、光は言った。まるで、まだそこに先生がいるかのように。
「でも、これから先生は、『自分は逃げたんだ』っていう負い目を、一生せおっていくことになる。自分の負い目と戦うのは、他人と戦うより、ずっとつらくて、むずかしいんだ。先生はまだ、そのことを知らない」
「井上……」
びっくりした顔で、高倉が光を見上げる。
「あ――、いや……。その……前に、ぼくにそう教えてくれた人がいるんだ」
「そう……」
高倉は少し、とまどうような表情になった。
「じゃあその人、あたしにも言うかな。……おまえだって、逃げたんだろうって」
「どうして、高倉が?」
「だってあたし、このクラスの連中と同じ学校に行きたくなくて、中学受験したんだもん。一人だけ別の学校に行こうと思ってさ」
「それは違うよ」
すぐに、光は言い切った。
「新しい学校に行ったからって、うまく行くとは限らないだろ。どこにだって嫌なヤツはいるし、新しい友達作ってくのだって、いろいろ努力しなきゃだしさ。前からの仲間とつきあってくほうが、楽なことだってあるじゃん。でも高倉は、楽な道を選ばないで、思いきって全部新しい道を選んだんだ。この先、どんなつらいことがあるかわからないけど、それでも、自分で全部作り直すことを選んだんだろ。だからそれは、逃げたんじゃない。うまく言えないけど――高倉は、チャレンジして、戦うことのほうを選んだんだ」
「井上」
今度は高倉が、少し照れくさそうな顔をした。
そして、にっこりと笑う。
「うん」
――高倉がこんなふうに笑うの、初めて、見た。
笑うと、高倉はとても可愛い。
「井上にそう言ってもらうと、なんか、ちょっと安心する。自分に、自信持てる気がする」
「うん。高倉なら大丈夫だよ」
高倉は持っていたショルダーバッグの中から、パールブルーのスマートフォンを取りだした。
「スマホ、新しいの買ってもらったの。受験に合格したお祝いにって。今までのクラスの連絡網とか、全部消したし」
あんたもスマホ出してよ、と、高倉は光にせっついた。
「こわしたとかっていうのも、どうせうそなんでしょ」
「うん、まあ……」
高倉は慣れた手つきでスマホを操作した。
光のスマホが赤外線で情報を受信して、ヴーッと短くバイブする。
「今、新しいIDと電話番号、送ったから。このID教えたの、あんただけだし。なんかヘンなメッセージとか来たら、井上からだってすぐにわかるからね!」
「し、しないよ、そんなこと!」
そして二人は、いっしょに昇降口へ向かって歩き出した。
「連絡するよ」
「うん。あたしも」
靴を履き替え、上履きシューズはそのまま手に持って、外へ出る。
「あ、ママだ! じゃあね、井上! またね!」
先に、高倉が走りだした。その先には、着物を着たきれいな女の人が立っている。高倉のお母さんだろう。
光は手を振って、高倉を見送った。
そして気がつけば、光のお母さんも、光のすぐそばに来ていた。
「光。卒業おめでとう」
「ありがとう、お母さん」
光はお母さんと並んで、明京小学校の校門を出た。
「光、ずいぶん背が高くなったね。その詰め襟、買う時にも思ったけど。もうすぐ、お母さん、追い越されちゃうね」
「え、そうかな」
六年間、通い慣れた通学路を、お母さんと二人で歩く。
もう二度と、通うことはないだろう道を。
「お母さん。ごめん……、先に帰っててくれるかな」
「どうかしたの?」
「うん。――どうしても、一人で寄りたい場所があるんだ」
光は立ち止まった。
お母さんも立ち止まり、光の顔をじっと見る。
そして、小さくうなずいた。
「わかったわ。じゃあ、家で待ってるね」
「ごめん、お母さん。わがままばっか言って」
ううん、と、お母さんは首を横にふった。
「早く帰っておいで。お祝いのごちそう作って、待ってるから」
マンションへ向かうお母さんと別れて、光は今来た道を戻り始めた。
大型車が行き交う、六車線の幹線道路。三月になって交通量はさらに増え、空気はひどく埃っぽい。
その上にかかる歩道橋を、光は駆け上がる。
ここで、ひかると出逢った。
あの時は、手がかじかむほど冷たい風が吹いていた。けれど今は、あったかい春のひざしがいっぱいにふりそそいでいる。
光も変わった。
ぼろぼろにされたリュックをかかえ、うつむいて泣いていた光が、今はこうして、新しい制服に身を包んで、しっかりと両脚を踏みしめて立っている。
――ひかる。今日、ぼく、小学校を卒業したよ。四月からは、中学生だ。
胸の中で、光はひかるに話しかけた。
ひかるに初めて会った時には、こんな日が来るなんて、想像もできなかった。
あれは、たった数ヶ月前のことなのに。
ひかるに、いろんなことを教わった。
いっしょに過ごした時間は、とても短かったけれど。
あの時、ひかるに出逢わなければ、きっと、ここにこうして立っていることはできなかっただろう。
――ありがとう、ひかる。
ひかるのおかげだ。
もう、ぼくは迷わないよ。苦しくても、つらくても、もう逃げないよ。
みんな、ひかるが教えてくれたんだ。
ひかるが教えてくれた言葉は、今も、ひとつ残らず、この胸の中にある。
――でも。
ひかる。
きみがいない。
今のぼくを、きみに見せたいと思っても。この気持ちを、どんなにきみにつたえたいと思っても。
ひかる。きみがいないんだ。
この世界中、どこを探しても、きみがいない。きみの名前をどんなに叫んでも、きみに届かない。
きみに逢いたい。ひかるに逢いたい。
でも、どこにもきみはいないんだ!
「ひかる――っ!!」
吹き抜ける風に向かって、光は思いきり、ひかるの名前を叫んだ。
涙があふれる。
こんなぼくを、きみはまた、泣き虫だと言って笑うだろうか。
それでも、いいよね。
泣いても、ころんでも、いい。泥だらけになって、傷ついて、それでも。
ぼくはまた、立ち上がるよ。
逃げないこと。戦うこと。そして生きること。みんなひかるが教えてくれた。
だから、ぼくは生きていく。
ひかる。もう二度と、きみに逢えないけれど。
それでもぼくは、生きていく。きみに守ってもらったこの命を、絶対にむだにしないために。
「好きだよ、ひかる」
光は、つぶやいた。
届くはずのない、告白。
それでも。
「大好きだよ。ずっとずっと、きみが大好きだよ、ひかる――!!」
光の声は、風に乗って、大空の向こうへ消えていった。
END
登校も下校もわざと遠回りして、信号のある大きな交差点を通った。歩道橋の見える場所までも近づかない。
ひかるに会いたくなかった。
会えばなにか言いたくなるけれど、なにを言えばいいのかもわからない。
ひかるのことを考えるだけで、どうしていいかわからなくなる。大声で叫びだしそうになってしまう。
逃げるしかなかったのだ。
だから、あの次の日、教室であったことを、ひかるに報告することはできなかった。
次の日、クラスの三分の一が欠席した。
森本も金子も休んでいた。きっと、怖かったのだろう。女子は半分近くの生徒が欠席していた。
出席した生徒も、みんなひどく顔色が悪くて、おちつきがなかった。まるで、みんな病人みたいだった。
全員、自分の席についたままうつむいて、顔をあげようともしない。
たまたま誰かと目があってしまうと、逃げるように顔をそむける。
たまに光を見る者もいるが、光と目が合うと、あわてて目をそらす。光が今もクラス中の話し声を録音しているとでも、思っているのだろうか。
インフルエンザでも流行してるみたいなクラスの様子に、相沢先生もとても驚いていた。
けれど、生徒たちに理由をたずねようとはしなかった。欠席した生徒の親からは「病気です」とかなんとか、連絡は入っていたのだろうし。
高倉は出席していたけれど、光と目が合うと、怒ったような顔をして、すぐにぷいっと横を向いてしまった。
――ま、あいつが女のくせに愛想悪いのは、もともとか。
教室はお葬式みたいに静まり返り、ものすごく居心地が悪かった。
みんな、ひかるのせいだ。光はそう思った。
――ひかるなんか、だいっきらいだ。エラそうなことばっか言って、結局、ぼくのクラスをめちゃくちゃにしただけじゃないか。
だいたい、ひかるなんて、ぼくのからだを乗っ取ろうとした、ずうずうしいヤツなんだ。
口ではぼくを助けたなんて言ってるけど、ほんとはなにを考えてるか、わかるもんか。
見ろよ、この教室。みんな休んじゃって、ガラガラで、こんなの見たことない。
こんなことになったのも、みんな、ひかるのせいなんだ。
言ってやるべきだろうか。ひかるに、これがあんたがやったことの結果だって。
もう一度ひかるを、この教室に連れてきて、見せてやるべきなんじゃないか。
――いいや、そんなことしたって、何の意味もないだろう。
光は小さく首をふり、自分の考えを否定した。
ひかるはきっと、こうなることもわかっていたはずだ。光が怒って、ひかるを許さないことも、最初からわかっていたと言ったのだから。
――そうだ。もう、ひかるに会う必要なんか、ない。
それよりは、これからどうするかを、考えなくちゃ。
……どうするかって、でも、いったいなにを?
六年B組の教室は、とても静かだった。
授業中によけいなおしゃべりをする生徒もいないし、休み時間にもなんのさわぎも起こらない。ケンカも、もちろん、いじめも。
教室の外から見れば、生徒たちはみんなおちついて、とてもいい子たちに見えるだろう。
給食当番はみんなに平等に給食をくばったし、放課後のそうじも、当番の生徒たちがきちんとやった。誰かひとりにむりやり押しつけるなんてことは、なかった。
理科の授業では、実験班を、今度は出席番号順に分けたので、光もふつうに顕微鏡をのぞくことができた。
ふつうに勉強して、トラブルなく一日をすごすこと。光のかわりに誰かがいじめられたりしないこと。
それはたしかに、光が望んだとおりの一日だった。
――ひかるはほんとうに、ぼくの願いをかなえてくれたんだ。
けして、うれしいとすなおによろこべはしない。
どんよりと沈んだ教室を見回すと、息が止まりそうに胸が苦しくなる。
怯えきったクラスメイトたちの目を見ると、光も泣きたいくらい、つらい。
……それでも。
やがて週末をすぎ、翌週の月曜になると、金子や福田、そして木島も登校してきた。
森本はまだ、休んでいた。
金子たちはふたりともひどく不安そうで、おちつきがなかった。
木島はひどくおどおどして、きょろきょろまわりを見回してばかりだ。顔色も悪く、今にも吐きそうだ。
光はあえて、彼らを無視した。
休み時間も一人ですごし、誰とも口をきかない。
そうやって、福田たちに態度で示してやろうと思ったのだ。ぼくはもう、おまえらなんかに興味はない、おまえらがぼくをほっといてくれるなら、ぼくもおまえらをほっといてやる、と。
おどおどきょろきょろが止まらない木島に、光の考えはつたわっていないのかもしれないが。
「ばかだな、木島。あんなにびくびくして、まるでニワトリみてえ。あれじゃ今度は、木島がいじめられるかもしんないぞ……」
「そこまであんたが心配する必要、ないんじゃない?」
「えっ!?」
突然の声に、光はびっくりして、思わず飛びあがりそうになってしまった。
木島について考えていたことが、つい声になっていたらしい。
「い、今のはべつに――!」
光はあわててまわりを見回した。
「気にすることないって。木島だって、いじめられたくなきゃ、井上のまねすればいいって、わかってるはずだもん」
妙にしらけた声で言ったのは、高倉だった。
「高倉……」
「ほら。あたしも持ってるし」
高倉は、メタリックピンクの小さな機械をポケットから取り出した。メーカーはちがうが、光のものと同じようなデジタルオーディオプレイヤーだった。
「イトコのお姉ちゃんにもらったの。新しいのに買い換えたって言うからさ、いらなくなった古いのをね」
「へえ……」
「もしかして、気がついてないの? 今、女子の半分は持ってるよ」
「――マジ?」
「だからみんな、前みたいにおしゃべりとか始めてんじゃん。ま、録音されても困んないように、天気の話くらいしかしないけどさ」
「天気の話、ね……」
光は小さく苦笑いした。
今日は寒いですね、ええ、そうですね、なんて、まるで知らない人どうしのあいさつみたいだ。
それでも、教室に少しずつ話し声が戻っていることに、光もようやく気がついた。
光と高倉がしゃべっているのが気になるのか、ちらちらこっちを見ている生徒もいる。
だが、ほとんどの生徒は関心なさそうな顔をしていた。よけいなことには首をつっこまないようにしているのだろう。
以前なら、男子と女子がちょっと口をきいただけで、すぐおおげさにさわぎたて、意地悪くからかうヤツがいたのに。
「でも考えたら、前だって、似たような話しかしてないしね。テレビのこととか、マンガのこととかさ。大事なことは、誰も話してなかったよ」
あまり感情のない声で、それこそお天気の話でもするみたいに、高倉は言った。
「このプレイヤーもらう時、あんたのやったこと、イトコに全部話したんだ。そしたらお姉ちゃん、『そいつ、すげーヤなヤツだね』って。『ヤなヤツ、マジ、友達になりたくないね。……でも、すげーアタマいいね』ってさ」
高倉は、まっすぐに光を見た。
「あたしもそう思う。井上、あんたって、マジで嫌なヤツだよね」
「……うん」
光はうなずいた。
――そうだ。ぼくはいやなヤツだ。
ひかるはぼくを守って、ぼくのために戦ってくれたのに。ぼくが望んでいたとおりの結果をもたらしてくれたのに。
ぼくはそれに、感謝することもできない。今もまだ、ひかるを許せないでいるんだ。
ぼくは……ひかるに守ってもらう価値なんて、きっと、なかったのに。
「でもあたし、あんたのしたことに、感謝してる」
はっきりと、高倉は言った。
「……え?」
「あたし……。ずっと、怖かった。あんたがいつか自殺するんじゃないかと思って」
するんじゃないか――じゃなくて、ほんとうに、しようと思ってたんだよ。その言葉を、光はぐっと飲み込んだ。
「そうなったらどうしようって、ずっと、怖かったんだ。いじめ自殺とかってなったら、きっとマスコミとかもいっぱい来て、大さわぎになっちゃう。そんな中で、クラス全員、顔隠しながら、あんたのお葬式とか行かされたりしてさ……。ほんとにそうなっちゃったらどうしようって、そんなことばっか、考えてたんだ。すげーヤなヤツだよね、あたしもさ。あんたがいじめられてるの、止めもしなかったくせに……!」
「高倉……」
高倉はちょっと、泣いているのかもしれない。光はそう思った。
「でもさ。あんた、もう自殺なんかしないよね」
「うん」
「ほかのヤツもさ、不登校してる森本だって、そうやって家ん中に引きこもってりゃ、とりあえず安全だしさ。少なくとも自殺だけはしないよね。あんたが森本ん家までおっかけてって、いじめのしかえししないかぎり」
「しないよ、そんなこと。めんどくさい」
ちょっとだけ、高倉は笑った。
「井上なら、そう言うと思った」
その笑顔に、光もなんだかほっとした。
やがてチャイムが鳴り、次の授業が始まった。
光はあわてて自分の席についた。高倉も、窓ぎわの席に戻る。
六年B組の教室はあいかわらず静かで、体育の時間なども、まったく活気がなかった。
それでも大きなトラブルはなく、また平穏に一日が終わった。
――これで、良かったんだろうか。
また遠回りして家に帰りながら、光は考えた。
高倉が言ったことを、ひかるに教えてあげようか。
クラスの中にも一人は、ひかるに感謝している子がいるって。
何度か立ち止まり、あの歩道橋へ行こうとした。
でも、どんな顔をしてひかるに会えばいいのか、わからない。
ひかるに会う、勇気がない。
結局、光はそのまま家に帰った。
マンションの玄関を開けるとすぐ、スマホが鳴った。
「あ、もしもし、光? ごめんね、お母さん、帰るの少し遅くなりそうなの。晩ご飯は……」
「うん、いいよ。カップメンでも食べてる」
お母さんが残業で遅くなるのは、今までにも何度かあった。そのたびに、光は一人でずっと留守番をしていた。
光はゲームやマンガで時間をつぶし、夕方になると、お湯を沸かしてカップメンを作った。
宿題を終わらせて、お風呂の用意をしても、お母さんをまだ帰ってこなかった。
お母さんが帰ってきたのは、夜九時近くになってからだった。
「ごめんね、光。遅くなっちゃって。ごはん、どうした?」
「うん、カップラーメン食べたよ」
「それだけじゃ、おなかすくでしょ。なにか、夜食作ろうか。お母さんもおなかすいたし」
「お母さん……。いいよ、ぼくがやる」
光は立ち上がった。お母さんをキッチンの椅子に座らせる。
「て言っても、カップメンくらいしか作れないけどさ。あ、それとも、パンでも焼こうか」
「どうしたの、光。急に親切になっちゃって」
お母さんは優しく、くすくす笑った。
「うん……」
光は少し、ためらった。
でも、思いきってお母さんにたずねてみる。
「お母さん、仕事、たいへん?」
「光……。どうしたの、いきなり」
「お父さんがいたころは、お母さん、働いてなかったじゃん。毎日、家にいてさ。それが、離婚してから急に働かなくちゃいけなくなって、家に帰ってきても、ぼくしかいないし、ぼく、あんまり家のこととか手伝ってないし……。やっぱり、たいへんだよね」
「光――」
お母さんの表情がくもった。少し哀しそうな目をして、光を見る。
「光……。お父さんとお母さんが離婚しないほうが良かったって、そう思ってる?」
「ううん!」
光は強く首を横にふった。
「離婚する前、お父さんとお母さん、毎日ケンカばっかりしてたよね。ぼくの前じゃ、二人とも、できるだけふつうの顔してたけど……。知ってたよ、ぼくも。お母さん……良く泣いてたよね。そんなつらい思いするなら、むりしていっしょにいることなんかない。少しくらい淋しくても、別れちゃったほうが良かったって、思ってる」
お母さんはじっと光の顔を見ていた。そして、小さくうなずく。
「そうよ。お母さんも、そう思ったの」
「だからお父さんと別れたんだよね。それがお母さんの、選択だったんだね」
「そうよ」
お母さんはうなずいた。
「お母さんは、まちがってないよ。自分で決めたことの責任を、ちゃんと自分ではたしてる。だからお母さんは、まちがってないよ」
お母さんは、自分が選んだ結果をちゃんと受け入れている。お父さんと二人で背負っていた責任を、今はたった一人で背負い続けて、それでもけんめいにがんばっている。
それがお母さんの、覚悟だ。
「光……」
お母さんは指先で、そっと目元をぬぐった。そうして、涙まじりの笑顔で笑顔で、光を見る。
「ありがとう、光。お母さんも、離婚はまちがいじゃないって思ってる。でも……あんたにそう言ってもらうと、ほんとうにうれしいわ」
光はポケットから、あのデジタルオーディオプレイヤーを出した。
ひかるが録音してくれた、いじめの証拠を。
「お母さん。ぼく、学校でずっと、いじめられてたんだ」
あの日の会話が再生された。
森本の声、福田の声、そして光の――ひかるの、声。
お母さんは息を飲んだ。大きく目を見開き、叫び声をおさえつけるように、片手で口をふさいだ。
「ごめん、お母さん。ぼく、ずっと言えなかった――!!」
その夜、光はお母さんと、夜遅くまでいろんなことを話しあった。
これからどうするの、と質問されて、光は、今はまだ、なにもするつもりはないよ、と答えた。
「さっきも言ったけど、今はクラスん中、けっこうおちついてるんだよ。いじめのリーダーだった森本ってヤツは、ずっと学校休んでるし。このままなにも起きないなら、ぼくはそれでいいと思うんだ」
「そう……。光がそう決めたんなら、お母さんも、もうなにも言わないわ」
お母さんは光の両手をにぎって、力強く言った。
「でも、あんた一人の力ではどうにもならないと思ったら、今度はもう、隠さないで。必ずお母さんに言ってね。お母さん、光のためなら、なんだってする。警察でも裁判所でも、どこへだって行くからね」
「お母さん」
光も、お母さんの手をぎゅっとにぎりかえした。
「光が戦うなら、お母さんもいっしょに戦う。二人っきりの家族なんだもの」
「うん。ありがとう、お母さん」
こんなに長いあいだ、お母さんと話をしたのは、ひさしぶりだった。
お母さんに、すなおにありがとうと言えたのも。
「あ……」
――そうだ。やっぱり、言わなくちゃ。
ひかるにも、「ありがとう」って、言わなくちゃ。
「お母さん、ごめん。ぼく、ちょっと出かけてくる」
「えっ? こんな夜中に?」
いけません、と言いかけたお母さんを、光はまっすぐに見上げた。
「だめなんだ。今すぐ行かなくちゃ、だめなんだよ」
今なら言える。でも、明日になったらまた、勇気がなくなってしまうかもしれない。
言わなくちゃ。ひかるに、会わなくちゃ。
「ほんの少しだけ。用事がすんだら、すぐに帰ってくる。約束するよ。だからお願い、お母さん!」
真剣な光の表情に、やがてお母さんも、あきらめたようにため息をついた。
「すぐ帰ってくるのよ。ケータイは持っていきなさい」
「うん! ありがとう、お母さん!」
光はジージャンをつかんで、ぱっと玄関へ向かった。
「なにかあったら、かならず連絡するのよ。お母さんが迎えに行くから」
「うん、わかってる。すぐに帰ってくるよ!」
靴をはくのももどかしく、光はマンションを飛び出した。
まっくらな夜の街を、あの歩道橋に向かって走る。
風はひどく冷たかった。もう冬が近いのだ。
けれどそんなことも、光はまったく気にならなかった。
やがて、六車線の大通りが見えてくる。
深夜になっても、幹線道路の交通量はあまり減っていない。大きなトラックが、昼間以上のスピードでどんどん走っていく。
そして、あの歩道橋の上に、ひかるはいた。
ひかるはとてもきれいだった。
長い髪が風にふわりとまいあがる。次々と足元を通りすぎる自動車のライトに照らされて、それはまるでひかるの翼みたいだった。
ひかる、と、光は大きな声で呼びかけようとした。
けれど全速力で走ってきたせいで、ぜいぜい息が切れて、うまく声が出ない。
「光」
さきにひかるのほうが、光の名を呼んだ。
「どうして、来たの?」
「どうしてって――」
苦しい息をおさえながら、どうにか光は声を出した。
「……迎えに、来たんだよ」
ゆっくりと、ひかるへ手を差し出す。
そして、気がついた。
ひかるの姿が、薄くなっている。
半透明の幽霊の姿が、さらに薄く、透けてしまっている。黒っぽいかっこいいパンツスーツは、ほとんど暗闇に溶けて、輪郭もはっきりわからないくらいだ。
「ど、どうしたの、ひかる……」
ひかるはなにも答えなかった。
だまって、優しい笑顔で、光を見ている。
「ね、ねえ。帰ろう。いっしょに家へ帰ろうよ、ひかる」
光は言った。
でも、その声が、みっともなくふるえだす。うわずって、まるで自分の声じゃないみたいだ。
「光――」
「帰ろう、ひかる! ゲーム、まだクリアしてないじゃんか! マンガだって――あれ、まだ連載中だよ。来週には、コミックスの最新刊が出るんだ。続きが読みたいって、ひかる、言ってたじゃんか!」
「ねえ、光」
「帰ろう、早く! また、ぼくのからだ、貸してあげるから!」
光は必死にしゃべり続けた。ひかるが口を開こうとするたびに、声をはりあげて、ひかるの言葉をかき消してしまう。
なにも聞きたくなかった。ひかるになにも言わせたくない。
聞いてしまったら――きっと、取り返しのつかないことになる。
「早く帰らないと、お母さんが心配する。だから、早くおいでよ、ひかる!」
ひかるは静かに、首を横にふった。
「家へは、あんたひとりで帰りなさい。あたしは……行けない」
「ど……どうして――。どうしてだよ、ひかる!」
今まで、ずっといっしょだったのに。
ひとつのからだを二人で使って、いっしょにゲームしたりマンガ読んだり、いろんなことを話したり。
とても楽しかった。
ひかるだって、とてもとても、楽しそうだったのに。
「ごめんよ、ひかる……。ぼくのこと、キライになっちゃったんだね。当然だよね。ぼく、ひかるにあんなひどいこと言っちゃって……」
光はこらえきれず、うつむいた。
そのほほに、すぅっと冷たい風のようなものがふれた。
ひかるの手だった。
「大好きよ。光」
光は顔をあげた。
ひかるが、光を見つめている。
今にも泣きそうな、けれどとてもきれいな笑顔で。
「じゃあ……、じゃあ、どうして――!」
「だってあたしは、もう死んじゃったんだもの」
透きとおったひかるの手は、たしかに光のほほにふれている。
けれど光は、それを感じることはできない。ただかすかに、冷たい風を感じるだけだ。
「あたしはもう、この世界のどこにもいないの。あんたが見てるあたしは、ただのまぼろしなのよ」
「う――うそだ!」
光は叫んだ。
「うそだ! そんなの、うそだ!!」
「いいえ。本当よ。光」
だって、ひかるはここにいるのに。
いろんなことを光に教えてくれて、今もこうして光と話をしているのに。
ひかるがまぼろしだと言うなら、どうしてこんなに苦しいんだ。胸の奥から熱い鋭い痛みがこみあげてきて、息もできないくらい、哀しいんだ。
「そんなこと、言わないでよ。ひかる……」
ぼろぼろと涙があふれてきた。
それでも光は、けんめいに笑おうとした。
なんでもないふりをして、笑って、そうして全部じょうだんだと思い込もうとした。
「そうだ、ひかる。ぼくのからだ、ひかるにあげるよ」
「――光!」
「言ってたじゃないか、ひかる。ぼくのからだがほしいって。だから、このからだをあげるよ。ぼくが幽霊になって、ひかるは生き返ればいい。そうすれば――」
「光」
静かに、ひかるは光の言葉をさえぎった。
「そんなこと、言っちゃだめだよ」
「どうして!? だって、ぼくはそれでいいんだ! ひかる……ひかる、あんなに楽しそうだったじゃないか。走ったり、ジャンプしたり、サッカーだって――! ぼくは、それを見てるだけで良かったんだ。ひかるが楽しいなら、ぼくだって楽しい。ぼく……ぼくは――!」
ひかるに、笑っていてもらいたいんだ。
ひかるが笑ってくれるなら、どんなことだって、できるよ。
「ぼくが、ひかるのためにしてあげられること……これしか、ないからさ。だから、ひかる――」
ひかるはもう一度、静かに首を横にふった。
「あんたに教えなきゃいけないことが、もうひとつ、残ってたね」
「ひかる……」
「ねえ、光。人はね、誰かの命を奪うことだけは、絶対にしちゃいけない。人の命を奪う権利は、この世の誰にも、ないんだよ」
ひかるは泣いていた。
涙が、すうっと銀の糸みたいに、ひかるのほほをこぼれていった。
「この世に生まれてきた以上、その命をむだにすることは、誰にも許されない。自分自身にもね。あんたの命を奪うことは、あたしにも、あんた自身にも、絶対に許されないの」
「だって……だって、ひかる――!」
ひかるの命は、奪われてしまったじゃないか。脇見運転していた、無責任なドライバーに。
「どうしてだか、わかる? 一度奪われた命は、もう二度と戻らないからだよ。あたしの命は、もう、誰にも取り戻せないの」
ひかるの姿が、ますます薄くなっていく。
声が遠ざかる。
「光。あたしのことなんか、もう、忘れちゃいな」
そんなこと、できない。光はそう叫ぼうとした。
どうして、ひかるのことを忘れられるだろう。
けれど。
「いいんだよ。忘れちゃいな。だってあたしは、もう死んじゃったんだから」
いやだよ、ひかる。
どうしてそんなことを言うの。
ぼくはまだ、ひかるといっしょにいたいよ。
もっともっと、ひかるといっしょに過ごしたい。二人でいろんなことを話して、いっぱい遊んで、いっぱい笑って。
そうだよ――ぼくは、ぼくは……!!
「あたしは、消えなきゃいけない。死んだ人間は死んだ人間、もうこの世界のどこにもいないの。あんたの目に、映っていちゃいけないんだよ」
もう、声が出ない。ひかるの名前が呼べない。
ひかるの姿が見えない。
行かないで、ひかる。
ぼくのそばから、いなくならないで。
「大好きよ、光」
ひかるは優しくささやいた。
冷たいひかるの手が、光のほほを包む。
くちびるがふれた。
その瞬間、光はたしかに、ひかるのぬくもりを感じた。
あたたかく、やさしい、ひかるのくちびるを感じた。
そしてひかるは消えてしまった。
それから、季節はあっという間に過ぎていった。
光の住む街にも、何度か雪が降り、冷たい冬が駆け抜けていった。
気がつけば、南のほうからちらほらと桜のたよりが届くようになり、そして、市立明京小学校も卒業式の日を迎えていた。
光は、四月から進学する市内の公立中学の制服を着て、卒業式に出席した。
六年B組38人全員が、なんとか無事にこの日を迎えることができた。
三学期もほとんど不登校だった森本も、卒業式にだけは出てきた。足りない出席日数をおぎなうために、春休み、特別に補習授業を受けるらしい。
出席番号順に名前を呼ばれ、ひとりひとり校長先生から卒業証書を受け取る。
光は胸をはって、どうどうと証書を受け取った。
保護者席にいるお母さんも、誇らしそうに光の姿を見つめていた。
式が終わると、今度は教室で、小学生最後の通信簿を受け取る。
ふつうならそのあと、担任の先生から、一年間の総まとめや、中学生になるにあたってのこころがまえなど、いろんなお話があるのだろう。
けれど相沢先生はほとんどなにも言わず、さっさと最後のホームルームを切り上げた。
「それじゃあみんな、春休みもじゅうぶんからだに気をつけてね。中学へ行っても、がんばってください」
先生のあいさつが終わると、生徒たちも自分の荷物をまとめ、次々に教室を出ていく。
光も早く帰ろうとした。
この教室にいたって、楽しい思い出がうかんでくるわけでもない。
――むしろ、ロクでもないことばっか、思い出すよな。
結局、卒業まで友達はできなかったし、福田や金子は、今でも光を怖がって、怪物でも見るかのような目で見る。森本なんか、不登校で卒業すらあぶなかった。
それでも、いい。
いやなことは、終わったんだ。もう思い出さなければいい。
教室を出ようとした時、ドアのそばに高倉が立っているのに気がついた。
高倉は、ほとんどの女子が着ている公立中学の制服ではなかった。見慣れない、ちょっとおしゃれなセーラー服を着ている。
「そっか。高倉、私立中学、受験したんだっけ。合格おめでとう」
高倉はあいかわらず素っ気なく、ぼそっと「ありがと」と言った。
「あたしが合格できたの、半分はあんたのおかげでもあるんだけどね」
「え、ぼくの?」
高倉はうなずいた。
「あたしさ、最初は受験するの、迷ってたんだ。勉強、めんどくさいし、受かる自信もなかったし。でも――公立中学に行ったら、またこいつらと三年間、いっしょじゃん」
二人は教室を見回した。
同じ小学校の出身者は、たいがい中学の学区も同じだ。
クラスは替わり、ほかの小学校出身者もおおぜいくわわるが、大半の生徒が同じ学校に顔をそろえることになる。
「絶対、いやだったの。こんなヤツらとまた三年間、つきあわなきゃいけないなんて。だからあたし、めちゃめちゃ勉強したよ。なにがなんでも、私立に合格してやるって。公立よりお金かかってたいへんだけど、親にもいっしょうけんめい頼んだ。あんたがあの時、さわぎを起こさなきゃ、あたし、きっと覚悟が決まらなかった。ずっと迷って、もしかしたら受験もしなかったかもしれない。あんたがあれだけのことやったから、あたしも思いきって受験決めたの。井上があれだけやったんだから、あたしにも絶対できるって、思って」
光はだまって、ちょっと横を向いてしまった。
あらためてそんなことを言われると、なんだかとても照れくさい。
――言わなきゃ、いけないかな。高倉に、私立に行ってもがんばれよって。
「井上は、地元の中学に行くの?」
「うん。ぼくん家、私立に通えるほど、お金ないしさ」
「そう。でも、今の井上なら、どこに行ってもきっと大丈夫だね」
小声でそんなことを話しているうちに、教室に残っている生徒の数は、どんどん減っていった。
ふと気がつくと、相沢先生が光たちのそばに来ていた。
「相沢先生……」
「ごめんなさいね、井上くん。きみには、本当に迷惑かけちゃって」
あいかわらず誰の目も見ないようにしながら、相沢先生は言った。
言葉のひとつひとつが聞き取りにくいくらいの早口だった。ほんとうは光となんか話もしたくない、という気持ちが見え見えだ。
「いいえ――」
どう返事していいかわからず、光はつい、ぶすっと答えてしまった。
「でもね、もう二度と、こんなことないから。あなたたちとも、これっきり会うこともなくなると思うわ」
「え? どういうことですか?」
「先生ね、この三月で学校、辞めることにしたの。――教師を辞めるの」
まるで同じ大人に話すみたいに、相沢先生は言った。
「無理だったみたい、わたしには。やりたいこととできることは違うって、よくわかったわ」
「教師を辞めて、どうするんですか?」
「親元に帰って、お見合いでもして、結婚するわ。それくらいしか、ないもの」
相沢先生はむりやり笑顔を作ろうとした。
けれどその笑いはとてもぎこちなくて、口元がひくひくしている。
「どうせこんなクラス、何年経ったって、同窓会やろうなんて思う子はひとりもいないだろうし。あなたたちとも、ほんとにもう、これっきりね。ごめんなさいね、一年間、なんの力にもなってあげられなくて。でも井上くんなら、わたしの手助けなんて、きっと必要なかったわよね?」
ええ、そうですね、と答えるのすら、腹が立って、光はもうなにも言わなかった。
「二人とも、ご家族が待ってらっしゃるわよ。急ぎなさい」
相沢先生は、窓の外を見下ろした。
校庭には保護者たちが立ち、それぞれの子供たちが出てくるのを待っている。
「はい、先生」
「さようなら、相沢先生」
二人のあいさつに、相沢先生も小さくお辞儀を返した。そして逃げるように、早足で教室から出ていった。
「――なに、あれ」
相沢先生が出ていくとすぐに、我慢できなくなったみたいに、高倉が言った。
「先生を辞めるって……結局、逃げるんじゃん! この一年、なんにもしなかったくせに。自分がなんにもできなかったの、まるで井上のせいみたいに言って……!」
光もうなずいた。
「そうだよ。先生は、逃げるんだ」
相沢先生が出ていったドアをにらみながら、光は言った。まるで、まだそこに先生がいるかのように。
「でも、これから先生は、『自分は逃げたんだ』っていう負い目を、一生せおっていくことになる。自分の負い目と戦うのは、他人と戦うより、ずっとつらくて、むずかしいんだ。先生はまだ、そのことを知らない」
「井上……」
びっくりした顔で、高倉が光を見上げる。
「あ――、いや……。その……前に、ぼくにそう教えてくれた人がいるんだ」
「そう……」
高倉は少し、とまどうような表情になった。
「じゃあその人、あたしにも言うかな。……おまえだって、逃げたんだろうって」
「どうして、高倉が?」
「だってあたし、このクラスの連中と同じ学校に行きたくなくて、中学受験したんだもん。一人だけ別の学校に行こうと思ってさ」
「それは違うよ」
すぐに、光は言い切った。
「新しい学校に行ったからって、うまく行くとは限らないだろ。どこにだって嫌なヤツはいるし、新しい友達作ってくのだって、いろいろ努力しなきゃだしさ。前からの仲間とつきあってくほうが、楽なことだってあるじゃん。でも高倉は、楽な道を選ばないで、思いきって全部新しい道を選んだんだ。この先、どんなつらいことがあるかわからないけど、それでも、自分で全部作り直すことを選んだんだろ。だからそれは、逃げたんじゃない。うまく言えないけど――高倉は、チャレンジして、戦うことのほうを選んだんだ」
「井上」
今度は高倉が、少し照れくさそうな顔をした。
そして、にっこりと笑う。
「うん」
――高倉がこんなふうに笑うの、初めて、見た。
笑うと、高倉はとても可愛い。
「井上にそう言ってもらうと、なんか、ちょっと安心する。自分に、自信持てる気がする」
「うん。高倉なら大丈夫だよ」
高倉は持っていたショルダーバッグの中から、パールブルーのスマートフォンを取りだした。
「スマホ、新しいの買ってもらったの。受験に合格したお祝いにって。今までのクラスの連絡網とか、全部消したし」
あんたもスマホ出してよ、と、高倉は光にせっついた。
「こわしたとかっていうのも、どうせうそなんでしょ」
「うん、まあ……」
高倉は慣れた手つきでスマホを操作した。
光のスマホが赤外線で情報を受信して、ヴーッと短くバイブする。
「今、新しいIDと電話番号、送ったから。このID教えたの、あんただけだし。なんかヘンなメッセージとか来たら、井上からだってすぐにわかるからね!」
「し、しないよ、そんなこと!」
そして二人は、いっしょに昇降口へ向かって歩き出した。
「連絡するよ」
「うん。あたしも」
靴を履き替え、上履きシューズはそのまま手に持って、外へ出る。
「あ、ママだ! じゃあね、井上! またね!」
先に、高倉が走りだした。その先には、着物を着たきれいな女の人が立っている。高倉のお母さんだろう。
光は手を振って、高倉を見送った。
そして気がつけば、光のお母さんも、光のすぐそばに来ていた。
「光。卒業おめでとう」
「ありがとう、お母さん」
光はお母さんと並んで、明京小学校の校門を出た。
「光、ずいぶん背が高くなったね。その詰め襟、買う時にも思ったけど。もうすぐ、お母さん、追い越されちゃうね」
「え、そうかな」
六年間、通い慣れた通学路を、お母さんと二人で歩く。
もう二度と、通うことはないだろう道を。
「お母さん。ごめん……、先に帰っててくれるかな」
「どうかしたの?」
「うん。――どうしても、一人で寄りたい場所があるんだ」
光は立ち止まった。
お母さんも立ち止まり、光の顔をじっと見る。
そして、小さくうなずいた。
「わかったわ。じゃあ、家で待ってるね」
「ごめん、お母さん。わがままばっか言って」
ううん、と、お母さんは首を横にふった。
「早く帰っておいで。お祝いのごちそう作って、待ってるから」
マンションへ向かうお母さんと別れて、光は今来た道を戻り始めた。
大型車が行き交う、六車線の幹線道路。三月になって交通量はさらに増え、空気はひどく埃っぽい。
その上にかかる歩道橋を、光は駆け上がる。
ここで、ひかると出逢った。
あの時は、手がかじかむほど冷たい風が吹いていた。けれど今は、あったかい春のひざしがいっぱいにふりそそいでいる。
光も変わった。
ぼろぼろにされたリュックをかかえ、うつむいて泣いていた光が、今はこうして、新しい制服に身を包んで、しっかりと両脚を踏みしめて立っている。
――ひかる。今日、ぼく、小学校を卒業したよ。四月からは、中学生だ。
胸の中で、光はひかるに話しかけた。
ひかるに初めて会った時には、こんな日が来るなんて、想像もできなかった。
あれは、たった数ヶ月前のことなのに。
ひかるに、いろんなことを教わった。
いっしょに過ごした時間は、とても短かったけれど。
あの時、ひかるに出逢わなければ、きっと、ここにこうして立っていることはできなかっただろう。
――ありがとう、ひかる。
ひかるのおかげだ。
もう、ぼくは迷わないよ。苦しくても、つらくても、もう逃げないよ。
みんな、ひかるが教えてくれたんだ。
ひかるが教えてくれた言葉は、今も、ひとつ残らず、この胸の中にある。
――でも。
ひかる。
きみがいない。
今のぼくを、きみに見せたいと思っても。この気持ちを、どんなにきみにつたえたいと思っても。
ひかる。きみがいないんだ。
この世界中、どこを探しても、きみがいない。きみの名前をどんなに叫んでも、きみに届かない。
きみに逢いたい。ひかるに逢いたい。
でも、どこにもきみはいないんだ!
「ひかる――っ!!」
吹き抜ける風に向かって、光は思いきり、ひかるの名前を叫んだ。
涙があふれる。
こんなぼくを、きみはまた、泣き虫だと言って笑うだろうか。
それでも、いいよね。
泣いても、ころんでも、いい。泥だらけになって、傷ついて、それでも。
ぼくはまた、立ち上がるよ。
逃げないこと。戦うこと。そして生きること。みんなひかるが教えてくれた。
だから、ぼくは生きていく。
ひかる。もう二度と、きみに逢えないけれど。
それでもぼくは、生きていく。きみに守ってもらったこの命を、絶対にむだにしないために。
「好きだよ、ひかる」
光は、つぶやいた。
届くはずのない、告白。
それでも。
「大好きだよ。ずっとずっと、きみが大好きだよ、ひかる――!!」
光の声は、風に乗って、大空の向こうへ消えていった。
END
2
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。
猫菜こん
児童書・童話
小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。
中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!
そう意気込んでいたのに……。
「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」
私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。
巻き込まれ体質の不憫な中学生
ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主
咲城和凜(さきしろかりん)
×
圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良
和凜以外に容赦がない
天狼絆那(てんろうきずな)
些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。
彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?
「おい、俺の和凜に何しやがる。」
「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」
「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」
王道で溺愛、甘すぎる恋物語。
最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

転生妃は後宮学園でのんびりしたい~冷徹皇帝の胃袋掴んだら、なぜか溺愛ルート始まりました!?~
☆ほしい
児童書・童話
平凡な女子高生だった私・茉莉(まり)は、交通事故に遭い、目覚めると中華風異世界・彩雲国の後宮に住む“嫌われ者の妃”・麗霞(れいか)に転生していた!
麗霞は毒婦だと噂され、冷徹非情で有名な若き皇帝・暁からは見向きもされない最悪の状況。面倒な権力争いを避け、前世の知識を活かして、後宮の学園で美味しいお菓子でも作りのんびり過ごしたい…そう思っていたのに、気まぐれに献上した「プリン」が、甘いものに興味がないはずの皇帝の胃袋を掴んでしまった!
「…面白い。明日もこれを作れ」
それをきっかけに、なぜか暁がわからの好感度が急上昇! 嫉妬する他の妃たちからの嫌がらせも、持ち前の雑草魂と現代知識で次々解決! 平穏なスローライフを目指す、転生妃の爽快成り上がり後宮ファンタジー!

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート
谷川 雅
児童書・童話
この世界、子どもがエリート。
“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。
そして14歳で、まさかの《定年》。
6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。
だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!
――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。
だが、そんな幸弘の前に現れたのは、
「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。
これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。
描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

極甘独占欲持ち王子様は、優しくて甘すぎて。
猫菜こん
児童書・童話
私は人より目立たずに、ひっそりと生きていたい。
だから大きな伊達眼鏡で、毎日を静かに過ごしていたのに――……。
「それじゃあこの子は、俺がもらうよ。」
優しく引き寄せられ、“王子様”の腕の中に閉じ込められ。
……これは一体どういう状況なんですか!?
静かな場所が好きで大人しめな地味子ちゃん
できるだけ目立たないように過ごしたい
湖宮結衣(こみやゆい)
×
文武両道な学園の王子様
実は、好きな子を誰よりも独り占めしたがり……?
氷堂秦斗(ひょうどうかなと)
最初は【仮】のはずだった。
「結衣さん……って呼んでもいい?
だから、俺のことも名前で呼んでほしいな。」
「さっきので嫉妬したから、ちょっとだけ抱きしめられてて。」
「俺は前から結衣さんのことが好きだったし、
今もどうしようもないくらい好きなんだ。」
……でもいつの間にか、どうしようもないくらい溺れていた。

モブの私が理想語ったら主役級な彼が翌日その通りにイメチェンしてきた話……する?
待鳥園子
児童書・童話
ある日。教室の中で、自分の理想の男の子について語った澪。
けど、その篤実に同じクラスの主役級男子鷹羽日向くんが、自分が希望した理想通りにイメチェンをして来た!
……え? どうして。私の話を聞いていた訳ではなくて、偶然だよね?
何もかも、私の勘違いだよね?
信じられないことに鷹羽くんが私に告白してきたんだけど、私たちはすんなり付き合う……なんてこともなく、なんだか良くわからないことになってきて?!
【第2回きずな児童書大賞】で奨励賞受賞出来ました♡ありがとうございます!
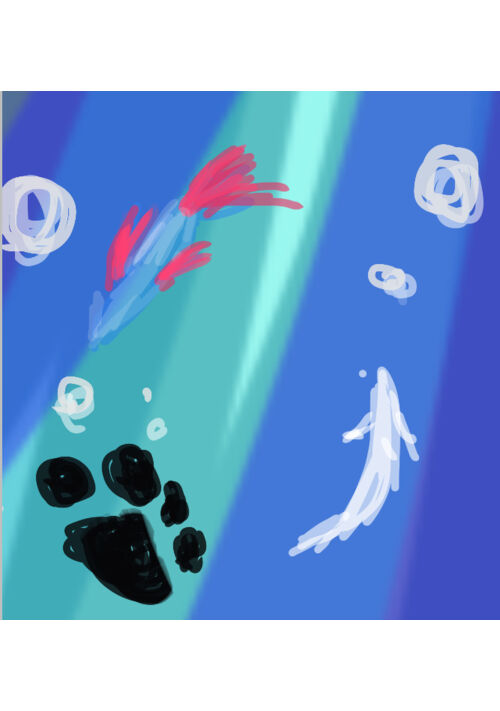
25匹の魚と猫と
ねこ沢ふたよ
児童書・童話
コメディです。
短編です。
暴虐無人の猫に一泡吹かせようと、水槽のメダカとグッピーが考えます。
何も考えずに笑って下さい
※クラムボンは笑いません
25周年おめでとうございます。
Copyright©︎

ホントのキモチ!
望月くらげ
児童書・童話
中学二年生の凜の学校には人気者の双子、樹と蒼がいる。
樹は女子に、蒼は男子に大人気。凜も樹に片思いをしていた。
けれど、大人しい凜は樹に挨拶すら自分からはできずにいた。
放課後の教室で一人きりでいる樹と出会った凜は勢いから告白してしまう。
樹からの返事は「俺も好きだった」というものだった。
けれど、凜が樹だと思って告白したのは、蒼だった……!
今さら間違いだったと言えず蒼と付き合うことになるが――。
ホントのキモチを伝えることができないふたり(さんにん?)の
ドキドキもだもだ学園ラブストーリー。

生贄姫の末路 【完結】
松林ナオ
児童書・童話
水の豊かな国の王様と魔物は、はるか昔にある契約を交わしました。
それは、姫を生贄に捧げる代わりに国へ繁栄をもたらすというものです。
水の豊かな国には双子のお姫様がいます。
ひとりは金色の髪をもつ、活発で愛らしい金のお姫様。
もうひとりは銀色の髪をもつ、表情が乏しく物静かな銀のお姫様。
王様が生贄に選んだのは、銀のお姫様でした。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















