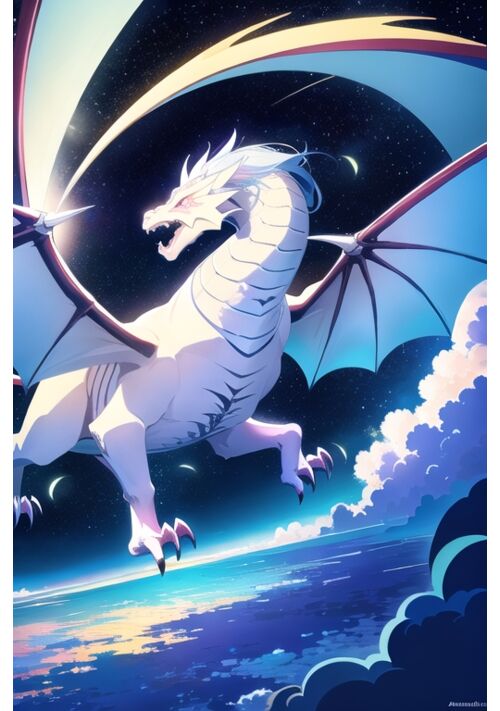4 / 67
一章 北の辺境伯領へ
4:北の老公
しおりを挟む
エリック=ハルドが危惧した通り、雨上がりの道は酷くぬかるんでいた。御者が苦戦しながら馬車を走らせること、四日。通常よりも一日長くかかったが、アメリアの乗る馬車は城塞都市バラリオスに到着した――。
「わあっ、高い城壁ですね!」
馬車の窓から見える景色にリサがはしゃいだ声を挙げる。緊張のせいか、当初のリサは大人びて見えていた。しかし半月余りを一緒に過ごしている内に、十三歳の彼女は年相応の子供らしさを見せるようになった。
アメリアは少女を横目で見たあと、自身も窓の外に目を向ける。
城塞都市と言うだけあって、まず目に飛びこんでくるのは石造りの高い城壁だ。城壁はぐるりと町を囲んでいて、出入りできる場所は東西南北にある四か所の門だけらしい。アメリアたちは馬車が行き交う、南門からバラリオスに入ることになった。
通行証を確認する門番はエリックの知人のようだ。彼が馬から降りて帰還を伝えると、門付近の詰所からワラワラと騎士たちが出てきた。誰もかれも屈強で、その場の密度がグッと上がる。
「エリック! 戻って来たんだな!」
「ああ」
「ってことは、その馬車に乗っているのが?」
「御老公様の奥方になられるご令嬢か!」
「どんな方だ? 女傑然りとした人物か?」
チラチラと視線を向けられているのに気付いた。アメリアの脳裏に挨拶すべきだろうかという考えもよぎったが、婚姻相手と顔を合わせていない状況で、先に臣下の騎士たちに声をかけるのもおかしな話だ。とはいえ無視をするのもどうだろう。正解がわからないでいると、馬車の窓を隠すようにエリックが立ちはだかった。
「興味本位で覗き見しようとするな。こんな風に取り囲むのも無礼だぞ」
「あ……そうだ、な。すまん……」
屈強な騎士たちは馬車から少し離れて並ぶと、胸に手を当てて一斉に頭を下げた。アメリアは目を丸くする。北の地を守る高潔な騎士が、たかだか男爵家の娘に対して敬意を表すなんて、想像もしていなかった。
婚姻を結ぶ事実が周知されているとも、辺境伯家の面々や関係者にまともな対応をされるとも思っていなかった。期待していなかったのだ。
エリックが馬車の窓越しにアメリアを見る。彼が何を言いたいのか察し、アメリアは小さく頷いた。エリックが未だ頭を下げる騎士たちに声をかけると、彼らは顔を上げる。彼女は名前も知らない騎士たちに頭を下げ返した。
止まっていた馬車が動き出す。
馬車から見える城塞都市の街並みに、リサが度々、感嘆の声を漏らしていた。その傍らでアメリアは口を閉じたまま、自分の中で言いようのない感情が湧き起こるのを感じていた。これまでに抱いたことのない、不思議な感情だ。
(もやもやする……ううん、じわじわ、かしら……変な気持ちね。こんなの初めてだわ……今なら……これまでとは違う味の絵が描けるかもしれないわね)
流れていく景色をぼんやりと眺める。
北に敵を抱える辺境伯領だからか、城塞都市だからか、バラリオスには武器屋や防具屋が多いようだ。近くには酒場や食料品店、衣料品店など大衆向けの店もある。この辺りは一般市民の居住区になっているらしい。
そのまま奥――町の中心へ進んで行くと、建物や商店の様相が変わってきた。どうやらバラリオスは中心に行くほど裕福な人間が多いようで、それに合わせた高級店が建ち並んでいる。
つまり中央に住んでいるのは――
「お嬢様、お城です。お城が近付いて来ました!」
リサが声を上げた。
馬車の先に高くそびえる城が見えた。町の中でも一段高いところにあり、そこもまた、外壁ほど高くはないが城壁に囲まれている。城塞都市の中心というだけあって物々しく、頑丈そうな建物だった。
城の正門でエリックが門番に声をかける。小さな馬車が城内へ入った。玄関まで距離があるらしい。速度を落とした馬車は長いアプローチを進んで行く。興奮を緊張が凌駕してきたのかリサはすっかり黙り込んでいた。
やがて動いていた馬車が、停まった。
扉がノックされる。到着したようだ。アメリアが席を立つのと同時に、エリックが外から扉を開けた。騎士が差し出した手の平に手を重ねて、彼女はバラリオスの地を踏んだ――
(あれは……)
地面に足をつけて前を向いたアメリアは、城の玄関に立つ人物を視界に入れて、目を見開く。遠目でもわかるくらい大きな、真っ白な人がいた。服も、髪も、整えられたヒゲも、肌も、白い。
後ろでリサが馬車を降りる気配がしたが、アメリアは近付いて来る人物から目が離せない。それほどの存在感があった。
足が長いからか、歩幅が広いからか、その人はあっと言う間にアメリアの前にやって来た。老人と呼ぶにはあまりにも屈強でたくましい身体つきで、凛としている。
名乗られなくても、その人物が誰なのかわかった。
「そなたがアメリア嬢で相違ないか」
腹の底に響くような、低く渋い声だ。
「はい。ローズハート男爵が長女、アメリアにございます」
アメリアは片足を後ろに引き、ドレスの裾をつまんで首を垂れる。視界に大きな足が映った。
「ああ、そんなに畏まらなくていい。頭を上げてくれ」
そう言われて素直に身体を起こし、自分よりも頭ふたつ分は高いところにある、顔を見上げる。白と銀が混ざったような光り輝く髪、鼻の下と顎で整えられたヒゲ、北の地に住む人特有の透けるような真っ白な肌、ホワイトディアの一族のみに許された白い軍服……その巨躯と相まって、白熊を彷彿とさせた。
けれど、アメリアの頭に浮かんだ白熊は、すぐに別の動物へと姿を変えていく。白の中で深い色の、紅玉の瞳が存在感を放っていた。生気に満ち溢れて爛々と燃えている。
「雪兎……」
頭の中で愛らしい小動物が跳ね回っていた。だから、無意識の内に呟いてしまった。
「雪兎?」
微かな呟きでも相手に届いてしまったようだ。紅玉の目を丸くした彼が、首を傾げながら聞き返してくる。自分の失態に気付いたアメリアは「失礼しました」と、小声で謝罪の言葉を告げた。
「ははっ、そうか、雪兎か!」
大きな白熊は肩を揺らして豪快に笑う。機嫌を損ねたわけではないらしく、ひとまずアメリアは安堵の息を漏らした。
やがてひとしきり笑うと、大柄な彼はアメリアを見下ろしてニッと目を細めた。目尻に皺が寄る。
「初対面で雪兎だと言われたのは、生まれて初めてだ。ホワイトディア――白鹿の名前ですら似合わんと言われるのに、雪兎ときたか。我が花嫁殿の翡翠のまなこは、えらく奇特な世界を映すらしい」
「花嫁……では、やはりあなた様が……」
「ああ。私が、恥ずかしげもなく孫ほど歳の離れた令嬢に婚姻を申し込んだ好色ジジイ、オリオン=デイヴィス=ホワイトディアだ」
「………………」
アメリアは目をまたたかせた。
(好色ジジイ……)
目の前の人物からそんな感じはまったくしないが、人は見かけによらないという言葉もある。そして、英雄色を好むという言葉も、あるのだ。オリオン=デイヴィス=ホワイトディアは間違いなく英雄だ。だとすれば……。
黙りこんでしまったアメリアと、オリオンが見つめ合う。
ふたりの沈黙を破ったのは、近付いて来たひとりの使用人だった。きっちりと身なりを整えた老人だ。細身の体躯だが姿勢は真っ直ぐで足取りもしっかりしている。薄いレンズのモノクルをかけていて、真面目そうな雰囲気を醸し出していた。
「オリオン様、僭越ながら申し上げます」
「ん? なんだ、エリティカ」
オリオンはエリティカと呼んだ男のほうを見る。ただの使用人ではないのだろう。エリティカは呆れたと言わんばかりの胡乱な目を、主人へ向けていた。
「貴方様の冗談は非常に分かりにくいのです」
「何?」
「何、ではありません。お嬢様が絶句しておられます」
「それはいかんな」
オリオンがハッとした顔でアメリアへ向き直る。
「今のは冗談だ」
「冗談、ですか」
「主はお嬢様が緊張なさっているのではないかと思い、雰囲気を和ませようとなさったのです。しかしご覧の通り、その手のことに慣れていらっしゃる方ではありませんので、下手を打ってしまわれたご様子。どうぞ寛大なお心でお許しいただけますと幸いにございます」
恭しく頭を下げるエリティカと、気まずげに頬を掻くオリオンを順に見て、アメリアは「そうだったのですね」と納得した。
「お気遣いいただきありがとうございます。その……今のお言葉が冗談であるとするなら、ひとつお尋ねしたいことがあります」
「ひとつと言わず、いくらでも構わんが……尋ねたいこととは?」
「わたしを伴侶として迎えていただく理由はなんでしょう? これまで、お目にかかったことすらないと思うのですが」
「ふむ……」
オリオンは顎で整えたヒゲを撫でながら頷く。
「もっともな疑問だ。今まで答えがわからぬまま、さぞかしやきもきしていたことだろう。その問いに答える前に場所を変えても良いだろうか?」
「あ、はい、もちろんです」
「エリティカ、温室の支度は?」
「万事整っております」
「さすがだな。我が執事は仕事が早い」
「恐れ入ります」
北の英雄は太い首を動かして満足そうに首肯すると、アメリアのほうへ手の平を差し出してきた。硬そうな、大きな手だ。自分のものとはまったく違う。長年、領地を守る為に武器を取り、最前線で戦ってきた戦士の手だった。
何故かその手が尊いもののように思えて、ほんの少し、アメリアは手を重ねるのを躊躇った。それでもそっと手を伸ばして、重ねる。かさついた皮膚の感触。指先に温かさを感じてようやく、彼女は自分の手が普段よりも冷たくなっていることに気付いた。
(寒さのせい、じゃないわ。わたし、緊張していたのね)
アメリアはオリオンにエスコートされながら、温室へ案内してもらう。足の長さが違うのに、早足になることも、遅れることもない。無理をしないように歩幅を合わせてくれていた。
温室は城内の中庭を通った先にあり、辿りつくまでに何人もの使用人や騎士とすれ違った。首を垂れる者たちに、オリオンは時折足を止めては、アメリアを我が花嫁殿だと紹介する。紹介された使用人たちは祝福の言葉を口にした。
アメリアの疑問がますます膨らんでいく。
オリオン=ホワイトディアとは祖父と孫ほど歳が離れている。その上、本来であれば顔を見ることすら叶わないような、先代とはいえ、偉大な北の王だ。男爵家の小娘でしかない自分を丁寧に扱ってくれることに、混乱せずにいられない。
(どういうことなのかしら……? 婚姻後わたしを捨て置くのなら、顔を見せて回らないほうがいいと思うのだけれど……)
後ろでは、バラリオスの城の巨大さにリサが感嘆の声を上げっぱなしだった。その度にエリックがあれはなんだ、これはなんだと短く説明をし、気心の知れた様子がうかがえる。
「旅路で打ち解け合ったらしいな」
オリオンがチラリと後ろに視線を向けた。
「リサたちのことですか?」
「ああ。まるで兄妹のようだ」
「ハルド卿には大変お世話になりました。旅に不慣れなわたしたちを気遣ってくださって、おかげでなんの不便もなく辿りつくことが叶いました」
「そうか。それは良かった。真面目と言えば聞こえはいいが、堅物な男だ。うら若き令嬢に粗相をしなかったと知れば、エリティカも安堵することだろう」
「先ほどの、執事の?」
「ああ。エリックはエリティカの末の息子だ。確か五番目か、六番目か……どっちだったかのう?」
隣を歩くオリオンが後ろをついて来る青年騎士に問いかける。エリックは「七番目です」と答えた。
「おそらく四番目の兄ミリスを飛ばされているのかと。あの人は自分の顔にもっとも似合う装いだと公言し、常日頃ドレス姿で過ごしていますので」
「男性がドレスを!?」
思わず声を上げてしまったのだろう。リサは口を挟んだ失態に気付き、慌てて「失礼しました!」と謝罪する。頭を下げて肩を震わせる幼い侍女にアメリアが声をかけるより先に、オリオンが笑い飛ばした。
「ははっ、よいよい。若い内の失敗はいい経験になる。礼儀作法はこれから学んでいけばいい」
「は、はい……!」
なんでもないように言って、オリオンは再び歩き出す。
(一概には言い切れないけれど、寛大な人、なのかもしれない……)
だとするなら、絵を描いても咎められないだろうか。男爵領を出て以来、初めて目にした数々の風景を、人が生み出した建造物を、描きたくてたまらない。スケッチではなく、大きなキャンバスに筆を走らせ、彩と光を乗せたいのだ。
彼はそれを許してくれる人なのだろうか。温室らしき建物が見えてくる中、アメリアはそれを考えずにはいられなかった。
「わあっ、高い城壁ですね!」
馬車の窓から見える景色にリサがはしゃいだ声を挙げる。緊張のせいか、当初のリサは大人びて見えていた。しかし半月余りを一緒に過ごしている内に、十三歳の彼女は年相応の子供らしさを見せるようになった。
アメリアは少女を横目で見たあと、自身も窓の外に目を向ける。
城塞都市と言うだけあって、まず目に飛びこんでくるのは石造りの高い城壁だ。城壁はぐるりと町を囲んでいて、出入りできる場所は東西南北にある四か所の門だけらしい。アメリアたちは馬車が行き交う、南門からバラリオスに入ることになった。
通行証を確認する門番はエリックの知人のようだ。彼が馬から降りて帰還を伝えると、門付近の詰所からワラワラと騎士たちが出てきた。誰もかれも屈強で、その場の密度がグッと上がる。
「エリック! 戻って来たんだな!」
「ああ」
「ってことは、その馬車に乗っているのが?」
「御老公様の奥方になられるご令嬢か!」
「どんな方だ? 女傑然りとした人物か?」
チラチラと視線を向けられているのに気付いた。アメリアの脳裏に挨拶すべきだろうかという考えもよぎったが、婚姻相手と顔を合わせていない状況で、先に臣下の騎士たちに声をかけるのもおかしな話だ。とはいえ無視をするのもどうだろう。正解がわからないでいると、馬車の窓を隠すようにエリックが立ちはだかった。
「興味本位で覗き見しようとするな。こんな風に取り囲むのも無礼だぞ」
「あ……そうだ、な。すまん……」
屈強な騎士たちは馬車から少し離れて並ぶと、胸に手を当てて一斉に頭を下げた。アメリアは目を丸くする。北の地を守る高潔な騎士が、たかだか男爵家の娘に対して敬意を表すなんて、想像もしていなかった。
婚姻を結ぶ事実が周知されているとも、辺境伯家の面々や関係者にまともな対応をされるとも思っていなかった。期待していなかったのだ。
エリックが馬車の窓越しにアメリアを見る。彼が何を言いたいのか察し、アメリアは小さく頷いた。エリックが未だ頭を下げる騎士たちに声をかけると、彼らは顔を上げる。彼女は名前も知らない騎士たちに頭を下げ返した。
止まっていた馬車が動き出す。
馬車から見える城塞都市の街並みに、リサが度々、感嘆の声を漏らしていた。その傍らでアメリアは口を閉じたまま、自分の中で言いようのない感情が湧き起こるのを感じていた。これまでに抱いたことのない、不思議な感情だ。
(もやもやする……ううん、じわじわ、かしら……変な気持ちね。こんなの初めてだわ……今なら……これまでとは違う味の絵が描けるかもしれないわね)
流れていく景色をぼんやりと眺める。
北に敵を抱える辺境伯領だからか、城塞都市だからか、バラリオスには武器屋や防具屋が多いようだ。近くには酒場や食料品店、衣料品店など大衆向けの店もある。この辺りは一般市民の居住区になっているらしい。
そのまま奥――町の中心へ進んで行くと、建物や商店の様相が変わってきた。どうやらバラリオスは中心に行くほど裕福な人間が多いようで、それに合わせた高級店が建ち並んでいる。
つまり中央に住んでいるのは――
「お嬢様、お城です。お城が近付いて来ました!」
リサが声を上げた。
馬車の先に高くそびえる城が見えた。町の中でも一段高いところにあり、そこもまた、外壁ほど高くはないが城壁に囲まれている。城塞都市の中心というだけあって物々しく、頑丈そうな建物だった。
城の正門でエリックが門番に声をかける。小さな馬車が城内へ入った。玄関まで距離があるらしい。速度を落とした馬車は長いアプローチを進んで行く。興奮を緊張が凌駕してきたのかリサはすっかり黙り込んでいた。
やがて動いていた馬車が、停まった。
扉がノックされる。到着したようだ。アメリアが席を立つのと同時に、エリックが外から扉を開けた。騎士が差し出した手の平に手を重ねて、彼女はバラリオスの地を踏んだ――
(あれは……)
地面に足をつけて前を向いたアメリアは、城の玄関に立つ人物を視界に入れて、目を見開く。遠目でもわかるくらい大きな、真っ白な人がいた。服も、髪も、整えられたヒゲも、肌も、白い。
後ろでリサが馬車を降りる気配がしたが、アメリアは近付いて来る人物から目が離せない。それほどの存在感があった。
足が長いからか、歩幅が広いからか、その人はあっと言う間にアメリアの前にやって来た。老人と呼ぶにはあまりにも屈強でたくましい身体つきで、凛としている。
名乗られなくても、その人物が誰なのかわかった。
「そなたがアメリア嬢で相違ないか」
腹の底に響くような、低く渋い声だ。
「はい。ローズハート男爵が長女、アメリアにございます」
アメリアは片足を後ろに引き、ドレスの裾をつまんで首を垂れる。視界に大きな足が映った。
「ああ、そんなに畏まらなくていい。頭を上げてくれ」
そう言われて素直に身体を起こし、自分よりも頭ふたつ分は高いところにある、顔を見上げる。白と銀が混ざったような光り輝く髪、鼻の下と顎で整えられたヒゲ、北の地に住む人特有の透けるような真っ白な肌、ホワイトディアの一族のみに許された白い軍服……その巨躯と相まって、白熊を彷彿とさせた。
けれど、アメリアの頭に浮かんだ白熊は、すぐに別の動物へと姿を変えていく。白の中で深い色の、紅玉の瞳が存在感を放っていた。生気に満ち溢れて爛々と燃えている。
「雪兎……」
頭の中で愛らしい小動物が跳ね回っていた。だから、無意識の内に呟いてしまった。
「雪兎?」
微かな呟きでも相手に届いてしまったようだ。紅玉の目を丸くした彼が、首を傾げながら聞き返してくる。自分の失態に気付いたアメリアは「失礼しました」と、小声で謝罪の言葉を告げた。
「ははっ、そうか、雪兎か!」
大きな白熊は肩を揺らして豪快に笑う。機嫌を損ねたわけではないらしく、ひとまずアメリアは安堵の息を漏らした。
やがてひとしきり笑うと、大柄な彼はアメリアを見下ろしてニッと目を細めた。目尻に皺が寄る。
「初対面で雪兎だと言われたのは、生まれて初めてだ。ホワイトディア――白鹿の名前ですら似合わんと言われるのに、雪兎ときたか。我が花嫁殿の翡翠のまなこは、えらく奇特な世界を映すらしい」
「花嫁……では、やはりあなた様が……」
「ああ。私が、恥ずかしげもなく孫ほど歳の離れた令嬢に婚姻を申し込んだ好色ジジイ、オリオン=デイヴィス=ホワイトディアだ」
「………………」
アメリアは目をまたたかせた。
(好色ジジイ……)
目の前の人物からそんな感じはまったくしないが、人は見かけによらないという言葉もある。そして、英雄色を好むという言葉も、あるのだ。オリオン=デイヴィス=ホワイトディアは間違いなく英雄だ。だとすれば……。
黙りこんでしまったアメリアと、オリオンが見つめ合う。
ふたりの沈黙を破ったのは、近付いて来たひとりの使用人だった。きっちりと身なりを整えた老人だ。細身の体躯だが姿勢は真っ直ぐで足取りもしっかりしている。薄いレンズのモノクルをかけていて、真面目そうな雰囲気を醸し出していた。
「オリオン様、僭越ながら申し上げます」
「ん? なんだ、エリティカ」
オリオンはエリティカと呼んだ男のほうを見る。ただの使用人ではないのだろう。エリティカは呆れたと言わんばかりの胡乱な目を、主人へ向けていた。
「貴方様の冗談は非常に分かりにくいのです」
「何?」
「何、ではありません。お嬢様が絶句しておられます」
「それはいかんな」
オリオンがハッとした顔でアメリアへ向き直る。
「今のは冗談だ」
「冗談、ですか」
「主はお嬢様が緊張なさっているのではないかと思い、雰囲気を和ませようとなさったのです。しかしご覧の通り、その手のことに慣れていらっしゃる方ではありませんので、下手を打ってしまわれたご様子。どうぞ寛大なお心でお許しいただけますと幸いにございます」
恭しく頭を下げるエリティカと、気まずげに頬を掻くオリオンを順に見て、アメリアは「そうだったのですね」と納得した。
「お気遣いいただきありがとうございます。その……今のお言葉が冗談であるとするなら、ひとつお尋ねしたいことがあります」
「ひとつと言わず、いくらでも構わんが……尋ねたいこととは?」
「わたしを伴侶として迎えていただく理由はなんでしょう? これまで、お目にかかったことすらないと思うのですが」
「ふむ……」
オリオンは顎で整えたヒゲを撫でながら頷く。
「もっともな疑問だ。今まで答えがわからぬまま、さぞかしやきもきしていたことだろう。その問いに答える前に場所を変えても良いだろうか?」
「あ、はい、もちろんです」
「エリティカ、温室の支度は?」
「万事整っております」
「さすがだな。我が執事は仕事が早い」
「恐れ入ります」
北の英雄は太い首を動かして満足そうに首肯すると、アメリアのほうへ手の平を差し出してきた。硬そうな、大きな手だ。自分のものとはまったく違う。長年、領地を守る為に武器を取り、最前線で戦ってきた戦士の手だった。
何故かその手が尊いもののように思えて、ほんの少し、アメリアは手を重ねるのを躊躇った。それでもそっと手を伸ばして、重ねる。かさついた皮膚の感触。指先に温かさを感じてようやく、彼女は自分の手が普段よりも冷たくなっていることに気付いた。
(寒さのせい、じゃないわ。わたし、緊張していたのね)
アメリアはオリオンにエスコートされながら、温室へ案内してもらう。足の長さが違うのに、早足になることも、遅れることもない。無理をしないように歩幅を合わせてくれていた。
温室は城内の中庭を通った先にあり、辿りつくまでに何人もの使用人や騎士とすれ違った。首を垂れる者たちに、オリオンは時折足を止めては、アメリアを我が花嫁殿だと紹介する。紹介された使用人たちは祝福の言葉を口にした。
アメリアの疑問がますます膨らんでいく。
オリオン=ホワイトディアとは祖父と孫ほど歳が離れている。その上、本来であれば顔を見ることすら叶わないような、先代とはいえ、偉大な北の王だ。男爵家の小娘でしかない自分を丁寧に扱ってくれることに、混乱せずにいられない。
(どういうことなのかしら……? 婚姻後わたしを捨て置くのなら、顔を見せて回らないほうがいいと思うのだけれど……)
後ろでは、バラリオスの城の巨大さにリサが感嘆の声を上げっぱなしだった。その度にエリックがあれはなんだ、これはなんだと短く説明をし、気心の知れた様子がうかがえる。
「旅路で打ち解け合ったらしいな」
オリオンがチラリと後ろに視線を向けた。
「リサたちのことですか?」
「ああ。まるで兄妹のようだ」
「ハルド卿には大変お世話になりました。旅に不慣れなわたしたちを気遣ってくださって、おかげでなんの不便もなく辿りつくことが叶いました」
「そうか。それは良かった。真面目と言えば聞こえはいいが、堅物な男だ。うら若き令嬢に粗相をしなかったと知れば、エリティカも安堵することだろう」
「先ほどの、執事の?」
「ああ。エリックはエリティカの末の息子だ。確か五番目か、六番目か……どっちだったかのう?」
隣を歩くオリオンが後ろをついて来る青年騎士に問いかける。エリックは「七番目です」と答えた。
「おそらく四番目の兄ミリスを飛ばされているのかと。あの人は自分の顔にもっとも似合う装いだと公言し、常日頃ドレス姿で過ごしていますので」
「男性がドレスを!?」
思わず声を上げてしまったのだろう。リサは口を挟んだ失態に気付き、慌てて「失礼しました!」と謝罪する。頭を下げて肩を震わせる幼い侍女にアメリアが声をかけるより先に、オリオンが笑い飛ばした。
「ははっ、よいよい。若い内の失敗はいい経験になる。礼儀作法はこれから学んでいけばいい」
「は、はい……!」
なんでもないように言って、オリオンは再び歩き出す。
(一概には言い切れないけれど、寛大な人、なのかもしれない……)
だとするなら、絵を描いても咎められないだろうか。男爵領を出て以来、初めて目にした数々の風景を、人が生み出した建造物を、描きたくてたまらない。スケッチではなく、大きなキャンバスに筆を走らせ、彩と光を乗せたいのだ。
彼はそれを許してくれる人なのだろうか。温室らしき建物が見えてくる中、アメリアはそれを考えずにはいられなかった。
応援ありがとうございます!
2
お気に入りに追加
3,700
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる