あなたにおすすめの小説

王家も我が家を馬鹿にしてますわよね
章槻雅希
ファンタジー
よくある婚約者が護衛対象の王女を優先して婚約破棄になるパターンのお話。あの手の話を読んで、『なんで王家は王女の醜聞になりかねない噂を放置してるんだろう』『てか、これ、王家が婚約者の家蔑ろにしてるよね?』と思った結果できた話。ひそかなサブタイは『うちも王家を馬鹿にしてますけど』かもしれません。
『小説家になろう』『アルファポリス』(敬称略)に重複投稿、自サイトにも掲載しています。

【完】あの、……どなたでしょうか?
桐生桜月姫
恋愛
「キャサリン・ルーラー
爵位を傘に取る卑しい女め、今この時を以て貴様との婚約を破棄する。」
見た目だけは、麗しの王太子殿下から出た言葉に、婚約破棄を突きつけられた美しい女性は………
「あの、……どなたのことでしょうか?」
まさかの意味不明発言!!
今ここに幕開ける、波瀾万丈の間違い婚約破棄ラブコメ!!
結末やいかに!!
*******************
執筆終了済みです。

私と子供より、夫は幼馴染とその子供のほうが大切でした。
小野 まい
恋愛
結婚記念日のディナーに夫のオスカーは現れない。
「マリアが熱を出したらしい」
駆けつけた先で、オスカーがマリアと息子カイルと楽しげに食事をする姿を妻のエリザが目撃する。
「また裏切られた……」
いつも幼馴染を優先するオスカーに、エリザの不満は限界に達していた。
「あなたは家族よりも幼馴染のほうが大事なのね」
離婚する気持ちが固まっていく。

断腸の思いで王家に差し出した孫娘が婚約破棄されて帰ってきた
兎屋亀吉
恋愛
ある日王家主催のパーティに行くといって出かけた孫娘のエリカが泣きながら帰ってきた。買ったばかりのドレスは真っ赤なワインで汚され、左頬は腫れていた。話を聞くと王子に婚約を破棄され、取り巻きたちに酷いことをされたという。許せん。戦じゃ。この命燃え尽きようとも、必ずや王家を滅ぼしてみせようぞ。

お前は家から追放する?構いませんが、この家の全権力を持っているのは私ですよ?
水垣するめ
恋愛
「アリス、お前をこのアトキンソン伯爵家から追放する」
「はぁ?」
静かな食堂の間。
主人公アリス・アトキンソンの父アランはアリスに向かって突然追放すると告げた。
同じく席に座っている母や兄、そして妹も父に同意したように頷いている。
いきなり食堂に集められたかと思えば、思いも寄らない追放宣言にアリスは戸惑いよりも心底呆れた。
「はぁ、何を言っているんですか、この領地を経営しているのは私ですよ?」
「ああ、その経営も最近軌道に乗ってきたのでな、お前はもう用済みになったから追放する」
父のあまりに無茶苦茶な言い分にアリスは辟易する。
「いいでしょう。そんなに出ていって欲しいなら出ていってあげます」
アリスは家から一度出る決心をする。
それを聞いて両親や兄弟は大喜びした。
アリスはそれを哀れみの目で見ながら家を出る。
彼らがこれから地獄を見ることを知っていたからだ。
「大方、私が今まで稼いだお金や開発した資源を全て自分のものにしたかったんでしょうね。……でもそんなことがまかり通るわけないじゃないですか」
アリスはため息をつく。
「──だって、この家の全権力を持っているのは私なのに」
後悔したところでもう遅い。
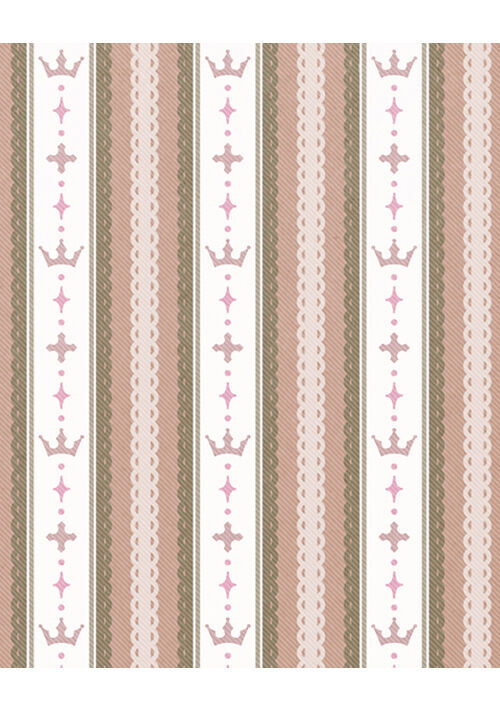
【完結】「神様、辞めました〜竜神の愛し子に冤罪を着せ投獄するような人間なんてもう知らない」
まほりろ
恋愛
王太子アビー・シュトースと聖女カーラ・ノルデン公爵令嬢の結婚式当日。二人が教会での誓いの儀式を終え、教会の扉を開け外に一歩踏み出したとき、国中の壁や窓に不吉な文字が浮かび上がった。
【本日付けで神を辞めることにした】
フラワーシャワーを巻き王太子と王太子妃の結婚を祝おうとしていた参列者は、突然現れた文字に驚きを隠せず固まっている。
国境に壁を築きモンスターの侵入を防ぎ、結界を張り国内にいるモンスターは弱体化させ、雨を降らせ大地を潤し、土地を豊かにし豊作をもたらし、人間の体を強化し、生活が便利になるように魔法の力を授けた、竜神ウィルペアトが消えた。
人々は三カ月前に冤罪を着せ、|罵詈雑言《ばりぞうごん》を浴びせ、石を投げつけ投獄した少女が、本物の【竜の愛し子】だと分かり|戦慄《せんりつ》した。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」
アルファポリスに先行投稿しています。
表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
2021/12/13、HOTランキング3位、12/14総合ランキング4位、恋愛3位に入りました! ありがとうございます!

【完結】離縁ですか…では、私が出掛けている間に出ていって下さいね♪
山葵
恋愛
突然、カイルから離縁して欲しいと言われ、戸惑いながらも理由を聞いた。
「俺は真実の愛に目覚めたのだ。マリアこそ俺の運命の相手!」
そうですか…。
私は離婚届にサインをする。
私は、直ぐに役所に届ける様に使用人に渡した。
使用人が出掛けるのを確認してから
「私とアスベスが旅行に行っている間に荷物を纏めて出ていって下さいね♪」

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました
ましゅぺちーの
恋愛
侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。
ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。
王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。
そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。
「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。





















