10 / 60
第10話
しおりを挟む
第10話
「……はい」
これからのこと──谷崎課長の言葉にビクッと体が強張る。
一体、何だろう。
離婚? いや、違う。そうだとしたら、私がここで生活する必要はない。だったら、何だ?
口調は穏やかだけど、それとなく避けていた現実からもう逃げられないんだぞと言われているようで落ち着かない。
この人は何を言い出すのだろう? と身構えながら続きを待つ。
「来週から仕事に復帰してみないか」
「は?」
予想外の言葉に間抜けな声が出る。
だって、おかしいでしよ。記憶喪失だっていう人間に仕事復帰って。随分とぶっ飛んだ思考をお持ちのようだ。
「仕事復帰って……今の私にはハードル高いですよ」
「いや、三年前つまり今の君と、現在の君がやっている仕事は殆ど同じだ。部署だって同じ。確かに多少の変更はあるだろう。だが、君なら問題なく対応できるはずだ」
「だからって……」
そう、私はまだMS精工に在籍している。
谷崎課長の部署に異動してから、一年後に契約社員になった。その後、結婚が決まりすぱっと会社を辞めるつもりだったけど、元の部署である技術営業支援課の業務量が増えたことや、育休明けの姫島さんのサポート等で、異動することになったらしい。
「続けようが辞めようが君の自由だけど、どっちにしろ手続きは必要だ。それに、一日中ここにいてもストレスが溜まるだけだと思うけど?」
うっ……確かに。一日中ここにいても気が滅入るだけな気がする。だからって、仕事復帰と言われても……。頭の中でイメージしてみる。イメージしてみよう。これってゲームで言うなら──
「武器や防具を剥がされた挙句、魔法も封じられた状態で戦うってこと!?」
口にしたつもりはなかった。
が、私の子供じみた喩えは声となり向かいに座っている人の耳にしっかりと届いてしまったらしい。
谷崎課長は思いっきり笑っている。
何がそんなに面白いんだ? そっちからしてみれば、バカみたいだろうけど、こっちは真剣に悩んでいるというのに。そう言えば、打ち合わせの時も跡がついた私の顔を見て噴き出したんだよね、この人。笑い上戸なのか? とりあえず、谷崎課長が落ち着くのを待とう。
「ごめん……ゲームに喩えて考えるところが、つぐみらしくて。だけど、魔法は封じられていないと思うよ。武器や防具はわからないけど、使えるアイテムはたくさんあるんじゃないか?」
「使えるアイテム?」
「チェンジの時もバッチリ引継書類を作っていたし、俺の部署にきた時も時間があればマニュアルを作っていたよ。本人曰く、覚えるには一番早いからって。忘れっぽいからって業務日誌らしきモノも書いていたし」
確かに……言われてみると、そんなものを作っていた気がする。私にとってあの職場は公認会計士になる為の通過点だった。元々、辞めることを前提にしてたし、引継ぎしやすいようにしていたのかも。
「でも、職場にとって迷惑じゃないですか? 記憶喪失の人間がいるって」
記憶喪失の人間を受け入れるって自分で言うのもなんだけど、面倒な気がする。それを尋ねると、谷崎課長はニヤリと笑って言った。
「そう思う人間もいるだろうな。でも、そういうヤツらを黙らせるのも面白いと思うけど。できないって言うんなら無理に復帰しろとは言わないけど」
「谷崎課長……」
ずるい。
そう言われると負けるもんかって挑みたくなるじゃない。淡々とした口調なのに、この人は私の負けず嫌いな性格を刺激してくる。私が単純なだけ? でも、この人って私が思う以上に頭が切れる厄介なタイプの人なのかもしれない。
「それと一緒に暮らす上で言っておきたいんだが……」
「何でしょう?」
「ここでは谷崎課長って呼び方は辞めてくれ」
「でも……」
「君の中で俺が新しい上司だという認識なのはわかる。だが、もう君は俺の直属の部下ではない。君は俺の妻で、俺は君の夫。君がどう思おうとそれは変えようのない事実だ。俺は君のことを今更、柏原さんなんて呼ぶ気はないから」
痛いところを突かれた。
私がこの人のことを谷崎課長と呼んでいたのは、それしか呼びようがなかったからだ。でも、そうすることでこの人やこの人と夫婦だという事実から距離を置こうとしていたのもある。そんな考えを見透かされた気がする。確かに谷崎課長の言っていることは正論かもしれない。けど、どう呼べと? いきなり名前で呼べとかはキツイ。
「では、どのようにお呼びすればいいんでしょうか?」
「そうだな……谷崎さんかな。今はそれでいい」
よかった。今はと言うのが気にかかるけど、とりあえず名前呼びは避けられた。でも、私はこの人のことをどう呼んでいたんだろう。あなた? 圭くん? ダーリン? うわっ……どれにしても鳥肌ものだ。
「わかりました。あの……ちなみに私は谷崎さんのことをどう呼んでいたんでしょう?」
「圭さんと呼んでいてくれていたよ。呼び捨てでいいっていったけど、年上の人間にそれはできないと堅く断られた」
ほっとした。そこだけはグッジョブ私。
「あとは家事だな」
「……」
家事。
一番自信がないところだ。実家に居候していた時に南ちゃんの手伝いはしたけど、「つぐみって仕事や試験勉強には几帳面なくせに、生活は大雑把なのよね」と南ちゃんと呆れられたし……。
「三年間の記憶がないってことは、家事とかさっぱりだよな?」
はい、さっぱりです。試験勉強にかまけて思いっきり手を抜いてました。結婚して十ヶ月みたいだけど、私はどうしていたんだろう。さっぱりだよなって言うぐらいだから、さっぱりな私を当然この人は知っているんだろうな。そう思うと本当にやりきれない。
「はい、というか私の家事ってどうだったんでしょう?」
「うん……頑張っていたよ」
変な間の後、谷崎さんは答えた。きっと色々やらかしたんだろう。基本的にアイロンとか大嫌いだし、料理なんてインスタント食品ですら美味しくなく作る才能がある。多分、この点に関しては迷惑を掛けたに違いない。
「すみませんでした」
自分がやらかしたであろう失敗を想像するだけで、恐ろしい。
「まあ、面白かったしいいよ。俺は一人暮らしが長かったから大抵のことはできる。平日は帰りが遅くなるから飯を作るのは無理だけど、スーパーも近くにあるし、商店街にも総菜屋があるからしばらくはそれで何とかしよう」
「……助かります」
面白い? なんか引っかかるけど、それをとやかく言う資格は私にはない。それに谷崎さんの申し出は今の私にはありがたい。
「それと洗濯だけど」
バカにしてるのか? 洗濯くらいは普通にできる。
「いくらなんでも、洗濯機ぐらいはきちんと扱えますけど。それとも私はここで何かやらかしちゃったんですか?」
憤慨している私の表情に谷崎さんは落ち着けとでも言うように、咳払いをした。
「いや、洗濯物とか一緒に洗ったりするの嫌かと思って」
「え?」
「今のつぐみにとって、俺は会社の上司という存在だから微妙じゃないか?」
不思議なことを言う。さっきはあれほど夫婦だって私に言ってたくせに、こういうところは気にしてくれてるんだ。そのアンバランスさに笑ってしまう。
正直、谷崎さんは好みのタイプではない。どうして彼を選んだのかもさっぱりわからない。じゃあ、生理的に受け付けないのかと聞かれるとそれも違う。だから、色々微妙なのだ。
「その辺は心配ご無用です。父や兄と一緒に住んでいたので、洗濯するのも干すのも抵抗ないです。ただ、私の下着とかは……微妙なので洗濯は私に一任してくださると嬉しいです」
「了解」
そんな感じでこれからの生活について一つ一つ確認していった。それは仕事の確認をする上司と部下みたいな会話だった。
最後に寝る部屋についての確認になった。谷崎さんは自分が別の部屋で寝ると言ってくれた。でも、私はそれを丁重に断った。
「寝室はお互いの着替えのある場所ですし、谷崎さんに気を使わせてしまうことが多いかと……。なので、私が客間で寝る方がいいと思います。洋服とかは谷崎さんのいない間に用意しますし。それに一度、布団で眠ってみたかったんです」
精一杯の建前だ。
本当はあのベッドで眠りたくないだけだ。恐らく、いや当たり前だけど夫婦の行為があのベッドで行われているはずだ。
そのベットで眠るのは今の私にはできない。意識しすぎだろって思うけど、気になるものは気になる。
でも、これを谷崎さんに悟られてはいけない。何度も悲しい顔にさせたくない。
谷崎さんは「気にしなくていいのに」と言いつつ、その我儘を聞いてくれた。
「ふぅー。やっと一日が終わる」
客間に引いた布団の上に寝転がり、大きく伸びをする。
今日は長い一日だった。
これからの生活の打ち合わせらしきものをした後、夕食を食べに行った。谷崎さんが連れて行ってくれたお店は、商店街から少し離れたところにある洋食屋さんだった。
谷崎さんのお勧めだというハンバーグステーキは、ボリュームがあってジューシでとてもおいしかった。
意外なことに、食が細そうな谷崎さんも同じメニューだった。私と同様にあっさりと平らげていたのにはビックリした。
何だか心配になって大丈夫ですか? と聞いたら、「大丈夫だよ」という返事と一緒に、「初めて食事に行った時にも同じこと聞かれたよ」と谷崎さんが目を細めて言った。何だかいたたまれない気持ちになったけど、食の好みが似ていることがわかったのはちょっとした収穫だった。
夕食から戻って来てからは、明日の洋服の準備をした。クローゼットの中身はダブルベッドと同じくらい衝撃的だった。
私の好みはモノトーン系でシンプルなデザインの洋服。それなのに、クローゼットの中にはパープルやグリーン等の、私が絶対に選ばなかった色のアウターがあったり、アシンメトリーのスカートがあったり……。とても同じ人間が選んだとは思えないものばかりだった。
本当に三年間の間に何があったの? 自分に問いかけたけど、答えは返って来なかった。
その後、谷崎さんからマンションの設備の説明を聞きお風呂に入って、歯を磨いて今、こうして寝る体制に入っている。
何か思い出すかと思ったけど、私の頭に浮かんだのは、最近のマンションは便利ですねってことぐらいだった。
キッチンに備え付けられている食洗機にディスポーザー、浴室には曇り止め加工済みの鏡に、雨が降っても安心な浴室乾燥機。……これって単なるお宅訪問のノリだ。
自分が生活している場所だというのに、マンガを始めとする私の私物がたくさんあるのに、他人の家のように見ている私。
このままじゃいけないってわかっている。でも、やっぱりここは自分の家という気がしなくて落ち着かない。いや、住めば都って言うから、慣れの問題かも。
色々な不安はあるけど、そこばかり気にしてもつまらない。楽しいこと……そうだ、マンガだ。今日は時間がなかったけど、明日は読みまくってやろう。封印する理由はもうないんだから。
そんなささやかな野望を抱きながら、私は眠りについた。
「……はい」
これからのこと──谷崎課長の言葉にビクッと体が強張る。
一体、何だろう。
離婚? いや、違う。そうだとしたら、私がここで生活する必要はない。だったら、何だ?
口調は穏やかだけど、それとなく避けていた現実からもう逃げられないんだぞと言われているようで落ち着かない。
この人は何を言い出すのだろう? と身構えながら続きを待つ。
「来週から仕事に復帰してみないか」
「は?」
予想外の言葉に間抜けな声が出る。
だって、おかしいでしよ。記憶喪失だっていう人間に仕事復帰って。随分とぶっ飛んだ思考をお持ちのようだ。
「仕事復帰って……今の私にはハードル高いですよ」
「いや、三年前つまり今の君と、現在の君がやっている仕事は殆ど同じだ。部署だって同じ。確かに多少の変更はあるだろう。だが、君なら問題なく対応できるはずだ」
「だからって……」
そう、私はまだMS精工に在籍している。
谷崎課長の部署に異動してから、一年後に契約社員になった。その後、結婚が決まりすぱっと会社を辞めるつもりだったけど、元の部署である技術営業支援課の業務量が増えたことや、育休明けの姫島さんのサポート等で、異動することになったらしい。
「続けようが辞めようが君の自由だけど、どっちにしろ手続きは必要だ。それに、一日中ここにいてもストレスが溜まるだけだと思うけど?」
うっ……確かに。一日中ここにいても気が滅入るだけな気がする。だからって、仕事復帰と言われても……。頭の中でイメージしてみる。イメージしてみよう。これってゲームで言うなら──
「武器や防具を剥がされた挙句、魔法も封じられた状態で戦うってこと!?」
口にしたつもりはなかった。
が、私の子供じみた喩えは声となり向かいに座っている人の耳にしっかりと届いてしまったらしい。
谷崎課長は思いっきり笑っている。
何がそんなに面白いんだ? そっちからしてみれば、バカみたいだろうけど、こっちは真剣に悩んでいるというのに。そう言えば、打ち合わせの時も跡がついた私の顔を見て噴き出したんだよね、この人。笑い上戸なのか? とりあえず、谷崎課長が落ち着くのを待とう。
「ごめん……ゲームに喩えて考えるところが、つぐみらしくて。だけど、魔法は封じられていないと思うよ。武器や防具はわからないけど、使えるアイテムはたくさんあるんじゃないか?」
「使えるアイテム?」
「チェンジの時もバッチリ引継書類を作っていたし、俺の部署にきた時も時間があればマニュアルを作っていたよ。本人曰く、覚えるには一番早いからって。忘れっぽいからって業務日誌らしきモノも書いていたし」
確かに……言われてみると、そんなものを作っていた気がする。私にとってあの職場は公認会計士になる為の通過点だった。元々、辞めることを前提にしてたし、引継ぎしやすいようにしていたのかも。
「でも、職場にとって迷惑じゃないですか? 記憶喪失の人間がいるって」
記憶喪失の人間を受け入れるって自分で言うのもなんだけど、面倒な気がする。それを尋ねると、谷崎課長はニヤリと笑って言った。
「そう思う人間もいるだろうな。でも、そういうヤツらを黙らせるのも面白いと思うけど。できないって言うんなら無理に復帰しろとは言わないけど」
「谷崎課長……」
ずるい。
そう言われると負けるもんかって挑みたくなるじゃない。淡々とした口調なのに、この人は私の負けず嫌いな性格を刺激してくる。私が単純なだけ? でも、この人って私が思う以上に頭が切れる厄介なタイプの人なのかもしれない。
「それと一緒に暮らす上で言っておきたいんだが……」
「何でしょう?」
「ここでは谷崎課長って呼び方は辞めてくれ」
「でも……」
「君の中で俺が新しい上司だという認識なのはわかる。だが、もう君は俺の直属の部下ではない。君は俺の妻で、俺は君の夫。君がどう思おうとそれは変えようのない事実だ。俺は君のことを今更、柏原さんなんて呼ぶ気はないから」
痛いところを突かれた。
私がこの人のことを谷崎課長と呼んでいたのは、それしか呼びようがなかったからだ。でも、そうすることでこの人やこの人と夫婦だという事実から距離を置こうとしていたのもある。そんな考えを見透かされた気がする。確かに谷崎課長の言っていることは正論かもしれない。けど、どう呼べと? いきなり名前で呼べとかはキツイ。
「では、どのようにお呼びすればいいんでしょうか?」
「そうだな……谷崎さんかな。今はそれでいい」
よかった。今はと言うのが気にかかるけど、とりあえず名前呼びは避けられた。でも、私はこの人のことをどう呼んでいたんだろう。あなた? 圭くん? ダーリン? うわっ……どれにしても鳥肌ものだ。
「わかりました。あの……ちなみに私は谷崎さんのことをどう呼んでいたんでしょう?」
「圭さんと呼んでいてくれていたよ。呼び捨てでいいっていったけど、年上の人間にそれはできないと堅く断られた」
ほっとした。そこだけはグッジョブ私。
「あとは家事だな」
「……」
家事。
一番自信がないところだ。実家に居候していた時に南ちゃんの手伝いはしたけど、「つぐみって仕事や試験勉強には几帳面なくせに、生活は大雑把なのよね」と南ちゃんと呆れられたし……。
「三年間の記憶がないってことは、家事とかさっぱりだよな?」
はい、さっぱりです。試験勉強にかまけて思いっきり手を抜いてました。結婚して十ヶ月みたいだけど、私はどうしていたんだろう。さっぱりだよなって言うぐらいだから、さっぱりな私を当然この人は知っているんだろうな。そう思うと本当にやりきれない。
「はい、というか私の家事ってどうだったんでしょう?」
「うん……頑張っていたよ」
変な間の後、谷崎さんは答えた。きっと色々やらかしたんだろう。基本的にアイロンとか大嫌いだし、料理なんてインスタント食品ですら美味しくなく作る才能がある。多分、この点に関しては迷惑を掛けたに違いない。
「すみませんでした」
自分がやらかしたであろう失敗を想像するだけで、恐ろしい。
「まあ、面白かったしいいよ。俺は一人暮らしが長かったから大抵のことはできる。平日は帰りが遅くなるから飯を作るのは無理だけど、スーパーも近くにあるし、商店街にも総菜屋があるからしばらくはそれで何とかしよう」
「……助かります」
面白い? なんか引っかかるけど、それをとやかく言う資格は私にはない。それに谷崎さんの申し出は今の私にはありがたい。
「それと洗濯だけど」
バカにしてるのか? 洗濯くらいは普通にできる。
「いくらなんでも、洗濯機ぐらいはきちんと扱えますけど。それとも私はここで何かやらかしちゃったんですか?」
憤慨している私の表情に谷崎さんは落ち着けとでも言うように、咳払いをした。
「いや、洗濯物とか一緒に洗ったりするの嫌かと思って」
「え?」
「今のつぐみにとって、俺は会社の上司という存在だから微妙じゃないか?」
不思議なことを言う。さっきはあれほど夫婦だって私に言ってたくせに、こういうところは気にしてくれてるんだ。そのアンバランスさに笑ってしまう。
正直、谷崎さんは好みのタイプではない。どうして彼を選んだのかもさっぱりわからない。じゃあ、生理的に受け付けないのかと聞かれるとそれも違う。だから、色々微妙なのだ。
「その辺は心配ご無用です。父や兄と一緒に住んでいたので、洗濯するのも干すのも抵抗ないです。ただ、私の下着とかは……微妙なので洗濯は私に一任してくださると嬉しいです」
「了解」
そんな感じでこれからの生活について一つ一つ確認していった。それは仕事の確認をする上司と部下みたいな会話だった。
最後に寝る部屋についての確認になった。谷崎さんは自分が別の部屋で寝ると言ってくれた。でも、私はそれを丁重に断った。
「寝室はお互いの着替えのある場所ですし、谷崎さんに気を使わせてしまうことが多いかと……。なので、私が客間で寝る方がいいと思います。洋服とかは谷崎さんのいない間に用意しますし。それに一度、布団で眠ってみたかったんです」
精一杯の建前だ。
本当はあのベッドで眠りたくないだけだ。恐らく、いや当たり前だけど夫婦の行為があのベッドで行われているはずだ。
そのベットで眠るのは今の私にはできない。意識しすぎだろって思うけど、気になるものは気になる。
でも、これを谷崎さんに悟られてはいけない。何度も悲しい顔にさせたくない。
谷崎さんは「気にしなくていいのに」と言いつつ、その我儘を聞いてくれた。
「ふぅー。やっと一日が終わる」
客間に引いた布団の上に寝転がり、大きく伸びをする。
今日は長い一日だった。
これからの生活の打ち合わせらしきものをした後、夕食を食べに行った。谷崎さんが連れて行ってくれたお店は、商店街から少し離れたところにある洋食屋さんだった。
谷崎さんのお勧めだというハンバーグステーキは、ボリュームがあってジューシでとてもおいしかった。
意外なことに、食が細そうな谷崎さんも同じメニューだった。私と同様にあっさりと平らげていたのにはビックリした。
何だか心配になって大丈夫ですか? と聞いたら、「大丈夫だよ」という返事と一緒に、「初めて食事に行った時にも同じこと聞かれたよ」と谷崎さんが目を細めて言った。何だかいたたまれない気持ちになったけど、食の好みが似ていることがわかったのはちょっとした収穫だった。
夕食から戻って来てからは、明日の洋服の準備をした。クローゼットの中身はダブルベッドと同じくらい衝撃的だった。
私の好みはモノトーン系でシンプルなデザインの洋服。それなのに、クローゼットの中にはパープルやグリーン等の、私が絶対に選ばなかった色のアウターがあったり、アシンメトリーのスカートがあったり……。とても同じ人間が選んだとは思えないものばかりだった。
本当に三年間の間に何があったの? 自分に問いかけたけど、答えは返って来なかった。
その後、谷崎さんからマンションの設備の説明を聞きお風呂に入って、歯を磨いて今、こうして寝る体制に入っている。
何か思い出すかと思ったけど、私の頭に浮かんだのは、最近のマンションは便利ですねってことぐらいだった。
キッチンに備え付けられている食洗機にディスポーザー、浴室には曇り止め加工済みの鏡に、雨が降っても安心な浴室乾燥機。……これって単なるお宅訪問のノリだ。
自分が生活している場所だというのに、マンガを始めとする私の私物がたくさんあるのに、他人の家のように見ている私。
このままじゃいけないってわかっている。でも、やっぱりここは自分の家という気がしなくて落ち着かない。いや、住めば都って言うから、慣れの問題かも。
色々な不安はあるけど、そこばかり気にしてもつまらない。楽しいこと……そうだ、マンガだ。今日は時間がなかったけど、明日は読みまくってやろう。封印する理由はもうないんだから。
そんなささやかな野望を抱きながら、私は眠りについた。
0
あなたにおすすめの小説

皇帝は虐げられた身代わり妃の瞳に溺れる
えくれあ
恋愛
丞相の娘として生まれながら、蔡 重華は生まれ持った髪の色によりそれを認められず使用人のような扱いを受けて育った。
一方、母違いの妹である蔡 鈴麗は父親の愛情を一身に受け、何不自由なく育った。そんな鈴麗は、破格の待遇での皇帝への輿入れが決まる。
しかし、わがまま放題で育った鈴麗は輿入れ当日、後先を考えることなく逃げ出してしまった。困った父は、こんな時だけ重華を娘扱いし、鈴麗が見つかるまで身代わりを務めるように命じる。
皇帝である李 晧月は、後宮の妃嬪たちに全く興味を示さないことで有名だ。きっと重華にも興味は示さず、身代わりだと気づかれることなくやり過ごせると思っていたのだが……

フローライト
藤谷 郁
恋愛
彩子(さいこ)は恋愛経験のない24歳。
ある日、友人の婚約話をきっかけに自分の未来を考えるようになる。
結婚するのか、それとも独身で過ごすのか?
「……そもそも私に、恋愛なんてできるのかな」
そんな時、伯母が見合い話を持ってきた。
写真を見れば、スーツを着た青年が、穏やかに微笑んでいる。
「趣味はこうぶつ?」
釣書を見ながら迷う彩子だが、不思議と、その青年には会いたいと思うのだった…
※他サイトにも掲載

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


王宮に薬を届けに行ったなら
佐倉ミズキ
恋愛
王宮で薬師をしているラナは、上司の言いつけに従い王子殿下のカザヤに薬を届けに行った。
カザヤは生まれつき体が弱く、臥せっていることが多い。
この日もいつも通り、カザヤに薬を届けに行ったラナだが仕事終わりに届け忘れがあったことに気が付いた。
慌ててカザヤの部屋へ行くと、そこで目にしたものは……。
弱々しく臥せっているカザヤがベッドから起き上がり、元気に動き回っていたのだ。
「俺の秘密を知ったのだから部屋から出すわけにはいかない」
驚くラナに、カザヤは不敵な笑みを浮かべた。
「今日、国王が崩御する。だからお前を部屋から出すわけにはいかない」
※ベリーズカフェにも掲載中です。そちらではラナの設定が変わっています。内容も少し変更しておりますので、あわせてお楽しみください。

27歳女子が婚活してみたけど何か質問ある?
藍沢咲良
恋愛
一色唯(Ishiki Yui )、最近ちょっと苛々しがちの27歳。
結婚適齢期だなんて言葉、誰が作った?彼氏がいなきゃ寂しい女確定なの?
もう、みんな、うるさい!
私は私。好きに生きさせてよね。
この世のしがらみというものは、20代後半女子であっても放っておいてはくれないものだ。
彼氏なんていなくても。結婚なんてしてなくても。楽しければいいじゃない。仕事が楽しくて趣味も充実してればそれで私の人生は満足だった。
私の人生に彩りをくれる、その人。
その人に、私はどうやら巡り合わないといけないらしい。
⭐︎素敵な表紙は仲良しの漫画家さんに描いて頂きました。著作権保護の為、無断転載はご遠慮ください。
⭐︎この作品はエブリスタでも投稿しています。

皇后陛下の御心のままに
アマイ
恋愛
皇后の侍女を勤める貧乏公爵令嬢のエレインは、ある日皇后より密命を受けた。
アルセン・アンドレ公爵を籠絡せよ――と。
幼い頃アルセンの心無い言葉で傷つけられたエレインは、この機会に過去の溜飲を下げられるのではと奮起し彼に近づいたのだが――
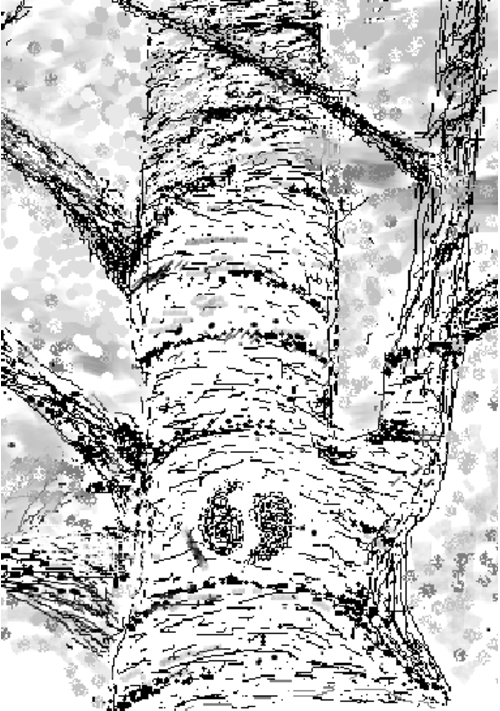
Pomegranate I
Uta Katagi
恋愛
婚約者の彼が突然この世を去った。絶望のどん底にいた詩に届いた彼からの謎のメッセージ。クラウド上に残されたファイルのパスワードと貸金庫の暗証番号のミステリーを解いた後に、詩が手に入れたものは?世代を超えて永遠の愛を誓った彼が遺したこの世界の驚愕の真理とは?詩は本当に彼と再会できるのか?
古代から伝承されたこの世界の秘密が遂に解き明かされる。最新の量子力学という現代科学の視点で古代ミステリーを暴いた長編ラブロマンス。これはもはや、ファンタジーの域を越えた究極の愛の物語。恋愛に憧れ愛の本質に悩み戸惑う人々に真実の愛とは何かを伝える作者渾身の超大作。
*本作品は「小説家になろう」にも掲載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















