10 / 33
第1章
仕方ない、ひと…
しおりを挟む
「侍女殿は、宰相閣下の縁の方なのか」
問いかける声に、ルナはお茶を淹れる手元から目を離さずに短く、いいえ、と応じた。
最初、名を尋ねた割に、シルヴィはルナの名を呼ばない。まあ、この離宮に侍女がルナ一人しかいない時点で、確かに名は必要ないだろう。
それに。
この人にとっては、呼びたくもない名だろう。
「お聞き及びかと思いますが、わたしは爵位のある家の縁の者ではありません。こういった場での作法も知りませんので、宰相閣下にはなにかとご指導いただいております」
シルヴィの前にカップを置き、下がって頭を下げながら、部屋を辞そうとする。レオボルトにシルヴィからの面会の希望を伝えに行かなければいけない。
「噂…か」
シルヴィの呟きに、そういえば、下世話なものの方が多かったな、と思いながらルナは表情には出さず、部屋を出た。
その下世話なものを肯定するような言い回しに聞こえてしまったかとも思ったが、正直、どうでもよかった。身分ある人たちには障りがあるだろうが、それを言っても無視しているのはあの人たちだ。
「お前…」
適当にレオボルトを探し歩き、鍛錬場でその姿を見つけて歩み寄ったルナに、レオボルトは思い切り顔を顰めて見せた。
「やっと顔を見せたな」
「は?」
きょとんと首をかしげ、ルナは気にしないことにして用件を伝える。
「辺境伯閣下が陛下にお会いしたいそうです。執務室でよろしいですか?」
「会うかどうかを、聞け。まずは」
「だって、暇ですよね?ここにいるんですから」
「……」
眉間のシワがさらに深くなり、レオボルトは舌打ちをしてその長い腕をルナに伸ばした。
「うわぁっ!?」
バランスを崩し、うっすらと汗をかいたレオボルトの胸元によろける。固く厚い胸板に額を当てる形で頭を抑えられ、そのままぐしゃぐしゃと掻き回された。
「なっ…なっ」
言葉にならないルナを見下ろして、レオボルトは苦虫を噛み潰したような顔だったものに笑みを浮かべた。
「全然俺のところに顔を見せないのはどういう了見だ」
「あなたが客人の世話をしろと命じたんでしょう!」
「あいつがいない時に様子を見るくらいの気遣いを見せろ。そもそもは俺の護衛だろうが。気にならんのか」
「何かあれば、すぐにわかります!シロがいるんだから。他にも騎士の方々もいるんです。わたしのようなおまけにそんなことは誰も期待していません」
「俺がしている」
さらっと言われた言葉に、ルナは開いた口が塞がらない思いだが、顔を胸板に押し付けられていてレオボルトの顔を見上げることもできない。後頭部に当てられた手はずっとぐしゃぐしゃと髪を撫で続けている。
(この人、ペットか何かだと思ってる…。絶対)
「わたしより毛並みのいいのが近くに今はいるじゃないですか」
「あれがお前以外に触らせるわけがなかろう」
呆れたように言い返されれば、それには頷くしかない。が、この状況は納得がいかない。
「とにかく、辺境伯様がお待ちですから。移動してください。辺境伯様をそちらに案内しますから」
「呼び方が安定しないな。昔のように呼べばいいだろう」
「…陛下。あなた、ばかですか?」
「くっ…はっはは」
堪えきれないように腹を抱えて声を立てて笑う、珍しい男をルナは迷惑げに見上げる。当たり前だ。胸元から逃してくれないのだから、腹を抱えられればさらに苦しい態勢になる。
巧みにルナを拘束していたレオボルトの腕の中から、ようやくするりと抜け出して、ルナは息苦しくて紅潮した顔でレオボルトを睨みあげた。
「執務室にいてください。すぐに案内しますから」
執務室で待ち構えていたヴァルトは、機嫌のよい顔で入ってきたレオボルトを一瞥して目を逸らし、小さくため息をついた。
ここ数日。ルナを客人につけてから日に日に機嫌が悪くなっていたのだが。これは、ルナが迷惑を被ったなとひと目でわかる。
こうなることはわかり切っていたのだから、そもそもルナを完全に客人につけてしまわなければよかったのだ。
「ほどほどにしろよ。逃げられるぞ」
「逃さんよ」
気楽な言葉で忠告すれば、人の悪い笑みで返される。
「あれは、ルナだからな」
「分かっている。俺が分かっていることも、分かってるんだろう?あれがカヤなら、俺の手元に置いておけない」
お前のものだからな、という言葉は飲み込む。
レオボルトにとっては、それはきっかけ。ルナを見るきっかけ。それが執着心を強めはしたけれど、混同はしていない。
ヴァルトにとってはあえていうなら、それは結果なのだろう。結果、ルナはカヤだったかもしれないが、カヤではない。ヴァルトがルナに向ける視線は、妹や…娘に向けるようなもの。それだからこそ、厄介だともレオボルトは思うけれど。
「レオ、なんでルナをあの男に近づけた?」
幼いレオボルトを庇護した時の呼び方で呼び、ヴァルトは厳しい目を向ける。その判断は、王としての客人への配慮や疑いをかけられた者への警戒の結果ではないと、長い付き合いからわかる。
「あの2人の、様子を見たかった」
「悪趣味だ」
ルナは相手をわかっている。
シルヴィは、おそらくわかっていない。疑っているかもしれないが、確証はない。
ひたすら、ルナが居心地悪く、そしてレオボルトがおそれた何かがあるなら、ひたすら辛い思いをするだけ。
離宮の中の執務室にシルヴィを案内し、ルナは中には入らずに外に控える。
何を話したのか、それほどかからずに出てきたシルヴィをまた居室に案内し、出て行こうとしたところでシルヴィに呼び止められた。
「もう少し、自由に動けないものか。だめだという場所には近寄らない」
「陛下のお赦しが出れば可能でしょうが。いつ何時でも、行きたい場所があればお呼びください。移動される時以外は、お一人で極力お過ごしいただけるよう、控えておりますので」
監視でもあり、それが護衛でもある。
それを言うわけにはいかないけれど。
「先ほど、願ってみたが、待てと言われた」
「だめだ、ではなく、待て、だったのですね。それでは、お待ちいただければ、いずれは」
静かに頭を下げ、次の間に下がると、ルナは息を吐き出す。
声をかけられるたびに緊張する。気づかれているのかも、それを伺うように顔を見ることもできない。その仕草で気づかれるのも怖くて。
罵言を浴びせられるのは慣れてしまったけれど、あの人からのそれは、怖い。
一度、最後にお互いに認識して顔をあわせたときにもう、経験しているけれど。そう誘導したのは自分だけれど。酷い言葉を、向けて。
その夜更。
ルナの頭にシロの声が届く。
(どうしたの?)
(少し、交代)
間を置いて、ルナはざわざわする胸を押さえ込む。
(陛下になにか?)
(刺客とかじゃない。それならなんとかする。とにかく、交代)
シロの声が言った瞬間、シロとルナの体が互いに入れ替わった。ルナのいた部屋にシロがあらわれ、シルヴィのために控える。
同時に、シロが伏せていた場所に、ルナは立っていた。
強引…。
あのシロがなにを、と思って顔を巡らせ、気付いて眉を下げた。
(仕方ないひと…)
問いかける声に、ルナはお茶を淹れる手元から目を離さずに短く、いいえ、と応じた。
最初、名を尋ねた割に、シルヴィはルナの名を呼ばない。まあ、この離宮に侍女がルナ一人しかいない時点で、確かに名は必要ないだろう。
それに。
この人にとっては、呼びたくもない名だろう。
「お聞き及びかと思いますが、わたしは爵位のある家の縁の者ではありません。こういった場での作法も知りませんので、宰相閣下にはなにかとご指導いただいております」
シルヴィの前にカップを置き、下がって頭を下げながら、部屋を辞そうとする。レオボルトにシルヴィからの面会の希望を伝えに行かなければいけない。
「噂…か」
シルヴィの呟きに、そういえば、下世話なものの方が多かったな、と思いながらルナは表情には出さず、部屋を出た。
その下世話なものを肯定するような言い回しに聞こえてしまったかとも思ったが、正直、どうでもよかった。身分ある人たちには障りがあるだろうが、それを言っても無視しているのはあの人たちだ。
「お前…」
適当にレオボルトを探し歩き、鍛錬場でその姿を見つけて歩み寄ったルナに、レオボルトは思い切り顔を顰めて見せた。
「やっと顔を見せたな」
「は?」
きょとんと首をかしげ、ルナは気にしないことにして用件を伝える。
「辺境伯閣下が陛下にお会いしたいそうです。執務室でよろしいですか?」
「会うかどうかを、聞け。まずは」
「だって、暇ですよね?ここにいるんですから」
「……」
眉間のシワがさらに深くなり、レオボルトは舌打ちをしてその長い腕をルナに伸ばした。
「うわぁっ!?」
バランスを崩し、うっすらと汗をかいたレオボルトの胸元によろける。固く厚い胸板に額を当てる形で頭を抑えられ、そのままぐしゃぐしゃと掻き回された。
「なっ…なっ」
言葉にならないルナを見下ろして、レオボルトは苦虫を噛み潰したような顔だったものに笑みを浮かべた。
「全然俺のところに顔を見せないのはどういう了見だ」
「あなたが客人の世話をしろと命じたんでしょう!」
「あいつがいない時に様子を見るくらいの気遣いを見せろ。そもそもは俺の護衛だろうが。気にならんのか」
「何かあれば、すぐにわかります!シロがいるんだから。他にも騎士の方々もいるんです。わたしのようなおまけにそんなことは誰も期待していません」
「俺がしている」
さらっと言われた言葉に、ルナは開いた口が塞がらない思いだが、顔を胸板に押し付けられていてレオボルトの顔を見上げることもできない。後頭部に当てられた手はずっとぐしゃぐしゃと髪を撫で続けている。
(この人、ペットか何かだと思ってる…。絶対)
「わたしより毛並みのいいのが近くに今はいるじゃないですか」
「あれがお前以外に触らせるわけがなかろう」
呆れたように言い返されれば、それには頷くしかない。が、この状況は納得がいかない。
「とにかく、辺境伯様がお待ちですから。移動してください。辺境伯様をそちらに案内しますから」
「呼び方が安定しないな。昔のように呼べばいいだろう」
「…陛下。あなた、ばかですか?」
「くっ…はっはは」
堪えきれないように腹を抱えて声を立てて笑う、珍しい男をルナは迷惑げに見上げる。当たり前だ。胸元から逃してくれないのだから、腹を抱えられればさらに苦しい態勢になる。
巧みにルナを拘束していたレオボルトの腕の中から、ようやくするりと抜け出して、ルナは息苦しくて紅潮した顔でレオボルトを睨みあげた。
「執務室にいてください。すぐに案内しますから」
執務室で待ち構えていたヴァルトは、機嫌のよい顔で入ってきたレオボルトを一瞥して目を逸らし、小さくため息をついた。
ここ数日。ルナを客人につけてから日に日に機嫌が悪くなっていたのだが。これは、ルナが迷惑を被ったなとひと目でわかる。
こうなることはわかり切っていたのだから、そもそもルナを完全に客人につけてしまわなければよかったのだ。
「ほどほどにしろよ。逃げられるぞ」
「逃さんよ」
気楽な言葉で忠告すれば、人の悪い笑みで返される。
「あれは、ルナだからな」
「分かっている。俺が分かっていることも、分かってるんだろう?あれがカヤなら、俺の手元に置いておけない」
お前のものだからな、という言葉は飲み込む。
レオボルトにとっては、それはきっかけ。ルナを見るきっかけ。それが執着心を強めはしたけれど、混同はしていない。
ヴァルトにとってはあえていうなら、それは結果なのだろう。結果、ルナはカヤだったかもしれないが、カヤではない。ヴァルトがルナに向ける視線は、妹や…娘に向けるようなもの。それだからこそ、厄介だともレオボルトは思うけれど。
「レオ、なんでルナをあの男に近づけた?」
幼いレオボルトを庇護した時の呼び方で呼び、ヴァルトは厳しい目を向ける。その判断は、王としての客人への配慮や疑いをかけられた者への警戒の結果ではないと、長い付き合いからわかる。
「あの2人の、様子を見たかった」
「悪趣味だ」
ルナは相手をわかっている。
シルヴィは、おそらくわかっていない。疑っているかもしれないが、確証はない。
ひたすら、ルナが居心地悪く、そしてレオボルトがおそれた何かがあるなら、ひたすら辛い思いをするだけ。
離宮の中の執務室にシルヴィを案内し、ルナは中には入らずに外に控える。
何を話したのか、それほどかからずに出てきたシルヴィをまた居室に案内し、出て行こうとしたところでシルヴィに呼び止められた。
「もう少し、自由に動けないものか。だめだという場所には近寄らない」
「陛下のお赦しが出れば可能でしょうが。いつ何時でも、行きたい場所があればお呼びください。移動される時以外は、お一人で極力お過ごしいただけるよう、控えておりますので」
監視でもあり、それが護衛でもある。
それを言うわけにはいかないけれど。
「先ほど、願ってみたが、待てと言われた」
「だめだ、ではなく、待て、だったのですね。それでは、お待ちいただければ、いずれは」
静かに頭を下げ、次の間に下がると、ルナは息を吐き出す。
声をかけられるたびに緊張する。気づかれているのかも、それを伺うように顔を見ることもできない。その仕草で気づかれるのも怖くて。
罵言を浴びせられるのは慣れてしまったけれど、あの人からのそれは、怖い。
一度、最後にお互いに認識して顔をあわせたときにもう、経験しているけれど。そう誘導したのは自分だけれど。酷い言葉を、向けて。
その夜更。
ルナの頭にシロの声が届く。
(どうしたの?)
(少し、交代)
間を置いて、ルナはざわざわする胸を押さえ込む。
(陛下になにか?)
(刺客とかじゃない。それならなんとかする。とにかく、交代)
シロの声が言った瞬間、シロとルナの体が互いに入れ替わった。ルナのいた部屋にシロがあらわれ、シルヴィのために控える。
同時に、シロが伏せていた場所に、ルナは立っていた。
強引…。
あのシロがなにを、と思って顔を巡らせ、気付いて眉を下げた。
(仕方ないひと…)
0
あなたにおすすめの小説



(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」
音爽(ネソウ)
ファンタジー
容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。
本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。
しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。
*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

私の容姿は中の下だと、婚約者が話していたのを小耳に挟んでしまいました
山田ランチ
恋愛
想い合う二人のすれ違いラブストーリー。
※以前掲載しておりましたものを、加筆の為再投稿致しました。お読み下さっていた方は重複しますので、ご注意下さいませ。
コレット・ロシニョール 侯爵家令嬢。ジャンの双子の姉。
ジャン・ロシニョール 侯爵家嫡男。コレットの双子の弟。
トリスタン・デュボワ 公爵家嫡男。コレットの婚約者。
クレマン・ルゥセーブル・ジハァーウ、王太子。
シモン・グレンツェ 辺境伯家嫡男。コレットの従兄。
ルネ ロシニョール家の侍女でコレット付き。
シルヴィー・ペレス 子爵令嬢。
〈あらすじ〉
コレットは愛しの婚約者が自分の容姿について話しているのを聞いてしまう。このまま大好きな婚約者のそばにいれば疎まれてしまうと思ったコレットは、親類の領地へ向かう事に。そこで新しい商売を始めたコレットは、知らない間に国の重要人物になってしまう。そしてトリスタンにも女性の影が見え隠れして……。
ジレジレ、すれ違いラブストーリー

ネグレクトされていた四歳の末娘は、前世の経理知識で実家の横領を見抜き追放されました。これからはもふもふ聖獣と美食巡りの旅に出ます。
☆ほしい
ファンタジー
アークライト子爵家の四歳の末娘リリアは、家族から存在しないものとして扱われていた。食事は厨房の残飯、衣服は兄姉のお下がりを更に継ぎ接ぎしたもの。冷たい床で眠る日々の中、彼女は高熱を出したことをきっかけに前世の記憶を取り戻す。
前世の彼女は、ブラック企業で過労死した経理担当のOLだった。
ある日、父の書斎に忍び込んだリリアは、ずさんな管理の家計簿を発見する。前世の知識でそれを読み解くと、父による悪質な横領と、家の財産がすでに破綻寸前であることが判明した。
「この家は、もうすぐ潰れます」
家族会議の場で、リリアはたった四歳とは思えぬ明瞭な口調で破産の事実を突きつける。激昂した父に「疫病神め!」と罵られ家を追い出されたリリアだったが、それは彼女の望むところだった。
手切れ金代わりの銅貨数枚を握りしめ、自由を手に入れたリリア。これからは誰にも縛られず、前世で夢見た美味しいものをたくさん食べる生活を目指す。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

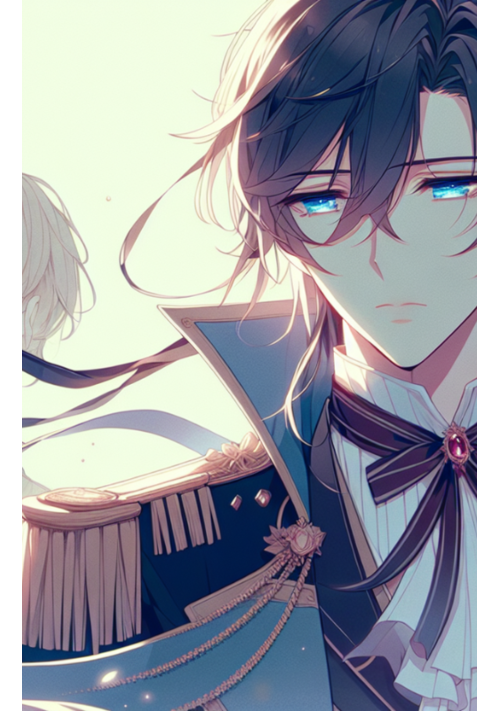
私たちの離婚幸福論
桔梗
ファンタジー
ヴェルディア帝国の皇后として、順風満帆な人生を歩んでいたルシェル。
しかし、彼女の平穏な日々は、ノアの突然の記憶喪失によって崩れ去る。
彼はルシェルとの記憶だけを失い、代わりに”愛する女性”としてイザベルを迎え入れたのだった。
信じていた愛が消え、冷たく突き放されるルシェル。
だがそこに、隣国アンダルシア王国の皇太子ゼノンが現れ、驚くべき提案を持ちかける。
それは救済か、あるいは——
真実を覆う闇の中、ルシェルの新たな運命が幕を開ける。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















