7 / 38
第7話 鍵のように、鍵のように
しおりを挟む
「この辺、か?」
南西隅に突き当たり、地面から天井へ壁を見上げる。当然何の変わりもなく、切り出されたままのごつごつとした表面を見せる石が積み上げられているのみだった。ただ、石と石とが触れる面はよほど磨き上げられ、計算されて積まれているのか、ナイフの刺さる隙間もなかった。まるで蛇の鱗みたいに、一つながりにでもなっているかのように。
ウォレスはため息をつきながら、その辺の壁を叩いてみる。やはり手応えはどこも変わらず、空洞があるような反響はない。徒労だとは知っているが、透視の呪文も唱えてみる。
「ヴ・イア・デアリ・イヴイル・リ・イヴイル・ノーチアル――【透過視】」
人差指の先から尾を引いて滴る青白い光を、片目のまぶたに塗りつける。ぬらりと冷たい。そちら側の目だけ開けて壁を見回す。青白い視界の中で目を細め、壁の表面に焦点を合わせる。そこから目を見開き、目の前をぼやけさせ遠くに焦点を移していく。それにつれて目に飛び込んでくるのは石、隙間なく積まれた石石石石石石石。
何度も目をしばたかせ、まぶたに残った光を手で拭う。
徒労だ。間違いなく徒労だ、これは。目が疲れただけだ。こんなことならあの店で吐くまで呑んでいた方がマシだった。
手にした欠片を投げ捨てようとして、だが思う。――あいつは、あの女は何をしに来たんだ? わざわざ俺の目を疲れさせに? あれが魔物だとして、アレシアの姿を真似られたとして。叩き殺されるかもしれない危険を冒して?
「……」
眉を寄せ、口回りに皺を寄せ、押し潰されたような顔でウォレスは欠片を握り締める。言い訳のように一瞬だけ壁へ当て、すぐに引く。
なのに。地響きも立てず壁は動き出した。まるでかさぶたが剥げ落ちるように、表面の石は剥がれ落ち。奥に詰まった石は花びらが開いていくように、小虫の群れが身を引いていくように、二つに分かれて道を開けた。
「……」
そのままの顔で、ウォレスは道の奥を見ていた。やがて頬が小さく震える。
なるほど、確かに知らない区域はあった。迷宮の全てを制した英雄ウォレスですら、知らなかった。未知だ。なるほど、ウォレスが探し求めていたものだ、王家ですらも与えられなかったものだ。なるほど。
奥歯を、音を立てて噛み締める。
どういうことだ。ないんじゃなかったのか? 英雄ウォレスが二年もかけて探したものは。九年間も求めたものは。
気に入らない。あるはずがないと諦めていたものが、犬に骨でも投げ与えるように放ってよこされるなんて。ああ、もしかしたらその辺で見て笑っているんじゃないか? あの女は。
歪みきった頬を震わせ、ウォレスは通路――波打ったような形で石壁が口を開けた、ようやく人がすれ違えるぐらい――の奥へと駆けた。
そこは確かに通路だった。わずかに道が曲がりくねる他、分かれ道も糞もなかった。ただ、それでも導くように、青い光が目に入る。最初はわずかだった、錯覚かと思った。それでも駆けるにつれて強くなる。確かに何かが在ると思ったときには終着点へ着いていた。あっけなく。
そこは小さく広間になっていた、半径三十歩ほどの円を描いて。天井も丸くそれぐらいの高さで、壁は相変わらず波打つようにでこぼこと石が積まれていた。そこに詰まっていたものが無理やり身を引いたかのように。
広間の中央には光の源があった。それは何かの伝説よろしく、石の台座に突き立てられた剣。その刀身から、ぎらぎらと青く光が漏れ出ていた。
「ふん……」
剣には触れず、周囲を回りながら刀身の地金や刃の具合を見る。もちろん、帯びた剣の鞘で地面を叩いて反響を確認することも忘れない。
まず、周囲に罠の類はない。剣自体は迷宮で目にした中でも最上級のもの――『絶聖剣』――で、つまりはウォレスが見飽きたものだ。ただ、その刀身には何か、文字のようなものが一面に刻まれ、塗料が青くそこへ塗り込まれていた。ひどく古いのか刻印はかすれ、塗料は剥がれかけている。それらはもちろんどう読むのか分からなかった。が、どこかで目にしたような気もする。迷宮の中だったかどうか。
「ふん」
鼻で息をついた。なるほど秘められた武器、確かに知らないものだ。だが、これだけか? 古代文字か何か分からないが描かれ、おそらくは何らかの魔法がかけられた武器。これを取ったらどうだというのだ。
そこまで考えて、絹のような声が頭の中を滑る――帰って来れる。帰って来れるの、昔のままに。今はほんの少しだけど――。
その声の内容が麦酒の泡のように、浮かんでは思考の表面へ溜まっていく――また会えるよ……ぼく――。
ウォレスは口を開けていた。突き立てられた剣の柄に手をかけていた。表情はなく、思考もなかった。ただそうする他のことは、考えつかなかった。
一息に引き抜く。石にこすれる感触を残し、素直に剣は台座から離れた。
そのとき、刀身から放たれていた光が切先へと集まり、一かたまりの滴となって地面へこぼれ落ちる。光は一歩ほどの大きさの円を描き、波紋のように地面へ広がる。そして地響きのような、石と石とがこすれ合う音を立てて震え、地面が隆起し、立ち上がり。一つの形を造った。
戦士。ウォレスの身長を越える、軽装鎧に身を包んだ石造りの戦士。その体は細かな石、一つ一つ四角い、刻んだように小さな積み石でできていた。腕の筋肉に盛り上がった血管や、額当ての上から伸びた髪の筋までも。
「……ふうん」
なるほど、これもまた知らないものではある。見たことはないし、聞いていないものでもある。そして、期待したものではない。
そう思う間に、目の前に戦士が踏み込んでくる。空気を斬る音を立てて振るう右手には、いつの間にか剣が――これは石でなく本身だ、光を発していた剣と同じ形――握られていた。
横へ跳んで身をかわす。戦士の剣は的を外し、何にも当たりはしなかったが。勢い余った風圧が壁を裂いた。
ウォレスは口笛を吹くように――実際には吹けもしないが――口を丸くすぼめて息を吐いた。
確かにこれは、見たことがない。踏み込みの速さも斬撃の強さも、あらゆる魔物とは次元が違う。今のを受けたのが例えば、覇王樹亭の店主なら――達人級の戦闘者なら――確実に真っ二つだった。ジェイナスなら二、三度は受けられるか。アランなら今はどうだろう。
考える間にも戦士は石の関節を軋らせ、さらに続けて踏み込んだ。真っ向からの一撃、斜め上へと払う斬り上げ。続けざまに胸へ腹へ、浴びせかけるような乱れ突き。その度、風圧に壁や床の石が弾ける。
なるほど、まるで次元が違う。最下層にもこれほどの速さを持つ魔物はいない。魔王ですら一たまりもあるまいし、あるいは邪神さえ――この速さをそれだけ維持できるのなら――十二、三分も持ちこたえられまい。
相手に致命傷がないと見てか、戦士がその動きを変えた。倒れ込むような姿勢で、身を低めつつさらに速度を上げて――倒れ込む勢いを利用しつつ空気抵抗を下げたか――床を踏み砕きつつ駆ける。その速さのまま下段を斬り抜ける、と見えたが。ウォレスの直前で、石畳を砕き散らしながら急停止。駆け込んだその勢いを、全て肩から腕へと伝える。突然の上段を横殴りに――ウォレスの視界の外からの攻撃を狙ったか――、首を刎ねるように襲い来る刃。なるほど、まるで次元が違う。
ウォレスは正面から手を伸ばした。剣を持った戦士の手首を取る。勢いにわずかに押し返され、ウォレスの足が地面を擦る。それで戦士の剣は止まった。ウォレスは握る手に力を込め、石の手首を折り砕く。
なるほど、まるで次元が違う。ここまでの強者とまみえたことなどない。そしてまあ、それだけだった。
姿勢を低めていた戦士の体を適当に踏みしだく。砕けかけたそれを片手でつかみ上げ、宙へ放り投げる。引き抜いていた剣をそこへ振るった。刃は遠く当たりはしなかったが、巻き起こす風圧が戦士の体を二つに分ける。さらに振るう、縦へ斜めへ細切れに。
確かに見たことがなかった。風圧だけで敵を斬るなどと、ウォレス以外でできる者を。
その辺の石くれと見分けがつかなくなった戦士を残し、元来た通路へ向かう。ウォレスが足を運ぶにつれて、背後の積み石は音もなくせり出し、未だかつて誰も通したことなどないという顔で閉じていった。
ため息をつく。
「……で?」
なるほど、言ったとおりの場所、言ったとおりの知らないもの。言ったとおりに手に入れて、で? 帰ってくるとは、地下に囚われたものとは? まさか今の戦士でもあるまい。解放されて感激しているという様子には見えなかった。それにこの武器は何だ、渡されたこの欠片は?
「まあ、いい」
取りにくると言っていた、あれは。アレシアの顔をした女は。そのときに問いただそう。
手にした剣は今のでちょっと曲がっていたが。まあ、壊すなとは言われていない。
南西隅に突き当たり、地面から天井へ壁を見上げる。当然何の変わりもなく、切り出されたままのごつごつとした表面を見せる石が積み上げられているのみだった。ただ、石と石とが触れる面はよほど磨き上げられ、計算されて積まれているのか、ナイフの刺さる隙間もなかった。まるで蛇の鱗みたいに、一つながりにでもなっているかのように。
ウォレスはため息をつきながら、その辺の壁を叩いてみる。やはり手応えはどこも変わらず、空洞があるような反響はない。徒労だとは知っているが、透視の呪文も唱えてみる。
「ヴ・イア・デアリ・イヴイル・リ・イヴイル・ノーチアル――【透過視】」
人差指の先から尾を引いて滴る青白い光を、片目のまぶたに塗りつける。ぬらりと冷たい。そちら側の目だけ開けて壁を見回す。青白い視界の中で目を細め、壁の表面に焦点を合わせる。そこから目を見開き、目の前をぼやけさせ遠くに焦点を移していく。それにつれて目に飛び込んでくるのは石、隙間なく積まれた石石石石石石石。
何度も目をしばたかせ、まぶたに残った光を手で拭う。
徒労だ。間違いなく徒労だ、これは。目が疲れただけだ。こんなことならあの店で吐くまで呑んでいた方がマシだった。
手にした欠片を投げ捨てようとして、だが思う。――あいつは、あの女は何をしに来たんだ? わざわざ俺の目を疲れさせに? あれが魔物だとして、アレシアの姿を真似られたとして。叩き殺されるかもしれない危険を冒して?
「……」
眉を寄せ、口回りに皺を寄せ、押し潰されたような顔でウォレスは欠片を握り締める。言い訳のように一瞬だけ壁へ当て、すぐに引く。
なのに。地響きも立てず壁は動き出した。まるでかさぶたが剥げ落ちるように、表面の石は剥がれ落ち。奥に詰まった石は花びらが開いていくように、小虫の群れが身を引いていくように、二つに分かれて道を開けた。
「……」
そのままの顔で、ウォレスは道の奥を見ていた。やがて頬が小さく震える。
なるほど、確かに知らない区域はあった。迷宮の全てを制した英雄ウォレスですら、知らなかった。未知だ。なるほど、ウォレスが探し求めていたものだ、王家ですらも与えられなかったものだ。なるほど。
奥歯を、音を立てて噛み締める。
どういうことだ。ないんじゃなかったのか? 英雄ウォレスが二年もかけて探したものは。九年間も求めたものは。
気に入らない。あるはずがないと諦めていたものが、犬に骨でも投げ与えるように放ってよこされるなんて。ああ、もしかしたらその辺で見て笑っているんじゃないか? あの女は。
歪みきった頬を震わせ、ウォレスは通路――波打ったような形で石壁が口を開けた、ようやく人がすれ違えるぐらい――の奥へと駆けた。
そこは確かに通路だった。わずかに道が曲がりくねる他、分かれ道も糞もなかった。ただ、それでも導くように、青い光が目に入る。最初はわずかだった、錯覚かと思った。それでも駆けるにつれて強くなる。確かに何かが在ると思ったときには終着点へ着いていた。あっけなく。
そこは小さく広間になっていた、半径三十歩ほどの円を描いて。天井も丸くそれぐらいの高さで、壁は相変わらず波打つようにでこぼこと石が積まれていた。そこに詰まっていたものが無理やり身を引いたかのように。
広間の中央には光の源があった。それは何かの伝説よろしく、石の台座に突き立てられた剣。その刀身から、ぎらぎらと青く光が漏れ出ていた。
「ふん……」
剣には触れず、周囲を回りながら刀身の地金や刃の具合を見る。もちろん、帯びた剣の鞘で地面を叩いて反響を確認することも忘れない。
まず、周囲に罠の類はない。剣自体は迷宮で目にした中でも最上級のもの――『絶聖剣』――で、つまりはウォレスが見飽きたものだ。ただ、その刀身には何か、文字のようなものが一面に刻まれ、塗料が青くそこへ塗り込まれていた。ひどく古いのか刻印はかすれ、塗料は剥がれかけている。それらはもちろんどう読むのか分からなかった。が、どこかで目にしたような気もする。迷宮の中だったかどうか。
「ふん」
鼻で息をついた。なるほど秘められた武器、確かに知らないものだ。だが、これだけか? 古代文字か何か分からないが描かれ、おそらくは何らかの魔法がかけられた武器。これを取ったらどうだというのだ。
そこまで考えて、絹のような声が頭の中を滑る――帰って来れる。帰って来れるの、昔のままに。今はほんの少しだけど――。
その声の内容が麦酒の泡のように、浮かんでは思考の表面へ溜まっていく――また会えるよ……ぼく――。
ウォレスは口を開けていた。突き立てられた剣の柄に手をかけていた。表情はなく、思考もなかった。ただそうする他のことは、考えつかなかった。
一息に引き抜く。石にこすれる感触を残し、素直に剣は台座から離れた。
そのとき、刀身から放たれていた光が切先へと集まり、一かたまりの滴となって地面へこぼれ落ちる。光は一歩ほどの大きさの円を描き、波紋のように地面へ広がる。そして地響きのような、石と石とがこすれ合う音を立てて震え、地面が隆起し、立ち上がり。一つの形を造った。
戦士。ウォレスの身長を越える、軽装鎧に身を包んだ石造りの戦士。その体は細かな石、一つ一つ四角い、刻んだように小さな積み石でできていた。腕の筋肉に盛り上がった血管や、額当ての上から伸びた髪の筋までも。
「……ふうん」
なるほど、これもまた知らないものではある。見たことはないし、聞いていないものでもある。そして、期待したものではない。
そう思う間に、目の前に戦士が踏み込んでくる。空気を斬る音を立てて振るう右手には、いつの間にか剣が――これは石でなく本身だ、光を発していた剣と同じ形――握られていた。
横へ跳んで身をかわす。戦士の剣は的を外し、何にも当たりはしなかったが。勢い余った風圧が壁を裂いた。
ウォレスは口笛を吹くように――実際には吹けもしないが――口を丸くすぼめて息を吐いた。
確かにこれは、見たことがない。踏み込みの速さも斬撃の強さも、あらゆる魔物とは次元が違う。今のを受けたのが例えば、覇王樹亭の店主なら――達人級の戦闘者なら――確実に真っ二つだった。ジェイナスなら二、三度は受けられるか。アランなら今はどうだろう。
考える間にも戦士は石の関節を軋らせ、さらに続けて踏み込んだ。真っ向からの一撃、斜め上へと払う斬り上げ。続けざまに胸へ腹へ、浴びせかけるような乱れ突き。その度、風圧に壁や床の石が弾ける。
なるほど、まるで次元が違う。最下層にもこれほどの速さを持つ魔物はいない。魔王ですら一たまりもあるまいし、あるいは邪神さえ――この速さをそれだけ維持できるのなら――十二、三分も持ちこたえられまい。
相手に致命傷がないと見てか、戦士がその動きを変えた。倒れ込むような姿勢で、身を低めつつさらに速度を上げて――倒れ込む勢いを利用しつつ空気抵抗を下げたか――床を踏み砕きつつ駆ける。その速さのまま下段を斬り抜ける、と見えたが。ウォレスの直前で、石畳を砕き散らしながら急停止。駆け込んだその勢いを、全て肩から腕へと伝える。突然の上段を横殴りに――ウォレスの視界の外からの攻撃を狙ったか――、首を刎ねるように襲い来る刃。なるほど、まるで次元が違う。
ウォレスは正面から手を伸ばした。剣を持った戦士の手首を取る。勢いにわずかに押し返され、ウォレスの足が地面を擦る。それで戦士の剣は止まった。ウォレスは握る手に力を込め、石の手首を折り砕く。
なるほど、まるで次元が違う。ここまでの強者とまみえたことなどない。そしてまあ、それだけだった。
姿勢を低めていた戦士の体を適当に踏みしだく。砕けかけたそれを片手でつかみ上げ、宙へ放り投げる。引き抜いていた剣をそこへ振るった。刃は遠く当たりはしなかったが、巻き起こす風圧が戦士の体を二つに分ける。さらに振るう、縦へ斜めへ細切れに。
確かに見たことがなかった。風圧だけで敵を斬るなどと、ウォレス以外でできる者を。
その辺の石くれと見分けがつかなくなった戦士を残し、元来た通路へ向かう。ウォレスが足を運ぶにつれて、背後の積み石は音もなくせり出し、未だかつて誰も通したことなどないという顔で閉じていった。
ため息をつく。
「……で?」
なるほど、言ったとおりの場所、言ったとおりの知らないもの。言ったとおりに手に入れて、で? 帰ってくるとは、地下に囚われたものとは? まさか今の戦士でもあるまい。解放されて感激しているという様子には見えなかった。それにこの武器は何だ、渡されたこの欠片は?
「まあ、いい」
取りにくると言っていた、あれは。アレシアの顔をした女は。そのときに問いただそう。
手にした剣は今のでちょっと曲がっていたが。まあ、壊すなとは言われていない。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

田舎農家の俺、拾ったトカゲが『始祖竜』だった件〜女神がくれたスキル【絶対飼育】で育てたら、魔王がコスメ欲しさに竜王が胃薬借りに通い詰めだした
月神世一
ファンタジー
「くそっ、魔王はまたトカゲの抜け殻を美容液にしようとしてるし、女神は酒のつまみばかり要求してくる! 俺はただ静かに農業がしたいだけなのに!」
ブラック企業で過労死した日本人、カイト。
彼の願いはただ一つ、「誰にも邪魔されない静かな場所で農業をすること」。
女神ルチアナからチートスキル【絶対飼育】を貰い、異世界マンルシア大陸の辺境で念願の農場を開いたカイトだったが、ある日、庭から虹色の卵を発掘してしまう。
孵化したのは、可愛らしいトカゲ……ではなく、神話の時代に世界を滅亡させた『始祖竜』の幼体だった!
しかし、カイトはスキル【絶対飼育】のおかげで、その破壊神を「ポチ」と名付けたペットとして完璧に飼い慣らしてしまう。
ポチのくしゃみ一発で、敵の軍勢は老衰で塵に!?
ポチの抜け殻は、魔王が喉から手が出るほど欲しがる究極の美容成分に!?
世界を滅ぼすほどの力を持つポチと、その魔素を浴びて育った規格外の農作物を求め、理知的で美人の魔王、疲労困憊の竜王、いい加減な女神が次々にカイトの家に押しかけてくる!
「世界の管理者」すら手が出せない最強の農場主、カイト。
これは、世界の運命と、美味しい野菜と、ペットの散歩に追われる、史上最も騒がしいスローライフ物語である!


アラフォーおっさんの週末ダンジョン探検記
ぽっちゃりおっさん
ファンタジー
ある日、全世界の至る所にダンジョンと呼ばれる異空間が出現した。
そこには人外異形の生命体【魔物】が存在していた。
【魔物】を倒すと魔石を落とす。
魔石には膨大なエネルギーが秘められており、第五次産業革命が起こるほどの衝撃であった。
世は埋蔵金ならぬ、魔石を求めて日々各地のダンジョンを開発していった。


裏切られ続けた負け犬。25年前に戻ったので人生をやり直す。当然、裏切られた礼はするけどね
竹井ゴールド
ファンタジー
冒険者ギルドの雑用として働く隻腕義足の中年、カーターは裏切られ続ける人生を送っていた。
元々は食堂の息子という人並みの平民だったが、
王族の継承争いに巻き込まれてアドの街の毒茸流布騒動でコックの父親が毒茸の味見で死に。
代わって雇った料理人が裏切って金を持ち逃げ。
父親の親友が融資を持ち掛けるも平然と裏切って借金の返済の為に母親と妹を娼館へと売り。
カーターが冒険者として金を稼ぐも、後輩がカーターの幼馴染に横恋慕してスタンピードの最中に裏切ってカーターは片腕と片足を損失。カーターを持ち上げていたギルマスも裏切り、幼馴染も去って後輩とくっつく。
その後は負け犬人生で冒険者ギルドの雑用として細々と暮らしていたのだが。
ある日、人ならざる存在が話しかけてきた。
「この世界は滅びに進んでいる。是正しなければならない。手を貸すように」
そして気付けは25年前の15歳にカーターは戻っており、二回目の人生をやり直すのだった。
もちろん、裏切ってくれた連中への返礼と共に。
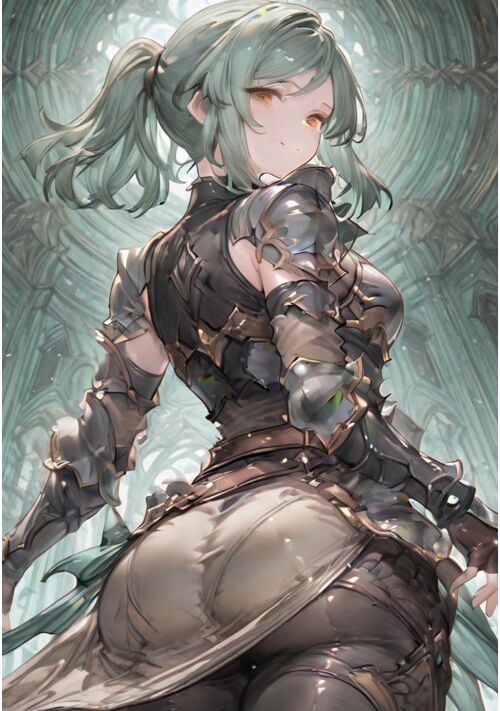
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















