12 / 38
第12話 一歩違えば夫婦(めおと)の仲
しおりを挟む
地の底への帰り道。鞘に納めた剣の先で、こつんこつんと壁を叩く。あるいは床に引きずって、床石の継ぎ目ごとに震動を感じる。隠し通路を探るわけではなく、アレシアを――壁に飲まれた、アシェル・アヴァンセンと名乗った女を――探しているわけでもなく。ただそうしていた、街の子供たちが棒切れで、石畳の道にそうするように。
ため息をつく。何なんだあれは、彼女は、あの壁は? あるいはこの迷宮は。どうすればいい? 分かっているのはただ一つ、帰ったら俺は呑むだろうということだけ。呑もう、という意気があるわけでもない、呑まなければやっていられない、というのでもない。ただ、だったら俺は呑むだろう。いつものように。
何を呑るか。不死鳥の唐黍酎や唐黍酎は俺の血のようなものだが――真っすぐに香り立つ、燃え上がるような血。俺とは大違いだ――、別のものもまたいい。
焦げ色をした褐色糖黍酎にするか、鼻の奥を甘く胃袋を渋く焦がしてくれる。糖黍酎漬けの干し葡萄がうらやましいなどと言う、冒険者も酒場にはいたものだ。馬鈴薯酎もたまにはいい。香りはないに等しいが、剣のような冷やかさで喉を通る。直後に走る、血のにじむような熱さまで刃物そっくりだ。
唾が湧くのを感じながら地下七百二十階を歩き、下層への階段――最下四層への――手前へ差し掛かったところで。ウォレスは足を止めていた。
音がした。こりり、こりり、とかじる音。魔物が骨でもかじっているのかと思ったが、もっと軽い音。まるで木の実でも頬張るような。しかし、地の底にそんな物があるはずもない。
音は続いた、こりこりと。こり、こりりこり、こりこ、こりこ、こり。頭蓋を内から引っかくような音が、耳障りに迷宮に響いた。辺りを見回しても何もない、積み石の壁が視界の果てまで続く迷宮に。
ウォレスは鞘ごと剣を提げた右手を垂らしたまま、左手を鞘に添えた。いつでも抜き打てる体勢。廊下の先に、階段の下に、闇の向こうに視線を巡らし、耳をそばだて、鼻を利かせる。
そうして気づいた、音の響いてくる先。下層への階段、そこから――下階ではなく階段の途中から――聞こえてくる。
構えを解いて階段の前まで歩き、ウォレスは言ってみる。
「何だ、君か? ……また、ずいぶんと気が早いな」
アレシア。彼女だろうとそう思った。他にこの階層を出歩ける者など――ディオンたちが部隊を組んでこない限り――いない。しかし先ほど壁に飲まれたばかり、新たな武器も抜いていないというのに。どういうことだ。
けれど響いてきた声は、絹のようなそれとは違った。
「……ほう。私が分かるか、英雄殿よ」
女の声、けれど低い。耳に引っかかる声だ、迷宮の積み石の間に挟んで、長年かけてすり潰したみたいな声音。しかし齢取っているというわけでもない。聞き覚えがある。確かに、ある。
こりり、と音を立てた後、くちゃくちゃとねぶるような音が続き、同じ声が後を受けた。
「しかし、君、とはご挨拶よな。それほど親しかったとも……いや、そうでもないか。なにせ一歩間違っておれば、私と汝とは夫婦の仲だ。なあ、婿殿よ」
ぱちん、と指を弾く音がして、階段上の空間が震えた。水面のような揺らぎが治まった後、何もなかったそこには女がいた。
薄闇の中、まずはっきりと見えたのは銀縁眼鏡。わずかな光を反射して、ぺかぺかと下品に輝いた。肩に下がる灰色の髪は荒く波打ち、何日も櫛を通していないのが――ウォレスが言うことでもないが――分かった。男ものか、大きなサイズの魔法衣、その下に見え隠れする首飾り。これはウォレスにも覚えがあった。首から下がる金の鎖、その先で金の型にはめ込まれた水晶玉。魔宝珠と呼ばれるそれからこぼれた青紫色の光が彼女の姿を照らす。手にした長い魔導杖も、もう片方の手に持った棒状の焼き菓子も。それを、こりり、とかじる、脂肪に膨れた頬も。
光を放つその首飾りは『王家の魔宝珠』。二十年ほど前に魔王が王宮から――王女と同時に――持ち去った秘宝。そして十三年ほど前、ウォレスたちが迷宮から――王女と同時に抱えて――奪い返した秘宝。
今、それを身につけているのは。かつてウォレスらが救出した王女。魔王を討伐した後、ウォレスと婚約を前提に、顔を見合わせた姫君。なるほど、あの顔に十一年ほどの歳月――それに脂肪――を詰め込んだならこうなるか。残酷にも。
ウォレスは口を開けていた。何を言えばいいか分からなかったが、とにかく口は動いていた。
「ああ、やあ、久しぶりで。姫……や、殿下、か」
喋ることもなしに顔は笑みの形を作り、口は動き続けていた。
「お元気そうで、何より。地上はどうです、変わりはありませ――」
「あるからこうして来ておるのさ。私ほどの者が直々にな」
へし折るようにそう言って、王女はさらに言葉を続けた。
「我が望みの宝珠は、手に入ってはおらんようだが。進展はあるか」
「……進展ってほどのもんはありませんがね。しかしそもそも、龍の宝珠ってのは――」
――いったい何だ。どんな物だ、何のためにある、王宮は何を知ってる? 失われて何が困る。それを使えば、いったいどうなる。それにあんた、どうやってここまで一人で――
口にしようとした言葉の先をかじるように、王女は白い歯を剥いた。そして言う。
「思い違うな。汝らに命じたのは、あくまで王宮による決定。私自身の意思は別だ。……汝らに、あれへ触れて欲しくはない」
ウォレスは眉を寄せた。
「触れるな、と? どういうことです、妙な話ですな。王宮にしろ何にしろ、探せと言ったのはそっち――」
「騒ぐな」
言い放った後、眼鏡を指で押し上げて王女は続けた。
「いいか? 私はあれを、汝らには触れさせん。汝らの出る幕もなく、私が全て終わらせる。……汝らは私が護ってやる、それが私の復讐よ」
復讐。されるいわれなどはないが、彼女がそうするだろう覚えならある。
何しろ言われたことがある、『許しはせぬ』と。ウォレスが婚約について、核心を切り出そうとしたそのときに。
ため息をつく。何なんだあれは、彼女は、あの壁は? あるいはこの迷宮は。どうすればいい? 分かっているのはただ一つ、帰ったら俺は呑むだろうということだけ。呑もう、という意気があるわけでもない、呑まなければやっていられない、というのでもない。ただ、だったら俺は呑むだろう。いつものように。
何を呑るか。不死鳥の唐黍酎や唐黍酎は俺の血のようなものだが――真っすぐに香り立つ、燃え上がるような血。俺とは大違いだ――、別のものもまたいい。
焦げ色をした褐色糖黍酎にするか、鼻の奥を甘く胃袋を渋く焦がしてくれる。糖黍酎漬けの干し葡萄がうらやましいなどと言う、冒険者も酒場にはいたものだ。馬鈴薯酎もたまにはいい。香りはないに等しいが、剣のような冷やかさで喉を通る。直後に走る、血のにじむような熱さまで刃物そっくりだ。
唾が湧くのを感じながら地下七百二十階を歩き、下層への階段――最下四層への――手前へ差し掛かったところで。ウォレスは足を止めていた。
音がした。こりり、こりり、とかじる音。魔物が骨でもかじっているのかと思ったが、もっと軽い音。まるで木の実でも頬張るような。しかし、地の底にそんな物があるはずもない。
音は続いた、こりこりと。こり、こりりこり、こりこ、こりこ、こり。頭蓋を内から引っかくような音が、耳障りに迷宮に響いた。辺りを見回しても何もない、積み石の壁が視界の果てまで続く迷宮に。
ウォレスは鞘ごと剣を提げた右手を垂らしたまま、左手を鞘に添えた。いつでも抜き打てる体勢。廊下の先に、階段の下に、闇の向こうに視線を巡らし、耳をそばだて、鼻を利かせる。
そうして気づいた、音の響いてくる先。下層への階段、そこから――下階ではなく階段の途中から――聞こえてくる。
構えを解いて階段の前まで歩き、ウォレスは言ってみる。
「何だ、君か? ……また、ずいぶんと気が早いな」
アレシア。彼女だろうとそう思った。他にこの階層を出歩ける者など――ディオンたちが部隊を組んでこない限り――いない。しかし先ほど壁に飲まれたばかり、新たな武器も抜いていないというのに。どういうことだ。
けれど響いてきた声は、絹のようなそれとは違った。
「……ほう。私が分かるか、英雄殿よ」
女の声、けれど低い。耳に引っかかる声だ、迷宮の積み石の間に挟んで、長年かけてすり潰したみたいな声音。しかし齢取っているというわけでもない。聞き覚えがある。確かに、ある。
こりり、と音を立てた後、くちゃくちゃとねぶるような音が続き、同じ声が後を受けた。
「しかし、君、とはご挨拶よな。それほど親しかったとも……いや、そうでもないか。なにせ一歩間違っておれば、私と汝とは夫婦の仲だ。なあ、婿殿よ」
ぱちん、と指を弾く音がして、階段上の空間が震えた。水面のような揺らぎが治まった後、何もなかったそこには女がいた。
薄闇の中、まずはっきりと見えたのは銀縁眼鏡。わずかな光を反射して、ぺかぺかと下品に輝いた。肩に下がる灰色の髪は荒く波打ち、何日も櫛を通していないのが――ウォレスが言うことでもないが――分かった。男ものか、大きなサイズの魔法衣、その下に見え隠れする首飾り。これはウォレスにも覚えがあった。首から下がる金の鎖、その先で金の型にはめ込まれた水晶玉。魔宝珠と呼ばれるそれからこぼれた青紫色の光が彼女の姿を照らす。手にした長い魔導杖も、もう片方の手に持った棒状の焼き菓子も。それを、こりり、とかじる、脂肪に膨れた頬も。
光を放つその首飾りは『王家の魔宝珠』。二十年ほど前に魔王が王宮から――王女と同時に――持ち去った秘宝。そして十三年ほど前、ウォレスたちが迷宮から――王女と同時に抱えて――奪い返した秘宝。
今、それを身につけているのは。かつてウォレスらが救出した王女。魔王を討伐した後、ウォレスと婚約を前提に、顔を見合わせた姫君。なるほど、あの顔に十一年ほどの歳月――それに脂肪――を詰め込んだならこうなるか。残酷にも。
ウォレスは口を開けていた。何を言えばいいか分からなかったが、とにかく口は動いていた。
「ああ、やあ、久しぶりで。姫……や、殿下、か」
喋ることもなしに顔は笑みの形を作り、口は動き続けていた。
「お元気そうで、何より。地上はどうです、変わりはありませ――」
「あるからこうして来ておるのさ。私ほどの者が直々にな」
へし折るようにそう言って、王女はさらに言葉を続けた。
「我が望みの宝珠は、手に入ってはおらんようだが。進展はあるか」
「……進展ってほどのもんはありませんがね。しかしそもそも、龍の宝珠ってのは――」
――いったい何だ。どんな物だ、何のためにある、王宮は何を知ってる? 失われて何が困る。それを使えば、いったいどうなる。それにあんた、どうやってここまで一人で――
口にしようとした言葉の先をかじるように、王女は白い歯を剥いた。そして言う。
「思い違うな。汝らに命じたのは、あくまで王宮による決定。私自身の意思は別だ。……汝らに、あれへ触れて欲しくはない」
ウォレスは眉を寄せた。
「触れるな、と? どういうことです、妙な話ですな。王宮にしろ何にしろ、探せと言ったのはそっち――」
「騒ぐな」
言い放った後、眼鏡を指で押し上げて王女は続けた。
「いいか? 私はあれを、汝らには触れさせん。汝らの出る幕もなく、私が全て終わらせる。……汝らは私が護ってやる、それが私の復讐よ」
復讐。されるいわれなどはないが、彼女がそうするだろう覚えならある。
何しろ言われたことがある、『許しはせぬ』と。ウォレスが婚約について、核心を切り出そうとしたそのときに。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

田舎農家の俺、拾ったトカゲが『始祖竜』だった件〜女神がくれたスキル【絶対飼育】で育てたら、魔王がコスメ欲しさに竜王が胃薬借りに通い詰めだした
月神世一
ファンタジー
「くそっ、魔王はまたトカゲの抜け殻を美容液にしようとしてるし、女神は酒のつまみばかり要求してくる! 俺はただ静かに農業がしたいだけなのに!」
ブラック企業で過労死した日本人、カイト。
彼の願いはただ一つ、「誰にも邪魔されない静かな場所で農業をすること」。
女神ルチアナからチートスキル【絶対飼育】を貰い、異世界マンルシア大陸の辺境で念願の農場を開いたカイトだったが、ある日、庭から虹色の卵を発掘してしまう。
孵化したのは、可愛らしいトカゲ……ではなく、神話の時代に世界を滅亡させた『始祖竜』の幼体だった!
しかし、カイトはスキル【絶対飼育】のおかげで、その破壊神を「ポチ」と名付けたペットとして完璧に飼い慣らしてしまう。
ポチのくしゃみ一発で、敵の軍勢は老衰で塵に!?
ポチの抜け殻は、魔王が喉から手が出るほど欲しがる究極の美容成分に!?
世界を滅ぼすほどの力を持つポチと、その魔素を浴びて育った規格外の農作物を求め、理知的で美人の魔王、疲労困憊の竜王、いい加減な女神が次々にカイトの家に押しかけてくる!
「世界の管理者」すら手が出せない最強の農場主、カイト。
これは、世界の運命と、美味しい野菜と、ペットの散歩に追われる、史上最も騒がしいスローライフ物語である!


アラフォーおっさんの週末ダンジョン探検記
ぽっちゃりおっさん
ファンタジー
ある日、全世界の至る所にダンジョンと呼ばれる異空間が出現した。
そこには人外異形の生命体【魔物】が存在していた。
【魔物】を倒すと魔石を落とす。
魔石には膨大なエネルギーが秘められており、第五次産業革命が起こるほどの衝撃であった。
世は埋蔵金ならぬ、魔石を求めて日々各地のダンジョンを開発していった。


裏切られ続けた負け犬。25年前に戻ったので人生をやり直す。当然、裏切られた礼はするけどね
竹井ゴールド
ファンタジー
冒険者ギルドの雑用として働く隻腕義足の中年、カーターは裏切られ続ける人生を送っていた。
元々は食堂の息子という人並みの平民だったが、
王族の継承争いに巻き込まれてアドの街の毒茸流布騒動でコックの父親が毒茸の味見で死に。
代わって雇った料理人が裏切って金を持ち逃げ。
父親の親友が融資を持ち掛けるも平然と裏切って借金の返済の為に母親と妹を娼館へと売り。
カーターが冒険者として金を稼ぐも、後輩がカーターの幼馴染に横恋慕してスタンピードの最中に裏切ってカーターは片腕と片足を損失。カーターを持ち上げていたギルマスも裏切り、幼馴染も去って後輩とくっつく。
その後は負け犬人生で冒険者ギルドの雑用として細々と暮らしていたのだが。
ある日、人ならざる存在が話しかけてきた。
「この世界は滅びに進んでいる。是正しなければならない。手を貸すように」
そして気付けは25年前の15歳にカーターは戻っており、二回目の人生をやり直すのだった。
もちろん、裏切ってくれた連中への返礼と共に。
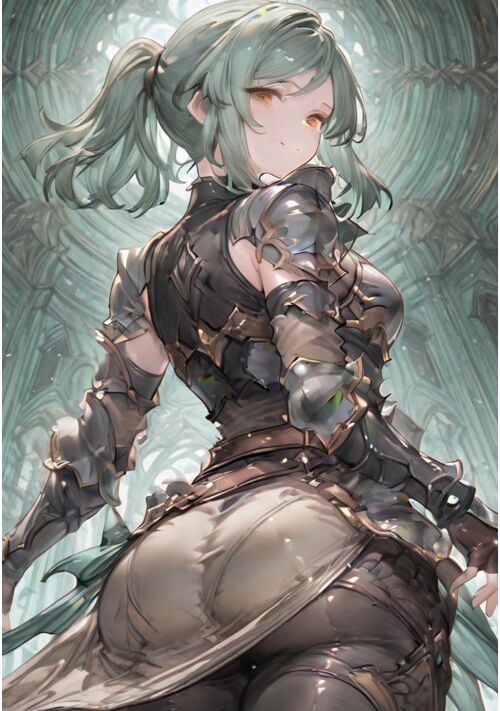
【完結】うだつが上がらない底辺冒険者だったオッサンは命を燃やして強くなる
邪代夜叉(ヤシロヤシャ)
ファンタジー
まだ遅くない。
オッサンにだって、未来がある。
底辺から這い上がる冒険譚?!
辺鄙の小さな村に生まれた少年トーマは、幼い頃にゴブリン退治で村に訪れていた冒険者に憧れ、いつか自らも偉大な冒険者となることを誓い、十五歳で村を飛び出した。
しかし現実は厳しかった。
十数年の時は流れてオッサンとなり、その間、大きな成果を残せず“とんまのトーマ”と不名誉なあだ名を陰で囁かれ、やがて採取や配達といった雑用依頼ばかりこなす、うだつの上がらない底辺冒険者生活を続けていた。
そんなある日、荷車の護衛の依頼を受けたトーマは――
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















