13 / 45
second contact
疑心
しおりを挟む
「気をつけたほうがいいんじゃないかなあ?」
カウンターに置いたホットミルクを手に取るとふぅっ……と息を吐きつけながら私を見て、河合千沙子は言った。
彼女の吐いた息が流れて、バニラビーンズの甘い香りが鼻先を駆け抜ける。
中学、高校時代の友人である千沙子はその香りを吸い込むように肩を小さくすぼめて嗅いでから口をつけてから、「ホッとするわあ」と静かにカップを置いた。
カウンターに肘をついて、小首を傾げるように手に顎を乗せた。
「そうかなあ?」
「まあ、断言はできないんだけどね」
そう言って困ったように彼女は笑う。
「新しい出会いかもしれないけど」
彼女の栗色の大きな二重の目を見つめ返して、私は微苦笑する。
育児の息抜きと称して千沙子はときどき喫茶店にやってきていた。
長い付き合いだからわかる。
彼女が喫茶店に来るのは私を気遣ってのことである。
そして彼女ができるだけ私の過去に触れないようにしていることも、彼女の家庭事情をあまり話さないことも、痛いほどよくわかっていた。
しあわせな家庭を築いている彼女の生活を聞けば、きっと私はひどく嫉妬するに違いない。
過去の話になればなったで、私の傷をえぐることになる――だから彼女は今の私のことしか話をしない。
『面白いことあった?』とか『昨日のドラマ観た?』とか『たまには女同士、ゆっくり飲みに行こう』とか。
そう言った話をするためだけに彼女はここに現れる。
そんな彼女に私は昨日の『佐々木海斗』のことを話したのだ。
「一目惚れされたってことも考えられなくもないんだけど、最近はいろいろ物騒だからさあ。その人のことで知ってることは他にないの?」
「なにも」
「名刺も置いて行かなかった?」
「うん」
千沙子の顔が曇っていく。
どう答えていいものか、考えあぐねているともとれる。
それでも私は誰かに『佐々木海斗』のことを話さずにはいられなかった。
心の水たまりにぽんっと小石が投げ込まれたあとのように、不安と期待が小さな波紋を作って広がっていく――そんな感覚を一人で抱え込むことが苦しくて。
だからと言って両親に話すのは少しばかり抵抗があった。
あんなことがあって戻ってきた娘が、またどこの馬の骨とも分からない男からまた会いに来ると言われたと聞かされたら――自分が親であったなら間違いなく不安になるだろう。
今度は娘がなにかよからぬことに巻き込まれるのではないのかと。
両親にしても優介の一件以来、ずいぶんピリピリと敏感になっている。これ以上心配させるようなことを言いだせなかったのだけれど。
「もしかしてなんだけど……その佐々木さん。あの『バラの花束の送り主』とかじゃないよね?」
千沙子が言った『バラの花束の送り主』というワードに、自然と体が硬くなった。
あのときの思い出がせせり上がるように脳裏に蘇る。
思わずエプロンの裾を握りしめる私に、千沙子は苦虫を噛み潰したような顔で「ごめん」と謝った。
そんな彼女に小さく頭を振って見せた。
「千沙子の言うとおり、可能性はゼロじゃないもの」
「考えたくはないけどね。優介さんのことがあるから、さ」
そこで一拍置くと私をじっと見て、肺の中の息を一気に鼻から押し出すようにして私に尋ねた。
「美緒は……佐々木さんのことが気になっているんだよね?」
じっと見つめる栗色の目が私の心を見透かすようだった。
そんな彼女の真っ直ぐな視線に私は固くなった頬の筋肉を緩め、こくりと静かにうなずく。
「似ている人……か」
「しぐさとか、一瞬見せた笑った顔とか……ちょっと似ていたかなあって」
私は佐々木海斗のことを思い出して伝える。
背格好は似ていない。
優介よりも佐々木海斗のほうがずっと大きかった。
肌の色も髪の色も違うのに私の頭ではなくて、心のずっと奥底で小さな鈴が鳴ったのだ。
チリンッ……と予感めいたものが。
「会いたい?」
千沙子の質問に私はかすかに口元に笑みを乗せた。
「それじゃあ、今度会うときは私も一緒のときで! その人が本当に優介さんに似ているかどうか。美緒の新しい恋の相手にふさわしいかどうか、私が見極める!」
「いつ来るかわからないのに? それに私、新しい恋は……」
「会いに来なかったらそれはそれ。でもね、1年は経ったの。新しい恋の準備をしても罰は当たらないと思うよ?」
そう言って千沙子はホットミルクの入ったカップを手に取った。
そのとき、カランコロンと音がして、買い物に出かけていた両親が帰ってきた。
「いらっしゃい」と一人きりのお客である千沙子に声を掛けると、大きな買い物袋を両手に提げた父は奥の厨房へと入って行く。
「千沙子ちゃん、さっき登美子さんが探していたわよお。うちの嫁はいつまで油売ってんだーって。英二君がママを探して泣きだしたから早く帰ってこいって伝言頼まれちゃったの」
そんな母の言葉に千沙子の顔が引きつった。
彼女はホットミルクを一気に飲み干すと、テーブルの上に小銭を置いて「ごちそうさま」と急いで立ち上がる。
店を出るその瞬間に千沙子は振り返って……
「さっきの話、忘れちゃダメだからね」
念を押して、彼女はそのまま風のように外へと飛び出していった。
その後ろ姿を見送ると母は「さっきの話って?」と尋ねたのだ。
ずいぶんと白髪が目立ってきた。
目じりのしわも増えたような気がする。
頬の肉が以前に比べて落ちた母の顔を見つめながら、答えるべきなのか、黙ったままでいるべきなのか一瞬悩んだ後で、私は「新しい恋の準備をしろって言われたの」と笑みを作ってなんでもない装いをした。
母はそんな私に「そうかもしれないわね」と答えた。
「もう1年だものね」
「まだ1年よ」
まだ1年。
優介を忘れるには早すぎる。
だって思い出は私の中にあまりにも生々しく残っている。
思い出が風化していないのに、どうやって新しい恋をしたらいいのかわからないのだ。
母は私の返事に悲しい笑みをこぼした。
「あなたのことを守ってくれる人に早く出会ってほしいとは思ってるの」
「なんで?」
「実は美緒には言ってなかったけど」
と、母は伏し目がちに切り出した。
その後に続いた話に私は体の震えがとまらなくなった。
時間が凍りつく。
カップを洗おうとひねった蛇口から勢いよく水が流れていた。
その音だけが外部からの音を跳ね除けるかのように膨らみ、感覚のぼやけた鼓膜を烈しく叩いていた。
「小さい頃、誘拐されるんじゃないかと胆を冷やしたことがあったの」
母は口を覆いながら、恐れと不安と戦うように吐露した。
私が三歳の頃の話だ。
フードを被った中肉中背の知らない男が家の前で遊ぶ私に話しかけていた。
私の手を両手で握りしめ、私に伝えたその一言に母は死ぬほど怖くなったのだと、私は初めて聞かされた。
『なにを言われたの?』と問う母に、幼い私が伝えた男の言葉は『いつかまた会えるよ』というものだった。
その一言を残して男は去っていった。
まるで家から出てきた母から顔を隠して逃げるように。
そして二度と現れることはなかった――怯えるようにそう吐き出した母に私は返す言葉もなかった。
またそれが実際に自分の身に起きていたことだと受け止めることもできなくて……ただ他人事のように母の話を聞くことしかできなかった。
カウンターに置いたホットミルクを手に取るとふぅっ……と息を吐きつけながら私を見て、河合千沙子は言った。
彼女の吐いた息が流れて、バニラビーンズの甘い香りが鼻先を駆け抜ける。
中学、高校時代の友人である千沙子はその香りを吸い込むように肩を小さくすぼめて嗅いでから口をつけてから、「ホッとするわあ」と静かにカップを置いた。
カウンターに肘をついて、小首を傾げるように手に顎を乗せた。
「そうかなあ?」
「まあ、断言はできないんだけどね」
そう言って困ったように彼女は笑う。
「新しい出会いかもしれないけど」
彼女の栗色の大きな二重の目を見つめ返して、私は微苦笑する。
育児の息抜きと称して千沙子はときどき喫茶店にやってきていた。
長い付き合いだからわかる。
彼女が喫茶店に来るのは私を気遣ってのことである。
そして彼女ができるだけ私の過去に触れないようにしていることも、彼女の家庭事情をあまり話さないことも、痛いほどよくわかっていた。
しあわせな家庭を築いている彼女の生活を聞けば、きっと私はひどく嫉妬するに違いない。
過去の話になればなったで、私の傷をえぐることになる――だから彼女は今の私のことしか話をしない。
『面白いことあった?』とか『昨日のドラマ観た?』とか『たまには女同士、ゆっくり飲みに行こう』とか。
そう言った話をするためだけに彼女はここに現れる。
そんな彼女に私は昨日の『佐々木海斗』のことを話したのだ。
「一目惚れされたってことも考えられなくもないんだけど、最近はいろいろ物騒だからさあ。その人のことで知ってることは他にないの?」
「なにも」
「名刺も置いて行かなかった?」
「うん」
千沙子の顔が曇っていく。
どう答えていいものか、考えあぐねているともとれる。
それでも私は誰かに『佐々木海斗』のことを話さずにはいられなかった。
心の水たまりにぽんっと小石が投げ込まれたあとのように、不安と期待が小さな波紋を作って広がっていく――そんな感覚を一人で抱え込むことが苦しくて。
だからと言って両親に話すのは少しばかり抵抗があった。
あんなことがあって戻ってきた娘が、またどこの馬の骨とも分からない男からまた会いに来ると言われたと聞かされたら――自分が親であったなら間違いなく不安になるだろう。
今度は娘がなにかよからぬことに巻き込まれるのではないのかと。
両親にしても優介の一件以来、ずいぶんピリピリと敏感になっている。これ以上心配させるようなことを言いだせなかったのだけれど。
「もしかしてなんだけど……その佐々木さん。あの『バラの花束の送り主』とかじゃないよね?」
千沙子が言った『バラの花束の送り主』というワードに、自然と体が硬くなった。
あのときの思い出がせせり上がるように脳裏に蘇る。
思わずエプロンの裾を握りしめる私に、千沙子は苦虫を噛み潰したような顔で「ごめん」と謝った。
そんな彼女に小さく頭を振って見せた。
「千沙子の言うとおり、可能性はゼロじゃないもの」
「考えたくはないけどね。優介さんのことがあるから、さ」
そこで一拍置くと私をじっと見て、肺の中の息を一気に鼻から押し出すようにして私に尋ねた。
「美緒は……佐々木さんのことが気になっているんだよね?」
じっと見つめる栗色の目が私の心を見透かすようだった。
そんな彼女の真っ直ぐな視線に私は固くなった頬の筋肉を緩め、こくりと静かにうなずく。
「似ている人……か」
「しぐさとか、一瞬見せた笑った顔とか……ちょっと似ていたかなあって」
私は佐々木海斗のことを思い出して伝える。
背格好は似ていない。
優介よりも佐々木海斗のほうがずっと大きかった。
肌の色も髪の色も違うのに私の頭ではなくて、心のずっと奥底で小さな鈴が鳴ったのだ。
チリンッ……と予感めいたものが。
「会いたい?」
千沙子の質問に私はかすかに口元に笑みを乗せた。
「それじゃあ、今度会うときは私も一緒のときで! その人が本当に優介さんに似ているかどうか。美緒の新しい恋の相手にふさわしいかどうか、私が見極める!」
「いつ来るかわからないのに? それに私、新しい恋は……」
「会いに来なかったらそれはそれ。でもね、1年は経ったの。新しい恋の準備をしても罰は当たらないと思うよ?」
そう言って千沙子はホットミルクの入ったカップを手に取った。
そのとき、カランコロンと音がして、買い物に出かけていた両親が帰ってきた。
「いらっしゃい」と一人きりのお客である千沙子に声を掛けると、大きな買い物袋を両手に提げた父は奥の厨房へと入って行く。
「千沙子ちゃん、さっき登美子さんが探していたわよお。うちの嫁はいつまで油売ってんだーって。英二君がママを探して泣きだしたから早く帰ってこいって伝言頼まれちゃったの」
そんな母の言葉に千沙子の顔が引きつった。
彼女はホットミルクを一気に飲み干すと、テーブルの上に小銭を置いて「ごちそうさま」と急いで立ち上がる。
店を出るその瞬間に千沙子は振り返って……
「さっきの話、忘れちゃダメだからね」
念を押して、彼女はそのまま風のように外へと飛び出していった。
その後ろ姿を見送ると母は「さっきの話って?」と尋ねたのだ。
ずいぶんと白髪が目立ってきた。
目じりのしわも増えたような気がする。
頬の肉が以前に比べて落ちた母の顔を見つめながら、答えるべきなのか、黙ったままでいるべきなのか一瞬悩んだ後で、私は「新しい恋の準備をしろって言われたの」と笑みを作ってなんでもない装いをした。
母はそんな私に「そうかもしれないわね」と答えた。
「もう1年だものね」
「まだ1年よ」
まだ1年。
優介を忘れるには早すぎる。
だって思い出は私の中にあまりにも生々しく残っている。
思い出が風化していないのに、どうやって新しい恋をしたらいいのかわからないのだ。
母は私の返事に悲しい笑みをこぼした。
「あなたのことを守ってくれる人に早く出会ってほしいとは思ってるの」
「なんで?」
「実は美緒には言ってなかったけど」
と、母は伏し目がちに切り出した。
その後に続いた話に私は体の震えがとまらなくなった。
時間が凍りつく。
カップを洗おうとひねった蛇口から勢いよく水が流れていた。
その音だけが外部からの音を跳ね除けるかのように膨らみ、感覚のぼやけた鼓膜を烈しく叩いていた。
「小さい頃、誘拐されるんじゃないかと胆を冷やしたことがあったの」
母は口を覆いながら、恐れと不安と戦うように吐露した。
私が三歳の頃の話だ。
フードを被った中肉中背の知らない男が家の前で遊ぶ私に話しかけていた。
私の手を両手で握りしめ、私に伝えたその一言に母は死ぬほど怖くなったのだと、私は初めて聞かされた。
『なにを言われたの?』と問う母に、幼い私が伝えた男の言葉は『いつかまた会えるよ』というものだった。
その一言を残して男は去っていった。
まるで家から出てきた母から顔を隠して逃げるように。
そして二度と現れることはなかった――怯えるようにそう吐き出した母に私は返す言葉もなかった。
またそれが実際に自分の身に起きていたことだと受け止めることもできなくて……ただ他人事のように母の話を聞くことしかできなかった。
0
あなたにおすすめの小説

君を探す物語~転生したお姫様は王子様に気づかない
あきた
恋愛
昔からずっと探していた王子と姫のロマンス物語。
タイトルが思い出せずにどの本だったのかを毎日探し続ける朔(さく)。
図書委員を押し付けられた朔(さく)は同じく図書委員で学校一のモテ男、橘(たちばな)と過ごすことになる。
実は朔の探していた『お話』は、朔の前世で、現世に転生していたのだった。
同じく転生したのに、朔に全く気付いて貰えない、元王子の橘は困惑する。

同窓会~あの日の恋をもう一度~
小田恒子
恋愛
短大を卒業して地元の税理事務所に勤める25歳の西田結衣。
結衣はある事がきっかけで、中学時代の友人と連絡を絶っていた。
そんなある日、唯一連絡を取り合っている由美から、卒業十周年記念の同窓会があると連絡があり、全員強制参加を言い渡される。
指定された日に会場である中学校へ行くと…。
*作品途中で過去の回想が入りますので現在→中学時代等、時系列がバラバラになります。
今回の作品には章にいつの話かは記載しておりません。
ご理解の程宜しくお願いします。
表紙絵は以前、まるぶち銀河様に描いて頂いたものです。
(エブリスタで以前公開していた作品の表紙絵として頂いた物を使わせて頂いております)
こちらの絵の著作権はまるぶち銀河様にある為、無断転載は固くお断りします。
*この作品は大山あかね名義で公開していた物です。
連載開始日 2019/10/15
本編完結日 2019/10/31
番外編完結日 2019/11/04
ベリーズカフェでも同時公開
その後 公開日2020/06/04
完結日 2020/06/15
*ベリーズカフェはR18仕様ではありません。
作品の無断転載はご遠慮ください。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

愛してやまないこの想いを
さとう涼
恋愛
ある日、恋人でない男性から結婚を申し込まれてしまった。
「覚悟して。断られても何度でもプロポーズするよ」
その日から、わたしの毎日は甘くとろけていく。
ライティングデザイン会社勤務の平凡なOLと建設会社勤務のやり手の設計課長のあまあまなストーリーです。

【完結】あなたに恋愛指南します
夏目若葉
恋愛
大手商社の受付で働く舞花(まいか)は、訪問客として週に一度必ず現れる和久井(わくい)という男性に恋心を寄せるようになった。
お近づきになりたいが、どうすればいいかわからない。
少しずつ距離が縮まっていくふたり。しかし和久井には忘れられない女性がいるような気配があって、それも気になり……
純真女子の片想いストーリー
一途で素直な女 × 本気の恋を知らない男
ムズキュンです♪
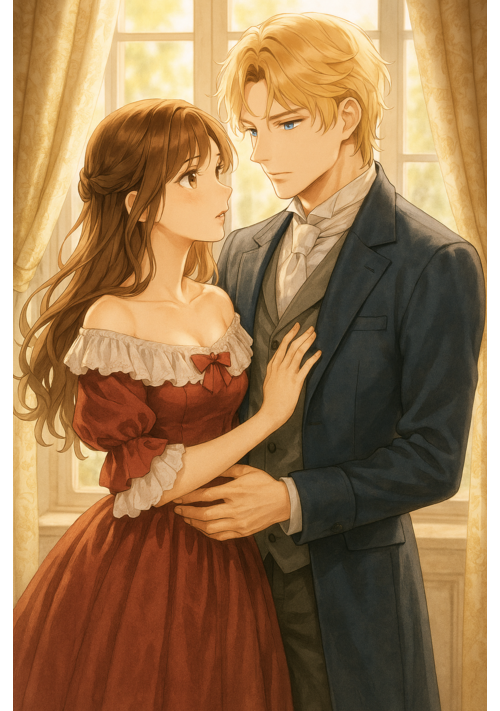
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。

一億円の花嫁
藤谷 郁
恋愛
奈々子は家族の中の落ちこぼれ。
父親がすすめる縁談を断り切れず、望まぬ結婚をすることになった。
もうすぐ自由が無くなる。せめて最後に、思いきり贅沢な時間を過ごそう。
「きっと、素晴らしい旅になる」
ずっと憧れていた高級ホテルに到着し、わくわくする奈々子だが……
幸か不幸か!?
思いもよらぬ、運命の出会いが待っていた。
※エブリスタさまにも掲載

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















