18 / 45
second contact
冷たい指先
しおりを挟む
2014年3月3日。
厳しい冬の寒さが和らいで丸みを帯びた風が吹き始めようとしていたこの日。
誕生日を一緒に祝うという約束を果たすために、海斗が店にやってきた。
今日の約束を前もって両親に話しておいた私は、仕事着から白いニットのワンピースに薄桃色のカーディガンという姿に着替えた。
カウンターに腰掛けて彼がやってくるのを待っていると、店の呼び鈴が鳴った。
伺うように首をのぞかせて入ってきた海斗が、カウンターに座る私を見るなり足をとめた。
私が笑顔を向けると、彼は顔を真っ赤にさせた。
コリコリと頭を軽く掻く。
「びっくりしました。その……別人かと思った」
真っ直ぐ私には向き合わずに、海斗は天井に目を泳がせた。
「それ、ほめ言葉ですか?」
口を尖らせてからかうように尋ねると、彼はハッとしたみたいに泳がせていた目をこちらに向けた。
すぐさま大きく頭を下げる。
「すみません! 失礼なこと言いました!」
直角以上の頭の下げ方に尖らせた口からせっつかれるように笑い声が飛び出てしまった。
「頭下げすぎですよ」
そう言うと、海斗はゆっくりと顔を上げた。
「いやあ」とまた頭をゴリゴリと掻いてみせた。
「その、いつも以上に綺麗で。本当にびっくりしちゃったんです。だから、その……」
そこで海斗は言葉を詰まらせた。
普段は大きな声なのに驚くほど小さな声で照れたように
「ドキドキしています」
と、こぼしたのだ。
その顔は店に入って来るときよりもずっと赤みを増して、熟れたリンゴのようだった。
照れくさそうに天井に視線を走らせながら、落ち着きなく頭を掻く姿に私も妙に照れくさくなった。
両手で口元を覆って小さく笑う。
「行きましょう」
「はい」
奥から出てきた両親に「行ってくるね」と告げる。
そんな私の隣で小さく海斗が会釈をした。
二人連れだって外に出ると、彼は助手席の扉を開けた。
「どうぞ」
「あっ、はい」
彼の姿に、私はまた優介を見た。
車のドアを開けるくらい、男性なら普通にすることなのだろう。
だけど心中は複雑だった。
初デートに遅れて迎えに来た優介が、車に乗り込もうと扉に手を掛けるのを盗むように手早く助手席の扉を開けたことを思い出す。
『どうぞ』
緊張したように背筋を伸ばしていた優介。
あのときの彼は私の顔を見ないようにしていた。
それに比べれば、海斗はとても優雅だった。
どちらかと言えば手慣れているように見えた。
一緒のようでほんの少し違う。
その違いに『別人』であることを感じるのに、どうしても『別人』と切り離せない自分がいた。
ちくりと小さなとげが胸に刺さっていく。
「瀬崎さん?」
ぼんやりと立ち尽くす私を、海斗が心配そうに眉を寄せて見ていた。
私は小さく頭を振って、助手席に腰を下ろす。
座席にヒーターがついているらしく、座るとお尻がじんわりと温かかった。
私の足が完全に中に入ったのを見届けた後で、海斗は静かに助手席の扉を閉めた。
それからすぐに運転席に回り込む。
かけっぱなしのエンジン音だけが、車内に静かに響いていた。
「少し遠いですけど、本当に大丈夫ですか?」
「門限は十時です」
「はい。それまでにはきっちり送り届けます」
「もうっ。冗談ですって。門限なんて三十路近くの女にありませんよ?」
「えっと……」
「佐々木さんの真似して自虐ネタを言ってみたんですけど、面白くなかったですかね?」
「いえ、そうじゃなくて」
緊張をほぐそうと思って冗談を言ったつもりだったのだが、海斗の顔はずいぶん固くなっていた。
予想に反した厳しい顔に、私は押し黙る。
するとこわばった顔を私のほうに向けた彼は小さく息を吐き出した。
「ダメですよ」
「え?」
「男はバカな生き物なので『その気』になっちゃいますよ、門限がないなんてこと言ったら。だから、これからはそういうことは絶対に言っちゃダメです」
そこで一拍置き、彼は満面の笑顔を私に向けた。
「俺の前以外では」
海斗の笑顔があまりにもまぶしくて、私は返す言葉を見つけられないでいた。
ぽかんと口を開ける。
海斗はくしゃっとさらに表情を緩めて「冗談ですよ」と大きく笑った。
「瀬崎さんの肩にすごく力が入っているみたいだったから、ちょっとびっくりさせてみました」
「ええっ! すっごくびっくりしたんですよお! もう、佐々木さんったらいじわるなんだから!」
ぷうっと頬をふくらませる私に海斗は「ごめんなさい」とまた笑ってからゆっくりと車を走らせる。
海斗が案内してくれたイタリアン料理店は、彼がプロデュースした店だった。
異国情緒あふれる白い壁に大きな窓。青い屋根。
外には壁と同じ白いパラソルを掲げたテラス席もあった。入り口のチャコール色の扉を潜り抜ける。
「ヨーロッパに少しモロッコ風のテイストを加えたんです」
店内を見回しながら海斗がそう説明をした。
彼の説明どおり、白い壁に赤やビビットピンクを取り入れたお皿が飾り付けられている。
正面のカウンターに備え付けられたガラスケースからいろいろな種類のワインボトルが透けて見えた。
仕切りのない長テーブルがいくつも並んだその奥に案内された。
白いソファークッションの背もたれが仕切りになっており、天井からはステンドグラスで作られたモロッコ風の照明が釣りさがっていた。
「カップルシートです。半個室。雰囲気あるでしょう?」
海斗はそう言いながらコートを脱ぐと、私に手を差しだす。
「え?」
「コート、掛けますよ」
「でも、自分でできますから」
「今日は瀬崎さんが主役なんです。ほら、貸して」
彼にコートを手渡す。
海斗は脱いだ私のコートを用意されたハンガーにくぐらせると壁にかけた。
「どうぞ」と私を先に座らせてから、彼も続くように腰を下ろした。
「ノンアルコールでもでいいですか? それとも飲みます?」
「佐々木さん、運転ですものね。一緒に飲めないなら、私もやめておきます」
そう答える私を海斗は笑みを潜めてじっと見つめた。
「わ、私の顔になにかついていますか?」
慌てる私を、海斗はじぃっと目を凝らすようにして見つめ続ける。
「あの、佐々木さん?」
「もしかしてさっきの言葉、気にしていませんか?」
「さっきの言葉?」
「その気になるってやつです」
ニッコリと彼は笑う。
いたずら好きな少年っぽい笑顔を私に向ける海斗を穴が開くほど見つめ返した。
「送り狼にはなりませんよ?」
「そんなふうに佐々木さんのこと思っていませんってば!」
「え? ああ、そうか。それ、ちょっと残念」
「もう、佐々木さんったら。からかわないでください」
唇をとがらせて責める私に、海斗は柔らかな笑みを向けた。
その笑みに踊るように胸が弾んで、思わず彼の顔から目を背けた。
結局、お酒は飲まなかった。
『誕生日おめでとう』とシャンパングラスに注がれたノンアルコールドリンクを傾けると、ぶつかり合ったグラスは透き通る高い和音を奏でた。
しばらくして、海斗が選んだ料理が運ばれてくる。
「これ、すごく美味しい」
白身魚とエビ、ムール貝やアサリ、トマトが鍋の中でひしめき合った料理を口に入れる。にんにくとオリーブオイルの香りが鼻から抜けていった。
優しい味のスープに頬を落とすと、海斗は「アクアパッツァです」と続けた。
「南イタリアの郷土料理なんですが、イタリア語で『水で薄めたワイン』という意味なんですよ」
「魚介の味が濃縮していて、出汁がしっかり出ていて本当においしい」
私がほおっと感嘆の息をもらすと、海斗は嬉しそうに目を細めた。
「このレシピも、俺とここのシェフで考え抜いたんですよ」
「これを佐々木さんとシェフで、ですか? なんか完璧な味って感じします。私じゃ、絶対に作れないもの!」
「ああ。俺、神の舌を持ってるみたいなんです」
「それもすごい!」
「じゃあ、今度瀬崎さんの料理もプロデュースしちゃいましょうかね?」
「それ、ぜひお願いしたいです!」
おいしい料理。
おしゃれな空間。
海斗の明るく楽しい話題。
そのすべてが私の心の中に広がっていた不安を払っていた。
緊張はすでに緩み、どんどん話がはずんだ。
料理の話もお酒の話もした。
仕事の話だけではなくて、好きなテレビや好きな本、音楽まで。
この人となら話題が尽きない――そう感じた。
料理を食べ終わって、綺麗に片付いたときだった。
ふと会話がやんだ。
テーブルにホールケーキが運ばれてくる。
白いデコレーションケーキには花火が刺さり、小さな火花が散っていた。
苺に囲まれたチョコプレートには『HAPPY BIRTHDAY MIO』の文字が並んでいて、それを見た瞬間に、私の胸がギュッと押しつぶれた。
優介と過ごした最後の誕生日。
その日に届けられたバラの花束が脳裏によみがえる。
添えられていたカードには、チョコプレートと同じ文字が並んでいた。
あの日の優介の声が私の耳にこだまする。
『絶対に君を守るから』
そう言った彼の声が――
でも、それは一瞬で掻き消えた。
海斗と店の従業員が揃って『HAPPY BIRTHDAY TO YOU』と歌い始めたからだ。
店に来ていた他のお客さんも一緒に歌い出したから、私のつぶれた胸が再びふくらみを取り戻した。
歌が終わると、まぶしいほどの満面の笑みを浮かべた海斗の顔に、また優介の影が重なった。
「『おめでとう』」
海斗の台詞が優介の声で再生される。
震えたのは私の唇だったのか、それとも心だったのかはわからない。
きっと、どちらもだったのだろう。
「ありがとう」
目頭が熱くなり、うっかり私はポロリと零してしまったのだ。
嬉しいのに悲しくて、寂しいのに温かくて。
私はどちらの感情からのものとはわからない涙を零していた。
「瀬崎さん……」
海斗の長い指先が伸びてきて、私の零れる涙を拾いあげた。
「俺と……これからも一緒にいませんか?『君を泣かせないようにずっと守るから』」
そう言った彼のひやりとした指先に――触れたものを一瞬で凍らせてしまう冷たい指先に、私は息をするのも忘れて彼を見つめる。
「『美緒。俺がずっと守るから』」
薄茶色をした彼の瞳の中に弾ける火花が映り込む。
ケーキの上の花火が燃えて徐々にその勢いを小さくしていく中で、彼はたしかにハッキリと、そう私に告げたのだった。
厳しい冬の寒さが和らいで丸みを帯びた風が吹き始めようとしていたこの日。
誕生日を一緒に祝うという約束を果たすために、海斗が店にやってきた。
今日の約束を前もって両親に話しておいた私は、仕事着から白いニットのワンピースに薄桃色のカーディガンという姿に着替えた。
カウンターに腰掛けて彼がやってくるのを待っていると、店の呼び鈴が鳴った。
伺うように首をのぞかせて入ってきた海斗が、カウンターに座る私を見るなり足をとめた。
私が笑顔を向けると、彼は顔を真っ赤にさせた。
コリコリと頭を軽く掻く。
「びっくりしました。その……別人かと思った」
真っ直ぐ私には向き合わずに、海斗は天井に目を泳がせた。
「それ、ほめ言葉ですか?」
口を尖らせてからかうように尋ねると、彼はハッとしたみたいに泳がせていた目をこちらに向けた。
すぐさま大きく頭を下げる。
「すみません! 失礼なこと言いました!」
直角以上の頭の下げ方に尖らせた口からせっつかれるように笑い声が飛び出てしまった。
「頭下げすぎですよ」
そう言うと、海斗はゆっくりと顔を上げた。
「いやあ」とまた頭をゴリゴリと掻いてみせた。
「その、いつも以上に綺麗で。本当にびっくりしちゃったんです。だから、その……」
そこで海斗は言葉を詰まらせた。
普段は大きな声なのに驚くほど小さな声で照れたように
「ドキドキしています」
と、こぼしたのだ。
その顔は店に入って来るときよりもずっと赤みを増して、熟れたリンゴのようだった。
照れくさそうに天井に視線を走らせながら、落ち着きなく頭を掻く姿に私も妙に照れくさくなった。
両手で口元を覆って小さく笑う。
「行きましょう」
「はい」
奥から出てきた両親に「行ってくるね」と告げる。
そんな私の隣で小さく海斗が会釈をした。
二人連れだって外に出ると、彼は助手席の扉を開けた。
「どうぞ」
「あっ、はい」
彼の姿に、私はまた優介を見た。
車のドアを開けるくらい、男性なら普通にすることなのだろう。
だけど心中は複雑だった。
初デートに遅れて迎えに来た優介が、車に乗り込もうと扉に手を掛けるのを盗むように手早く助手席の扉を開けたことを思い出す。
『どうぞ』
緊張したように背筋を伸ばしていた優介。
あのときの彼は私の顔を見ないようにしていた。
それに比べれば、海斗はとても優雅だった。
どちらかと言えば手慣れているように見えた。
一緒のようでほんの少し違う。
その違いに『別人』であることを感じるのに、どうしても『別人』と切り離せない自分がいた。
ちくりと小さなとげが胸に刺さっていく。
「瀬崎さん?」
ぼんやりと立ち尽くす私を、海斗が心配そうに眉を寄せて見ていた。
私は小さく頭を振って、助手席に腰を下ろす。
座席にヒーターがついているらしく、座るとお尻がじんわりと温かかった。
私の足が完全に中に入ったのを見届けた後で、海斗は静かに助手席の扉を閉めた。
それからすぐに運転席に回り込む。
かけっぱなしのエンジン音だけが、車内に静かに響いていた。
「少し遠いですけど、本当に大丈夫ですか?」
「門限は十時です」
「はい。それまでにはきっちり送り届けます」
「もうっ。冗談ですって。門限なんて三十路近くの女にありませんよ?」
「えっと……」
「佐々木さんの真似して自虐ネタを言ってみたんですけど、面白くなかったですかね?」
「いえ、そうじゃなくて」
緊張をほぐそうと思って冗談を言ったつもりだったのだが、海斗の顔はずいぶん固くなっていた。
予想に反した厳しい顔に、私は押し黙る。
するとこわばった顔を私のほうに向けた彼は小さく息を吐き出した。
「ダメですよ」
「え?」
「男はバカな生き物なので『その気』になっちゃいますよ、門限がないなんてこと言ったら。だから、これからはそういうことは絶対に言っちゃダメです」
そこで一拍置き、彼は満面の笑顔を私に向けた。
「俺の前以外では」
海斗の笑顔があまりにもまぶしくて、私は返す言葉を見つけられないでいた。
ぽかんと口を開ける。
海斗はくしゃっとさらに表情を緩めて「冗談ですよ」と大きく笑った。
「瀬崎さんの肩にすごく力が入っているみたいだったから、ちょっとびっくりさせてみました」
「ええっ! すっごくびっくりしたんですよお! もう、佐々木さんったらいじわるなんだから!」
ぷうっと頬をふくらませる私に海斗は「ごめんなさい」とまた笑ってからゆっくりと車を走らせる。
海斗が案内してくれたイタリアン料理店は、彼がプロデュースした店だった。
異国情緒あふれる白い壁に大きな窓。青い屋根。
外には壁と同じ白いパラソルを掲げたテラス席もあった。入り口のチャコール色の扉を潜り抜ける。
「ヨーロッパに少しモロッコ風のテイストを加えたんです」
店内を見回しながら海斗がそう説明をした。
彼の説明どおり、白い壁に赤やビビットピンクを取り入れたお皿が飾り付けられている。
正面のカウンターに備え付けられたガラスケースからいろいろな種類のワインボトルが透けて見えた。
仕切りのない長テーブルがいくつも並んだその奥に案内された。
白いソファークッションの背もたれが仕切りになっており、天井からはステンドグラスで作られたモロッコ風の照明が釣りさがっていた。
「カップルシートです。半個室。雰囲気あるでしょう?」
海斗はそう言いながらコートを脱ぐと、私に手を差しだす。
「え?」
「コート、掛けますよ」
「でも、自分でできますから」
「今日は瀬崎さんが主役なんです。ほら、貸して」
彼にコートを手渡す。
海斗は脱いだ私のコートを用意されたハンガーにくぐらせると壁にかけた。
「どうぞ」と私を先に座らせてから、彼も続くように腰を下ろした。
「ノンアルコールでもでいいですか? それとも飲みます?」
「佐々木さん、運転ですものね。一緒に飲めないなら、私もやめておきます」
そう答える私を海斗は笑みを潜めてじっと見つめた。
「わ、私の顔になにかついていますか?」
慌てる私を、海斗はじぃっと目を凝らすようにして見つめ続ける。
「あの、佐々木さん?」
「もしかしてさっきの言葉、気にしていませんか?」
「さっきの言葉?」
「その気になるってやつです」
ニッコリと彼は笑う。
いたずら好きな少年っぽい笑顔を私に向ける海斗を穴が開くほど見つめ返した。
「送り狼にはなりませんよ?」
「そんなふうに佐々木さんのこと思っていませんってば!」
「え? ああ、そうか。それ、ちょっと残念」
「もう、佐々木さんったら。からかわないでください」
唇をとがらせて責める私に、海斗は柔らかな笑みを向けた。
その笑みに踊るように胸が弾んで、思わず彼の顔から目を背けた。
結局、お酒は飲まなかった。
『誕生日おめでとう』とシャンパングラスに注がれたノンアルコールドリンクを傾けると、ぶつかり合ったグラスは透き通る高い和音を奏でた。
しばらくして、海斗が選んだ料理が運ばれてくる。
「これ、すごく美味しい」
白身魚とエビ、ムール貝やアサリ、トマトが鍋の中でひしめき合った料理を口に入れる。にんにくとオリーブオイルの香りが鼻から抜けていった。
優しい味のスープに頬を落とすと、海斗は「アクアパッツァです」と続けた。
「南イタリアの郷土料理なんですが、イタリア語で『水で薄めたワイン』という意味なんですよ」
「魚介の味が濃縮していて、出汁がしっかり出ていて本当においしい」
私がほおっと感嘆の息をもらすと、海斗は嬉しそうに目を細めた。
「このレシピも、俺とここのシェフで考え抜いたんですよ」
「これを佐々木さんとシェフで、ですか? なんか完璧な味って感じします。私じゃ、絶対に作れないもの!」
「ああ。俺、神の舌を持ってるみたいなんです」
「それもすごい!」
「じゃあ、今度瀬崎さんの料理もプロデュースしちゃいましょうかね?」
「それ、ぜひお願いしたいです!」
おいしい料理。
おしゃれな空間。
海斗の明るく楽しい話題。
そのすべてが私の心の中に広がっていた不安を払っていた。
緊張はすでに緩み、どんどん話がはずんだ。
料理の話もお酒の話もした。
仕事の話だけではなくて、好きなテレビや好きな本、音楽まで。
この人となら話題が尽きない――そう感じた。
料理を食べ終わって、綺麗に片付いたときだった。
ふと会話がやんだ。
テーブルにホールケーキが運ばれてくる。
白いデコレーションケーキには花火が刺さり、小さな火花が散っていた。
苺に囲まれたチョコプレートには『HAPPY BIRTHDAY MIO』の文字が並んでいて、それを見た瞬間に、私の胸がギュッと押しつぶれた。
優介と過ごした最後の誕生日。
その日に届けられたバラの花束が脳裏によみがえる。
添えられていたカードには、チョコプレートと同じ文字が並んでいた。
あの日の優介の声が私の耳にこだまする。
『絶対に君を守るから』
そう言った彼の声が――
でも、それは一瞬で掻き消えた。
海斗と店の従業員が揃って『HAPPY BIRTHDAY TO YOU』と歌い始めたからだ。
店に来ていた他のお客さんも一緒に歌い出したから、私のつぶれた胸が再びふくらみを取り戻した。
歌が終わると、まぶしいほどの満面の笑みを浮かべた海斗の顔に、また優介の影が重なった。
「『おめでとう』」
海斗の台詞が優介の声で再生される。
震えたのは私の唇だったのか、それとも心だったのかはわからない。
きっと、どちらもだったのだろう。
「ありがとう」
目頭が熱くなり、うっかり私はポロリと零してしまったのだ。
嬉しいのに悲しくて、寂しいのに温かくて。
私はどちらの感情からのものとはわからない涙を零していた。
「瀬崎さん……」
海斗の長い指先が伸びてきて、私の零れる涙を拾いあげた。
「俺と……これからも一緒にいませんか?『君を泣かせないようにずっと守るから』」
そう言った彼のひやりとした指先に――触れたものを一瞬で凍らせてしまう冷たい指先に、私は息をするのも忘れて彼を見つめる。
「『美緒。俺がずっと守るから』」
薄茶色をした彼の瞳の中に弾ける火花が映り込む。
ケーキの上の花火が燃えて徐々にその勢いを小さくしていく中で、彼はたしかにハッキリと、そう私に告げたのだった。
0
あなたにおすすめの小説

君を探す物語~転生したお姫様は王子様に気づかない
あきた
恋愛
昔からずっと探していた王子と姫のロマンス物語。
タイトルが思い出せずにどの本だったのかを毎日探し続ける朔(さく)。
図書委員を押し付けられた朔(さく)は同じく図書委員で学校一のモテ男、橘(たちばな)と過ごすことになる。
実は朔の探していた『お話』は、朔の前世で、現世に転生していたのだった。
同じく転生したのに、朔に全く気付いて貰えない、元王子の橘は困惑する。

極上の彼女と最愛の彼 Vol.3
葉月 まい
恋愛
『極上の彼女と最愛の彼』第3弾
メンバーが結婚ラッシュの中、未だ独り身の吾郎
果たして彼にも幸せの女神は微笑むのか?
そして瞳子や大河、メンバー達のその後は?

メイウッド家の双子の姉妹
柴咲もも
恋愛
シャノンは双子の姉ヴァイオレットと共にこの春社交界にデビューした。美しい姉と違って地味で目立たないシャノンは結婚するつもりなどなかった。それなのに、ある夜、訪れた夜会で見知らぬ男にキスされてしまって…?
※19世紀英国風の世界が舞台のヒストリカル風ロマンス小説(のつもり)です。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

同窓会~あの日の恋をもう一度~
小田恒子
恋愛
短大を卒業して地元の税理事務所に勤める25歳の西田結衣。
結衣はある事がきっかけで、中学時代の友人と連絡を絶っていた。
そんなある日、唯一連絡を取り合っている由美から、卒業十周年記念の同窓会があると連絡があり、全員強制参加を言い渡される。
指定された日に会場である中学校へ行くと…。
*作品途中で過去の回想が入りますので現在→中学時代等、時系列がバラバラになります。
今回の作品には章にいつの話かは記載しておりません。
ご理解の程宜しくお願いします。
表紙絵は以前、まるぶち銀河様に描いて頂いたものです。
(エブリスタで以前公開していた作品の表紙絵として頂いた物を使わせて頂いております)
こちらの絵の著作権はまるぶち銀河様にある為、無断転載は固くお断りします。
*この作品は大山あかね名義で公開していた物です。
連載開始日 2019/10/15
本編完結日 2019/10/31
番外編完結日 2019/11/04
ベリーズカフェでも同時公開
その後 公開日2020/06/04
完結日 2020/06/15
*ベリーズカフェはR18仕様ではありません。
作品の無断転載はご遠慮ください。

短編【シークレットベビー】契約結婚の初夜の後でいきなり離縁されたのでお腹の子はひとりで立派に育てます 〜銀の仮面の侯爵と秘密の愛し子〜
美咲アリス
恋愛
レティシアは義母と妹からのいじめから逃げるために契約結婚をする。結婚相手は醜い傷跡を銀の仮面で隠した侯爵のクラウスだ。「どんなに恐ろしいお方かしら⋯⋯」震えながら初夜をむかえるがクラウスは想像以上に甘い初体験を与えてくれた。「私たち、うまくやっていけるかもしれないわ」小さな希望を持つレティシア。だけどなぜかいきなり離縁をされてしまって⋯⋯?
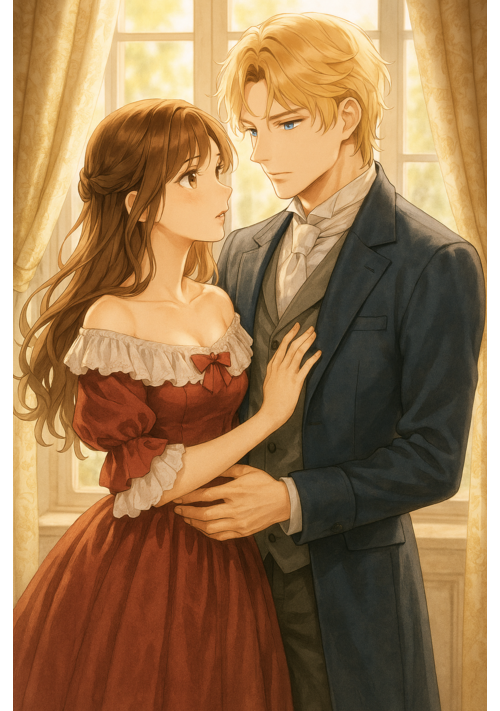
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。

愛してやまないこの想いを
さとう涼
恋愛
ある日、恋人でない男性から結婚を申し込まれてしまった。
「覚悟して。断られても何度でもプロポーズするよ」
その日から、わたしの毎日は甘くとろけていく。
ライティングデザイン会社勤務の平凡なOLと建設会社勤務のやり手の設計課長のあまあまなストーリーです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















