あなたにおすすめの小説

君を探す物語~転生したお姫様は王子様に気づかない
あきた
恋愛
昔からずっと探していた王子と姫のロマンス物語。
タイトルが思い出せずにどの本だったのかを毎日探し続ける朔(さく)。
図書委員を押し付けられた朔(さく)は同じく図書委員で学校一のモテ男、橘(たちばな)と過ごすことになる。
実は朔の探していた『お話』は、朔の前世で、現世に転生していたのだった。
同じく転生したのに、朔に全く気付いて貰えない、元王子の橘は困惑する。
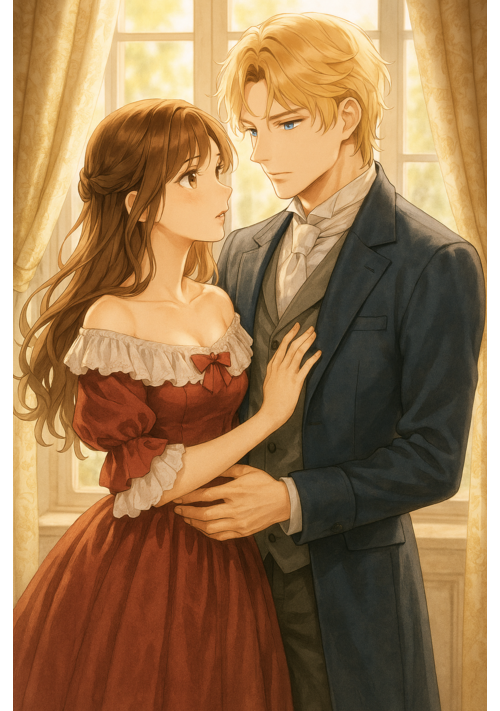
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

一億円の花嫁
藤谷 郁
恋愛
奈々子は家族の中の落ちこぼれ。
父親がすすめる縁談を断り切れず、望まぬ結婚をすることになった。
もうすぐ自由が無くなる。せめて最後に、思いきり贅沢な時間を過ごそう。
「きっと、素晴らしい旅になる」
ずっと憧れていた高級ホテルに到着し、わくわくする奈々子だが……
幸か不幸か!?
思いもよらぬ、運命の出会いが待っていた。
※エブリスタさまにも掲載

【完結】あなたに恋愛指南します
夏目若葉
恋愛
大手商社の受付で働く舞花(まいか)は、訪問客として週に一度必ず現れる和久井(わくい)という男性に恋心を寄せるようになった。
お近づきになりたいが、どうすればいいかわからない。
少しずつ距離が縮まっていくふたり。しかし和久井には忘れられない女性がいるような気配があって、それも気になり……
純真女子の片想いストーリー
一途で素直な女 × 本気の恋を知らない男
ムズキュンです♪

メイウッド家の双子の姉妹
柴咲もも
恋愛
シャノンは双子の姉ヴァイオレットと共にこの春社交界にデビューした。美しい姉と違って地味で目立たないシャノンは結婚するつもりなどなかった。それなのに、ある夜、訪れた夜会で見知らぬ男にキスされてしまって…?
※19世紀英国風の世界が舞台のヒストリカル風ロマンス小説(のつもり)です。

同窓会~あの日の恋をもう一度~
小田恒子
恋愛
短大を卒業して地元の税理事務所に勤める25歳の西田結衣。
結衣はある事がきっかけで、中学時代の友人と連絡を絶っていた。
そんなある日、唯一連絡を取り合っている由美から、卒業十周年記念の同窓会があると連絡があり、全員強制参加を言い渡される。
指定された日に会場である中学校へ行くと…。
*作品途中で過去の回想が入りますので現在→中学時代等、時系列がバラバラになります。
今回の作品には章にいつの話かは記載しておりません。
ご理解の程宜しくお願いします。
表紙絵は以前、まるぶち銀河様に描いて頂いたものです。
(エブリスタで以前公開していた作品の表紙絵として頂いた物を使わせて頂いております)
こちらの絵の著作権はまるぶち銀河様にある為、無断転載は固くお断りします。
*この作品は大山あかね名義で公開していた物です。
連載開始日 2019/10/15
本編完結日 2019/10/31
番外編完結日 2019/11/04
ベリーズカフェでも同時公開
その後 公開日2020/06/04
完結日 2020/06/15
*ベリーズカフェはR18仕様ではありません。
作品の無断転載はご遠慮ください。

あなたと恋に落ちるまで~御曹司は、一途に私に恋をする~
けいこ
恋愛
カフェも併設されたオシャレなパン屋で働く私は、大好きなパンに囲まれて幸せな日々を送っていた。
ただ…
トラウマを抱え、恋愛が上手く出来ない私。
誰かを好きになりたいのに傷つくのが怖いって言う恋愛こじらせ女子。
いや…もう女子と言える年齢ではない。
キラキラドキドキした恋愛はしたい…
結婚もしなきゃいけないと…思ってはいる25歳。
最近、パン屋に来てくれるようになったスーツ姿のイケメン過ぎる男性。
彼が百貨店などを幅広く経営する榊グループの社長で御曹司とわかり、店のみんなが騒ぎ出して…
そんな人が、
『「杏」のパンを、時々会社に配達してもらいたい』
だなんて、私を指名してくれて…
そして…
スーパーで買ったイチゴを落としてしまったバカな私を、必死に走って追いかけ、届けてくれた20歳の可愛い系イケメン君には、
『今度、一緒にテーマパーク行って下さい。この…メロンパンと塩パンとカフェオレのお礼したいから』
って、誘われた…
いったい私に何が起こっているの?
パン屋に出入りする同年齢の爽やかイケメン、パン屋の明るい美人店長、バイトの可愛い女の子…
たくさんの個性溢れる人々に関わる中で、私の平凡過ぎる毎日が変わっていくのがわかる。
誰かを思いっきり好きになって…
甘えてみても…いいですか?
※after story別作品で公開中(同じタイトル)
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















