25 / 45
third contact
白い天井
しおりを挟む
俺が彼に会ったのは、かなり前の話になる。
白色の電灯が煌々と輝いていた。
周りを取り囲む白い壁に反射して、色はより強さを増している。
視界を覆う天井には黒いシミひとつなかった。
純粋の白が広がっている。
それをぼんやり見つめていた。
見たことがない天井。
見慣れない天井だと言い換えてもいい。
いや、そもそも見慣れた天井などあったかさえ疑問が残る。
――それにしても。
はっきりとしているのは思考だけだった。
体はいっさい力が入らない。
感覚もない。
手足の指一本さえ動かすももちろんのことながら、身をよじることもできない。
体が重い?
そんな感覚もない。
まったくもって無だった。
横たわっていると想定はできても、感覚はない。
だからあくまで状況から集めた推察に過ぎない。
首から上だけの意識が残っているおかげで、物を見ることはできる。
おそらく言葉を発することもできるだろう。
――声を上げるべきだろうか?
だが留まった。
なにかしらのアクションをとる前に情報収集が必要だった。
今できる最大限で、より多くの判断材料を集めなければならない。
耳を澄ませば、複数の機械音が絶え間なく聞こえてくる。
ピッ……ピッ……と規則正しく繰り返される高音の他に、何かのデータを取るようなジジッ、ジジッ……という低音も混じって聞こえた。
床を擦る靴音もある。
忙しく動き回っている。
足音からすると体重は六十キロほどだろうか。
床との摩擦音からすると四十才以上の男性だと思われる。
しかしそれ以外の音は聞こえなかった。
首から上の感覚器は生かされていると言い換えるべきか。
しかし首が動かせないとなると、頭を固定された状態で横たわっている――ということだ。
視線を足のほうへと向ける。
視界の端に自分の体をなんとか捉えることができた。
身にまとっているものは何もない。
掛けられているものもなかった。
まっさらな状態で晒された体には何十本もの細長いチューブ状のコードが繋がれている。
チューブ状のコードの色はさまざまだ。
濃い赤、黄色、青、真緑。
それが自分の体と繋がって、奥のフォログラムモニターのほうへ長く伸びている。
モニターはいくつあるのか。
目を動かしただけの視界ではすべてを捉えることができない。
情報収集をあきらめて、自分の体から視線を逸らした。
もう一度天井を見上げる。
煌々と輝く白色電灯は目が痛いほどまぶしい。
天井にはやはり影ひとつ見えない。
それでも目を細めることなくじっと見つめる。
痛いほどまぶしいと頭で思うだけだ。
実際に目が痛いわけではない。
明かりのレベルを分析する。
『まぶしい』レベルという判断はできても、それに追随する感覚まではない。
だから目を細めて視覚を守る必要性はない。
この程度のレベルの明かりでは焼けることはないのだ、この目は。
――どうなるのだろう。
体の自由は奪われている。
奪われる?
元よりうまく動かなかった。
これは正しい表現とは言い難い。
いや、そもそも問題はそこではない。
どうしてこんなところで寝かされているのかということのほうが重要だ。
自分の中に残っている最後の記憶はとても断片的だ。
男物のスニーカーの映像を記憶している。
ずいぶんと履き古しているらしく、鮮やかであったはずの青と黄色は色落ちしてくすんでいた。
それが目に飛び込んだのは、いつだっただろう。
バケツをひっくり返したような土砂降りの雨だった。
その靴元にも大きな水たまりができていた。
水たまりを躊躇なく踏んでいた靴が水を吸い込んでぐっしょりと濡れている。
水たまりを踏まなくても、すでにずぶ濡れだったから気にならないのかもしれない。
足首が締まった灰色のズボンが雨露に濡れて濃くなっていた。
ゆっくりと視線を上へ向ければ、黒いに近い灰色の景色が広がっていた。
空気はスモッグに覆われ淀んでいた。
不思議なのはそんな土砂降りの雨の中を傘も差さずに立っている男がいたことだ。
それもひとりきり。
ズボンと同じグレーの上着のフードを目深に被った男は雨の雫をぼたぼたとフードからも、またそのフードに収まらずに外に出ているあごからも滴らせていた。
こちらをじっと見つめていた。
この時点で理解不能だった。
男がゆっくりと自分の前にひざまづいた。
同じ高さの目線になった。
視覚から入ってきた男の情報を懸命に整理しようとしたがうまくいかなかった。
どうやら分析機能も著しく低下してしまっているらしい。
ある程度の状況整理はできるが、それ以上のことはできない。
思考力にも記憶力にも支障が起きている。
それでもひとつだけはわかった。
目の前の男が、今まで一度も認識したことがない人物であるということだ。
彼は言った。
『一緒に来るか』と――
問いかけると同時に男は優しく自分の頭をなでた。
大きな手だった。
自分の頭を優しく包み込む男の大きな手に、自分は一も二もなく返事をしていた。
『でも……動かないんだ』
『いいんだ』
彼の口元が大きく弧を描いていた。
闇を落とした茶色の目がかすかに光を取り戻したかのように光って見えたのは錯覚だったのか。
彼はとても嬉しそうに笑っていた。
『だから拾うんだ』とそう言って――
どういう経緯でここまで来たのかは覚えていない。
それこそ砂嵐のようにぷっつりと情報が途切れている。
だけど確信はできた。
雨の中、動けくことができずにじっとうずくまっていた場所ではないということだ。
そんなことに思考をめぐらしているときだ。
まばゆい電灯の光を遮るように暗がりができた。
にょきっと湧いて出た影をじっと見つめる。
――ああ。
『あなたか……』と、言おうとして声が出なかった。
どうやらそこの神経も断絶されてしまったようだ。
どしゃぶりの雨の中で声を掛けてきた中年の男が自分のことを観察していた。
無精ひげには少しだけ白い物が混じっている。
黒と白の入り混じった髪を後ろで一つに結っている男の額に、収まりきれなかった一筋の前髪が垂れている。
少しこけた頬に、同じように少し窪んだ双眸。
その目は濃い茶色だった。
「もうすぐだ」
しゃがれ声の男が自分の額をなでた。
かさついた手だった。
けれど心地のいい温もりがそこにはあった。
皮膚の表面の感覚はまだ断絶されていないらしい。
男は自分の額をなんども優しくなでつけて「大丈夫だ」と笑った。
「すぐに動けるようになる」
男が自分の口元に分厚いマスクを装着した。
金属製のマスクが鼻と、耳と、口元を覆う。
男の手が離れていくと同時に、体に繋がれていたチューブ状のコードが一斉に外れた。
一歩身を引いた彼と自分を遮断するように分厚い壁が両側から現れる。
それは自分の数十cm上あたりでピッタリと閉まる。
次の瞬間、ゴポゴポッ……という音が閉じ込められた空間内に響き渡った。
液体がなだれ込んでくる。
ねっとりとした液体だった。
それが自分を包み込む。
けれど液体に覆われる感覚がなかった。
皮膚の感覚が遮断されたせいだ。
唯一残された視界が液体によって覆われ滲む。
滲んだ世界で最後に見た彼の口元が緩やかなカーブを描いていた。
『目が覚めたら話をしよう』
彼は粘着性のある液体に満たされた自分を壁越しに見つめ語りかけていた。
意識が反転する。
まばゆい白の世界から、薄緑の世界へ――
そして一気に深い闇の世界に変わり、そこで思考も記憶もぷっつりと閉ざされた。
そう、これが俺と彼との出会いの全て。
ここから俺と彼の物語は始まっていったのだ。
白色の電灯が煌々と輝いていた。
周りを取り囲む白い壁に反射して、色はより強さを増している。
視界を覆う天井には黒いシミひとつなかった。
純粋の白が広がっている。
それをぼんやり見つめていた。
見たことがない天井。
見慣れない天井だと言い換えてもいい。
いや、そもそも見慣れた天井などあったかさえ疑問が残る。
――それにしても。
はっきりとしているのは思考だけだった。
体はいっさい力が入らない。
感覚もない。
手足の指一本さえ動かすももちろんのことながら、身をよじることもできない。
体が重い?
そんな感覚もない。
まったくもって無だった。
横たわっていると想定はできても、感覚はない。
だからあくまで状況から集めた推察に過ぎない。
首から上だけの意識が残っているおかげで、物を見ることはできる。
おそらく言葉を発することもできるだろう。
――声を上げるべきだろうか?
だが留まった。
なにかしらのアクションをとる前に情報収集が必要だった。
今できる最大限で、より多くの判断材料を集めなければならない。
耳を澄ませば、複数の機械音が絶え間なく聞こえてくる。
ピッ……ピッ……と規則正しく繰り返される高音の他に、何かのデータを取るようなジジッ、ジジッ……という低音も混じって聞こえた。
床を擦る靴音もある。
忙しく動き回っている。
足音からすると体重は六十キロほどだろうか。
床との摩擦音からすると四十才以上の男性だと思われる。
しかしそれ以外の音は聞こえなかった。
首から上の感覚器は生かされていると言い換えるべきか。
しかし首が動かせないとなると、頭を固定された状態で横たわっている――ということだ。
視線を足のほうへと向ける。
視界の端に自分の体をなんとか捉えることができた。
身にまとっているものは何もない。
掛けられているものもなかった。
まっさらな状態で晒された体には何十本もの細長いチューブ状のコードが繋がれている。
チューブ状のコードの色はさまざまだ。
濃い赤、黄色、青、真緑。
それが自分の体と繋がって、奥のフォログラムモニターのほうへ長く伸びている。
モニターはいくつあるのか。
目を動かしただけの視界ではすべてを捉えることができない。
情報収集をあきらめて、自分の体から視線を逸らした。
もう一度天井を見上げる。
煌々と輝く白色電灯は目が痛いほどまぶしい。
天井にはやはり影ひとつ見えない。
それでも目を細めることなくじっと見つめる。
痛いほどまぶしいと頭で思うだけだ。
実際に目が痛いわけではない。
明かりのレベルを分析する。
『まぶしい』レベルという判断はできても、それに追随する感覚まではない。
だから目を細めて視覚を守る必要性はない。
この程度のレベルの明かりでは焼けることはないのだ、この目は。
――どうなるのだろう。
体の自由は奪われている。
奪われる?
元よりうまく動かなかった。
これは正しい表現とは言い難い。
いや、そもそも問題はそこではない。
どうしてこんなところで寝かされているのかということのほうが重要だ。
自分の中に残っている最後の記憶はとても断片的だ。
男物のスニーカーの映像を記憶している。
ずいぶんと履き古しているらしく、鮮やかであったはずの青と黄色は色落ちしてくすんでいた。
それが目に飛び込んだのは、いつだっただろう。
バケツをひっくり返したような土砂降りの雨だった。
その靴元にも大きな水たまりができていた。
水たまりを躊躇なく踏んでいた靴が水を吸い込んでぐっしょりと濡れている。
水たまりを踏まなくても、すでにずぶ濡れだったから気にならないのかもしれない。
足首が締まった灰色のズボンが雨露に濡れて濃くなっていた。
ゆっくりと視線を上へ向ければ、黒いに近い灰色の景色が広がっていた。
空気はスモッグに覆われ淀んでいた。
不思議なのはそんな土砂降りの雨の中を傘も差さずに立っている男がいたことだ。
それもひとりきり。
ズボンと同じグレーの上着のフードを目深に被った男は雨の雫をぼたぼたとフードからも、またそのフードに収まらずに外に出ているあごからも滴らせていた。
こちらをじっと見つめていた。
この時点で理解不能だった。
男がゆっくりと自分の前にひざまづいた。
同じ高さの目線になった。
視覚から入ってきた男の情報を懸命に整理しようとしたがうまくいかなかった。
どうやら分析機能も著しく低下してしまっているらしい。
ある程度の状況整理はできるが、それ以上のことはできない。
思考力にも記憶力にも支障が起きている。
それでもひとつだけはわかった。
目の前の男が、今まで一度も認識したことがない人物であるということだ。
彼は言った。
『一緒に来るか』と――
問いかけると同時に男は優しく自分の頭をなでた。
大きな手だった。
自分の頭を優しく包み込む男の大きな手に、自分は一も二もなく返事をしていた。
『でも……動かないんだ』
『いいんだ』
彼の口元が大きく弧を描いていた。
闇を落とした茶色の目がかすかに光を取り戻したかのように光って見えたのは錯覚だったのか。
彼はとても嬉しそうに笑っていた。
『だから拾うんだ』とそう言って――
どういう経緯でここまで来たのかは覚えていない。
それこそ砂嵐のようにぷっつりと情報が途切れている。
だけど確信はできた。
雨の中、動けくことができずにじっとうずくまっていた場所ではないということだ。
そんなことに思考をめぐらしているときだ。
まばゆい電灯の光を遮るように暗がりができた。
にょきっと湧いて出た影をじっと見つめる。
――ああ。
『あなたか……』と、言おうとして声が出なかった。
どうやらそこの神経も断絶されてしまったようだ。
どしゃぶりの雨の中で声を掛けてきた中年の男が自分のことを観察していた。
無精ひげには少しだけ白い物が混じっている。
黒と白の入り混じった髪を後ろで一つに結っている男の額に、収まりきれなかった一筋の前髪が垂れている。
少しこけた頬に、同じように少し窪んだ双眸。
その目は濃い茶色だった。
「もうすぐだ」
しゃがれ声の男が自分の額をなでた。
かさついた手だった。
けれど心地のいい温もりがそこにはあった。
皮膚の表面の感覚はまだ断絶されていないらしい。
男は自分の額をなんども優しくなでつけて「大丈夫だ」と笑った。
「すぐに動けるようになる」
男が自分の口元に分厚いマスクを装着した。
金属製のマスクが鼻と、耳と、口元を覆う。
男の手が離れていくと同時に、体に繋がれていたチューブ状のコードが一斉に外れた。
一歩身を引いた彼と自分を遮断するように分厚い壁が両側から現れる。
それは自分の数十cm上あたりでピッタリと閉まる。
次の瞬間、ゴポゴポッ……という音が閉じ込められた空間内に響き渡った。
液体がなだれ込んでくる。
ねっとりとした液体だった。
それが自分を包み込む。
けれど液体に覆われる感覚がなかった。
皮膚の感覚が遮断されたせいだ。
唯一残された視界が液体によって覆われ滲む。
滲んだ世界で最後に見た彼の口元が緩やかなカーブを描いていた。
『目が覚めたら話をしよう』
彼は粘着性のある液体に満たされた自分を壁越しに見つめ語りかけていた。
意識が反転する。
まばゆい白の世界から、薄緑の世界へ――
そして一気に深い闇の世界に変わり、そこで思考も記憶もぷっつりと閉ざされた。
そう、これが俺と彼との出会いの全て。
ここから俺と彼の物語は始まっていったのだ。
0
あなたにおすすめの小説

君を探す物語~転生したお姫様は王子様に気づかない
あきた
恋愛
昔からずっと探していた王子と姫のロマンス物語。
タイトルが思い出せずにどの本だったのかを毎日探し続ける朔(さく)。
図書委員を押し付けられた朔(さく)は同じく図書委員で学校一のモテ男、橘(たちばな)と過ごすことになる。
実は朔の探していた『お話』は、朔の前世で、現世に転生していたのだった。
同じく転生したのに、朔に全く気付いて貰えない、元王子の橘は困惑する。

極上の彼女と最愛の彼 Vol.3
葉月 まい
恋愛
『極上の彼女と最愛の彼』第3弾
メンバーが結婚ラッシュの中、未だ独り身の吾郎
果たして彼にも幸せの女神は微笑むのか?
そして瞳子や大河、メンバー達のその後は?

メイウッド家の双子の姉妹
柴咲もも
恋愛
シャノンは双子の姉ヴァイオレットと共にこの春社交界にデビューした。美しい姉と違って地味で目立たないシャノンは結婚するつもりなどなかった。それなのに、ある夜、訪れた夜会で見知らぬ男にキスされてしまって…?
※19世紀英国風の世界が舞台のヒストリカル風ロマンス小説(のつもり)です。

エリート警察官の溺愛は甘く切ない
日下奈緒
恋愛
親が警察官の紗良は、30歳にもなって独身なんてと親に責められる。
両親の勧めで、警察官とお見合いする事になったのだが、それは跡継ぎを産んで欲しいという、政略結婚で⁉

同窓会~あの日の恋をもう一度~
小田恒子
恋愛
短大を卒業して地元の税理事務所に勤める25歳の西田結衣。
結衣はある事がきっかけで、中学時代の友人と連絡を絶っていた。
そんなある日、唯一連絡を取り合っている由美から、卒業十周年記念の同窓会があると連絡があり、全員強制参加を言い渡される。
指定された日に会場である中学校へ行くと…。
*作品途中で過去の回想が入りますので現在→中学時代等、時系列がバラバラになります。
今回の作品には章にいつの話かは記載しておりません。
ご理解の程宜しくお願いします。
表紙絵は以前、まるぶち銀河様に描いて頂いたものです。
(エブリスタで以前公開していた作品の表紙絵として頂いた物を使わせて頂いております)
こちらの絵の著作権はまるぶち銀河様にある為、無断転載は固くお断りします。
*この作品は大山あかね名義で公開していた物です。
連載開始日 2019/10/15
本編完結日 2019/10/31
番外編完結日 2019/11/04
ベリーズカフェでも同時公開
その後 公開日2020/06/04
完結日 2020/06/15
*ベリーズカフェはR18仕様ではありません。
作品の無断転載はご遠慮ください。

短編【シークレットベビー】契約結婚の初夜の後でいきなり離縁されたのでお腹の子はひとりで立派に育てます 〜銀の仮面の侯爵と秘密の愛し子〜
美咲アリス
恋愛
レティシアは義母と妹からのいじめから逃げるために契約結婚をする。結婚相手は醜い傷跡を銀の仮面で隠した侯爵のクラウスだ。「どんなに恐ろしいお方かしら⋯⋯」震えながら初夜をむかえるがクラウスは想像以上に甘い初体験を与えてくれた。「私たち、うまくやっていけるかもしれないわ」小さな希望を持つレティシア。だけどなぜかいきなり離縁をされてしまって⋯⋯?
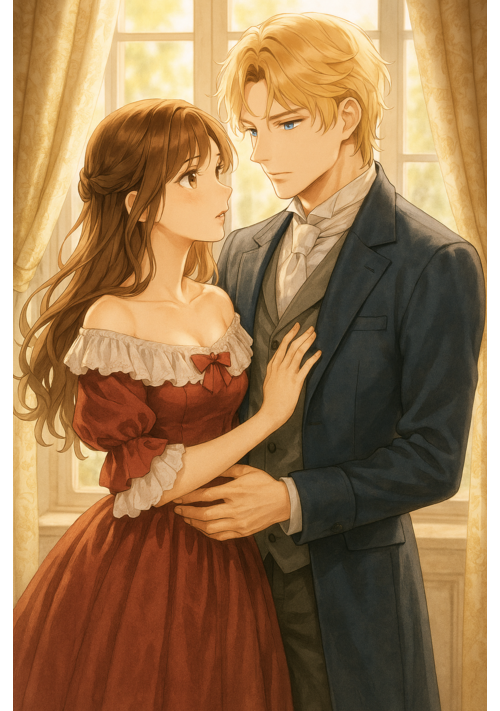
《完結》追放令嬢は氷の将軍に嫁ぐ ―25年の呪いを掘り当てた私―
月輝晃
恋愛
25年前、王国の空を覆った“黒い光”。
その日を境に、豊かな鉱脈は枯れ、
人々は「25年ごとに国が凍る」という不吉な伝承を語り継ぐようになった。
そして、今――再びその年が巡ってきた。
王太子の陰謀により、「呪われた鉱石を研究した罪」で断罪された公爵令嬢リゼル。
彼女は追放され、氷原にある北の砦へと送られる。
そこで出会ったのは、感情を失った“氷の将軍”セドリック。
無愛想な将軍、凍てつく土地、崩れゆく国。
けれど、リゼルの手で再び輝きを取り戻した一つの鉱石が、
25年続いた絶望の輪を、少しずつ断ち切っていく。
それは――愛と希望をも掘り当てる、運命の物語。

愛してやまないこの想いを
さとう涼
恋愛
ある日、恋人でない男性から結婚を申し込まれてしまった。
「覚悟して。断られても何度でもプロポーズするよ」
その日から、わたしの毎日は甘くとろけていく。
ライティングデザイン会社勤務の平凡なOLと建設会社勤務のやり手の設計課長のあまあまなストーリーです。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















