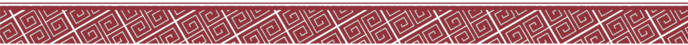32 / 59
26、シールド演習
しおりを挟む翌朝、いつもより早い時間に朝食が運ばれてきた。
「おはようございます、旅の疲れは取れましたか?」
「クランがわざわざ持ってきてくれたの? ごめん、そんなに心配させてたなんて思わなかった」
「昨日お話できなかったのが気になってしまって……」
てきぱきとクランが支度をしてくれるのを見ながらふと思った。
「そういえば、クランたちはいつもどこでごはん食べているの?」
「わたしたちですか?」
今までわたしは食事をいつも部屋に運んで来てもらっていたので、他の誰かと一緒に食事をとったことがない。
お茶なら、不特定の顔ぶれとすることはあるが、トラントランでの食事はいつもひとりだった。
だからビアンさん一家での食事や旅の間みんなで一緒に食べるのが、けっこう楽しかったのだ。
「わたしたちは、本堂でそろっていただく習慣なんです。今、ちょうど準備をしているところですよ」
「そうだったんだ。ひとり分だけわざわざこっちに運んでくれてたの? ごめんね、わたしも今度からそちらでいただくよ」
「えっ、でも……」
「もしかして僧侶じゃないから、一緒に食べちゃだめとか、決まりがあるの?」
「本来なら、美波はこの寺で最上位の目上のかたにあたるので、我々下々のものとは……」
「今さらそんな差をつけられても……。お茶は普通に一緒に飲んでるのに」
「でも、寺では食事も修行のひとつなので……」
「食べることが修行のひとつなんだ。へー、そんな風に考えたことなかったな。じゃあ、邪魔しないほうがいいんだね? みんなと一緒に食べたかったんだけど」
「そういうことでしたら、ご一緒にいかがですか?」
「いいの?」
わたしたちはお膳をもって、本堂へ向かった。
本堂にはお膳と共に、僧侶たちが規則正しく同じ方を向いて座っていた。
なんか修学旅行? みたいにも見える。
引率の先生ならぬ、コルグさんだけがこちらを向いている。
「父上、美波浮者がこちらで食事なされたいとおっしゃられましたので、お連れいたしました」
「おはようございます、美波浮者、こちらのお席へどうぞ」
コルグさんが自分の居た席を譲ろうと立ち上がった。
「あ、いえ、どうぞそのままで。クラン、隣に座ってもいい?」
「はい、こちらへ」
クランの席は、本堂の上座で、師父たちよりも上だった。
やっぱり、クランは重きを置かれる立場なんだね。
ここに来ればそういうことがすぐわかったんだなあ。
みんなが席に着くと、コルグさんが短い経を上げた。
「高き恵みわが身にいただきます」
「高き恵みわが身にいただきます」
コルグさんの言葉に、僧侶たちが一斉に手を合わせ、声を合わせて復唱した。
ハナムンのお寺も、日本に似てる。
わたしもみんなをならって、手を合わせた。
「高き恵みわが身にいただきます」
今日のご飯は、豆ごはんだ。
小指の先くらいの大きさの緑色の豆が米と一緒に炊かれている。
このごはん、ちょっと塩味がついていて、好きな味なんだよね。
でもお汁にもやしがはいってた。
あんまりもやしの入ったお味噌汁、好きじゃないんだよね……。
ふと、視線を感じて顔を上げると、まわりから食事の音が聞こえてこないことに気がついた。
コルグさんは箸にも手を付けていない。
あっ、これが修行なのかな。
まだ食べちゃいけないみたい。
手に持った箸を慌てておいた。
「美波浮者、目上の者が手を付けなければ、下の者は食べることが出来ません」
クランが耳打ちしてくれた。
「それから、残しても構わないので、すべてのお皿に箸をつけてください。これも、目上の者が手を付けていないものを下の者はいただけませんから」
そ、そんな決まりがなんだ……!
修行って、そういう事かあ。
目上の人を敬って、その行いを見習うっていうことなんだ。
うわー、目上の人って責任重大。
好き嫌いとかいえないね……。
お椀に口をつけると、ようやくみんなの食事が始まった。
食器の音や租借する音は聞こえても、話し声が一つも聞こえてこない。
声を低くしてクランに尋ねた。
「食事中はおしゃべりしちゃいけないの?」
「はい。わが身の糧となる食材のひとつひとつとに向か合うことが食事とされています。こうして目の前の膳に並ぶまでに携わったすべての人、もの、力に思いを馳せて頂くのです」
ふえー……。
す、すごいなあ……。
食事って、高尚なことなんだ……。
ビアンさんの家では、みんな貪るようにして食べていたけど、ローワンさんやカーツさんはお経も唱えてから食べていたもんね。
一般家庭はわからないけど、お寺の人たちの精神的教養の高さには恐れ入る。
ここにいる僧侶たちが礼儀正しいのも、ちゃんとマナーがなっているのもしてるのも、これなら納得だよ。
わ、わたしも見習おう……。
お豆、お米、塩、水……。
運んでくれたクラン、よそってくれた小坊主さん、作ってくれた檀家のみなさん、取引をしてくれる商家さん、荷物を背中に乗せて運んでくれる馬、野菜やお米を作ってくれる農家さん……。
そ、そうか。
そう考えたら、もやしが好きじゃないとか、言えないよね……。
すみません、ちゃんといただきます。
食べものに感謝するって、日本にいるときはあんまり考えたことなかったけど、本来はこういうことなのかもしれない。
東京にいたら、コンビニでパッケージされたおにぎりやサンドイッチがいつでも買えるし、飲食店に入れば、どこどこ産の地鶏とか、産地直送の海鮮とかが、普通に食べられる。外国の食材だって、地方の田舎料理だって、SNSで流行りのスウィーツだって、当たり前のように口にしてきた。
ひと口ひと口噛みしめながら、今まで考えたことがないくらいに、今食べているものが、どうやって自分の口に入るまでの過程や人の手を経ているのかを考えた。
命ってこうやってつながっているのかな。
そんな深遠な気持ちになる。
浮流が見えないわたしには、力のことまではわからないけれど、それを感じられるハナムンの人にとっては、ごく自然なことなのかもしれない。
考えながら食べていると、いつもよりお腹が満たされた気がした。
手を止めて、みんなが食べ終わるのを待っていると、次第に食器の音が収まっていった。
「尊き糧としてわが身にいただきました」
「尊き糧としてわが身にいただきました」
尊き糧としてわが身にいただきました……。
こういう気持ち、忘れちゃいけないね。
それぞれ自分のお膳をもって、炊房に片付けに行く。
躾の行き届いた光景というのか、高い精神性を身に着けている集団というのか、なんていっていいのかわからないけれど、改めてすごすぎる。
お寺の生活って本当に修行の場なんだ。
わたし、もうずいぶんお世話になってるけど、まだ知らないことがたくさんありそう。
まあ、とにかくビアンさん一家で見たものとは大違いだよ……。
「美波浮者、あまり食事が進まなかったようですが……」
わたしの膳を覗き込んだクランが気を遣わしげな顔をした。
「いろいろ考えながら食べてたら、お腹がいっぱいになっちゃった」
「お昼はお部屋にご準備しましょうか?」
「ううん、なんか思ってたのと違かったけど、これはこれで一体感があるっていうか。一人で食べるよりずっといいよ」
「それならいいんですけど」
膳をもって廊下にでると、片付けに向かうカーツさんがいた。
「美波浮者、クラン様、わたしが持ちましょう」
「ありがとう、カーツ」
「え、三つも大丈夫ですか?」
「はい。……美波浮者、半分も残っています。召し上がるのが遅いのでしたら、ゆっくり召し上がってくださってよいのですよ。我々に気を使ったのですか?」
「いや、もうお腹がいっぱいで」
カーツさんがじっとわたしを見下ろす。
「腰回りに肉をつけるためには、もっとしっかり食べるべきだと思います」
だから……、余計なお世話だってば……。
わたしが呆れるのと同時に、クランの顔が引きつった。
クランの顔を見て、ようやくはっとしたようなカーツさんだったが、はい残念。
「行きましょう、美波浮者」
「うん、行こうか」
カーツさんはもっと人の機微を察する修行をしたらいいよ。
わたしたちは大きな直立不動像の脇を抜けて、庭を散歩することにした。
「昨日のこと、ローワンから聞きました」
「うん、いろいろあって、結構疲れちゃったんだけど、ビアンさんの手足は治ったし、旬さんの新しい術のおかげで長旅もしなくてよくなって、体力的には楽だったよ。行く前はクランにあんなに心配かけちゃってごめんね」
「美波が無事でしたら、それでいいんです。実は、一日中美波になにかあったらどうしようとそればっかり、なにも手につきませんでした」
「いっぱい心配してくれてたんだね、ありがとう。血が落ちなくて使えなくなっちゃったけど、靴にも安全祈願をしてくれたよね。クランには本当にいつも助けられてるよ。ありがとうね」
クランはどこかためらいを浮かべて、首をふった。
「そんな……、あの靴では美波をお守りすることができず、自分の未熟さを痛感しました……」
「なにいってるの。クランがいなかったら、わたしはここまで回復してないよ。本当だよ」
「美波……」
「あのね、わたし考えていたの」
ビアンさんから、お友達価格はと聞かれて、明確な答えがわたしには出せなかった。
だけど、今ならわかる。
夜布団に入ったとき、その人の顔が思い浮かぶ人。
浮かんだなら、その人はもう、わたしにとってお友達なのだ。
なにかを相談したかったり、頼りにしたいとき、安心したかったり、助けてもらいたいとき、わたしはその人のことを思い出す。
わたしの場合、身一つでこの世界に来たその日から今日まで、お世話になりっぱなしなのだから、本当はお友達というよりも、気持ちとしてはもっともっと近い。
「クランはわたしにとって友達っていうより、妹みたいなの。兄弟姉妹がいないから、実は憧れてたの」
「妹ですか……」
「マシンくんは弟みたいに可愛いしね。トラントランの人たちはみんな、わたしにとって家族みたいに大切だよ。困っていたとき、傷ついたとき、ここの人たちがたくさんの親切と、温かいいたわりをくれなかったら、わたしは生きてない」
「美波……、その言葉、とてもうれしいです……。ですが……」
「ん?」
「すみません、美波が姉っていう気がしないというか……」
「えっ、わたしのほうがずっと年上だよ?」
「そ、そうなんですけどね、不思議ですねぇ、なぜか、うーん……」
「ええっ、わたしがお姉さんだよね?」
「はい、そうなんですけど、姉というには、うーん……、あの、すごく大事な家族みたいっていうのは、わたしもそう思っているんですが。姉というのが……、えーと、せめて、同い年のいとこ、とか、ですかね……」
「どうしても、姉じゃないっていうの?」
「だって、さすがに妹とはいえませんよね、さすがに。だから、妥協点というか」
「わ、わたしが姉だってば~っ!」
「う、う~ん……、それはちょっと……」
なんでーっ!?
まさかの裏切りだよーっ!
クランは最後まで、姉とは認めなかった。
ひどいっ、わたしの姉心を返して……っ。
工房で鼻息を荒くしながら、わたしはアクセサリーの研磨に精を出すことにした。
ムラークくんがビーズに色を付けながらこちらを伺う。
「美波浮者、どうかしたのですか?」
「クランに、すごーい、さすがお姉様! っていわせるのよ!」
ムラークくんにクランとの会話を聞かせると、意外やクランと同じような反応が返ってきた。
「実は、僕もクラン様と同じっていうか」
「え、まさかムラークくんまでもわたしのこと、妹なんて言わないよね?」
「まさか! そうではなく、僕も兄がいるんですが、ちょっと子どもっぽいといいますか」
こ、子どもっぽい……。
子どもの君にいわれると、思わなかったよ……。
「歳の順から行って兄に違いないのですが、話をしてもいろいろとかみ合わないというか」
「かみ合わない……」
「マシンは上の兄がふたりとも立派なかたなので、そういったことは感じたことはないかと思いますが、僕と兄はちょっとそういう関係性じゃないので……」
「頼りにならない……?」
「頼りにならないとまで言い切れませんが、僕の分野においてはあまり頼りにするということはありませんね」
そ……そりゃそっか……。
日本にいて、クランに東京案内でもするなら先輩風を吹かせるけど、こっちじゃクランに教わるばっかりだもんね。
体調を崩しても、一番世話を焼いてくれるのは、やっぱりクランだし。
作業の手を止めて、アクセサリーを仕掛りの箱にしまった。
「美波浮者?」
「今日はもうやめておく。下手にやって壊しちゃったらいやだから」
帰る間際に、カーツさんが工房にやってきた。
「あの、美波浮者、さきほどは……」
「……その話はまた今度」
カーツさんの脇をすり抜けて、部屋に戻った。
旬さんの左手をぎゅっと握って、目の前に置いた。
「旬さん、どう思う?」
「どうもこうも、みなみはもともと、あねとかいうタイプじゃないだろ」
「旬さんまで」
「たよられたいのかもしれないけど、クランからしたら、みなみのどこにたよれるポイントがあるのか、わからないんじゃないか?」
「うう……」
「それより、みなみ、みてほしいものがある。かみをよういしてくれ」
「あ、うん……。墨はどれくらい擦る?」
「かみだけでいい」
紙だけ?
疑問に思いながらも、旬さんの前に紙を広げた。
旬さんは人差し指をひょいと上げると、紙に指を落とした。
指が滑りだしたかと思うと、紙の上に黒い文字が書きつけられていく。
「旬さん、これ!」
紙の上の文字は、流れるように走っていき「どうだ、ビックリしたろ?」とくっきりと映った。
「すごーい、どうやったの? 手品みたい!」
「浮をインクに物質化したんだよ」
「そんなこともできるの? 旬さんて本当にすごい」
「実は、美波の特訓のおかげだ」
「特訓?」
「ビアンの手足を細かく調整したおかげで、液体というか、それに近い触りを以前よりうまくコントロールできるようになったんだ」
「そうなの?」
「今までは塊っぽいものしかできなくて、文字とか図形のような細かいものがつくれなかったけど、ほら」
旬さんが指をペン回しのようにくるりと回すしぐさをすると、灰色の万年筆のようなものが現れた。
「こうして、ペンとインクが使える」
万年筆はさらさらと、紙の上をすべり、丸や直線、簡単な絵など書いていった。
「す、すごーい!」
「こんなとこだな」
「この紙、けっこうザラザラしているのに、すこしも引っかからなかったね!」
「まあ、浮で書いてるからな。いらないと思ったら使った浮を回収すれば、字も消える」
「ええっ、消すこともできるの! 便利! びっくりだよ~!」
「ふはは、もっと褒めなさい」
「旬さん、すごいです! 天才、かっこいい、超かっこいい! 大好き!」
わたしと旬さんはしばらく高めのテンションで話をした。
これまでのように、墨を擦ったり、紙を取り変える必要もないから、とても楽ちんだ。
「これからは紙だけ持ち歩けばいいね。あれ、でも……」
「どうした?」
「えっと、ちょっと思ったんだけど、紙に書く必要あるの? 旬さんはもともと浮流の通ってない物体をあまり感知できないんでしょ? だとしたら、そのまま空気に書いても同じなんじゃないの?」
「そうか、なるほど、ちょっと待ってろ」
旬さんが空中に向かって万年筆を走らせた。
思った通り、空中に黒いインクの文字がさらさらと書かれていく。
「どうだ、できてるか?」
「うん、空中に書けてるよ」
「これでペーパーレス化だ」
「でも、これだと知らずに壁とか人の服とかに書いちゃうことがあるかもね」
「確かにな。やっぱ、書いたら消すだな」
「でも、ここまでできるなら、旬さんが翻訳の術を使えるようになるのも、そう遠い話しじゃなさそうだね。わたしの役目がなくなっちゃうのはさみしいけど、でも、旬さんも他の人と早くコミュニケーションとりたいよね」
「いや、それは急いでない」
「そうなの?」
「言葉については、美波の通訳で今のところ大きな不便はないし、ちょっと試してはみたが、そちらの視覚的な情報が少ないせいか、翻訳のイメージがうまくできなくて、時間がかかりそうなんだ。会得に時間のかかるものにとりかかるよりも、得意なことや重要度の高い術を開発した方がいい」
「そっか、なら、わたしもう少し役に立てそうだね」
「もう少しどころか、やっぱり左手しかそこにいない俺には限界があるよ。エレベーターも浮流の触りだけを頼りに飛ばすっていうのは、かなりリスクが高いと分かったし、もっと改善が必要だ。現地の情報を目で見て肌で感じている美波が絶対必要だ」
「わたしになにができるかな……?」
「今考えていることがある。近いうちにまたユーファオーの樹に行きたい」
「わかった、コルグさんに相談してみるね」
「それから、美波左手を出して」
「はい」
旬さんは指輪の位置を確かめると、なでるように何度か触れた。
「ちゃんとしてるか確かめたの? 一度も外したことないよ」
「今この指輪に浮を付与したんだ」
「え? でも物体に力を込めるのは苦手だって」
「だから、指輪に浮のメッキをかけたんだ。サイズはかわってないとおもうけど。色は少し変わったんじゃないかな」
「あっ、本当だ。すこし灰色が濃くなって、使い込んだシルバーアクセサリーみたい」
「俺の浮って灰色とか黒ばっかだな。おれには青っぽく見えているんだが」
「うーん、わたしには灰色にしか……。他の人には違って見えるのかも」
「とにかく、これからもその指輪を外さないように。美波を守る付与をかけたからな」
「わあ、ありがとう」
「なんの付与か聞かないのか?」
「なんの付与?」
「美波に悪意を持って触れようとするものを排除する」
「高熱焼却炉?」
「今度はスタンガンだ」
「それって、死なない程度の電流だよね……? あれ、でも、電流が使えるなら、スマホの充電もできる?」
「やってもいいけど、スマホはただの物体だから、うまくいくかどうか。どっちにしろ電波はつながらないんじゃないのか?」
「そうかもしれないね」
「あと、これまで物理的な攻撃や浮流を使った攻撃みたいなものはなかったけど、防御機能としてシールド兼シェルターを付与した」
「わあ、なんかゲームの魔法っぽいね」
「さっきのスタンガンもそうだけど、間違って俺の攻撃が美波にかかってしまったときのことを想定してる。俺には物理的なものがあまり見えないからな。シードとシェルターは、浮流による攻撃、物理的な攻撃を感知した場合に、自動発動する」
「自動的に発動するの? すごい高度だね」
「ちなみに、物理的な攻撃はいいとして、浮流を使った攻撃については今のところまだ、攻撃とそうでないものとはっきり区別ができない。だから、コルグさんや他の流者の術を施してもらうときは、一旦オフにしなきゃいけないから、覚えておいてくれ。カウンター機能もついているから」
「わあ、それは注意が必要だね」
「なんとなく、ゼンジ辺りが一回カウンターにやられそうな気がするな」
「し、死なない程度でお願いします」
「とりあえず、浮について話しておくべきことはこんなところかな」
「旬さんて本当にすごいね。指輪が使えるようになったかと思ったら、とんでもなく大きなものを物質化しちゃうし、体も治すし、浮で字まで書けちゃうし、守りの術もかけてくれるし。不思議だらけで驚いちゃうよ」
「俺たちに起こっていること自体が不思議だからな。できるだけ早くこの謎を解き浮かして、美波に会えるようになりたい」
「旬さん……」
「課題は残ったが、知っている人物がいさえすれば、その対象者がいる場所にエレベーターを飛ばすことが出来るってことはわかった。今後は、行ったことのない場所にも行けるようなやり方が見つかればいいんだが。イエウエンに行ったことがある人から、なにかそれらしい浮流の物体を借りるとかな」
「そうだね、大将軍の触りと同じもので、下賜された茶道具とか? そんなのがあればいいかも」
「そのあたりは、ユーファオーの樹でまたいろいろ試してみるよ。美波ももっとこの世界のことを情報収集してくれ」
「うん。今日もお寺の食事の修行にびっくりしちゃった」
「もっと俯瞰的な情報も欲しいな。まだこの世界の浮者にも会えてないし」
「浮者なら、近いうちに中央からサイシュエンに来ることになっているみたいだよ。クランの第一お婿さん候補」
「婿っていうか、主導権はむこうだろ?」
「でも、クランはお寺を継ぎたいと思ってるから」
「どんなやつなんだろうな。よぼよぼの爺さんだったりして」
「そっ、そんなの絶対だめだよ! クランは十七なんだよ」
「いずれにしても、楽しみだな」
「最高でも……二十七……二十九くらいまでね」
「七十二か、九十二だったりしてな」
もーっ!
そんなの絶対反対に決まってるじゃん!
お姉さんが、許しませんから!
……自称だけど。
その後、コルグさんにユーファオーの樹に行きたいということを伝えにいった。
昨日のことや、旬さんの新しい力のことを話すと、とても興味深そうだ。
「今ローワンを使いに出しておりますので、ユーファオーの樹へ向かうのは明日にして頂くとして。その前に新しい術、特にそのシールドやカウンターなるものをぜひ一度拝見させていただけませんでしょうか?」
コルグさんの提案により、その演習を行うことになった。
修練場には話を聞きつけた面々が集まり、ちょっと物々しい雰囲気さえしている。
「な、なんか怖くなってきちゃった」
「美波浮者、これでもわしは、三十年以上この土地の流者を名乗ってまいりました。心配はご無用です」
「う、うう……」
人だかりの一角に、マシンくんがいるのが見えた。
その顔に強い緊張と恐怖が見えたとき、わたしは尻すごんでしまった。
「す、すみません、コルグさん、やっぱり怖いです。旬さん、やめようよ」
旬さんは浮のインクでさらさらと空中をなぞる。
初めて見た僧侶たちから、どよとざわめきが聞こえた。
「試しもせずにいきなり使う羽目になるほうがよっぽど怖い。俺も、美波をちゃんと守れるかどうか知りたい」
「そ、そうだけど……」
さすがにマローみたいなことにはならないと思うけど、またマシンくんに怖がられるのだと思うと、気が進まない。
「それなら、ゼンジと代わってもらおう。あいつなら、万が一失敗しても大丈夫だ」
「だっ、大丈夫じゃないよ!」
「万が一傷つけても、ゼンジの触りは俺にも治しやすい。コルグさんとは一度反発し合ってるしな」
「そ、それは……」
しかたなく、わたしはゼンジさんを見た。
「えっ、僕!?」
「すみません、旬さんがそういってます……」
「ええっ、僕なにか気に障ることしたのかなぁ?」
「そ、そうではなく、万が一のことがあっても、ゼンジさんなら治しやすいそうです」
「うわあ、怖いなあ」
突然の指名に、僧侶たちの顔も戦々恐々だ。
クランを見ると、不安そうな表情でこちらを見ていた。
ご、ごめんね、クラン。
コルグさんにしても、ゼンジさんにしても、心配だよね……。
「僕攻撃の術なんて使ったことないんだけどな。えっと、どうすればいいんですか?」
「とりあえず、殴りかかってみてくれ、だそうです……」
「女性に? 気が引けるなあ……」
「ちゃんと、攻撃意識を向けてくれ、といってます……」
「頼む人、間違えてるよ~」
ゼンジさんがコルグさんと入れ替わり、わたしと旬さんの前に立った。
わたしも緊張していたが、ゼンジさんの顔も引きつっていた。
周りの何十もの目が、こちらを注視している。
殴りかかられる前に、わたしの膝が先にくずれそうな気がする。
「い、いきますよ……」
「は、はい……」
ゼンジさんが構えて、ぐっとこぶしに力を入れた。
その瞬間からもう、怖くて目をつぶってしまった。
次の瞬間、バツッという音がして、歓声が沸き起こった。
恐る恐る目を開けると、ゼンジさんが二メートルほど飛ばされたようにして転んでいた。
「いてて……」
「ゼンジさん、大丈夫ですか!?」
「う、うん……。なんか、全身ビリッとしたけど……、とりあえず無事ですよ」
「よ、よかった……」
クランやマシンくんの顔にも安堵が浮かんでいる。
コルグさんや師父たちも、ほっと肩をなでおろしていた。
「もう何人か、試してみてもらえるか?」
「旬さん、まだやるの?」
「害意というか、人の攻撃の流を掴みたい」
旬さんの言葉を伝えると、何人かの僧侶たちが進んで前に出た。
その中にはカーツさんもいる。
もう、なんで、みんなやる気になるの?
力試しならよそでやろーよ!
「カーツならもう少し強めでも死ななそうだな」
「加減、加減ね、旬さん」
進み出た僧侶たちはいずれも武闘派の腕に覚えのある人ばかりだ。
空手というのかカンフーというのかなにも持たない体術と、棒や槍などを使っての武術を、日々訓練している。
格闘技などに興味のないわたしには、映画みたいにすごいとしかいいようがなく、それと同じ位非現実な旬さんの力と、どっちが強いかとかどれくらい強いかなんて、まったくわからない。
一番手の僧侶パトナンさんがわたしの前に立った。
手には長い木の棒を持っている。
それでわたしを叩く気なんですか。
勘弁してよ~……!
パトナンさんが棒を振り上げた瞬間、わたしは目をつぶった。
やはり、バチッと跳ね返すような音がして、目を開けると、ハナムンさんは遠くに飛ばされていた。
「次鋒、ムンシューです! お願いいたします!」
「ぬうう……、中堅、ケイラクです! お願いいたします! やーっ!」
「副将、バン! お頼み申します! ハイヤーッ!」
三人立て続けてに飛ばされた後、カーツさんが前に出た。
「大将、頼みます!」
「カーツ、わが寺の力を見せてくれ!」
「カーツ様、行け―っ!」
もうなに、このテンション……。
ついていけない。
「わたしは師父に流の術を使う事を許された身です。流術を持って攻撃いたしますが、よろしいでしょうか?」
「……い、いいといってますが……。そのぶんのカウンターの威力は大きいといっています」
「これまでの反撃からみて承知しております。ではいざ、尋常に!」
カーツさんは武器はなにも持たず、空手のように手足を形づくった。
カッと目が開いたかと思うと、カーツさんの姿が一瞬で消えたように見えた。
次の瞬間に、バリバリッと激しい音が響いた。
目を開けると、黒い煙のようなものが立っていて、カーツさんは後ろに飛ばされていたものの、両足を踏ん張ってそこに立っていた。
防御で交差した黒く焦げた腕を降ろすと、カーツさんの熱のこもった瞳がそこにあった。
旬さんが指を滑らせた。
「今のが全力か?」
「それ、聞いたほうがいいの……?」
「カーツはこの寺で一番強いやつなんだろう? その力がどの程度か知っておくのは、カウンターの設定するにあたって参考になる」
うわー……、でもそれいうと火に油注いじゃう感じになりそうなんだけど……。
「も、もしカーツさんが大丈夫そうなら、全力を見せてほしいそうです……。その、カウンターの参考になるからって……」
「願ってもない!」
ほらあ……!
カーツさんは再び前に出てくると、腰のあたりから師筆を取り出した。
自分の拳になにかを書きつけている。
マヌーケルエンの青い光で「炎」と書かれていた。
「美波浮者、焦げたらお許しください」
「えっ、焦げ……、ちょっと待って……!」
「大丈夫、美波、落ち着け」
カーツさんが両足で力んで、こぶしを固めた。
わっ、ちょっと待って、ちょっと待ってってばぁ……!
カーツさんが動き出す前に、わたしはもう顔を覆って目をつぶっていた。
バツンとか、バクンというような、なにかが爆発するような轟音がした。
恐る恐る目を開くと、あたりは白い煙に覆われていた。
目を凝らすと、吹っ飛んであおむけに倒れているカーツさんがいた。
「カ、カーツさん……!」
「カーツ様!」
「カーツ、大丈夫か!」
一斉に駆け寄っていった僧侶たちに遅れて、わたしも駆け寄った。
カーツさんの皮膚は火傷の様にただれ、服は焦げてちりじりになっていた。
重しの珠も粉々に砕けている。
「皆に退くよういってくれ」
「す、すみません、みなさん、旬さんがどいてくれといってます」
僧侶たちが空けてくれた場所に座ると、旬さんはカーツさんの上に飛び乗った。
確かめるように胸のあたりに触れると、いつかのようにじっとそこにとどまった。
「おお……っ」
あたりから感嘆が漏れ始めた。
わたしにはなにも見えないけど、みんなにはもうなにか変化が見えているらしい。
わたしにもようやく変化が見えてきた。
カーツさんの皮膚が新しい油膜を張っていくかのように再生し始めた。
焼け焦げた着物以外がすっかり元に戻るまで、時間はそうはかからなかった。
「旬さん、カーツさんは大丈夫なの? ちゃんと息してるの?」
「問題ないと思う。今は気を失っているみたいだ」
「流は? また流が減っちゃったの?」
武人でなくとも、流者を志す僧侶にとって、ビアンさんと同じように流を失ってしまうことは、致命的なはずだ。
「カウンターは相手の攻撃がそのまま跳ね返る。だから、カーツの傷は流によるもので、浮によるものじゃない。流が減ることはない」
「そ、そうだったんだ……」
その説明を伝えて、カーツさんが運ばれていくのを見送った。
コルグさんとクランがそばにやってきた。
その後ろにゼンジさんと、演習に参加してくれた面々が連なった。
「術の披露のみならず、カーツの手当てまで、まことにありがたく存じます」
「あ……。ええと、旬さんがこちらこそいろいろためになったといっています。ありがとうございました。……でも、わたしは二度とやりたくないですけど……」
「美波浮者、顔色が優れませんよ。薬湯を入れて持っていきますから、部屋でお休みください」
「ゼンジさんこそ、体を安めて下さい。慣れないことをして大変だったでしょう? 無理をいってすみませんでした」
「なんのこれしき。目の前の体調の悪そうな人を治療できる機会を、僕が逃すはずがないじゃないですか」
「そうですよ、美波浮者。部屋までお送りします」
「ありがとう、クラン……」
部屋に戻ると、急にぐっと疲れが出た。
思った以上に緊張して普段使わない気を使っていたようだ。
ゼンジさんが運んできてくれた薬湯を飲むと、少しうとうとした。
「旬浮者の力はまるで、ひなを守る親鳥のようでした」
「ひな……」
クランにはわたしはそんな風に見えていたのか……。
そうか……。
それじゃあとても姉らしさは感じられないよね。
「旬浮者の力はとても強大で、やはり怖くもありました……」
「あ、そうだ……。マシンくん、怖がってなかったかな。他のみんなはどんな反応だったの? ユーファオーの樹のに注力したときは、マシンくんにすごく怖がられちゃって。……みんなに怖がられたら嫌だなあ……。マシンくんとまた距離が出来ちゃうと悲しいよ」
「そうですね。旬浮者の力には、みな畏怖を感じたと思います。でも、それは美波を守るためだけに力を発揮しているということも、よくわかりました。すくなくとも、この寺のもので美波にちょっかいを出そうするものは一人もいなくなったと思いますよ」
「みんな僧侶なんだから、そんなこと思うはずもないよ」
「それもそうですが」
少し目を閉じた。
旬さんはためになったといっていたから、今回の演習は実際やったいみはあったのだろう。
イスウエンに行くためにも、自衛の方法は大切だ。
でも、できれば極力、ハナムンの人たちと衝突やトラブルを起こさず、穏便な関係を築きたい。
正直、マローでのことを思うと、わたしはまだ怖い。
彼らは、わたしが浮者だということを承知で襲ってきた。
コルグさんの話では、中央に浮者が集まってしまうために、各地の有力者が浮者を確保しようと暗躍しているのかもしれないといっていた。
それはサイシュエンの大名だったかもしれないとも。
だとしても、浮のない浮者であるわたしには、権力者の求める力がない。
力のない者がどういう立場に置かれるかは、もう身をもって経験済みだ。
クランは奴隷を見たことがないといっていたけれど、清廉潔白な寺で大切にされてきたクランには目にする機会がなかったのだろう。
わたしには旬さんがいて、今もこうして守ってくれるけれど、あのとき旬さんがいなかったら、恐らくは奴隷のような扱いで売られていたはずだ。
わたしひとりだったら、本当に、この世界でどうなっていたかわからない。
そう思うともひたすらに怖い。
目を開けると、すぐにクランが気付いて微笑みかけてくれた。
「明日はユーファオーの森へ行くそうですね。このまま少し眠りますか?」
「うん……。クラン、もう少しだけ側にいてくれる?」
クランはすこし眉をあげてみせて、小さく笑った。
8
あなたにおすすめの小説

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

裏切りの代償
中岡 始
キャラ文芸
かつて夫と共に立ち上げたベンチャー企業「ネクサスラボ」。奏は結婚を機に経営の第一線を退き、専業主婦として家庭を支えてきた。しかし、平穏だった生活は夫・尚紀の裏切りによって一変する。彼の部下であり不倫相手の優美が、会社を混乱に陥れつつあったのだ。
尚紀の冷たい態度と優美の挑発に苦しむ中、奏は再び経営者としての力を取り戻す決意をする。裏切りの証拠を集め、かつての仲間や信頼できる協力者たちと連携しながら、会社を立て直すための計画を進める奏。だが、それは尚紀と優美の野望を徹底的に打ち砕く覚悟でもあった。
取締役会での対決、揺れる社内外の信頼、そして壊れた夫婦の絆の果てに待つのは――。
自分の誇りと未来を取り戻すため、すべてを賭けて挑む奏の闘い。復讐の果てに見える新たな希望と、繊細な人間ドラマが交錯する物語がここに。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子
satomi
ファンタジー
主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。
「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。
辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】
田中又雄
恋愛
18の誕生日を迎えたその翌日のこと。
俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。
「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」
そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。
「あの...相手の人の名前は?」
「...汐崎真凛様...という方ですね」
その名前には心当たりがあった。
天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。
こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる