あなたにおすすめの小説

【完結】亡くなった婚約者の弟と婚約させられたけど⋯⋯【正しい婚約破棄計画】
との
恋愛
「彼が亡くなった?」
突然の悲報に青褪めたライラは婚約者の葬儀の直後、彼の弟と婚約させられてしまった。
「あり得ないわ⋯⋯あんな粗野で自分勝手な奴と婚約だなんて!
家の為だからと言われても、優しかった婚約者の面影が消えないうちに決めるなんて耐えられない」
次々に変わる恋人を腕に抱いて暴言を吐く新婚約者に苛立ちが募っていく。
家と会社の不正、生徒会での横領事件。
「わたくしは⋯⋯完全なる婚約破棄を準備致します!」
『彼』がいるから、そして『彼』がいたから⋯⋯ずっと前を向いていられる。
人が亡くなるシーンの描写がちょっとあります。グロくはないと思います⋯⋯。
ーーーーーー
ゆるふわの中世ヨーロッパ、幻の国の設定です。
完結迄予約投稿済。
R15は念の為・・

[完結]貴方なんか、要りません
シマ
恋愛
私、ロゼッタ・チャールストン15歳には婚約者がいる。
バカで女にだらしなくて、ギャンブル好きのクズだ。公爵家当主に土下座する勢いで頼まれた婚約だったから断われなかった。
だから、条件を付けて学園を卒業するまでに、全てクリアする事を約束した筈なのに……
一つもクリア出来ない貴方なんか要りません。絶対に婚約破棄します。

わたくしが社交界を騒がす『毒女』です~旦那様、この結婚は離婚約だったはずですが?
澤谷弥(さわたに わたる)
恋愛
※完結しました。
離婚約――それは離婚を約束した結婚のこと。
王太子アルバートの婚約披露パーティーで目にあまる行動をした、社交界でも噂の毒女クラリスは、辺境伯ユージーンと結婚するようにと国王から命じられる。
アルバートの側にいたかったクラリスであるが、国王からの命令である以上、この結婚は断れない。
断れないのはユージーンも同じだったようで、二人は二年後の離婚を前提として結婚を受け入れた――はずなのだが。
毒女令嬢クラリスと女に縁のない辺境伯ユージーンの、離婚前提の結婚による空回り恋愛物語。
※以前、短編で書いたものを長編にしたものです。
※蛇が出てきますので、苦手な方はお気をつけください。


これ以上私の心をかき乱さないで下さい
Karamimi
恋愛
伯爵令嬢のユーリは、幼馴染のアレックスの事が、子供の頃から大好きだった。アレックスに振り向いてもらえるよう、日々努力を重ねているが、中々うまく行かない。
そんな中、アレックスが伯爵令嬢のセレナと、楽しそうにお茶をしている姿を目撃したユーリ。既に5度も婚約の申し込みを断られているユーリは、もう一度真剣にアレックスに気持ちを伝え、断られたら諦めよう。
そう決意し、アレックスに気持ちを伝えるが、いつも通りはぐらかされてしまった。それでも諦めきれないユーリは、アレックスに詰め寄るが
“君を令嬢として受け入れられない、この気持ちは一生変わらない”
そうはっきりと言われてしまう。アレックスの本心を聞き、酷く傷ついたユーリは、半期休みを利用し、兄夫婦が暮らす領地に向かう事にしたのだが。
そこでユーリを待っていたのは…
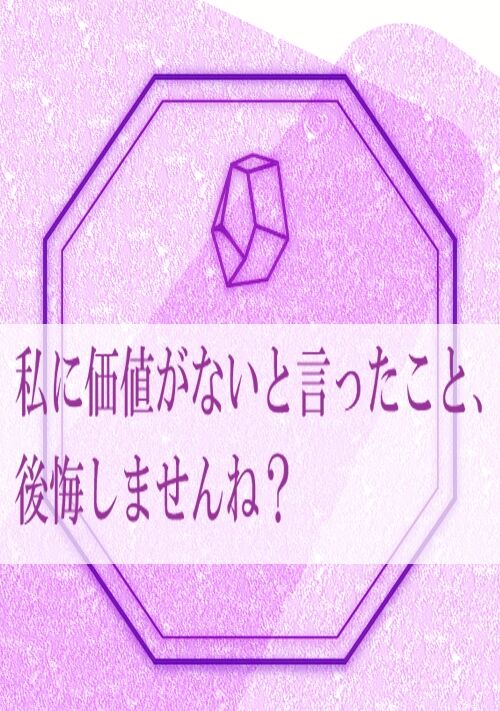
私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね?
みこと。
恋愛
鉛色の髪と目を持つクローディアは"鉱石姫"と呼ばれ、婚約者ランバートからおざなりに扱われていた。
「俺には"宝石姫"であるタバサのほうが相応しい」そう言ってランバートは、新年祭のパートナーに、クローディアではなくタバサを伴う。
(あんなヤツ、こっちから婚約破棄してやりたいのに!)
現代日本にはなかった身分差のせいで、伯爵令嬢クローディアは、侯爵家のランバートに逆らえない。
そう、クローディアは転生者だった。現代知識で鉱石を扱い、カイロはじめ防寒具をドレス下に仕込む彼女は、冷えに苦しむ他国の王女リアナを助けるが──。
なんとリアナ王女の正体は、王子リアンで?
この出会いが、クローディアに新しい道を拓く!
※小説家になろう様でも「私に価値がないと言ったこと、後悔しませんね? 〜不実な婚約者を見限って。冷え性令嬢は、熱愛を希望します」というタイトルで掲載しています。

婚約破棄から始まる物語【完】
mako
恋愛
メープル王国王太子であるアレクセイの婚約者である公爵令嬢のステファニーは生まれた時から王太子妃になるべく育てられた淑女の中の淑女。
公爵家の一人娘であるステファニーが生まれた後は子どもができぬまま母親は亡くなってしまう。バーナディン公爵はすぐさま再婚をし新たな母親はルシャードという息子を連れて公爵家に入った。
このルシャードは非常に優秀であり文武両道で背の高い美男子でもあったが妹になったステファニーと関わる事はなかった。
バーナディン公爵家は、今ではメープル王国のエリート一家である。
そんな中王太子より、ステファニーへの婚約破棄が言い渡される事になった。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~
放浪人
恋愛
「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」
大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。
生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。
しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。
「すまない。私は父としての責任を果たす」
かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。
だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。
これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















