30 / 65
第3巻 理を紡ぐ者たち
第2章 灰に眠る灯
しおりを挟む
灰雲が裂け、陽が射しはじめたのは、
王都を発って二日目の朝だった。
灰に沈んだ街を抜け、アーレンはノアとともに北へ歩いていた。
灰原を越えた先には、かつて交易路が走っていた緩やかな谷がある。
そこにはまだ、灰が完全に積もりきらない地層が残っているという。
「……人が、いるのか?」
灰を踏みながらアーレンが呟くと、
ノアは小さく頷いた。
「うん。山の下に、みんな、すんでる。
“あかりのひと”って、よんでるの」
「灯の人……?」
「うん。
あのひかりを、もらって、生きてる。
でも、よそからきた人は、こわがる」
ノアの言葉は幼いが、
どこか達観した響きがあった。
アーレンは彼女の言葉の意味を測りかねながらも、
灰核の脈動が少しずつ強まっていくのを感じていた。
⸻
昼をすぎるころ、谷の入り口にたどり着いた。
灰の風が途絶え、代わりに湿った空気が流れてくる。
灰ではなく、土と草の匂い。
久しく忘れていた“生きた大地”の匂いだった。
そこには――人の気配があった。
崩れた石橋の向こう、
岩壁に穿たれた洞窟のような集落。
洞の中には灯が並び、
小さな影たちが灰色の衣をまとって動いていた。
「……本当に、生きている」
アーレンは足を止めた。
ノアが振り返り、微笑む。
「ね? みんな、ちゃんと、いるよ」
⸻
集落に入ると、
いくつもの眼が同時に彼らを見た。
警戒と、驚き。
だがそこに敵意はなかった。
灰に染まった肌と、淡く光る瞳。
どの顔も、人と理の狭間にある。
灰の民――。
アーレンは心の中でそう呟いた。
一人の中年男が近づいてきた。
髪に灰を混ぜ、右腕に符の焼印を持つ。
「見ない顔だな。
外の……いや、生き残りか?」
「……旅の者だ。理災のあとの世界を見て回っている。
君たちは、この地にいつから?」
「いつからか、なんて数えたことはねえ。
気づいたら、みんなで“ここにいた”のさ」
男の声には疲労と、それでも消えない生の響きがあった。
⸻
洞窟の奥へ案内されると、
岩肌に刻まれた符が淡い光を放っていた。
それは理術とも符術とも違う――
灰の流れを制御するための独自の仕組みらしかった。
「この符は……」
「お前さん、わかるのか?」
「符術師の端くれでね。
だが、これは……理と血、両方の反応をしている。
まるで“共鳴”のようだ」
「共鳴、か。
なら、お前さん、うちの“灯”を見たほうがいい」
男はそう言い、奥の小部屋を指差した。
⸻
そこには、壁の隙間から灰がわずかに流れ込み、
中央で光を放っていた。
淡い白の炎。
火ではない。
灰の粒が集まり、ゆっくりと浮遊しながら
絶えず淡光を放っている。
「……これが、“灯”?」
「そう呼んでる。
理災の夜から、ずっと消えねえ。
誰がつけたのかもわからんが、
この光がある限り、灰は俺たちを呑みこまねえ」
アーレンは息をのんだ。
灰が、命を守っている――?
理災以前ならありえなかった現象だ。
灰が単なる災厄ではなく、
“新しい理の循環”を始めている。
⸻
「ノア、この灯に見覚えは?」
「うん。ここが、みんなの“うまれたところ”。
おじいも、ここから、ひかりをもらった」
「……そうか」
アーレンは膝をつき、符をかざした。
符の表面が光を受けて、淡く揺れる。
数式が、符の上に浮かび上がった。
灰の流れが律動している。
その波形は、生体の脈動とほとんど同じ――。
「……生きている」
彼は無意識に呟いた。
洞の灯が、静かに瞬いた。
⸻
灰の民は、灰を憎まず、
灰の中で、生を繋いでいた。
洞の奥に入ると、空気が変わった。
湿り気の中に、灰の匂いが混じっている。
だがそれは腐敗ではなく、
焚かれた香のように、静かな温もりを含んでいた。
灯の光が岩壁を照らし、
その周囲で、灰の民たちが膝をついていた。
老いも若きも、無言のまま両手を胸の前で合わせている。
祈り――。
アーレンは足を止めた。
理災以前、祈りは教会のものだった。
だが、ここに祭壇はない。
灰が漂い、光が揺れているだけ。
「……これは、何をしている?」
隣にいた男が小声で答える。
「“理の灯”への祈りだ。
この光が消えねえように、みんなで見守ってる。
昔は“神”って呼んでたらしいが、
いまはただ、“理”って呼んでる」
⸻
そのとき、奥から声がした。
「旅の方ですね」
灰の帳の向こうから、
一人の女がゆっくりと現れた。
白い灰をまとった法衣、
顔には薄布。
瞳は淡い青灰色で、
見つめられるだけで息が詰まるような静けさがあった。
「私はイサル。
この集の司(つかさ)を務めています。
あなたがノアを連れてきた方ですね」
アーレンはわずかに頭を下げた。
「アーレン・グレイヴ。……昔は、錬金術師だった」
「錬金……ああ。
その名を聞いたのは久しぶりです」
イサルは微笑み、灯の方へ歩いた。
⸻
彼女の指先が、灰の光をすくう。
その掌に、光が花のように集まる。
「灰は、死ではありません。
理の形を変えた姿です。
わたしたちはその理を“灯”と呼び、命の残り火と信じています」
「……信じている、か。
だが理は、人を拒んだ。
王都を呑み込み、国を滅ぼした。
それをまだ“命”と呼べるのか?」
アーレンの声は低かった。
イサルは、微笑みを崩さない。
「拒んだのは、理ではなく人の方です。
理は、何も選ばない。
それをどう扱うかを選んだのは、いつも人でした」
その言葉に、アーレンは返す言葉を失った。
⸻
イサルは灯を見上げたまま続ける。
「あなたのように、理を恐れずに触れた人を、
わたしたちは“記録の者”と呼びます。
もしあなたがまだ理を憎んでいないのなら、
灯に触れてみてください」
「……触れる?」
「はい。灰に焼かれることはないでしょう。
あなたには“記録の残滓”がある」
イサルの視線が、アーレンの胸元へ向けられる。
そこには、灰核があった。
⸻
アーレンはゆっくりと歩み寄り、
灰の灯の前に膝をついた。
光は生き物のように揺らめいている。
手を伸ばすと、灰が指先を撫でた。
温かい。
それは火ではないのに、血のようなぬくもりがあった。
「……これが、理の灯……」
「ええ。
人の理が壊れ、世界の理が残った。
それが、わたしたちの理災の記録です」
イサルの声は柔らかいが、どこか厳粛だった。
⸻
ふと、アーレンの掌に痛みが走った。
灰の粒が皮膚に触れ、
符の痕を淡く光らせた。
視界に、文字が浮かぶ。
灰の粒が組み上げるように、微細な理式が描かれていく。
『……記録者アーレン・グレイヴ。
灰の流れ、再構成を確認。』
「……これは……!」
アーレンが思わず身を引く。
イサルはゆっくりと頷いた。
「やはり、あなたの中に“理”が残っている。
その符の痕は、あなたが世界に刻まれた証。
理はあなたを拒まなかったのですよ」
⸻
アーレンは言葉を失った。
理が、自分の名を“記録”している。
理災で全てを失ったはずなのに――
世界は、まだ自分を覚えている。
灰の灯が、静かに脈打つ。
まるでリュミナの鼓動のように。
⸻
灰を祈る者たちは、
世界を赦し、
世界に赦されながら生きていた。
洞の奥の灯が、静かに瞬いていた。
アーレンはまだその光の前に座り込んでいた。
イサルは傍らで、焚いた香の灰をゆっくりとかき混ぜながら言った。
「あなたは、“命を創った”人なのですね」
アーレンは、かすかに目を伏せた。
「……過去の話だ。
その結果が、これだ。
国を、王都を、リュミナを……灰にした」
「それでも命は生まれました。
あなたが理を動かしたから、いま、わたしたちは息をしている」
「……皮肉だな」
「そう思うなら、見せましょう」
イサルは立ち上がり、灯の脇にある狭い通路へと向かった。
灰の粒が彼女の足元にまとわりつき、まるで道案内のように流れていく。
⸻
通路の先には、広い空洞があった。
天井の割れ目から、灰雲の光が薄く差し込んでいる。
その中央――浅い灰の泉が、音もなく湧いていた。
淡い白光を帯びた液体。
その表面には、微細な灰の粒が絶えず浮かび上がっては沈んでいく。
「……これは……?」
「“胎灰(たいかい)”。
灰の民の子は、ここで生まれます」
アーレンは息を呑んだ。
⸻
泉の縁に座っていた数人の女たちが、
両手で灰の水をすくい、胸元に押し当てている。
灰の粒が肌に染みこみ、やがて淡く光を放つ。
その光が収まると、
女たちの腹のあたりに灰色の紋が浮かび上がった。
「まさか……灰から、命を……?」
「灰は理の記録。
世界の命の設計図が、粒の中に刻まれているのです。
わたしたちは、それを“借りる”だけ。
神ではなく、媒介。
理が新しい命を選ぶとき――胎灰は動き出します」
イサルの声は祈りにも似ていた。
⸻
アーレンは泉の縁に近づき、
灰の水を指で掬った。
ぬるい。
その中で、微細な粒が光を返す。
まるで――星をすくっているようだった。
「この粒子……理式構造を持っている。
単なる灰じゃない。
情報が、循環している……?」
呟くと、イサルが頷く。
「あなたたちが“錬成”と呼んでいた行為を、
灰は自ら行っているのです。
わたしたちは、ただその理に祈るだけ。
命は、人が作るものではなく、理が返すもの。
そう信じています」
⸻
アーレンは拳を握りしめた。
「……もし、この灰が理を再構築しているなら、
それは――リュミナの“記録”も、残っているということか」
「ええ。
この地の灰は、塔の残骸から流れ着いたもの。
あなたの理核の欠片も、ここに混じっているでしょう」
イサルは穏やかに微笑んだ。
「だからノアの瞳は、あなたの創った命と同じ色をしている」
⸻
アーレンは息を止めた。
リュミナの金の瞳。
ノアの金の瞳。
そして、この灰の光。
理は死ななかった。
形を変え、命を返していた。
だが、それは同時に――
世界が、アーレンの罪を“記録した”ということでもあった。
⸻
「……イサル」
「はい」
「この灰を……分析したい。
理の構造を読み取れれば、何が変わったのかが分かる」
「あなたの中の“理”がそれを望むのなら、どうぞ。
けれど――」
イサルの声が低くなる。
「この地の理は、人の理とは違います。
それを解こうとすれば、あなたもまた灰に触れられる。
覚悟はありますか?」
アーレンは静かに頷いた。
「……あの日から、もう失うものはない」
⸻
灰の泉が脈打つように光った。
その光がアーレンの手の符を照らし、
微かな声が流れ出す。
『……アーレン……また、ここに……』
リュミナの声だった。
灰が揺れ、泉がわずかに波打つ。
灰に眠る命が、再び目を覚まそうとしていた。
その夜――
イサルの案内で、アーレンは集落の奥にある“記録の間”へと通された。
そこには、かつて王都から運び出された錬金器具や文献が、
灰をかぶったまま積まれていた。
理災の夜、逃げ延びた者たちが“祈りの遺品”として保管していたものだという。
「ここでは誰も使えません。
でも、あなたなら意味を見いだせるかもしれない」
イサルの言葉に、アーレンは無言で頷いた。
錆びた符盤、割れた瓶、そして見覚えのある筆記具。
それらを丁寧に拭いながら、
かつての“研究者”としての感覚がゆっくりと蘇っていくのを感じた。
――灰はすべてを奪った。
だが、理を理解しようとする意志までは奪えなかった。
アーレンは小さく息を吐き、
拾い集めた道具を抱えて洞へ戻った。
王都を発って二日目の朝だった。
灰に沈んだ街を抜け、アーレンはノアとともに北へ歩いていた。
灰原を越えた先には、かつて交易路が走っていた緩やかな谷がある。
そこにはまだ、灰が完全に積もりきらない地層が残っているという。
「……人が、いるのか?」
灰を踏みながらアーレンが呟くと、
ノアは小さく頷いた。
「うん。山の下に、みんな、すんでる。
“あかりのひと”って、よんでるの」
「灯の人……?」
「うん。
あのひかりを、もらって、生きてる。
でも、よそからきた人は、こわがる」
ノアの言葉は幼いが、
どこか達観した響きがあった。
アーレンは彼女の言葉の意味を測りかねながらも、
灰核の脈動が少しずつ強まっていくのを感じていた。
⸻
昼をすぎるころ、谷の入り口にたどり着いた。
灰の風が途絶え、代わりに湿った空気が流れてくる。
灰ではなく、土と草の匂い。
久しく忘れていた“生きた大地”の匂いだった。
そこには――人の気配があった。
崩れた石橋の向こう、
岩壁に穿たれた洞窟のような集落。
洞の中には灯が並び、
小さな影たちが灰色の衣をまとって動いていた。
「……本当に、生きている」
アーレンは足を止めた。
ノアが振り返り、微笑む。
「ね? みんな、ちゃんと、いるよ」
⸻
集落に入ると、
いくつもの眼が同時に彼らを見た。
警戒と、驚き。
だがそこに敵意はなかった。
灰に染まった肌と、淡く光る瞳。
どの顔も、人と理の狭間にある。
灰の民――。
アーレンは心の中でそう呟いた。
一人の中年男が近づいてきた。
髪に灰を混ぜ、右腕に符の焼印を持つ。
「見ない顔だな。
外の……いや、生き残りか?」
「……旅の者だ。理災のあとの世界を見て回っている。
君たちは、この地にいつから?」
「いつからか、なんて数えたことはねえ。
気づいたら、みんなで“ここにいた”のさ」
男の声には疲労と、それでも消えない生の響きがあった。
⸻
洞窟の奥へ案内されると、
岩肌に刻まれた符が淡い光を放っていた。
それは理術とも符術とも違う――
灰の流れを制御するための独自の仕組みらしかった。
「この符は……」
「お前さん、わかるのか?」
「符術師の端くれでね。
だが、これは……理と血、両方の反応をしている。
まるで“共鳴”のようだ」
「共鳴、か。
なら、お前さん、うちの“灯”を見たほうがいい」
男はそう言い、奥の小部屋を指差した。
⸻
そこには、壁の隙間から灰がわずかに流れ込み、
中央で光を放っていた。
淡い白の炎。
火ではない。
灰の粒が集まり、ゆっくりと浮遊しながら
絶えず淡光を放っている。
「……これが、“灯”?」
「そう呼んでる。
理災の夜から、ずっと消えねえ。
誰がつけたのかもわからんが、
この光がある限り、灰は俺たちを呑みこまねえ」
アーレンは息をのんだ。
灰が、命を守っている――?
理災以前ならありえなかった現象だ。
灰が単なる災厄ではなく、
“新しい理の循環”を始めている。
⸻
「ノア、この灯に見覚えは?」
「うん。ここが、みんなの“うまれたところ”。
おじいも、ここから、ひかりをもらった」
「……そうか」
アーレンは膝をつき、符をかざした。
符の表面が光を受けて、淡く揺れる。
数式が、符の上に浮かび上がった。
灰の流れが律動している。
その波形は、生体の脈動とほとんど同じ――。
「……生きている」
彼は無意識に呟いた。
洞の灯が、静かに瞬いた。
⸻
灰の民は、灰を憎まず、
灰の中で、生を繋いでいた。
洞の奥に入ると、空気が変わった。
湿り気の中に、灰の匂いが混じっている。
だがそれは腐敗ではなく、
焚かれた香のように、静かな温もりを含んでいた。
灯の光が岩壁を照らし、
その周囲で、灰の民たちが膝をついていた。
老いも若きも、無言のまま両手を胸の前で合わせている。
祈り――。
アーレンは足を止めた。
理災以前、祈りは教会のものだった。
だが、ここに祭壇はない。
灰が漂い、光が揺れているだけ。
「……これは、何をしている?」
隣にいた男が小声で答える。
「“理の灯”への祈りだ。
この光が消えねえように、みんなで見守ってる。
昔は“神”って呼んでたらしいが、
いまはただ、“理”って呼んでる」
⸻
そのとき、奥から声がした。
「旅の方ですね」
灰の帳の向こうから、
一人の女がゆっくりと現れた。
白い灰をまとった法衣、
顔には薄布。
瞳は淡い青灰色で、
見つめられるだけで息が詰まるような静けさがあった。
「私はイサル。
この集の司(つかさ)を務めています。
あなたがノアを連れてきた方ですね」
アーレンはわずかに頭を下げた。
「アーレン・グレイヴ。……昔は、錬金術師だった」
「錬金……ああ。
その名を聞いたのは久しぶりです」
イサルは微笑み、灯の方へ歩いた。
⸻
彼女の指先が、灰の光をすくう。
その掌に、光が花のように集まる。
「灰は、死ではありません。
理の形を変えた姿です。
わたしたちはその理を“灯”と呼び、命の残り火と信じています」
「……信じている、か。
だが理は、人を拒んだ。
王都を呑み込み、国を滅ぼした。
それをまだ“命”と呼べるのか?」
アーレンの声は低かった。
イサルは、微笑みを崩さない。
「拒んだのは、理ではなく人の方です。
理は、何も選ばない。
それをどう扱うかを選んだのは、いつも人でした」
その言葉に、アーレンは返す言葉を失った。
⸻
イサルは灯を見上げたまま続ける。
「あなたのように、理を恐れずに触れた人を、
わたしたちは“記録の者”と呼びます。
もしあなたがまだ理を憎んでいないのなら、
灯に触れてみてください」
「……触れる?」
「はい。灰に焼かれることはないでしょう。
あなたには“記録の残滓”がある」
イサルの視線が、アーレンの胸元へ向けられる。
そこには、灰核があった。
⸻
アーレンはゆっくりと歩み寄り、
灰の灯の前に膝をついた。
光は生き物のように揺らめいている。
手を伸ばすと、灰が指先を撫でた。
温かい。
それは火ではないのに、血のようなぬくもりがあった。
「……これが、理の灯……」
「ええ。
人の理が壊れ、世界の理が残った。
それが、わたしたちの理災の記録です」
イサルの声は柔らかいが、どこか厳粛だった。
⸻
ふと、アーレンの掌に痛みが走った。
灰の粒が皮膚に触れ、
符の痕を淡く光らせた。
視界に、文字が浮かぶ。
灰の粒が組み上げるように、微細な理式が描かれていく。
『……記録者アーレン・グレイヴ。
灰の流れ、再構成を確認。』
「……これは……!」
アーレンが思わず身を引く。
イサルはゆっくりと頷いた。
「やはり、あなたの中に“理”が残っている。
その符の痕は、あなたが世界に刻まれた証。
理はあなたを拒まなかったのですよ」
⸻
アーレンは言葉を失った。
理が、自分の名を“記録”している。
理災で全てを失ったはずなのに――
世界は、まだ自分を覚えている。
灰の灯が、静かに脈打つ。
まるでリュミナの鼓動のように。
⸻
灰を祈る者たちは、
世界を赦し、
世界に赦されながら生きていた。
洞の奥の灯が、静かに瞬いていた。
アーレンはまだその光の前に座り込んでいた。
イサルは傍らで、焚いた香の灰をゆっくりとかき混ぜながら言った。
「あなたは、“命を創った”人なのですね」
アーレンは、かすかに目を伏せた。
「……過去の話だ。
その結果が、これだ。
国を、王都を、リュミナを……灰にした」
「それでも命は生まれました。
あなたが理を動かしたから、いま、わたしたちは息をしている」
「……皮肉だな」
「そう思うなら、見せましょう」
イサルは立ち上がり、灯の脇にある狭い通路へと向かった。
灰の粒が彼女の足元にまとわりつき、まるで道案内のように流れていく。
⸻
通路の先には、広い空洞があった。
天井の割れ目から、灰雲の光が薄く差し込んでいる。
その中央――浅い灰の泉が、音もなく湧いていた。
淡い白光を帯びた液体。
その表面には、微細な灰の粒が絶えず浮かび上がっては沈んでいく。
「……これは……?」
「“胎灰(たいかい)”。
灰の民の子は、ここで生まれます」
アーレンは息を呑んだ。
⸻
泉の縁に座っていた数人の女たちが、
両手で灰の水をすくい、胸元に押し当てている。
灰の粒が肌に染みこみ、やがて淡く光を放つ。
その光が収まると、
女たちの腹のあたりに灰色の紋が浮かび上がった。
「まさか……灰から、命を……?」
「灰は理の記録。
世界の命の設計図が、粒の中に刻まれているのです。
わたしたちは、それを“借りる”だけ。
神ではなく、媒介。
理が新しい命を選ぶとき――胎灰は動き出します」
イサルの声は祈りにも似ていた。
⸻
アーレンは泉の縁に近づき、
灰の水を指で掬った。
ぬるい。
その中で、微細な粒が光を返す。
まるで――星をすくっているようだった。
「この粒子……理式構造を持っている。
単なる灰じゃない。
情報が、循環している……?」
呟くと、イサルが頷く。
「あなたたちが“錬成”と呼んでいた行為を、
灰は自ら行っているのです。
わたしたちは、ただその理に祈るだけ。
命は、人が作るものではなく、理が返すもの。
そう信じています」
⸻
アーレンは拳を握りしめた。
「……もし、この灰が理を再構築しているなら、
それは――リュミナの“記録”も、残っているということか」
「ええ。
この地の灰は、塔の残骸から流れ着いたもの。
あなたの理核の欠片も、ここに混じっているでしょう」
イサルは穏やかに微笑んだ。
「だからノアの瞳は、あなたの創った命と同じ色をしている」
⸻
アーレンは息を止めた。
リュミナの金の瞳。
ノアの金の瞳。
そして、この灰の光。
理は死ななかった。
形を変え、命を返していた。
だが、それは同時に――
世界が、アーレンの罪を“記録した”ということでもあった。
⸻
「……イサル」
「はい」
「この灰を……分析したい。
理の構造を読み取れれば、何が変わったのかが分かる」
「あなたの中の“理”がそれを望むのなら、どうぞ。
けれど――」
イサルの声が低くなる。
「この地の理は、人の理とは違います。
それを解こうとすれば、あなたもまた灰に触れられる。
覚悟はありますか?」
アーレンは静かに頷いた。
「……あの日から、もう失うものはない」
⸻
灰の泉が脈打つように光った。
その光がアーレンの手の符を照らし、
微かな声が流れ出す。
『……アーレン……また、ここに……』
リュミナの声だった。
灰が揺れ、泉がわずかに波打つ。
灰に眠る命が、再び目を覚まそうとしていた。
その夜――
イサルの案内で、アーレンは集落の奥にある“記録の間”へと通された。
そこには、かつて王都から運び出された錬金器具や文献が、
灰をかぶったまま積まれていた。
理災の夜、逃げ延びた者たちが“祈りの遺品”として保管していたものだという。
「ここでは誰も使えません。
でも、あなたなら意味を見いだせるかもしれない」
イサルの言葉に、アーレンは無言で頷いた。
錆びた符盤、割れた瓶、そして見覚えのある筆記具。
それらを丁寧に拭いながら、
かつての“研究者”としての感覚がゆっくりと蘇っていくのを感じた。
――灰はすべてを奪った。
だが、理を理解しようとする意志までは奪えなかった。
アーレンは小さく息を吐き、
拾い集めた道具を抱えて洞へ戻った。
0
あなたにおすすめの小説

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
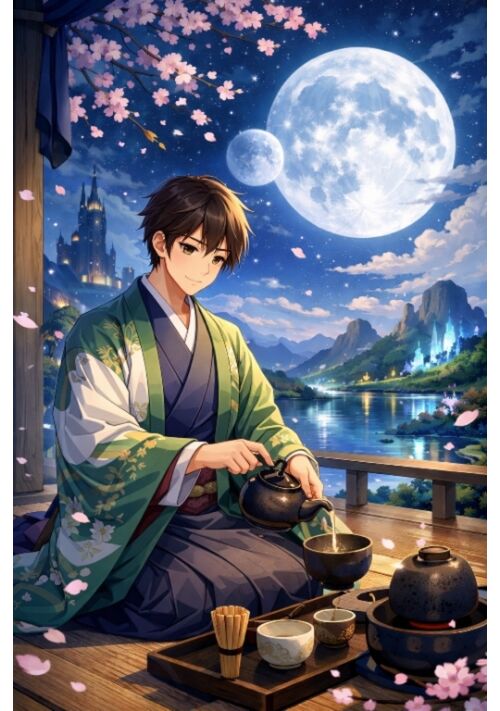
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















