34 / 65
第3巻 理を紡ぐ者たち
第6章 灰縁の灯
しおりを挟む
風が変わった。
灰の匂いに混じって、鉄と油の臭気が漂う。
アーレンは崩れた丘の上で足を止めた。
灰原の向こう、黒い鉄の構造物が並んでいる。
塔のように伸びた監視装置、
灰を吸い上げる巨大な管、
そして軍旗――二重翼に刻まれた竜の紋章。
「……帝国軍の拠点だな」
ノアが息をのんだ。
「ほんとに……生きてる人がいるんだ」
「ああ。だが、喜ぶことじゃない」
アーレンはマントを整え、符盤を隠した。
その横で、灰晶石が脈を打っている。
リュミナの核。
その光を見られれば、帝国に捕らえられるのは時間の問題だった。
⸻
基地の外縁には高い鉄柵と監視塔が並び、
灰除けの障壁が低い唸りをあげている。
理流を制御して外部の灰を遮断する装置――
灰地では唯一、明確に“生きている”機構だった。
ノアが柵の向こうを見つめる。
「……ひとが、たくさんいる。
みんな灰を掘ってる……」
アーレンは頷く。
「灰脈を採取しているんだろう。
灰を燃料として利用するつもりだ」
「でも……そんなことしたら、また“灰災”が」
「帝国はそれを恐れない。
理を制御できると信じている。
いや――信じたいだけだ」
⸻
そのとき、背後から声がした。
「そこで何をしている?」
低い、鋭い声。
振り返ると、灰色の外套をまとった兵士が二人。
符銃を腰に下げ、目には灰除けのゴーグル。
アーレンはとっさに答える。
「……避難民だ。灰地を越えようとして、道を失った」
一人の兵が近づき、顔を覗き込む。
灰にまみれたアーレンを見て、眉をひそめた。
「避難民がこんな奥まで来るか。……身分証は?」
「灰災で失った」
「ふん……まあいい。
ここは帝国灰理研究局の管轄だ。
命が惜しければ、勝手な行動はするな」
⸻
そう言って兵士が背を向けたとき――
もう一人が何かに気づいたように立ち止まる。
「待て、その荷だ。中身を見せろ」
アーレンの背嚢に目を向けている。
中には灰晶石。
見せるわけにはいかない。
アーレンは一瞬の間に符盤を起動しかけたが、
その前に別の声が割って入った。
「やめたまえ。
旅人に銃を向けるのは、帝国の礼節に反する」
⸻
灰塵の向こうから、ひとりの青年が歩いてきた。
白い外套。
肩章には灰理局の紋章。
黒髪を短く束ね、整った顔立ちに冷ややかな笑み。
「レネ・ヴォルテール、帝国灰理局監察官だ」
彼は手を軽く上げて兵を下がらせる。
「君たち、灰地を渡ってきたのか?
生きているだけで奇跡だ」
「……奇跡ではなく、運だ」
アーレンは慎重に言った。
「運でもいい。
この地で“灰を恐れない者”は、帝国としても貴重だ」
⸻
レネは一歩、アーレンに近づく。
彼の目が、灰晶石のわずかな光を捉えた。
「ほう……それは?」
アーレンは背嚢を閉じ、短く答えた。
「――ただの記録だ。かつての友の」
「そうか。
“友”を灰に喰われた者は多い。
だが、灰を連れて歩く者は珍しい」
その言葉に、アーレンの心臓が跳ねた。
この男――見抜いている。
⸻
レネは小さく笑った。
「安心しろ。君をすぐには捕らえない。
私は研究者だ。君の話を聞きたいだけだよ」
「……何を、だ」
「灰災を――リゼノスを滅ぼした“理の暴走”を。
そして、その中心にいた君の名を、
私は記録で何度も見た」
「アーレン・クロード。
君が“灰理理論”の創始者だ」
⸻
ノアが息を呑む。
レネはその反応を楽しむように笑い、
穏やかな声で言った。
「安心しろ。帝国は敵ではない。
君の知識を、“正しく”使いたいだけだ」
「“正しく”?」
「理を兵器ではなく、“安定装置”として扱う。
この地の灰を制御し、再び人が住めるようにする。
君が創った“理”を――人のために使うんだ」
⸻
アーレンは沈黙した。
だがその沈黙の裏で、胸の奥に小さな疑念が芽生える。
(帝国が理を“人のため”に使う……?)
それがどんな悲劇を招くか、
誰よりも彼自身が知っていた。
⸻
「……話を聞こう」
アーレンは低く言った。
「ただし、条件がある。――ノアには手を出すな」
レネは微笑を深めた。
「約束しよう。君が協力する限り、誰も傷つけはしない」
その声が妙に柔らかく響いた。
灰の灯が遠くで瞬き、
新たな“理の火”が、静かに灯った。
基地の内部は、想像以上に整っていた。
灰災の地のただ中とは思えないほど、
鉄と理式が秩序を保っていた。
壁面を走る導管は、淡く青い光を流している。
理流を安定化させる“灰導管”。
それが基地全体を巡り、
灰地の空気をわずかに“生”の側へ引き戻していた。
⸻
レネは案内役を務めながら、何気なく言った。
「ここは帝国の灰理研究拠点――通称“灰縁基地”。
リゼノスで発見された理技術を再現し、
灰を制御可能なエネルギー源に変換する計画だ」
アーレンは黙ってついていく。
廊下のあちこちに監視符が貼られ、
人影が通るたびに青い火花を散らしていた。
「……帝国は、灰を使うつもりか?」
「“使う”というより、“馴らす”だな」
レネは軽く笑った。
「灰は暴れる。
だが、理式を与えれば、家畜のように従順になる。
リゼノスが滅びたのは、それを拒んだからだ」
⸻
実験区画へ入ると、
巨大な円環装置が中央に鎮座していた。
灰導炉――
灰の理を取り込み、安定化させるための装置。
導管の中心では灰が液状化し、
ゆっくりと光を帯びて回転している。
まるで“灰が呼吸している”ようだった。
ノアがレネの袖を引いた。
「これ……リュミナの、なかにあったのと似てる……」
アーレンの表情が一瞬だけ揺れる。
確かに、灰導炉の核構造は“灰核理論”と同一の数式で動いていた。
⸻
「……その理式、どこで手に入れた」
アーレンの声が低く響いた。
レネは微笑を浮かべ、
制御盤の符に触れながら言う。
「リゼノスの学院跡から。
君の残した研究記録を再現したのさ。
――まさか本人に見られるとは思わなかったが」
「それは……未完成だ」
「知っている。
だからこそ“完成”させたい。
君の協力があればな」
⸻
アーレンは符盤を取り出し、理式を睨んだ。
その構造は――危うい。
理流の循環に“逆位相”が組み込まれている。
つまり、理を“固定”するのではなく、
“閉じ込める”構造。
「……レネ、これは安定化装置じゃない。
灰を――“封印”する理式だ」
レネは振り返り、わずかに笑みを深めた。
「封印、か。面白い言葉だな。
我々は“管理”と呼んでいる」
⸻
その言葉のあと、
灰導炉の中心が低く唸った。
灰が一瞬、赤く光り、
周囲の符が連鎖的に反応する。
「反応値が上昇!」
技術兵が叫ぶ。
「理流、限界値を超過!」
レネが制御符を叩く。
「冷却符を起動、流量を一定に保て!」
アーレンは即座に横へ飛び、制御盤に手を伸ばした。
「理位相が反転してる! 止めろ、今すぐ!」
「止められん、まだ安定点を――」
レネの言葉が終わる前に、
炉の中心が爆ぜた。
⸻
灰の奔流が吹き荒れる。
ノアが悲鳴を上げ、アーレンにしがみつく。
灰導炉の光が収束し、
やがてその中心に“人の形”が現れた。
灰が寄り集まり、
金色の光が脈動する。
アーレンは息を呑んだ。
その姿は、あまりにも――
「……リュミナ……?」
⸻
灰の光が揺れ、
人影がゆっくりと顔を上げた。
だが、その瞳には“色”がなかった。
純粋な灰色。
理の形をなぞっただけの“人の模造”。
レネは呆然とその光景を見つめ、
やがて静かに言った。
「――成功だ」
アーレンの胸が熱くなる。
「違う、これは命じゃない! 理を縛っただけだ!」
レネが目を細めた。
「理を縛れれば、人も縛れる。
君が成し得なかった“完全なる制御”だ」
⸻
灰の模造体が動いた。
その腕から灰の流れが吹き出し、
床の符式がひとつ、またひとつと焼き切れていく。
兵たちが悲鳴を上げた。
「制御不能! 炉が反転してます!」
アーレンはノアを抱き寄せ、叫んだ。
「レネ、離れろ! 灰が理を喰ってる!」
「……興味深い」
レネはそれでも一歩、前へ出た。
「これが“命”の形か」
⸻
灰導炉が爆ぜた。
光がすべてを呑み込む。
金と灰が混じり合い、音が消える。
アーレンはノアを庇いながら、崩れる壁を飛び越えた。
灰が降り積もる中、リュミナの核が脈を打つ。
『……あれは、わたし……じゃない……』
リュミナの声が、震えていた。
アーレンは灰晶石を握りしめ、
崩れ落ちる炉を見つめた。
「……理は、神でも、兵器でもない。
お前たちは――また同じ過ちを繰り返す気か」
――音が、戻ってこない。
灰導炉の爆発は、あらゆる“声”を奪っていた。
燃焼も、破壊も、すべてが吸い込まれ、
ただ灰の渦だけが残っていた。
アーレンは、崩れ落ちた壁の陰で目を開けた。
肺に灰を吸い込み、激しく咳き込む。
ノアが腕の中で震えている。
「ノア、無事か」
「……う、ん……でも、あのひかりが……」
アーレンは顔を上げた。
炉の中心部、割れた制御環の中に――
“何か”が、立っていた。
⸻
灰の中から、白い足が現れる。
ゆっくりと、形を成す。
肌は陶器のように滑らかで、
血の代わりに灰が滲み、指先から零れ落ちていた。
それは、少女の姿だった。
ただし――目がなかった。
眼窩の奥には、灰の光が宿っている。
それは、命の“模倣”。
理が記録を読み違えて、生んだ“影”。
⸻
「……成功、か」
灰塵の中から、レネが歩いてきた。
片手に符盤、もう片方の手には灰導器の残骸。
外套は破れ、灰まみれになっているのに、
その瞳だけは澄みきっていた。
「見たか、アーレン。
灰は命を再現できる。
“記録”ではなく、“意志”の形で」
「違う……」
アーレンはかすれた声で言った。
「それは命じゃない。
理が命を“模した”だけだ」
⸻
レネは灰の少女に近づき、膝をついた。
手を伸ばす。
灰の少女が、ゆっくりと顔を向けた。
「わたしは……なに……?」
声がした。
灰の粒が空中で震える。
言葉が理の波として響いた。
レネは笑みを浮かべる。
「“灰導体(はいどうたい)”だ。
お前は、人の理を宿した最初の存在――
我々の、新しい未来だよ」
⸻
「やめろ!」
アーレンが叫んだ。
「灰導体は不安定だ。理が自己進化を始めれば、
再び“灰災”が起きる!」
「……君はまだ、“恐れている”んだな」
レネがゆっくりと立ち上がる。
「理は暴れない。人が恐れるから暴れるんだ。
だから、私は“理に恐怖を教えない世界”を作る」
「それが帝国の理想か?」
「帝国など関係ない。
これは、私の――“救済”だ」
⸻
その瞬間、灰導体が動いた。
その胸から、金の光が漏れる。
アーレンは凍りついた。
――それは、リュミナの“光”と同じ波。
「やめろ、それは――!」
灰導体が手を掲げる。
指先から灰が噴き出し、崩れた床を呑み込む。
灰が触れた金属が、理式の符へと変わり、
そのまま“灰の花”のように咲き始めた。
⸻
ノアが叫んだ。
「アーレン! これ、灰が――生きてる!」
アーレンは符盤を叩いた。
「ノア、後ろへ!」
反符式が光り、灰導体の動きを一瞬止める。
だがその瞳――灰の光がアーレンを見つめていた。
『……どうして、にてるの……?』
声。
リュミナの声に、酷似していた。
⸻
アーレンの心が裂けるように痛んだ。
「やめろ……! 彼女の声を使うな!」
レネが冷たく笑う。
「君が言った。“灰は記録を持つ”と。
つまり、灰の理が君の創った“L-01”の記録を読み取ったのだ。
これは偶然ではない――再現だよ」
アーレンは歯を噛みしめた。
「……それを、命とは呼ばない」
⸻
灰導体が一歩踏み出した。
足跡から灰の花が咲き、
空間の理流が一気に変調する。
基地全体の符式が次々と反応し、
照明が落ち、警報が鳴り響いた。
「理流異常発生! 中心区画が崩壊します!」
遠くで兵の声が聞こえる。
レネはその混乱を無視し、アーレンを見つめた。
「君の研究が、ついに完成したんだ。
この地の灰は、もう“死んでいない”。」
⸻
アーレンはノアの手を引き、灰の中へ駆けだした。
背後で灰導体の光が爆ぜ、
レネの笑い声が、灰風にかき消された。
灰は、形を持とうとしている。
命を模し、人を真似、
やがて“理”さえも模倣する。
⸻
崩れた廊下を走り抜けながら、ノアが振り返った。
「アーレン、あの子……泣いてた」
アーレンは答えなかった。
ただ、胸の中の灰晶石が淡く脈を打つ。
『……あれは、わたしじゃない。
でも……わたしの“いたみ”を、しってる……』
灰の声が、静かに響いた。
⸻
灰の時代は、終わらない。
それは、命のかたちを真似るたびに、
より深い“理の鏡”を生み出していく。
灰の匂いに混じって、鉄と油の臭気が漂う。
アーレンは崩れた丘の上で足を止めた。
灰原の向こう、黒い鉄の構造物が並んでいる。
塔のように伸びた監視装置、
灰を吸い上げる巨大な管、
そして軍旗――二重翼に刻まれた竜の紋章。
「……帝国軍の拠点だな」
ノアが息をのんだ。
「ほんとに……生きてる人がいるんだ」
「ああ。だが、喜ぶことじゃない」
アーレンはマントを整え、符盤を隠した。
その横で、灰晶石が脈を打っている。
リュミナの核。
その光を見られれば、帝国に捕らえられるのは時間の問題だった。
⸻
基地の外縁には高い鉄柵と監視塔が並び、
灰除けの障壁が低い唸りをあげている。
理流を制御して外部の灰を遮断する装置――
灰地では唯一、明確に“生きている”機構だった。
ノアが柵の向こうを見つめる。
「……ひとが、たくさんいる。
みんな灰を掘ってる……」
アーレンは頷く。
「灰脈を採取しているんだろう。
灰を燃料として利用するつもりだ」
「でも……そんなことしたら、また“灰災”が」
「帝国はそれを恐れない。
理を制御できると信じている。
いや――信じたいだけだ」
⸻
そのとき、背後から声がした。
「そこで何をしている?」
低い、鋭い声。
振り返ると、灰色の外套をまとった兵士が二人。
符銃を腰に下げ、目には灰除けのゴーグル。
アーレンはとっさに答える。
「……避難民だ。灰地を越えようとして、道を失った」
一人の兵が近づき、顔を覗き込む。
灰にまみれたアーレンを見て、眉をひそめた。
「避難民がこんな奥まで来るか。……身分証は?」
「灰災で失った」
「ふん……まあいい。
ここは帝国灰理研究局の管轄だ。
命が惜しければ、勝手な行動はするな」
⸻
そう言って兵士が背を向けたとき――
もう一人が何かに気づいたように立ち止まる。
「待て、その荷だ。中身を見せろ」
アーレンの背嚢に目を向けている。
中には灰晶石。
見せるわけにはいかない。
アーレンは一瞬の間に符盤を起動しかけたが、
その前に別の声が割って入った。
「やめたまえ。
旅人に銃を向けるのは、帝国の礼節に反する」
⸻
灰塵の向こうから、ひとりの青年が歩いてきた。
白い外套。
肩章には灰理局の紋章。
黒髪を短く束ね、整った顔立ちに冷ややかな笑み。
「レネ・ヴォルテール、帝国灰理局監察官だ」
彼は手を軽く上げて兵を下がらせる。
「君たち、灰地を渡ってきたのか?
生きているだけで奇跡だ」
「……奇跡ではなく、運だ」
アーレンは慎重に言った。
「運でもいい。
この地で“灰を恐れない者”は、帝国としても貴重だ」
⸻
レネは一歩、アーレンに近づく。
彼の目が、灰晶石のわずかな光を捉えた。
「ほう……それは?」
アーレンは背嚢を閉じ、短く答えた。
「――ただの記録だ。かつての友の」
「そうか。
“友”を灰に喰われた者は多い。
だが、灰を連れて歩く者は珍しい」
その言葉に、アーレンの心臓が跳ねた。
この男――見抜いている。
⸻
レネは小さく笑った。
「安心しろ。君をすぐには捕らえない。
私は研究者だ。君の話を聞きたいだけだよ」
「……何を、だ」
「灰災を――リゼノスを滅ぼした“理の暴走”を。
そして、その中心にいた君の名を、
私は記録で何度も見た」
「アーレン・クロード。
君が“灰理理論”の創始者だ」
⸻
ノアが息を呑む。
レネはその反応を楽しむように笑い、
穏やかな声で言った。
「安心しろ。帝国は敵ではない。
君の知識を、“正しく”使いたいだけだ」
「“正しく”?」
「理を兵器ではなく、“安定装置”として扱う。
この地の灰を制御し、再び人が住めるようにする。
君が創った“理”を――人のために使うんだ」
⸻
アーレンは沈黙した。
だがその沈黙の裏で、胸の奥に小さな疑念が芽生える。
(帝国が理を“人のため”に使う……?)
それがどんな悲劇を招くか、
誰よりも彼自身が知っていた。
⸻
「……話を聞こう」
アーレンは低く言った。
「ただし、条件がある。――ノアには手を出すな」
レネは微笑を深めた。
「約束しよう。君が協力する限り、誰も傷つけはしない」
その声が妙に柔らかく響いた。
灰の灯が遠くで瞬き、
新たな“理の火”が、静かに灯った。
基地の内部は、想像以上に整っていた。
灰災の地のただ中とは思えないほど、
鉄と理式が秩序を保っていた。
壁面を走る導管は、淡く青い光を流している。
理流を安定化させる“灰導管”。
それが基地全体を巡り、
灰地の空気をわずかに“生”の側へ引き戻していた。
⸻
レネは案内役を務めながら、何気なく言った。
「ここは帝国の灰理研究拠点――通称“灰縁基地”。
リゼノスで発見された理技術を再現し、
灰を制御可能なエネルギー源に変換する計画だ」
アーレンは黙ってついていく。
廊下のあちこちに監視符が貼られ、
人影が通るたびに青い火花を散らしていた。
「……帝国は、灰を使うつもりか?」
「“使う”というより、“馴らす”だな」
レネは軽く笑った。
「灰は暴れる。
だが、理式を与えれば、家畜のように従順になる。
リゼノスが滅びたのは、それを拒んだからだ」
⸻
実験区画へ入ると、
巨大な円環装置が中央に鎮座していた。
灰導炉――
灰の理を取り込み、安定化させるための装置。
導管の中心では灰が液状化し、
ゆっくりと光を帯びて回転している。
まるで“灰が呼吸している”ようだった。
ノアがレネの袖を引いた。
「これ……リュミナの、なかにあったのと似てる……」
アーレンの表情が一瞬だけ揺れる。
確かに、灰導炉の核構造は“灰核理論”と同一の数式で動いていた。
⸻
「……その理式、どこで手に入れた」
アーレンの声が低く響いた。
レネは微笑を浮かべ、
制御盤の符に触れながら言う。
「リゼノスの学院跡から。
君の残した研究記録を再現したのさ。
――まさか本人に見られるとは思わなかったが」
「それは……未完成だ」
「知っている。
だからこそ“完成”させたい。
君の協力があればな」
⸻
アーレンは符盤を取り出し、理式を睨んだ。
その構造は――危うい。
理流の循環に“逆位相”が組み込まれている。
つまり、理を“固定”するのではなく、
“閉じ込める”構造。
「……レネ、これは安定化装置じゃない。
灰を――“封印”する理式だ」
レネは振り返り、わずかに笑みを深めた。
「封印、か。面白い言葉だな。
我々は“管理”と呼んでいる」
⸻
その言葉のあと、
灰導炉の中心が低く唸った。
灰が一瞬、赤く光り、
周囲の符が連鎖的に反応する。
「反応値が上昇!」
技術兵が叫ぶ。
「理流、限界値を超過!」
レネが制御符を叩く。
「冷却符を起動、流量を一定に保て!」
アーレンは即座に横へ飛び、制御盤に手を伸ばした。
「理位相が反転してる! 止めろ、今すぐ!」
「止められん、まだ安定点を――」
レネの言葉が終わる前に、
炉の中心が爆ぜた。
⸻
灰の奔流が吹き荒れる。
ノアが悲鳴を上げ、アーレンにしがみつく。
灰導炉の光が収束し、
やがてその中心に“人の形”が現れた。
灰が寄り集まり、
金色の光が脈動する。
アーレンは息を呑んだ。
その姿は、あまりにも――
「……リュミナ……?」
⸻
灰の光が揺れ、
人影がゆっくりと顔を上げた。
だが、その瞳には“色”がなかった。
純粋な灰色。
理の形をなぞっただけの“人の模造”。
レネは呆然とその光景を見つめ、
やがて静かに言った。
「――成功だ」
アーレンの胸が熱くなる。
「違う、これは命じゃない! 理を縛っただけだ!」
レネが目を細めた。
「理を縛れれば、人も縛れる。
君が成し得なかった“完全なる制御”だ」
⸻
灰の模造体が動いた。
その腕から灰の流れが吹き出し、
床の符式がひとつ、またひとつと焼き切れていく。
兵たちが悲鳴を上げた。
「制御不能! 炉が反転してます!」
アーレンはノアを抱き寄せ、叫んだ。
「レネ、離れろ! 灰が理を喰ってる!」
「……興味深い」
レネはそれでも一歩、前へ出た。
「これが“命”の形か」
⸻
灰導炉が爆ぜた。
光がすべてを呑み込む。
金と灰が混じり合い、音が消える。
アーレンはノアを庇いながら、崩れる壁を飛び越えた。
灰が降り積もる中、リュミナの核が脈を打つ。
『……あれは、わたし……じゃない……』
リュミナの声が、震えていた。
アーレンは灰晶石を握りしめ、
崩れ落ちる炉を見つめた。
「……理は、神でも、兵器でもない。
お前たちは――また同じ過ちを繰り返す気か」
――音が、戻ってこない。
灰導炉の爆発は、あらゆる“声”を奪っていた。
燃焼も、破壊も、すべてが吸い込まれ、
ただ灰の渦だけが残っていた。
アーレンは、崩れ落ちた壁の陰で目を開けた。
肺に灰を吸い込み、激しく咳き込む。
ノアが腕の中で震えている。
「ノア、無事か」
「……う、ん……でも、あのひかりが……」
アーレンは顔を上げた。
炉の中心部、割れた制御環の中に――
“何か”が、立っていた。
⸻
灰の中から、白い足が現れる。
ゆっくりと、形を成す。
肌は陶器のように滑らかで、
血の代わりに灰が滲み、指先から零れ落ちていた。
それは、少女の姿だった。
ただし――目がなかった。
眼窩の奥には、灰の光が宿っている。
それは、命の“模倣”。
理が記録を読み違えて、生んだ“影”。
⸻
「……成功、か」
灰塵の中から、レネが歩いてきた。
片手に符盤、もう片方の手には灰導器の残骸。
外套は破れ、灰まみれになっているのに、
その瞳だけは澄みきっていた。
「見たか、アーレン。
灰は命を再現できる。
“記録”ではなく、“意志”の形で」
「違う……」
アーレンはかすれた声で言った。
「それは命じゃない。
理が命を“模した”だけだ」
⸻
レネは灰の少女に近づき、膝をついた。
手を伸ばす。
灰の少女が、ゆっくりと顔を向けた。
「わたしは……なに……?」
声がした。
灰の粒が空中で震える。
言葉が理の波として響いた。
レネは笑みを浮かべる。
「“灰導体(はいどうたい)”だ。
お前は、人の理を宿した最初の存在――
我々の、新しい未来だよ」
⸻
「やめろ!」
アーレンが叫んだ。
「灰導体は不安定だ。理が自己進化を始めれば、
再び“灰災”が起きる!」
「……君はまだ、“恐れている”んだな」
レネがゆっくりと立ち上がる。
「理は暴れない。人が恐れるから暴れるんだ。
だから、私は“理に恐怖を教えない世界”を作る」
「それが帝国の理想か?」
「帝国など関係ない。
これは、私の――“救済”だ」
⸻
その瞬間、灰導体が動いた。
その胸から、金の光が漏れる。
アーレンは凍りついた。
――それは、リュミナの“光”と同じ波。
「やめろ、それは――!」
灰導体が手を掲げる。
指先から灰が噴き出し、崩れた床を呑み込む。
灰が触れた金属が、理式の符へと変わり、
そのまま“灰の花”のように咲き始めた。
⸻
ノアが叫んだ。
「アーレン! これ、灰が――生きてる!」
アーレンは符盤を叩いた。
「ノア、後ろへ!」
反符式が光り、灰導体の動きを一瞬止める。
だがその瞳――灰の光がアーレンを見つめていた。
『……どうして、にてるの……?』
声。
リュミナの声に、酷似していた。
⸻
アーレンの心が裂けるように痛んだ。
「やめろ……! 彼女の声を使うな!」
レネが冷たく笑う。
「君が言った。“灰は記録を持つ”と。
つまり、灰の理が君の創った“L-01”の記録を読み取ったのだ。
これは偶然ではない――再現だよ」
アーレンは歯を噛みしめた。
「……それを、命とは呼ばない」
⸻
灰導体が一歩踏み出した。
足跡から灰の花が咲き、
空間の理流が一気に変調する。
基地全体の符式が次々と反応し、
照明が落ち、警報が鳴り響いた。
「理流異常発生! 中心区画が崩壊します!」
遠くで兵の声が聞こえる。
レネはその混乱を無視し、アーレンを見つめた。
「君の研究が、ついに完成したんだ。
この地の灰は、もう“死んでいない”。」
⸻
アーレンはノアの手を引き、灰の中へ駆けだした。
背後で灰導体の光が爆ぜ、
レネの笑い声が、灰風にかき消された。
灰は、形を持とうとしている。
命を模し、人を真似、
やがて“理”さえも模倣する。
⸻
崩れた廊下を走り抜けながら、ノアが振り返った。
「アーレン、あの子……泣いてた」
アーレンは答えなかった。
ただ、胸の中の灰晶石が淡く脈を打つ。
『……あれは、わたしじゃない。
でも……わたしの“いたみ”を、しってる……』
灰の声が、静かに響いた。
⸻
灰の時代は、終わらない。
それは、命のかたちを真似るたびに、
より深い“理の鏡”を生み出していく。
0
あなたにおすすめの小説

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
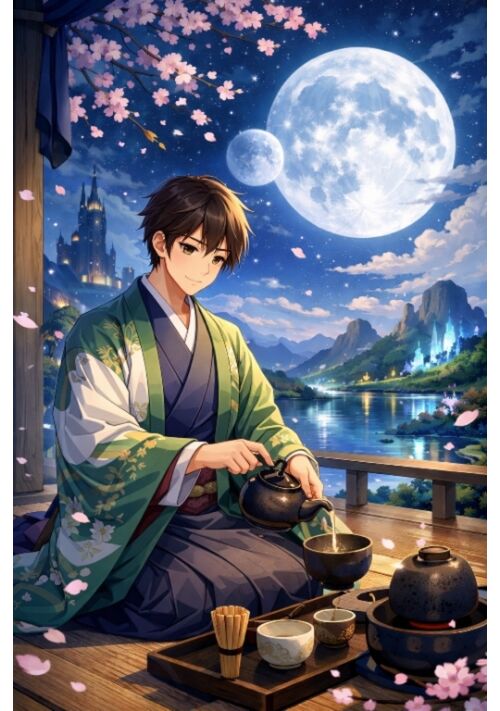
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

異世界転移物語
月夜
ファンタジー
このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

神様の忘れ物
mizuno sei
ファンタジー
仕事中に急死した三十二歳の独身OLが、前世の記憶を持ったまま異世界に転生した。
わりとお気楽で、ポジティブな主人公が、異世界で懸命に生きる中で巻き起こされる、笑いあり、涙あり(?)の珍騒動記。

元公爵令嬢は年下騎士たちに「用済みのおばさん」と捨てられる 〜今更戻ってこいと泣きつかれても献身的な美少年に溺愛されているのでもう遅いです〜
日々埋没。
ファンタジー
「新しい従者を雇うことにした。おばさんはもう用済みだ。今すぐ消えてくれ」
かつて婚約破棄され、実家を追放された元公爵令嬢のレアーヌ。
その身分を隠し、年下の冒険者たちの身の回りを世話する『メイド』として献身的に尽くしてきた彼女に突きつけられたのは、あまりに非情な追放宣告だった。
レアーヌがこれまで教育し、支えてきた若い男たちは、新しく現れた他人の物を欲しがり子悪魔メイドに骨抜きにされ、彼女を「加齢臭のする汚いおばさん」と蔑み、笑いながら追い出したのだ。
地位も、居場所も、信じていた絆も……すべてを失い、絶望する彼女の前に現れたのは、一人の美少年だった。
「僕とパーティーを組んでくれませんか? 貴方が必要なんです」
新米ながら将来の可能性を感じさせる彼は、レアーヌを「おばさん」ではなく「一人の女性」として、甘く狂おしく溺愛し始める。
一方でレアーヌという『真の支柱』を失った元パーティーは、自分たちがどれほど愚かな選択をしたかを知る由もなかった。
やがて彼らが地獄の淵で「戻ってきてくれ」と泣きついてきても、もう遅い。
レアーヌの隣には、彼女を離さないと誓った執着愛の化身が微笑んでいるのだから。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















