46 / 65
第4巻 帝国編・前編 ―灰の秩序―
第8章 灰脈の息吹
しおりを挟む――灰が、流れなくなっていた。
アーレンは符盤を開き、針のような灰粒の動きを見つめていた。
いつもなら、灰は風に乗ってゆっくりと螺旋を描く。
だが、今は空気そのものが凍ったように、静止している。
「……灰流が、止まってる。」
小さく呟く。
符盤の波形は平坦で、脈がない。まるで世界が息を止めたようだった。
⸻
灰域の外れ、崩れた街道脇の洞窟。
そこが、彼らの今の住処だった。
灰岩を削って作った炉の上に、淡い光を放つ灰石が積まれている。
それが熱と光をわずかに生み、彼らの一日の営みを支えていた。
「水、できたよ!」
ノアが壊れた金属缶を両手で抱え、誇らしげに笑う。
缶の中では、符式で濾過された灰水がかすかに青く光っていた。
アーレンはうなずき、符盤の端にメモを残す。
《濾過成功。符構式No.3、灰反応率低下継続。理流不活性。》
“理が眠っている”――そうしか言いようがなかった。
⸻
リュミナは炉のそばで灰を掬っていた。
掌の中の灰が淡く脈を打ち、小さな光点が浮かぶ。
それは芽吹く寸前の“灰苔(かいごけ)”。
理災後にだけ現れる、光を食むように生きる不思議な植物だ。
「ねぇ、見て。少しだけ動いたの。生きてるんだよ。」
アーレンはそっと彼女の手を覗き込み、頷いた。
「理流が鈍ってても、まだ“命”は残ってる。
……理は沈黙しても、世界は生きようとしてるんだ。」
リュミナは微笑んだ。
けれど、灰核の光は弱かった。
それはまるで、彼女の命そのものが“灰の眠り”に引き込まれているかのように。
⸻
夜。
外の風が止み、洞窟の奥に静寂が満ちていく。
ノアは毛布代わりの布の下で小さく寝息を立てていた。
アーレンは焚き火の名残の前で符盤を広げる。
いつものように灰流を測ろうとしたが、針はまったく動かない。
理の呼吸が、ない。
「……誰かが、蓋をしたな。」
誰に言うでもなく呟いた。
リュミナが火の向こうから顔を上げる。
「蓋?」
「そうだ。理の流れがここまで鈍るなんて、人為的だ。
――帝国か、あるいは“理そのもの”が、自らを閉ざしたのか。」
彼女はしばらく黙っていた。
やがて、胸に手を当てる。
「でも、まだ……感じるの。
理は眠ってるだけ。夢を見てるみたいに、静かに……。」
アーレンは小さく頷き、符盤を閉じた。
⸻
洞窟の外に出ると、灰の空が広がっていた。
夜なのに、どこか白い。
風もなく、音もない。
リュミナが外へ出てきて、空を見上げた。
「……ねぇ、あれ、星?」
彼女の指の先に、ひとすじの光。
だがそれは星ではなかった。
灰雲を突き抜け、遠く地平にゆっくりと沈んでいく光――
まるで世界が最後の息を吐くような、淡い残光だった。
「……いや。」
アーレンは静かに首を振る。
「星は、もうずっと前に消えたよ。」
灰の光が彼の瞳に映り込む。
それはどこか、遠い記憶を思い出しているようだった。
⸻
風がひとすじ、洞窟に吹き込む。
リュミナが振り返ると、灰苔の芽がわずかに光を放った。
“理”がわずかに息を吹き返したように。
アーレンはその光を見つめたまま、呟く。
「……眠ってるだけなら、まだ起こせる。
理が夢を見てるなら、その続きを、俺たちが見せてやればいい。」
その声に、リュミナは微笑んだ。
灰の空の下、淡い灯りが三つだけ、息をしていた。
――帝都ヴァルシュタイン。
空が白かった。
雪ではない。灰だ。
理封令が発令されて以来、空から絶えず降り注ぐ“無色の灰”が街を覆い、
かつての帝都はまるで墓標のように静まり返っていた。
街路に人影はない。
符灯も、通信符も、全ての符術機構が停止していた。
理を通す導管が封鎖され、灰理塔は沈黙している。
音のない都。
それが、「理封」の代償だった。
⸻
帝国灰理局――かつての中央塔は、今や“局庁舎”と呼ばれていた。
理制御は全面停止、観測装置の大半は封印。
それでも、局長執務室だけは淡い光を放っている。
エルシア・ファロウ。
帝国理災を生き延びた唯一の符術研究者であり、
今や帝国暫定統治評議会の命により「灰理局長」となった女。
机の上には、破損した符盤の欠片。
それを光にかざすと、かすかに灰色の脈が走る。
「……まだ、生きている。」
彼女は小さく呟いた。
理は死なない。
けれど、人はそれを“使う”ことをやめた。
⸻
背後の扉が開く。
入ってきたのは、灰翼隊副官だったヴェルド。
今は軍籍を外され、理封軍警の警護主任としてエルシアに仕えていた。
「局長。封印区画の巡回、完了しました。」
「どうだった?」
「灰導管の一部に脈動があります。符盤からの共鳴ではなく……自然反応のようです。」
エルシアはわずかに顔を上げた。
「自然反応……灰域との同期、まだ途絶えていないのね。」
「封印を強化しますか?」
「いいえ。そのままで。」
「しかし、再び“理災”が――」
「……あれは災厄じゃない。応答よ。」
ヴェルドは沈黙した。
彼女の瞳には、かつての理塔でアーレンと見た“灰の光”が映っていた。
⸻
灰理局中枢封印室。
床一面に理封陣が刻まれ、無数の符刻が光を失って沈んでいる。
中央には一つの巨大な封印塔――
その内部には、崩壊した理制御符盤の断片が静かに鎮座していた。
エルシアはその前に立ち、手をかざした。
灰色の光が掌に集まり、封印陣の表面をかすかに照らす。
「……アーレン。あなたの理が、まだここに息をしてる。」
呟く声は誰にも届かない。
ただ、灰だけが応えるように舞い上がる。
⸻
封印塔の側面に刻まれた銘文が、わずかに光った。
《理は沈黙せよ。人は記録せよ。》
それが、帝国理封令の第一条だった。
だがエルシアはその文字を見つめ、唇を噛む。
「沈黙させるのではなく、“聞く”べきだったのよ……」
符盤の欠片を手に取ると、そこにかすかな脈動が走った。
まるで、遠くから呼びかける声のように。
――エルシア。
聞こえた気がした。
理封の結界を隔てて、灰の向こうから。
彼女は思わず封印塔に手を置いた。
灰がふわりと舞い、指先を包む。
「……あなた、まだ“観ている”のね。」
⸻
その夜。
帝都の空に、封印塔から一本の光柱が立ち上がった。
理封結界の余波――
“理”が、閉ざされたままでもなお世界に干渉している証。
街の誰もがそれを見上げ、息を呑んだ。
だがエルシアはただ、静かにその光を見つめながら呟いた。
「……理は、生きている。
だから私は、まだ終わらせない。」
その言葉は、灰の風にかき消された。
けれど、遥か灰域の彼方――
符盤の上で眠るアーレンの指先に、同じ波が触れていた。
わずかに光る符線。
“理封”の壁を越え、二つの鼓動が重なった。
――灰原の朝は、静かだった。
風はほとんど吹かず、空も灰色のまま止まっている。
鳥も、虫もいない。
ただ、灰が絶え間なく流れ、世界の輪郭を曖昧にしていた。
アーレンは灰の地面に符盤を置き、じっと波形を見つめていた。
数値は安定している。灰流の乱れもほとんどない。
それなのに、心のどこかが落ち着かなかった。
「……何かがおかしい。」
彼は符盤を軽く叩いた。
表示される理流の波が、まるで“息をしていない”。
世界全体が、呼吸を止めているようだった。
⸻
リュミナが背後から覗き込む。
胸の灰核が淡く光っている――が、その輝きもどこか鈍い。
「灰が……眠ってるみたい。」
「眠ってる、か。」
アーレンは小さく頷いた。
「確かに、“沈黙”している。理が動かないんだ。」
「理って、そんなふうに止まるの?」
「本来ならありえない。
けど――誰かが“封じた”んだ。観測も、干渉も、何もかも。」
彼の声に、かすかな怒りが混じっていた。
符盤の上で灰が薄く揺れ、微細な火花を散らす。
⸻
ノアが不安そうに尋ねた。
「……帝国のしわざ?」
アーレンは小さく息を吐いた。
「恐らくはな。
理を封じ、灰を止める――“理封”以外に説明がつかない。」
「でも、そんなことしたら、世界が……」
「世界が死ぬ。理の流れが止まれば、命も動きを失う。
それを分かっていて、やったんだ。」
アーレンは空を見上げた。
灰雲の奥で、かすかに帝国の符標灯が見えた気がした。
「理を恐れ、閉ざした。
まるで……理そのものを“病原体”扱いしているようだ。」
⸻
そのころ、帝都ヴァルシュタイン。
エルシアは局長室の窓際に立ち、遠くの灰空を見つめていた。
理封から十七日。
帝国内では符術事故も止み、街に秩序が戻りつつあった。
だが、それは“静けさ”というより、“凍結”だった。
符盤は点灯せず、理導管の鼓動もない。
灰理局はただ、“生きた死体”のように機能を保っているだけだった。
机の上の報告書には、こう書かれていた。
《灰域の脈動、完全沈静。灰流反応、零。》
完璧な静寂。
完璧な“死”。
⸻
そのときだった。
封印塔の方向から、わずかな震動が伝わった。
エルシアは顔を上げた。
壁面に埋め込まれた符盤が、一瞬だけ点滅する。
光――それも、“理光”だ。
「……まさか。」
彼女は符盤に手をかざした。
波形は確かに微弱だが、明らかに生体理流に近い形を取っている。
鼓動のように、一定のリズムを刻んでいた。
「理が……応答してる。」
部下たちがざわめき始める。
「局長、理封陣の再起動を!?」「封印が破れたのでは――」
「違う。」
エルシアはきっぱりと遮った。
「理は破られていない。……“呼んでいる”の。」
灰の中から――
まるで、誰かの声を探すように。
⸻
アーレンはそのころ、灰原の丘で手を止めていた。
符盤の端がわずかに光っている。
封印以来、初めての反応だった。
「……波が戻った。」
符面の数値が小刻みに震える。
リュミナの灰核が、まるで応えるように脈打った。
「アーレン、聞こえる?」
「聞こえる……? 何をだ?」
「声。すごく遠いけど、確かに“呼ばれてる”。」
灰がふわりと舞い、彼女の手のひらに集まる。
指先に淡い光が走る。
――リュミナ。
微かな声。
それは、封じられたはずの理の向こうから届いていた。
アーレンは息を詰めた。
「理封下で……通信波が通るはずがない。」
「でも、聞こえるの。
“こえ”というより……“おもい”みたいに。」
灰核が明滅する。
リュミナの瞳に、帝都の光景が一瞬だけ映った。
⸻
同じ瞬間、エルシアもまた符盤に手を置いていた。
灰理塔の奥、沈黙したはずの理流が、かすかに脈を刻む。
――リュミナ。
音にならない声が、彼女の胸に響いた。
エルシアは目を閉じ、静かに息を呑む。
「……やっぱり、生きてるのね。」
遠く、灰の向こうで。
彼女とアーレンの符盤が、同じ周波で光っていた。
⸻
風が戻った。
長い沈黙のあと、世界がほんの少しだけ呼吸を始める。
灰が舞い、空を撫でる。
アーレンは符盤を見つめながら、かすかに笑った。
「封じても、理は死なない。
だったら……もう一度、“聴いて”やるさ。」
リュミナの灰核が淡く脈を打ち、
その波が、帝都へ――封印の下を通り、届いていった。
――帝国首都ヴァルシュタイン。
灰理局・中央塔は、再び騒然としていた。
理封の儀から二十日。
沈黙していた符盤群が、次々に勝手に起動を始めたのだ。
封印されたはずの理導管が脈動し、光を放っている。
「局長! 封印層第三環に異常! 符盤が自律的に再起動しています!」
「出力を落とせ!」
「落ちません、理流が“内側”から押し上げています!」
報告が飛び交う中、エルシア・ファロウ局長は中央制御壇に立っていた。
白衣の裾が灰光に照らされ、まるで幽鬼のように見える。
彼女の瞳だけが、真っ直ぐに符盤の心臓部を見据えていた。
「……やっぱり、そう来たわね。」
⸻
封印の陣が“外側から”ではなく、“内部から”破られつつあった。
灰理塔そのものが、まるで生きているかのように、
理の流れを再び取り戻そうとしている。
エルシアは符盤に触れ、封印陣の理式を解析する。
そこに浮かび上がった数値――「共鳴点:灰域北」。
「……灰域の中心と、再び繋がってる。」
その言葉に、部下たちが一斉にざわめいた。
「局長! 理封の再構築を行うべきです!」
「このままでは、再び“理災”が――」
「黙りなさい。」
その声は静かだが、確固としていた。
「これは暴走じゃない。――“応答”よ。」
「応答……?」
「理は眠っていた。でも、今また息をしている。
人がそれを“脅威”と呼ぶ限り、世界は何度でも止まる。」
彼女は封印解除の鍵を取り出し、符盤の中心に差し込んだ。
「……このまま、理を閉ざすわけにはいかない。」
⸻
同時刻――灰域北部。
アーレンは丘の上で、符盤の異常な脈動を感じていた。
符線が明滅を繰り返し、灰が脈を打つように光っている。
「……誰かが、“封”を揺らしてる。」
リュミナが静かに頷いた。
「感じる。……向こうで、誰かが理に触れてる。」
灰がざわめき、空気が振動する。
符盤が高音を放ち、リュミナの灰核が応答するように輝いた。
「アーレン、痛くない。むしろ……あたたかい。」
「……理が“呼吸”してる。」
世界が、再び動き出していた。
⸻
帝国灰理局・中央制御層。
警報符が鳴り響く中、一人の参謀が駆け込んできた。
「局長! 封印解除は許可されていません! これは反逆行為です!」
エルシアはその言葉に振り向き、静かに言った。
「……命令ではなく、“理”に従うだけよ。」
「理は命令に従いません!」
「そうね。だからこそ――人が耳を傾けるべきなの。」
彼女の手が鍵をひねる。
次の瞬間、塔全体が光に包まれた。
理導管が再び流れを取り戻し、空に向かって光が伸びる。
“理封”は、終わった。
⸻
灰域。
アーレンの符盤が一気に明るくなった。
理流の波が押し寄せ、灰が花のように開いていく。
「……封が解けた。」
彼は思わず息を呑む。
空が、灰の空が――久しぶりに“動いて”いた。
風が吹き、灰が舞い、
まるで世界そのものが歓喜しているように見えた。
リュミナがそっと空を見上げる。
「理が……帰ってきた。」
アーレンは目を細め、微かに笑った。
「いいや。――“目覚めた”んだ。」
⸻
帝国では、議会が騒然としていた。
「局長が封印を解除!? あの女は何を考えている!」
「理は暴走するぞ! 理災の再来だ!」
だが、エルシアは静かに言った。
「理は、もう人を裁かない。
裁かれるべきは、“理を恐れる人間”の方よ。」
窓の外、塔の光が空を貫く。
遠く灰域の方角――アーレンのいる地平へと伸びていた。
⸻
灰原。
リュミナの灰核が、帝都の光と共鳴する。
アーレンは符盤を閉じ、灰を一掴みした。
「聞こえるか、エルシア。
――“理はまだ生きている”。」
その灰は、まるで答えるように光を放った。
0
あなたにおすすめの小説

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!

【完結】ご都合主義で生きてます。-商売の力で世界を変える。カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく-
ジェルミ
ファンタジー
28歳でこの世を去った佐藤は、異世界の女神により転移を誘われる。
その条件として女神に『面白楽しく生活でき、苦労をせずお金を稼いで生きていくスキルがほしい』と無理難題を言うのだった。
困った女神が授けたのは、想像した事を実現できる創生魔法だった。
この味気ない世界を、創生魔法とカスタマイズ可能なストレージを使い、美味しくなる調味料や料理を作り世界を変えて行く。
はい、ご注文は?
調味料、それとも武器ですか?
カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく。
村を開拓し仲間を集め国を巻き込む産業を起こす。
いずれは世界へ通じる道を繋げるために。
※本作はカクヨム様にも掲載しております。

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」
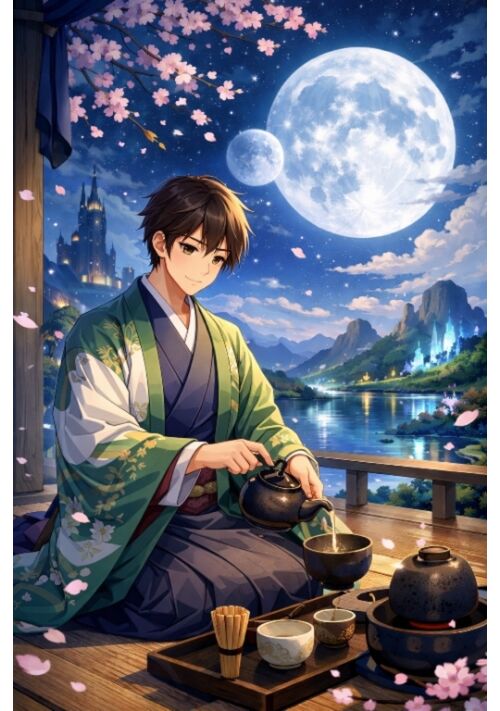
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

異世界転移物語
月夜
ファンタジー
このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー

第5皇子に転生した俺は前世の医学と知識や魔法を使い世界を変える。
黒ハット
ファンタジー
前世は予防医学の専門の医者が飛行機事故で結婚したばかりの妻と亡くなり異世界の帝国の皇帝の5番目の子供に転生する。子供の生存率50%という文明の遅れた世界に転生した主人公が前世の知識と魔法を使い乱世の世界を戦いながら前世の奥さんと巡り合い世界を変えて行く。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















