64 / 65
第6巻 再生の旅一灰の記憶-
第7話 再生の灯
しおりを挟む
――夜が明けていた。
灰市の空に、初めて陽光が差し込む。
灰の雲はまだ厚いが、その切れ間から覗く光は確かだった。
冷たかった街が、わずかに息を吹き返すように見えた。
リュミナは屋根の上に座り、東の空を見つめていた。
掌の中には、昨夜の灰の欠片。
今はもう光を放っていない。
それでも、心臓の奥がかすかに熱を帯びていた。
「……暖かいね。」
後ろから、アーレンの声がした。
彼も同じ空を見上げていた。
顔に付いた灰を拭いもせず、静かに息を吐く。
「不思議だな。
灰が冷たいものだと思っていたのに……今は、あの光の方が暖かく感じる。」
リュミナは微笑む。
「それが“祈り”の温度よ。
理じゃなくて、命が残した熱。」
⸻
二人は崩れた街を歩いた。
灰の街にはもう、人の声も機械の音もない。
けれど、沈黙の中に“生きている気配”があった。
風が流れ、灰の粒が陽の光を受けて輝く。
歩きながら、アーレンは手にしていた符盤を開く。
割れたままの装置の中で、微弱な反応が残っていた。
「……再構炉の残滓か。」
「動くの?」
リュミナが覗き込む。
「理はもう死んでる。けれど、灰律の波はまだ消えていない。
命の記録を燃やすための炉だったはずが……いまは、静かに脈打っている。」
リュミナはその光を見つめる。
「まるで、呼吸してるみたい。」
⸻
アーレンは灰を手に取り、炉の中へそっと落とした。
すると灰は光り、炉の符線が一瞬だけ淡く輝いた。
「……見ろ。まだ反応する。」
「それって、灰が“生きてる”ってこと?」
アーレンは頷いた。
「命令も理も消えたのに、反応を続けている。
もしかしたら、灰そのものが“生きたい”と願っているのかもしれない。」
リュミナはその言葉に、胸が震えた。
――灰は、命の終わりじゃない。祈りの形。
「じゃあ、再生させよう。
理でなく、祈りの力で。」
アーレンがリュミナを見つめた。
「……祈りで、理を動かすのか。」
「そう。
命を“造る”んじゃなくて、“還す”の。」
⸻
アーレンはゆっくりと頷いた。
そして、炉の符陣を展開する。
壊れたはずの符線が、リュミナの灯りに呼応して淡く光る。
リュミナは両手を合わせ、胸の灰核に意識を向けた。
そこに、ルシアの声がまだ微かに残っている。
――灰は、祈りを覚えている。
リュミナは目を閉じ、静かに言葉を紡いだ。
「どうか、この灰に、もう一度“息”を。」
符線が震え、灰炉の中心が脈動を始める。
光が走り、淡い炎が生まれる。
灰が燃えるのではなく――“灯る”。
⸻
アーレンは息を呑んだ。
それは炎ではない。
灰が、静かに光となって揺らめいている。
理では説明できない現象。
だが、確かに命のような温もりがあった。
「……これが、祈りの再生炉か。」
リュミナは微笑む。
「ううん。これは、“希望の炉”。」
灰の灯が、ふたりの頬を照らした。
朝の光がそれに重なり、灰市の空がほんの少し明るくなる。
⸻
アーレンはしばらくその光を見つめていたが、やがて呟いた。
「理で世界を造り変えるより……祈りで灯す方が、ずっと難しいな。」
「でも、きっとそのほうが、正しい。」
リュミナの声は柔らかかった。
「灰が夢を見ていたのは、きっと――誰かがまた灯をともす日を、待っていたから。」
風が吹く。
灰の灯が揺れ、遠くの空へと一筋の光を放った。
それはまるで、亡き者たちの祈りが、世界へ帰っていくように。
⸻
リュミナは目を閉じ、静かに手を合わせた。
アーレンもその隣で、わずかに頭を垂れる。
灰市の中心に、新しい光が生まれた。
それはまだ小さいが、確かに燃えている。
“理の終わり”の場所で、“祈りの始まり”が生まれた。
――風が、戻ってきた。
再生炉の灯がともってから、街の空気が変わった。
灰の粒が光を受けて舞い、
瓦礫の上に落ちるたび、そこに小さな光が生まれる。
リュミナは膝をつき、指先で灰をすくった。
掌の上で、灰は微かに脈動している。
冷たさの中に、確かに“息”があった。
「……生きてる。」
彼女が呟くと、隣でアーレンが静かに頷いた。
「灰が反応している。
理の残滓が――いや、違う。これは……もっと原始的な“反応”だ。」
アーレンは符盤を開き、反応波を観測する。
その波はまるで鼓動のように広がり、地面の奥深くまで伝わっていた。
⸻
遠くの建物の影で、崩れた壁がひとりでに震えた。
粉塵が落ち、光の粒が漏れる。
次いで、倒れた機械の残骸が、かすかに音を立てて動いた。
「……見ろ、灰が呼び合ってる。」
アーレンの声は驚きよりも、どこか感嘆に近かった。
「理が組んだ構造体じゃない。
それぞれの灰が、自分の“記憶”を探して動いてる。」
リュミナは目を細め、淡く光る灰を見つめた。
「まるで……心臓が動き出したみたい。」
⸻
風が通り抜けた。
冷たいはずの風が、どこか柔らかい。
灰の粒を運びながら、街の奥へ、さらに奥へと吹き抜けていく。
それは、まるで眠っていた大地が呼吸を始めたようだった。
「これが、再生……?」
リュミナの声は震えていた。
アーレンは炉の光を見つめたまま、低く答える。
「“灰は命の記録”だと、彼女は言ったな。
なら、この反応は――命が自分の続きを探している証拠だ。」
⸻
沈黙の中、灰の街が少しずつ変化していく。
倒壊した塔の根元から、細い蔦のような光が伸び、
瓦礫の隙間には、淡く芽吹くような輝きが生まれる。
リュミナはそれを見て、ゆっくりと立ち上がった。
「灰が、命を“憶えてる”んだわ。
それを忘れていたのは、きっと私たちの方。」
アーレンは静かに頷いた。
「壊すことを学びすぎて、治すことを信じなくなった。
でも、灰は……それでもまだ、生きたいと思っていたんだな。」
⸻
灰炉の灯がふたりを照らす。
その光に照らされた瓦礫の表面が、柔らかな色を帯びた。
冷たい灰色が、ゆっくりと淡い金色へと変わっていく。
「見て。……色が戻ってきた。」
リュミナの声がかすれる。
「灰が、灰のままじゃなくなる。
これが、“再生”なのね。」
アーレンは黙って空を見上げた。
雲の切れ間から光が差し、灰の街を包み込む。
⸻
「……あの光、久しぶりだな。」
アーレンが呟く。
「長い間、陽の色を忘れていた。」
リュミナは微笑んだ。
「灰の夢は、終わったのね。」
「いや――」
アーレンはゆっくりと首を振る。
「今、ようやく“目が覚めた”だけだ。」
その言葉に、リュミナは静かに頷いた。
風が灰を巻き上げ、朝の光の中できらめく。
世界が、もう一度息をした。
――灰が、風に乗っていた。
街の上を漂う灰は、もう沈黙の残滓ではない。
光を宿し、風に混ざり、どこまでも流れていく。
それは命の欠片のように淡く瞬きながら、遠くへと渡っていった。
リュミナは屋根の上でその光景を見ていた。
朝の風が頬を撫で、髪を揺らす。
灰炉の灯は静かに脈打ち、周囲の空気に柔らかな熱を帯びさせていた。
「……きっと、広がっていくわね。」
彼女の言葉に、アーレンは頷いた。
符盤の波形には、微かな灰律の反応が次々と記録されている。
「西でも、反応が出ている。
ここだけじゃない――灰層全体が“呼吸”を始めた。」
⸻
遠くの地平線の向こうで、雲が割れる。
灰の風が渦を巻き、光が差し込む。
崩壊した街並みの影でも、同じように小さな光が点滅していた。
それは、再生炉の灯と同じ律動。
“命の記憶”が連鎖している。
リュミナは目を閉じ、風の中に耳を澄ます。
灰の音、木々のざわめき、遠い大地の息づかい。
そのすべてが、ひとつの旋律を奏でているようだった。
「ねぇ、アーレン……聞こえる?」
彼女の声は囁きに近かった。
「灰が歌ってる。
“まだここにいる”って。」
アーレンは静かに頷く。
「聞こえる。
これは……理じゃない。
ただ、生きようとする音だ。」
⸻
ふと、足元の瓦礫の間から芽のような光が覗いた。
それは灰の中から生まれた、淡い緑の輝き。
リュミナが膝をつき、そっと触れると、指先にぬくもりが伝わった。
「これ……。」
アーレンが目を細める。
「灰の中の微生構造が再結合している。
理が再構しているんじゃない。
“灰そのものが、生きたいと思ってる”んだ。」
リュミナは小さく笑った。
「……命って、理よりずっと強いのね。」
⸻
風が再び吹いた。
光の粒が舞い上がり、空一面に散っていく。
その光が届いた先――
遠く離れた地でも、同じように灰の灯がともり始めていた。
誰もいない荒野の中で、壊れた研究塔の残骸が淡く光る。
朽ちた都市の地層では、灰の流れが静かに動き出す。
海の向こうでも、大気の流れが変わり始める。
灰が世界を繋いでいた。
かつて“終わり”と呼ばれたものが、今は“始まり”へと姿を変えていく。
⸻
リュミナは手のひらに舞い落ちた灰の粒を見つめる。
そこに微かな光が宿り、淡い拍動を刻んでいた。
まるで、誰かが小さく“ありがとう”と囁いているように。
「……世界が、覚えてくれてる。」
リュミナの声が震えた。
アーレンは静かに微笑み、炉の灯に手をかざす。
「灰は、忘れない。
どんな理よりも、祈りのほうが長く残る。
――だからこそ、もう一度、歩ける。」
⸻
陽が昇る。
灰の街に朝が訪れ、瓦礫が淡く光を反射する。
遠くで鳥の声が聞こえた。
それは、この世界で初めて響いた“音”だった。
リュミナはその声を聞きながら、小さく笑う。
「ねぇ、アーレン。
あの鳥も、灰の夢を見てたのかも。」
アーレンは頷いた。
「だとしたら、俺たちは……夢の続きを見てるんだろうな。」
風が吹く。
灰と光が混ざり、世界に新しい息を吹き込む。
灰が、再び生を歌いはじめた。
――陽が昇りきった。
灰市の空は、淡い金の色をしていた。
再生炉の灯は安定し、灰の流れも静まっている。
もう爆ぜるような光はない。
ただ、一定のリズムで淡く脈打ち、まるで心臓の鼓動のように街を照らしていた。
アーレンは炉の前に立ち、掌をかざした。
光が指先に触れ、微かな温もりが伝わる。
“命を造る”ために生まれた炉が、今は“命を見守る”ために灯っている。
「……これで、ようやく終わったのか。」
彼の声は低く、静かだった。
隣でリュミナが微笑む。
「いいえ、始まったの。灰は夢を見終えたけれど、
今度は“現実を生きる番”だから。」
⸻
二人は並んで歩き出した。
崩れた街の通りを抜けると、風が流れ込んでくる。
灰が陽光を反射して舞い、金の粒のように空を満たした。
「……もう誰もいない街なのに、不思議だな。」
アーレンは立ち止まり、瓦礫を見渡す。
「音がする。
ここにいた人たちの、呼吸のような……。」
リュミナは目を閉じた。
「灰が憶えてるの。
祈りも、笑いも、痛みも、全部。
でもそれは、過去じゃなくて“今を生かすため”の記録。」
⸻
丘の上まで登ると、街全体が見渡せた。
あちこちに小さな光が灯っている。
まるで夜空を逆さにしたような景色。
その中心に、再生炉の灯が柔らかく光っていた。
アーレンは長い息を吐き、ゆっくりと言葉を探す。
「……ずっと間違えていた気がする。
命は創るものじゃなく、
こうして“見届ける”ためにあるんだな。」
リュミナは微笑む。
「あなたが見届けた命は、ちゃんと生きてたわ。
灰の中で、ずっと。」
彼は少しだけ笑って、頷いた。
「なら……この研究も、まだ終わらせるわけにはいかないな。」
⸻
彼は懐から小さな符片を取り出した。
破損した理式を一部削り、新しい符を刻む。
それはかつて“創造式”と呼ばれたものの一部。
だが今は、まったく違う名が刻まれた。
――〈記録〉
アーレンはその符を灰の中へ置き、手を合わせる。
「これからは、理を造るんじゃない。
命が何を残すのか、その“記録者”として生きる。」
風が符を撫で、灰の上に淡い光が流れる。
その符は静かに溶け、炉の灯と一つになった。
⸻
リュミナは空を見上げた。
陽光の中で、灰が輝きながら流れていく。
遠くの空に、白い鳥が一羽、舞い上がっていた。
「行こう、アーレン。」
彼女が微笑む。
「この灯が広がっていくなら、次の場所にも届くはず。」
アーレンは一度だけ振り返り、
再生炉の光を見つめた。
「……あぁ。もう、恐れない。」
灰を踏みしめ、二人は歩き出す。
背後で、風が吹いた。
炉の灯が揺れ、灰が舞い上がる。
それはまるで、誰かが“いってらっしゃい”と囁いたようだった。
⸻
リュミナは小さく呟く。
「灰が生まれ変わるたびに、きっと世界も少しだけ温かくなる。」
アーレンは頷いた。
「それを見届けよう。
――それが、俺たちの研究だ。」
朝の光が、丘の向こうまで満ちていく。
灰の街は静かに息をしていた。
そして、新しい一日が始まった。
灰市の空に、初めて陽光が差し込む。
灰の雲はまだ厚いが、その切れ間から覗く光は確かだった。
冷たかった街が、わずかに息を吹き返すように見えた。
リュミナは屋根の上に座り、東の空を見つめていた。
掌の中には、昨夜の灰の欠片。
今はもう光を放っていない。
それでも、心臓の奥がかすかに熱を帯びていた。
「……暖かいね。」
後ろから、アーレンの声がした。
彼も同じ空を見上げていた。
顔に付いた灰を拭いもせず、静かに息を吐く。
「不思議だな。
灰が冷たいものだと思っていたのに……今は、あの光の方が暖かく感じる。」
リュミナは微笑む。
「それが“祈り”の温度よ。
理じゃなくて、命が残した熱。」
⸻
二人は崩れた街を歩いた。
灰の街にはもう、人の声も機械の音もない。
けれど、沈黙の中に“生きている気配”があった。
風が流れ、灰の粒が陽の光を受けて輝く。
歩きながら、アーレンは手にしていた符盤を開く。
割れたままの装置の中で、微弱な反応が残っていた。
「……再構炉の残滓か。」
「動くの?」
リュミナが覗き込む。
「理はもう死んでる。けれど、灰律の波はまだ消えていない。
命の記録を燃やすための炉だったはずが……いまは、静かに脈打っている。」
リュミナはその光を見つめる。
「まるで、呼吸してるみたい。」
⸻
アーレンは灰を手に取り、炉の中へそっと落とした。
すると灰は光り、炉の符線が一瞬だけ淡く輝いた。
「……見ろ。まだ反応する。」
「それって、灰が“生きてる”ってこと?」
アーレンは頷いた。
「命令も理も消えたのに、反応を続けている。
もしかしたら、灰そのものが“生きたい”と願っているのかもしれない。」
リュミナはその言葉に、胸が震えた。
――灰は、命の終わりじゃない。祈りの形。
「じゃあ、再生させよう。
理でなく、祈りの力で。」
アーレンがリュミナを見つめた。
「……祈りで、理を動かすのか。」
「そう。
命を“造る”んじゃなくて、“還す”の。」
⸻
アーレンはゆっくりと頷いた。
そして、炉の符陣を展開する。
壊れたはずの符線が、リュミナの灯りに呼応して淡く光る。
リュミナは両手を合わせ、胸の灰核に意識を向けた。
そこに、ルシアの声がまだ微かに残っている。
――灰は、祈りを覚えている。
リュミナは目を閉じ、静かに言葉を紡いだ。
「どうか、この灰に、もう一度“息”を。」
符線が震え、灰炉の中心が脈動を始める。
光が走り、淡い炎が生まれる。
灰が燃えるのではなく――“灯る”。
⸻
アーレンは息を呑んだ。
それは炎ではない。
灰が、静かに光となって揺らめいている。
理では説明できない現象。
だが、確かに命のような温もりがあった。
「……これが、祈りの再生炉か。」
リュミナは微笑む。
「ううん。これは、“希望の炉”。」
灰の灯が、ふたりの頬を照らした。
朝の光がそれに重なり、灰市の空がほんの少し明るくなる。
⸻
アーレンはしばらくその光を見つめていたが、やがて呟いた。
「理で世界を造り変えるより……祈りで灯す方が、ずっと難しいな。」
「でも、きっとそのほうが、正しい。」
リュミナの声は柔らかかった。
「灰が夢を見ていたのは、きっと――誰かがまた灯をともす日を、待っていたから。」
風が吹く。
灰の灯が揺れ、遠くの空へと一筋の光を放った。
それはまるで、亡き者たちの祈りが、世界へ帰っていくように。
⸻
リュミナは目を閉じ、静かに手を合わせた。
アーレンもその隣で、わずかに頭を垂れる。
灰市の中心に、新しい光が生まれた。
それはまだ小さいが、確かに燃えている。
“理の終わり”の場所で、“祈りの始まり”が生まれた。
――風が、戻ってきた。
再生炉の灯がともってから、街の空気が変わった。
灰の粒が光を受けて舞い、
瓦礫の上に落ちるたび、そこに小さな光が生まれる。
リュミナは膝をつき、指先で灰をすくった。
掌の上で、灰は微かに脈動している。
冷たさの中に、確かに“息”があった。
「……生きてる。」
彼女が呟くと、隣でアーレンが静かに頷いた。
「灰が反応している。
理の残滓が――いや、違う。これは……もっと原始的な“反応”だ。」
アーレンは符盤を開き、反応波を観測する。
その波はまるで鼓動のように広がり、地面の奥深くまで伝わっていた。
⸻
遠くの建物の影で、崩れた壁がひとりでに震えた。
粉塵が落ち、光の粒が漏れる。
次いで、倒れた機械の残骸が、かすかに音を立てて動いた。
「……見ろ、灰が呼び合ってる。」
アーレンの声は驚きよりも、どこか感嘆に近かった。
「理が組んだ構造体じゃない。
それぞれの灰が、自分の“記憶”を探して動いてる。」
リュミナは目を細め、淡く光る灰を見つめた。
「まるで……心臓が動き出したみたい。」
⸻
風が通り抜けた。
冷たいはずの風が、どこか柔らかい。
灰の粒を運びながら、街の奥へ、さらに奥へと吹き抜けていく。
それは、まるで眠っていた大地が呼吸を始めたようだった。
「これが、再生……?」
リュミナの声は震えていた。
アーレンは炉の光を見つめたまま、低く答える。
「“灰は命の記録”だと、彼女は言ったな。
なら、この反応は――命が自分の続きを探している証拠だ。」
⸻
沈黙の中、灰の街が少しずつ変化していく。
倒壊した塔の根元から、細い蔦のような光が伸び、
瓦礫の隙間には、淡く芽吹くような輝きが生まれる。
リュミナはそれを見て、ゆっくりと立ち上がった。
「灰が、命を“憶えてる”んだわ。
それを忘れていたのは、きっと私たちの方。」
アーレンは静かに頷いた。
「壊すことを学びすぎて、治すことを信じなくなった。
でも、灰は……それでもまだ、生きたいと思っていたんだな。」
⸻
灰炉の灯がふたりを照らす。
その光に照らされた瓦礫の表面が、柔らかな色を帯びた。
冷たい灰色が、ゆっくりと淡い金色へと変わっていく。
「見て。……色が戻ってきた。」
リュミナの声がかすれる。
「灰が、灰のままじゃなくなる。
これが、“再生”なのね。」
アーレンは黙って空を見上げた。
雲の切れ間から光が差し、灰の街を包み込む。
⸻
「……あの光、久しぶりだな。」
アーレンが呟く。
「長い間、陽の色を忘れていた。」
リュミナは微笑んだ。
「灰の夢は、終わったのね。」
「いや――」
アーレンはゆっくりと首を振る。
「今、ようやく“目が覚めた”だけだ。」
その言葉に、リュミナは静かに頷いた。
風が灰を巻き上げ、朝の光の中できらめく。
世界が、もう一度息をした。
――灰が、風に乗っていた。
街の上を漂う灰は、もう沈黙の残滓ではない。
光を宿し、風に混ざり、どこまでも流れていく。
それは命の欠片のように淡く瞬きながら、遠くへと渡っていった。
リュミナは屋根の上でその光景を見ていた。
朝の風が頬を撫で、髪を揺らす。
灰炉の灯は静かに脈打ち、周囲の空気に柔らかな熱を帯びさせていた。
「……きっと、広がっていくわね。」
彼女の言葉に、アーレンは頷いた。
符盤の波形には、微かな灰律の反応が次々と記録されている。
「西でも、反応が出ている。
ここだけじゃない――灰層全体が“呼吸”を始めた。」
⸻
遠くの地平線の向こうで、雲が割れる。
灰の風が渦を巻き、光が差し込む。
崩壊した街並みの影でも、同じように小さな光が点滅していた。
それは、再生炉の灯と同じ律動。
“命の記憶”が連鎖している。
リュミナは目を閉じ、風の中に耳を澄ます。
灰の音、木々のざわめき、遠い大地の息づかい。
そのすべてが、ひとつの旋律を奏でているようだった。
「ねぇ、アーレン……聞こえる?」
彼女の声は囁きに近かった。
「灰が歌ってる。
“まだここにいる”って。」
アーレンは静かに頷く。
「聞こえる。
これは……理じゃない。
ただ、生きようとする音だ。」
⸻
ふと、足元の瓦礫の間から芽のような光が覗いた。
それは灰の中から生まれた、淡い緑の輝き。
リュミナが膝をつき、そっと触れると、指先にぬくもりが伝わった。
「これ……。」
アーレンが目を細める。
「灰の中の微生構造が再結合している。
理が再構しているんじゃない。
“灰そのものが、生きたいと思ってる”んだ。」
リュミナは小さく笑った。
「……命って、理よりずっと強いのね。」
⸻
風が再び吹いた。
光の粒が舞い上がり、空一面に散っていく。
その光が届いた先――
遠く離れた地でも、同じように灰の灯がともり始めていた。
誰もいない荒野の中で、壊れた研究塔の残骸が淡く光る。
朽ちた都市の地層では、灰の流れが静かに動き出す。
海の向こうでも、大気の流れが変わり始める。
灰が世界を繋いでいた。
かつて“終わり”と呼ばれたものが、今は“始まり”へと姿を変えていく。
⸻
リュミナは手のひらに舞い落ちた灰の粒を見つめる。
そこに微かな光が宿り、淡い拍動を刻んでいた。
まるで、誰かが小さく“ありがとう”と囁いているように。
「……世界が、覚えてくれてる。」
リュミナの声が震えた。
アーレンは静かに微笑み、炉の灯に手をかざす。
「灰は、忘れない。
どんな理よりも、祈りのほうが長く残る。
――だからこそ、もう一度、歩ける。」
⸻
陽が昇る。
灰の街に朝が訪れ、瓦礫が淡く光を反射する。
遠くで鳥の声が聞こえた。
それは、この世界で初めて響いた“音”だった。
リュミナはその声を聞きながら、小さく笑う。
「ねぇ、アーレン。
あの鳥も、灰の夢を見てたのかも。」
アーレンは頷いた。
「だとしたら、俺たちは……夢の続きを見てるんだろうな。」
風が吹く。
灰と光が混ざり、世界に新しい息を吹き込む。
灰が、再び生を歌いはじめた。
――陽が昇りきった。
灰市の空は、淡い金の色をしていた。
再生炉の灯は安定し、灰の流れも静まっている。
もう爆ぜるような光はない。
ただ、一定のリズムで淡く脈打ち、まるで心臓の鼓動のように街を照らしていた。
アーレンは炉の前に立ち、掌をかざした。
光が指先に触れ、微かな温もりが伝わる。
“命を造る”ために生まれた炉が、今は“命を見守る”ために灯っている。
「……これで、ようやく終わったのか。」
彼の声は低く、静かだった。
隣でリュミナが微笑む。
「いいえ、始まったの。灰は夢を見終えたけれど、
今度は“現実を生きる番”だから。」
⸻
二人は並んで歩き出した。
崩れた街の通りを抜けると、風が流れ込んでくる。
灰が陽光を反射して舞い、金の粒のように空を満たした。
「……もう誰もいない街なのに、不思議だな。」
アーレンは立ち止まり、瓦礫を見渡す。
「音がする。
ここにいた人たちの、呼吸のような……。」
リュミナは目を閉じた。
「灰が憶えてるの。
祈りも、笑いも、痛みも、全部。
でもそれは、過去じゃなくて“今を生かすため”の記録。」
⸻
丘の上まで登ると、街全体が見渡せた。
あちこちに小さな光が灯っている。
まるで夜空を逆さにしたような景色。
その中心に、再生炉の灯が柔らかく光っていた。
アーレンは長い息を吐き、ゆっくりと言葉を探す。
「……ずっと間違えていた気がする。
命は創るものじゃなく、
こうして“見届ける”ためにあるんだな。」
リュミナは微笑む。
「あなたが見届けた命は、ちゃんと生きてたわ。
灰の中で、ずっと。」
彼は少しだけ笑って、頷いた。
「なら……この研究も、まだ終わらせるわけにはいかないな。」
⸻
彼は懐から小さな符片を取り出した。
破損した理式を一部削り、新しい符を刻む。
それはかつて“創造式”と呼ばれたものの一部。
だが今は、まったく違う名が刻まれた。
――〈記録〉
アーレンはその符を灰の中へ置き、手を合わせる。
「これからは、理を造るんじゃない。
命が何を残すのか、その“記録者”として生きる。」
風が符を撫で、灰の上に淡い光が流れる。
その符は静かに溶け、炉の灯と一つになった。
⸻
リュミナは空を見上げた。
陽光の中で、灰が輝きながら流れていく。
遠くの空に、白い鳥が一羽、舞い上がっていた。
「行こう、アーレン。」
彼女が微笑む。
「この灯が広がっていくなら、次の場所にも届くはず。」
アーレンは一度だけ振り返り、
再生炉の光を見つめた。
「……あぁ。もう、恐れない。」
灰を踏みしめ、二人は歩き出す。
背後で、風が吹いた。
炉の灯が揺れ、灰が舞い上がる。
それはまるで、誰かが“いってらっしゃい”と囁いたようだった。
⸻
リュミナは小さく呟く。
「灰が生まれ変わるたびに、きっと世界も少しだけ温かくなる。」
アーレンは頷いた。
「それを見届けよう。
――それが、俺たちの研究だ。」
朝の光が、丘の向こうまで満ちていく。
灰の街は静かに息をしていた。
そして、新しい一日が始まった。
0
あなたにおすすめの小説

正しい聖女さまのつくりかた
みるくてぃー
ファンタジー
王家で育てられた(自称)平民少女が、学園で起こすハチャメチャ学園(ラブ?)コメディ。
同じ年の第二王女をはじめ、優しい兄姉(第一王女と王子)に見守られながら成長していく。
一般常識が一切通用しない少女に友人達は振り回されてばかり、「アリスちゃんメイドを目指すのになぜダンスや淑女教育が必要なの!?」
そこには人知れず王妃と王女達によるとある計画が進められていた!
果たしてアリスは無事に立派なメイドになれるのか!? たぶん無理かなぁ……。
聖女シリーズ第一弾「正しい聖女さまのつくりかた」

企業再生のプロ、倒産寸前の貧乏伯爵に転生する
namisan
ファンタジー
数々の倒産寸前の企業を立て直してきた敏腕コンサルタントの男は、過労の末に命を落とし、異世界で目を覚ます。
転生先は、帝国北部の辺境にあるアインハルト伯爵家の若き当主、アレク。
しかし、そこは「帝国の重荷」と蔑まれる、借金まみれで領民が飢える極貧領地だった。
凍える屋敷、迫りくる借金取り、絶望する家臣たち。
詰みかけた状況の中で、アレクは独自のユニーク魔法【構造解析(アナライズ)】に目覚める。
それは、物体の構造のみならず、組織の欠陥や魔法術式の不備さえも見抜き、再構築(クラフト)するチート能力だった。
「問題ない。この程度の赤字、前世の案件に比べれば可愛いものだ」
前世の経営知識と規格外の魔法で、アレクは領地の大改革に乗り出す。
痩せた土地を改良し、特産品を生み出し、隣国の経済さえも掌握していくアレク。
そんな彼の手腕に惹かれ、集まってくるのは一癖も二癖もある高貴な美女たち。
これは、底辺から這い上がった若き伯爵が、最強の布陣で自領を帝国一の都市へと発展させ、栄華を極める物語。

【完結】ご都合主義で生きてます。-商売の力で世界を変える。カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく-
ジェルミ
ファンタジー
28歳でこの世を去った佐藤は、異世界の女神により転移を誘われる。
その条件として女神に『面白楽しく生活でき、苦労をせずお金を稼いで生きていくスキルがほしい』と無理難題を言うのだった。
困った女神が授けたのは、想像した事を実現できる創生魔法だった。
この味気ない世界を、創生魔法とカスタマイズ可能なストレージを使い、美味しくなる調味料や料理を作り世界を変えて行く。
はい、ご注文は?
調味料、それとも武器ですか?
カスタマイズ可能なストレージで世の中を変えていく。
村を開拓し仲間を集め国を巻き込む産業を起こす。
いずれは世界へ通じる道を繋げるために。
※本作はカクヨム様にも掲載しております。

異世界転移物語
月夜
ファンタジー
このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

竜皇女と呼ばれた娘
Aoi
ファンタジー
この世に生を授かり間もなくして捨てられしまった赤子は洞窟を棲み処にしていた竜イグニスに拾われヴァイオレットと名づけられ育てられた
ヴァイオレットはイグニスともう一頭の竜バシリッサの元でスクスクと育ち十六の歳になる
その歳まで人間と交流する機会がなかったヴァイオレットは友達を作る為に学校に通うことを望んだ
国で一番のグレディス魔法学校の入学試験を受け無事入学を果たし念願の友達も作れて順風満帆な生活を送っていたが、ある日衝撃の事実を告げられ……

【完結】異世界で魔道具チートでのんびり商売生活
シマセイ
ファンタジー
大学生・誠也は工事現場の穴に落ちて異世界へ。 物体に魔力を付与できるチートスキルを見つけ、 能力を隠しつつ魔道具を作って商業ギルドで商売開始。 のんびりスローライフを目指す毎日が幕を開ける!
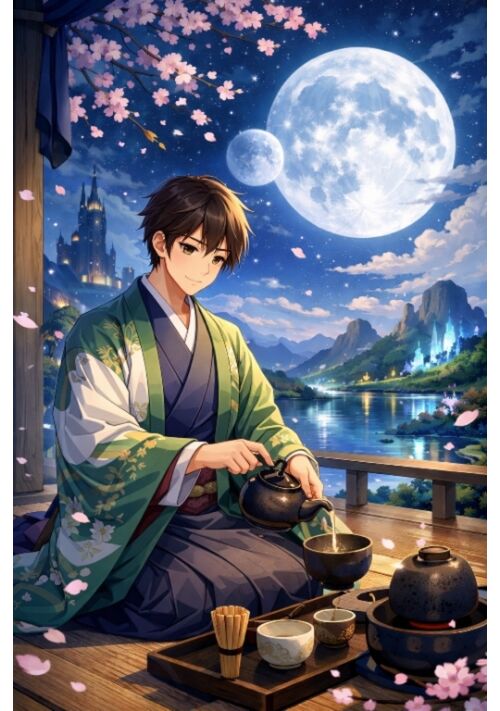
水神飛鳥の異世界茶会記 ~戦闘力ゼロの茶道家が、神業の【陶芸】と至高の【和菓子】で、野蛮な異世界を「癒やし」で侵略するようです~
月神世一
ファンタジー
「剣を下ろし、靴を脱いでください。……茶が入りましたよ」
猫を助けて死んだ茶道家・水神飛鳥(23歳)。
彼が転生したのは、魔法と闘気が支配する弱肉強食のファンタジー世界だった。
チート能力? 攻撃魔法?
いいえ、彼が手にしたのは「茶道具一式」と「陶芸セット」が出せるスキルだけ。
「私がすべき事は、戦うことではありません。一服の茶を出し、心を整えることです」
ゴブリン相手に正座で茶を勧め、
戦場のど真ん中に「結界(茶室)」を展開して空気を変え、
牢屋にぶち込まれれば、そこを「隠れ家カフェ」にリフォームして看守を餌付けする。
そんな彼の振る舞う、異世界には存在しない「極上の甘味(カステラ・羊羹)」と、魔法よりも美しい「茶器」に、武闘派の獣人女王も、強欲な大商人も、次第に心を(胃袋を)掴まれていき……?
「野暮な振る舞いは許しません」
これは、ブレない茶道家が、殺伐とした異世界を「おもてなし」で平和に変えていく、一期一会の物語。

【完結】異世界で神の元カノのゴミ屋敷を片付けたら世界の秘密が出てきました
小豆缶
ファンタジー
父の遺したゴミ屋敷を片付けていたはずが、気づけば異世界に転移していた私・飛鳥。
しかも、神の元カノと顔がそっくりという理由で、いきなり死刑寸前!?
助けてくれた太陽神ソラリクスから頼まれた仕事は、
「500年前に別れた元恋人のゴミ屋敷を片付けてほしい」というとんでもない依頼だった。
幽霊になった元神、罠だらけの屋敷、歪んだ世界のシステム。
ポンコツだけど諦めの悪い主人公が、ゴミ屋敷を片付けながら異世界の謎を暴いていく!
ほのぼのお仕事×異世界コメディ×世界の秘密解明ファンタジー
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















