4 / 27
第一章 夏
第四話 騎士
しおりを挟む
女が震える手を握り締める。
止めようとしていると見えて、少しだけ震えが小さくなる。
だが、直ぐに握る前より大きくなった。
俺は無意識にもう一歩退いた。
女が胸の前で腕を交差させながら少し顔を上げて上目遣いで睨み付けてくる。
顔を真っ赤に紅潮させて若干涙目だ。
また来るか?
俺は軽く身構える。
しかし、女は気を静めるように「はああ」と息を吐くと、両膝を突き、両手を突いた。
更に額を床に着ける。
「先刻は申し訳ないことをした!」
土下座であった。
「問答無用で魔法を放ち、更にそれを謝罪せねばならぬ相手に手を上げるなど騎士にあるまじき行い。
恥じ入るばかりだ」
「騎士……?」
意外な言葉を聞いて口は鸚鵡返しに問いを返すが、視線は女に釘付けにされてしまった。
けしからん胸が身体と頭に隠れて見えなくなった一方、背中から尻にかけてが目に入る。
熟し切っていないながらもウエストからヒップにかけての艶めかしい曲線が着けている革の防具の上からも判る。
土下座に慣れていないと見えて尻を突き上げるような姿勢になっているので余計にだ。
正面からはよく判らなかった腰の細さも一入である。
「吾輩はホーリー・シュリーマー。
騎士の称号を戴き、王家に仕えている者だ」
女は律儀に答えた。
その律儀さは確かに騎士っぽい。
騎士は王宮に勤める兵士にあって上級職のようなもので、規律と誠実さが求められるらしい。
王宮に行ったことなんて無いので「らしい」としか判らないだけとも言う。
そして妙に力が強いのも納得だ。
逆に納得できないのは振る舞いの方。
騎士ならもっと冷静沈着であって欲しかった。
土下座をする騎士も聞いたことが無い。
「らしい」でしか知らないのだから、聞いたことが無いのも当然ではあるが。
はたまたこうして油断させておいて一気に命を狙ってくる算段か。
……とは流石になりそうにないので、少し俺も落ち着いた。
「その騎士さんが、いきなり魔法を撃ったのか」
「う……」
ホーリーが小さく呻いた。
「お、男に、は、裸を見られたのが、は、初めてで、ど、動揺してしまったのだ」
舌を噛み噛みして目に余る動揺ぶりである。
言葉に詐りは無さそうだ。
しかしだ。
「恥ずかしいならあんな所で水浴びなんてするなよ。
青髪の癖に」
「吾輩は火魔法を使うのだ」
「はあ?」
ホーリーの答えに思わず素っ頓狂な声が出た。
青髪が水魔法なのは殆ど常識と言って良い。
氷も青髪だが希少な存在だ。
他の例外は更に希少で、火に至っては想像もできない。
疑問の答えはホーリーの口から紡がれた。
「あまり知られていないが、火魔法は黄色より高い温度で白、青となる。
吾輩も不思議に思って調べたのだ」
俄には信じられなかったが、それは真実だと俺の本能が囁いている。
あの時はあまりに一瞬で痛みすら知覚できないほどだったが、ほんのりと熱を感じた覚えが有る。
炎の中に一瞬だけ手を突っ込んだような感覚だ。
だとすれば、どれ程温度が高いのか。
そのお陰で苦痛を感じずに済んだのでもあるが、些か背筋が冷たい。
「どの位の温度なんだ?」
「極力絞っても岩が融ける」
「はあ?」
さっきから変な声ばかりが口から出てしまって些か羞恥を禁じ得ない。
それはそれとして明らかに戦闘以外には使えそうにないものだ。
鍛冶にも温度が高すぎて無理だろう。
岩を融かすような場面がどこかに有ればまた別かも知れないが、そんな場面が草草有るとも思えない。
騎士と言う職業を鑑みれば戦闘特化はむしろ好ましいかも知れないが。
だからそこは納得した。
動揺していたのなら調節も疎かになっていたことだろう。
俺は一瞬で灰になったに違いない。
「魔法については解った」
しかしまだまだ解らないことが有る。
町を巡回する兵士でさえ二人一組で行動する。
遠くから職務で来たのなら騎士であっても独りだけとはおかしい。
「どうしてあの泉に独りで居たんだ?」
ホーリーは沈黙した。
答えるべきかどうかを悩んでいるのか、尻が悩ましげに揺れる。
暫くしてその揺れが治まった。
「頼みが有る」
ホーリーは答えの代わりに願い事を言い出した。
「吾輩の魔法が当たっても無事でいられるその術を教えて貰いたい」
何を言い出すやらだ。
それを教えるとは即ち俺の魔法を教えることなのだから、易々と教えられるものではない。
少し話を逸らしてうやむやにできないものか。
「当たったと決め付けているようだが、外れたとは考えないのか?」
「それは無い」
やけにきっぱり言い切った。
「どうして?」
「魔法が当たった痕跡が地面や木々に残されていなかった。
その場から消えた人物に確かに当たったのだ」
「む……」
唸らざるを得なかった。
魔法を発動可能な範囲は個人によって異なるが、身体からの距離は短かければ腕の長さまで、長くてもその倍までとされる。
それより遠い場所に発現させるには魔法を投射する。
投射された魔法は軌跡を描いて飛び、発現するのは予め距離を定めたものならその距離で、そうでないものは何かに当たった時点でとなる。
当たらなければある程度の距離を進んだ後に霧散する。
あの時の二人の距離はホーリーが非常識な発動範囲を持っていないのなら投射が必要な距離だった。
そして泉の周囲は森の木立に覆われている。
つまりは俺に当たらなければどこかの木が燃えていた。
もしくは魔法が当たった部分だけ灰も残さず抉れたか。
「背負子とこのナイフだけが残っていた」
ホーリーが腰に提げていたポーチから右手だけでナイフを取り出して差し出して来た。
柄は殆ど喪われているが、鞘にははっきりと見覚えがある。
俺の愛用品だ。
背負子とナイフを回収しているのを見せられれば、周囲をしっかり確認したと認めざるを得ない。
そして確信している相手を煙に巻けるほどの弁舌は俺には無い。
だから逆に判らないことを質問する。
「その術がどんなものか予想しているのか?」
「うむ。
最も可能性が高いと考えているのは、ナイフを身代わりとして魔法に当て、魔法が発現する時の光で周囲が見えなくなっている隙に姿を暗ませたと言うものだ」
そんなことができるのなら俺が知りたい。
ともあれホーリーはあれが身体能力と技術によるものと考えたらしい。
もしそうなら身体能力が俺より明らかに上のホーリーなら容易に修得できよう。
技術じゃないので無理だが。
魔法で有るとするなら闇魔法の一種だろうか。
闇魔法とは酷く曖昧な魔法で、僅かながら人の精神に作用するものや虚像を作るものなどが有ると言う。
俺の親父が闇魔法の使い手で、人の嘘を知るものだった。
強い魔法ではないが、取り引きにおいてぼったくられることが無い。
それで雑貨屋を営んでいた訳だ。
そんな闇魔法の中にはホーリーの言った通りの働きをするものが有るかも知れない。
勿論「かも知れない」だけであり、譬え俺の魔法がそうだったとしても答えは決まっている。
「無理だ」
きっぱりと答えた。
魔法の副作用だから伝授などできない。
するとホーリーが顔を上げ、「駄目なのか?」と恨めしげに涙目で訴えてくる。
一瞬息が詰まった。
本当に美少女は狡い。
ぐらんぐらんに心を揺さぶってくる。
揺らす方が悪いと言えばそれまでだが、はらはらと儚く花びらが散るかの如き風情を見せ付けられて「揺らすな」と言うのも酷だ。
ホーリーが顔を上げたことでまた視界に入ったけしからん峡谷も心を揺さぶってくる。
ここで更にけしからん揺さぶりを畳み掛けられていようものなら堪えられないところだった。
幸いなことにその最後の揺さぶりは無い。
「無理なものは無理だ」
「駄目なのか」
ホーリーは上体を起こして右膝を浮かせ、尻を床に着けてぺたんと座った。
左手を股の間に、右手を右脚の外側に突く。
土下座は願い事込みだった模様。
しかし座った姿は土下座よりも破壊力が有る。
何と狂おしいほどに萌える姿なのだろう。
「もう何でも教えちゃう」と口から溢れそうになる。
先刻に町の通りで俺が一方的に悪者にされたのも頷けると言うものだ。
これが噂に聞くハニートラップか!
内心で呪文のように唱えて気を落ち着かせた。
「それを知りたい理由は何なんだ?」
そう問うと、ホーリーは少しびっくりしたように目を瞬かせた。
止めようとしていると見えて、少しだけ震えが小さくなる。
だが、直ぐに握る前より大きくなった。
俺は無意識にもう一歩退いた。
女が胸の前で腕を交差させながら少し顔を上げて上目遣いで睨み付けてくる。
顔を真っ赤に紅潮させて若干涙目だ。
また来るか?
俺は軽く身構える。
しかし、女は気を静めるように「はああ」と息を吐くと、両膝を突き、両手を突いた。
更に額を床に着ける。
「先刻は申し訳ないことをした!」
土下座であった。
「問答無用で魔法を放ち、更にそれを謝罪せねばならぬ相手に手を上げるなど騎士にあるまじき行い。
恥じ入るばかりだ」
「騎士……?」
意外な言葉を聞いて口は鸚鵡返しに問いを返すが、視線は女に釘付けにされてしまった。
けしからん胸が身体と頭に隠れて見えなくなった一方、背中から尻にかけてが目に入る。
熟し切っていないながらもウエストからヒップにかけての艶めかしい曲線が着けている革の防具の上からも判る。
土下座に慣れていないと見えて尻を突き上げるような姿勢になっているので余計にだ。
正面からはよく判らなかった腰の細さも一入である。
「吾輩はホーリー・シュリーマー。
騎士の称号を戴き、王家に仕えている者だ」
女は律儀に答えた。
その律儀さは確かに騎士っぽい。
騎士は王宮に勤める兵士にあって上級職のようなもので、規律と誠実さが求められるらしい。
王宮に行ったことなんて無いので「らしい」としか判らないだけとも言う。
そして妙に力が強いのも納得だ。
逆に納得できないのは振る舞いの方。
騎士ならもっと冷静沈着であって欲しかった。
土下座をする騎士も聞いたことが無い。
「らしい」でしか知らないのだから、聞いたことが無いのも当然ではあるが。
はたまたこうして油断させておいて一気に命を狙ってくる算段か。
……とは流石になりそうにないので、少し俺も落ち着いた。
「その騎士さんが、いきなり魔法を撃ったのか」
「う……」
ホーリーが小さく呻いた。
「お、男に、は、裸を見られたのが、は、初めてで、ど、動揺してしまったのだ」
舌を噛み噛みして目に余る動揺ぶりである。
言葉に詐りは無さそうだ。
しかしだ。
「恥ずかしいならあんな所で水浴びなんてするなよ。
青髪の癖に」
「吾輩は火魔法を使うのだ」
「はあ?」
ホーリーの答えに思わず素っ頓狂な声が出た。
青髪が水魔法なのは殆ど常識と言って良い。
氷も青髪だが希少な存在だ。
他の例外は更に希少で、火に至っては想像もできない。
疑問の答えはホーリーの口から紡がれた。
「あまり知られていないが、火魔法は黄色より高い温度で白、青となる。
吾輩も不思議に思って調べたのだ」
俄には信じられなかったが、それは真実だと俺の本能が囁いている。
あの時はあまりに一瞬で痛みすら知覚できないほどだったが、ほんのりと熱を感じた覚えが有る。
炎の中に一瞬だけ手を突っ込んだような感覚だ。
だとすれば、どれ程温度が高いのか。
そのお陰で苦痛を感じずに済んだのでもあるが、些か背筋が冷たい。
「どの位の温度なんだ?」
「極力絞っても岩が融ける」
「はあ?」
さっきから変な声ばかりが口から出てしまって些か羞恥を禁じ得ない。
それはそれとして明らかに戦闘以外には使えそうにないものだ。
鍛冶にも温度が高すぎて無理だろう。
岩を融かすような場面がどこかに有ればまた別かも知れないが、そんな場面が草草有るとも思えない。
騎士と言う職業を鑑みれば戦闘特化はむしろ好ましいかも知れないが。
だからそこは納得した。
動揺していたのなら調節も疎かになっていたことだろう。
俺は一瞬で灰になったに違いない。
「魔法については解った」
しかしまだまだ解らないことが有る。
町を巡回する兵士でさえ二人一組で行動する。
遠くから職務で来たのなら騎士であっても独りだけとはおかしい。
「どうしてあの泉に独りで居たんだ?」
ホーリーは沈黙した。
答えるべきかどうかを悩んでいるのか、尻が悩ましげに揺れる。
暫くしてその揺れが治まった。
「頼みが有る」
ホーリーは答えの代わりに願い事を言い出した。
「吾輩の魔法が当たっても無事でいられるその術を教えて貰いたい」
何を言い出すやらだ。
それを教えるとは即ち俺の魔法を教えることなのだから、易々と教えられるものではない。
少し話を逸らしてうやむやにできないものか。
「当たったと決め付けているようだが、外れたとは考えないのか?」
「それは無い」
やけにきっぱり言い切った。
「どうして?」
「魔法が当たった痕跡が地面や木々に残されていなかった。
その場から消えた人物に確かに当たったのだ」
「む……」
唸らざるを得なかった。
魔法を発動可能な範囲は個人によって異なるが、身体からの距離は短かければ腕の長さまで、長くてもその倍までとされる。
それより遠い場所に発現させるには魔法を投射する。
投射された魔法は軌跡を描いて飛び、発現するのは予め距離を定めたものならその距離で、そうでないものは何かに当たった時点でとなる。
当たらなければある程度の距離を進んだ後に霧散する。
あの時の二人の距離はホーリーが非常識な発動範囲を持っていないのなら投射が必要な距離だった。
そして泉の周囲は森の木立に覆われている。
つまりは俺に当たらなければどこかの木が燃えていた。
もしくは魔法が当たった部分だけ灰も残さず抉れたか。
「背負子とこのナイフだけが残っていた」
ホーリーが腰に提げていたポーチから右手だけでナイフを取り出して差し出して来た。
柄は殆ど喪われているが、鞘にははっきりと見覚えがある。
俺の愛用品だ。
背負子とナイフを回収しているのを見せられれば、周囲をしっかり確認したと認めざるを得ない。
そして確信している相手を煙に巻けるほどの弁舌は俺には無い。
だから逆に判らないことを質問する。
「その術がどんなものか予想しているのか?」
「うむ。
最も可能性が高いと考えているのは、ナイフを身代わりとして魔法に当て、魔法が発現する時の光で周囲が見えなくなっている隙に姿を暗ませたと言うものだ」
そんなことができるのなら俺が知りたい。
ともあれホーリーはあれが身体能力と技術によるものと考えたらしい。
もしそうなら身体能力が俺より明らかに上のホーリーなら容易に修得できよう。
技術じゃないので無理だが。
魔法で有るとするなら闇魔法の一種だろうか。
闇魔法とは酷く曖昧な魔法で、僅かながら人の精神に作用するものや虚像を作るものなどが有ると言う。
俺の親父が闇魔法の使い手で、人の嘘を知るものだった。
強い魔法ではないが、取り引きにおいてぼったくられることが無い。
それで雑貨屋を営んでいた訳だ。
そんな闇魔法の中にはホーリーの言った通りの働きをするものが有るかも知れない。
勿論「かも知れない」だけであり、譬え俺の魔法がそうだったとしても答えは決まっている。
「無理だ」
きっぱりと答えた。
魔法の副作用だから伝授などできない。
するとホーリーが顔を上げ、「駄目なのか?」と恨めしげに涙目で訴えてくる。
一瞬息が詰まった。
本当に美少女は狡い。
ぐらんぐらんに心を揺さぶってくる。
揺らす方が悪いと言えばそれまでだが、はらはらと儚く花びらが散るかの如き風情を見せ付けられて「揺らすな」と言うのも酷だ。
ホーリーが顔を上げたことでまた視界に入ったけしからん峡谷も心を揺さぶってくる。
ここで更にけしからん揺さぶりを畳み掛けられていようものなら堪えられないところだった。
幸いなことにその最後の揺さぶりは無い。
「無理なものは無理だ」
「駄目なのか」
ホーリーは上体を起こして右膝を浮かせ、尻を床に着けてぺたんと座った。
左手を股の間に、右手を右脚の外側に突く。
土下座は願い事込みだった模様。
しかし座った姿は土下座よりも破壊力が有る。
何と狂おしいほどに萌える姿なのだろう。
「もう何でも教えちゃう」と口から溢れそうになる。
先刻に町の通りで俺が一方的に悪者にされたのも頷けると言うものだ。
これが噂に聞くハニートラップか!
内心で呪文のように唱えて気を落ち着かせた。
「それを知りたい理由は何なんだ?」
そう問うと、ホーリーは少しびっくりしたように目を瞬かせた。
0
あなたにおすすめの小説

【最強モブの努力無双】~ゲームで名前も登場しないようなモブに転生したオレ、一途な努力とゲーム知識で最強になる~
くーねるでぶる(戒め)
ファンタジー
アベル・ヴィアラットは、五歳の時、ベッドから転げ落ちてその拍子に前世の記憶を思い出した。
大人気ゲーム『ヒーローズ・ジャーニー』の世界に転生したアベルは、ゲームの知識を使って全男の子の憧れである“最強”になることを決意する。
そのために努力を続け、順調に強くなっていくアベル。
しかしこの世界にはゲームには無かった知識ばかり。
戦闘もただスキルをブッパすればいいだけのゲームとはまったく違っていた。
「面白いじゃん?」
アベルはめげることなく、辺境最強の父と優しい母に見守られてすくすくと成長していくのだった。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !
本条蒼依
ファンタジー
地球とは違う異世界シンアースでの物語。
主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。
その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。
そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。
主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。
ハーレム要素はしばらくありません。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!
HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。
跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。
「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」
最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!
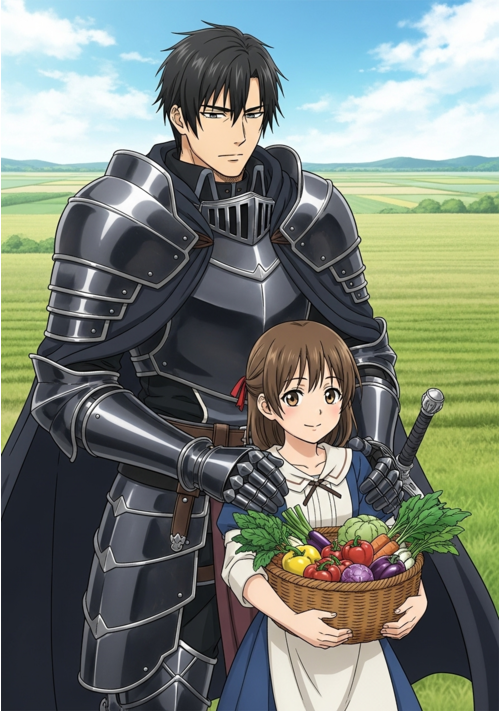
婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!
黒崎隼人
ファンタジー
「君は偽りの聖女だ」――。
地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。
しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。
これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。
王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~
名無し
ファンタジー
とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















