11 / 27
第二章 秋
第一一話 温泉
しおりを挟む
「頼もう!」
入り口を入った所でホーリーは叫んだ。
ドヤ顔だ。
どうしてドヤ顔なのかは計り知れない。
別にどんな顔をしていても良いのだが、右手の壁際に「御用の方はこの紐をお引きください」と書かれていて紐が垂れている。
ホーリーは一度来ている筈なのに紐の存在を知らないのだろうか。
そして案の定、待てど暮らせど誰も出て来ない。
さてどうしたものか。
こそこそとホーリーの視界に入らないように動いて紐を引く。
チリンチリンと涼やかな音が小さく聞こえた。
直ぐ上からだ。
上を見れば、小さな鐘が紐に繋がっている。
恐らく呼び鈴が鳴ったことを紐を引いた人に知らせるためのものだろう。
本来の呼び鈴は遠くに有るに違いない。
振り返ると、ホーリーが口を菱形にして驚いていた。
その視線は紐に注がれている。
やはり紐の存在を知らなかったらしい。
どうしてだろうかと、ぼんやりホーリーの顔を見ていれば、俺の視線に気付いたらしいホーリーが「前に来た時は近くに女将が居たのだ」と顔を真っ赤にしてそっぽを向いた。
焦る姿が可愛いらしい。
「いらっしゃいませー」
声がしたのはホーリーがそっぽを向いたのとほぼ同時だ。
見れば、エプロン姿の少女がパタパタと駆けて来る。
一〇歳くらいでつぶらな瞳。
濃紺でポニーテールの後ろ髪が揺れている。
「女将、此度は世話になる」
「女将!?」
ホーリーの突拍子もない言葉に変な声が出た。
女の子が女将はないだろうと。
「はい。
メーアが当宿の女将なのです」
しかしながら真実らしい。
一人称に名前を使うような女の子が女将だと言うのだ。
暫し呆然とする間にも「お部屋にご案内なのです」とメーアが先導してホーリーがそれに続く。
俺は慌てて追い掛けた。
温泉宿は二〇部屋ほど有るようだが、他の客が見当たらない。
「夏場の早い時間なので、今いらっしゃるお客さんはお客さん方お二人だけなのですよ」
疑問を口に出す前に答えが貰えた。
「夏場は客の入りが悪い?」
「なのです。
暑い最中に温かい温泉を浴びるお客さんは少ないのですよ」
尤もだ。
「ですが、折角のお越しなのですから、是非温泉を楽しんで欲しいのですよ。
今なら貸し切りみたいなものなのです」
それは堪能せざるを得ない。
そんなこんなの話をしている内に部屋に着いた。
俺とホーリーは部屋は同じ部屋に通された。
あれっと思いながらも、部屋の説明を聞いたら納得した。
部屋に入って直ぐの場所は居間で、貴族用にも使える寝室二つと付き人用の寝室一つが小部屋として付随している。
だから俺とホーリーが二人が並んで眠るようなことにはならない。
寝室を分ければ良いのだ。
それにしても広い。
貴族が泊まるような部屋なら当然なのかも知れないが、居間だけでも俺の自宅の一階と二階を足したくらいの床面積が有る。
貴族用の寝室は俺の自室の三倍は有る。
付き人用の寝室で俺の自室くらいだ。
「お食事の用意が調いましたら食堂にご案内なのです」
そう言い残してメーアは退出した。
部屋の広さに俺が半ば呆然としつつ生返事でメーアを見送る横で、ホーリーはケロッとしている。
「広くはないが、宿としては十分なのだ」
「え?」
ちょっと待ってくれと、声に出そうとして出なかった。
これで「広くない」なら俺の家はどうなのかと。
「俺の家は比べものにならないくらいに狭いんだが……」
一瞬だけきょとんとしたホーリーが不敵に笑う。
むむっ、こんな表情でも可愛いから困る。
「秘密基地みたいで楽しいのだ」
おい……。
「それに、ペッテの手料理を食べられるなら狭いくらいは大したことではないのだ」
……一晩で目的が変わっておられる。
俺との契約はどこへ?
考えると切なくなりそうなので止めた。
「それはともかく、温泉とやらに行ってみないか?」
俺は荷物を下ろしつつ提案した。
未経験の温泉には割りと期待している。
近くに住んでいようと、生活に必須でなければ足を運んだりしないものなのだ。
「うむ。
そうしようではないか」
ホーリーも良い笑顔で同意した。
大浴場は男女で分かれている。
その男性用の脱衣所だけでも泊まる部屋の倍ほどの広さだ。
しかし、一〇組程度が別々に寛げるようにソファーやテーブルが配置されているため、広さはそれほど感じない。
それでも場違い感が酷くて落ち着かない。
貧乏性だからふかふかなソファーにも座りにくい。
入浴の手引きが置かれていたので熟読し、読み終わったらそそくさと服を脱いで浴室へ行く。
脱衣所の棚に備えられていた桶、手拭い、石鹸のセットを手にするのを忘れずに。
浴室の広さは脱衣所の更に倍。
洗い場が半分、湯船が半分と言った塩梅で、湯船は幾つかに分かれている。
その理由は後で確かめるとして、まずは手引きの通りに身体を洗おう。
洗い場の壁際には水が流れ落ちている場所が幾つも有る。
触ってみれば、お湯だ。
それを桶に汲んで使うらしい。
用意されていた手拭いも上等な布で、俺がいつも使っているボロ布とは肌触りが全然違う。
石鹸の泡立ちもすこぶる良く、日頃使っているのが石鹸もどきに思えるほどだ。
その手拭いと石鹸で一度ならず、二度三度と隅々まで身体を洗う。
使い残しの石鹸は返却するよう手引きに書かれていたので、この機会を逃せないのだ。
そうして洗い終わった後、不思議と身体が軽く感じた。
湯船の広さも信じられない。
小さい湯船でさえ、俺の自室ほどもある。
最も大きい湯船になると、更にその何倍もの大きさなのだ。
どれほどお湯を贅沢に使っているのだろうか。
ともあれ、一つ一つ湯船を確かめる。
最も大きい湯船は中くらいの温度のお湯で、小さい湯船は熱めのお湯、温めのお湯、温めのお湯に加えて浅めの湯船と言った具合に微妙に違いが有る。
浅めの湯船は子供用だろう。
随分、至れり尽くせりだ。
よくぞここまでのものを作ったものだが、どうやって作ったかに至っては想像もできない。
疑問は尽きないが、今は湯船に浸かるのが先決だろう。
どうせだから最も大きな湯船に挑む。
足を差し入れると、ちょっと熱く感じた。
それでも我慢できないようなものではないので、ゆっくりと入り、ゆっくりと腰を下ろす。
「ふああぁ」
自分の口から出た変な声に驚いて辺りを見回した。
誰も居ない。
そう聞いていたから当たり前なのだけど、安心した。
変な声を誰にも聞かれずに済んだのだ。
換気口らしき穴が有るだけで窓が無いので誰かに見られたりもしていない。
問題無しだ。
窓が無いことを一瞬疑問に思ったが、有ったとしてもダンジョンの壁が見えるだけだから意味が無いと納得した。
浴室は広々としているので圧迫感も無い。
その広さに最初は戸惑ったものの、泳げそうなほどに広い湯船にこうして独りで浸かっていると、何だか気が大きくなる。
泳ぎはしないまでも、潜ってみたり、指先で支えて身体を浮かしたり、そのまま我が息子だけ水面から出してみたり。
いや、何となく。
そしてもう暫く湯船を楽しんだところで少し気怠さを感じたので、湯から上がることにした。
絞った手拭いで身体に付いた水滴を拭ってから浴室を出る。
すると、どこかひんやりと感じる脱衣所の空気に「ほぅ」と息が漏れた。
用意されていたローブを羽織って暫し寛ぐ。
着替えるのは火照った身体が冷めて汗が引いてからだ。
脱衣所の一角に飲み物が用意されていると手引きに書かれていたのを思いだし、そこへ行く。
一人一本だけ無料だと言う。
行った先に置かれていた四角い箱の蓋を開けると、氷水に浸された瓶詰めのミルクが入っていた。
何のミルクかまでは判らない。
多分、飲んでも判らない。
飲んだことが無いんだもん。
……「だもん」は無いな……。
折角だから一本頂戴する。
手にする瓶はすこぶる冷たい。
初めての経験に、知らず胸も踊れば顔もニヤける。
瓶に付いた滴を拭ってコルクの栓を抜く。
まずは一口。
ゆっくりと味わうと、少し癖を感じるものの結構美味い。
だが、ちびちびと飲むものではないような気がした。
何となく左手を腰に当て、右手に瓶を持って一気に呷る。
「ぷはぁっ」
冷たいのど越しが何とも言えず、自然と声が出た。
「いい飲みっぷりだな」
突然の声にビクッとした。
恐る恐る振り返ると、良い笑顔の猟師らしき中年男が立っている。
「あ、あの……」
「おう、すまねぇ。
兄ちゃんの惚れ惚れするようなミルクの飲みっぷりに思わず声を掛けちまったぜ」
「ミルクですか?」
「おう。
温泉上がりのミルクはやっぱり腰に手を当ててこう一気にだよな」
男は俺がミルクを飲んだのと同じ身振りをした。
「はあ……」
訳が判らずに生返事をしたら、男が怪訝そうな顔をした。
「知らねぇのか?」
「はあ……」
「飲みっぷりが堂に入ってたからてっきり俺と同類だと思ったんだが、違ったのか」
意味が判らず首を傾げる俺に男が言葉を繋ぐ。
「いやな、もう何度もこの温泉に通ってる口なんじゃないかってな」
「いえ、初めてです」
「おっと、こりゃ悪かったな。
初めてだったら何の気なしにやっちまうことがどれだかまだ判らねぇな」
男はぺしんと自分の額を叩いた。
「なあ、湯船に浸かった時『ふああぁ』なんて言っちまったろ?」
男のにやけながらの問いにびっくりした。
まさか見ていたのだろうか。
「その顔はやっぱりな。
いやぁ、声が出ちまうもんなんだよな」
男が納得したように腕を組んで何度も頷いた。
どうやら見られた訳ではないようで、少し安堵した。
それに声を掛けられてから少し時間が経ったことで動転していた心も落ち着いてきた。
すると素朴な疑問も起きる。
「この宿に何度も泊まってるなんて凄いですね」
「俺か?」
男が小首を傾げる。
「いや、俺は温泉に入りに来ただけだ」
温泉だけとはどう言うことだろうと今度は俺の方が小首を傾げると、男が不敵に笑った。
「知らなかったのか? この宿は夏場だけだが温泉に入るだけの客も入れてくれるんだ。
それでも安くはないし、早い時間だけなんだが、年に一度の贅沢と思えば出せない金額じゃないのさ」
ほうほうと俺が感心していると、男がハッとしたように目を見開いた。
「いけねぇ、いけねぇ、長話していたら温泉を楽しむ時間が無くなっちまう。
それじゃ、兄ちゃんも温泉を楽しみな」
そう言うなり、男は手早く服を脱いで浴室へと入って行った。
そして話している間にすっかり身体が冷えて汗も引いていた俺は着替えを済ませて部屋へと戻った。
入り口を入った所でホーリーは叫んだ。
ドヤ顔だ。
どうしてドヤ顔なのかは計り知れない。
別にどんな顔をしていても良いのだが、右手の壁際に「御用の方はこの紐をお引きください」と書かれていて紐が垂れている。
ホーリーは一度来ている筈なのに紐の存在を知らないのだろうか。
そして案の定、待てど暮らせど誰も出て来ない。
さてどうしたものか。
こそこそとホーリーの視界に入らないように動いて紐を引く。
チリンチリンと涼やかな音が小さく聞こえた。
直ぐ上からだ。
上を見れば、小さな鐘が紐に繋がっている。
恐らく呼び鈴が鳴ったことを紐を引いた人に知らせるためのものだろう。
本来の呼び鈴は遠くに有るに違いない。
振り返ると、ホーリーが口を菱形にして驚いていた。
その視線は紐に注がれている。
やはり紐の存在を知らなかったらしい。
どうしてだろうかと、ぼんやりホーリーの顔を見ていれば、俺の視線に気付いたらしいホーリーが「前に来た時は近くに女将が居たのだ」と顔を真っ赤にしてそっぽを向いた。
焦る姿が可愛いらしい。
「いらっしゃいませー」
声がしたのはホーリーがそっぽを向いたのとほぼ同時だ。
見れば、エプロン姿の少女がパタパタと駆けて来る。
一〇歳くらいでつぶらな瞳。
濃紺でポニーテールの後ろ髪が揺れている。
「女将、此度は世話になる」
「女将!?」
ホーリーの突拍子もない言葉に変な声が出た。
女の子が女将はないだろうと。
「はい。
メーアが当宿の女将なのです」
しかしながら真実らしい。
一人称に名前を使うような女の子が女将だと言うのだ。
暫し呆然とする間にも「お部屋にご案内なのです」とメーアが先導してホーリーがそれに続く。
俺は慌てて追い掛けた。
温泉宿は二〇部屋ほど有るようだが、他の客が見当たらない。
「夏場の早い時間なので、今いらっしゃるお客さんはお客さん方お二人だけなのですよ」
疑問を口に出す前に答えが貰えた。
「夏場は客の入りが悪い?」
「なのです。
暑い最中に温かい温泉を浴びるお客さんは少ないのですよ」
尤もだ。
「ですが、折角のお越しなのですから、是非温泉を楽しんで欲しいのですよ。
今なら貸し切りみたいなものなのです」
それは堪能せざるを得ない。
そんなこんなの話をしている内に部屋に着いた。
俺とホーリーは部屋は同じ部屋に通された。
あれっと思いながらも、部屋の説明を聞いたら納得した。
部屋に入って直ぐの場所は居間で、貴族用にも使える寝室二つと付き人用の寝室一つが小部屋として付随している。
だから俺とホーリーが二人が並んで眠るようなことにはならない。
寝室を分ければ良いのだ。
それにしても広い。
貴族が泊まるような部屋なら当然なのかも知れないが、居間だけでも俺の自宅の一階と二階を足したくらいの床面積が有る。
貴族用の寝室は俺の自室の三倍は有る。
付き人用の寝室で俺の自室くらいだ。
「お食事の用意が調いましたら食堂にご案内なのです」
そう言い残してメーアは退出した。
部屋の広さに俺が半ば呆然としつつ生返事でメーアを見送る横で、ホーリーはケロッとしている。
「広くはないが、宿としては十分なのだ」
「え?」
ちょっと待ってくれと、声に出そうとして出なかった。
これで「広くない」なら俺の家はどうなのかと。
「俺の家は比べものにならないくらいに狭いんだが……」
一瞬だけきょとんとしたホーリーが不敵に笑う。
むむっ、こんな表情でも可愛いから困る。
「秘密基地みたいで楽しいのだ」
おい……。
「それに、ペッテの手料理を食べられるなら狭いくらいは大したことではないのだ」
……一晩で目的が変わっておられる。
俺との契約はどこへ?
考えると切なくなりそうなので止めた。
「それはともかく、温泉とやらに行ってみないか?」
俺は荷物を下ろしつつ提案した。
未経験の温泉には割りと期待している。
近くに住んでいようと、生活に必須でなければ足を運んだりしないものなのだ。
「うむ。
そうしようではないか」
ホーリーも良い笑顔で同意した。
大浴場は男女で分かれている。
その男性用の脱衣所だけでも泊まる部屋の倍ほどの広さだ。
しかし、一〇組程度が別々に寛げるようにソファーやテーブルが配置されているため、広さはそれほど感じない。
それでも場違い感が酷くて落ち着かない。
貧乏性だからふかふかなソファーにも座りにくい。
入浴の手引きが置かれていたので熟読し、読み終わったらそそくさと服を脱いで浴室へ行く。
脱衣所の棚に備えられていた桶、手拭い、石鹸のセットを手にするのを忘れずに。
浴室の広さは脱衣所の更に倍。
洗い場が半分、湯船が半分と言った塩梅で、湯船は幾つかに分かれている。
その理由は後で確かめるとして、まずは手引きの通りに身体を洗おう。
洗い場の壁際には水が流れ落ちている場所が幾つも有る。
触ってみれば、お湯だ。
それを桶に汲んで使うらしい。
用意されていた手拭いも上等な布で、俺がいつも使っているボロ布とは肌触りが全然違う。
石鹸の泡立ちもすこぶる良く、日頃使っているのが石鹸もどきに思えるほどだ。
その手拭いと石鹸で一度ならず、二度三度と隅々まで身体を洗う。
使い残しの石鹸は返却するよう手引きに書かれていたので、この機会を逃せないのだ。
そうして洗い終わった後、不思議と身体が軽く感じた。
湯船の広さも信じられない。
小さい湯船でさえ、俺の自室ほどもある。
最も大きい湯船になると、更にその何倍もの大きさなのだ。
どれほどお湯を贅沢に使っているのだろうか。
ともあれ、一つ一つ湯船を確かめる。
最も大きい湯船は中くらいの温度のお湯で、小さい湯船は熱めのお湯、温めのお湯、温めのお湯に加えて浅めの湯船と言った具合に微妙に違いが有る。
浅めの湯船は子供用だろう。
随分、至れり尽くせりだ。
よくぞここまでのものを作ったものだが、どうやって作ったかに至っては想像もできない。
疑問は尽きないが、今は湯船に浸かるのが先決だろう。
どうせだから最も大きな湯船に挑む。
足を差し入れると、ちょっと熱く感じた。
それでも我慢できないようなものではないので、ゆっくりと入り、ゆっくりと腰を下ろす。
「ふああぁ」
自分の口から出た変な声に驚いて辺りを見回した。
誰も居ない。
そう聞いていたから当たり前なのだけど、安心した。
変な声を誰にも聞かれずに済んだのだ。
換気口らしき穴が有るだけで窓が無いので誰かに見られたりもしていない。
問題無しだ。
窓が無いことを一瞬疑問に思ったが、有ったとしてもダンジョンの壁が見えるだけだから意味が無いと納得した。
浴室は広々としているので圧迫感も無い。
その広さに最初は戸惑ったものの、泳げそうなほどに広い湯船にこうして独りで浸かっていると、何だか気が大きくなる。
泳ぎはしないまでも、潜ってみたり、指先で支えて身体を浮かしたり、そのまま我が息子だけ水面から出してみたり。
いや、何となく。
そしてもう暫く湯船を楽しんだところで少し気怠さを感じたので、湯から上がることにした。
絞った手拭いで身体に付いた水滴を拭ってから浴室を出る。
すると、どこかひんやりと感じる脱衣所の空気に「ほぅ」と息が漏れた。
用意されていたローブを羽織って暫し寛ぐ。
着替えるのは火照った身体が冷めて汗が引いてからだ。
脱衣所の一角に飲み物が用意されていると手引きに書かれていたのを思いだし、そこへ行く。
一人一本だけ無料だと言う。
行った先に置かれていた四角い箱の蓋を開けると、氷水に浸された瓶詰めのミルクが入っていた。
何のミルクかまでは判らない。
多分、飲んでも判らない。
飲んだことが無いんだもん。
……「だもん」は無いな……。
折角だから一本頂戴する。
手にする瓶はすこぶる冷たい。
初めての経験に、知らず胸も踊れば顔もニヤける。
瓶に付いた滴を拭ってコルクの栓を抜く。
まずは一口。
ゆっくりと味わうと、少し癖を感じるものの結構美味い。
だが、ちびちびと飲むものではないような気がした。
何となく左手を腰に当て、右手に瓶を持って一気に呷る。
「ぷはぁっ」
冷たいのど越しが何とも言えず、自然と声が出た。
「いい飲みっぷりだな」
突然の声にビクッとした。
恐る恐る振り返ると、良い笑顔の猟師らしき中年男が立っている。
「あ、あの……」
「おう、すまねぇ。
兄ちゃんの惚れ惚れするようなミルクの飲みっぷりに思わず声を掛けちまったぜ」
「ミルクですか?」
「おう。
温泉上がりのミルクはやっぱり腰に手を当ててこう一気にだよな」
男は俺がミルクを飲んだのと同じ身振りをした。
「はあ……」
訳が判らずに生返事をしたら、男が怪訝そうな顔をした。
「知らねぇのか?」
「はあ……」
「飲みっぷりが堂に入ってたからてっきり俺と同類だと思ったんだが、違ったのか」
意味が判らず首を傾げる俺に男が言葉を繋ぐ。
「いやな、もう何度もこの温泉に通ってる口なんじゃないかってな」
「いえ、初めてです」
「おっと、こりゃ悪かったな。
初めてだったら何の気なしにやっちまうことがどれだかまだ判らねぇな」
男はぺしんと自分の額を叩いた。
「なあ、湯船に浸かった時『ふああぁ』なんて言っちまったろ?」
男のにやけながらの問いにびっくりした。
まさか見ていたのだろうか。
「その顔はやっぱりな。
いやぁ、声が出ちまうもんなんだよな」
男が納得したように腕を組んで何度も頷いた。
どうやら見られた訳ではないようで、少し安堵した。
それに声を掛けられてから少し時間が経ったことで動転していた心も落ち着いてきた。
すると素朴な疑問も起きる。
「この宿に何度も泊まってるなんて凄いですね」
「俺か?」
男が小首を傾げる。
「いや、俺は温泉に入りに来ただけだ」
温泉だけとはどう言うことだろうと今度は俺の方が小首を傾げると、男が不敵に笑った。
「知らなかったのか? この宿は夏場だけだが温泉に入るだけの客も入れてくれるんだ。
それでも安くはないし、早い時間だけなんだが、年に一度の贅沢と思えば出せない金額じゃないのさ」
ほうほうと俺が感心していると、男がハッとしたように目を見開いた。
「いけねぇ、いけねぇ、長話していたら温泉を楽しむ時間が無くなっちまう。
それじゃ、兄ちゃんも温泉を楽しみな」
そう言うなり、男は手早く服を脱いで浴室へと入って行った。
そして話している間にすっかり身体が冷えて汗も引いていた俺は着替えを済ませて部屋へと戻った。
0
あなたにおすすめの小説

【最強モブの努力無双】~ゲームで名前も登場しないようなモブに転生したオレ、一途な努力とゲーム知識で最強になる~
くーねるでぶる(戒め)
ファンタジー
アベル・ヴィアラットは、五歳の時、ベッドから転げ落ちてその拍子に前世の記憶を思い出した。
大人気ゲーム『ヒーローズ・ジャーニー』の世界に転生したアベルは、ゲームの知識を使って全男の子の憧れである“最強”になることを決意する。
そのために努力を続け、順調に強くなっていくアベル。
しかしこの世界にはゲームには無かった知識ばかり。
戦闘もただスキルをブッパすればいいだけのゲームとはまったく違っていた。
「面白いじゃん?」
アベルはめげることなく、辺境最強の父と優しい母に見守られてすくすくと成長していくのだった。

役立たずと言われダンジョンで殺されかけたが、実は最強で万能スキルでした !
本条蒼依
ファンタジー
地球とは違う異世界シンアースでの物語。
主人公マルクは神聖の儀で何にも反応しないスキルを貰い、絶望の淵へと叩き込まれる。
その役に立たないスキルで冒険者になるが、役立たずと言われダンジョンで殺されかけるが、そのスキルは唯一無二の万能スキルだった。
そのスキルで成り上がり、ダンジョンで裏切った人間は落ちぶれざまあ展開。
主人公マルクは、そのスキルで色んなことを解決し幸せになる。
ハーレム要素はしばらくありません。

【完結】うさぎ転生 〜女子高生の私、交通事故で死んだと思ったら、気づけば現代ダンジョンの最弱モンスターに!?最強目指して生き延びる〜
旅する書斎(☆ほしい)
ファンタジー
女子高生の篠崎カレンは、交通事故に遭って命を落とした……はずが、目覚めるとそこはモンスターあふれる現代ダンジョン。しかも身体はウサギになっていた!
HPはわずか5、攻撃力もゼロに等しい「最弱モンスター」扱いの白うさぎ。それでもスライムやコボルトにおびえながら、なんとか生き延びる日々。唯一の救いは、ダンジョン特有の“スキル”を磨けば強くなれるということ。
跳躍蹴りでスライムを倒し、小動物の悲鳴でコボルトを怯ませ、少しずつ経験値を積んでいくうちに、カレンは手応えを感じ始める。
「このままじゃ終わらない。私、もっと強くなっていつか……」
最弱からの“首刈りウサギ”進化を目指して、ウサギの身体で奮闘するカレン。彼女はこの危険だらけのダンジョンで、生き延びるだけでなく“人間へ戻る術(すべ)”を探し当てられるのか? それとも新たなモンスターとしての道を歩むのか?最弱うさぎの成り上がりサバイバルが、いま幕を開ける!
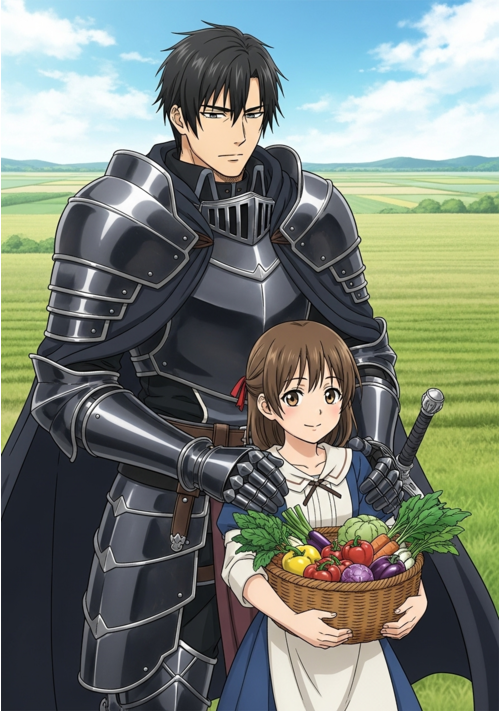
婚約破棄&濡れ衣で追放された聖女ですが、辺境で育成スキルの真価を発揮!無骨で不器用な最強騎士様からの溺愛が止まりません!
黒崎隼人
ファンタジー
「君は偽りの聖女だ」――。
地味な「育成」の力しか持たない伯爵令嬢エルナは、婚約者である王太子にそう断じられ、すべてを奪われた。聖女の地位、婚約者、そして濡れ衣を着せられ追放された先は、魔物が巣食う極寒の辺境の地。
しかし、絶望の淵で彼女は自身の力の本当の価値を知る。凍てついた大地を緑豊かな楽園へと変える「育成」の力。それは、飢えた人々の心と体を癒す、真の聖女の奇跡だった。
これは、役立たずと蔑まれた少女が、無骨で不器用な「氷壁の騎士」ガイオンの揺るぎない愛に支えられ、辺境の地でかけがえのない居場所と幸せを見つける、心温まる逆転スローライフ・ファンタジー。
王都が彼女の真価に気づいた時、もう遅い。最高のざまぁと、とろけるほど甘い溺愛が、ここにある。

アルフレッドは平穏に過ごしたい 〜追放されたけど謎のスキル【合成】で生き抜く〜
芍薬甘草湯
ファンタジー
アルフレッドは貴族の令息であったが天から与えられたスキルと家風の違いで追放される。平民となり冒険者となったが、生活するために竜騎士隊でアルバイトをすることに。
ふとした事でスキルが発動。
使えないスキルではない事に気付いたアルフレッドは様々なものを合成しながら密かに活躍していく。
⭐︎注意⭐︎
女性が多く出てくるため、ハーレム要素がほんの少しあります。特に苦手な方はご遠慮ください。

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる
竜頭蛇
ファンタジー
ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。
評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。
身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます
菻莅❝りんり❞
ファンタジー
貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。
嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。
「居なくていいなら、出ていこう」
この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~
名無し
ファンタジー
とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















